労働基準法36条をわかりやすく!残業時間の限度と企業リスクとは
労働問題・労働法務
2025.06.30 ー 2025.12.18 更新

労働基準法36条(いわゆる「36協定」)をわかりやすく理解し、正しく運用できていますか?
企業が従業員に時間外労働を命じるには、この協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。未締結のまま残業をさせれば、労働基準法違反とみなされ、懲役刑や罰金の対象になるおそれもあるため注意が必要です。
とくに2024年の法改正以降、時間外労働の上限規制が厳格化され、36協定の不備があれば是正勧告や企業名の公表といった制裁措置を受けるリスクも高まっています。未払い残業代の請求や採用活動への悪影響など、経営に直結する問題に発展するケースも珍しくありません。
本記事では、労働基準法36条の基本から、36協定の種類・締結手順・届出方法・罰則内容までを実務目線でわかりやすく解説します。制度を正しく理解し、自社の労務リスクを防ぐための見直しに、ぜひご活用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>労働基準法36条の基礎知識をわかりやすく解説
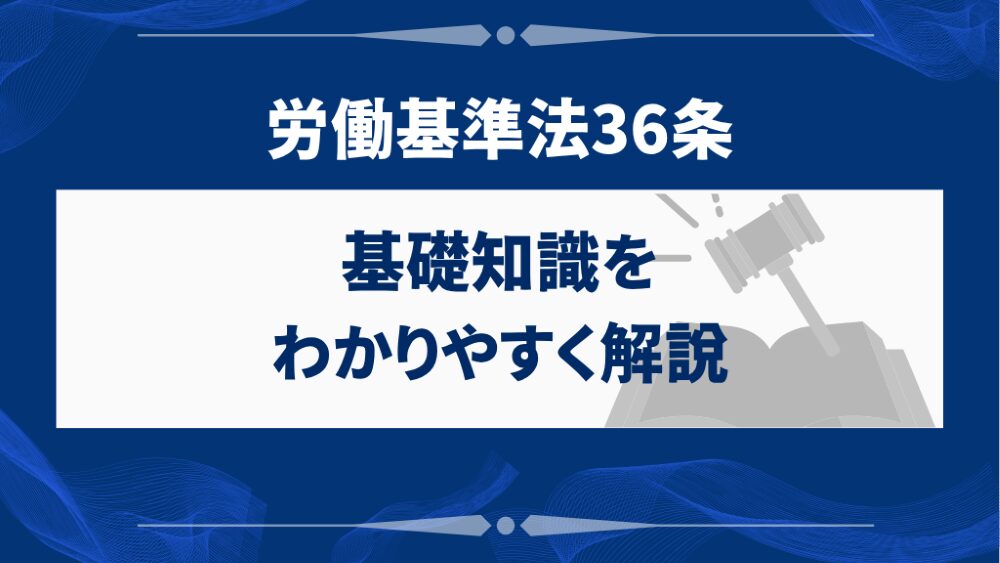
労働基準法第36条は、企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる際の、法的な前提条件を定めた重要な条文です。この規定に基づき、労使で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければ、残業を命じることはできません。
本章では、36協定の基本的な仕組みや法律上の位置づけ、企業が締結すべき理由について、人事・労務担当者の視点からわかりやすく解説します。
36協定の法的意義と導入の背景
労働基準法は、労働時間の上限を「1日8時間・週40時間」(法定労働時間)と定め、週1日以上の休日(法定休日)を義務付けています。これを超えて労働させることは、原則として法律で禁じられています。
しかし、臨時的な必要性などから法定労働時間を超えなければならない場合、その例外として機能するのが36協定です。労使間で協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで、初めて時間外・休日労働を適法に行うことが認められます。
この協定は、企業の円滑な事業活動と、過重労働を防止し労働者の健康を守るという、企業活動と労働者保護を両立する枠組みです。過去の長時間労働問題への反省から、実効性のあるルールとして整備されました。
36協定未締結のリスクと違法性
36協定を締結せず、労働基準監督署への届け出も行わないまま、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働者に時間外労働を課す行為は、労働基準法に違反します。これは、法律で定められた最低限の労働条件を満たしておらず、看過できるものではありません。
36協定が未締結の状態で違法な時間外労働を実施した場合、労働基準法第119条に基づき、使用者(企業)に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
さらに、罰則にとどまらず、企業にはさまざまなリスクが及ぶおそれがあります。主なリスクは以下のとおりです。
- 従業員から未払い残業代や精神的苦痛に対する損害賠償を請求される民事訴訟
- 労働基準監督署による是正指導や企業名の公表
- ハローワークでの求人が受理されなくなるなど、社会的信用の失墜
実際に、36協定を締結しないまま残業を強いたことで、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、送検されたりした事例もあります。
こうしたリスクを避け、適正な労務管理を実現するには、時間外労働や休日労働の可能性がある職場において、36協定の締結と届け出を必ず行う必要があります。
もし「36協定の作り方」や「締結・届出手順」について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
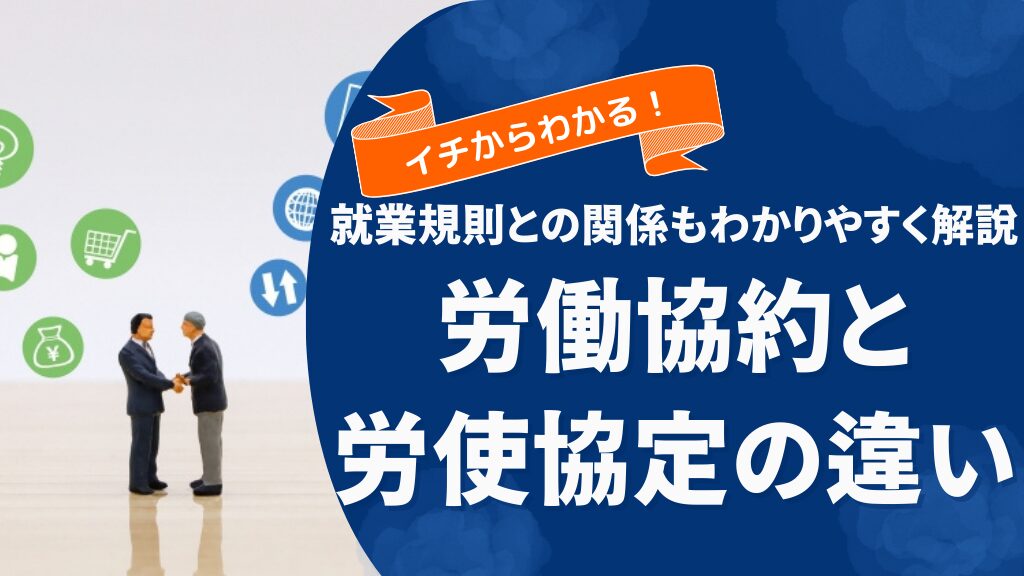
労働協約と労使協定の違いとは?就業規則との関係もわかりやすく解説
企業の労務管理において、労働協約と労使協定は重要な役割を果たしていますが、その違いを正確に理解している方は意外と少ないものです。 これらの違いを理解することは、人事担当者だけでなく、一般の従業員にとっても自身の労働条件を […]
36協定の種類と仕組み|基本協定と特別条項を理解
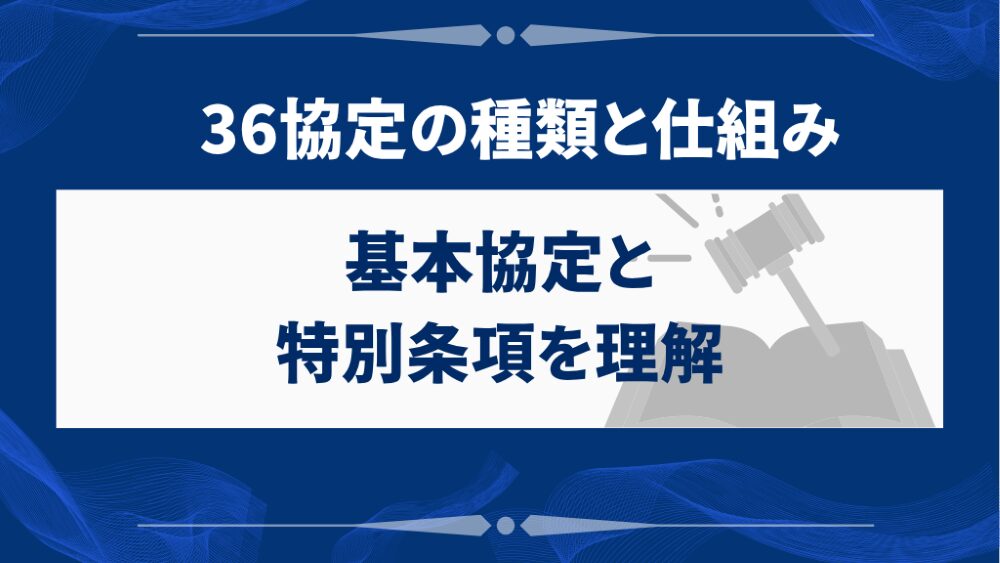
36協定には「基本協定」と「特別条項付き協定」の2種類があり、業務状況に応じて適切に使い分ける必要があります。本章では、それぞれの違いや法的な仕組み、例外業種の取り扱い、締結の流れについて解説します。
企業が法令を順守しつつ、無理のない労務運用を行うために欠かせないポイントです。
基本協定と特別条項の違いと運用基準
36協定には、企業の円滑な事業活動と労働者の健康確保という要請を両立させるための法的な時間外労働の上限時間を原則的な範囲内で定める基本協定と、それを超える場合に結ぶ特別条項付き協定があります。
まず、基本協定は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合に必須となる基本の協定です。この条項で定められる時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
一方、特別条項付き36協定は、予測できない受注増といった臨時的な事情に限り、一般条項の上限を超える労働を可能にします。ただし、特別条項付き36協定が適用されるには、以下の厳格な上限規制を超えないようにしなくてはなりません。
■超えられない上限規制
- 時間外労働の上限:年720時間以内
- 時間外労働+休日労働の合計:月100時間未満
- 原則(月45時間)を超えられる回数:年6回まで
さらに、企業にはなぜ上限を超える理由があるのかという事情を協定書に明記すること、医師による面接指導や代替休暇の付与といった労働者の健康を守る措置を講じることも要求されます。
結論として、特別条項は無制限の残業を認めるものではなく、あくまで労働者の健康確保を大前提とした、厳格なルール下での例外的な措置となります。
上限時間と例外業種の取り扱い
36協定の特別条項には、これまで述べた上限に加え、「時間外労働と休日労働の合計を2~6ヶ月の平均で80時間以内に収める」という複数月平均の規制も設けられています。
もっとも、建設事業や自動車運転の業務、医師、新技術の研究開発業務など、一部の事業はこれまで上限規制の適用が猶予または除外されてきました。これらの事業では、年間の時間外労働が960時間まで認められる一方、単月の上限(月100時間未満)や前述の複数月平均の規制が適用されない特例が存在したのです。
しかし、この猶予措置は働き方改革関連法により見直され、2024年4月1日から建設事業や自動車運転業務なども原則的な上限規制の適用対象となりました。この法改正を受け、該当する事業では36協定の見直しを含む、労務管理体制の再構築が急務となっています。
36協定の構造と締結の流れ
36協定は、使用者と労働者代表が当事者となり、時間外労働の対象業務や上限時間といった協定事項を定めます。一般条項のみの協定と特別条項付き協定の基本構造は同じですが、特別条項付き協定には臨時的な上限延長に関する定めが付加される点が大きな違いです。
協定の締結から届出までは、①労働者代表の選出、②労使間の協議・合意、③協定書の作成・署名、④労働基準監督署への届出、という手順で進められます。
協定は所轄の労働基準監督署へ届け出ることで初めて法的な効力を持ち、多くは有効期間を1年とするため、期間満了後の継続には更新手続きが不可欠となります。
36協定の締結手順と届出方法を実務に即して解説
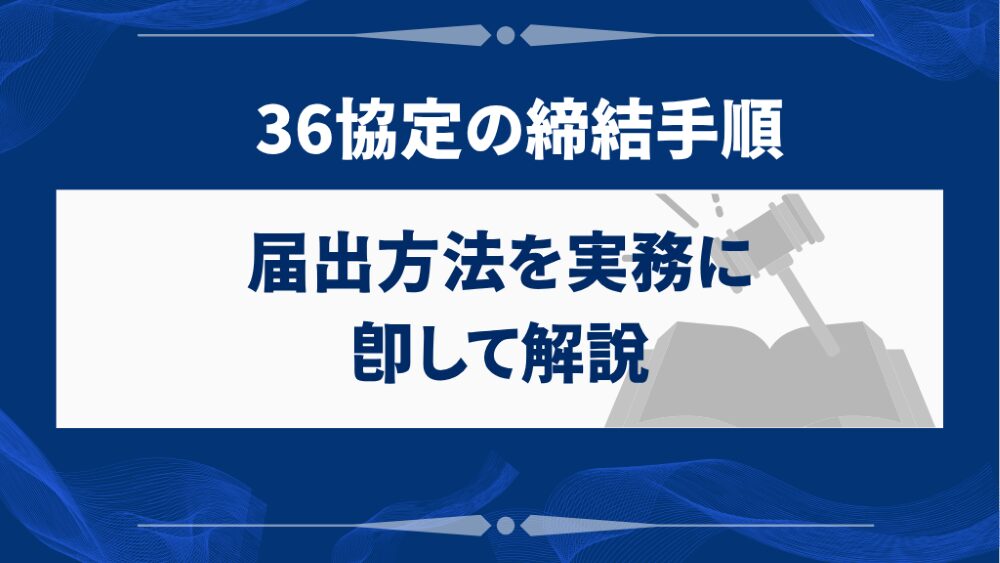
本章では、時間外労働を適法に行うために不可欠な36協定について、その締結から労働基準監督署への届出までの一連の手順と、実務上のポイントを解説します。
労働者代表の選出・協議・締結までの流れ
企業が法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日労働を命じる場合、労働基準法に基づき36協定を締結する必要があります。
さらに、その協定書を所轄の労働基準監督署長へ届け出て初めて法的な効力が認められるため、この一連の手続きを正しく踏むことが法令遵守の基本です。
締結から届出に至るまでの実務的なプロセスは、主に以下のステップで構成されています。
- 労働者代表の選出:労働者の過半数を代表する者(労働組合がない場合)を選ぶ
- 協定内容の協議・合意:時間外労働を行う業務の種類や上限時間など、具体的な内容を労使で話し合い、合意を形成する
- 36協定書の作成・締結:合意内容を基に協定書を作成し、使用者と労働者代表の双方が署名または記名押印する
- 労働基準監督署への届出:完成した協定書を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出る
届出書類の提出要件・提出先・期限チェック
36協定を有効にするための届出について、その要点を以下の表にまとめました。特に提出期限は、協定の効力に直結するため注意が必要です。
■36協定届の提出要点チェック
| 項目 | 内容・注意点 |
| ① 届出書類 | ・厚生労働省指定の様式(様式第9号など)を使用します ・有効期間、事由、対象者、延長時間数などの必須項目を漏れなく記載することが求められます |
| ② 提出先・方法 | ・提出先: 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(事業場ごとに届出が原則) ・提出方法: 窓口持参、郵送、電子申請(e-Gov)から選択できます |
| ③ 提出期限 | ・協定の有効期間が始まる前日までに必ず届け出なくてはなりません ・届出後に初めて効力が発生するため、遅れるとその間の時間外労働は違法となります |
| ④ 更新手続き | ・有効期間(通常1年)が満了する前に、新たな協定の締結と届出が不可欠です |
これらの手続きを正確に行い、常に有効な36協定を維持することが、企業のコンプライアンス体制の基本となります。
協定書テンプレートと記載の注意点
36協定の効力を発生させるには、協定届(様式第9号など)を労働基準監督署へ届け出る必要があります。協定届には、以下の主要項目を漏れなく正確に記載します。
- 協定の有効期間
- 時間外労働等をさせる具体的な事由
- 対象となる業務の種類と労働者数
- 延長できる時間数(1日・1ヶ月・1年)
提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署で、複数事業場を持つ場合は原則として個別の届出が求められます。提出方法は以下の3つから選択可能です。
- 窓口への持参
- 郵送
- 電子申請(e-Gov)
提出にあたり、特に注意すべきは期限管理です。協定の効力は届出後に発生するため、有効期間の開始前日までに手続きを完了させなくてはなりません。
届出が遅れるとその間の時間外労働は違法となり、遡及適用も認められない点に留意しましょう。また、有効期間は通常1年であり、満了後も継続する場合は更新手続きが不可欠です。
よくある記入ミスと監督署での指摘例
36協定の届出で頻発する不備には、軽微な記載ミスから法令違反にあたる重大なものまでさまざまです。本章では、よくある不備の類型とその回避策を、以下の表で対比させながら解説します。
■36協定届における主な不備とチェックポイント
| 不備の類型 | 具体的な不備の例 | 回避のためのチェックポイント |
| 形式的な不備(書類の記載ミス) | ・有効期間の記載漏れや誤記 ・労働者代表の選出方法が不明確 ・時間外労働をさせる事由が抽象的 ・対象業務や労働者の範囲が曖昧 | ・協定書の必須記載事項が網羅されているか ・日付、人数、署名などに漏れや誤りはないか ・誰が見ても内容を特定できる具体性があるか |
| 内容的な不備(法令違反のおそれ) | ・法定の上限時間(年720時間等)を超える設定 ・特別条項の回数制限(年6回まで)の記載漏れ ・健康確保措置の内容が具体的でない ・実態と異なる労働時間の記載(虚偽申告) | ・労働基準法で定める上限規制を遵守しているか ・特別条項の適用要件をすべて満たしているか ・講じる健康確保措置が具体的に明記されているか |
このような不備は、届出前の確認作業によってその多くを防ぐことが可能です。法規制は複雑なため、担当者一人に任せるのではなく、複数人でチェックする社内体制を整えることが、リスク管理の観点から強く推奨されます。
36協定違反による罰則と行政リスク
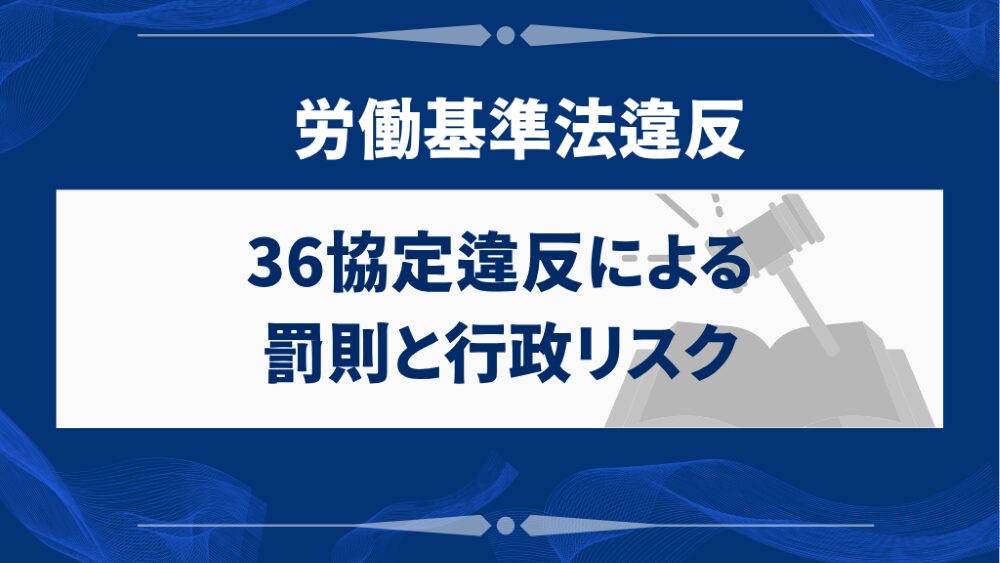
36協定に違反した場合、法的な罰則はもちろん、企業イメージの低下といった経営上の重大なリスクも伴います。本章では、企業が直面する具体的な罰則と、事業の存続に影響を及ぼしかねない多様なリスクについて解説します。
労働基準法違反による罰則・企業名公表のリスク
36協定に違反した場合、企業は複数のリスクに直面します。
- 刑事罰:使用者には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があり、法人の両罰規定により企業自体も処罰の対象です。
- 行政処分:労働基準監督署から法令違反の是正を求める「是正勧告」が出されます。悪質なケースでは、指導に従わないことを理由に企業名が公表されることもあります。
- 経営への影響:企業名の公表は社会的信用を大きく損ない、採用活動の難化や従業員の士気低下といった、深刻な経営問題に発展しかねません。
労働基準監督署の調査対応と改善報告書の書き方
36協定違反を理由に労働基準監督署の調査が入った場合、誠実に対応する必要があります。調査では、協定の有効性、労働時間の実態、割増賃金の支払い状況などが重点的に確認されます。
労働者名簿、賃金台帳、タイムカードといった関連書類を事前に準備しておくと、その後の対応が円滑に進むでしょう。
調査で法令違反が指摘されると、是正勧告と共に「改善報告書」の提出を求められるのが一般的です。報告書には、客観的な事実に基づき、以下の項目を具体的に記載しなくてはなりません。
- 指摘された違反内容
- 違反に至った原因の分析
- 具体的な改善策と再発防止策
- 改善策の実施スケジュールと責任者
実現可能な再発防止策を盛り込むことが特に重要であり、対応に不安があれば社会保険労務士など専門家への相談も有効です。
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
36協定の運用を支える残業管理と改善施策
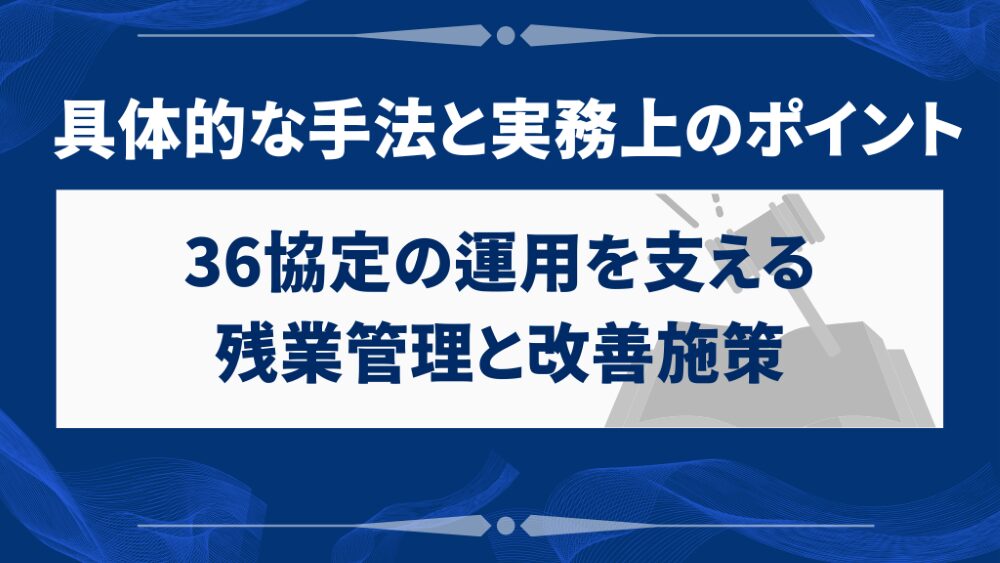
36協定を適切に運用するためには、「①正確な残業管理」「②残業を削減する改善策」「③継続的な効果検証」という3つの取り組みが欠かせません。本章では、これらの具体的な手法と実務上のポイントを解説します。
残業時間の記録とシステム導入のポイント
36協定の遵守と適正な残業代支払いのために、客観的な労働時間の把握は法的な義務です。自己申告制であっても、申告時間と実態が乖離していないかを確認する実態調査が求められます。
手書きやExcelでの管理は非効率かつ不正のリスクがあるため、勤怠管理システムの導入が有効となります。システム化により、客観的な記録の保持と管理業務の効率化が実現できるほか、不正打刻の防止にも繋がります。
システム選定時は、自社の規模や業種への適合性、コスト、サポート体制を比較検討することが重要です。導入後は、従業員への周知と記録データの定期的なチェックも欠かせません。
協定時間内で業務を回すための現場改善例
36協定の時間内で業務を完了させるには、組織的な業務効率化が不可欠です。まず業務プロセス全体を見直し、不要な会議や複雑な承認フローといった「無理・無駄・ムラ」をなくすことが改善の第一歩となります。
具体的な改善策として、以下のアプローチが有効です。
- ITツール・RPAの活用: 定型業務を自動化し、大幅な工数削減を目指します。Web会議システムの導入なども移動時間の削減に貢献します
- 業務の標準化: マニュアルを作成して業務の属人化を防ぎ、チーム全体の負荷を平準化します
- 社内制度の整備: ノー残業デーの設定や、時間外労働の事前申請制を導入し、残業に対する意識改革を図ります
これらの多角的な改善は、36協定の遵守と生産性向上を両立させる上で重要なポイントとなるでしょう。
月次チェックリストで運用状況を可視化
月次チェックリストは、36協定の遵守状況を可視化し、問題の早期発見につなげる有効なツールです。継続的な改善サイクルを確立し、コンプライアンス体制を強化する基盤となります。
チェックリストには、少なくとも以下の項目を含めるべきです。
- 各従業員の月間残業時間と特別条項の発動状況
- 長時間労働者に対する健康状態の確認や産業医面談の実施状況
- 法定上限(月45時間・年360時間等)や特別条項の上限(月100時間未満・複数月平均80時間以内)の遵守状況
各部署でチェックを行い、その結果を労務担当部署が集約・分析する運用が求められます。データから問題が見つかった際は、速やかに業務改善や人員配置の見直しといった対応を講じなくてはなりません。
チェックと改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことで、実効性のある運用が実現します。
専門家に相談すべきケースと相談先の選び方
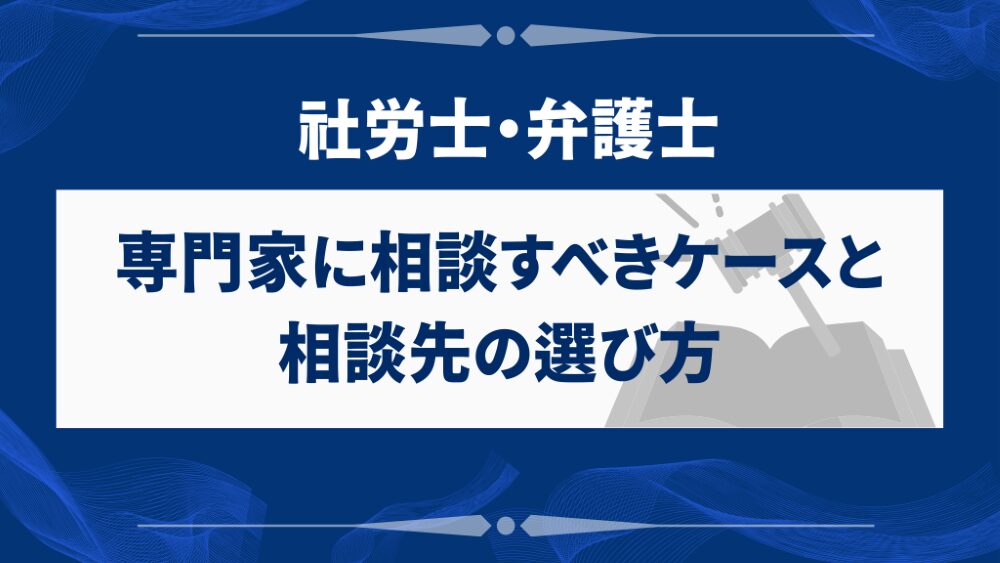
36協定の運用は複雑で、法改正への対応や労使トラブルなど、自社だけでの対応が難しい場面も少なくありません。本章では、専門家のサポートを検討すべき具体的なケースと、社会保険労務士や弁護士といった相談先の選び方を解説します。
自社だけで対応が難しい場合のシグナル
36協定の運用は複雑で、法改正も頻繁なため、自社のみでの対応が困難な場面も少なくありません。特に次の状況は、専門家への相談を検討すべきシグナルです。
- 法解釈や実務対応に自信が持てない
- 労働基準監督署の調査や是正勧告への対応に苦慮している
- 従業員との間で残業に関するトラブルが発生するリスクがある
- 残業管理体制の構築方法がわからない
これらの状況に該当する場合、専門家の知見を活用することが、問題の早期解決に繋がります。
社労士・弁護士など相談先の特徴と選定ポイント
36協定に関する相談先は、主に社会保険労務士(社労士)と弁護士です。両者の得意分野は異なり、状況に応じて適切な専門家を選ぶ必要があります。
| 専門家 | 主な得意分野 | 特徴・メリット | 注意点 |
| 社会保険労務士 | ・日常的な労務管理 ・協定書作成、届出代行 ・就業規則の整備 | ・手続き業務の効率化 ・助成金申請などとの連携 | 依頼形式に応じた費用が発生する |
| 弁護士 | ・法的紛争、訴訟対応 ・労働基準監督署の調査、勧告対応 ・法的リスク判断 | ・トラブル発生時の交渉・代理 ・法的リスクの高い場面に強い | 依頼内容により費用が高額になる場合がある |
専門家を選ぶ際は、相談内容の緊急性や専門性、予算、過去の実績などを総合的に比較検討しましょう。予防的な労務相談は社労士、既にトラブルが発生している場合は弁護士が適任となるケースが一般的です。
「どこに相談すべきか迷っている」「費用感を知りたい」という方は、以下の記事も参考にしてください。
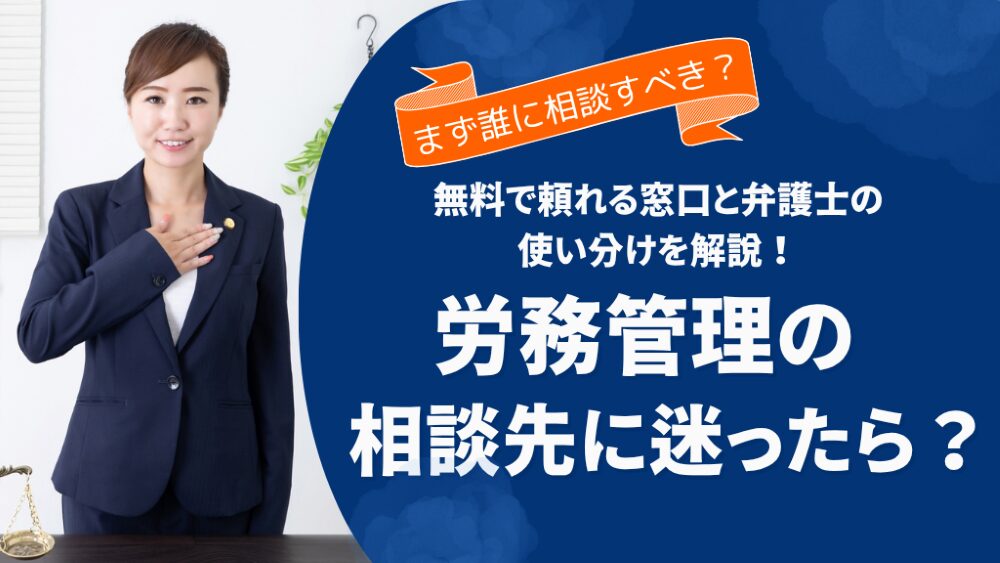
労務管理の相談はどこにすればいい?無料で頼れる窓口と弁護士の使い分けを解説
「従業員から突然『残業代の件で相談があります』と言われて、正直どう答えていいか分からない…」そんな経験はありませんか。 最近、従業員からの相談が増えてきて『このままで大丈夫だろうか?』と不安を感じている経営者の方も多いか […]
まとめ
労働基準法36条(いわゆる「36協定」)は、企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる際の法的な前提条件を定めた、非常に重要な制度です。適切に協定を締結し、労働基準監督署に届け出ていなければ、残業そのものが違法となり、企業は懲役刑・罰金・企業名公表など、重大なリスクに直面します。
また、2024年以降は法改正により時間外労働の上限規制がさらに厳格化され、特別条項付き協定を結ぶ場合も、年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内など、細かな条件を守らなければなりません。
この記事では、36協定の種類・締結手順・届出方法から、よくある記入ミス、違反時の罰則、残業管理の実務ポイント、さらには専門家相談の必要性まで網羅的に解説しました。
自社のリスクを最小化するためには、以下の対策が不可欠です。
- 現在の36協定の内容と運用状況を定期的に見直すこと
- 正確な労働時間管理を行い、適法に残業代を支払うこと
- 必要に応じて、社労士や労務に強い弁護士のサポートを受けること
労働時間管理や法令対応に不安がある企業は、専門家への相談を早めに検討してください。適正な36協定運用が、企業の信頼性向上と労働トラブル防止への第一歩となります。
参考:【実話】なぜゲーム会社は残業が多いの?残業時間とその原因を解説します
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ
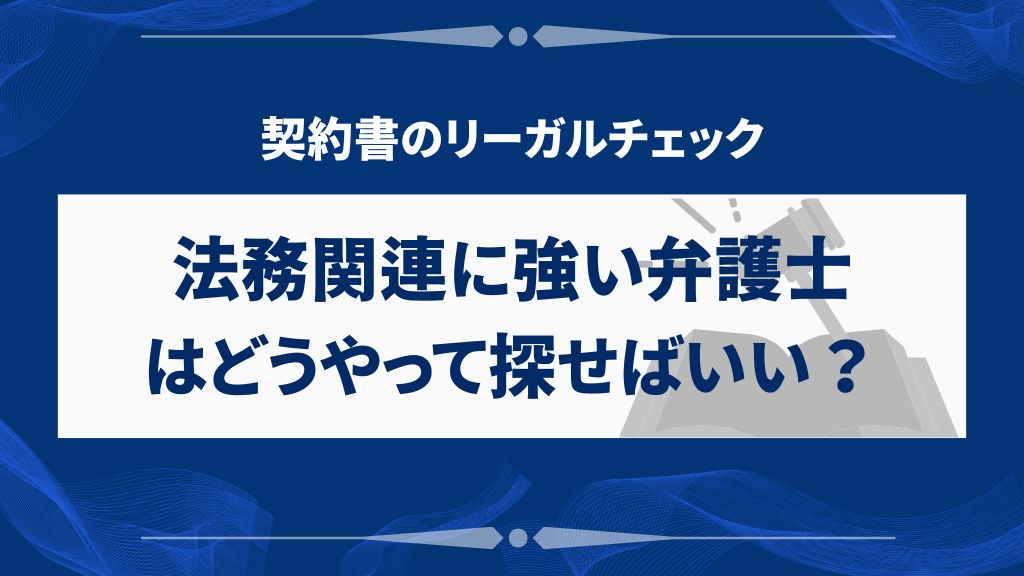
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












