会社はどうやって倒産させる?破産手続きの種類や費用相場、弁護士に依頼するメリットを徹底解説
臨床法務
2025.04.26 ー 2025.05.08 更新

会社の資金繰りが限界を迎えると、「倒産」という選択肢を考えざるを得なくなります。しかし、会社が倒産すると取引先や金融機関への支払いが滞り、従業員の雇用や自身の生活へ大きな影響を及ぼす可能性があります。
会社倒産を法的に進めるためには、法人破産・民事再生・私的整理などいくつかの選択肢があり、それぞれ手続きの流れや必要な対応が異なります。こうした対策は専門知識が必要になるため、慎重に検討しなければいけません。
そのため、弁護士に依頼することで手続きをスムーズに進められ、不要なリスクを回避しやすくなります。
この記事では、会社の倒産手続きの種類や流れ、弁護士に相談するメリット、費用相場について解説します。「破産すべきか迷っている」「手続きをどこから始めればいいのか分からない」と悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>会社破産とは?

会社破産とは、法人が多額の債務を抱え、事業継続が困難になった際に行う法的な清算手続きです。資金繰りが破綻し、資産よりも負債が上回る状況では、裁判所を通じて破産手続きを進めることになります。
この手続きでは、企業の全資産を調査・評価し、債権者への公正な分配が行われます。会社破産は法人としての事業を終える重大な決断であり、社会的影響も大きいため、慎重な対応が求められます。
中でも書類作成や手続きにおいては専門的な知識が求められるため、弁護士に依頼することで、手続きを適切かつ円滑に進めることが可能になります。
破産手続きは、会社が倒産の危機に陥った際の最終手段として選択肢にあげられます。つまり、安易に破産を選ぶのではなく、破産を回避するためにさまざまな解決方法を模索する必要があります。
倒産手続きの種類
倒産手続きには複数の方法があり、企業の状況や目的に応じて適切な手段を選ぶことが重要になります。主な手続きとしては、以下の4つが挙げられます。
- 破産:法人としての活動を終了させるための手続き
- 民事再生:事業継続を前提とした再建型の手続き
- 任意整理:債権者との個別交渉によって返済条件を緩和する手続き
- 特別清算:倒産後の負債整理で必要な手続き
企業が債務超過に陥り、返済能力を完全に喪失した場合には、破産手続きが選ばれます。強制力があるため、すべての債権者が対象となる点が特徴です。
一方、民事再生は返済が困難でも一定の収益が見込まれる場合に利用され、債務の一部免除や返済条件の変更によって再建を図ります。裁判所の監督下で進行しますが、経営権は原則として現経営陣が維持します。
任意整理は、事業を継続したいが破産や民事再生を避けたい場合に活用されます。交渉が成立すれば柔軟な対応が可能ですが、すべての債権者の合意が必要であり、法的拘束力は限定的です。
そして、特別清算は負債の整理が必要な場合に選ばれる手続きです。通常清算と異なり、債務超過などの事情がある際に裁判所の監督のもとで実施されます。破産ほど厳格ではなく、債権者との協議によって柔軟に進められる点が特徴です。
これらの手続きはいずれも法的な知識と判断が求められるため、専門の弁護士に相談することで、リスク回避と円滑な対応が可能です。
会社破産が選ばれるケース
会社破産が選ばれるのは、事業の継続が困難となり、負債の返済が現実的でなくなった場合です。具体的には、以下のような状況が想定されます。
- 売上の大幅な減少
- 取引先の倒産
- 過剰な借入による資金繰りの悪化
- 金融機関からの追加融資が見込めない
こうした状況が組み合わさることで、事業を続けるための資金が確保できなくなり、資産よりも負債が上回る債務超過に陥ってしまいます。企業は破産に追い込まれます。
また、再建を目的とした民事再生では再建計画の見通しが立たない場合や、債権者との合意形成が困難と判断された場合も、最終的な手段として破産が選ばれやすいです。破産手続きでは裁判所の監督のもとで企業の資産を処分し、債権者に公平な分配が可能になります。
破産は法人を終了させるための手続きであり、経営者にとっては避けたい方法と言えるでしょう。しかし、破産によって経営者の法的責任や再起の道も明確になるため、無計画な継続よりも早期の破産決断が望まれる場面も少なくありません。
会社経営者がするべき破産手続き

破産を決断した場合、経営者は以下のような手続きを行う必要があります。これらのプロセスは破産手続きを進める上で必須とされています。
- 弁護士へ相談する
- 破産を債権者に通知する
- 従業員の解雇・テナントの立ち退きに関する手続きを行う
- 申立書や必要書類を用意する
- 裁判所に破産申立てを行う
- 債権者集会に参加する
それぞれの手続きについて解説していきます。
弁護士へ相談する
会社が破産を検討する際、最初に行うべき手続きは弁護士への相談です。
破産手続きは法律に基づいて厳格に進められるため、専門的な知識や経験がなければ適切な判断が難しく、結果的に債権者とのトラブルや不利益を招く可能性があります。弁護士に相談することで、現時点の財務状況を把握し、破産手続きが最適な選択かどうかから判断してもらえます。
また、法人破産以外の選択肢である民事再生や任意整理の可能性についても、客観的なアドバイスを受けることが可能です。さらに、手続き開始後の複雑な対応も、弁護士のサポートがあれば円滑に進めることができます。
早期の相談は準備期間を確保するうえでも重要です。破産という選択肢が浮かんだ時点で、法律事務所や弁護士に相談するようにしましょう。
破産を債権者に通知する
弁護士への相談を経て破産手続きに進むことが決定した後は、その旨を債権者へ通知します。通知手続きは、会社が法的整理に入ることを正式に伝えるものであり、債権者にとっても自身の債権がどのように扱われるかを把握する役割を果たします。
通知は弁護士を通じて書面で行われるのが一般的で、以下のような内容を記載します。
- 会社が破産申立ての準備を進めている旨
- 申立て予定日
- 今後の流れ
債権者にとっても破産は大きな影響を及ぼすため、誠実かつ正確な情報提供が求められます。通知を怠ると、信頼関係の悪化や法的なトラブルを招くおそれがあるため、早い段階での対応が不可欠です。
債権者が会社破産を認識した時点で、次の手続きに進みます。
従業員の解雇・テナントの立ち退きに関する手続きを行う
破産手続きに進む過程で避けて通れないのが、従業員の解雇およびテナント物件の立ち退きに関する対応です。
会社が事業継続を断念し、資産を清算する段階に入ると、従業員との雇用契約を終了させる必要があります。この場合は労働基準法に基づき、原則として少なくとも30日前の解雇予告が必要であり、予告期間を設けない場合は解雇予告手当を支払う義務が発生します。
また、未払い給与や退職金、社会保険の手続きも迅速に行わなければなりません。
加えて、事務所や店舗などを賃借している場合は、賃貸借契約の解約手続きと物件の明け渡しが必要です。貸主との協議で契約解除日を調整し、原状回復義務を果たさなければいけません。
これらの手続きは、破産申立ての前後に行うべき対応であり、従業員や関係者への誠実な対応が企業としての社会的責任にも直結します。
申立書や必要書類を用意する
会社破産の正式な手続きに進むには、裁判所へ提出する申立書や各種必要書類の準備が必要です。弁護士と連携しながら事実関係を整理し、正確な情報に基づいた書類を整えることが求められます。
申立書には、以下のような情報を記載します。
- 会社名
- 代表者
- 資産と負債の状況
- 破産に至った経緯
また、必要書類としては以下のようなものが必要です。
- 財務諸表
- 債権者一覧
- 取引履歴
提出書類が不備であったり、内容に虚偽があった場合は、申立て自体が却下されるかもしれません。また、破産申立てに先立って、裁判所との事前相談が必要となるケースもあり、地域によって手続きの詳細が異なるケースもあります。
これらの準備を円滑に進めることで、申立て後の手続きがスムーズに運び、債権者への配当や清算処理も的確に行われます。
裁判所に破産申立てを行う
必要書類の準備が整った後は、裁判所へ破産申立てを行います。申し立ては法人破産の正式な開始を求める手続きであり、弁護士を通じて地方裁判所に申立書類が提出されます。
申立てが受理されると、裁判所は書類内容を審査し、破産手続き開始の可否を判断します。この審査においては、債務超過の状態・支払い不能であるかどうかが重視され、形式的な不備がないかも確認されます。
審査の結果、問題がなければ破産手続き開始決定が下され、同時に破産管財人が選任されます。この破産管財人が今後の資産処分や債権調査を担うこととなり、企業としての財産管理権は管財人に移ります。
債権者集会に参加する
裁判所による破産手続き開始決定後、企業側は債権者集会に参加しなければいけません。
債権者集会とは、破産管財人の業務報告や資産処分の進捗、債権の調査結果などを債権者に説明する場であり、手続きの透明性と公正性を確保するために設けられます。集会は裁判所の指定日に開催され、破産した企業の代表者も原則として出席が求められます。
債権者は、自身の債権状況や配当見込みに関する説明を受けたり、破産管財人への質問や意見表明を行うことができます。また、異議のある債権や特別な利害関係が存在する場合には、集会内での議論が判断材料となることもあります。
企業側としては、誠実な対応と情報提供を心がけることが、信頼関係の維持につながります。債権者集会は一度だけでなく、必要に応じて複数回行われることもあり、破産手続き全体の進行する上で重要なプロセスです。
会社の倒産を弁護士に相談するべき理由

会社の倒産を検討する際、最初に弁護士へ相談することが非常に重要です。弁護士に相談せず破産を進めると、弁護士に相談することで、現状分析とともに最適な手続きの選定が可能になります。
特に、問題が発生した時点で相談するようにしましょう。費用や手間を惜しんで後回しにしていると、会社が再建不可能な状態まで陥る可能性もあります。
以下では、弁護士に相談しないリスクや相談のタイミングについて解説していきます。
破産手続きを弁護士なしで行うリスク
破産手続きを弁護士なしで進めることは、企業にとって大きなリスクを伴います。
破産は法律に基づく複雑な手続きであり、専門的な知識と経験が求められます。弁護士の支援がない場合、申立書の内容不備や手続き上のミスによって、破産開始決定が遅れる、もしくは却下されるおそれがあります。
また、債権者への通知や従業員の解雇手続きなどを誤れば、法的責任を問われる可能性もあります。破産に至る経緯や資産の取り扱いに問題があれば、不当利得や詐害行為と見なされ、経営者個人への追及が及ぶかもしれません。
弁護士の関与がないことで、こうしたリスクが生じやすく、企業と関係者の損失が拡大することにつながります。これらのリスクを回避するためには、弁護士への相談が不可欠です。
会社破産を相談するベストなタイミング
会社破産を弁護士に相談するタイミングとしては、資金繰りが慢性的に悪化し、返済や給与の支払いに支障が出始めた段階がベストです。売上の減少や金融機関からの借入が困難になり、将来的な事業継続に不安を感じた時点で、相談するのがおすすめです。
破産は事後対応ではなく、事前準備が成否を左右する法的手続きであるため、手遅れになる前に相談することが大切になります。
早めに弁護士に相談することで、破産となった場合の解雇手続きや債権者への対応も計画的に進められるため、企業としての社会的責任を果たすうえでも有利に働きます。資金が底をついてからでは選択肢が限られるため、経営危機を感じた段階での早期相談を心掛けましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。会社の倒産について弁護士に相談したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>会社破産にかかる費用はどれくらい?

会社破産にかかる費用は、企業の規模や資産状況、債権者の数によって異なります。破産の一連の手続きでは、以下の種類の費用が発生します。
- 弁護士費用:弁護士に支払う費用、依頼料
- 予納金:裁判所に納める費用
弁護士費用は事案の複雑さにより変動しますが、中小企業の場合で50万~150万円程度が相場とされています。
これに加えて必要となるのが予納金で、これは破産管財人の報酬などに充てられます。債権者の数や資産の有無に応じて、20万円から最大で100万円以上になることもあります。特に資産がある場合や債権者が多い場合は、管財事件として扱われるため予納金が高額になります。
なお、弁護士に相談すれば、会社の財務状況に応じた費用の見積もりや分割払いの相談も可能です。
裁判にかかる費用を抑える方法
会社破産に伴う裁判費用を抑えるには、以下のような方法や準備が有効です。
- 弁護士への早期
- 必要書類の準備
- 複数の法律事務所で見積もりを取る
相談を早期に行うことで、不要な法的トラブルを回避し、手続きの簡素化が可能です。
資産が少なく債権者も限定される場合、「少額管財」や「同時廃止」といった簡易な手続きが認められる可能性があり、裁判所へ納める予納金を抑えられることがあります。一般的な管財事件では50万円以上の予納金が必要ですが、少額管財では20万円程度で済むケースもあります。
重要なのは、弁護士への負担を軽減することです。自社で対応できる業務、たとえば書類の準備や整理をしておけば、弁護士は専門業務のみに対応できます。これによって、費用を軽減できる可能性があります。
これらの対策を講じることで、限られた資金の中でも適切に破産手続きを進めることが可能となります。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。会社の倒産について弁護士に相談したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>破産手続きを行う前に知っておくべき情報

破産手続きを始める前だと、「これからどうなってしまうのか」と不安を抱くのは当然です。そのため、以下のような情報を手続き開始前に知っておくと、見通しを立てやすくなります。
- 代表者は破産後どうなるのか?
- 弁護士と司法書士どちらに依頼するべき?
- 倒産が完了するまでにどれくらい時間がかかる?
それぞれの疑問や不安について回答していきます。
代表者は破産後どうなるのか?
会社が破産した場合、その代表者自身も今後の生活や事業活動に大きな影響を受けることがあります。
ただし、会社と代表者は法的観点から見ると別の人格であるため、法人破産を行っただけでは代表者個人が直ちに破産するとは限りません。代表者が会社の債務に個人保証をしていない場合、その責任は会社にとどまり、代表者個人の財産が差し押さえられることはありません。
しかし、多くの中小企業では代表者が金融機関や取引先の借入に連帯保証しているケースが多く、会社が支払不能になると、債務の返済を個人に請求される可能性があります。その場合、代表者も個人として破産申立てを行う必要が生じます。
さらに、破産後一定期間は会社役員や士業としての就任に制限がかかるなど、法的な影響も発生します。ただし、免責が認められれば債務の支払い義務は消滅します。
弁護士と司法書士どちらに依頼するべき?
破産手続きを検討する際、弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきかを理解していなければいけません。結論から言うと、破産手続きでは弁護士に依頼するのがおすすめです。
司法書士は一定の法的手続きを代行できますが、代理権の範囲は限定されており、裁判所での代理や複雑な債権者対応はできません。一方、弁護士は破産に関わるあらゆる法的対応を一括で担えるため、法人破産の場合には弁護士への依頼が原則となります。
特に企業の資産や債務が多岐にわたる場合、専門的な視点から判断が必要な場面が多く、司法書士では対応が難しいのが現実です。また、破産後のトラブルや経営者への法的影響についても、弁護士であれば適切なアドバイスと対応が可能です。
司法書士は弁護士に比べて安い費用で対応してもらえますが、結果的に手続きが滞ったり再申立てが必要になるリスクもあります。会社破産においては、弁護士に依頼するのが最適と言えるでしょう。
倒産が完了するまでにどれくらい時間がかかる?
会社が破産手続きを開始してから完了するまでの期間は、一般的に6か月から1年程度が目安とされています。
資産が少なく、債権者の数も限られているケースでは、早期に手続きが終了する「同時廃止型」となり、申立てから数か月で完了することもあります。一方で、破産管財人が選任されるケースでは、財産の調査・売却、債権者への配当といった手続きが必要になるため、1年を超えることもあります。
さらに、債権者の異議申し立てや訴訟が発生した場合には、それに対応するための時間がかかる可能性もあります。詳細な期間については対応する弁護士によって異なるため、契約前に確認しておきましょう。
まとめ
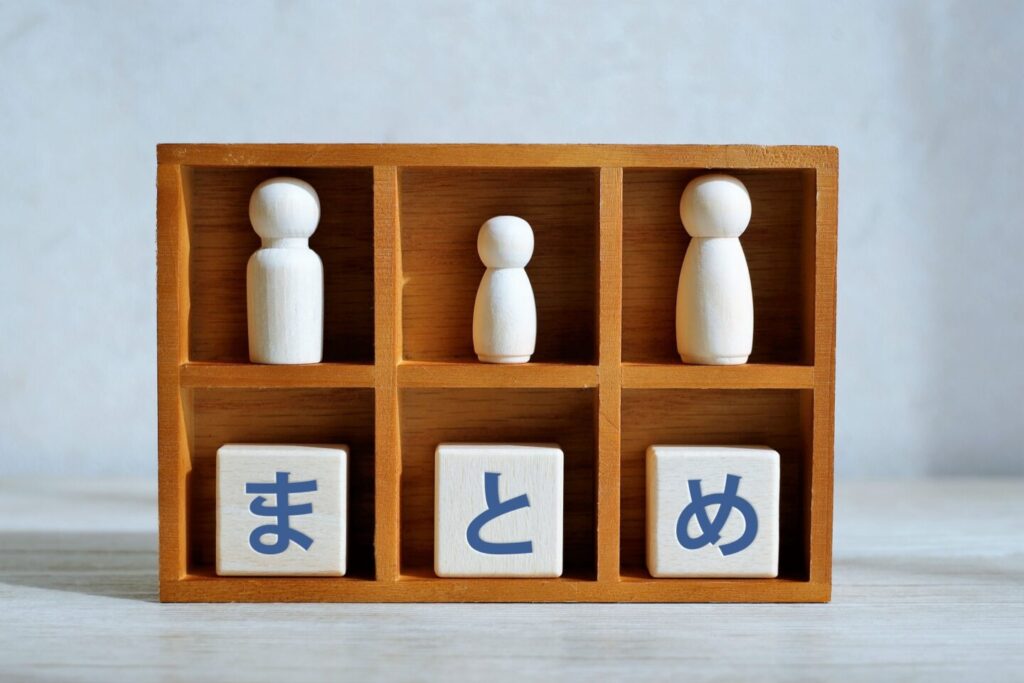
会社が倒産する場合、破産申請という法的手続きが必要です。これには専門知識が求められるため、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に依頼しなければいけない法律はありませんが、依頼しない場合のリスクを考慮すると、費用がかかってでも相談するべきでしょう。
また、弁護士は破産以外の解決策も提案してくれます。「もうどうしようもない」と思っても、弁護士に相談することで再建できる可能性もあるため、まずは法律事務所に足を運んでみることが大切です。気軽に相談できる弁護士を見つけ、破産が最適かどうかを検討することから始めてみましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。会社の倒産について弁護士に相談したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












