労務訴訟とは?企業が訴えられる原因と適切な対応策を徹底解説
訴訟・紛争解決
2025.02.25 ー 2025.03.06 更新

労働環境の変化や法改正が進む昨今ですが、企業と従業員の間で労務トラブルが発生する事例は少なくありません。労務トラブルが発生した場合、従業員が労務訴訟を起こす可能性があります。
労務訴訟は法的な手続きが必要になるため、企業側としても適切な対応が求められます。お互いが納得できる着地点を探すには、まず労務訴訟について理解を深めることが重要です。
そこで本記事では、労務訴訟の種類や訴訟時の対策方法について解説していきます。
労務訴訟とは?

労務訴訟とは、企業と従業員の間で発生した労働条件や雇用に関するトラブルについて、裁判所を通じて解決を図る法的手続きのことを指します。
主に未払い賃金の請求、不当解雇の無効確認、ハラスメントに対する損害賠償請求などが争点となることが多く、労働者が原告となって企業を相手取るケースが一般的です。
労務訴訟は、地方裁判所または簡易裁判所で審理され、企業側は証拠をもとに主張を整理し、法的な対応を取る必要があります。訴訟の進行は、労働者が訴状を提出することから始まり、企業側が答弁書を提出した後、口頭弁論や証拠調べを経て判決が下されます。
通常、労務訴訟の解決には半年から2年以上かかることもあり、企業にとっては時間的・金銭的負担が大きくなります。
労務訴訟は労働審判と異なり、原則として判決まで争われるため、和解が成立しない限り最終的な裁判所の判断が必要となります。
労務訴訟の種類

労務訴訟には、以下の3つの種類があります。
- 労働審判
- 民事訴訟
- 仮処分
それぞれの労務訴訟について解説していきます。
労働審判
労働審判とは、労働者と企業の間で生じた個別労働紛争を解決するための制度であり、労働審判法に基づいて地方裁判所で行われます。一般的な裁判と異なり、原則として3回以内の審理で結論が出るため、労務トラブルを早期に解決できるのが特徴です。
労働審判は、労働者が企業に対して賃金未払い、解雇の無効、ハラスメントによる損害賠償などを求める際に利用されることが多く、訴訟よりも柔軟な解決が可能です。審判手続きでは裁判官1名と労働審判員2名が審理を担当し、当事者双方の主張や証拠を基に解決策を提示します。
労働審判は訴訟よりも費用や時間の負担が少なく、労働者・企業双方にとってメリットがあります。しかし、証拠の整理や適切な対応が求められるため、企業側としては事前の準備が必要です。
民事訴訟
民事訴訟は、労務訴訟の中でも最も一般的な手続きであり、労働者と企業の間で発生したトラブルを裁判所が法的に解決する制度です。労働者が企業に対して、未払い賃金の請求や不当解雇の無効確認、パワハラやセクハラによる損害賠償請求などを求める場合に利用されます。
企業側は、労働契約や就業規則の適用が適正であったことを証拠に基づいて主張し、裁判での争いに対応する必要があります。この手続きは労働審判とは異なり、和解に至らなければ判決まで争われるため、企業にとってはリスクが高まります。
民事訴訟は、労働者が裁判所に訴状を提出することで開始され、企業側はこれに対する答弁書を提出します。その後、証拠調べや口頭弁論が行われ、裁判官が双方の主張を整理した上で判決を下します。
訴訟の期間は通常半年から2年程度かかることが多く、双方にとって時間的・費用的負担が大きい点が特徴です。
仮処分
仮処分とは、労務訴訟において労働者が救済を求める際に利用される手続きです。裁判の本案判決が確定する前に、一定の権利を暫定的に保護することを目的としています。
解雇の効力を争う場合や、未払い賃金の支払いを求めるケースなどで活用されることが多く、訴訟の長期化による労働者の不利益を回避する手段としての役割を果たします。
仮処分の手続きは、労働者が裁判所に対して申立てを行うことで開始されます。裁判所がこれを認めると、企業に対し解雇された従業員の地位の仮の保全や未払い賃金の仮払い命令などを下します。
仮処分の決定は迅速に行われることが多く、数週間から数カ月で結果が出るため、労働者にとっては早期救済の手段として有効です。
ただし、仮処分はあくまで暫定的な措置であり、本訴訟における最終判断とは異なります。企業としては、仮処分の申立てに対して適切な反論を行い、必要に応じて本訴で争う準備を進めることが求められます。
企業が労務訴訟で訴えられる原因

労務訴訟は企業が従業員に訴えられる手続きであるため、企業としては避けたい事案だと思われます。労務訴訟が発生する原因として、以下の要因が挙げられます。
- 労働条件
- 雇用関係
それぞれの原因について解説していきます。
労働条件
労働条件とは、労働者が企業に雇用される際に適用される以下のような取り決めを指します。
- 賃金
- 労働時間
- 休暇
- 福利厚生
これらの条件は、労働基準法をはじめとする労働関連法規によって一定の基準が定められており、企業はこれを遵守する義務があります。しかし、労働条件に関する不備や不当な変更が原因で、労務訴訟に発展するケースも少なくありません。
企業が労務訴訟で訴えられる主な要因として、以下のような問題があります。
- 賃金未払い
- 長時間労働
- 違法な残業代の未払い
- 労働契約の不適切な変更
特に、サービス残業や時間外労働に関するトラブルは深刻な問題となることが多く、労働者が企業に対して訴訟を提起するケースが増えています。契約社員やパートタイム労働者が不当な労働条件を課された場合、労働契約法違反を理由に争われることもあります。
雇用関係
雇用関係に関するトラブルは、企業が労務訴訟で訴えられる主要な原因の一つです。雇用契約の締結や終了に伴い、企業と労働者の間で認識の違いが生じることで、労働者が法的手段に訴えるケースが発生します。
解雇に関する訴訟では、企業が労働者を一方的に解雇した場合に、その解雇が「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を満たしているかが問われます。
労働契約法では、不当解雇が無効と判断された場合、企業は労働者の地位を回復させる義務を負い、未払い賃金の支払いを命じられることがあります。
また、雇用契約の内容に関するトラブルも少なくありません。試用期間の終了後に本採用を拒否された労働者が不当な扱いを受けたと主張するケースや、雇用契約書の内容と実際の労働条件が異なる場合、企業側に契約違反を問う訴訟が提起されることがあります。
企業としては、適切な手続きを経て雇用契約を締結し、労働者への説明責任を果たすことが不可欠です。
労務訴訟を起こされた企業がやるべき対応

労務訴訟を起こされた場合、企業としては初期対応として以下のようなものが必要です。
- 専門家への相談・依頼の検討
- 訴状内容を精査する
- 関係者間での情報共有
- 情報漏洩の防止
それぞれの対応について解説していきます。
専門家への相談・依頼の検討
労務訴訟では法律や判例に基づく専門的な知識が求められるため、企業が独自に対応しようとすると、不利な立場に追い込まれる可能性があります。
そこで訴訟の初期対応を誤ると、裁判の進行に悪影響を及ぼすこともあるため、早い段階で弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することが推奨されます。
弁護士に依頼することで、訴訟の見通しを適切に把握し、企業の立場を守るための戦略を立てることが可能になります。また、社内の業務負担を軽減できるメリットもあります。
労務訴訟は、判決が確定するまでに長期間を要することが多いため、費用対効果を考慮しながら対応することが重要です。企業の規模や訴訟内容に応じて、弁護士の関与の度合いを調整し、適切なサポートを受けましょう。
訴状内容を精査する
訴状とは、労働者が裁判所に提出する正式な書類です。企業側へは裁判所を経て通知されます。
訴状には、労働者が主張する事実関係や請求内容、法律的根拠が記載されています。そのため、従業員側の認識と相違がないかを確認し、具体的な請求額や争点を明確にすることが重要です。例えば未払い賃金の請求であれば、労働者が主張する金額の根拠を精査し、実際の勤務実態と比較する必要があります。
訴状には証拠が添付されることも多く、これらの内容を分析することで、企業にとって不利な要素があるかどうかを判断できます。企業はこれに対し、反証となる証拠を整理し、労働者の主張が誤っている点を準備を進めることが求められます。
関係者間での情報共有
訴訟対応は法務部門や人事部門だけでなく、経営陣や現場の管理職など複数の関係者が関与するため、関係者全員が統一した対応を取る必要があります。情報共有が不十分だと、企業側の主張に矛盾が生じたり、対応の遅れるリスクが高まります。
企業は労働者から訴状が届いた段階で、事実関係を確認し、関係者に共有することが求められます。この際、社内のやり取りや関係書類を整理し、弁護士とも連携しながら法的リスクを洗い出す必要があります。
また、和解交渉を進めるのか、裁判で争うのかといった基本的な方針について協議し、関係者全員がその方針に沿って行動することが必要です。労務訴訟は企業の信用にも関わるため、外部への情報発信についても統一した対応を取ることが求められます。
さらに、従業員や管理職へのヒアリングを実施し、客観的な証拠を収集することも重要です。現場の担当者と連携し、証言内容や証拠資料を整理することで、裁判における企業側の主張を明確にすることができます。
情報漏洩の防止
労務訴訟では、企業の内部情報や従業員の個人情報が訴訟資料として扱われます。そのため、訴訟中に機密情報が外部に漏洩すると、経営上のリスクが高まり、企業の評判にも大きな影響を及ぼします。
情報を適切に管理するには、訴訟に関する情報の管理体制を強化し、関係者以外が訴訟の詳細にアクセスできないようにします。情報共有は必要最小限にとどめ、社内でのアクセス権限を厳格に設定しましょう。
また、訴訟に関する資料は適切に管理し、漏洩リスクを最小限に抑える必要があります。紙の資料であれば施錠できる保管庫に保管し、電子データの場合はアクセスログを記録するシステムを導入するなど、物理的・技術的な対策を講じることが有効です。
万が一情報漏洩が発生した場合には、速やかに原因を特定し、影響範囲を最小限に抑えるための対応を講じる必要があります。企業の信頼を守るためには、慎重な情報管理が不可欠です。
労務訴訟の相談は弁護士がおすすめ
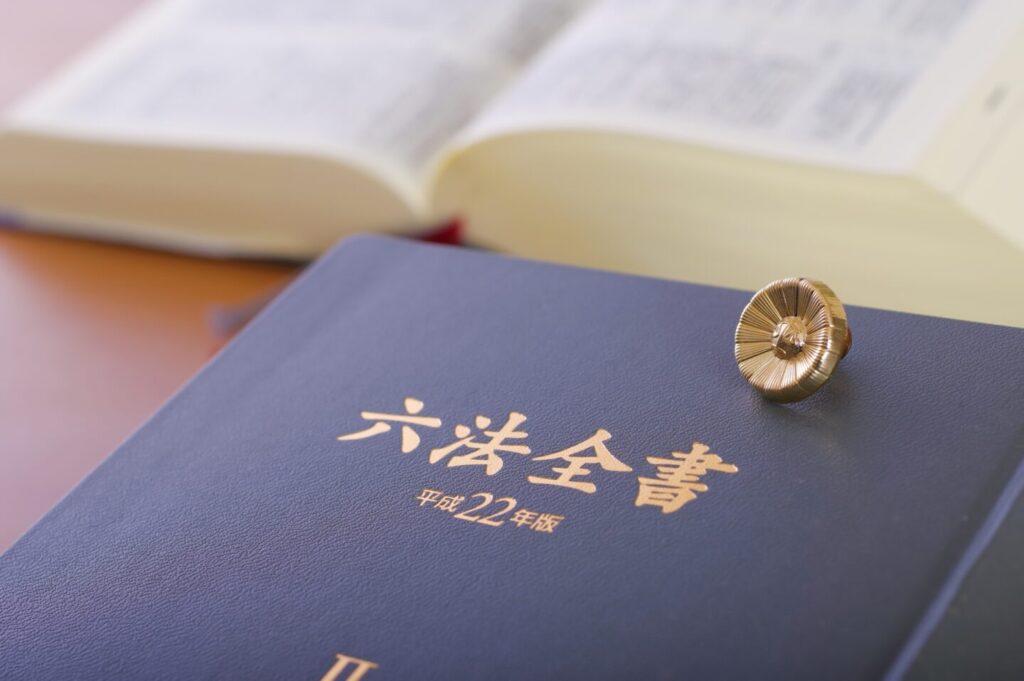
労務訴訟に関する相談は、専門的な知識と経験を持つ弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、訴訟の見通しを把握し、企業のリスクを最小限に抑える戦略を立てることができます。また、訴訟手続きに関する適切なアドバイスを受けることで、不必要な対立を避け、円滑な解決につなげることが可能になります。
和解の選択肢を検討する際にも、弁護士の交渉力が有利に働くため、企業側にとって大きなメリットとなります。
労務トラブルは企業の経営に大きな影響を及ぼすため、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を講じるようにしましょう。
企業が弁護士に依頼するタイミング
企業が弁護士に依頼するタイミングは、できるだけ早い段階で相談してください。訴訟の可能性が高まった場合は、速やかに弁護士に依頼することで、企業のリスクを最小限に抑えることができます。
まず、従業員から未払い賃金の請求や不当解雇の主張が届いた時点で、弁護士に相談することが望ましいです。また、労働基準監督署から是正勧告を受けた場合も、弁護士のアドバイスを受けながら適切な対応を取ることで、法的リスクを回避できます。
労働審判や訴訟を起こされた際にも、できるだけ早く弁護士を依頼し、適切な反論を準備する必要があります。訴訟の進行は専門的な法律知識が求められるため、企業が独自に対応するのは困難です。
まとめ
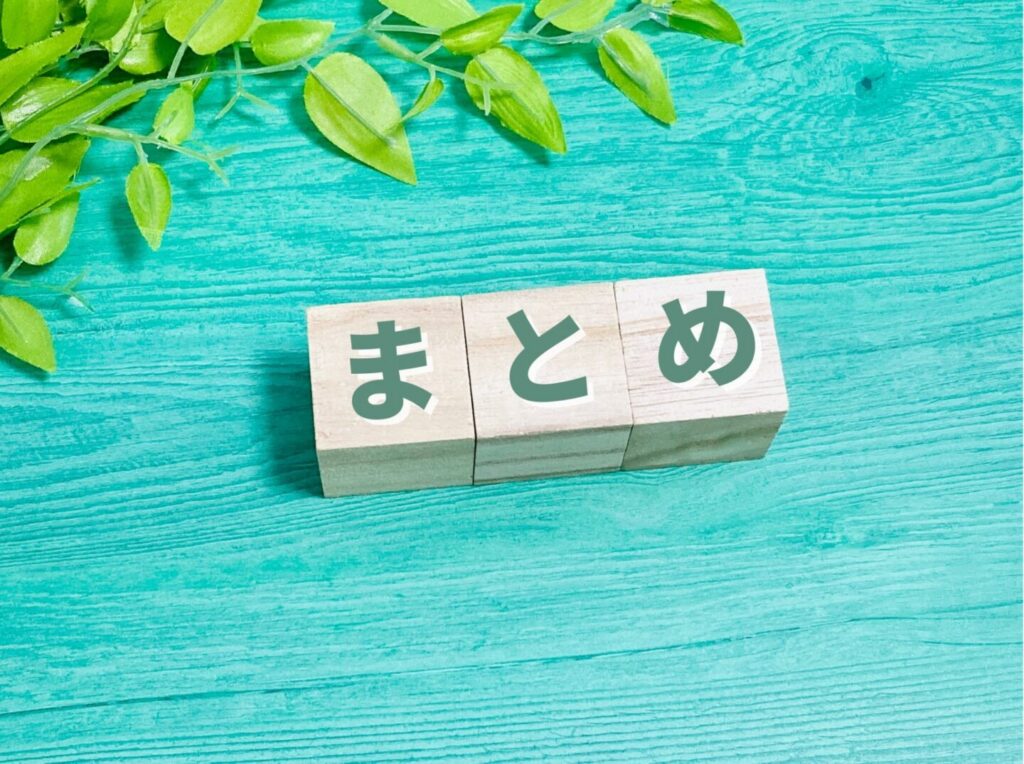
従業員が労働条件に対して訴訟を起こせる労務訴訟ですが、企業にとっては避けたいものです。訴訟関連の手続きに時間を取られるだけでなく、企業の信用にも悪影響を及ぼすため、訴訟が発生した時点で迅速に対応する必要があります。
しかし、適切な対応を目指すには専門的な知識が求められるため、弁護士に相談するのがおすすめです。労務訴訟をスムーズに解決し、従業員との和解を目指すのであれば、弁護士に依頼して労務訴訟に対応しましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。労務訴訟に対応できる弁護士を探している方は、法務救済を利用してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












