商標権侵害の疑いがある場合の訴訟手続きや実際の判例、対応策を徹底解説
訴訟・紛争解決
2025.02.25 ー 2025.03.06 更新
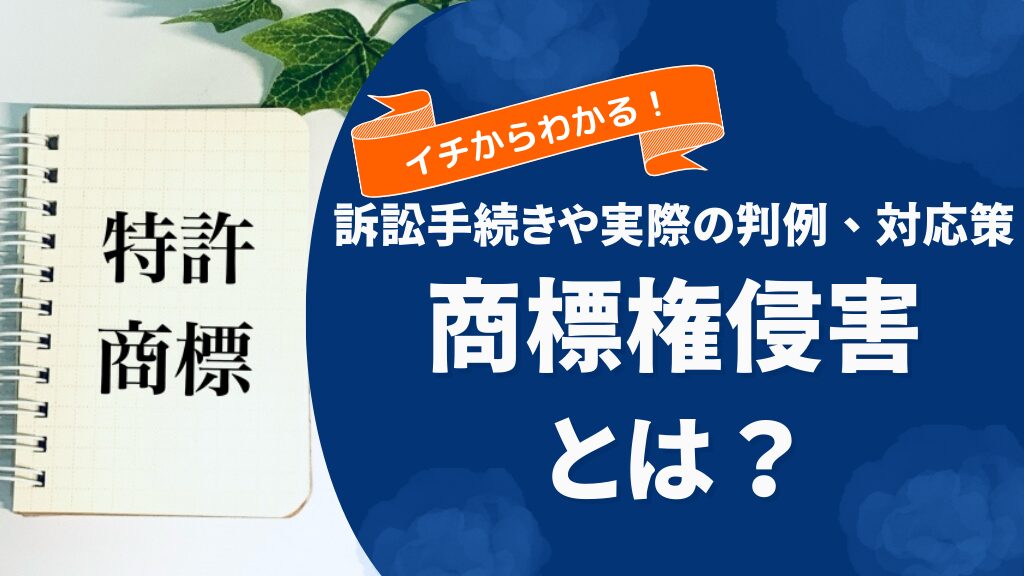
企業の経営資産として重要なブランドを守る商標権。価値が高まることで大切な資産になりますが、一方で商標権侵害というリスクに直面することがあります。他社や個人に商標権を侵害された場合、法的措置で対抗することができます。
しかし、どのようなケースが商標権侵害に該当するのか、また訴訟になった場合の具体的な流れを把握している人は少ないのが実情です。
本記事では、商標権訴訟の流れや対処法、実際の判例について解説します。自社の大切なブランドを守るためにも、商標権の訴訟について理解を深めてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>商標権訴訟とは?

商標権訴訟とは、特定の商標を独占的に使用する権利を持つ商標権者が、その権利を侵害された場合に、侵害者に対して法的措置を講じる訴訟のことを指します。
商標権は、特許庁に商標登録を行うことで得られる知的財産権の一つであり、登録された商標を無断で使用された場合に差止請求や損害賠償請求などの手続きを行うことができます。
商標権訴訟では、過去の判例が重要な判断材料となります。例えば、著名なブランドが類似の商標を使用した企業を提訴し、損害賠償が認められたケースもあります。一方で、商標の使用状況によっては、権利が制限される場合もあります。
企業は自社の商標権を守るために、適切な対応を取ることが求められます。
商標権侵害の判断基準
商標権侵害の判断は、商標の類似性と使用態様を基準に行われます。類似性の評価では、以下の三要素を総合的に検討します。
- 外観
- 称呼
- 観念
商標権訴訟が発生する主なケースは、他社が自社の登録商標と同一または類似の標章を、同一または類似の商品やサービスに使用する場合です。
例えば、有名ブランドのロゴを模倣した商品の販売や、既存の商標と紛らわしい名称で事業を展開する行為が該当します。
さらに、商標の希釈化や名声の毀損といった間接的な侵害も訴訟の対象となることがあります。著名な商標の識別力やブランド価値が低下する行為は、長期的に企業の信用を損なうリスクがあるため、権利者は法的措置を講じることになるでしょう。
商標権訴訟の動向
近年、商標権訴訟の件数は増加しており、企業のブランド価値を守るための知的財産権の保護が重要視されています。特に、インターネットの普及により商標の使用範囲が国境を越えて広がり、企業が商標権侵害のリスクに直面するケースが増えています。
近年の動向として、AIやブロックチェーン技術を活用した商標管理システムの導入が進み、商標の監視や侵害の早期発見が容易になっています。これにより、訴訟に至る前に適切な対応を行うことが可能になり、企業がより迅速に商標権を保護できる環境が整いつつあります。
また、商標権訴訟の対象も多様化しており、従来の商品名やサービス名だけでなく、色彩・音・動きなどの非伝統的商標に関する紛争が増加しています。さらに、SNSやオンラインマーケットプレイスにおける訴訟も注目されており、デジタル時代ならではの商標権侵害の問題が浮き彫りになっています。
一方で、商標権訴訟の長期化や高額化が企業にとって負担となるケースもあり、代替的紛争解決手段(ADR)の活用が進んでいます。今後は、企業が商標権を効率的に保護できる新たな解決策が求められるでしょう。
商標権訴訟の判例

商標権の訴訟事例として有名なのは、以下の4つの事件です。
- OGGETTI事件
- サクラホテル事件
- フレッドペリー事件
- 任天堂事件
それぞれの訴訟概要と判例について見ていきましょう。
【ロゴマークの事例】OGGETTI事件
こちらの判例は、ロゴマークが訴訟対象となった事例です。原告が「OGGETTI」という商標で日用雑貨店を運営しており、被告が「Oggetti」という類似したロゴを使用して商品を販売していたため、被告の行為が自社の商標権を侵害しているとして、ロゴの使用差止めと損害賠償を求めて訴訟を提起しました。
東京地方裁判所は2019年1月31日の判決で、原告の商標「OGGETTI」と被告の使用する「Oggetti」のロゴが類似しており、消費者に混同を生じさせる可能性が高いと判断しました。両者のロゴがイタリア語で「物」を意味する同じ単語でありることから、商標権侵害が成立すると認定されました。
その結果、裁判所は被告に対してロゴの使用差し止めと約50万円の損害賠償を命じました。この判例は、商標の類似性判断において単なる文字の一致だけでなく、デザインや言語的背景も考慮されることを示しています。
【名称類似の事例】サクラホテル事件
商標権訴訟における名称類似の事例として有名なのが、サクラホテルです。原告であるサクラホテルが、自社の登録商標「サクラホテル」に類似した名称を被告が使用しているとして、商標権侵害を主張しました。
東京地方裁判所は令和2年2月20日の判決において、原告の商標と被告の使用する標章は称呼や観念において同一または極めて類似していると判断しました。
さらに、被告の標章には桜の花びらのマークや「桜」「SAKURA」「HOTEL」といった文字が組み合わされており、外観上の差異はあるものの、取引の実情を考慮すると需要者に与える印象は大きく異ならないとされました。
結果として、被告の標章使用は原告の商標権を侵害すると認定され、被告に対して標章の使用差止めと損害賠償が命じられました。
【並行輸入の事例】フレッドペリー事件
商標権訴訟における代表的な事例として、フレッドペリーが挙げられます。この事例では、並行輸入品が商標権侵害に該当するか否かが争点となりました。
最高裁判所は、並行輸入品が商標権侵害とならないための要件として、以下の3つを示しました。
- 当該商標が外国の商標権者またはその許諾を受けた者によって適法に付されたものであること
- 外国の商標権者と日本の商標権者が同一人物、または法律的・経済的に同一とみなせる関係にあり、商標が同一の出所を示すものであること
- 日本の商標権者が直接的または間接的に商品の品質管理を行える立場にあり、輸入品と日本国内の商標権者が提供する商品との間に品質の実質的な差異がないこと
シンガポールのライセンシーが契約上の製造地制限に違反していたため、中国で製造した商品が問題となりました。
最高裁は、この製造地違反が商標の出所表示機能や品質保証機能を損なうと判断し、並行輸入品は商標権侵害に該当すると結論づけました。
【真正品改造の事例】任天堂事件
商標権訴訟における重要な判例の一つに、任天堂株式会社が関与した「真正品改造の事例」があります。
この事例では、任天堂が商標登録している「Wii」や「Nintendo」の商標が付された家庭用ゲーム機「Wii」の内蔵プログラム(ファームウェア)を改変し、正規品以外のアプリケーションを実行可能とした上で、商標をそのままに販売した行為が問題となりました。
これに対し裁判所は、ハードウェア自体に変更がなくとも、ファームウェアの改変により製品の本質的機能が変わり、商標の出所表示機能や品質保証機能が損なわれると判断しました。その結果、被告人の行為は商標権侵害に該当すると認定されました。
この判例は、商標が付された製品の内部ソフトウェアの改変が、商標権侵害とみなされる可能性を示しています。
商標権侵害の訴訟を起こす流れ

商標権の侵害が確認できた場合、企業は法的措置として訴訟を起こすことが可能です。商標権について訴訟を起こす際は、以下のような流れで手続きを進めます。
- 侵害された事実を証明する証拠を集める
- 相手方に警告文を送付する
- 民事訴訟を提起する
それぞれの手順について解説していきます。
侵害された事実を証明する証拠を集める
商標権侵害の訴訟を起こすためには、侵害された事実を証明する証拠を収集することが重要です。商標権侵害の証拠とは、相手が無断で商標を使用していることを示す具体的な資料のことを指し、裁判において権利者の主張を裏付ける役割を果たします。
証拠収集では、侵害が行われている商品の現物や販売サイトのスクリーンショット、広告資料などが有効です。オンライン上での商標権侵害は短期間で削除される可能性があるため、ウェブページのURLや更新履歴などを記録し、証拠として保持しておきましょう。
加えて、第三者による証言や公的機関の調査報告を証拠として活用することも可能です。特許庁の商標登録情報と比較し、侵害品が類似性の高い商標を使用していることを示す資料を準備することで、訴訟における立証を強化できます。
証拠収集の際には、弁護士に事前に相談しておくことで、効率的かつ確実な証拠を集めることが可能です。素早く動き出し、訴訟に有効な証拠を集めましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>相手方に警告文を送付する
商標権侵害が確認できた場合、相手方に対して警告文を送付します。警告文とは、無断使用の中止や違反行為の是正を求める正式な通知であり、訴訟に発展する前の解決手段として広く活用されています。
警告文には、以下のような情報を記載します。
- 商標権の内容
- 侵害の具体的事実
- 要求事項
- 対応期限
例えば、「貴社が販売している○○商品は、当社の商標権を侵害しており、直ちに使用を中止し、販売済み商品の回収を求めます」といった形で、法的根拠を示しながら明確な要求を記載します。
警告文の送付は書面で行うのが一般的であり、内容証明郵便を利用することで、送付の事実や内容を公的に証明することができます。これにより、相手方が後に「警告を受けていない」と主張することを防ぐことができます。
警告文の段階で相手方が商標の使用を中止し、和解に至るケースも多くあります。しかし、対応が得られない場合や、相手方が争う姿勢を示した場合は、次の段階として訴訟の準備を進めることが必要になります。
民事訴訟を提起する
商標権侵害に対して警告文を送付しても相手方が対応しない場合、事訴訟を提起することになります。これにより、侵害行為の差し止めや損害賠償の請求が可能となります。
訴訟を提起するには、まず訴状を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。訴状には、以下の情報を記載します。
- 原告(商標権者)の情報
- 被告(侵害者)の情報
- 侵害の具体的な内容
- 請求の趣旨(差止請求・損害賠償請求など)
- 侵害を証明する証拠
訴訟が開始されると、裁判所が審理を進め、双方の主張や証拠に基づいて判断を下します。商標権については、商標の類似性・商品の関連性・混同の可能性などが主要な争点となり、過去の判例も参考にされます。
商標権侵害が認められれば、被告に対して商標の使用禁止や損害賠償の支払いが命じられます。
商標権侵害を受けた場合の対処法

商標権の侵害が確認された場合、すぐに裁判を提起したいかもしれませんが、手続きや必要書類の用意をしなければいけません。そのため、民事訴訟は即効性のある対処法とは言えないでしょう。
商標権侵害を受けた場合は、以下のような対処をすぐに行うことが重要です。
- 弁護士に相談する
- 差止請求の手続き
- 損害賠償請求・不当利得返還請求を行う
それぞれの対処法について解説していきます。
弁護士に相談する
商標権は専門的な知識を必要とする分野であり、侵害の判断や適切な対処方法を誤ると、企業のブランド価値に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、専門家である弁護士に相談することで、法的根拠に基づいた適切な対応を検討することができます。
弁護士は商標権の侵害状況を整理し、証拠の有効性を精査してくれます。相手方が商標をどのように使用しているのか、その影響による損害の有無などを明確にし、商標登録証や侵害を示す広告・販売資料などの準備をサポートしてくれます。
商標権侵害は迅速な対応が求められるため、侵害の疑いが生じた段階で早めに弁護士に相談することが望ましいです。適切な法的措置を講じることで、ブランド価値の低下を防ぎ、企業の競争力を維持することができます。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。商標権の訴訟について弁護士に相談したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>差止請求の手続き
差止請求とは、商標権を侵害する行為を直ちに中止するよう求める法的措置であり、商標法第36条に基づいて請求することが可能です。
差止請求の手続きは、侵害の証拠を収集することから始めます。具体的には、以下の証拠を確保し、商標権の侵害が明確であることを示す証拠を整えます。
- 侵害品の購入記録
- 広告資料
- 販売サイトのスクリーンショット
- 取引記録
その後、相手方に対して警告文を送付します。警告文を送付しても相手方が対応しない場合、地方裁判所に対して正式に差止請求の訴訟を提起します。
差止請求は、商標権者が自社のブランドを守るために有効な手段ですが、法的手続きには時間とコストがかかるため、慎重に進める必要があります。
損害賠償請求・不当利得返還請求
商標権を侵害された場合、権利者は損害賠償請求や不当利得返還請求を行うことができます。これらの請求は、侵害によって生じた経済的損失を補填し、不正に得られた利益を返還させることを目的としています。
損害賠償請求は、商標権侵害によって発生した売上減少やブランド価値の毀損に対する補償を求めるものです。損害額を立証する方法には、以下のようなものがあります。
- 侵害者の売上高を基に算出する
- 商標権者が本来得られたはずの利益を算出する
- ライセンス料相当額を基準にする
不当利得返還請求は、侵害者が商標権を無断使用することで得た不当な利益の返還を求めるものです。損害賠償請求と異なり、商標権者の損害を証明する必要はなく、侵害者が不当に得た利益を返還する義務があることを立証すれば成立します。
裁判での請求が認められれば、侵害者に対して損害の補填や利益の返還が命じられます。企業が商標権を守るためには、これらの法的手段を理解し、迅速に対応することが重要です。
商標権侵害を防ぐための予防策

商標権訴訟は法的措置として正式な手続きや書類を用意する必要があるため、訴える企業としても負担になるはずです。そこで、以下のような予防策を行っておくことで、商標権が侵害されるリスクを軽減できます。
- 商標調査を行う
- グレーゾーンの商標は使用しない
- 商標権に関する最新の法令をチェックする
それぞれの予防策について解説していきます。
商標調査を行う
商標調査とは、企業が新しい商標を使用または登録する際に、既存の商標権と競合しないかを事前に確認する調査です。
商標調査には、大きく分けて「簡易調査」と「詳細調査」の2つの方法があります。
簡易調査では、特許庁が提供する商標検索システムやオンラインデータベースを活用し、類似する商標がすでに登録されていないかを確認します。しかし、商標の類似性は単純な一致だけでなく、読み方やデザイン、使用する商品・サービスの範囲も考慮されます。
詳細調査では、専門の弁理士や調査会社が国内外の商標データベースを用いて、より精密な分析を行います。商標が類似しているかどうかは専門的な判断が必要となるため、法的なリスクを最小限に抑えるためにも、専門家による調査を活用することが推奨されます。
商標調査を事前に行うことで、企業は商標権侵害のリスクを未然に防ぎ、安全にブランド戦略を進めることができます。特に、グローバル市場で事業展開を考えている企業にとっては、国内外の商標調査を徹底するようにしましょう。
グレーゾーンの商標は使用しない
商標権におけるグレーゾーンとは、他社の商標と類似している可能性がありながら、明確に侵害と断定できない状態を指します。こうした商標を使用すると、後に商標権侵害で訴えられるリスクがあり、企業にとって大きな損害を招く可能性があります。
商標の類似性は、以下のような情報から判断されます。
- 文字の構成
- 発音
- 意味
- デザイン
業界内で認知度の高い商標と類似した名称やロゴを使用すると、消費者の混同を招く恐れがあります。たとえ意図的でなくても、他社の商標と類似していると判断されれば、訴訟の対象となってしまうでしょう。
このようなグレーゾーンの商標を避けることで、法的リスクを未然に防ぐことが可能です。独自性の高い商標を選ぶことで、ブランドを守りながら事業を展開することができます。
商標権に関する最新の法令をチェックする
商標権侵害を防ぐためには、商標権に関する最新の法令をチェックし、適切な対応を取ることが不可欠です。
商標法は、経済の変化や新たなビジネスモデルの登場に伴い改正されることがあり、企業が知らないうちに法規制に違反したり、適切な権利保護を受けられなくなる可能性があります。そのため、最新の法令や判例を把握し、適切な対策を講じることが重要です。
例えば、日本では商標法の改正により、新たに「音」や「動き」などの非伝統的商標が登録可能となるなど、保護対象が拡大しています。これにより、企業は自社のブランド戦略を見直し、商標登録の範囲を広げることで、侵害リスクを低減できます。
最新の法令や判例をチェックする方法として、特許庁や法務省のウェブサイトを定期的に確認することが有効です。また、商標専門の弁護士や知財コンサルタントに相談することで、最新の規制や判例をふまえたアドバイスを受けることができます。
まとめ

商標権が侵害されることは、企業にとって大きな損害であり、最優先で対処すべきです。民事訴訟や損害賠償請求を起こすことで、相手方の商標利用を差し止めることができます。
訴訟での解決を目指す場合は、弁護士に依頼しましょう。弁護士と訴訟を進めることで、手続きの負担を軽減できるだけでなく、裁判でも有利に進められるようになります。まずは弁護士や法律事務所に相談し、解決の方向性を共有してから訴訟に向けて動き出しましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。商標権侵害に対する訴訟を検討している方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












