労働審判が訴訟に移行するのはどんなとき?手続きの流れと注意点をわかりやすく解説
訴訟・紛争解決
2025.07.06 ー 2025.07.18 更新
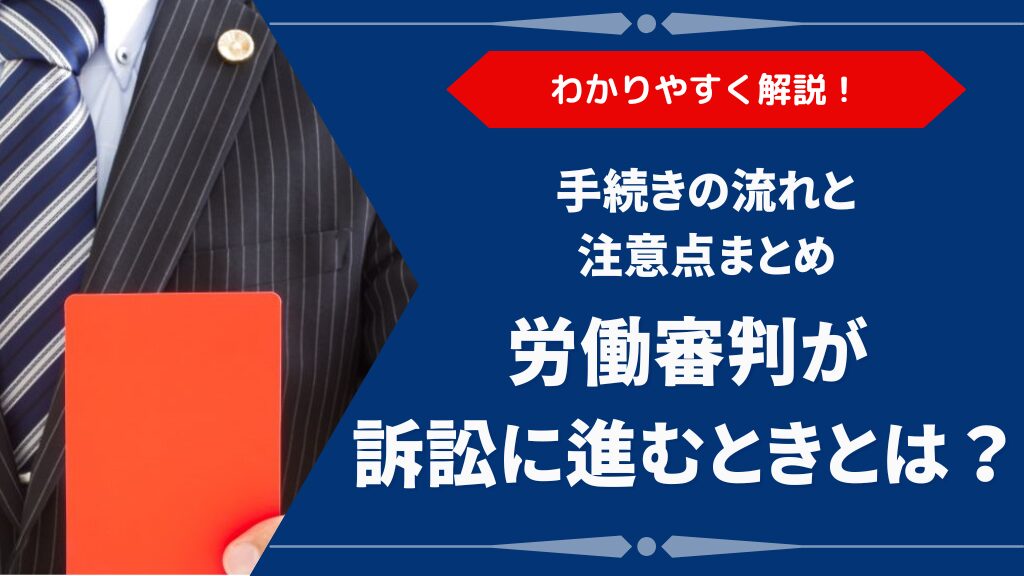
労働審判が訴訟に移行するのは、どのような場合なのでしょうか。
労働審判は、迅速な解決を目指す制度として活用されています。話し合いによる解決が重視される一方で、一定の条件を満たすと訴訟に進む場合もあります。
訴訟へ移行する主なパターンは、「審判手続きの打ち切り」または「異議申し立て」があったときです。いずれも労働審判法に基づき、自動的に訴訟が始まる仕組みとなっています。
訴訟に進んだ後は、証拠提出や主張立証のルールが厳格になり、当事者の負担も大きくなりがちです。時間や費用の面でも、審判より重くなる点には注意が必要でしょう。
本記事では、労働審判から訴訟へ移行する際の条件や手続き、押さえておきたい注意点をわかりやすく解説します。訴訟に備えて事前に知識を整理したい方は、ぜひ最後までご確認ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>労働審判とは
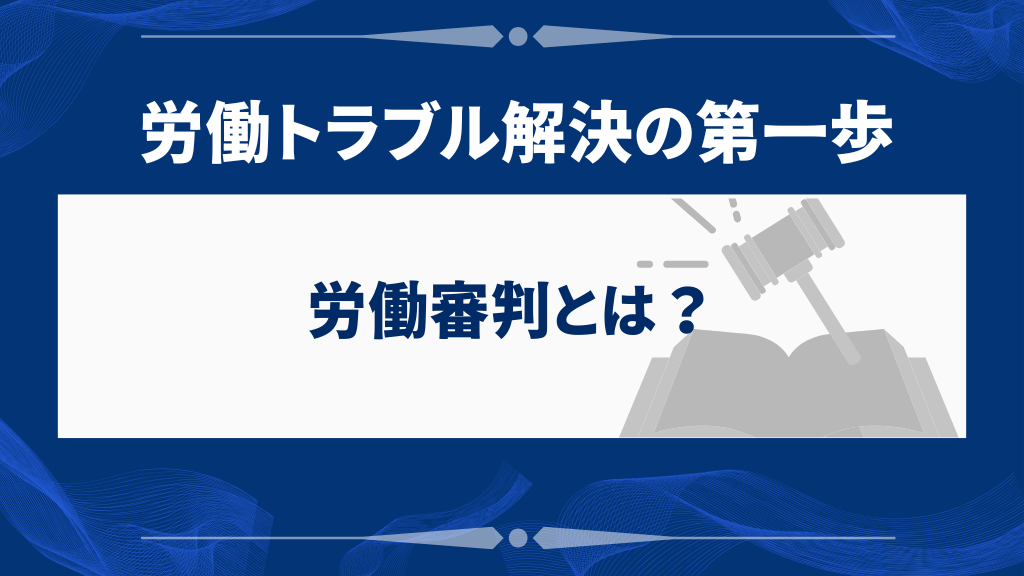
労働審判とは、労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争について裁判所で解決を目指す手続きの一つです。残業代や有給取得の請求、パワハラ・セクハラなどのすべての労働トラブルで利用できます。
実際に労働に関する紛争が起こった場合、まずは当事者の話し合いが第一歩ですが、当事者のみで解決できない場合には調停や訴訟の選択肢が生まれます。
訴訟は双方に負担が大きく時間もかかるため、可能な限り訴訟を行わずに迅速な解決を目指すのが調停や審判の手続きです。
労働審判では、裁判官および労働関係の専門知識を有する委員会が関与し、まずは調停の成立の見込みがある場合にはこれを試みます。解決に至らない場合は、労働審判を行う手続きに進みます。
そして、労働審判の委員会でも解決の見込みがないと判断されると必然的に訴訟へ移行しなければならなくなります。
引用:労働審判法第一条(目的)
第一条 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
なお、これらのトラブルの背景には「労働条件」に関する誤解や認識のズレが原因となっていることも少なくありません。労働条件の基本をわかりやすく解説した以下の記事もあわせてご覧ください。
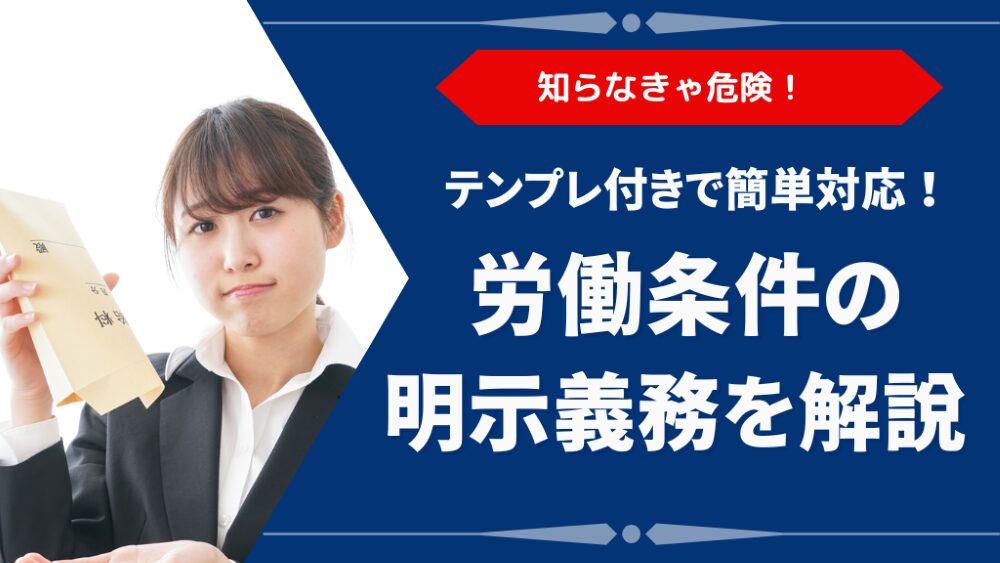
労働条件とは?簡単に押さえる明示項目・交付義務・違反リスクまで解説【テンプレ付】
労働条件とは何かを簡単に説明すると、賃金や労働時間など、働くうえでの基本ルールのことです。労働条件は、企業が労働者に明確に伝えることが法律で義務づけられています。 本記事は、人事・労務を担当する方や、初めてアルバイトを雇 […]
労働審判が訴訟に進むのはどんなとき?移行の条件を解説
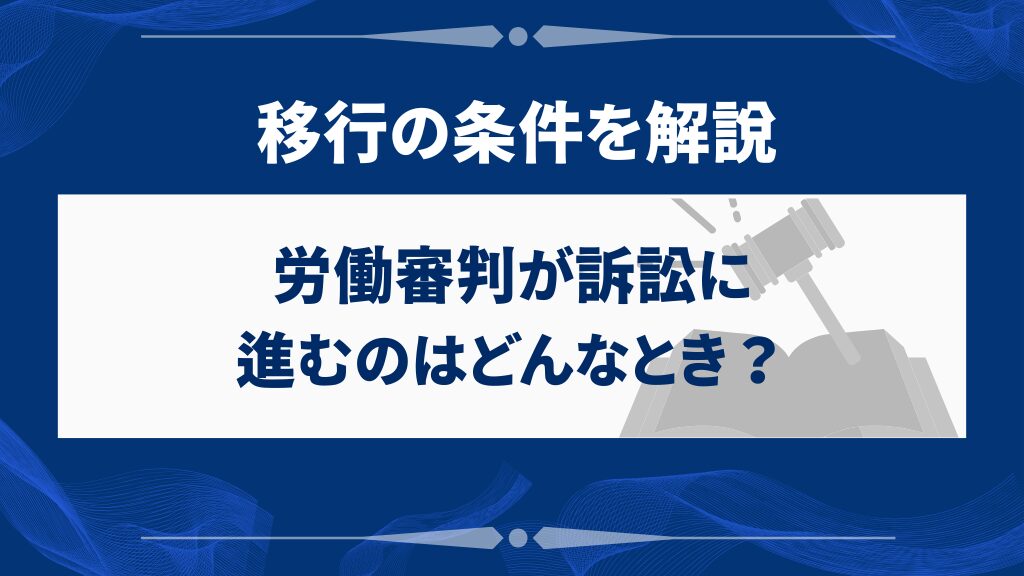
労働審判から訴訟へ移行するケースには主に以下の二つのパターンがあります。
- 労働審判法24条に基づいて審判手続が終了した場合
- 当事者のいずれかが労働審判の結果に不服を申し立てた場合
以下、詳しく解説していきます。
労働審判法24条により労働審判手続が終了した場合
労働審判法24条は、労働審判手続きが特定の状況下で終了し、自動的に訴訟へ移行する根拠となる重要な条文です。
具体的には、労働審判委員会が審理を続行しても適切な労働審判を行うことが困難であると認めた場合に適用されます。労働審判は最大3回の期日までの手続きのため、事案が複雑で短期間での審理が難しい場合や、証拠調べに相当な時間を要すると判断された場合などが該当します。
この条文に基づいて手続きが終了すると、当事者は特別な申立てをしなくても、自動的に訴訟手続きへと移行します。労働審判手続の終了決定がなされた日から2週間以内に訴訟が係属したものとみなされるため、当事者は改めて訴状を提出する必要がありません。ただし、訴訟に向けた準備として、より詳細な主張書面や証拠の整理が求められることが多いでしょう。
労働審判法24条による終了は、委員会の判断によって行われるため、特に決まったトリガーがあるわけではありません。そのため、短期解決を望んでいた当事者にとっては予想外の展開となることもあります。
訴訟移行後は審理がより厳格になり、証拠の提出や法的主張の精緻化が必要となるため、専門家のサポートがより重要になってくるでしょう。
引用:労働審判法第24条
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。
第二項 省略
労働審判に対する適法な異議があった場合
労働審判が適法に下された場合、その審判に不満がある場合には当事者が異議を唱えることができます。事業者または労働者のいずれかが適法な異議を申し立てた場合、その審判は効力を失い、自動的に訴訟へと移行します。
この異議申立ては、審判書の送達を受けた日の翌日から2週間以内に裁判所に対して書面で行う必要があります。期間を過ぎると異議申立ての権利は失効するため、期限管理は極めて重要です。
訴訟に移行すると審理の方式が大きく変わります。訴訟では証拠調べや証人尋問など厳格な手続きが必要となり、解決までの期間が長期化する傾向があります。最終的には裁判長による『判決』が下され、判決が確定すると争いの蒸し返しができなくなります。
訴訟を起こしても必ずメリットが大きくなるわけではないため、移行による時間的・経済的コストを考慮した上で判断すべきでしょう。
訴訟移行のポイント
労働審判から訴訟への移行過程において、重要なポイントは次のとおりです。
- 訴状提出の必要はなく、準備書面が提出される
- 労働審判の申立書が引き継がれる
- 労働審判手続きの申立ての時に、訴えの提起があったものとみなされる
- 事業者側は答弁書を提出する
- 証拠調べ手続や口頭弁論など、訴訟手続きへ対応する
なお、異議申し立てが却下されるケースは複数存在します。最も一般的な理由は、法定期間である2週間を経過してからの異議申し立てです。この期間制限は厳格に適用され、期限を1日でも過ぎると却下される可能性が高まります。
また当事者適格を欠く場合、つまり正当な申立権を持たない第三者からの異議申し立ても認められません。形式的な不備も却下理由となります。
例えば、異議申立書に必要事項の記載漏れがあった場合などです。特に代理人を通さず本人が手続きを行う際に見落としがちな点といえるでしょう。
こうした却下を避けるためには、専門家のアドバイスを受けながら適切な手続きを踏むことが重要です。
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
異議申し立てをする前に確認したい注意点と落とし穴
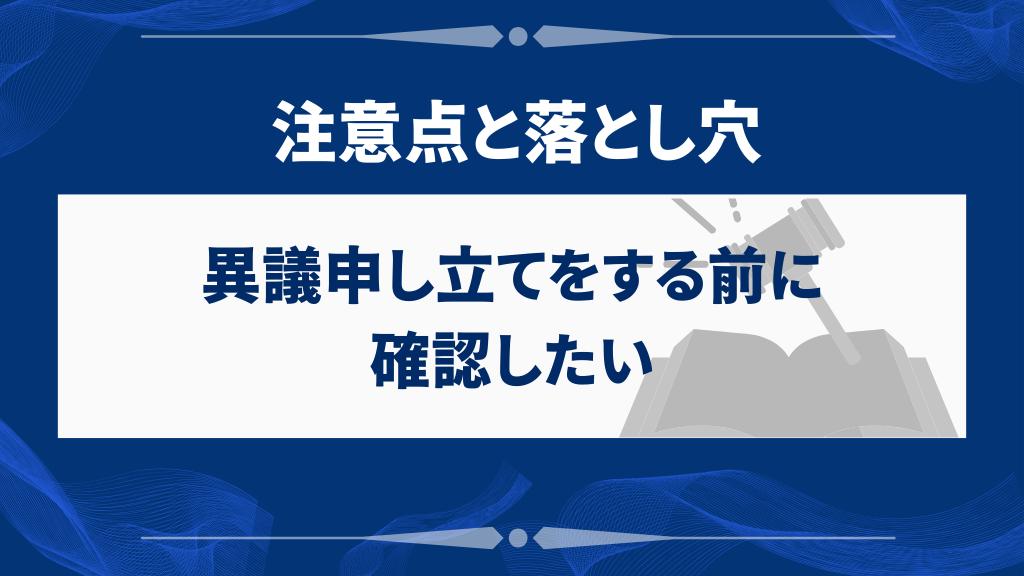
労働審判に対して異議申立てを行う際には、いくつかの重要な注意点があります。
中でも特に意識すべきなのが申立て期限です。異議申立書は、審判書の送達を受けた翌日から2週間以内に裁判所へ提出しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、労働審判は確定し、訴訟に移行することができなくなります。
異議申立ての理由については、法的には詳細な記載が求められているわけではありません。しかし、申立て後に訴訟へ進むことを前提とする場合には、今後の方針を見据えたうえで、ある程度の戦略性を持たせた内容にしておくとよいでしょう。
もうひとつ見落とされがちな落とし穴として、訴訟移行後の証拠提出ルールの違いが挙げられます。労働審判よりも訴訟のほうが手続きは厳格であり、提出できる証拠にも一定の制限が生じることがあります。
とくに審判段階で証拠を出しそびれていた場合、訴訟で活用できない可能性もあるため、早い段階から証拠収集と整理を進めておくことが重要です。
また、訴訟に進むことで費用や時間の負担が増える点も忘れてはなりません。弁護士費用が発生するほか、判決が出るまでに1年以上かかることもあります。
異議申立てを検討する際には、訴訟移行後のリスクやコストも視野に入れて、慎重に判断することが求められます。
訴訟に進んだ後のリスクとは?事前に備えるべき対応策
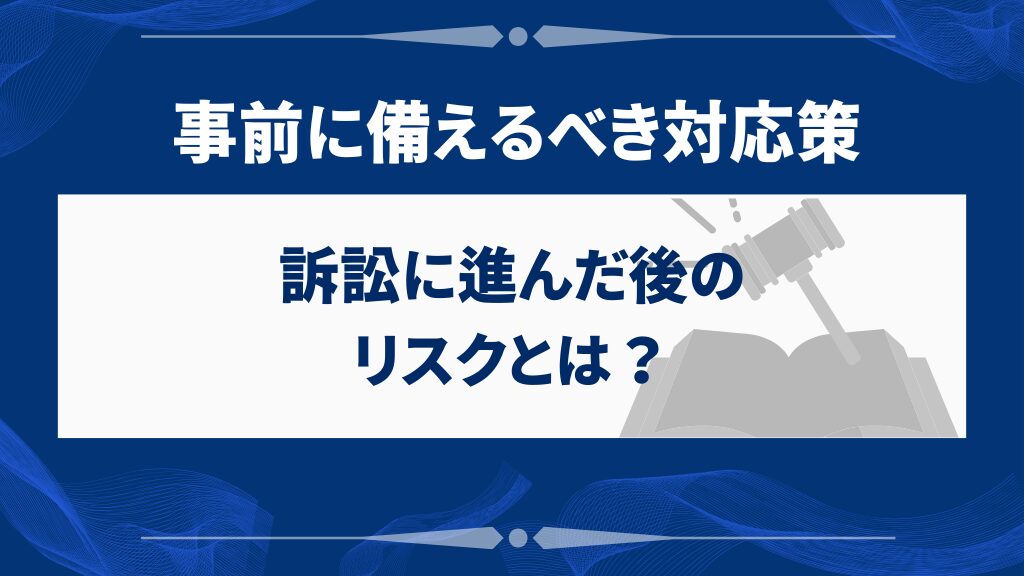
労働審判から訴訟へ移行すると、いくつかの重要なリスクが生じます。最も顕著なのは時間的コストで、審判の数ヶ月に対し、訴訟は1〜2年以上かかることも珍しくありません。
この長期化は精神的負担だけでなく、弁護士費用の増加にも直結します。また、訴訟では証拠や証人尋問がより厳格に扱われるため、準備不足が致命的になることがあります。
こうしたリスクに備えるには、まず証拠資料を整理・保全することが不可欠です。特に労働時間の記録や上司とのやり取りなど、自分に有利な証拠を早期に確保しておきましょう。
次に、訴訟費用の見積もりと資金計画を立てることも重要です。さらに、精神的な準備として、長期戦を覚悟し、日常生活や仕事への影響を最小限に抑える生活設計も必要になるでしょう。場合によっては、訴訟移行前に再度和解の可能性を探ることも検討すべきかもしれません。
解雇・残業代請求など事案別にみる訴訟時の注意点
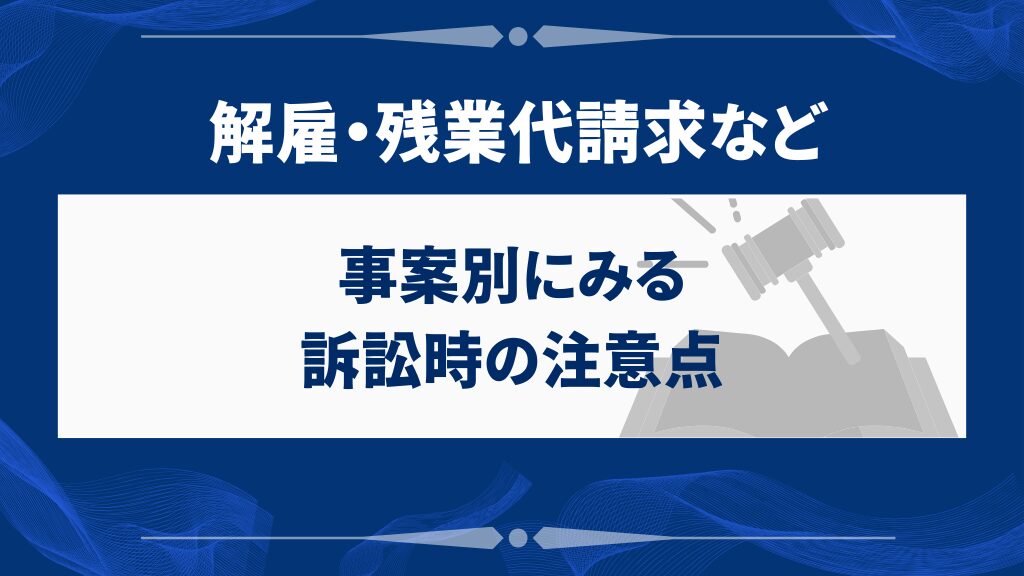
労働訴訟では事案の性質によって注意すべきポイントが大きく異なります。
解雇無効を争う地位確認請求事件では、解雇理由の妥当性だけでなく、解雇に至るまでの手続きの適正さも重要な争点となります。特に就業規則に定められた手順を踏んでいるかどうかが裁判所の判断に影響するため、証拠の保全が必須です。
一方、残業代請求事件においては、労働時間の立証が最大の課題となります。タイムカードやメール送信記録など客観的な証拠がない場合、裁判所の心証形成が難しくなるケースが少なくありません。また、管理監督者性の有無や固定残業代制度の有効性についても争われることが多いです。
以下それぞれの事案について詳しく解説します。
解雇無効を理由とする地位確認請求事件
解雇無効を理由とする地位確認請求は労働契約法16条を根拠とするいわゆる不当解雇を争う訴えです。
労働者が自身の解雇が法的に無効であると主張し、雇用関係の継続を求める訴訟へと発展します。この請求では、解雇の無効性を立証するために、解雇に至った経緯や会社側の手続き上の瑕疵、解雇理由の不当性などを具体的に主張する必要があります。
特に重要なのは証拠の準備です。就業規則、雇用契約書、解雇通知書、業務評価資料、そして会社とのやり取りを記録したメールや録音などが有力な証拠となります。また、解雇前後の給与明細や社会保険関係の書類も重要な証拠となるでしょう。
訴訟に移行すると、労働審判よりも厳格な証拠調べが行われ、証人尋問なども実施されることがあります。
地位確認請求が認められた場合、解雇期間中の賃金支払いを求める「バックペイ」の請求もセットになるのが一般的です。労働者は訴訟期間中の生活費をどう確保するかという現実的な問題も考慮しておく必要があるでしょう。
残業代請求事件
残業代請求事件では、労働審判から訴訟へ移行する際に特有の争点が生じます。
企業側としては従業員に反論の余地があるか、残業代の計算が正確かなどの確認が必要です。多くの場合、残業時間の算定方法や証拠の信頼性が中心的な論点となります。
特に企業側がタイムカードやシフト表などの客観的記録を提出しない場合、労働者側は業務メールの送受信時刻や同僚の証言など、間接的な証拠を積極的に活用する必要があります。
訴訟に移行すると、労働審判よりも厳格な証明責任が求められるため、残業の実態を示す証拠の収集と整理が重要です。また、残業代請求事件では割増賃金の計算方法も争点になりやすく、基本給に含まれる手当の範囲や、みなし残業代制度の有効性についても検討が必要です。
訴訟への移行を検討する際は、これらの争点について事前に整理し、証拠の補強を行うことで、より有利な展開を期待できるでしょう。
その他の労働問題における争点
労働問題は解雇や残業代請求以外にも多岐にわたります。
パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、育児・介護休業に関する紛争、配置転換の不当性など、職場では様々な問題が発生します。これらの事案が訴訟に移行する際、争点となるのは「使用者の安全配慮義務違反」や「職場環境配慮義務」の有無です。
特にハラスメント事案では、具体的な言動の事実認定が難しく、当事者間で主張が大きく食い違うことが少なくありません。また、メンタルヘルス不調による休職や退職の場合、因果関係の立証が重要な争点となります。労働者側は職場環境と健康被害の関連性を示す医師の診断書や同僚の証言が必要になるでしょう。
配置転換や降格の事案では、会社側の「人事権の範囲内」という主張に対し、その権利濫用性が問われます。こうした事案では、会社の就業規則や人事制度の合理性、過去の運用実態なども重要な証拠となります。
労働審判から訴訟へ移行する際は、これらの争点に応じた証拠の収集と整理が必要です。
弁護士にはいつ相談すべき?頼るメリットと選び方
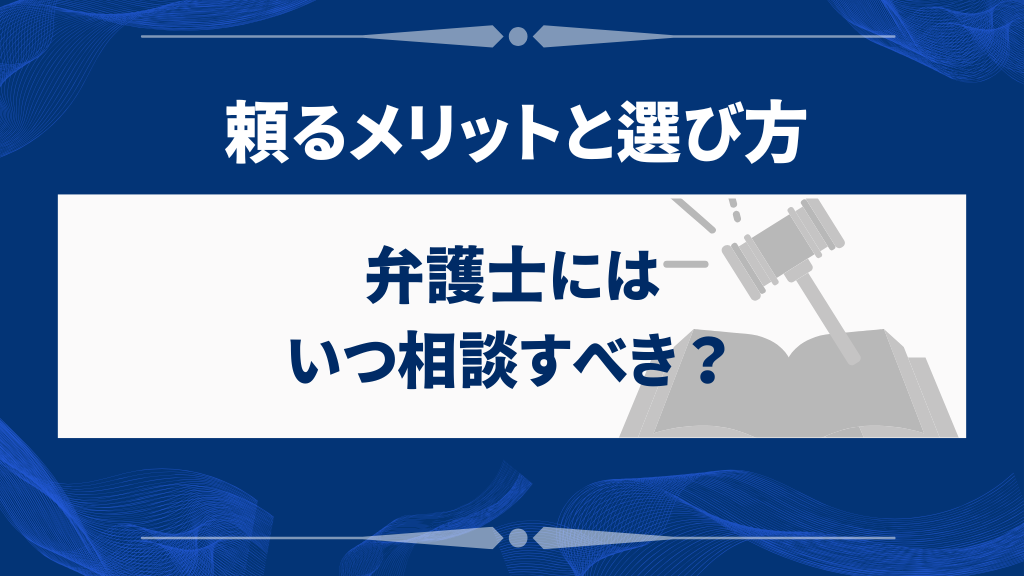
労働審判から訴訟への移行を検討する際、弁護士への相談は早い段階で行うことが望ましいです。
可能であれば、労働問題が起こらないように法務部門を設置するか、あるいは外部の法律事務所を法務顧問として迎えてコンプライアンス研修を行うなどの予防法務を行うことが望ましいです。
また、労働者とのトラブルが発生した時点で弁護士に相談するのも良いでしょう。最後に、当事者同士で労働審判の手続きに進んだ場合には、訴訟移行が弁護士に依頼するタイミングになります。
異議申し立ては形式的な不備で却下されることもあるため、専門家に依頼して確実な手続きを進めることが望ましいです。
弁護士に依頼するメリットは、専門的な法律知識に基づく戦略立案や、複雑な手続きの代行だけでなく、精神的な負担軽減にもつながります。
弁護士選びでは、労働問題の専門性や過去の解決実績を確認することが重要です。初回相談の際に、コミュニケーションの取りやすさや費用体系の明確さをチェックしましょう。
また、弁護士によって得意分野が異なるため、自分のケースに適した経験を持つ弁護士を選ぶことで、より効果的な解決が期待できます。ただ、相性の問題もあるため、複数の弁護士に相談してから決定することも一つの方法かもしれません。
訴訟移行でかかる費用はいくら?経済的準備と見通し
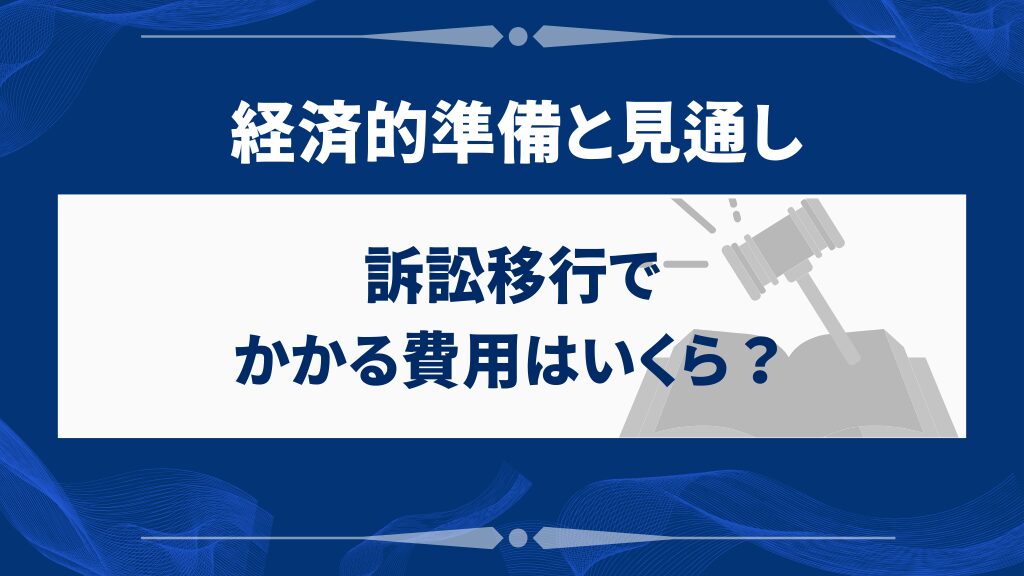
労働審判・労働訴訟にかかる一般的な費用は次のとおりです。
審判費用(実費)
- 印紙代 5,000円~20,000円
- 予納郵券代 250円~3,500円
- 印刷代 1,750円~5,500円
- 郵送費 0円~1,000円
- 交通費 500円~3,000円
弁護士費用
- 着手金 0~30万円ほど
- 報酬 経済的利益の5~30%程度
- 日当 1期日につき0~3万円程度
ただし、あくまで事案によるため注意が必要です。
例えば、残業代や退職金の支払いを求める訴訟では成功報酬として5%~20%ほどの報酬となることが多いですが、不当解雇を争う訴えの場合は数か月分の給与と同額という形式になることもあります。
弁護士事務所によっては訴額ごとに明確に報酬基準を公開しているところもあります。
まとめ|労働審判から訴訟移行の流れを把握し、早めの対応を心がけよう
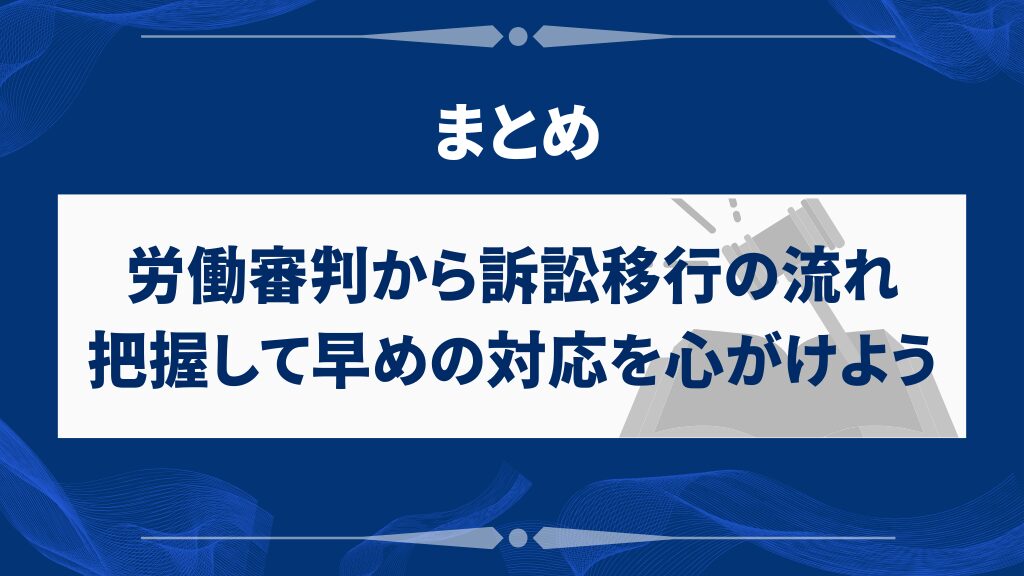
労働審判から訴訟へ移行するケースは決して珍しくありませんが、その流れや手続きには重要なポイントや期限が存在します。とくに「異議申し立て」や「審判手続きの終了」に伴う訴訟移行では、当事者の準備不足が後のリスクにつながることもあります。
訴訟に進むと、証拠の厳格な提出や手続きの長期化、弁護士費用の発生など、労働審判とは異なる負担が発生するでしょう。移行が確実になった段階で、できるだけ早く証拠の整理や資金計画を進めることが重要です。
また、訴訟を見据えた対応には専門家の支援が欠かせません。法的な視点での戦略立案や手続きのサポートを受けることで、より有利に進められる可能性が高まります。
訴訟への移行を想定した場合は、早めに弁護士へ相談し、冷静に対策を講じることが、トラブル解決への第一歩です。
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ
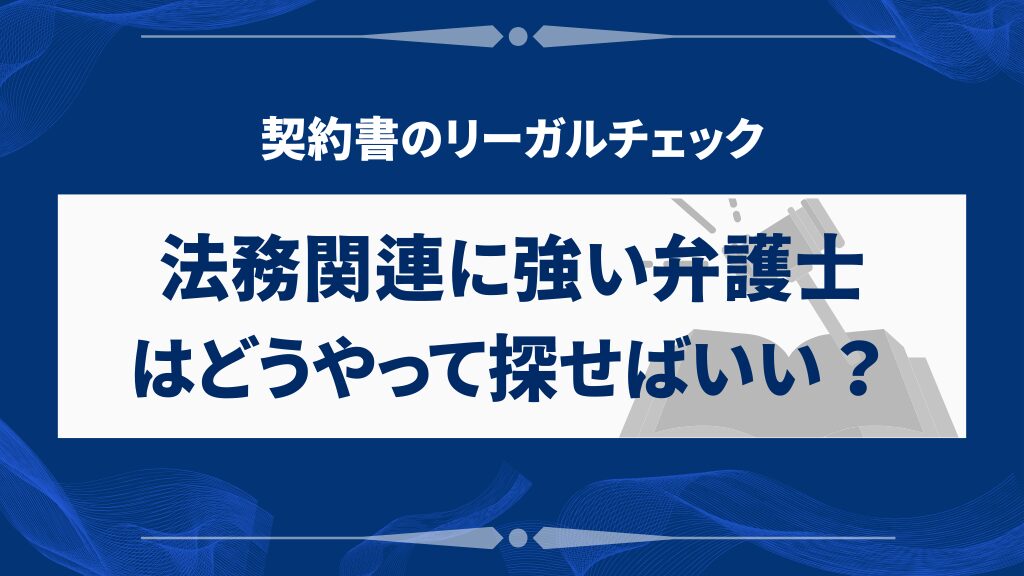
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












