民事訴訟法の基本と2022年改正まとめ
訴訟・紛争解決
2025.02.26 ー 2025.06.22 更新
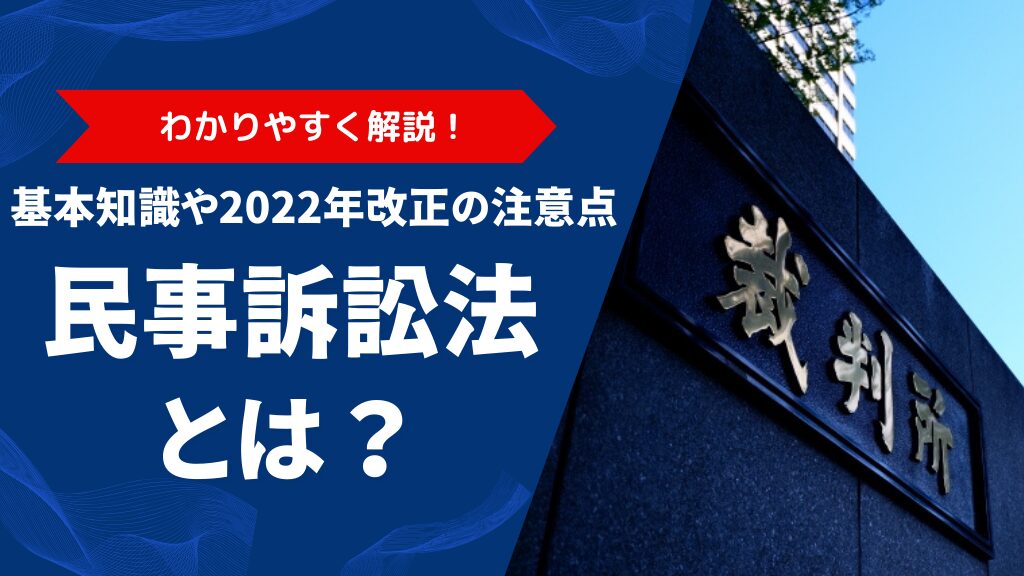
「民事訴訟法」と聞くと、難しい法律用語が並び、専門家でなければ理解しにくいと感じるかもしれません。しかし、実際には私たちの生活や仕事にも関わる法律の1つでもあります。
契約トラブルや金銭の請求問題など、身近な場面で民事訴訟が必要になった場合、民事訴訟法を理解しなければいけません。そのため、弁護士などの専門家ほど理解しなくてもよいですが、基礎的な知識は身に付けておくべきでしょう。
本記事では、法律に詳しくない方に向けて民事訴訟法の基本をわかりやすく解説します。今回は民事訴訟法について簡単に取り上げて紹介しますので、初心者の方も最後までご覧ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>民事訴訟法とは?
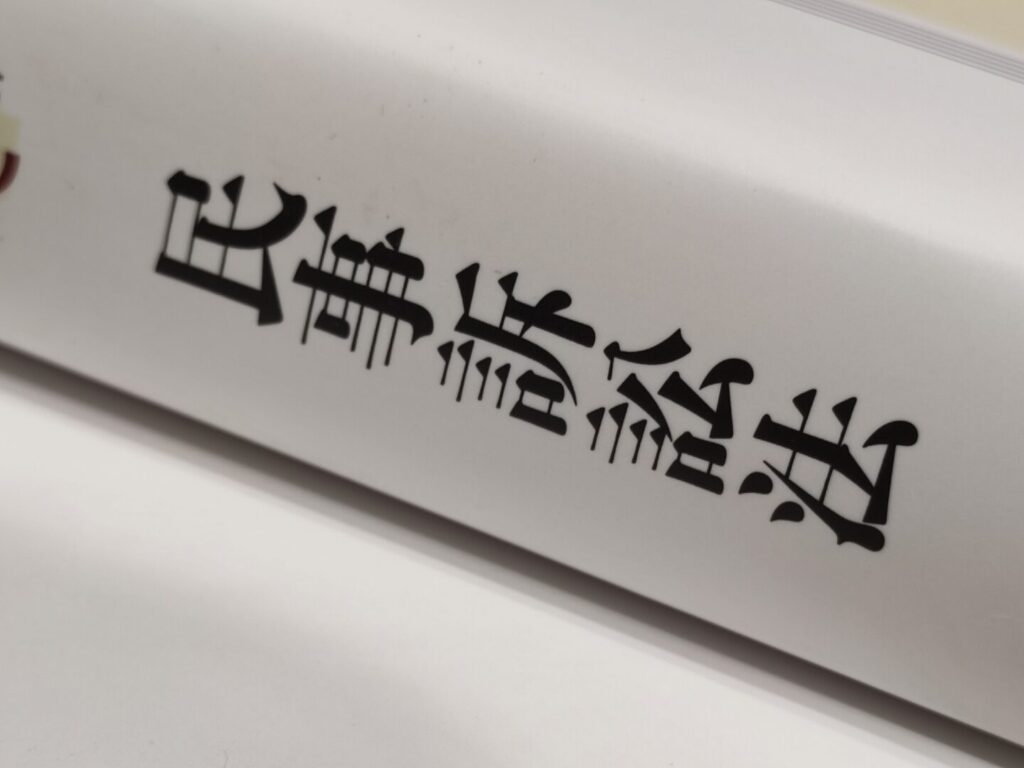
民事訴訟法とは、個人や法人同士の紛争を裁判所で解決するための手続きを定めた法律であり、その概要を説明しています。訴訟の準備や手続きの期間、当事者の権利義務の原則など、訴訟全体の流れとルールを明確にしています。裁判の結果には法的な効力があり、公正な解決を目指すことが旨です。
この法律は、訴訟手続きの各種細かい規定を含み、例えば第一審の進行、上訴や再審、少額訴訟、督促手続きなど幅広い制度の整備と手続きの実施を規定しています。2022年の改正では、訴状などの提出をオンラインで可能にするなど、デジタル化が推進され、利便性の向上という効果が期待されています。
刑事事件とは違い、、民事訴訟法は個人同士の間におけるの権利や義務を巡る争いを公平に解決するためのルールを規定しています。例えば、民法に基づいた契約上の義務を巡る事件などが対象で、この理由から円滑な訴訟の実施に不可欠な規則を定めています。
民事訴訟の基本的な流れは、原告が訴えを提起し、被告がこれに対して答弁を行い、裁判所が証拠を検討した上で判決を下すというものです。訴訟は地方裁判所などの裁判所で行われ、判決に納得できない場合は、控訴や上告を通じて上級裁判所で審理を求めることができます。
また、民事訴訟法では和解制度も定められており、訴訟を回避し、当事者同士が合意によって紛争を解決する方法も用意されています。
民事訴訟法の全8編

民事訴訟法については、以下の8編で構成されています。
- 総則
- 第一審の訴訟手続
- 上訴
- 再審
- 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
- 少額訴訟に関する特則
- 督促手続き
- 執行手続き
それぞれについて簡潔に紹介していきます。
1.総則
民事訴訟法の「総則」は、民事訴訟の基本原則や手続全体に共通するルールを定めた部分です。裁判の進行や当事者の権利義務、裁判所の権限などが規定されており、公平で適正な裁判の実施を支える基盤となっています。総則は民事訴訟法の第1編に位置し、訴訟の基盤となる以下のような事項を規定しています。
- 裁判の進行
- 当事者の権利・義務
- 裁判所の管轄
総則では、民事訴訟の基本原則として「当事者対等の原則」や「適正手続の原則」が定められています。当事者対等の原則は、原告・被告の双方が平等な立場で裁判を受ける権利を持つことを意味します。また、適正手続の原則により、当事者は適切な手続を経た公正な裁判を受ける権利が保障されています。
このように、総則は関連するすべての民事訴訟の基本構造を定め、公平かつ適正な裁判手続を実現するための基盤となる重要な規定が含まれています。
2.第一審の訴訟手続
第一審の訴訟手続は、訴訟の最初の段階の進行や書類の提出、口頭弁論などについて定められています。訴えの提起や訴状の変更、証拠の取扱いに関する規定があり、適正な手続きの実施が求められます。第一審とは、訴訟が最初に審理される裁判所での手続であり、通常、地方裁判所または簡易裁判所が担当します。
第一審の訴訟手続では、以下のような事項が規定されています。
- 訴えの提起・変更等
- 口頭弁論・争点整理の手続き
- 証拠の取り扱い
- 判決
- 裁判によらない訴訟の完結
- 簡易裁判所における訴訟手続きの特則
訴訟は原告が裁判所に訴状を提出することで開始されます。訴えが受理されると、裁判所は被告に対し、訴状を送達し、答弁書の提出を求めます。書面による答弁が求められ、被告は請求に対する認否や反論を記載した答弁書を提出し、訴訟が本格的に進行します。
その後、口頭弁論や証拠調べが行われます。口頭弁論では双方の主張を述べ、証拠調べでは事実の確認が行われます。
これらのプロセスは、第一審の訴訟手続で定められた規定に沿って進められます。
3.上訴
上訴とは、第一審の判決に不服がある場合に、上級裁判所に再審理を求める手続きのことを指します。第一審の判決に不服がある場合の再審理を求める手続で、控訴や上告などが含まれており、判決の誤りを正し、公正な裁判を実現するための制度で、これにより誤った判決の終了や修正が可能となります。民事訴訟法では、3種類の上訴が規定され、それぞれ異なる要件や手続きが定められています。
- 控訴:地方裁判所や簡易裁判所の第一審判決に対して高等裁判所に再審理を求める
- 上告:控訴審の判決に対する不服申し立て
- 抗告:決定や命令に対する不服申し立て
控訴審では事実関係の審理が可能で、証拠の再評価も行われます。判決に納得できない当事者は、原則として判決の送達後2週間以内に控訴を申し立てる必要があります。
上訴制度は、誤った判決を正す機会を確保し、公正な裁判を実現するために重要な役割を果たしています。
4.再審
再審とは、確定した民事裁判の判決に重大な誤りがあった場合に、その判決を覆し、新たに審理を行う手続きです。通常、判決が確定すると原則として変更はできませんが、再審は例外的に認められる制度となっています。
再審請求が認められるには、法律で定められた「再審事由」が必要です。例えば、判決の基礎となった証拠が偽造された場合や、裁判官が賄賂を受けて不正な判決を下した場合などが該当します。
再審請求は、確定判決を下した裁判所に対して行い、請求が認められた場合は改めて審理が行われます。ただし、再審の乱用を防ぐために、請求が認められる要件は厳格に定められています。
5.手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則は、手形や小切手に関する紛争を解決するための手続を定めています。
手形や小切手は、金融取引で広く利用される支払手段ですが、支払い拒否や不渡りなどのトラブルが発生することがあります。通常の民事訴訟よりも迅速な解決が求められるため、手形訴訟や小切手訴訟では証拠調べが原則として制限され、被告が抗弁できる範囲も通常の訴訟より狭められています。
また、裁判所が迅速な判断を下せるように、手形や小切手の存在自体が証拠として重視される仕組みになっています。原告が必要な証拠を提示できれば、短期間で判決が出されることが特徴です。
ただし、被告が通常訴訟への移行を求めることも可能であり、その場合は通常の民事訴訟の手続きが適用されます。
6.少額訴訟に関する特則
少額訴訟に関する特則は、比較的少額の金銭を簡易に請求できる制度です。原則として1回の期日で判決が出されるため、個人でも利用しやすい仕組みとなっています。
少額訴訟の対象となるのは、請求金額が60万円以下の金銭請求に限られます。この場合の手続きは簡略化されており、証拠の提出や証人尋問も必要最低限に抑えられます。
ただし、被告が通常訴訟を希望した場合、通常の民事訴訟手続に移行する可能性があります。また、少額訴訟の判決に不服がある場合控訴は認められず、異議申立てのみ可能となるため、注意が必要です。
7.督促手続
督促手続とは、金銭の支払いを求める場合に、通常の民事訴訟よりも素早く解決できる制度です。貸金や売掛金の回収など、支払い義務が明確なケースで利用されます。相手方(債務者)が異議を申し立てない限り、裁判所の審理を経ずに支払いを強制することが可能です。
督促手続は、債権者が地方裁判所に対して支払督促の申立てを行うことで開始されます。裁判所は申立内容を審査し、問題がなければ支払督促を発令します。
一方、債務者が異議を申し立てた場合、通常の訴訟手続きへ移行します。
8.執行手続
民事訴訟では、勝訴判決を得ても相手方が義務を履行しなければ意味がありません。そのため、裁判所が強制的に権利を実現させる仕組みとして、民事訴訟法の「執行手続」が定められています。
例えば、金銭の支払いを求める場合には「強制執行」として、相手の預金や給与を差し押さえることが可能です。不動産の明け渡しなどの場合には、裁判所の執行官が実力行使を伴う執行を行うこともあります。
これらの手続を実行するには、「債務名義」と呼ばれる裁判所の判決書や公正証書などが必要です。
また、手続の選択や執行申立書の作成、相手方の財産調査などには法律の専門知識が求められます。そのため、執行手続をスムーズに進めたい場合は、弁護士などの専門家に相談するのが安心です。
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
民事訴訟における基本原則

民事訴訟法では、民事訴訟における各プロセスのルールだけでなく、民事訴訟全体における基本原則も規定しています。定められている基本原則は、以下の通りです。
- 審理の進行:裁判所
- 主張や立証:当事者
それぞれの基本原則について解説していきます。
審理の進行:裁判所
審理の進行において、裁判所は公正かつ適正な手続きを確保する役割を担います。民事訴訟における過程を適切に進めるのが、裁判所の重要な責務です。
裁判所が果たす役割は、以下の通りです。
- 訴状の審査
- 当事者双方の主張の整理・争点の明確化
- 口頭弁論での主張や意見の事実認定
- 証人尋問や当事者尋問の証拠の信用性・妥当性の確認
裁判所は当事者の手続上の権利を保障しながらも、不当な引き延ばしを防ぎ、適正な審理を維持するために訴訟指揮権を行使します。また、裁判所は和解を勧めることもあり、訴訟の長期化を防ぐために対応を取ることもあります。
審理の進行を適切に管理することで、裁判の公平性と迅速性が確保され、法的安定が保たれるのです。
主張や立証:当事者
民事訴訟において、主張や立証は当事者が担う重要な役割です。
裁判所は訴訟の進行を管理しますが、当事者が積極的に主張や証拠を提出しなければなりません。これを「弁論主義」といい、裁判所は当事者が示した事実や証拠に基づいて判断を下します。
原告は自らの請求が正当であることを裁判所に示すため、具体的な事実を主張し、証拠を提出する必要があります。一方、被告も反論し、必要に応じて証拠を提示しなければなりません。
また、裁判所は当事者の主張にない事実を考慮できず、証拠の収集も当事者に委ねられます。これにより、当事者は訴訟を主体的に進める責任を負います。
民事訴訟に該当する訴訟の種類

民事訴訟に該当する訴訟の種類として、以下の5つが挙げられます。
- 通常訴訟
- 手形小切手訴訟
- 少額訴訟
- 人事訴訟
- 行政訴訟
それぞれの訴訟について解説していきます。
1.通常訴訟
通常訴訟とは、個人同士の間における権利義務に関する紛争を解決するための手続きです。通常訴訟には、以下のような民事上のトラブルが対象となります。
- 契約違反
- 金銭の支払い請求
- 損害賠償請求
通常訴訟は厳格な手続きを伴いますが、公正な判断を得るための基本的な手段とも言えます。和解や調停とは異なり、法律に基づいた明確な判決が下されるため、権利を確定させる手段として重要な役割を果たします。
2.手形小切手訴訟
手形小切手訴訟とは、手形や小切手に関する紛争を迅速に解決するための特別な訴訟手続きです。一般的な民事訴訟よりも審理が簡略化されており、金銭の支払い請求を迅速に処理できる仕組みとなっています。
通常の民事訴訟と異なり、手形小切手訴訟では証拠調べの範囲が限定されるのが特徴です。原則として手形や小切手そのものの有効性に関する争点のみを審理し、複雑な事実関係の調査は行いません。
手形や小切手の支払いをめぐる紛争を効率的に解決する手段として、特に商取引の場面で手形小切手訴訟は重要な役割を果たします。
3.少額訴訟
少額訴訟とは、少額の金銭請求を迅速に解決することを目的とした訴訟です。通常の訴訟に比べて手続きが簡略化され、裁判官が1回の審理で判決を下すため、時間や費用の負担を抑えられるのが特徴です。
少額訴訟を利用できるのは、請求額が60万円以下の場合に限られます。通常の民事訴訟では複数回の期日が設定されることが多いですが、少額訴訟では原則として1回の期日で審理が完了し、その場で判決が言い渡されます。
また、少額訴訟の判決には「仮執行宣言」が付されるため、相手方が控訴した場合でも、すぐに強制執行の手続きが可能です。ただし、被告が通常の訴訟を希望する場合は、通常訴訟への移行が認められる点も考慮しなければなりません。
4.人事訴訟
人事訴訟とは、個人の身分関係に関する紛争を解決するための訴訟です。財産や金銭に関する訴訟とは異なり、当事者の身分に関わる法律関係を確定させることを目的としています。具体的には、以下のような内容が該当します。
- 結婚や離婚
- 親子関係の確認
- 養子縁組の無効
通常の民事訴訟とは異なり、和解による解決ができない場合が多いです。例えば離婚訴訟では、夫婦の一方が離婚に同意しない場合でも、法律上の離婚原因が認められれば裁判所が離婚を認めることがあります。
人事訴訟は個人の人生に大きな影響を与えるため、法律に基づいた慎重な審理が求められます。
5.行政訴訟
行政訴訟とは、国や地方公共団体などの行政機関の処分や決定に対して、市民や企業が不服を申し立てるための訴訟手続きです。行政機関の行為が違法であるかどうかを裁判所が判断し、必要に応じてその取り消しや変更を求めることができます。
行政訴訟には、以下のような種類があります。
- 抗告訴訟:行政処分の取り消しや無効確認を求める
- 義務付け訴訟:行政機関に一定の行為を求める
- 損害賠償訴訟:国家賠償を請求する
行政訴訟は行政事件訴訟法に基づいて行われ、訴訟の相手方は国や自治体などの行政機関となります。裁判を通じて行政の適正な運用を確保し、市民の権利を守る重要な役割を果たしています。
2022年の民事訴訟法の改正は何が変わった?

2022年5月18日に成立した改正民事訴訟法は、民事訴訟手続のIT化を主な目的としています。この改正により、訴状や準備書面などの裁判書類をオンラインで提出できるようになり、弁護士が代理人となる場合にはオンライン提出が義務化されました。
また、裁判所からの送達もオンラインで行うことが可能となり、弁護士にはオンライン送達の受領が義務付けられています。
さらに、口頭弁論や弁論準備手続などの期日へのウェブ会議システムを利用した参加が認められ、当事者が遠隔地からでも裁判に参加しやすくなりました。訴訟記録の電子化も進められ、当事者はオンラインで記録の閲覧や複写が可能となり、紙媒体の資料に依存しない手続が実現します。
これらの改正は、2026年5月までに段階的に施行される予定であり、民事訴訟の利便性と効率性の向上が期待されています。
オンライン裁判の可能性と今後の課題
オンライン裁判の導入は、民事訴訟のプロセスを大きく変革する可能性があります。
裁判所へ出向く必要がなくなることで、時間や場所の制約が緩和され、より多くの人が司法サービスを利用しやすくなると期待されています。さらに、訴訟手続きのデジタル化が進むことで、書類のやり取りがスムーズになり、業務効率の向上や費用削減にもつながります。
しかし、オンライン裁判を実現するには、セキュリティ対策や本人確認の厳格化が必要であり、現時点では不正アクセスやデータ流出のリスクが指摘されています。また、インターネット環境に依存するため、デジタルデバイドの問題にも対応しなければなりません。
専門家の間では、オンライン裁判の適用範囲についても議論が続いています。単純な事案や少額訴訟から段階的に導入すべきなのか、それとも全面的に移行すべきなのか、意見が分かれています。現状では試験的な運用を重ね、実務上の課題を明確にしながら改良を進めることが求められています。
今後の展望としては、法制度の整備と技術の進歩が実用化のカギとなるでしょう。裁判官や弁護士、当事者の意見を反映させながら、信頼性の高いオンライン裁判のシステムを構築することが重要になります。
まとめ

民事訴訟法は多様な分野の手続きを規定し、公正で迅速な訴訟の実施を支えています。訴訟や上訴、和解の手続きの説明を理解し、適切な対応をとることが裁判の効果的な解決につながります。
民事訴訟の法律について定められた民事訴訟法は、2022年に改正され、デジタル化が進められています。今後段階的な施行が進めば、書類のデジタル化やオンラインでの口頭論弁などが可能になるでしょう。
そのため、民事訴訟を提起する際は、最新の民事訴訟法を理解しておく必要があります。詳細なことは弁護士に相談して、適切に手続きを進められるようにしましょう。
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












