労働基準法39条とは?有給休暇の付与日数早見表・管理義務・違反リスクを解説
労働問題・労働法務
2025.07.11 ー 2025.10.29 更新
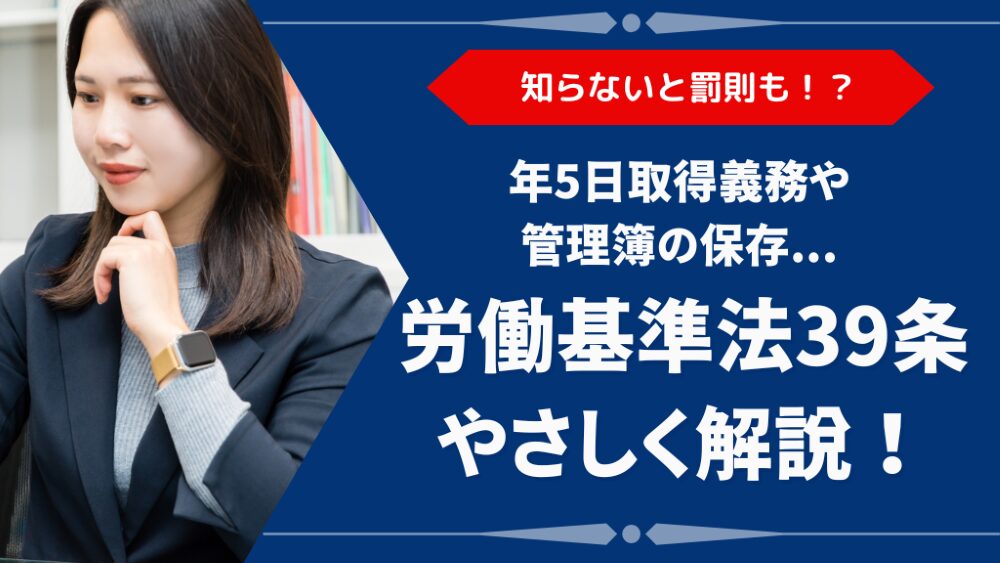
労働基準法39条は、年次有給休暇の付与日数や取得義務、管理方法について企業に明確なルールが定められています。
とくに「年5日取得義務」や「有給管理簿の保存義務」など、実務で対応が求められるポイントは多く、怠れば罰則や是正勧告のリスクもあります。
本記事では、付与条件や出勤率の判定方法、日数の早見表、管理簿の作り方、違反時の罰則までをわかりやすく整理しました。
法令遵守と労務リスクの回避を両立するための実務対応を解説していますので、ぜひ最後までご確認ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>労働基準法39条とは?年次有給休暇の基本と企業の義務
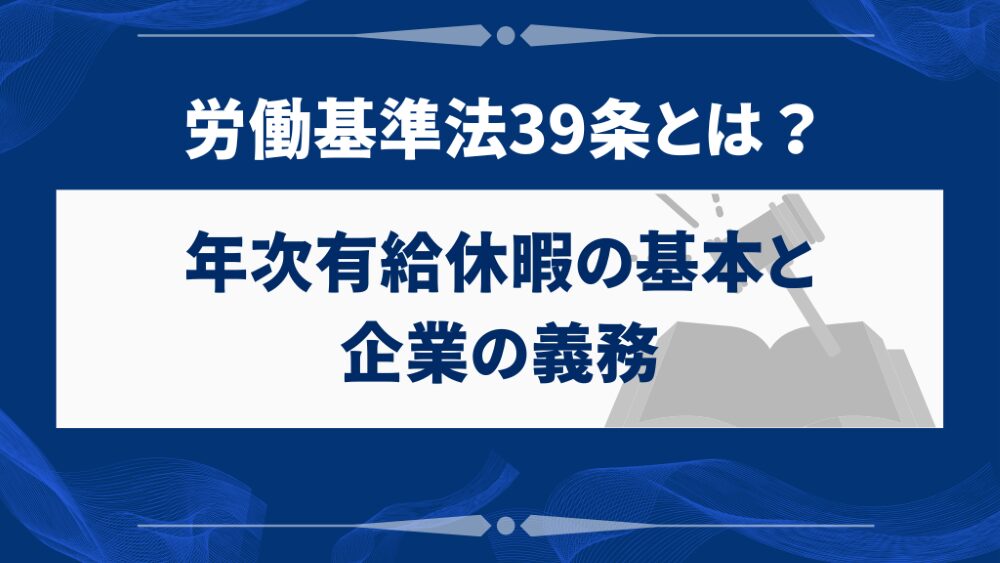
「労働基準法39条」は、年次有給休暇に関する基本ルールを定めた重要な条文です。有給は労働者の当然の権利であり、企業にはこの有給を適切に付与・管理する義務があります。
近年では年5日の取得義務や管理簿の作成も義務化され、違反時には罰則も。まずは、有給休暇の基本的な考え方と、39条の条文内容について見ていきましょう。
- そもそも「有給休暇」とは何か?労働者の権利と企業の責任
- 労働基準法39条の条文をわかりやすく解説
そもそも「有給休暇」とは何か?労働者の権利と企業の責任
年次有給休暇、通称「有給」は、労働者が心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を送るために設けられた重要な制度です。
これは単なる会社の福利厚生ではなく、労働基準法第39条によって保障された労働者の「権利」で、休暇を取得してもその期間の賃金が支払われることが原則です。正式には「年次有給休暇」と呼ばれています。
労働者からの適切な有給休暇の請求があった場合、企業は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則としてその請求を拒むことはできません。また、企業には、労働者に対して法律で定められた日数・範囲の有給休暇を確実に付与する義務があります。
さらに、労働者が気兼ねなく有給休暇を取得できるよう、職場の雰囲気作りや取得しやすい環境を整備することも企業の重要な責任と言えます。
労働基準法39条の条文内容をわかりやすく整理
労働基準法第39条は、労働者の年次有給休暇に関する最も基本的なルールを定めた条文です。
この条文によって、どのような労働者に対して、どのくらいの有給休暇が付与されるのか、そして企業にはどのような義務があるのかが明確に定められています。専門的な法律用語を避け、その主要なポイントを紹介します。
労働者は、まず「雇い入れの日から起算して6か月間継続して勤務」していることが条件です。さらに、その期間の「全労働日の8割以上を出勤」している必要があります。
これらの条件を満たした労働者に向けて、労働基準法第39条は、原則として「10労働日」の年次有給休暇を付与することを定めています。これは、継続または分割して取得できる労働者の正当な権利です。
この条文は、単に休暇を与える義務を使用者に課すだけでなく、労働者が心身のリフレッシュを図り、健康で文化的な生活を送れるようにするためのものです。
企業は、この規定に基づき、条件を満たした労働者に向けて確実に年次有給休暇を付与する義務を負います。
この義務は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、労働者の請求を原則として拒むことはできないという強いものです。
賃金や労働時間を含めた「労働条件」全体の基本を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
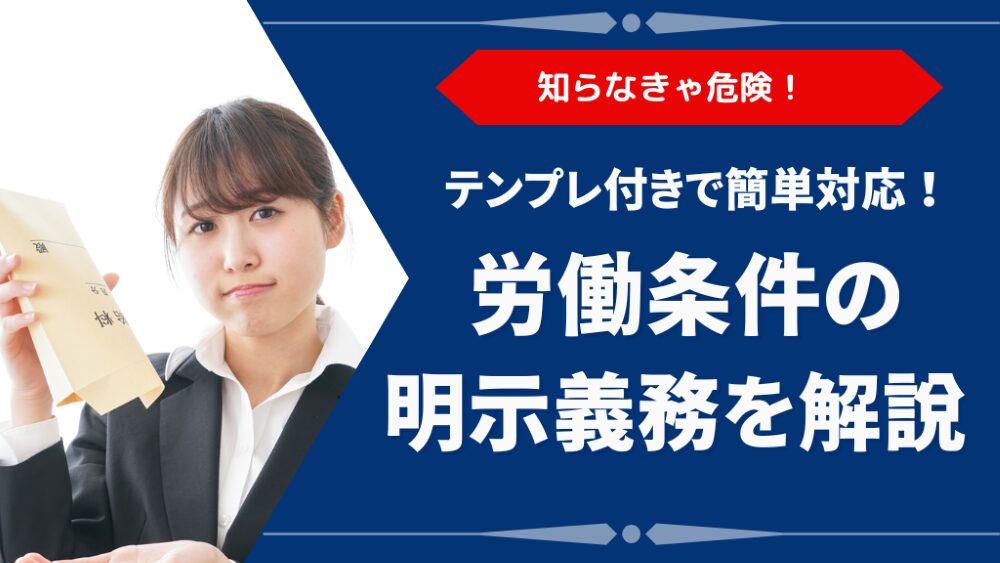
労働条件とは?簡単に押さえる明示項目・交付義務・違反リスクまで解説【テンプレ付】
労働条件とは何かを簡単に説明すると、賃金や労働時間など、働くうえでの基本ルールのことです。労働条件は、企業が労働者に明確に伝えることが法律で義務づけられています。 本記事は、人事・労務を担当する方や、初めてアルバイトを雇 […]
年次有給休暇の付与条件と日数早見表
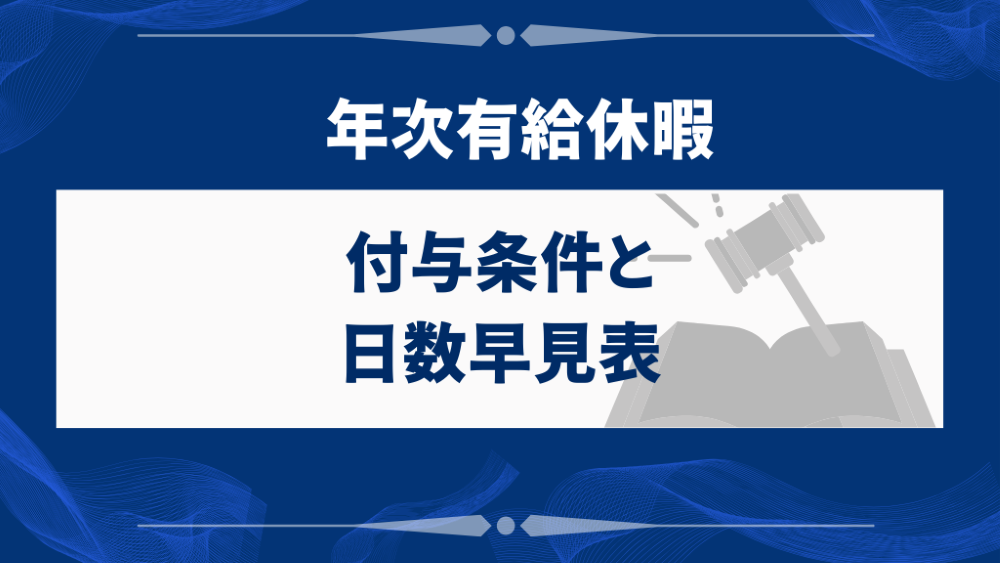
年次有給休暇は、「6ヶ月以上の継続勤務」と「出勤率8割以上」という2つの条件を満たすことで取得対象となります。
勤続年数や所定労働日数に応じて付与日数は増加し、パートやアルバイトも取得可能です。
この章では、付与日数の早見表や出勤率の判定方法など、実務に役立つポイントを整理します。
- 勤続年数と週労働日数による有給休暇の付与日数一覧
- パート・アルバイトでも取れる?
- 出勤率8割の判定方法と注意点
勤続年数と週労働日数による有給休暇の付与日数一覧
労働基準法では、年次有給休暇は勤続年数と労働日数によって決まります。所定労働日数が週5日以上の労働者に対しては、以下のように付与されます。
| 勤続年数 | 付与日数 |
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
パート・アルバイトでも取れる?
前述の表は週5日以上の労働者に適用されるものですが、パートタイムやアルバイトといった短時間労働者の方々にも、年次有給休暇を取得する権利があります。これは労働基準法によって定められた労働者の権利であり、雇用形態によって失われるものではありません。
パート・アルバイトの方が有給休暇を取得するための条件は、正社員と同様に「雇い入れの日から6ヶ月以上継続勤務していること」と「その期間の全労働日の8割以上出勤していること」の2つです。
これらの条件を満たせば、週の所定労働日数や1年間の所定労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。これが「比例付与」と呼ばれる仕組みです。
「パートだから有給はない」という認識は誤りです。有給休暇は法律上の正当な権利として、条件を満たせば全ての労働者に認められています。
企業は、条件を満たしたパート・アルバイトからの有給取得の申請を原則として拒否することはできません。もし企業がこれを拒否したり、有給取得を理由に不利益な扱いをしたりした場合、労働基準法違反となる可能性があります。
出勤率8割の判定方法と注意点
年次有給休暇が付与されるための重要な条件の一つである「全労働日の8割以上の出勤率」は、具体的に「出勤日数 ÷ 全労働日」という計算式で求めます。
ここでいう「全労働日」とは、あらかじめ労働契約や就業規則などで定められた労働日を指し、会社の休日や不可抗力による休業日は含まれません。
一方、「出勤日数」には、実際に労働した日だけでなく、労働基準法で出勤日として扱うと定められている期間も含まれます。
具体的には、業務上の傷病による休業期間、育児休業や介護休業の期間、産前産後休業期間、そして年次有給休暇を取得して休んだ日などは「出勤日」として扱われます。遅刻や早退をした日であっても、原則としてその日は「出勤日」として計算。
出勤率の算定期間は、最初の有給休暇が付与される際は雇入れの日から6ヶ月間、それ以降は原則として直前の1年間の期間で判定。
試用期間中は、その期間は継続勤務期間に含まれるため、出勤率の計算対象です。企業はこれらのルールを正確に把握し、適切に出勤率を計算する必要があります。
年5日の有給取得義務とは?時季指定・管理義務の実務対応
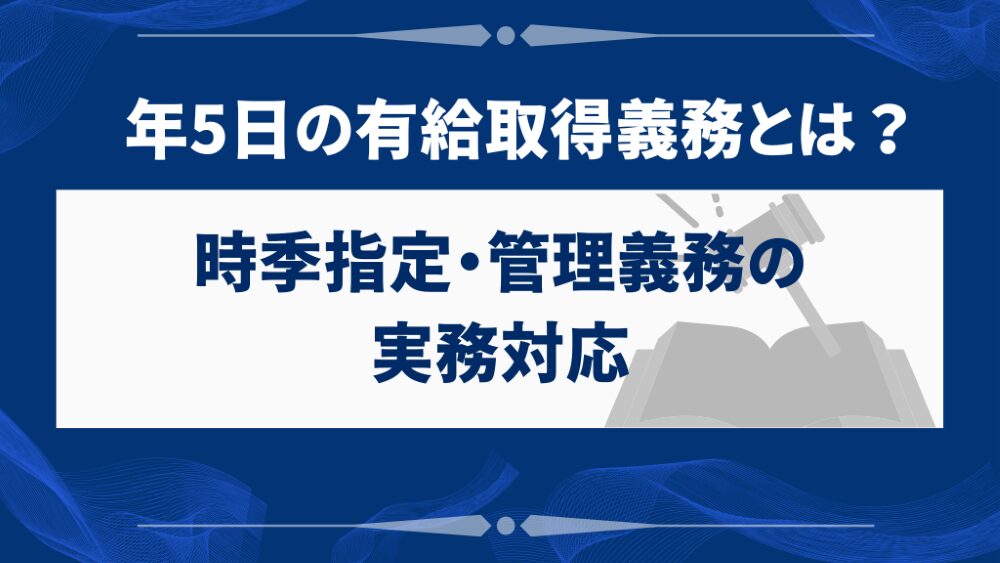
| 項目 | 内容 |
| 義務内容 | 年5日の年次有給休暇を労働者に取得させること |
| 義務の対象 | 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者(管理監督者を含む) |
| 取得期限 | 付与日から1年以内 |
2019年の法改正により、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、企業は年5日の取得を義務付けられました。
時季指定により企業側が取得日を決めることも可能で、取得状況は管理簿で3年間保存が必要です。これらを怠ると労基法違反となり罰則の対象になります。
そうならないためにも、以下の内容を確認しておくことをおすすめします。
- 年5日取得義務と企業が取らせなければならないケース
- 時季指定義務の正しい運用方法と留意点
- 時間単位付与・半日有給の扱いと例外
年5日取得義務と企業が取らせなければならないケース
2019年4月1日に施行された働き方改革関連法により、企業は労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています。
この義務は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)が対象です。企業は、有給休暇を付与した日から1年以内に、この5日間の休暇を取得させる必要があります。
年5日取得義務の主なポイントは、次の通りです。
- 義務化開始日:2019年4月1日
- 対象となる労働者:法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)
- 企業が取得させる義務のある日数:年間5日
- 取得させる期限:有給休暇を付与した日から1年以内
この義務を履行するため、企業は労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、有給休暇を取得する時季を指定できます。ただし、労働者自身がすでに年間5日以上の有給休暇を自ら申請・取得している場合は、企業が時季を指定する必要はありません。
一方、労働者が5日に満たない場合、企業側が時季を指定して取得させる義務があります。
この義務を怠った場合、企業は労働基準法第120条により、1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督署からの是正指導の対象にもなるため、有給の取得状況を正確に管理することが重要です。
時季指定義務の正しい運用方法と留意点
労働者に年5日の有給休暇を確実に取得させるため、企業は「時季指定義務」を適切に運用する必要があります。
これは労働者自身が5日取得していない場合に、企業が労働者の意見を聴き、その意見を尊重した上で、有給休暇を取得する時季を指定するという義務です。
時季指定を行う際の手順は以下の通りです。
- 対象となる労働者から希望する時期について意見を聴取します。(希望時季のアンケート調査や個別ヒアリングなどの方法で行うことが考えられます。)
- 聴取した労働者の意見を十分に尊重し、調整を図った上で、企業が具体的な有給休暇の取得時季を指定し、労働者に通知します。
時季指定にあたっては、労働者の意見を最大限尊重するよう努めることが法律で定められています。
また、労働者が指定した時季が「事業の正常な運営を妨げる場合」には、企業は他の時季に変更するよう求める「時季変更権」を行使できますが、これは限定的な場合にのみ認められる権利です。
一方的な時季指定や、時季指定を理由とした不利益な取り扱いは認められていません。企業はこれらのルールを守り、労働者が円滑に有給休暇を取得できるよう配慮する必要があります。
時間単位付与・半日有給の扱いと例外
年次有給休暇は原則として「日」単位で取得するものですが、労働者の多様なニーズに応えるため、「時間単位」や「半日単位」での取得制度を導入する企業が増えています。
まず、時間単位年休制度は、労働基準法で定められた制度です。導入するには、労使協定を締結する必要があります。
これにより、年5日分の年次有給休暇を限度として、時間単位で取得できるようになります。
例えば、「通院のために午前中だけ休みたい」、「子どもの学校行事に参加するために午後だけ抜けたい」といった場合に活用でき、仕事と生活の調和を図る上で有効な手段です。
一方、半日単位年休制度は、労働基準法に直接の定めがない、企業独自の制度です。導入するには、就業規則に規定を設ける必要があります。
午前または午後の半日を単位として取得できるため、終日の休みは必要ないが、午前中や午後いっぱいを休みたい場合におすすめです。
ただし、労働者に年5日の有給休暇取得を義務付けるにあたっては、時間単位で取得した有給休暇は、この5日の中に含めてカウントすることはできません。
これは、時間単位年休が労働者の請求に基づく時季指定の対象ではないためです。これに対し、半日単位で取得した有給休暇は、0.5日として年5日のカウントに含めることが可能です。
企業は、これらのルールを正確に理解し、適切に運用する必要があります。
有給休暇の管理簿・記録の義務とは?
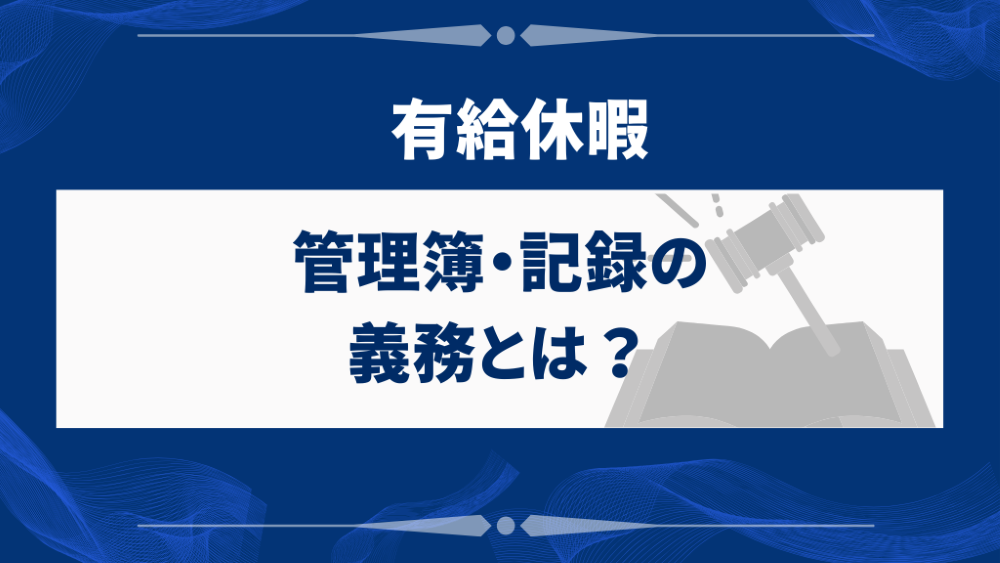
2019年4月の法改正により、企業は労働者の有給取得状況を正確に把握・管理する義務が課され、「年次有給休暇管理簿」の作成が必須となりました。
これはすべての労働者が対象で、企業規模を問わず適用されます。管理簿には基準日、付与日数、取得日数、残日数、取得時季を記載し、有給取得の記録として機能します。
以下では、次の内容を紹介します。
- 有給管理簿に記録すべき内容と保存期間
- 管理簿を作成していない場合のペナルティ
有給管理簿に記録すべき内容と保存期間
年次有給休暇管理簿には、労働者ごとに以下の項目を記録することが労働基準法で義務付けられています。これらの情報は、労働者の有給休暇の状況を正確に把握するために不可欠です。
- 基準日:労働者に年次有給休暇を付与した日です。最初の付与日以降は、原則として1年ごとに到来します。
- 付与日数:基準日において、労働基準法に基づき労働者に付与された年次有給休暇の日数です。
- 取得した時季:労働者が実際に年次有給休暇を取得した具体的な日付(または時間)です。時間単位や半日単位で取得した場合も記録が必要です。
- 残日数:付与された日数から取得日数を差し引いた、現時点での残りの有給休暇日数です。
これらの記録は、労働基準法第109条に基づき、作成と保存が義務付けられています。管理簿の保存期間は、「当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間」と定められています。
この期間を適切に守り、管理簿を保管することが企業には必須の対応です。紙媒体でも電子データでも保存可能ですが、必要な時にすぐにチェックできる状態にしておく必要があります。
管理簿を作成していない場合のペナルティ
年次有給休暇管理簿の作成と保存は、労働基準法によって企業に課せられた重要な義務の一つです。この義務を怠り、管理簿を作成していなかった場合、労働基準法違反となります。
具体的には、労働基準法第120条に基づき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。これは、対象となる労働者一人につき適用されるケースもあるため、複数の従業員がいる企業では罰金の総額が大きくなることも考えられるでしょう。
罰則だけでなく、管理簿の未作成は労働基準監督署による立ち入り調査(臨検)の際に指摘される事項であり、是正勧告や指導の対象となります。
是正勧告を受けたにも関わらず改善が見られない場合、さらなる厳しい措置が取られることも否めません。
また、このような状況は、企業の社会的信用を大きく損なうことにも繋がります。従業員は自身の有給取得状況を正確に把握できず、企業に対する不信感を抱く可能性も否定できません。
これは、従業員のエンゲージメント低下や離職リスクの上昇といった、長期的な企業経営にとって看過できない問題に発展する恐れがあります。適切な管理簿の作成・運用は、法的なリスク回避だけでなく、良好な労使関係を築く上でも不可欠です。
有給休暇を拒否・未取得にした場合の企業リスク
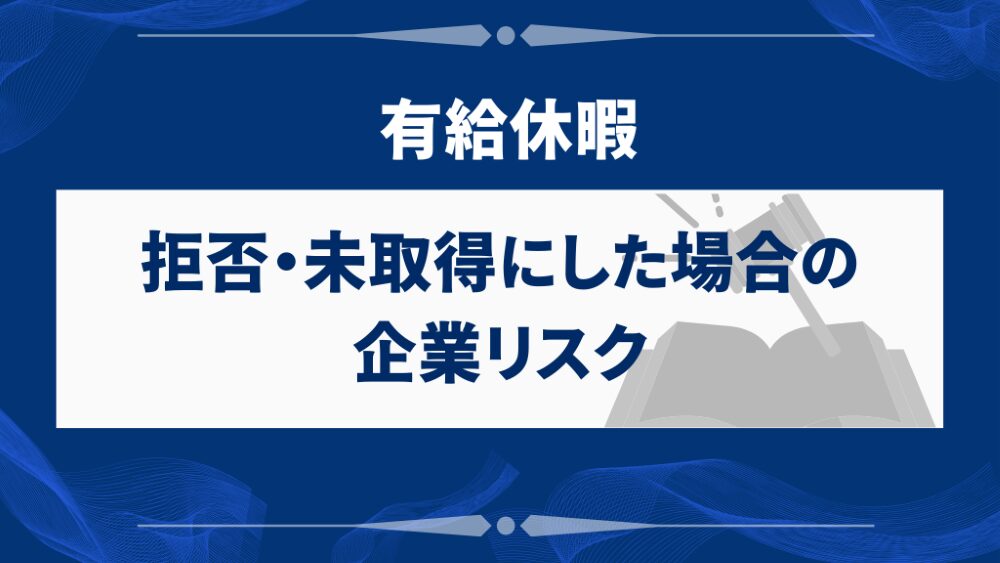
企業が有給休暇の取得を妨げたり、年5日の取得義務を怠ったりすると、法令違反や企業イメージの毀損といった深刻なリスクを招きかねません。以下では、その具体的なリスクと注意点を3つの観点から解説します。
- 年5日未取得は労基法違反!罰則と企業責任
- 有給取得を妨げるとどうなる?違法対応のリスク
- 有給買取や口頭却下の法的扱い
年5日未取得は労基法違反!罰則と企業責任
2019年4月の法改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、企業に「年5日の取得義務」が課されました。
この義務を履行しない場合、労働基準法第39条第7項違反とされ、労働者1人あたり最大30万円の罰金が科される可能性があります(労基法第120条)。
罰則の適用は従業員ごとに行われるため、対象者が多数に及ぶ企業では、リスクの影響も大きくなるでしょう。
また、違反が発覚した場合は、労働基準監督署の是正勧告や書類送検といった行政措置の対象となるケースもあります。
さらに、有給休暇を取得できない職場環境は、従業員の心身疲労の蓄積やモチベーションの低下、離職率の上昇を引き起こす要因にもなり得ます。こうした状態は、企業の生産性やエンゲージメント、そして対外的な信用にも悪影響を及ぼしかねません。
実際に、取得義務を怠ったことで書類送検された事例も報告されています。法令遵守と働きやすい職場環境の両立を実現するうえでも、年5日の有給休暇取得は、企業が軽視できない責任といえるでしょう。
有給取得を妨げるとどうなる?違法対応のリスク
労働者からの適法な有給休暇の申請に対して、企業が不当な対応を取ることは、労働基準法違反となる可能性があります。
例えば、以下のような行為が労働基準法違反にあたります。
- 有給休暇取得の理由を執拗に詮索する
- 本来認められない状況で時季変更権を行使する
- 有給を取得したこと自体を理由に評価を下げる
- 降格させるなどの不利益な取り扱いを示唆する
このような有給休暇の取得を妨げる行為は、労働者の正当な権利を侵害するものです。また、労働基準法第39条に違反する可能性が高いです。
労働基準法第119条に基づき、これに違反した使用者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、法的な罰則だけでなく、企業は以下のような様々な経営上のリスクを負うことになります。
- 従業員の企業に対する信頼の喪失、士気の低下
- 生産性の低下
- 優秀な人材の離職
- インターネット上の口コミ等による企業評判の悪化
- 新たな人材採用への悪影響
過去には、有給休暇取得を妨害されたとして従業員が損害賠償を請求し、これが認められた裁判例も存在します。
企業は労働者の有給休暇取得権を尊重し、適切な対応を取る必要があるでしょう。
有給買取や口頭却下の法的扱い
年次有給休暇をめぐっては、「休暇を買い取ってもらえないか」、「申請したのに口頭で却下された」といった疑問やトラブルが生じる場合があります。これらの行為は、法的にどのように扱われるのでしょうか。
まず、有給休暇の「買取」は、原則として労働基準法で認められていません。これは、労働者に確実に休暇を与え、心身の疲労回復を図るという有給休暇制度の趣旨に反するからです。しかし、例外的に買取が認められるケースがあります。
例えば、法定の日数を超えて会社が付与した有給休暇や、退職時に未消化となっている有給休暇、時効により消滅する有給休暇などです。ただし、これらの場合も企業に買取の義務はなく、労働者の同意が必要となります。
次に、有給休暇の申請に対する企業の対応についてです。労働者には、原則として希望する時季に有給休暇を取得できる「時季指定権」があります。
企業は、労働者が指定した時季に休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ、他の時季に変更を求める「時季変更権」を行使できます。
したがって、正当な理由がないのに有給休暇の申請を一方的に却下したり、ましてや口頭で安易に拒否したりする行為は、労働基準法に違反する可能性が高いです。
不適切な有給買取や、理由なき却下を行った場合、企業は労働基準監督署からの指導や是正勧告の対象となるだけでなく、労働基準法違反として30万円以下の罰金等の罰則が科されるリスクがあります。
さらに、労働者から損害賠償請求を受ける可能性も否定できません。企業は有給休暇に関する正しい知識を持ち、法令を遵守した対応を行うことが不可欠です。
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
有給管理を効率化するシステム活用と専門家相談のすすめ
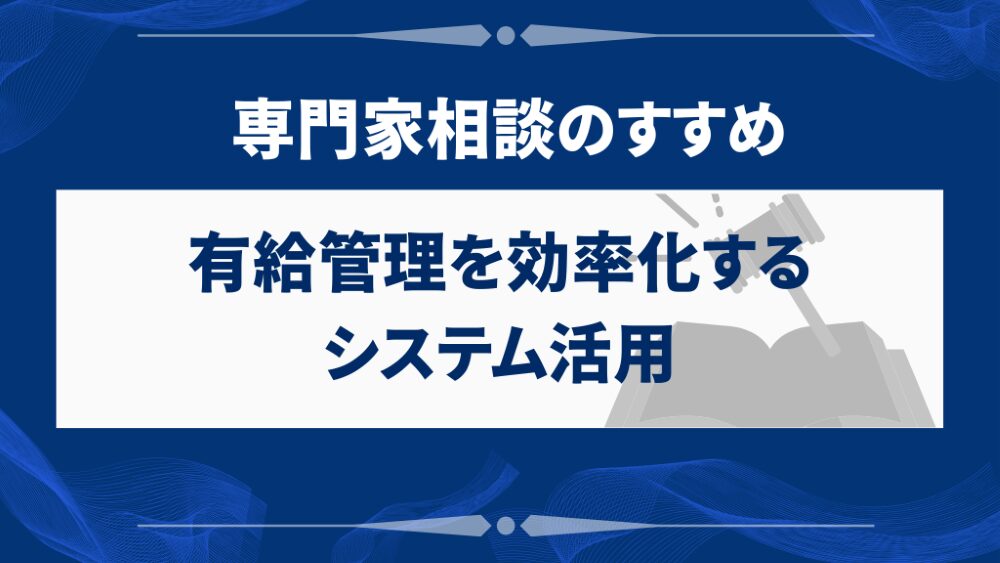
法改正により有給休暇の管理は複雑化し、手作業ではミスや記録漏れが起こりやすくなっています。その対策として、有給管理システムの導入や社会保険労務士への相談が有効です。
システムは付与日数の自動計算や取得状況の管理、アラート機能により効率化。複雑な労務問題には専門家のアドバイスが役立ち、法令違反のリスク軽減にもつながるはずです。
以下では、次の内容を紹介します。
- 有給管理システムでミスゼロに!導入のメリット
- サポートが必要な場合は社労士や労基署へ相談
有給管理システムでミスゼロに!導入のメリット
年次有給休暇の管理では、付与日数の計算、取得状況の記録、残日数の把握など、多くの作業が発生します。これを紙やExcelで行っている場合、計算ミスや記入漏れといったヒューマンエラーが起こりやすく、担当者の負担も大きくなりがちです。
こうしたリスクを回避する手段として、有給管理システムの導入が有効です。入社日や勤続年数に応じた付与日数の自動計算、取得状況や残日数のリアルタイム管理、さらには年5日の取得義務や時効(2年)に関するアラート機能など、法令対応を強力にサポートする機能が備わっています。
また、申請・承認・記録といった一連の流れをシステム上で完結できるため、業務効率が大幅に向上します。従業員にとっても、自分の残日数や取得履歴をいつでも確認できる環境が整うことで、有給取得への心理的ハードルが下がり、取得率の向上が期待できるでしょう。
有給休暇管理を適切に行うことは、企業のコンプライアンス対応だけでなく、従業員満足度や労働環境の改善にもつながります。法令違反のリスクを防ぎ、働きやすい職場づくりを実現するためにも、システムの活用は重要な施策のひとつと言えるでしょう。
サポートが必要な場合は社労士や労基署へ相談
有給休暇を含む労務管理は、法改正への対応や制度運用の面で専門的な知識が求められる場面が多くあります。対応に不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)や労働基準監督署に相談するのがおすすめです。
社労士は、就業規則の整備や有給管理制度の構築、法令対応のアドバイスなどを通じて、企業の労務リスクを未然に防ぎ、実務面でのサポートを行います。制度設計から運用までを一貫して支援できるため、継続的な労務管理の強化にもつながります。
一方で、労働基準監督署は、労働基準法に違反している疑いがある場合や、是正・指導を必要とする場面で相談できる行政機関です。賃金未払いや有給取得妨害、不当な対応が疑われるケースでは、従業員側からの相談窓口としても機能します。
課題が予防的か、すでに問題が発生しているかによって、相談先を適切に選ぶことが大切です。労務管理に不安がある企業は、早めの相談を検討しましょう。
【事例紹介】有給管理ミスで指導・罰則を受けたケース集
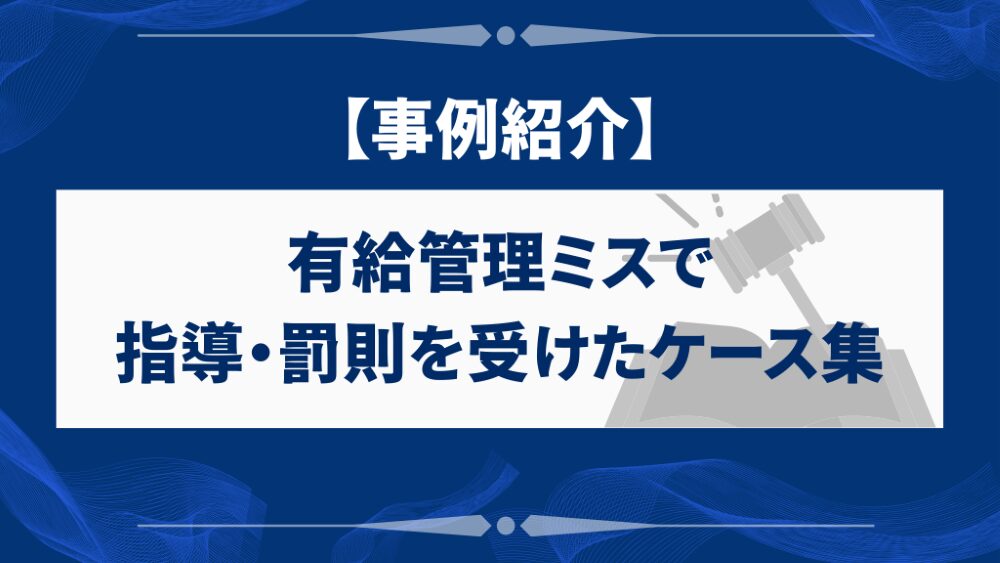
労働基準法39条に基づく有給休暇の管理義務を怠った結果、実際に企業が指導や罰則を受けた事例が複数報告されています。
たとえば、ある製造業の企業では、年5日の有給休暇取得義務(2019年施行)に対応していなかったことが発覚し、労働基準監督署から是正勧告を受けました。
この企業は「取得の管理は個人に任せていた」という姿勢で、有給休暇管理簿の作成すら行っていませんでした。結果的に、複数の労働者が法定5日間を取得できていない状態にあり、1人あたり最大30万円の罰金対象となる可能性が生じました。
また、別のケースでは、小売業の会社がアルバイト従業員の有給取得申請を「人手不足」を理由に却下し続け、労働者から労基署に通報。調査の結果、不当な時季変更権の行使とみなされ、労働基準法第119条違反として是正指導が行われました。
このような事例に共通するのは、「有給管理の曖昧さ」と「ルールを知らないことによる対応ミス」です。小規模企業であっても例外ではなく、法律を軽視した対応は即座にリスクとなり得ます。
まとめ|労働基準法39条を理解し、企業リスクを未然に防ごう
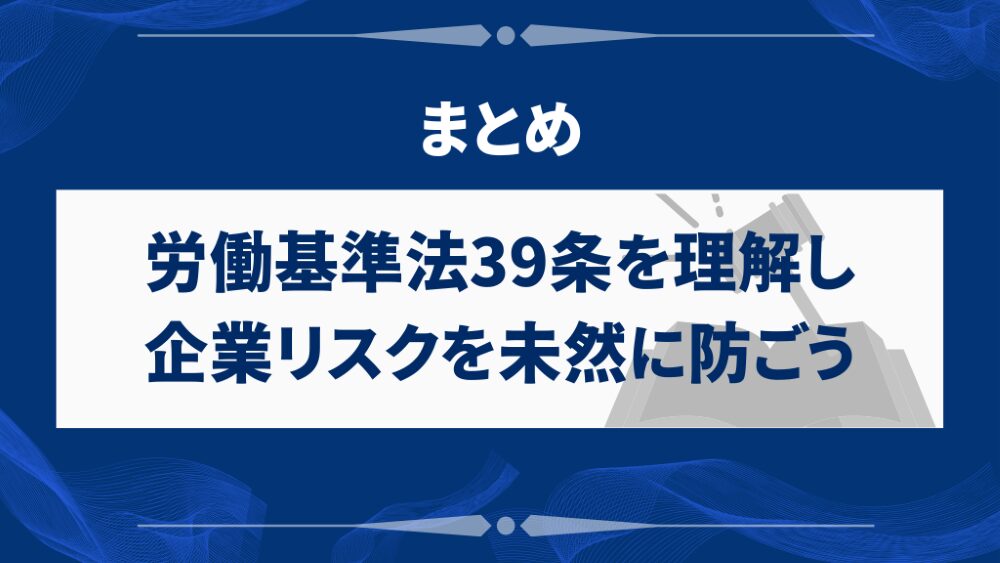
年次有給休暇の取得は、労働者にとって当然の権利で、それを適切に付与・管理することは企業に課せられた重要な義務です。
とくに2019年の法改正によって「年5日の取得義務化」や「有給管理簿の作成・保存義務」が明確に制度化されて以降、法令違反に対する監督や罰則は強化の一途をたどっています。
実際に、有給休暇の取得を怠ったり管理簿を作成していなかった企業が、労働基準監督署の是正勧告や罰金、場合によっては書類送検にまで至ったケースも少なくありません。
こうしたリスクは、経営の信頼性や従業員のモチベーション低下にも直結し、組織全体のパフォーマンスを損なうことになり得ます。
一方で、こうした問題は「法令知識の欠如」や「管理体制の不備」に起因していることが多く、早期に対処することで十分に回避可能です。
現在では、社労士や弁護士といった専門家によるサポート体制や、クラウド型の有給管理システムなどを活用することで、法令遵守と実務の効率化を両立させることができます。
「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされないのが、労働基準法39条の現実です。もしあなたの企業が有給管理や就業規則の整備に不安を抱えているなら、まずは労働法務に強い専門家に相談することが最善の第一歩です。
退職を考えている方は城都不動産株式会社が運営している不動産WEB相談室の以下の記事も役に立つと思いますのでご参考ください。
退職代行おすすめランキング6選!サービス内容や料金を徹底解説!
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ
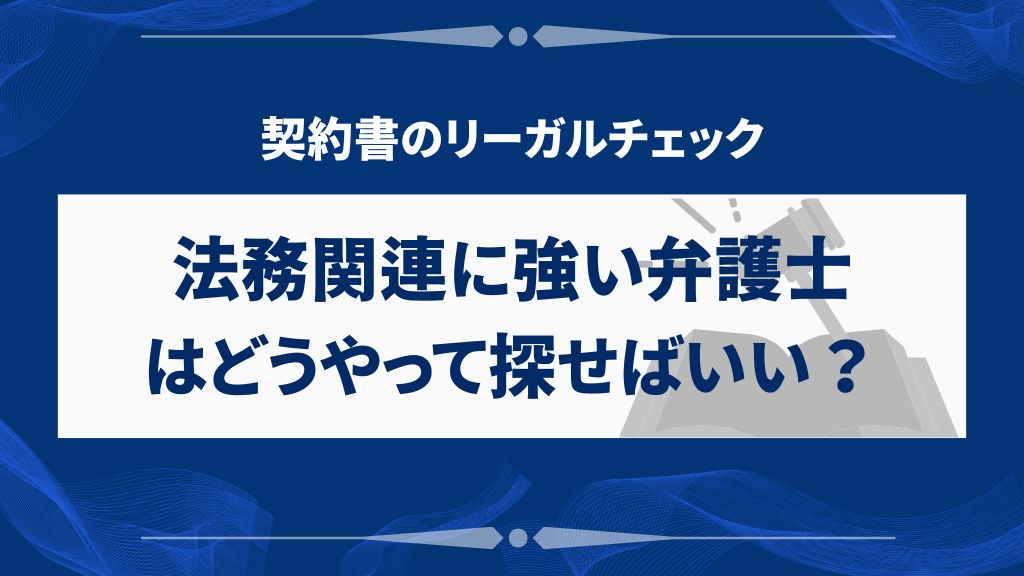
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












