役員退職慰労金の訴訟事例や基本ルール、法律上のポイントを解説
労働問題・労働法務
2025.02.06 ー 2025.05.06 更新
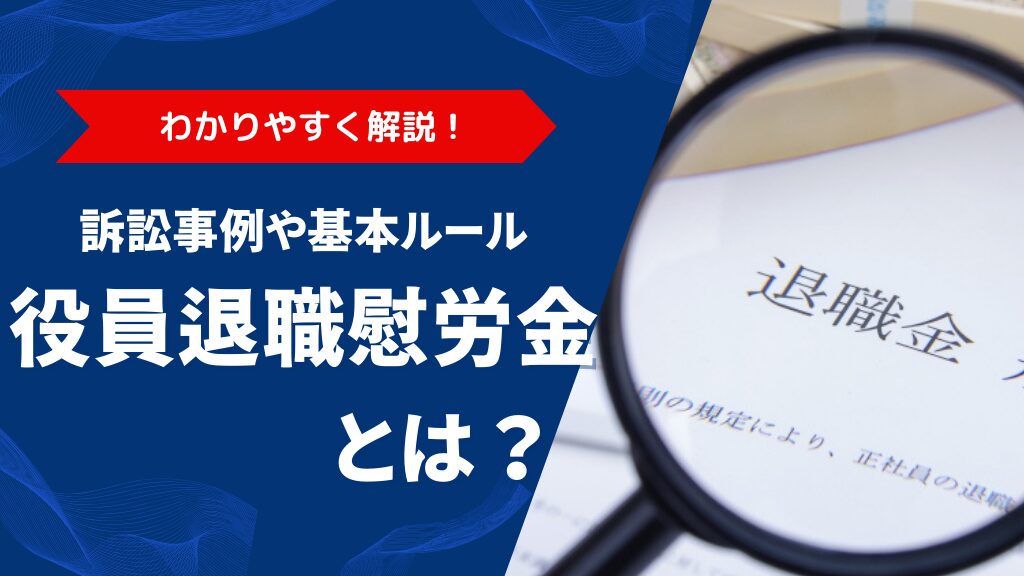
役員になってほしいと依頼された場合や、すでに役員として業務を行っている場合、退職金はもらえるのか?と疑問に思ったことはないでしょうか?
会社と役員の関係やは民法上の委任契約が基本とされており、通常の労働契約や雇用契約ではありません。そのため、従業員向けの退職金規定は原則として適用されないことになります。
本記事では、会社役員が退任する際の退職慰労金の仕組みや訴訟になりやすい事例等を解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。
役員退職金の相談ができる弁護士を探す➜

〒460‐0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目18-1 三晃丸の内ビル10階
・労働事件の企業法務の経験
・【顧問契約】【契約書作成・確認】【債権回収】【労使問題】【クレーム対応】事前にご連絡いただければ時間外・定休日でもご対応いたします。
契約書・リーガルチェック 訴訟・紛争解決
- 法律一辺倒ではなく、親切、丁寧に対応することはもとより、じっくりとお話に耳を傾けます。
- ご依頼者の希望を汲み取り、迅速、的確に実現してご満足いただけるよう最大限の努力をいたします。
- 離婚、交通事故、企業法務は弁護士になってから一貫して取り組んでおり事例も豊富です。
| 住所 | 〒460‐0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目18-1 三晃丸の内ビル10階 |
| 最寄駅 | 地下鉄名城線、桜通線「久屋大通駅」西改札2番出口から徒歩3分 |
| 対応エリア | 愛知県 |
顧問契約/契約書作成・確認/債権回収/労使問題/クレーム対応/分割払い可/後払い可/休日面談可/夜間面談可/電話相談可
役員退職慰労金とは?仕組みと支給の基本ルール

役員退職慰労金は、企業が役員の長年の貢献に報いるために支給する特別な報酬です。通常、役員が任期満了または辞任により退任する際に支払われ、その金額は在任期間や業績などを考慮して決定されます。この制度は、役員のモチベーション維持や優秀な人材の確保を目的としています。
役員退職慰労金は法律上の用語ではなく、あくまで役員報酬の一種です。そのため役員退職慰労金の決定機関は定款または株主総会であり、その取り決めがなければ原則として支払いは行われません。
ただし当該決議等がなくても、同等の意思決定があったとされる場合や、不払いが信義則上認められないケースなど、退職慰労金の支払いが認められたケースもあります。
近年では役員退職慰労金制度を廃止する企業も増えており、その背景には企業統治の強化や経営の透明性向上への要請があります。また、業績連動型報酬の導入など、役員報酬体系の見直しも進んでいます。
役員退職慰労金をめぐっては、支給の是非や金額の妥当性について株主や社会から厳しい目が向けられることもあり、企業は慎重な対応を求められています。
役員退職慰労金の法律上の考え方
会社役員と会社の関係は、民法上の委任契約に基づくとされています。委任契約は民法上無報酬が原則であり、特約がなければ報酬を請求できません。
そして役員退職慰労金は役員報酬のひとつであり、報酬の決定は定款または株主総会決議によって行われるのが原則です。
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
会社の事業利益は変動するため、役員報酬や退職慰労金の具体的な金額を定款で定めておくケースはほとんどなく、通常は株主総会で定めることになります。なお、業績が良い場合等に、臨時株主総会で役員賞与を定めることも可能です。
報酬の定め方は、具体的な金額で定める方法のほか、業績に合わせた変動制となるように計算方法を定めたり、上限額のみを定めて取締役会に金額や計算を委任したりする方法も一般的です。
役員退職慰労金も『報酬』であるため、定款の定めか株主総会、または株主総会の委任に取締役会の決定などが必要となります。
株主総会決議等を得ずに役員報酬を受け取った場合、法律上の原因がないことになるため、報酬の返還や賠償を求められるケースも発生します。
取締役の報酬に関する会社法規定は、下記の引用のとおりです。
(取締役の報酬等)
第三百六十一条:
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一:報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二:報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三:報酬等のうち当該株式会社の募集株式(中略)については、当該募集株式の数(中略)の上限その他法務省令で定める事項
四:報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(中略)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五:報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
イ:当該株式会社の募集株式 取締役が引き受ける当該募集株式の数(中略)の上限その他法務省令で定める事項
ロ:当該株式会社の募集新株予約権 取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
六:報酬等のうち金銭でないもの(中略)については、その具体的な内容
役員退職慰労金が支給されないケースとは?

役員退職慰労金が支給されないケースは、いくつか存在します。
まず、会社の定款や社内規定に支給の定めがない場合が挙げられます。また株主総会で否決されたケースも該当します。これらの場合、法的根拠が乏しくなるため、支給が困難になる可能性が高まります。
さらに役員が問題を起こして解任された場合も、退職慰労金が支給されないことがあります。会社に損害を与えたり、信用を失墜させたりするような行為があった場合、支給の正当性が問われる可能性があるためです。支給が決定していても金額が減額されたり、支給自体が拒否されたりするケースもあります。取締役の独断で他の取締役に退職慰労金を支払ったような場合にも、原則として返還請求の対象となります。
反対に、解任が不当であると主張する場合には、役員としての地位確認のほか、報酬の請求、損害賠償等を会社に対して請求するケースもあります。
こうした状況では、会社との交渉や法的手段を検討する必要が出てくるでしょう。ただし具体的にどのような対応が最適かは、個々の状況によって異なります。
役員退職慰労金を巡る法的トラブル事例
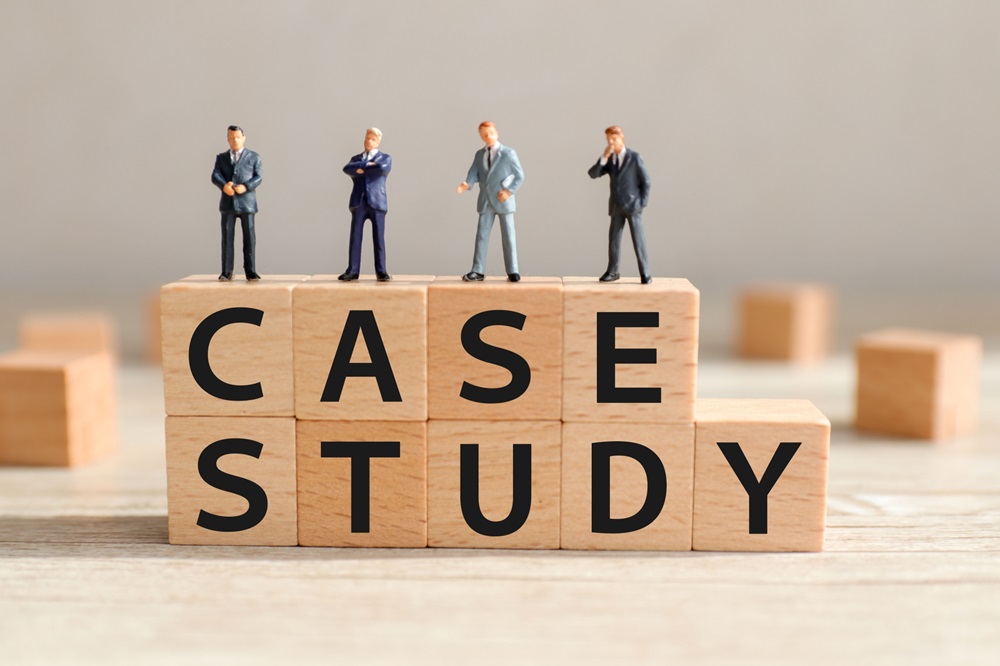
役員退職慰労金は役員報酬の一種であり、雇用・労働契約における賃金とは法的性質が異なります。
年額や月額の役員報酬については、就任の際に決定することが多いですが、退職金については就任時点で将来の業績等を予想することが難しいことなどから、確約することは一般的に難しい場合が多いです。
役員報酬を定めるには定款、株主総会、または株主総会による取締役会への委任等が必要ですが、これらの決議要件を欠いたまま報酬が支払われたり、役員退職慰労金の規定が策定されたりすると、その有効性がしばしば問題になります。
このような法的トラブルを避けるためには、事前に退職慰労金の支給規定を明確にし、透明性のある手続きを踏むことが重要です。しかし、規定があっても解釈の余地が残る場合もあり、完全な予防は難しいかもしれません。
過去の判例を参考にしつつ、個々の状況に応じた適切な対応が求められるでしょう。以下、争いになりやすい事例について紹介します。
事例1)定款の定めや株主総会の決議なく役員退職慰労金を支給した場合
定款の定めや株主総会の決議がないまま、取締役等の決定によって退任した役員に対し役員退職慰労金を支給した場合、法律上の原因がないまま報酬を支給したことになるため原則として返還が必要です。
取締役は、株主からの委任によって会社財産や経営を任された立場であり、会社財産の中から自己の報酬を決定する権限はありません。また善管注意義務や忠実義務を負うため、これに反して自己や第三者の利益を優先した場合には、損害賠償責任を負う可能性や背任罪に該当する場合もあります。
取締役が他の退任する取締役に対して自由に退職慰労金を渡すことができてしまうと、お手盛りやキックバック等の危険も発生するため、会社との関係で許されません。
ただし会社の事情を考慮し、返還請求が権利の濫用であるとされ支払いが認められた事例などもあります。
こうした事例が発生した場合には速やかに弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
事例2)株主全員の同意がある場合
定款の定めか株主総会などの法律上の要件を欠く場合、原則として役員退職慰労金の支給はできません。
ただし実質的に株主全員の同意がある場合には、定款変更や株主総会の決議を経ていなくても、退職慰労金の支払いが認められるとされた事例があります。
原則として、定款変更は株主総会特別決議、報酬決定は普通決議によってそれぞれ行われますが、それぞれ株主全員の同意よりも少ない賛成数で済む決議と言えます。そのため、定款変更や株主総会の手続きを経ていなくても、全員同意があれば信義則上は退職慰労金の支払いを認めていると言えるのでしょう。
事例3)退職金が支払われる旨の契約を代表取締役等と行っていた場合
役員としての入社時もしくは入社後に、会社(代表取締役や取締役会等)との間で退職金が支払われる旨の契約を行った場合、退職金を受け取れるのでしょうか?
答えとしては、本件契約のみでは退職金を受け取れないのが原則です。
なぜなら代表取締や取締役会による意思決定と株主総会決議による決定は、次元が違うためです。そもそも会社のオーナーシップは株主にあり、取締役らは経営を受任している立場です。そのため取締役らには会社財産から自己の報酬や他の役員報酬を自由に決定する権限はありません。
この場合は本件契約の他に、定款の定め、株主総会の決議、または株主総会による取締役会への委任等が必要となります。
事例4)取締役兼従業員の場合の退職金の扱い
取締役兼従業員という働き方をしている場合、取締役の地位においては委任契約、従業員の地位においては労働契約が行われていると考えられます。
取締役としての退職金は役員報酬であり、従業員としての退職金は賃金としての性質があります。そのため請求にかかる法的な根拠は別物です。
このような場合、役員としての退職慰労金を否定して従業員としての退職金を特定して支払いが命じられた事例があります。
判例1)退職金請求事件 平成18年12月14日 大阪高等裁判所
本判決は、会社の執行役員を退任した者が会社に対し退職慰労金の支払を請求することができないとされた事例です。
本判決においては、争いとなった会社における退職金内規の性質を考慮し、退職金の請求を認めないこととされました。
引用元:裁判所最高裁判所判例集
全文:pdf
会社の従業員であった者が退職して執行役員に就任し、その後退任した場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,会社が従前支給してきた内規所定の金額の退職慰労金は,功労報償的な性格が極めて強く、執行役員退任の都度,代表取締役の裁量的判断により支給されてきたにすぎないものであり,上記の者が会社に対し退職慰労金の支払を請求することはできない。
(1) 会社の導入した執行役員制度の下において、執行役員は、従前は取締役が就いていた職務上の地位に就任し、報酬その他の待遇面においても、従前の取締役と同等の待遇が保障されていた。
(2) 上記制度の下において、従業員であった者が執行役員に就任する場合、いったん退職した上で、取締役会からの委任により執行役員に就任するものとされていた。
(3) 退職慰労金の支給金額を定めた上記内規は,代表取締役の決裁で作成,改定されるものであり,上記内規には,退任する執行役員に対し退職慰労金を支給する場合に適用する旨が定められていたにすぎず,これを必ず支給する旨の規定は置かれていなかった。
判例2)退職金返還請求事件 東京地方裁判所(第一審)
本判決は、退職慰労金につき、送金したお金の返還を求めることは信義則に反するとして退職慰労金の支払いを認めた事例です。
本事例における会社において、事前に株主総会の決議を経ることなく退職慰労金が支払われることが慣習となっており、発行済株式の99%以上を保有する代表者の決済によって追認するという形で行われていました。
本件では退任した役員への慰労金が送金されたあと約1年後に返還請求がされたものであり、信義則に反して返還請求は許されないとされました。
会社法上の決議要件を経ていない場合でも、同等以上の意思決定があり、慰労金の返還請求が権利の濫用にあたるようなケースでは、支払いが認められることがあります。
役員退職慰労金の支給を拒否または減額された場合の具体的な対応策

役員退職慰労金の支給拒否や減額に直面した場合、まず冷静に状況を分析することが重要です。
初めに、定款の確認を行いましょう。会社法31条により、定款は会社本店及び支店への備え置く義務があり、株主及び債権者は閲覧や謄写請求が可能です。(謄写の場合、定められた手数料を支払います。)
ただし、定款に役員報酬が記載されていることは稀です。定款に記載がない場合、株主総会決議が必要になります。
会社の決定に納得がいかない場合、社内での対話を試みる方法があります。取締役会や株主総会での決定の経緯や根拠を確認し、自身の貢献度や実績を丁寧に説明することで再考の余地を探ることができるかもしれません。
ただし、直接の対話によって争いが大きくなってしまうケースもあるため、早めに弁護士など専門家のアドバイスを受けることが賢明です。
交渉のために証拠となり得るものは基本的に全て残しておくようにしましょう。
企業との交渉が難しい場合は弁護士への相談が有効
役員退職慰労金のトラブルに関しては弁護士への早めの相談が有効です。
慰労金を請求したい場合、請求できる法律の根拠が必要です。専門家でなければ、事例と法的根拠の判断が難しい場合があります。また、根拠をもとに本人が会社に対して主張を行っても取り合ってもらえないケースもあるでしょう。
専門家に相談するメリットは、法的な観点から状況を分析し、最適な対応策を見出せることにあります。また交渉の場に弁護士が同席することで、より公平な立場での話し合いが可能になります。
事案についての方針も明確になるため、精神的な安心にもつながります。
事前に準備すべき書類と証拠
役員退職慰労金の請求に際しては、適切な書類と証拠の準備が不可欠です。退任前にできるだけ資料を準備しておきましょう。
例えば、定款や退職金に関する社内規定、退職慰労金の支払いを決議した株主総会議事録、過去の支払い実績、自己の勤務実績や功労実績を表す資料などです。
これらは、退職慰労金の妥当性を裏付ける証拠となります。
さらに、退職に至る経緯を示す文書、例えば辞任届や退職願の写しも準備しておくべきでしょう。これらは、退職が正当な手続きを経て行われたことを証明します。
これらの書類や証拠を事前に整理し、必要に応じて弁護士などの専門家のアドバイスを受けることで、より適切な請求を行うことができるでしょう。
最後に、会社との良好な関係を維持することも忘れてはいけません。退職後も取引先や業界内での評判に影響する可能性があるため、互いの立場を尊重しながら建設的な話し合いを心がけることが長期的には有利に働く場合があります。
役員退職慰労金についてのご相談は、法務救済から弁護士をお探しください
役員退職金は、企業運営の中で重要な役割を果たす一方で、法的な問題や計算方法など、複雑な点が多いものです。退職金の計算が不適切だったり、法的に問題がある場合、後々トラブルになることもあります。
法務救済では、役員退職金に関する法律相談を扱う弁護士を簡単に検索し、相談することができます。信頼できる弁護士を探し、まずは無料相談からスタートして、今後の対応方法をしっかりと確認していきましょう。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












