取締役の退職金を巡る訴訟を回避する対策やトラブルの解決方法を徹底解説
訴訟・紛争解決
2025.03.26 ー 2025.03.28 更新
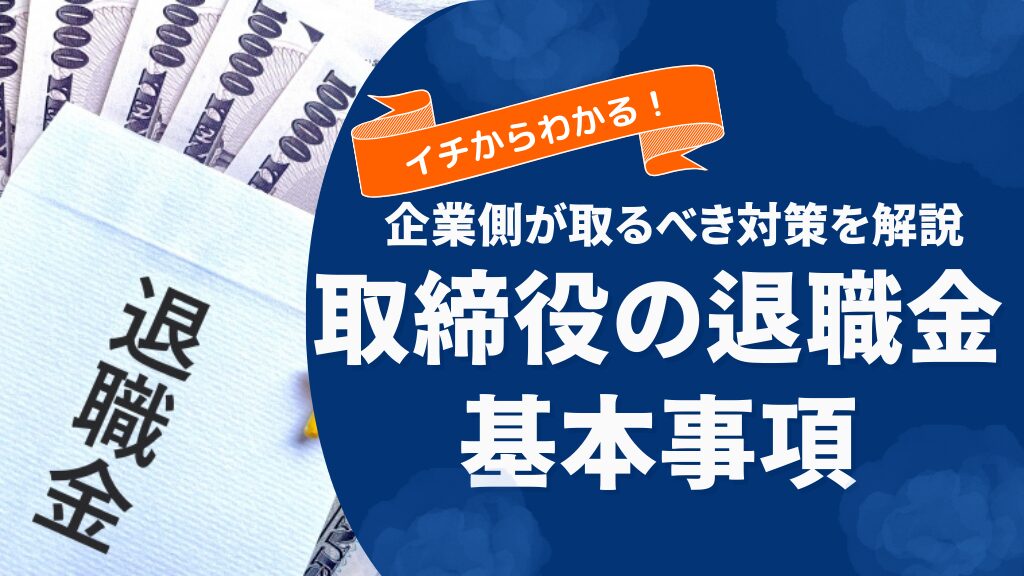
取締役という会社でも重要なポストを担った人材が退職する場合、高額な退職金を請求されることがあります。企業としては、退職金を巡って訴訟を引き起こさないための対策が必要です。
また、取締役が退職金を多く受け取ろうとしている可能性もあります。そのため、退職金の支払いが法的に認められるかを判断し、適していない場合は断ることも可能です。
この記事では、取締役の退職金に関する基本事項や企業側が取るべき対策について解説していきます。退職金を巡る訴訟問題を解決したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>取締役と従業員の退職金の違い

取締役と従業員の退職金には、法的な性質や決定方法に違いがあります。
従業員の退職金は、以下のようなものに基づいて支給されることが一般的です。
- 労働基準法
- 就業規則
- 労働協約
企業によっては退職金制度を設けていない場合もありますが、制度がある場合は事前に基準が定められており、長年の勤続に対する報酬として支給されます。
一方、取締役は会社の経営を担う立場であり、退職金は労働基準法の適用外です。そのため、金額や支給の可否について明確なルールがなく、株主の判断が大きく影響することになります。
また、税務上従業員の退職金は「退職所得」として扱われ、優遇税制が適用されることが多いです。一方で取締役の退職金は「役員退職慰労金」として支給されるため、税務上の制約を受けやすく、適正額を超えると法人税の課税対象になる可能性があります。
役員退職慰労金とは?
役員退職慰労金とは、取締役や監査役などの会社役員が退任する際に支給される報酬のことを指します。労働基準法に基づく従業員の退職金とは異なり、役員としての功績や会社への貢献度を評価して支払われるものです。
役員退職慰労金の支給には、株主総会の承認が必要です。会社法上、株主総会での決議を経ることで適正な支給が確保される仕組みになっています。一般的には役員報酬の一定割合を基準に算出されることが多いですが、明確な法律上の基準は存在しません。
税務上、役員退職慰労金は「退職所得」として扱われるものの、支給額が不相当に高額であると認定された場合、会社側に法人税の追徴課税が発生する可能性があります。また、適正額を超えた部分については、受け取る役員側にも厳しい税務上の扱いが適用されます。
取締役の退職金請求を拒否できるケース

取締役への退職金の支払いに関するトラブルにおいて、企業が支払いを拒否できるケースがあります。以下のケースに該当する場合、企業は取締役への退職金の支払いを拒むことが可能です。
- 不祥事を理由とした退職の場合
- 株主総会の決議で支払いが拒否された場合
それぞれのケースについて解説していきます。
不祥事を理由とした退職の場合
取締役が在任中に重大な法令違反や社内規則違反を犯し、企業に損害を与えた場合、退職金の支給を制限または拒否することが可能です。
会社法上、取締役の退職金は株主総会の決議を経て支給が決まるため、不祥事が発覚した場合、株主がその支給を拒否する判断を下すことができます。以下のような経済犯罪に関与したケースでは、会社の信用や財務状況に悪影響を及ぼすため、退職金を支払わない合理的な理由として有効です。
- 横領
- 背任行為
- 粉飾決算
また、企業が就業規則や役員報酬規程に「懲戒解任された場合は退職金を支給しない」といった条項を定めている場合も、退職金の支払いを拒否する根拠となります。ただし、取締役は労働者ではないため、取締役会や株主総会で正式に解任手続きを行うことが必要です。
企業としては、取締役の不祥事が発覚した時点で調査を行い、退職金の支払い可否を慎重に判断することが重要になります。
株主総会の決議で支払いが拒否された場合
株主総会で支払いが拒否された場合、取締役は退職金を請求することができません。取締役の退職金は従業員の退職金と異なり、労働基準法の適用を受けないため、株主総会での決議が重要になります。
株主総会で退職金の支払いが拒否される理由として、以下のようなものが挙げられます。
- 会社の業績悪化
- 取締役の経営責任
- 企業の資金繰りの問題
また、定款に「退職金は株主総会の決議をもって決定する」と明記されている場合、取締役は支給を強制することができません。
企業側としては、取締役の退職金支給に関するルールを明確にし、あらかじめ合理的な基準を設定することが望ましいです。
取締役の退職金に関連する訴訟判例

取締役の退職金を巡って訴訟まで発展した判例として、以下の3つがあります。
- 株式会社テレビ宮崎
- 東京地裁平成6年12月20日の判決
- 東京地裁平成20年9月24日の判決
各判例について解説していきます。
判例1:株式会社テレビ宮崎
株式会社テレビ宮崎の前社長が退職慰労金の減額を不服として起こした訴訟事例があります。
前社長は在任中、社内規程を超える宿泊費の受領や、過剰な交際費の支出などが指摘されていました。これらの行為により、同社は約3億5,551万円の損害を被ったとされています。
同社の取締役退任慰労金内規には、「在任中特に重大な損害を与えたもの」に対しては、退職慰労金を減額できる旨が定められており、取締役会はこの規定に基づき、退職慰労金を基準額の85%減額し、5,700万円とする決議を行いました。
前社長はこの減額を不当として訴訟を提起し、一審・二審では減額は裁量権の逸脱・濫用に当たるとして、会社側に約2億円の支払いを命じる判決が下されました。
しかし、最高裁判所は「取締役会には退職慰労金の減額に関して広範な裁量権があり、同社の減額決議は合理的な根拠に基づくもので、裁量権の逸脱・濫用は認められない」と判断し、前社長の請求を棄却しました。
判例2:東京地裁平成6年12月20日の判決
取締役の退職金に関する訴訟の一例として、東京地方裁判所が平成6年12月20日に下した判決があります。退任した取締役が、株主総会で退職慰労金の支給が決議されたにもかかわらず、取締役会が具体的な金額や支給時期を決定しなかったことが問題となりました。
株主総会において退任する取締役への退職慰労金の支給が決議され、その金額や支給時期、方法などの決定が取締役会に一任されました。しかし、その後取締役会は合理的な期間内にこれらの詳細を決定せず、結果として退任取締役への退職慰労金の支払いが長期間にわたり行われませんでした。
裁判所は、このような取締役会の対応を「取締役としての善管注意義務および忠実義務に違反する任務懈怠」と判断しました。その結果、取締役個人に対しても損害賠償責任が認められ、約5,000万円の賠償が命じられました。
この判例は、取締役会が株主総会の決議を受けて速やかに対応を取らない場合、取締役個人が任務懈怠として損害賠償責任を負う可能性があることを示しています。
判例3:東京地裁平成20年9月24日の判決
東京高等裁判所が平成20年9月24日に下したものとしては、株主総会で取締役の退職慰労金の支給が決議され、詳細な決定を取締役会に一任することが決められたということを発端とする事例があります。
しかし、取締役会は何ら合理的な理由もなく、長期間にわたりこれらの詳細を決定せず放置しました。結果として退任した取締役は、取締役会の構成員である取締役らに対し、任務懈怠があるとして損害賠償責任を追及しました。
裁判所は「取締役会が合理的な理由なく退職慰労金の詳細を決定せず放置したことは、取締役としての任務を怠ったものである」と認定し、取締役らに損害賠償責任を認めました。
取締役会が株主総会からの一任を受けた事項を処理しない場合、取締役個々人が任務懈怠として損害賠償責任を負う可能性があることを、この判例が示しています。
退職金を巡る訴訟問題を防ぐ方法

企業としては、退職金を巡るトラブルを訴訟まで発展させたくないと考えるでしょう。これらの対策としては、未然に防止することに加え、問題が表面化した際に素早く行動することが重要です。
訴訟問題への発展を防ぐ対策として、以下の4つが有効です。
- 取締役の実績や貢献度を評価する
- 株主総会では議事録を作成する
- 定款を確認しておく
- 労務問題に強い弁護士に相談する
それぞれの対策方法について解説していきます。
取締役の実績や貢献度を評価する
取締役の退職金を巡る訴訟問題を防ぐには、退職金の支給基準を明確にし、公平性を確保することが重要です。その方法の一つとして、取締役の実績や貢献度を客観的に評価する仕組みを導入することが挙げられます。
取締役の企業への貢献度を評価する指標として、以下のような項目を設けましょう。
- 在任中の経営成績
- 株主への利益還元
- 企業の成長への寄与
- 業績目標の達成度
- 利益の増加率
- コーポレートガバナンスの向上に関する取り組み
客観的なデータに基づいて支給額を決定することで、株主や他の利害関係者からの異議を最小限に抑えることができます。
また、評価基準を社内規程として定めておくことで、不透明な判断によるトラブルを防ぐことが可能です。株主総会での決議の際にも合理的な説明ができるため、取締役自身の納得感も高まり、不必要な訴訟リスクを回避することにつながります。
株主総会では議事録を作成する
株主総会で退職金の支給を決議する際に、議事録を記録しておくことで、後に訴訟が発生した場合に証拠として活用できます。
株主総会の議事録には、以下のようなことを記録しましょう。
- 退職金に関する決議の内容
- 賛成・反対の意見
- 決議に至るまでの議論の経緯
- 退職金の支給額や計算根拠
- 支給の是非を判断した理由
- 出席した株主の人数
- 議決権の行使状況
決議の過程が公正に行われたことを示すことで、退職金の支払いを拒否した場合でも、その決定が適法であることを証明できます。取締役が退職金の請求を目的に訴訟を提起した場合でも、議事録が適切に残されていれば、会社側の正当性を示す重要な証拠として機能します。
さらに、議事録は会社法で保存義務が課されており、少なくとも10年間は保管する必要があります。
定款を確認しておく
取締役の退職金を巡る訴訟を防ぐには、事前に定款を確認しておくことが重要です。
定款には、会社の基本的な運営ルールが記載されており、取締役の退職金に関する規定が設けられている場合があります。退職金の支給条件や決定方法について明確に定められていれば、企業の主張の根拠として有効になります。
一般的に、定款には「取締役の退職金は株主総会の決議によって決定する」といった条文が記載されることが多いです。このような規定がある場合、取締役が一方的に退職金を請求することはできず、株主総会での承認が不可欠です。
また、定款に退職金の計算方法や支給基準が記載されていれば、支払額をめぐるトラブルも回避しやすくなります。たとえば、役員報酬の一定割合を基準とする規定がある場合、客観的な基準に従った支給が行われるため、不当な請求や過大な支給には拒否することが可能です。
労務問題に強い弁護士に相談する
退職金の支払いに関する紛争は、会社法や税法、契約の解釈などが絡み、専門的な知識が必要となるため、弁護士によるアドバイスが有効です。
弁護士に相談することで、退職金の支給に関するルールの策定や、支給額の算定基準の設定をサポートしてくれます。こうしたプロセスは法的観点が必要になるため、社内では補えない知見を弁護士が提供してくれます。
また、弁護士は退職金の支払いを巡る紛争が発生した場合の対応にも有効です。例えば、株主総会の決議で支払いが拒否された場合、その決議が適法に行われたことを証明するための資料を整備し、法的な正当性を主張することが可能になります。
労務問題に強い弁護士と顧問契約を結ぶことで、退職金を巡るリスクを事前に回避し、紛争の発生を最小限に抑えることができます。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。退職金に関するトラブルや訴訟について弁護士に相談したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>まとめ

退職時の金銭トラブルは、後味を悪くすることになるため、企業としても対策しておくべきです。特に取締役の退職金に関するトラブルは、未然に防ぐことも可能なので、議事録の作成や評価制度の確立など、トラブルを最小限に抑える努力が必要になります。
「規定が適切であるか」「取締役とトラブルになっている」といった企業の担当者は、弁護士に相談することをおすすめします。訴訟に発展すると法的視点からの対策が必要になるため、素早く弁護士に依頼し、退職金のトラブルで訴訟を引き起こさないようにしましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。取締役の退職金について訴訟やトラブルを解決したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












