特定商取引法とは?基づく表記完全ガイド:作成方法から実装例まで解説
商取引・契約法務
2025.03.22 ー 2025.03.27 更新
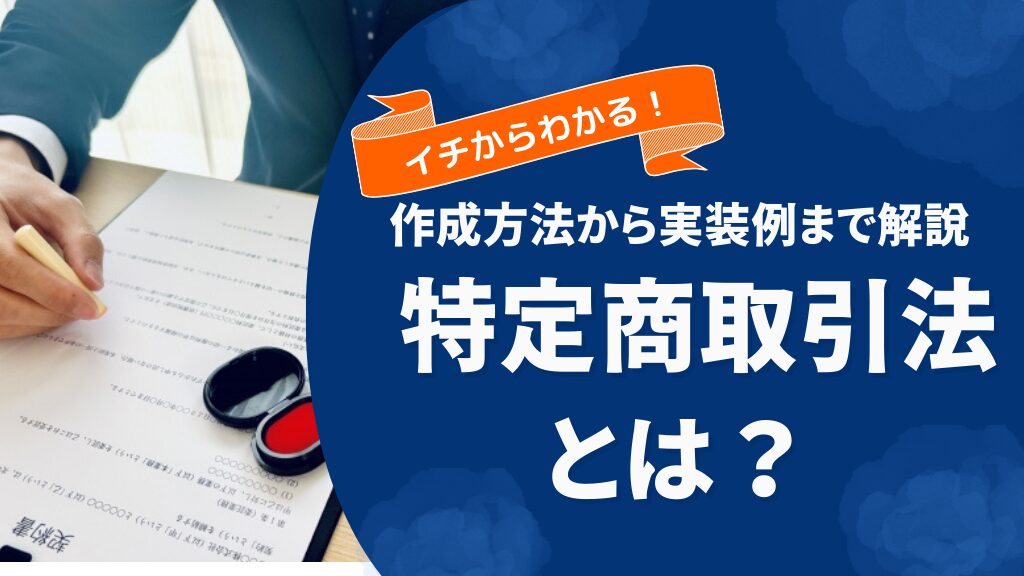
オンラインビジネスやECサイトを運営する際、法的リスクを回避し、顧客の信頼を得るために欠かせないのが「特定商取引法に基づく表記」です。この法律は、消費者を保護し、取引の透明性を確保することを目的としており、事業者には特定の情報を正確かつ分かりやすく表示する義務があります。
しかし、「何をどのように書けばよいのか」「自分のビジネスにどこまで適用されるのか」といった疑問を抱える方も多いでしょう。特に、個人事業主やスタートアップ、ネットショップ初心者にとって、これらのルールを理解し適切に適用することは大きな課題です。
本記事では、特定商取引法に基づく表記の基本から必要な記載項目、具体例やテンプレート、さらには違反時のリスクまでを分かりやすく解説します。また、Webサイトや販売プラットフォーム上での実装方法や、適法な表示がもたらす信頼性向上のポイントについても紹介。適切な表記を行うことで、法的トラブルを防ぎながら顧客に安心感を与えるビジネス運営を目指しましょう。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>特定商取引法に基づく表記とは?

特定商取引法に基づく表記は、インターネット通販やECサイトを運営する事業者にとって重要な法的義務です。この表記は、消費者が安心して商品やサービスを購入できるよう、取引の透明性を確保することを目的としています。
以下で、特定商取引法の役割や特徴、表記の目的や内容について詳しく解説します。
特定商取引法は消費者保護のために定められた法律
特定商取引法は、消費者と事業者の間の取引における公正性を確保し、消費者の利益を保護することを目的として制定された法律です。
この法律は、通信販売やインターネット取引など、対面販売以外の取引形態が増加する中で、消費者が安心して商品やサービスを購入できる環境を整備するために重要な役割を果たしています。
特定商取引法の主な特徴は、事業者に対して取引条件の明示を義務付けていることです。これにより、消費者は商品やサービスの内容、価格、支払い方法、返品条件などの重要な情報を事前に確認できます。また、クーリングオフ制度や中途解約権など、消費者の権利を保護する規定も設けられています。
一方で、この法律は事業者にとっても重要な意味を持ちます。法律を遵守することで、消費者との信頼関係を構築し、トラブルを未然に防げるからです。ただし、法律の解釈や適用には複雑な側面もあり、事業者によっては対応に苦慮する場合もあるようです。
消費者保護と事業者の責任のバランスを取りながら、公正な取引環境を実現することが、特定商取引法の本質的な目的といえるでしょう。
特定商取引法に基づく表記の目的と企業が守るべき基本事項
特定商取引法に基づく表記の目的は、消費者と事業者の間の取引の公正性を確保し、消費者保護を図ることにあります。この表記により、消費者は取引の重要な情報を事前に把握できるため、トラブルを未然に防げます。
企業が守るべき基本事項として、まず正確かつ明確な情報提供が挙げられます。事業者名、所在地、連絡先などの基本情報はもちろん、商品やサービスの価格、支払い方法、引き渡し時期なども明記する必要があります。また、返品や交換の条件も明確に示すことが求められます。
表記の内容は、消費者にとって理解しやすい平易な言葉で記述し、誤解を招く表現は避けなければなりません。さらに、表記の掲載場所も重要で、消費者が容易に見つけられる位置に配置することが求められます。
ただし、すべての取引に対して同じ基準が適用されるわけではありません。取引の形態や規模によって、記載すべき内容や方法に若干の違いが生じる可能性があります。そのため、自社の事業形態に合わせた適切な表記方法を検討することが重要です。
特定商取引法に基づく表記は非対面取引に必要

特定商取引法に基づく表記が必要となるのは、主に通信販売やインターネット取引などの非対面取引を行う場合です。これらの取引形態では、消費者が直接商品を確認できないため、事業者側が詳細な情報を提供する義務があります。
ただし、すべての取引に表記が必要というわけではありません。例えば、対面販売や店舗での販売、継続的な取引関係がある場合などは、表記義務が免除されることがあります。また、取引金額が少額の場合や、一定の条件を満たす場合にも例外が認められることがあります。
事業者は、自社の取引形態や商品・サービスの特性を考慮し、法律の適用範囲を正確に把握する必要があります。特定商取引法の解釈には複雑な側面もあるため、専門家に相談するのも一つの方法かもしれません。
特定商取引法に基づく表記の対象となる取引の具体例
特定商取引法の対象となる取引には、通信販売をはじめとするいくつかの形態があります。例えば、インターネットショッピングや通信カタログによる商品販売は、最も一般的な通信販売の例です。テレビショッピングも、消費者が画面を見て商品を注文するため、この範疇に含まれます。
また、定期購入サービスも対象となることがあります。例えば、毎月自動的に化粧品や健康食品が届くようなシステムです。ただし、これらのサービスの中には、特定商取引法の適用範囲が曖昧なケースも存在します。
さらに、オンラインでのデジタルコンテンツ販売も対象となる可能性があります。電子書籍や音楽、ソフトウェアなどがこれに該当します。ただし、即時ダウンロード可能な商品については、法律の適用が異なる場合があります。
最後に、オンライン予約システムを使用したサービス提供も、特定商取引法の対象となることがあります。例えば、宿泊施設や飲食店の予約、各種レッスンの申し込みなどが挙げられます。これらの取引形態は、消費者と事業者が対面せずに契約を結ぶという点で共通しています。
特定商取引法に基づく表記義務が免除されるケース
特定商取引法に基づく表記義務には、一部免除されるケースが存在します。
- 対面販売のみを行う店舗型の小売業
- 個人間取引や、企業間の取引(BtoB)取引金額が少額の場合
- 通信販売で3,000円未満の取引や、特定継続的役務提供で5万円未満の取引などが該当。ただし、金額の基準は取引形態によって異なるため、注意が必要。
- 広告スペースが極めて限られている場合
- 一部の表記項目を省略できる可能性あり。例えば、新聞や雑誌の小さな広告枠では、詳細情報へのリンクを掲載することで代替可能。
ただし、これらの免除規定は絶対的なものではなく、取引の性質や消費者保護の観点から個別に判断される場合もあります。そのため、事業者は自社の取引形態や商品特性を踏まえ、適切に判断することが求められます。
特定商取引法に基づく表記に記載すべき内容

特定商取引法に基づく表記には、消費者が安心して取引を行えるよう、以下の重要な情報を明記する必要があります。
- 事業者の基本情報
- 販売価格、送料、支払い方法
- 商品の引き渡し時期や返品・交換の条件
これらの情報は、消費者が購入を決断する際の判断材料となるため、できるだけ詳細に記述することが望ましいでしょう。ただし、業種や取引形態によっては、記載すべき内容に若干の違いが生じる可能性があります。
さらに、特定商取引法の改正により、新たに追加された記載事項もあるかもしれません。事業者は常に最新の法令を確認し、適切な表記を心がける必要があります。消費者との信頼関係を築くためにも、わかりやすく誠実な表記を心がけましょう。
事業者の基本情報(氏名、住所、連絡先)
特定商取引法に基づく表記において、事業者の基本情報は最も重要な要素の一つです。この情報には、事業者の氏名または名称、住所、そして連絡先が含まれます。
個人事業主の場合は個人名を、法人の場合は会社名を正確に記載する必要があります。住所は、実際の事業所や本社の所在地を明記し、郵便番号も忘れずに記載します。連絡先については、消費者が容易に問い合わせできるよう、電話番号やメールアドレスを明確に示すことが求められます。
これらの情報を正確に記載することで、消費者は取引相手の信頼性を判断し、必要に応じて連絡を取れます。ただし、個人情報保護の観点から、どこまで詳細な情報を開示するべきかについては、事業者によって判断が分かれる場合もあります。
また、事業者の基本情報は、変更があった場合には速やかに更新することが重要です。古い情報のままでは、消費者とのトラブルの原因となる可能性があるためです。特に、住所や連絡先の変更は、顧客とのコミュニケーションに直接影響を与えるため、注意が必要です。
販売価格、送料、支払い方法の記載
販売価格、送料、支払い方法は、消費者が商品やサービスを購入する際の判断材料となるため、明確かつ正確な記載が求められます。
販売価格については、税込価格を表示することが原則ですが、税抜価格を併記することも可能です。ただし、その場合は税抜であることを明示する必要があります。
送料に関しては、具体的な金額や計算方法を記載します。地域によって送料が異なる場合は、その旨を明記し、詳細な料金表へのリンクを設けるなどの工夫が効果的です。場合によっては、送料無料の条件なども併せて記載するとよいでしょう。
支払い方法については、クレジットカード、銀行振込、代金引換など、利用可能な全ての選択肢を列挙します。各支払い方法に手数料が発生する場合は、その金額も明記する必要があります。ただし、支払い方法によっては、手数料の正確な金額を事前に確定できない場合もあるかもしれません。
これらの情報を適切に表示することで、消費者は購入前に必要な費用を把握でき、トラブルを未然に防げます。ただし、表記方法によっては、消費者に誤解を与える可能性もあるため、分かりやすさと正確さのバランスに注意が必要です。
商品引き渡し時期や返品・交換の条件
商品の引き渡し時期や返品・交換の条件は、消費者が購入を決める際の重要な判断材料です。特定商取引法に基づく表記では、これらの情報を明確に示す必要があります。
商品の引き渡し時期については、注文から何日以内に発送するかを具体的に記載します。即日発送や在庫状況による変動がある場合は、その旨も併せて説明しましょう。
返品・交換に関しては、可能な期間や条件を詳細に記述することが求められます。例えば、商品到着後14日以内であれば返品可能といった具合です。ただし、食品や使用済み商品など、返品不可の場合はその理由も明記します。また、返品時の送料負担者や、交換に伴う差額の精算方法なども忘れずに記載しましょう。
これらの条件を明確に示すことで、購入後のトラブルを未然に防げます。ただし、業種や取り扱い商品によって適切な条件は異なるため、自社の状況に応じて慎重に検討する必要があるでしょう。
特定商取引法に基づく表記を書く際の注意点

特定商取引法に基づく表記を作成する際は、いくつかの重要な点に注意を払う必要があります。
まず、消費者が容易に見つけられる場所への掲載や誤解を招かない明確な表現方法に留意しましょう。
また、最新の法改正に注意を払い、必要に応じて表記内容を更新することも忘れてはいけません。特に近年、オンラインビジネスの急速な発展に伴い、法律の解釈が変化することがあります。定期的に内容を見直し、最新の法令に準拠しているか確認することが望ましいでしょう。
消費者が容易に見つけられる場所への掲載
特定商取引法に基づく表記は、消費者が容易に見つけられる場所に掲載することが重要です。
多くの場合、ウェブサイトのフッター部分やトップページの目立つ位置に「特定商取引法に基づく表記」というリンクを設置することが一般的です。しかし、単にリンクを置くだけでなく、消費者の目線に立って、どこに配置すれば最も見つけやすいかを考慮する必要があります。
モバイル端末での閲覧が増加している現在、スマートフォンやタブレットでの表示も考慮に入れるべきでしょう。レスポンシブデザインを採用し、デバイスに関わらず表記へのアクセスが容易になるよう工夫することが求められます。
また、特定商取引法に基づく表記へのリンクは、単独で設置するだけでなく、関連する情報と併せて掲載することも効果的です。例えば、プライバシーポリシーや利用規約などと同じセクションに配置することで、消費者が必要な情報を一箇所で確認できるようになります。
ただし、表記の掲載場所については、業界や取引形態によって最適な方法が異なる可能性があります。そのため、自社のビジネスモデルや顧客層を考慮しつつ、最適な掲載方法を検討することが望ましいでしょう。
誤解を招かない明確な表現方法
特定商取引法に基づく表記を作成する際は、消費者が容易に理解できる明確な表現を心がけることが重要です。専門用語や業界特有の言い回しは避け、一般的な言葉を用いて説明することで、誤解を招くリスクを軽減できます。また、曖昧な表現や解釈の余地がある文言は使用せず、具体的かつ明瞭な記述を心がけましょう。
表記の内容は、箇条書きや表を活用して視覚的に整理することで、消費者が必要な情報を素早く把握しやすくなります。ただし、デザイン面に注力しすぎると、かえって読みづらくなる可能性もあるため、適度なバランスを保つことが大切です。
さらに、法律で定められた必須項目以外にも、消費者からよくある質問や懸念事項について補足説明を加えることで、より親切で分かりやすい表記となります。ただし、情報量が多すぎると逆効果になる場合もあるため、適切な情報量を見極める必要があります。
特定商取引法に基づく表記の例文とテンプレート

特定商取引法に基づく表記の例文やテンプレートは、事業者にとって重要な指針です。一般的なテンプレートを基に、自社の事業内容や規模に合わせてカスタマイズすることが推奨されます。
例えば、小規模なオンラインショップの場合、シンプルな表記で十分かもしれません。一方、大手ECサイトでは、より詳細な情報を記載することが求められるでしょう。
汎用的なテンプレートの紹介
特定商取引法に基づく表記のテンプレートは、多くの事業者にとって便利なツールです。基本的な構成要素を含む汎用的なテンプレートを使用することで、法律遵守の手間を軽減できます。ただし、業種や取引形態によって必要な情報が異なる場合があるため、完全に統一されたものはありません。
一般的なテンプレートには、事業者名、代表者名、所在地、連絡先情報、販売価格、送料、支払方法、引渡し時期、返品・交換条件などの項目が含まれます。これらの項目を順序立てて記載し、必要に応じて詳細な説明を加えることで、消費者にとって分かりやすい表記となります。
テンプレートを活用する際は、自社の事業内容に合わせてカスタマイズすることが重要です。ただし、テンプレートに頼りすぎると、重要な情報が抜け落ちる可能性があります。そのため、定期的に表記内容を見直し、最新の法律や自社の取引条件と照らし合わせて更新することが大切です。
事業規模や業種ごとのカスタマイズ例
特定商取引法に基づく表記は、事業規模や業種によってカスタマイズが必要となる場合があります。
小規模な個人事業主と大手企業では、記載すべき情報の詳細さが異なることがあります。例えば、個人事業主の場合、屋号と代表者名を併記し、自宅兼事務所の住所を記載することが多いでしょう。一方、大企業では法人名と代表取締役名を明記し、本社所在地や顧客対応窓口の連絡先を詳細に記載することが一般的です。
業種別のカスタマイズ例として、飲食店のテイクアウトサービスでは、食品衛生法に基づく営業許可番号の記載が求められることがあります。また、美容関連商品を扱う事業者は、効能効果の表現に関する注意事項を追記するケースもあるでしょう。
実店舗を持つ事業者の場合、店舗の営業時間や定休日を記載するのも良いでしょう。デジタルコンテンツを販売する事業者であれば、ダウンロード方法や利用環境の説明を加えることも検討すべきです。
また、定期購入サービスを提供する場合は、解約条件や次回発送予定日などの情報を追加することが望ましいでしょう。さらに、越境ECを展開する事業者の場合、海外発送や関税に関する情報を明記する必要があります。
ただし、業種や取扱商品によっては、どの程度まで詳細な情報を記載すべきか判断が難しい場合もあります。このような場合、専門家に相談することで適切な表記方法を見出せる可能性があります。
特定商取引法に基づく表記がない場合のリスク

特定商取引法に基づく表記を怠ると、事業者は重大なリスクに直面する可能性があります。消費者との信頼関係が損なわれ、トラブルが発生しやすくなるだけでなく、法的な制裁を受ける恐れもあります。具体的には、行政処分や罰金、場合によっては懲役刑が科される可能性があります。
また、表記不備は消費者庁や都道府県の監視対象となり、改善命令や業務停止命令を受ける可能性も高まります。これらの処分は、企業イメージを著しく損ない、売上減少や取引先との関係悪化につながることがあります。
さらに、消費者から訴訟を起こされるリスクも無視できません。適切な情報開示がなされていないことで、消費者が不利益を被ったと主張する根拠となる可能性があるためです。ただし、表記不備が直ちに法的責任に結びつくかどうかは、個々の状況によって異なる場合があります。
消費者トラブルと法的ペナルティ
特定商取引法に基づく表記を怠ると、消費者との間でトラブルが発生するリスクが高まります。法律を遵守しない事業者は、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。具体的には、業務停止命令や指示、さらには懲役刑や罰金刑が科される場合もあります。
特に悪質な違反事例では、消費者庁による立入検査や、事業者名の公表といった厳しい措置が取られることがあります。これにより、企業イメージが大きく損なわれ、信頼回復に多大な時間と労力を要することになりかねません。
一方で、適切な表記を行うことで、消費者との信頼関係を築き、トラブルを未然に防げます。透明性の高い取引環境を整えることは、長期的な事業の成功につながる重要な要素といえるでしょう。
ただし、法律の解釈や適用には複雑な側面もあり、事業者によっては対応に苦慮する場面もあるかもしれません。そのため、専門家のアドバイスを受けながら、自社の状況に合わせた適切な対応を検討することが望ましいでしょう。
ECサイト運営者が知るべき特定商取引法の改正ポイント

特定商取引法の改正により、ECサイト運営者にとって重要な変更点が生じています。最新の改正では、通信販売における表示義務の強化や、販売業者等が遵守すべき事項の明確化が図られました。
具体的には、定期購入契約に関する規制が厳格化され、顧客に対する説明責任がより重視されるようになりました。また、デジタルプラットフォーム事業者の役割や責任についても新たな規定が設けられ、取引の透明性向上が求められています。
これらの変更は、消費者保護の強化を目的としていますが、同時にECサイト運営者にとっては対応すべき課題も増えることになりました。法改正の詳細を把握し、適切な対策を講じることが、今後のビジネス展開において不可欠となるでしょう。
最新改正による重要な変更点
2021年の特定商取引法改正では、通信販売における契約の申込み段階での広告表示に関する規制が強化されました。
具体的には、詐欺的な定期購入商法への対策として、定期購入契約の場合は、その旨を容易に認識できるよう表示することが義務付けられました。また、契約の申込み画面では、申込みの内容を容易に確認し、訂正できる措置を講じることが求められるようになりました。
さらに、通信販売業者が不当な方法で顧客の意に反して契約の申込みをさせた場合、その契約を取り消せる制度が導入されました。これにより、消費者保護がより一層強化されることとなりました。
また、送料の表示方法についても明確化され、送料が商品の購入価格に含まれない場合は、送料を別途記載することが求められるようになりました。ただし、具体的な表示方法については、業界によって多少の違いがあるかもしれません。
これらの改正により、通信販売業者は広告表示や契約プロセスの見直しが必要となり、コンプライアンス体制の強化が求められることとなりました。
法改正が事業者に与える影響
特定商取引法の改正は、事業者に大きな影響を与えています。
特に注目すべき点は、返品特約に関する規定の変更です。従来は返品特約を設けていない場合、商品到着後8日間は無条件で返品が可能でしたが、改正後は返品特約を明示しない限り、商品到着後1年間は返品に応じなければならなくなりました。この変更は、多くの事業者にとって大きな負担となる可能性があります。
また、広告表示に関する規制も厳格化されました。虚偽・誇大な表示はもちろん、消費者に誤解を与えるような表現も禁止されるようになり、事業者はより慎重な広告作成が求められるようになりました。
さらに、法改正によって罰則も強化されており、違反した場合のリスクが高まっています。事業者は、これらの変更点を十分に理解し、適切な対応を取ることが求められます。
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務救済がおすすめ
法務救済は、契約書のリーガルチェックから労務、国際取引時の法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争など、企業法務に精通する専門家を相談内容に応じて、検索・相談できるポータルサイトです。初回の無料相談を提供している弁護士事務所も多数掲載しています。
全国の弁護士事務所を「相談内容」や「エリア」から簡単に検索・相談できます。なお、お問い合わせは無料で、当サイトから費用を頂戴することはありません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務救済をご活用ください。
法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












