特定商取引法のトラブルは弁護士に相談しよう!相談方法や必要なケースを徹底解説
商取引・契約法務
2025.03.26 ー 2025.03.28 更新

商品やサービスを販売する際に、特定商取引法に違反しないよう注意しなければいけません。企業から消費者へ販売するBtoC型だと、特定商取引法を巡って法的対応が求められるケースも少なくありません。
特定商取引法に関するトラブルが発生した場合、弁護士に相談するのがおすすめです。法律の分野に関しては専門家であるため、企業が特定商取引法に違反していないか、訴訟となった場合のアドバイスまで、トータルでサポートしてくれます。
この記事では、特定商取引法に関連するトラブルが発生した際に弁護士に相談する方法やメリット、信頼できる弁護士の見つけ方について解説していきます。特定商取引法の概要や該当する行為、対策まで紹介するので、初めて弁護士に依頼する方もぜひ参考にしてみてください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>特定商取引法とは?

特定商取引法とは、事業者と消費者の間で行われる取引の公正を確保し、消費者被害を防ぐことを目的とした法律です。1976年に制定され、その後の改正を経て、現在も消費者保護の法律として機能しています。
特定商取引法の主な内容には、以下のようなものがあります。
- 不適切な勧誘行為の禁止
- 契約書面の交付義務
- クーリング・オフ制度の導入
- 誇大広告の規制
- 前払い式契約の適正化
特定商取引法違反があった場合、行政指導や業務停止命令が下されるだけでなく、刑事罰が科される可能性もあります。企業は特定商取引法を正しく理解し、適切な対応を行うことが求められます。
特定商取引法が対象とする取引類型

特定商取引法が対象としているトラブルが発生しやすい取引類型として、以下の6つが挙げられます。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
それぞれについて解説していきます。
訪問販売
訪問販売とは、事業者が自宅や職場などに訪問し、対面で商品やサービスを販売する取引形態を指します。特定商取引法の規制対象の一つであり、消費者が冷静な判断をしにくい状況で契約を結ばされるリスクがあるため、厳格なルールが設けられています。
訪問販売には、事前にアポイントを取った上での営業だけでなく、突然訪問して勧誘を行うケースも含まれます。
特定商取引法では、訪問販売を行う事業者に対して、契約の際に重要事項を記載した書面を交付する義務を課しています。また、消費者が契約を拒否したにもかかわらず執拗に勧誘を続ける行為や、誤解を招く説明で契約を促す行為は法律違反となります。
通信販売
通信販売とは、インターネットやカタログ、テレビショッピングなどを通じて商品やサービスを販売する取引形態です。
通信販売では「広告表示の規制」が設けられており、以下の事項を表示することが義務付けられています。
- 商品の価格
- 送料
- 支払方法
- 返品条件
実際の内容と異なる広告は禁じられており、誇大広告が問題となった場合は行政処分の対象になることもあります。
また、通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されませんが、返品に関するルールをあらかじめ明示する必要があります。返品の可否や条件を明確にせずに販売すると、消費者が一方的に返品できる「8日間返品ルール」が適用されるため、企業側も適切な表示を行うことが求められます。
電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、事業者が消費者に対して電話をかけ、商品やサービスの契約を勧める取引形態のことを指します。特定商取引法では、消費者が不要な契約を強いられないよう、厳格な規制が設けられています。
事業者は電話をかけた際に、自社の名称や勧誘の目的を明確に伝える義務があります。また、消費者が契約を希望しない意思を示した場合、事業者は勧誘を中止しなければなりません。しつこく勧誘を続けた場合、業務停止命令などの行政処分が下されることがあります。
さらに、電話勧誘販売による契約にはクーリング・オフ制度が適用されます。消費者は契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できます。
連鎖販売取引
連鎖販売取引とは、いわゆる「マルチ商法」と呼ばれる取引形態で、特定商取引法の規制対象となっています。この取引は、販売組織に新規会員を勧誘し、その会員がさらに別の会員を勧誘することで拡大していく仕組みを持ちます。
特定商取引法では、連鎖販売取引における不当な勧誘や違法な契約を防ぐため、以下のような規制を設けています。
- 勧誘時には「連鎖販売取引であること」を明確に説明する
- 契約後20日以内であればクーリング・オフ制度が利用可能
違法な連鎖販売取引を行った場合、行政指導や業務停止命令が下されるほか、刑事罰の対象になることもあります。過大な収益を見込ませて勧誘する手口や、契約解除を妨害する行為は厳しく取り締まられています。
特定継続的役務提供
特定継続的役務提供とは、長期間にわたり高額な費用を支払うサービス契約を指します。この規制は、消費者が契約後に後悔するケースが多いため設けられました。
対象となるのは、以下の6種類です。
- エステティックサロン
- 語学教室
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
- 家庭教師
これらのサービスは、一定期間継続する契約が基本であり、一度契約すると解約が困難になる場合があります。そのため、契約内容の明確化や消費者保護のための措置が義務付けられています。
業務提供誘引販売取引
業務提供誘引販売取引とは、事業者が「仕事を提供する」と勧誘し、その仕事を始めるために商品やサービスの購入、登録料などの支払いを求める場合に該当します。「内職商法」「副業商法」とも呼ばれます。
例えば、「簡単な作業で高収入を得られる」「副業で安定した収入を確保できる」といった勧誘がなされ、実際には十分な収入が得られないケースが多く、消費者トラブルが発生しやすい取引です。
特定商取引法では、この取引に関する広告や契約の適正化を義務付け、違法な勧誘を防ぐための規制を設けています。具体的には、以下の通りです。
- 契約時に業務内容・収益の見込みを書面を交付すること
- 誤認を招く表示の禁止
- クーリング・オフの適用
特定商取引法違反に該当するケース

特定商取引法に違反するケースとして、以下の3つが代表的な事例です。
- 虚偽広告の問題
- クーリングオフ妨害
- 不適切な契約内容
それぞれの内容や事例について解説していきます。
違反事例1:虚偽広告の問題
企業が商品の性能やサービスの内容を誇張したり、根拠のない表現を用いたりすることで、消費者が適切な判断をできない状態にさせる虚偽広告の行為は、特定商取引法に違反しています。通信販売や訪問販売など、事前に実物を確認しにくい取引では、虚偽広告による被害が発生しやすくなっています。
具体例として、以下のようなものがあります。
- 「誰でも簡単に月収100万円を稼げる」といった根拠のない副業広告
- 「特別価格で今だけ提供」としながら、実際には常に同じ価格で販売している
- 「絶対にシミが消える」「〇日で痩せる」など科学的根拠がない
こうした広告は、消費者の購買意欲を不当にあおるため、特定商取引法により厳しく規制されています。
違反事例2:クーリングオフ妨害
クーリング・オフ妨害とは、特定商取引法で認められたクーリング・オフ制度を事業者が不当に阻害する行為を指します。訪問販売や電話勧誘販売、業務提供誘引販売取引など、特定商取引法で定められた取引が対象となります。
事業者によるクーリング・オフ妨害にはさまざまな手口があります。
- 「クーリング・オフはできない」「契約解除には違約金が発生する」といった虚偽の説明をする
- 解約手続きに必要な書類を渡さない
- 解約手続きの対応を意図的に遅らせる
- 事実と異なる説明で消費者を諦めさせる
クーリング・オフ妨害が発生した場合、消費者は行政機関や消費生活センター、弁護士に相談することで適切な対応が可能です。特定商取引法では、事業者が不当な対応をした場合、業務停止命令や罰則の対象となることがあり、消費者の権利が守られる仕組みが整えられています。
違反事例3:不適切な契約内容
消費者にとって著しく不利な条件を含むものや、法律で義務付けられた情報を記載していない契約も、特定商取引法に違反しています。契約内容を不適切に設定すると、法的責任を問われる可能性があり、契約自体が無効と判断される場合もあります。
特に問題となるのは、契約書面に必要な事項が記載されていないケースです。訪問販売や電話勧誘販売などの取引において、特定商取引法では事業者が以下の内容を書面に記載し、消費者に交付する義務があります。
- 契約の内容
- 解約条件
- 提供する商品やサービスの詳細
- 代金の支払い方法
これが守られていない場合、契約が適正に成立していないとみなされることがあります。
また、契約条項が消費者の権利を過度に制限する内容になっている場合も、不適切な契約内容に該当します。クーリング・オフの権利を消費者に知らせず、「一度契約したらキャンセルできない」と誤認させる契約や、高額な違約金を請求する契約は、法律上無効とされるでしょう。
特定商取引法のトラブルを弁護士に相談するメリット

特定商取引法に関連してトラブルが発生した場合、会社と消費者で解決することも可能ですが、お互いの利益を優先した議論になりやすく、スムーズな解決は難しいとされています。
そのため、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
- 専門的なアドバイスを受けられる
- 手続きや書類作成の手間を省ける
- 早期の解決が期待できる
それぞれのメリットについて解説していきます。
専門的なアドバイスを受けられる
特定商取引法は、取引類型ごとに細かい規制が設けられており、一般の消費者や事業者がすべてを理解するのは容易ではありません。また、違反が発覚した場合の行政処分や損害賠償請求などの対応には、法律の専門知識が不可欠です。
弁護士に相談すれば、現在抱えているトラブルが特定商取引法に違反しているかどうかを正確に判断してもらえます。自社の販売方法が法律に抵触していないかを確認し、適正な運営を行うためのアドバイスを受けられます。
手続きや書類作成の手間を省ける
特定商取引法に関するトラブルを弁護士に相談することで、手続きや書類作成の手間を省くことができます。消費者との交渉や訴訟に備えた準備など、企業にとって負担になるプロセスを代行してくれます。
弁護士に依頼すれば、法律の要件を満たした適切な書面を作成し、確実に手続きを進めることができます。弁護士が代理人として交渉することで、円滑な解決が期待できるでしょう。
早期の解決が期待できる
法律問題は、放置すると状況が悪化し、被害額が増大する可能性があります。弁護士に依頼することで、適切な対策を迅速に講じ、問題の長期化を防ぐことができます。
特定商取引法に関するトラブルの多くは、法律の専門知識を要します。事業者であっても消費者との交渉が難航したり、適切な手続きを見落としたりすることがあります。一方、弁護士は特定商取引法の規定に基づき、相手方との交渉や法的手続きを迅速に進めることができます。
弁護士への相談が必要なケースとは?

企業が特定商取引法について弁護士へ相談するケースとして、以下の3つが挙げられます。
- 特定商取引法違反の指摘を受けた
- クーリングオフや契約解除の対応が難航している
- 新規事業の立ち上げ時に特定商取引法の適合を確認したい
それぞれのケースについて解説していきます。
特定商取引法違反の指摘を受けた
事業者が特定商取引法違反の指摘を受けた場合、早急に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。行政機関(消費者庁や都道府県の担当部署)からの指導や消費者からの苦情が相次いでいる場合、対応を怠ると業務停止命令や罰則の対象となる可能性があります。
消費者との間でトラブルが発生している場合は、返金対応や契約解除の判断を誤ると、さらなるクレームや訴訟リスクを招くリスクがあるため、注意が必要です。
事業者としては、自社の販売手法や契約内容が法令に適合しているかを確認し、再発防止策を講じることが求められます。
クーリングオフや契約解除の対応が難航している
特定商取引法では、消費者にクーリング・オフの権利が認められています。しかし、契約内容やクーリング・オフの適用範囲を巡り、消費者とトラブルに発展するケースも少なくありません。
例えば、消費者がクーリング・オフの期間を過ぎてから契約解除を求める場合や、クーリング・オフが適用されない取引であるにもかかわらず、一方的な解約を要求してくるケースが考えられます。また、事業者が契約時に書面を交付していなかった場合、クーリング・オフの期間が延長される可能性があります。
このような状況では、弁護士に相談することで、事業者にとって適正な対応策を講じることが可能です。解約交渉が難航している場合でも、弁護士が代理人として対応することで、トラブルの拡大を防ぐことができます。
新規事業の立ち上げ時に特定商取引法への適合を確認したい
新規事業を立ち上げる際、特定商取引法への適合を確認することは、事業者にとって非常に重要です。法律を十分に理解せずに事業を開始すると、意図せず法令違反となり、行政指導や業務停止命令などのリスクを抱えることになります。
例えば通信販売を行う場合、広告表示や返品対応のルールを遵守しなければなりません。また、訪問販売では契約書面の交付義務やクーリング・オフの対応が求められ、適正な手続きを確保しなければ法的責任を問われる可能性があります。
こうしたリスクを避けるためには、事前に弁護士に相談し、特定商取引法に適合しているか確認することが重要です。弁護士のアドバイスを受けることで、適法なビジネスモデルを構築できるだけでなく、消費者トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
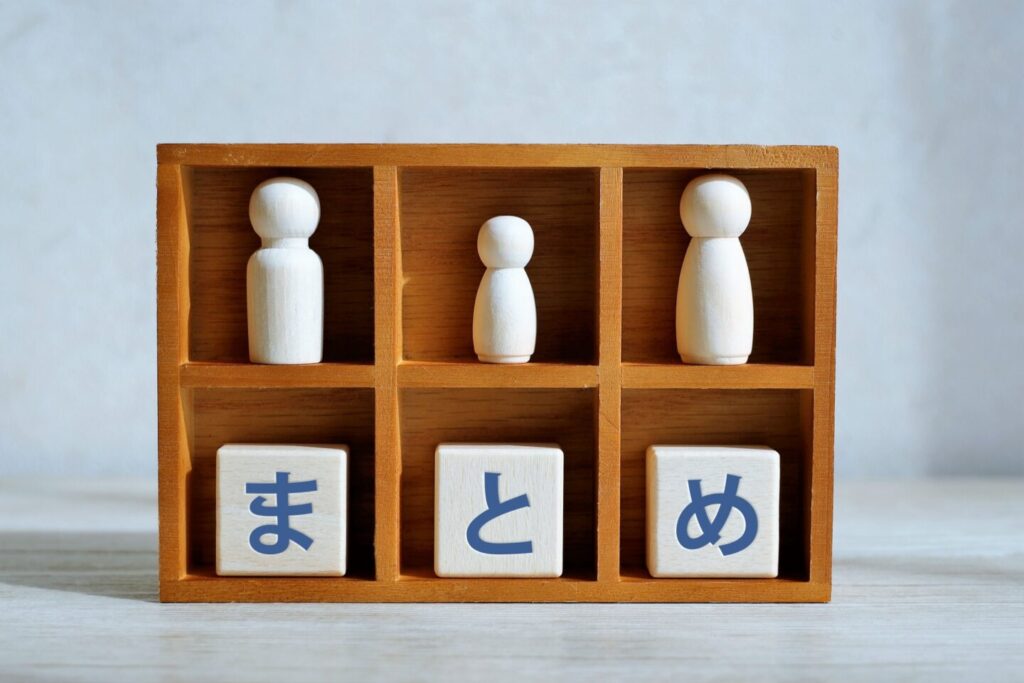
特定商取引法は、消費者との取引の公平性を確保するための法律です。事業者は特定商取引法を守って取引する必要があり、違反すると消費者から法的措置を受ける可能性があります。
特定商取引法に違反していると指摘された、今の事業が特定商取引法に違反していないか確認したいという方は、弁護士に依頼しましょう。トラブル時の対応だけでなく、予防としても活用できるため、健全な事業運営を目指すことができます。
特定商取引法に違反しない販売取引を行うためにも、弁護士への相談がおすすめです。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。特定商取引法について弁護士に相談したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












