特定商取引とは?概要から法律の適用範囲、対象、企業が取るべき対応策までを徹底解説
商取引・契約法務
2025.03.26 ー 2025.03.28 更新
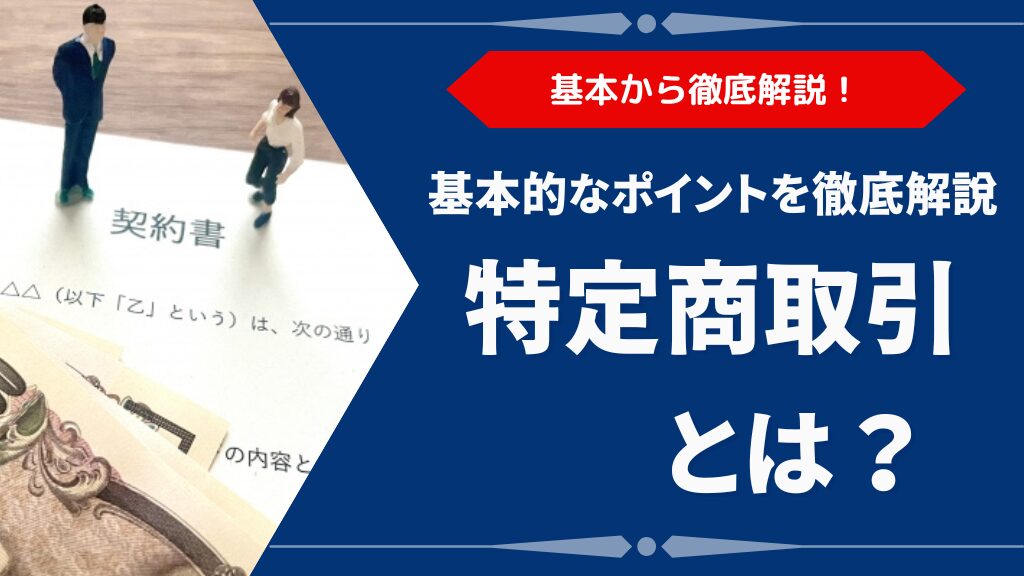
特定商取引とは、訪問販売や通信販売など、日常生活やビジネスの現場で目にする取引を指します。特定商取引について定めた法律によって規制があり、事業者と消費者の間で発生しやすいトラブルを防ぐためのルールが決められています。
特定商取引に関するトラブルが発生した場合、法的措置で対抗することも可能です。しかし、まずは「特定商取引って何」という基本的な部分を知っておく必要があります。
この記事では、特定商取引の概要から適用範囲、対象、対応策について解説していきます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>特定商取引とは?

特定商取引とは、消費者と事業者の間で行われる特定の取引を対象とした法律に基づく取引を指します。消費者保護を目的としており、公正な取引環境の維持を目指しています。
特定商取引の対象は、消費者が日常的に関わる可能性の高い取引形態です。これらの取引では、十分な情報を得ないまま契約を結ぶリスクがあるため、事業者には一定の義務が課せられています。
具体的な義務は、以下の通りです。
- 取引条件の明示
- 契約書面の交付
- クーリング・オフ制度の適用
しかし、特定商取引の適用範囲は常に明確ではなく、技術の進歩や新たな取引手法の登場により、法律の適用が不明確になることもあります。そのため、事業者は最新の法解釈や判例を注視し、適切に対応することが必要です。
特定商取引が必要とされる背景
特定商取引法が制定された背景には、消費者保護の必要性が高まったことがあります。
高度経済成長期以降、取引形態が多様化し、通信販売や訪問販売といった非対面取引での消費者トラブルが増加しました。こうした問題を受け、以下の流れで法律が定められました。
- 1976年:訪問販売法が施行
- 社会変化に対応する形で適用範囲が拡大
- 2000年:現在の特定商取引法が確立
特定商取引は、消費者の利益を守ると同時に、健全な市場環境を整備することを目的としています。事業者には適切な情報開示や不当な勧誘の禁止が義務付けられ、消費者が安心して取引できる環境の確保が求められます。
一方で、インターネットの普及により新たな取引形態が登場し、法律の適用範囲や規制の見直しが継続的に行われています。しかし、技術の進展に法整備が追いつかず、一部では規制が明確でない取引も存在しているのが現状です。
特定商取引法の対象取引

特定商取引に該当する取引類型は、以下の7つです。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
それぞれの取引形態について解説していきます。
訪問販売
訪問販売とは、事業者が消費者の自宅や職場などを訪れ、対面で商品やサービスを販売する取引形態を指します。
訪問販売は、事前に申し込みをしていないにもかかわらず、販売員が訪問し契約を勧めるケースが典型的です。一般的には、以下のような販売が該当します。
- 化粧品
- 健康食品
- 浄水器
- リフォーム工事
- 学習教材
特に、高齢者を狙った強引な勧誘や、高額な契約を結ばせる手口が問題視されることがあります。
事業者が不当な勧誘を行った場合、行政指導や業務停止命令などの措置が取られることもあります。
通信販売
通信販売は、消費者が販売者と直接対面することなく、インターネットやカタログ、テレビ、新聞広告などを通じて商品やサービスを購入する取引形態です。特定商取引法では、通信販売に関する規制を設け、消費者保護を図っています。
訪問販売や電話勧誘販売とは異なり、通信販売にはクーリング・オフ制度が適用されません。これは、消費者が自らの意思で購入を決定するため、契約撤回の特例を設ける必要がないと考えられているためです。
しかし、販売業者が独自に返品可能な期間を設けることは可能であり、その場合はその条件を明示する義務があります。
電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、電話を用いて商品やサービスの契約を勧誘する販売方法を指します。
電話勧誘販売を行う場合、事業者は取引の内容や契約条件を説明する義務を負います。また、契約締結後であっても、消費者にはクーリング・オフ制度が適用され、契約から8日以内であれば無条件で解約することが可能です。
電話勧誘販売を行う事業者は、消費者の信頼を得るために適正な営業活動を行うことが求められます。違反行為が発覚した場合、業務停止命令や罰則が科される可能性があり、企業の信用にも影響を及ぼします。
連鎖販売取引
連鎖販売取引は、一般的にはマルチ商法とも呼ばれ、商品やサービスの販売に加えて販売員を勧誘し、その勧誘による収益を得る取引を指します。
特定商取引法では、連鎖販売取引が消費者に不利益をもたらす可能性があるため、一定の規制が設けられています。取引内容の説明や、クーリング・オフ制度の適用が義務付けられています。
連鎖販売取引は、適正に運営されている場合は問題ありませんが、実際には違法な勧誘や高額な初期投資を求めるケースも存在します。特に、新たな会員を勧誘することが主な収益源となる場合、実態としてはネズミ講に近い違法なスキームとなる可能性があります。
特定継続的役務提供
特定継続的役務提供とは、長期間にわたり継続的に役務(サービス)を提供する契約を指します。一定期間にわたる契約で高額な費用が発生しやすく、解約が困難なケースが多いです。
特定継続的役務提供に該当するのは、以下のような役務です。
- エステティックサロン
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
これらのサービスは契約期間が1カ月を超え、かつ一定額以上の支払いが伴うものが対象となります。契約締結時には、事業者は契約内容を明記した書面を交付する義務があり、不適切な勧誘や虚偽説明は禁止されています。
特定継続的役務提供の契約にはクーリング・オフ制度が適用され、契約書面を受領した日から8日以内であれば、消費者は無条件で契約を解除できます。また、8日を過ぎても中途解約が可能であり、消費者は合理的な損害賠償を支払うことで契約解除が可能です。
業務提供誘引販売取引
業務提供誘引販売取引とは、仕事を提供することを前提に、消費者に対して高額な金銭や商品を購入させる取引を指します。「簡単に収入が得られる」「高額な報酬が期待できる」などの説明が行われ、消費者が契約を結ぶよう誘導される仕組みです。
しかし、実際には十分な仕事が提供されなかったり、想定していた収入が得られなかったりするケースが多く、トラブルにつながりやすい取引形態とされています。特定商取引法では、事業者に対して厳格な規制を設けています。
業務提供誘引販売取引の代表的な例として、以下のようなものがあります。
- 在宅ワーク
- フランチャイズ契約
例えば、簡単な作業で高収入が得られると勧誘され、高額な教材や機材を購入したものの、仕事が提供されず収益を得られなかったという事例が報告されています。
訪問購入
訪問購入とは、事業者が消費者の自宅や職場などを訪れ、商品を買い取る取引を指します。事業者が事前の契約なしに訪問し、消費者が不要な品物を売却することが多い点が挙げられます。
不当な価格での買い取りや強引な取引が問題視されてきたのは、以下のような高額商品の購入です。
- 貴金属
- ブランド品
- 美術品
事業者は訪問購入の際に目的を明示しなければならず、消費者の承諾なしに居宅へ訪問することは禁止されています。また、契約成立後でも消費者には一定期間のクーリング・オフ権が認められ、契約を解除できる仕組みがあります。
特定商取引に対する法的義務

特定商取引を行う際には、消費者側と事業者側双方に義務が課されます。特定商取引法に適した公正・公平な取引を実現するために、義務は守らなければいけません。
以下では、消費者・事業者それぞれの法的義務について解説していきます。
消費者側の義務
特定商取引法は主に事業者を規制し、不当な取引から消費者を守ることを目的としていますが、消費者側も適切に行動しなければ、トラブルの原因となることがあります。
消費者は、取引の契約内容を正しく理解する義務があります。訪問販売や通信販売などでは事業者が説明を行いますが、その内容を確認しないまま契約を結ぶと、思わぬ不利益を被ることがあります。特に、高額商品や定期購入契約では、支払い条件や解約方法を事前に確認することが重要です。
また、クーリング・オフの適用範囲や手続きについて理解する義務もあります。消費者は自身の契約がクーリング・オフの対象かどうかを確認します。
事業者側の義務
特定商取引法において、事業者には消費者を保護するための義務が課されています。不適切な取引を防ぎ、公正な商取引を維持するために設けられています。
事業者に課されている義務として、以下が挙げられます。
- 情報開示
- 不当な勧誘行為の禁止
- クーリングオフ制度への対応
- 返金・返品対応
通信販売や訪問販売などの取引形態に応じて、事業者は、以下のような情報を表示しなければなりません。
- 名称
- 所在地
- 連絡先
- 販売価格
- 支払方法
- 返品条件
これらの義務を遵守することで、事業者は適法な取引を行い、消費者の信頼を確保することができます。
特定商取引のトラブルを回避する対応策
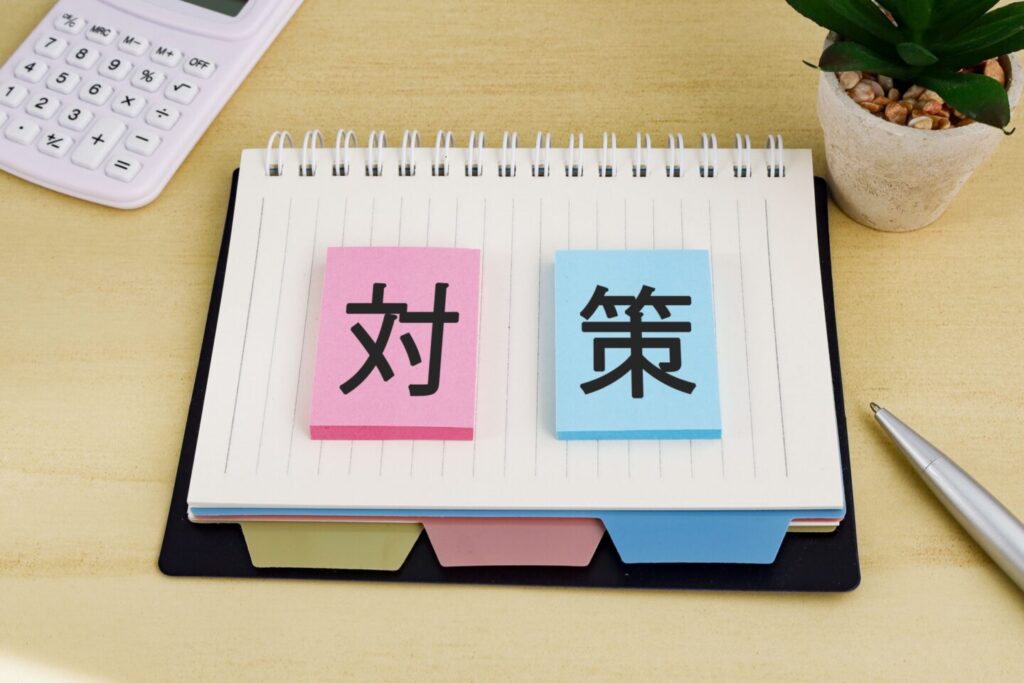
特定商取引に関するトラブルを回避するために、事業者は以下の対策を取ることが必要です。
- 法令順守の実務を徹底する
- 契約の締結・解除時に威圧的にならない
- 消費者の問い合わせや苦情に素早く対応する
- しつこい勧誘はやめる
それぞれの対応策について解説していきます。
法令順守の実務を徹底する
特定商取引におけるトラブルを回避するためには、事業者が法令順守の実務を徹底することが重要です。事業者は特定商取引法に関する規制を正しく理解し、日々の業務に適用しなければなりません。
事業者は社内で特定商取引法に関する研修や教育を実施し、従業員全員が法令を理解できている状態にしておく必要があります。特に、販売担当者やカスタマーサポート担当者は、誤った説明や違法な勧誘行為を行わないよう、適切な指導を受けることが求められます。
また、契約時の説明義務を徹底し、消費者に対して以下のような情報を明確に伝えることも欠かせません。
- 商品やサービスの内容
- 価格
- 返品条件
- クーリング・オフの適用可否
特に、電話勧誘販売や訪問販売では誤解を招くような説明を避け、消費者が納得した上で契約できる環境を整えることが必要です。
契約の締結・解除時に威圧的にならない
特定商取引法では、消費者を守るため、不当な勧誘や契約の強要を禁止しており、事業者がこれに違反すると法的責任を問われる可能性があります。そのため、威圧的な態度や対応は避けるべきです。
契約の締結時には、消費者が十分な情報を得たうえで、自らの意思で判断できる環境を整えることが求められます。また、契約内容について十分な説明を行わず、消費者が不安を感じるような態度をとることも避けましょう。
事業者が解約を妨げるような威圧的な態度をとったり、消費者に不安を与えるような発言をしたりすることは法律で禁止されています。
消費者に安心感を与え、公正な取引を維持するためにも、事業者は契約時や解除時に冷静で丁寧な対応を徹底しましょう。
消費者の問い合わせや苦情に素早く対応する
特定商取引におけるトラブルを回避するために、事業者は消費者からの問い合わせや苦情に素早く対応することが重要です。これらができてないと、トラブルにつながりやすくなります。
問い合わせ対応の基本として、消費者が簡単に連絡できる窓口を設置することが求められます。具体的には、以下のような対策が必要です。
- 電話対応
- メール
- チャットサポート
- FAQページの充実
- 24時間対応のシステム
苦情対応に関しては、消費者の意見に耳を傾け、冷静に対応する姿勢が求められます。感情的な対応を避け、誤解がある場合は丁寧に説明を行い、トラブルの早期解決を目指すことが大切です。
加えて、クレーム対応のマニュアルを作成し、担当者が適切な対応をできるよう教育することも効果的です。特定商取引法に基づくルールを従業員が理解し、法令違反を防ぐための研修を実施することが望まれます。
しつこい勧誘はやめる
特定商取引法では、事業者が消費者に対して「しつこい勧誘」を行うことを禁止しています。消費者が契約を拒否したにもかかわらず、繰り返し営業を行う行為や、心理的圧力をかけて契約を迫る行為などが該当し、消費者の自由な意思決定を妨げるものです。
訪問販売や電話勧誘販売においては、消費者が一度断った場合、それ以上の勧誘を控えることが求められます。契約を急がせるような発言や、不安をあおる営業手法は、消費者に過度なプレッシャーを与えるため注意が必要です。
また、営業活動の際には、従業員に対する適切な教育や研修を実施し、法令順守の意識を徹底することも重要です。特定商取引法のルールを理解し、適切な販売手法を身につけることで、違法な勧誘を防ぐことができます。
しつこい勧誘は、消費者からの信頼を損ない、事業者の評判を落とすリスクがあります。不適切な勧誘が原因で行政処分や罰則を受ける可能性もあるため、事業者は適正な勧誘を心がけ、公正な取引を行いましょう。
特定商取引に対して法的措置が必要なら、弁護士に相談しよう!
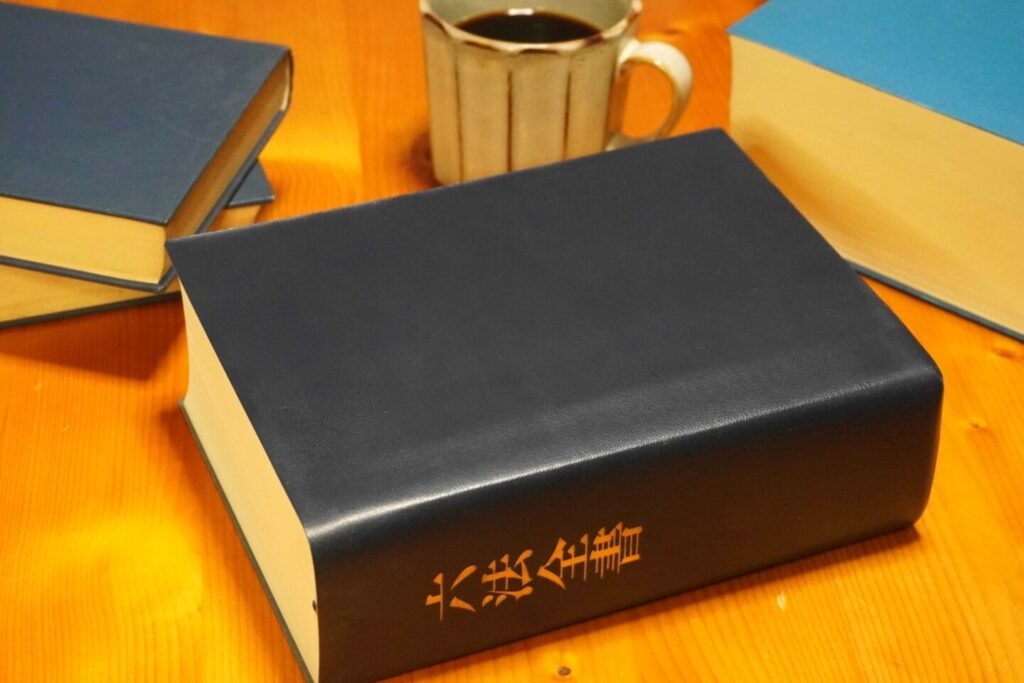
特定商取引に関するトラブルが発生し、法的措置が必要な場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
事業者側であっても、特定商取引法違反のリスクを回避するために弁護士のアドバイスを受けることが重要です。特に、広告表示や勧誘方法が法令に適合しているかどうかの確認、消費者とのトラブルが発生した際の対応について弁護士に相談することで、不要な訴訟リスクを減らすことができます。
法的トラブルは放置すると状況が悪化する可能性があるため、早期対応がポイントとなります。特定商取引に関する問題で不安を感じたら、速やかに弁護士へ相談し、適切な対応策を講じましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。特定商取引について弁護士に相談したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>まとめ

企業活動において、特定商取引への理解は非常に重要です。特定商取引法に違反していると、消費者から訴訟や請求された際に限りなく事業者側の責任となるため、適切に販売・取引を行わなければいけません。
特定商取引に適した活動が行えているかどうかをチェックする際は、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士は法的観点から特定商取引に適合しているかを確認してくれるため、事業活動を見直す機会としても最適です。また、実際にトラブルとなった際にも、弁護士に相談するべきです。
法律の専門家である弁護士に依頼しながら、特定商取引に適した販売活動を行いましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。特定商取引法に適合しているか確認したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












