裁判にかかる費用はどのくらい?訴訟費用と弁護士費用の違いと全体像を解説
訴訟・紛争解決
2024.12.25 ー 2025.12.03 更新
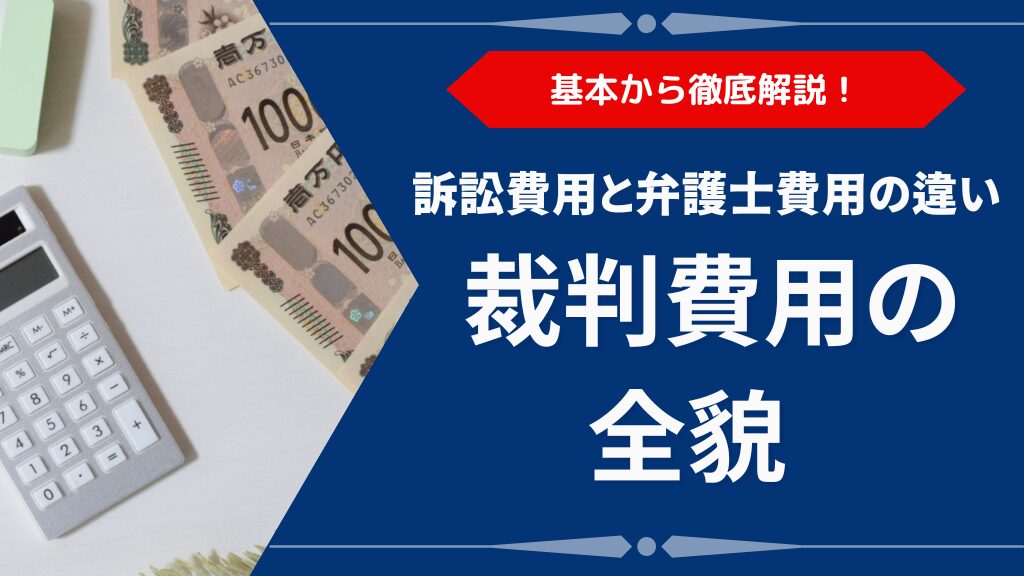
訴訟を起こす際には、様々な費用が発生します。これらを総称して「訴訟費用」と呼びます。
訴訟費用には、裁判所に納める手数料や書類作成費用、証人の旅費など、裁判に直接関わる費用が含まれます。また、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用も重要な要素となります。
訴訟費用の全体像を把握することは、裁判に臨む上で非常に重要です。費用の内訳を理解することで、予算の見積もりや資金の準備が可能となり、不測の事態を防ぐことができます。
さらに、訴訟の結果によっては費用負担のルールが変わることもあるため、事前に費用の全体像を知っておくことは、リスク管理の観点からも欠かせません。本記事では、訴訟費用の内訳や仕組み、負担ルールなどについて詳しく解説していきます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>訴訟にかかる費用は大きくわけて2つ

民事裁判にかかる費用は、大きく分けて次の2つです。
- 裁判所に納付する訴訟費用(印紙代や郵便代などの公的費用)
- 弁護士に支払う弁護士費用(着手金や報酬などの私的費用)
これらの費用はそれぞれ支払先や性質が異なり、訴訟にかかる総額を把握するためには、両者の違いを理解することが重要です。
訴訟費用の内訳(裁判所に支払う費用)
民事訴訟を起こす際には、まず裁判所に対していくつかの費用を納める必要があります。これらは法定の費用であり、請求額や訴訟の進行状況によって異なります。
以下に主な項目を表でまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立費用(印紙代) | 訴額に応じて定められており、訴状提出時に裁判所へ納付(例:請求額300万円→印紙代2万円程度) |
| 郵便切手代(予納郵券) | 裁判所から当事者へ送付する書類用。数千円~1万円程度が一般的 |
| 証人・鑑定人の日当・旅費 | 必要に応じて発生する追加費用 |
| 書類の謄写費用など | 書類のコピーや閲覧の際にかかる費用 |
加えて、仮差押えや仮処分などの民事保全手続、または強制執行を行う際には別途費用が必要となります。
弁護士費用の内訳(弁護士に支払う費用)
弁護士に訴訟を依頼する場合には、事前に費用の内訳を把握しておくことが大切です。弁護士費用は法律で定められたものではなく、契約内容や事務所ごとの方針によって異なります。
一般的な構成は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談料 | 初回無料〜1時間1万円程度が相場 |
| 着手金 | 事件着手時に支払う費用で、請求額の5〜10%程度が目安(例:300万円の請求→約15万円〜30万円) |
| 成功報酬 | 判決や和解などの結果に応じて支払う報酬(回収額の10〜20%程度が相場) |
| 実費 | 裁判に必要な交通費や収入印紙・郵券など、弁護士が立替えた費用 |
訴訟費用と弁護士費用の違いとは?
訴訟費用と弁護士費用は、いずれも裁判に関わる費用ですが、「誰に支払うのか」「何に基づいて発生するのか」が異なります。
以下の表で両者の違いを整理しましたので、混同しないように確認しておきましょう。
| 比較項目 | 訴訟費用 | 弁護士費用 |
|---|---|---|
| 支払先 | 裁判所 | 弁護士 |
| 性質 | 公的費用(法律に基づく) | 私的費用(契約に基づく) |
| 支払タイミング | 訴状提出時、手続ごとに都度納付 | 着手時・終了時(報酬) |
| 負担者 | 原則、敗訴側(裁判費用の一部) | 原則、各自負担(報酬の請求は限定的) |
訴訟費用は敗訴した側が負担するのが原則ですが、弁護士費用は基本的に各当事者が自己負担となります。ただし、裁判の内容や判決によっては、一部の弁護士費用を相手方に請求できるケースもあります(例:不法行為による損害賠償請求など)。
次の章では、通常の訴訟費用とは別に発生する可能性のある「仮差押え」や「強制執行」に関する追加費用と注意点を見ていきましょう。
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
仮差押え・強制執行にかかる追加費用とは?

民事裁判では、判決で勝っても、相手が任意に支払わない限り、実際の回収にはつながりません。そこで活用されるのが、「仮差押え」や「強制執行」といった手続きです。
これらは、相手の財産を差し押さえることで債権回収を実現する重要な手段ですが、通常の訴訟費用とは別に、まとまった金額の費用が発生する点に注意が必要です。
以下で、それぞれの手続きにかかる費用と注意点を解説します。
仮差押えとは?費用の内訳
仮差押えは、判決前に相手方の財産(預金、不動産など)を凍結しておくことで、支払い逃れや財産隠しを防ぐための保全手続きです。
実行には、以下のような費用がかかります。
| 費用項目 | 概要 |
|---|---|
| 申立費用 | 数千円~1万円前後の印紙代(請求額に応じて異なる) |
| 予納郵券 | 書類の送付などに必要な切手代(数千円程度) |
| 登録免許税 | 不動産仮差押えの場合、請求額の0.4% |
| 担保金(供託) | 裁判所が必要と判断した場合に供託。数十万~数百万円のケースもあり |
担保金は「仮に請求が認められなかった場合の損害補填」を目的とした制度で、返還されることもあります。
強制執行とは?費用の内訳
強制執行は、判決や和解が成立しても相手が支払わない場合に、財産を差し押さえて回収する手続きです。以下のような種類と費用があります。
| 執行手続 | 費用概要 |
|---|---|
| 債権執行/動産執行 | 申立費用・郵券などで数万円~十数万円 |
| 不動産執行 | 競売や収益執行に必要な予納金として、80万~200万円程度が相場 |
不動産の強制執行は費用が高額になるため、事前に十分な見積もり・戦略設計が重要です。
手続き前に知っておきたいポイント
- 判決確定が原則必要:強制執行は「確定判決」や「仮執行宣言付き判決」に基づいて行われます。
- 費用の一時立替が必要:手続きを申し立てる側が、原則すべての費用を一時的に負担します。
- 回収可能性の見極めが重要:高額な費用をかけても、相手に財産がなければ費用倒れになるリスクがあります。
- 費用の一部は相手方に請求可能:訴訟費用の一部や執行費用は、後に回収できる場合もありますが、全額保証されるわけではありません。
仮差押えや強制執行は、債権回収において非常に強力な手段である一方、手続きコスト・リスクも高いため、事前の弁護士相談が強く推奨されます。
訴訟費用は原則として敗訴者が負担する
訴訟費用の負担ルールは、一般的に「敗訴者負担主義」が適用されます。これは、裁判で負けた側が訴訟にかかった費用を負担するという原則です。
その理由は、敗訴者側が訴訟の原因を作らなければ、訴訟自体が発生しなかったと考えられるためです。
ただし双方に責任があるケースも多く、敗訴者負担の原則は絶対的なものではありません。裁判所が事案の内容や当事者の経済状況などを考慮して、柔軟に適用することがあります。判決書には『訴訟費用は〇〇の負担とする。』等の文言が記載されます。
敗訴者負担の対象となる費用には、次のようなものがあります。
- 申立て費用、郵券費
- 官公署からの書類取り寄せ費用
これらの算出基準は『民事訴訟費用等に関する法律』によって詳細に定められています。
ただし、弁護士費用は原則として訴訟費用に含まれず、各自が負担することになります。
訴訟費用の負担ルールや、和解時・少額訴訟時の費用分担など、具体的な支払いの仕組みを知りたい方は、以下の記事で詳しく解説されています。
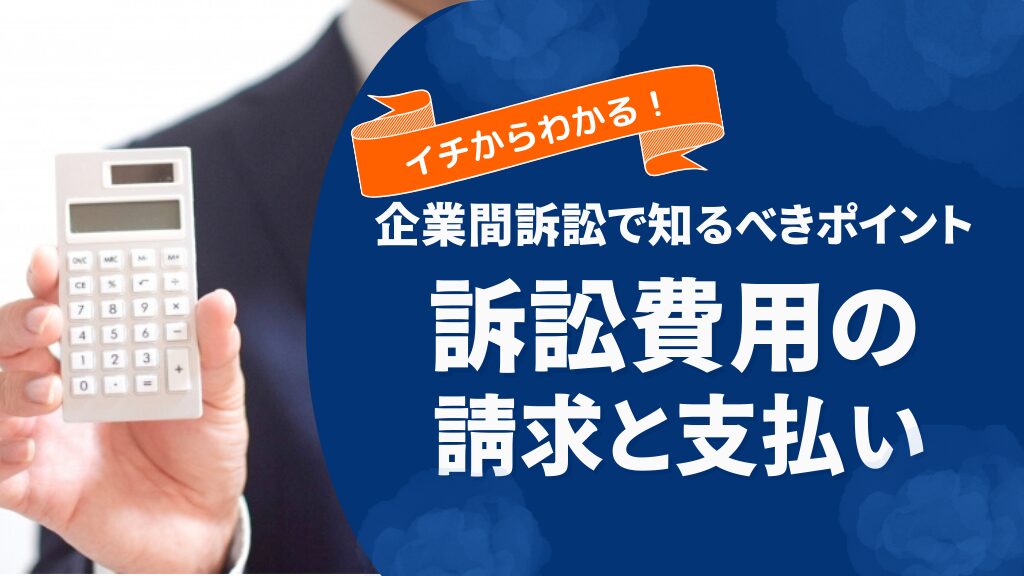
訴訟費用の請求と支払いのルール|企業間訴訟で知るべきポイント
企業間でトラブルが発生した場合、民事訴訟を検討するケースもあります。その際に、訴状に貼る収入印紙代、証人の日当といった訴訟費用が必要です。 しかし、訴訟費用には負担割合があり、裁判の結果によって負担が異なります。そのため […]
民事裁判にかかる弁護士報酬の相場を解説

民事裁判に係る弁護士報酬は自由化していますが、旧基準がひとつの目安として利用されています。
(旧)日本弁護士連合会報酬基準によると、着手金および報酬基準は次のとおりです。
着手金
| 経済的な利益の額 | 弁護士の着手金の額 |
| 300万円以下 | 経済的利益の8%(最低額は10万円) |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 経済的利益の5%+9万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の3%+69万円 |
| 3億円を超える | 経済的利益の2%+369万円 |
報酬金
| 経済的な利益の額 | 弁護士の着手金の額 |
| 300万円以下 | 経済的利益の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下 | 経済的利益の10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6%+138万円 |
| 3億円を超える | 経済的利益の4%+738万円 |
これらの金額について、訴訟に至らず調停や示談等で終了した場合は3分の2に減額できるとされています。
ただし、これらはあくまで目安です。報酬基準は事務所によって違いますし、実働に応じて費用が加算される場合もあるため、具体的な費用は弁護士へ直接相談するのが良いでしょう。
費用負担を軽減する方法
訴訟費用の負担を軽減するためには、次のとおりいくつかの方法があります。
- 法テラスを利用する
- 費用について弁護士に相談する
- 弁護士費用特約を利用する
以下、一つずつ解説していきます。
法テラス(日本司法センター)を利用する
法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法的トラブル解決のための総合窓口です。
利用には資力要件など一定の条件がありますが法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、一時的に費用の立て替えを受けられる可能性があります。
弁護士や司法書士との交渉により、着手金や報酬金の分割払い等が可能になる場合もあります。
法テラスのホームページによると、2024年3月現在までで187万件の建て替え事例があったと公表されています。
費用について弁護士に相談する
弁護士に直接相談することにより、その事務所で着手金を建て替えてくれる場合や、分割払いにしてくれるケースがあります。着手金が建て替えられた場合、成功報酬に加えて請求されるのが一般的です。
また、事案によっては着手金なしで動いてくれる弁護士もいます。
例えばもらい事故による損害賠償請求など、勝訴が充分に望める請求については着手金不要で進めてくれる事務所が多くなる傾向にあります。
弁護士保険、弁護士費用特約を利用する
月々の保険料を支払うことによって、トラブルの際の弁護士費用の全部または一部を補償してくれる保険サービスがあります。
加入から1カ月程度で保険が開始されるサービスが一般的ですが、加入していれば弁護士への依頼費用を抑えることができます。
また、自動車保険や火災保険などで提供される『弁護士費用特約』への加入があれば、一定額を条件として弁護士費用が補償されます。
こうした保険へ加入しておくことにより、弁護士費用が抑えられる場合があります。
訴訟をスムーズに進めるためのポイント
訴訟を円滑に進めるためには、裁判の流れを十分に理解することが大切です。
例えば、金銭を請求する際に財産隠しをされてしまっては訴訟で勝っても現実に強制執行が空振りになる可能性があります。このように、訴訟を提起する前に相手に予告せず、まずは保全手続きを行った方がよいケースもあります。
事前に弁護士と相談し、各段階での必要な手続きや提出書類について確認しておくことで、不安を軽減できます。また、証拠資料の収集と整理も重要です。関連する書類や証拠物を漏れなく準備し、時系列に沿って整理しておくことで、主張の裏付けがしやすくなります。
弁護士とのコミュニケーションを密に取り、冷静な態度を保つことでより効率的な解決につながる可能性があります。
まずは弁護士に相談し、現在の状況を法的な面から理解することで、訴訟をより円滑に進めることができ、結果的に時間と費用の節約にもつながります。
弁護士選びのチェックポイント
弁護士選びは訴訟の成否を左右する重要な要素です。
まずは専門性と実績等の情報を確認しましょう。離婚や債務整理、企業法務、労務など、特に専門性を持って活動する弁護士や法律事務所も多いため、専門性の高い事務所に解決を依頼することが特に重要になります。
全く専門分野の違う事務所に相談すると、見積もりが大きく異なる場合もあるため注意が必要です。
自己の問題・悩みについて専門が分からない場合は、まず専門性を確認するところから質問して問題ありません。弁護士同士の横のつながりによって、特に専門性の高い事務所を紹介してくれる場合もあります。
また、直接話をした際の信頼性やコミュニケーション能力も重視すべきポイントです。
費用面についても、明確な説明を行ってくれる事務所を選択すると良いでしょう。これらのポイントを総合的に判断し、自分に最適な弁護士を選ぶことが訴訟を有利に進める鍵となります。
弁護士探しは『法務急済』をご利用ください
本サイト『法務急済』では、各種業務に強い弁護士・法律事務所を全国を対象として紹介しています。『エリア』と『相談内容』から検索できますので、弁護士探しにお役立てください。
ご利用の際は本サイトへの登録不要で、各弁護士事務所へ直接お問い合わせいただくことが可能です。
また、各事務所へは無料相談が利用できますので、まずは連絡し相談してみてください。ご相談の際は、お悩みの内容とどのように解決したいかなど、要点をまとめておくとスムーズです。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












