労働基準監督署からの呼び出し?!企業が知るべき権限・対応フロー・リスクと対策
労働問題・労働法務
2025.07.11 ー 2025.07.11 更新
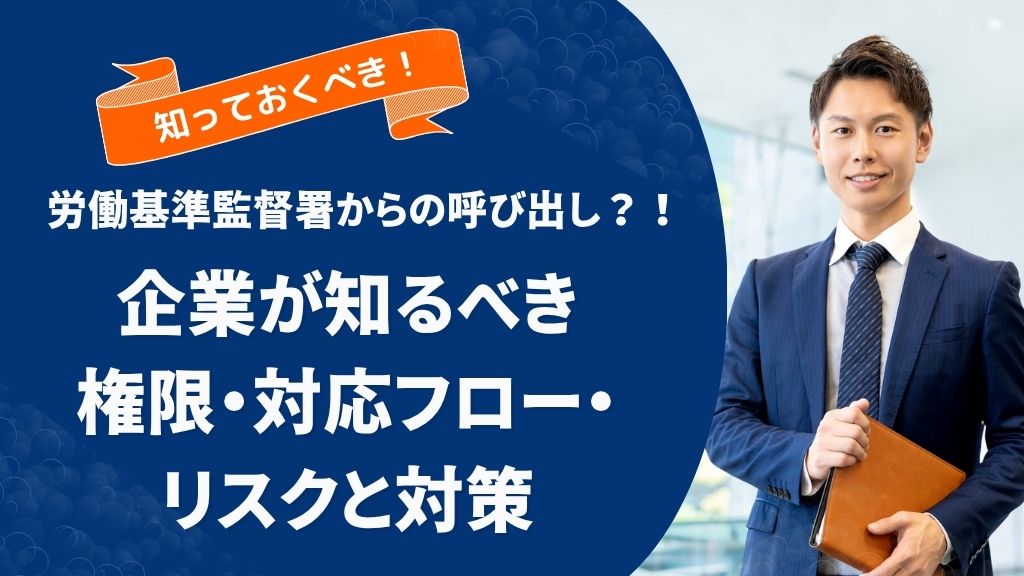
突然、労働基準監督署から「呼び出し通知」や「是正勧告書」が届き、どう対応すればいいのか困っていませんか?
働き方改革や労務コンプライアンスが厳しく求められる中、労働基準監督署は厚生労働省の管轄機関として、企業に対して強い調査権限を持ちます。
しかし、「そもそも労働基準監督署とは何なのか?」「呼び出し後にどんな流れで調査が進むのか?」「無視するとどんなリスクがあるのか?」を具体的に理解している経営者は多くありません。
本記事では、労働基準監督署の役割・権限から、呼び出し後の対応フロー、是正勧告の対処法、さらに弁護士に依頼すべきケースや費用感まで、実務に役立つ視点でわかりやすく解説します。
突然の通知に動揺しないためにも、最後までご覧ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>労働基準監督署とは?企業が知るべき役割と権限
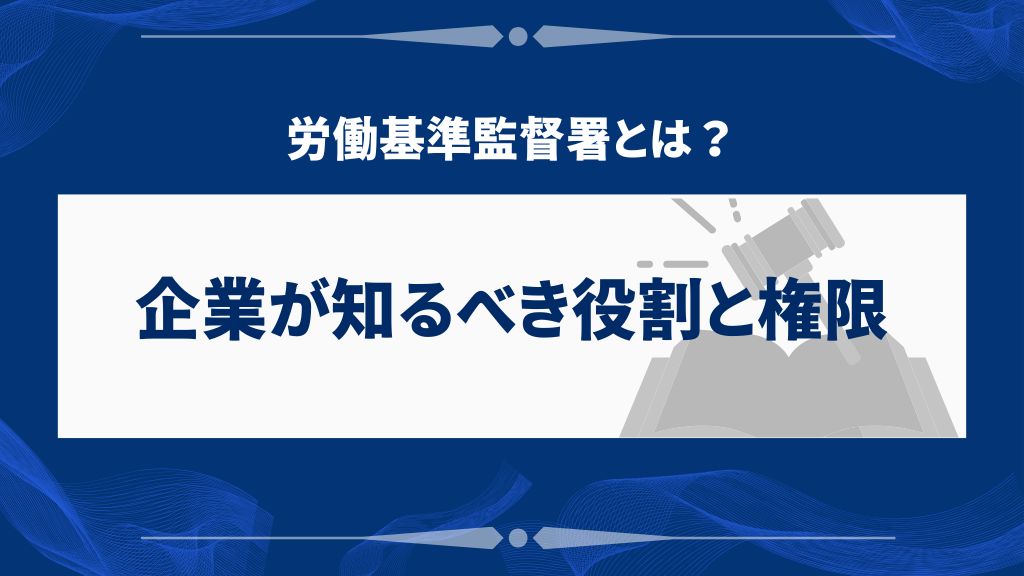
労働基準監督署は、厚生労働省の第一線の機関として、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令に基づき、事業場を監督・指導する役割を担っています。
その最大の目的は、労働者の労働条件の確保や改善、安全衛生の確保、労働災害の防止を通じて、労働者を保護することにあります。
企業にとっては、突然の呼び出しや調査への対応が必要となるケースもあり、適切な理解が欠かせません。ここでは、労働基準監督官が担う主な業務内容と、企業に対して行われる行政指導の種類について、順に解説していきます。
- 労働基準監督官の業務
- 主な行政指導の種類
労働基準監督官の業務
労働基準監督署では、企業が労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令に適切に従っているかを監督しています。具体的には、労働時間、賃金、休日・休暇などの労働条件が法令通りかどうかを確認し、職場の安全衛生状況についても指導を行います。
また、万が一労働災害が発生した際には、その原因を調査し、再発防止に向けた指導も実施。労働者災害補償保険(労災保険)の給付に関する業務も、監督官の重要な役割のひとつです。
これらの役割を果たすために、労働基準監督官には以下のような強力な権限が与えられています(労働基準法第101条)。
- 臨検監督権:予告なしで事業場に立ち入り、帳簿や書類の内容を調査する権限
- 尋問権:事業主や労働者に対し、事実関係を聴取できる権限
- 司法警察権:悪質または重大な違反が認められた場合、刑事事件として捜査し、検察庁に送致できる権限
特に「臨検監督」は、企業の実態を正確に把握するため、予告なしで実施されることが一般的です。調査対象となるのは、タイムカード、賃金台帳、就業規則などの法定書類。場合によっては、従業員への直接ヒアリングが行われるケースもあります。
このような調査を経て、法令違反が判明した場合は、企業側に対して改善を求める行政指導が行われる流れです。
次に、その行政指導の種類と特徴について詳しく解説します。
主な行政指導の種類
労働基準監督署が企業に対して行う行政指導には、主に次の2つがあります。
まず1つ目が「指導票」です。これは、法令違反とまでは言えないものの、改善が望ましい事項について注意や助言を行うために交付されるものとなります。比較的軽微な問題に対して使用されるのが特徴です。
次に、「是正勧告書」です。こちらは、労働基準法などの法令違反が明確に確認された場合に交付される書類で、違反状態を是正するよう企業に勧告するものです。たとえば、未払い残業代、違法な長時間労働、安全衛生管理上の不備など、具体的な違反内容が指摘されます。
これらの行政指導は、いずれもあくまで「行政指導」に位置づけられ、法的な強制力はありません。ただし注意すべきなのは、是正勧告に従わない場合や、違反が悪質・重大と判断された場合です。このようなケースでは、労働基準監督官に与えられた「司法警察権」に基づき、刑事事件として捜査が行われ、最終的に検察庁へ送致(送検)される可能性があります。
送検は、司法手続きにおける最初の段階です。仮に起訴された場合、企業や経営者が刑事罰の対象となることもあります。
もちろん、是正勧告を受けたからといって即座に罰則が科されるわけではありません。ただし、指摘を放置したまま放置することは非常にリスクが高いため、誠実かつ速やかな対応が不可欠です。
労働基準法について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

労働基準法35条をわかりやすく解説!シフト作成で押さえる法定休日と割増賃金のルール
シフト作成を担当している店長や店舗経営者の方にとって、労働基準法35条の理解は避けて通れない重要テーマです。 「法定休日って週1回でいいんだよね?」「代休と振替休日ってどう違うの?」そんな疑問を感じたことはありませんか。 […]
労働基準監督署から呼び出し通知が届いたら?
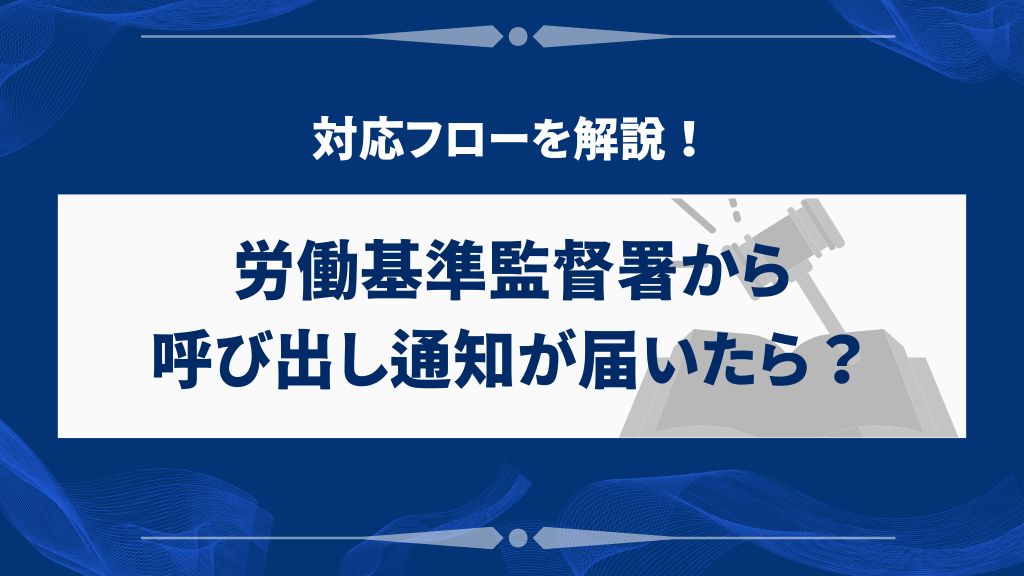
労働基準監督署から、「出頭要求書」が届くことがあります。この通知書は、労働基準監督官が事業場へ立ち入る臨検監督とは異なり、労働基準監督署に企業側が出向き、帳簿書類の提出やヒアリングを受ける形式で実施される調査手法です。
具体的には、企業の労務管理状況や法令違反の有無について、担当官による事実確認や状況聴取が行われます。
ここでは、呼び出しが発生する主な理由、通知書で確認すべき重要ポイント、さらに無視や対応遅延によるリスクについて、順に解説していきます。
労働基準監督署の調査の種類と流れ
労働基準監督署から出頭を求められる調査には、主に3つのケースがあります。これら3種類の調査はそれぞれ実施される背景が異なるため、企業としては、いつ、どのような形で調査が入るか予測できない場合もあります。
日頃から労働関係法令を遵守し、適切な労務管理体制を整備しておくことが重要です。
| 定期監督 | 労働基準監督署が年度計画に基づき、特定の業種や地域を選定して行う調査 |
| 申告監督 | 労働者や退職者からの労働基準法違反に関する申告を受けて行われる調査 |
| 災害時監督 | 労働災害が発生した際に原因究明のために行われる調査 |
特に申告監督は最も多い呼び出し理由の一つ。未払い残業代、不当解雇、ハラスメントなどが典型的な申告内容です。実際に労働基準監督署から呼び出しを受ける際に送付されるものに、「出頭要求通知書」があります。
この通知書には、出頭すべき日時や場所(通常は管轄の労働基準監督署)、聴取される事項、そして当日持参すべき書類が具体的に記載されています。
通知書の中で特に重要なのは、「持参すべき書類」の項目です。ここにリストアップされている書類を確認することで、どのような問題について調査が行われるのかをある程度推測できます。
例えば、「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」のように法定三帳簿の提出が求められている場合、労働時間や賃金の未払いが主な調査対象である可能性が高いと考えられます。
無視や遅延のリスクと罰則
労働基準監督署から呼び出し通知を受けた際、これを無視したり、対応を遅らせたりすることは絶対に避けるべきです。
労働基準法第120条では、労働基準監督官による臨検や尋問、帳簿書類の提出要求を拒否した場合などに、30万円以下の罰金が科されることが定められています。
呼び出しへの対応を怠ると、労働基準監督官は「法令違反を隠蔽しようとしているのではないか」と疑われるリスクも無視できません。このような場合、事前の予告なしに事業場への立ち入り調査(臨検)が実施される可能性が高まります。準備不足のまま突然の調査に直面し、企業側が不利な状況に追い込まれることも十分に考えられます。
正当な理由なく対応を遅らせることは、労働基準監督官の心証を悪化させる一因となるでしょう。これにより、その後の行政指導や是正勧告の内容がより厳しくなることも考えられます。
以上のことから、呼び出し通知に対しては、誠実かつ迅速に対応する姿勢が不可欠です。
聴取・立ち入り・是正指導までの流れ
労働基準監督署による調査は、いくつかの段階を踏んで進められます。一般的にはまず、事業場の経営者や労務担当者に対して、労働基準監督署への「出頭」が求められるのが最初のステップです。
出頭時には「聴取(ヒアリング)」が行われ、事前に提出を指示された書類をもとに、労働時間や賃金支払い状況などが確認されます。
提出が求められる書類には、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの法定三帳簿に加え、就業規則、時間外・休日労働に関する協定書(36協定)、雇用契約書(労働条件通知書)などが含まれるのが一般的です。
聴取結果だけでは事実確認が不十分と判断された場合や、労働者からの申告内容に基づく追加調査が必要な場合には、労働基準監督官による事業場への「臨検監督(立ち入り調査)」が実施されることがあります。
この調査では、組織図や安全衛生設備、現場の労働環境といった物理的な側面まで詳細に確認されます。さらに、必要に応じて現場の労働者に対して直接ヒアリングが行われることもあります。
調査の結果、法令違反が見つかった場合には、労働基準監督署から「是正勧告書」が交付される流れです。この書面には、違反事項が具体的に記載され、企業側には指定された期日までの改善が求められることになります。
一方で、法令違反とは言えないものの、労働環境の改善が望ましいケースについては「指導票」が交付される形です。この場合は、自主的な対応が求められることになります。
いずれの文書にも法的な強制力はありませんが、内容を放置したままにすると、さらに厳しい措置に発展するリスクがあるため注意が必要です。
是正報告書の書き方と提出期限
是正勧告は行政指導にあたるため、それ自体に法的な強制力はありません。しかし、是正勧告を無視したり、対応を怠ったりすれば、違反が悪質と判断される可能性があります。最終的には司法処分(送検)に至るケースもあるため、是正勧告を受けた際は、真摯に対応することが大切です。
労働基準監督署から是正勧告を受けた場合は、指定された期日までに「是正報告書」を作成して提出する必要があります。
この報告書は、是正勧告で指摘された法令違反に対し、企業がどのような是正措置を講じたのかを明確に伝えるためのものです。法令で定められた特定の様式はありませんが、事業場の是正状況が正確に伝わるよう、任意の書面で作成します。
是正報告書には、一般的に以下の項目を記載します。
- 是正勧告書に記載された違反事項
- 講じた具体的な是正内容
- 是正が完了した日付
特に是正内容の記載にあたっては、「今後注意します」「善処します」といった曖昧な表現は避けてください。「いつ」「誰が」「何を」「どのように改善したのか」を、具体的かつ客観的に記述する必要があります。
例えば、長時間労働の是正であれば、「〇月〇日から勤怠管理システムを導入し、従業員の労働時間をリアルタイムで把握できる体制を整えた」といった具合に記載するとよいでしょう。
さらに、是正内容を裏付ける客観的な資料の添付も重要です。未払い残業代の是正であれば、精算額一覧表や振込明細書、就業規則の不備であれば、改訂後の就業規則の写しなどが該当します。これらの資料を添付することで、是正措置が実際に行われたことを効果的に示せます。
是正勧告書には、是正期日が明記されています。指定された期限は必ず守るようにしましょう。やむを得ない事情で期日内の対応が難しい場合は、必ず事前に担当の労働基準監督官に相談し、対応方針や期限延長の可否について確認を取ってください。
無断で提出が遅れると、「対応が不誠実である」と判断され、その後の行政指導に悪影響を及ぼす恐れがあります。迅速かつ適切な対応が、企業にとって最善のリスク回避策と言えるでしょう。
弁護士に相談すべきケースと費用相場
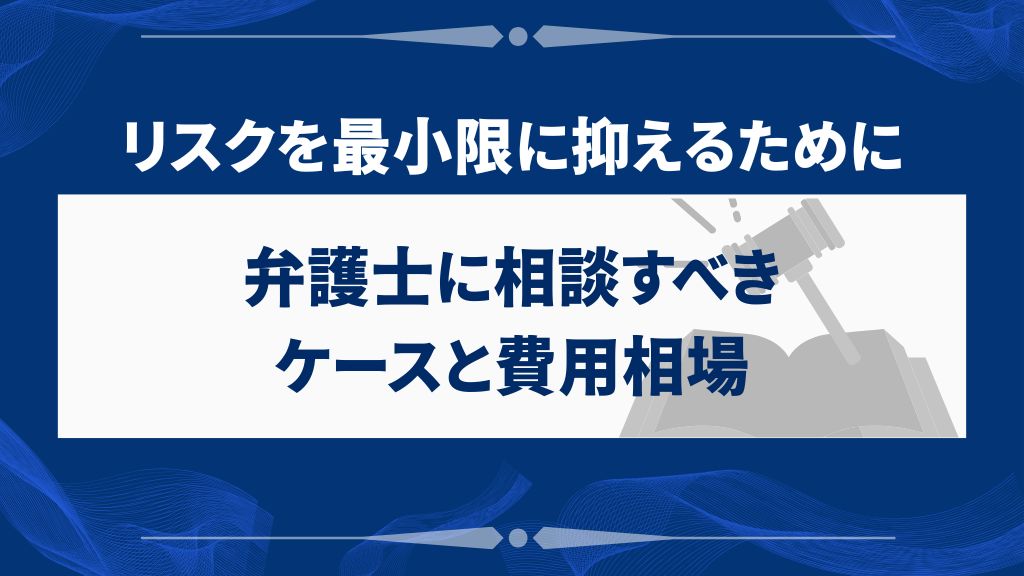
労働基準監督署からの呼び出しや調査、あるいは是正勧告への対応は、企業にとって大きな負担となりがちです。
自社だけで対応することに不安がある、もしくは法的リスクをできる限り抑えたいと考える場合には、労働問題に詳しい弁護士への相談が有効です。
特に、指摘内容が複雑だったり、過去にも同様の是正勧告を受けた経験がある企業では、専門家の支援によってリスクを最小限に抑えることが期待できます。
このあとの章では、弁護士が労基署対応時にどのような役割を果たすのか、また契約形態ごとの特徴や費用相場について、詳しくご紹介します。
呼び出し・是正対応における弁護士の役割
労働基準監督署からの呼び出しや調査、是正勧告への対応は、専門的な知識が求められるうえ、担当者にとって精神面、時間面ともに大きな負担となりがちです。このような場面では、弁護士に相談することで、適切かつスムーズな対応が可能となります。
弁護士はまず、労働基準監督署からの指摘事項について法的な観点から妥当性を判断し、企業がとるべき最も適切な対応策について具体的なアドバイスを提供します。
企業の代理人として労働基準監督署との連絡窓口を担当し、必要に応じて聴取や立ち入り調査への同席も可能です。これにより、企業担当者の精神的なストレスや実務上の負担を大幅に軽減できるでしょう。
また、是正勧告を受けた場合には、是正報告書の作成支援も行います。弁護士は、法的に適切で実現可能な改善計画を立案し、再発防止策を盛り込んだ実効性の高い内容に仕上げるサポートを提供します。
さらに、企業にとって不利となる是正勧告内容や、万が一の刑事事件化(送検)リスクを最小限に抑えるため、労働基準監督署との交渉も弁護士の重要な役割のひとつです。
このように、弁護士の支援を受けることで、企業は安心して労働基準監督署への対応を進めることができるようになります。
顧問契約とスポット契約の違いと費用
労働基準監督署対応をはじめ、労務問題に関する継続的なサポートが必要な場合と、特定の案件だけを依頼したい場合とでは、弁護士との契約形態が異なります。主な契約形態としては、「顧問契約」と「スポット契約」の2種類が一般的です。
顧問契約は、月額固定の顧問料を支払うことで、日常的な法律相談や契約書のリーガルチェック、予防法務などの継続的なサポートを随時受けられる仕組みとなっています。
中小企業における顧問弁護士の費用相場は、月額3万円から5万円程度が目安です。
継続的な契約により、弁護士側が企業の事業内容や社内事情を深く把握できるため、より実情に即した迅速なアドバイスが期待できます。
一方で、スポット契約は労働基準監督署対応など、特定の案件が発生した際にのみ単発で依頼する契約形態です。費用は、相談料、着手金、成功報酬などで構成されるのが一般的で、案件の難易度や作業内容によって大きく変動します。
法律相談の相場は、30分あたり5,000円から1万円程度が目安です。また、労基署対応に関する着手金は、10万円以上となるケースが多く見受けられます。スポット契約は、必要な時だけ利用できるため、コストを抑えやすい点がメリットと言えるでしょう。
どちらの契約形態を選ぶべきかは、問題の深刻度や、今後の労務トラブル発生リスク、さらに弁護士に求めるサポート範囲などを踏まえて総合的に判断することをおすすめします。
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
労働基準監督署と向き合うための経営者のチェックリスト
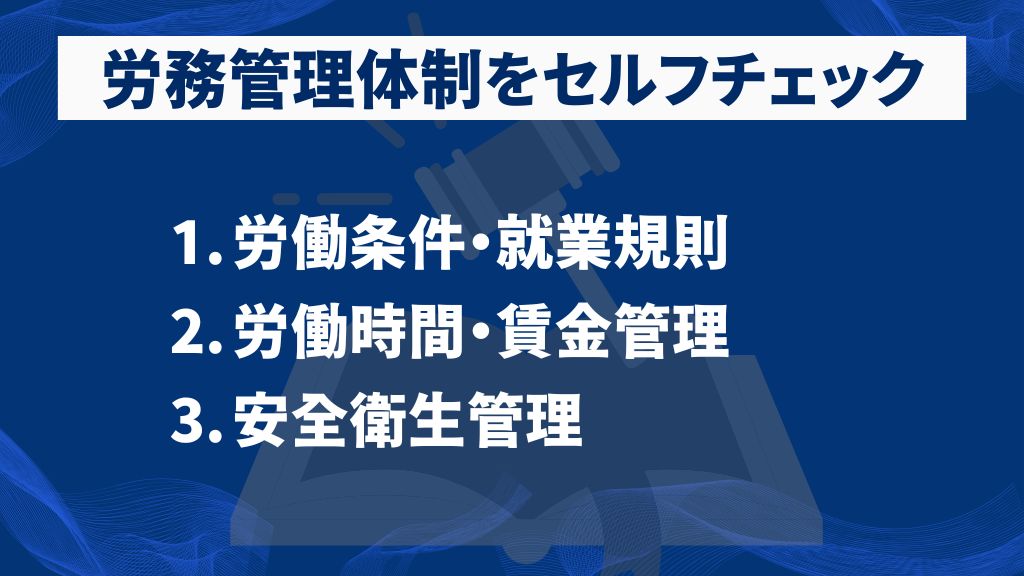
これまで、労働基準監督署の役割や調査、是正勧告への対応について解説してきました。
万が一調査が入った際に、落ち着いて適切に対応できる体制を整えておくことはもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、日頃から労働関係法令を遵守し、適切な労務管理を徹底することです。結果として、労働基準監督署による調査そのものを「未然に防ぐ」ことにつながるでしょう。
ここでは、経営者の方が自社の労務管理体制をセルフチェックできるよう、実践的なチェックリストをご紹介します。
内容は「労働条件・就業規則」「労働時間・賃金管理」「安全衛生管理」など、労働基準監督署が特に重視するポイントごとに整理しています。
社内体制の整備と記録管理のポイント
労働基準監督署による調査や是正勧告のリスクを低減し、万が一の場合にも適切に対応するためには、日頃から自社の労務管理体制を整備し、必要な記録を正確に管理しておくことをおすすめします。
まず、労務管理の責任者を明確にし、労働基準法の改正内容に合わせて就業規則や時間外・休日労働に関する協定届(36協定)などの各種規程を定期的に見直しましょう。改定した規程は、全従業員に確実に周知徹底する体制を構築することが重要です。
また、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のいわゆる「法定三帳簿」は、法律に基づき正確に作成・管理し、定められた期間(原則5年間、当面の間は3年間)保管することが義務付けられています。これらの書類は、労働基準監督署の調査において必ず確認される重要な記録です。
労働時間の管理については、タイムカード、PCの利用ログ、勤怠管理システムなど、客観的な方法で正確に記録する仕組みを導入し、労働者の自己申告との間に乖離がないか定期的に確認することが求められています。
さらに、従業員が労働条件や職場環境に関する疑問や不満を会社に直接相談できる窓口を設置し、問題が大きくなる前に社内で解決できる体制を整えることも、労働基準監督署への通報リスクを減らすことにつながります。
再発防止に向けた社内教育とルール策定
労働基準監督署からの指摘を受けた場合には、その内容を真摯に受け止め、再発防止策を講じることが求められます。全従業員が労働関連法令や社内ルールを正しく理解することが、予防策として非常に重要です。
たとえば、管理職に対しては、労務管理の基礎知識や労働時間管理、ハラスメント防止策についての研修を実施することが効果的です。一般従業員には、労働条件や就業規則の内容、ハラスメントの定義などをわかりやすく周知することが欠かせません。
これにより、従業員のコンプライアンス意識が高まり、健全な職場環境づくりにもつながります。
また、法改正や労基署からの指摘に応じて、就業規則や各種社内規程を適宜見直し、改定サイクルを明確にしておくことも大切です。特に「残業事前申請制」や「ハラスメント防止規程」など、実効性のあるルール整備が求められます。
さらに、雇用契約書や就業規則の内容を最新の法令に適合させ、それを確実に従業員へ周知する体制を整えることも忘れてはなりません。労働条件の明示は、労働基準法で明確に義務付けられている事項です。
従業員が安心して働ける職場環境を実現するためには、気軽に相談できる社内窓口の設置も有効です。寄せられた声には迅速かつ真摯に対応し、問題が深刻化する前に解決を図る姿勢が大切と言えるでしょう。
こうした取り組みを積み重ねることで、従業員のエンゲージメントが向上し、企業全体の持続的な成長にもつながります。
なお、労務管理についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
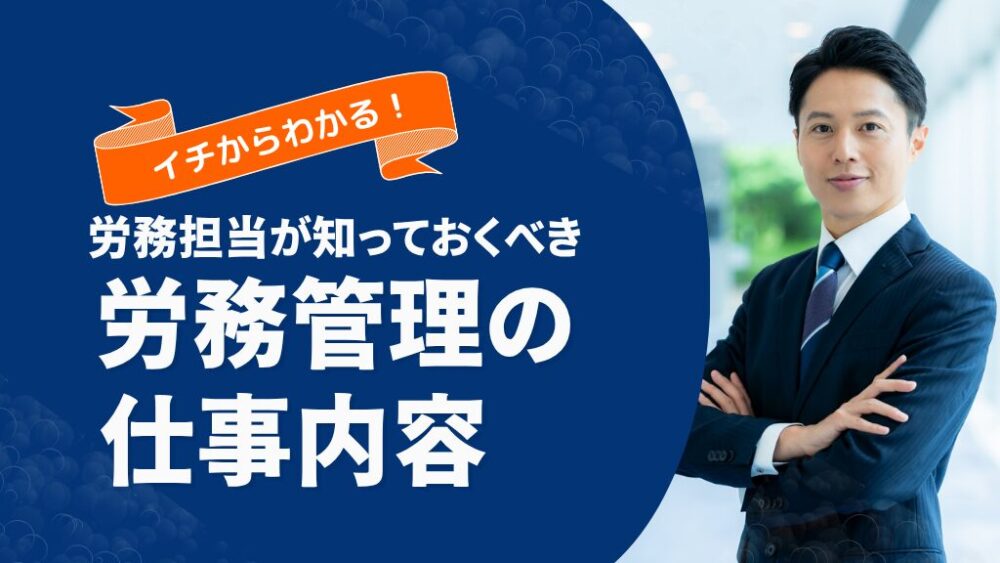
労務管理とは?具体的な仕事内容や人事との違いを3ステップで簡単に解説!
「労務管理って、実際どんなことをするの?」 初めて労務担当になった方や、これから従業員を雇う経営者の方にとって、労務管理は少しハードルが高く感じるかもしれません。難しい言葉に戸惑ったり、「何から手をつければいいかわからな […]
まとめ|労働関係法令を遵守して適切な労務管理体制を整えよう
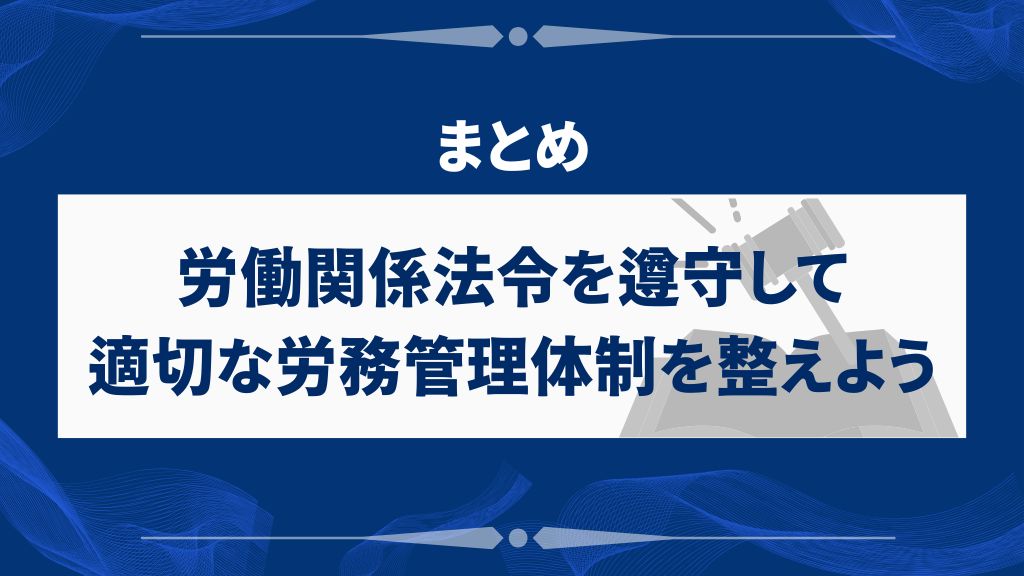
この記事では、労働基準監督署の役割や権限、さらに企業が呼び出しや調査、是正勧告を受けた場合の具体的な対応フローについて詳しく解説しました。
労働基準監督署は、労働基準法をはじめとする各種労働関連法令に基づき、企業が適正な労働環境を整備しているかを監督・指導する公的機関です。
主な活動には、計画的に実施される定期監督や、労働者からの申告によって実施される申告監督などがあり、違反が確認された場合には是正勧告や行政指導が行われます。場合によっては、司法処分として送検に至ることもあります。
特に、労働基準監督署による調査は、特定の業種や規模に限らず、あらゆる企業に対して突然実施される可能性がある点に注意が必要です。法令違反の有無にかかわらず、申告監督などはいつでも発生し得ます。
万が一、労働基準監督署から呼び出しや調査、是正勧告を受けた場合、自社対応が難しいと感じる場面や、法的リスクが懸念されるケースでは、労働問題に精通した弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
専門家の支援を受けることで、適切かつ迅速な対応が可能となり、リスクを最小限に抑えながら企業経営の安定を図ることができるでしょう。
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ
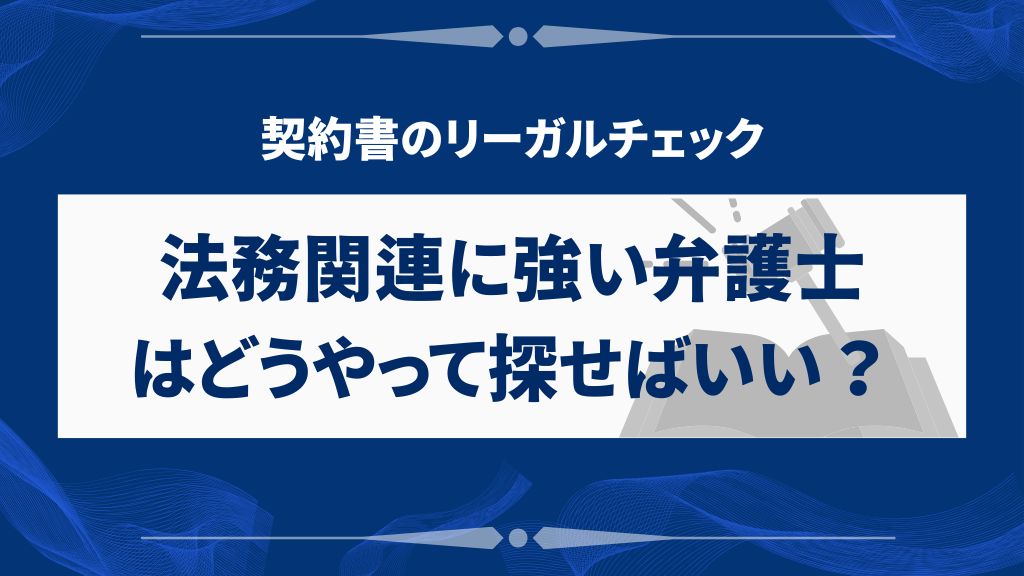
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












