内容証明とは?弁護士に頼むべき理由と費用・書き方・送付手順まで全解説
予防法務
2025.07.22 ー 2026.01.05 更新
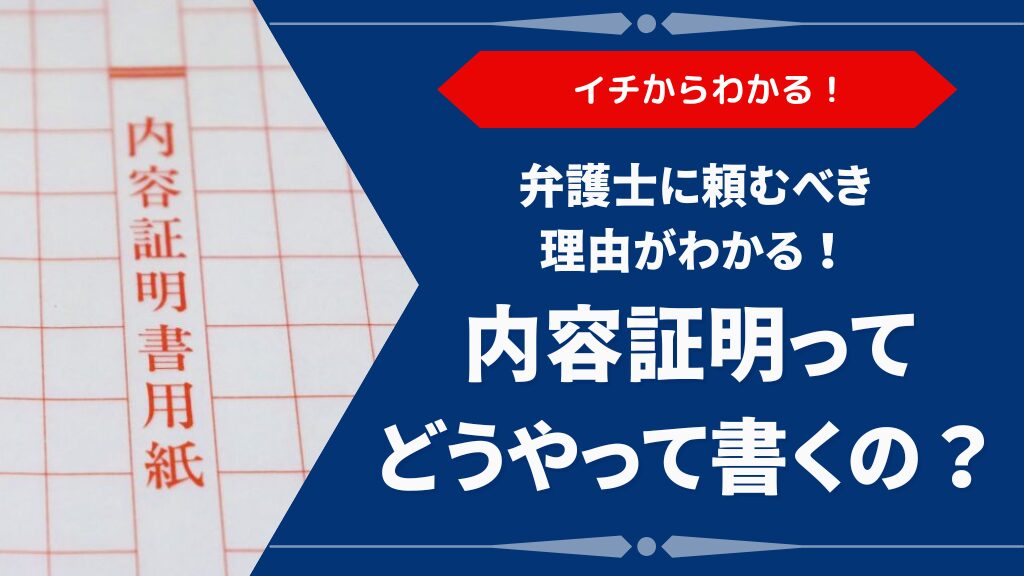
「内容証明について聞いたことはあるけれど、実際どんな効力があるのか分からない」「弁護士に頼むべきか、自分で出しても大丈夫なのか迷っている」そんな不安を抱えていませんか?
また、相手が支払いに応じない場合や、自分で内容証明を作成する際のリスクについて、悩んでいる方も多いでしょう。
本記事では、内容証明の基本から、弁護士に依頼するメリット、費用相場まで幅広く解説します。初めて内容証明を使う方でも安心できるよう、内容証明の効力や注意点も交えて解説しますので、 ぜひ参考にしてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>内容証明とは?定義とメリットについて解説
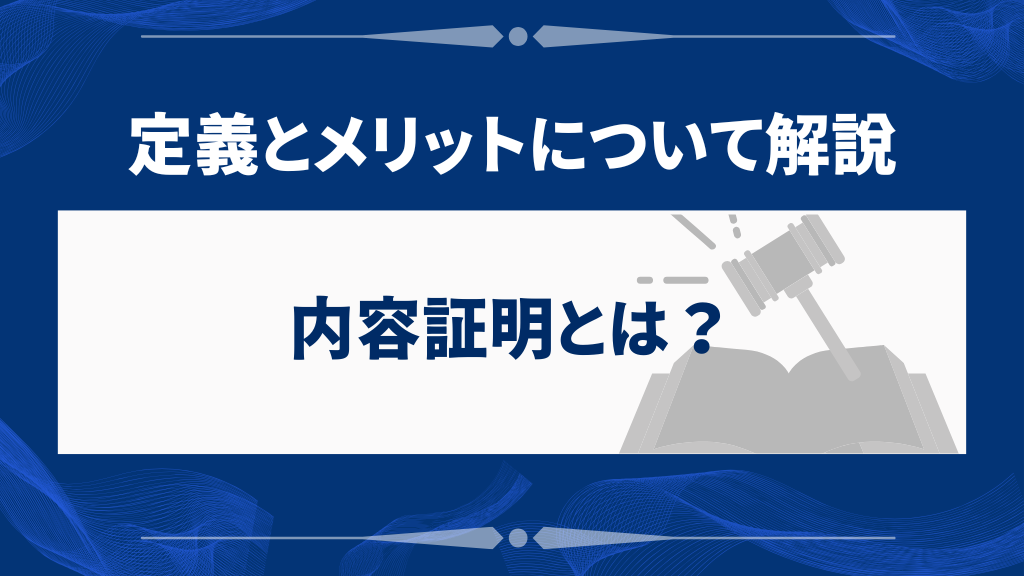
内容証明郵便は、日本郵便が「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明してくれるサービスです。内容証明自体には「相手に強制する法的な力」はありませんが、「送った事実」として証拠として残るので、後々の裁判などで効力を発揮します。
ここでは、内容証明を使うメリットを分かりやすく解説します。
到達証明
配達証明を付加すれば、「相手に郵便物が無事配達された」という事実を証明できます。
先ほど解説した通り、内容証明自体には、相手に何らかの行為を強制するような法的な強制力はありません。しかし、その内容が公的に証明されるため、裁判で証拠として使えます。
時効中断の効果
内容証明には、債権の消滅時効が間近に迫っている場合などに「催告」として送付することで、時効の完成を最大6ヶ月間猶予させる効果があります(民法第150条第1項)。
ただし、この6ヶ月の猶予期間内に訴訟の提起など次の法的措置を取らなければ、時効の完成を阻止できない点には注意が必要です。このように、内容証明は証拠保全や時効の猶予などに役立ちます。
内容証明が効果を発揮する主なトラブル例
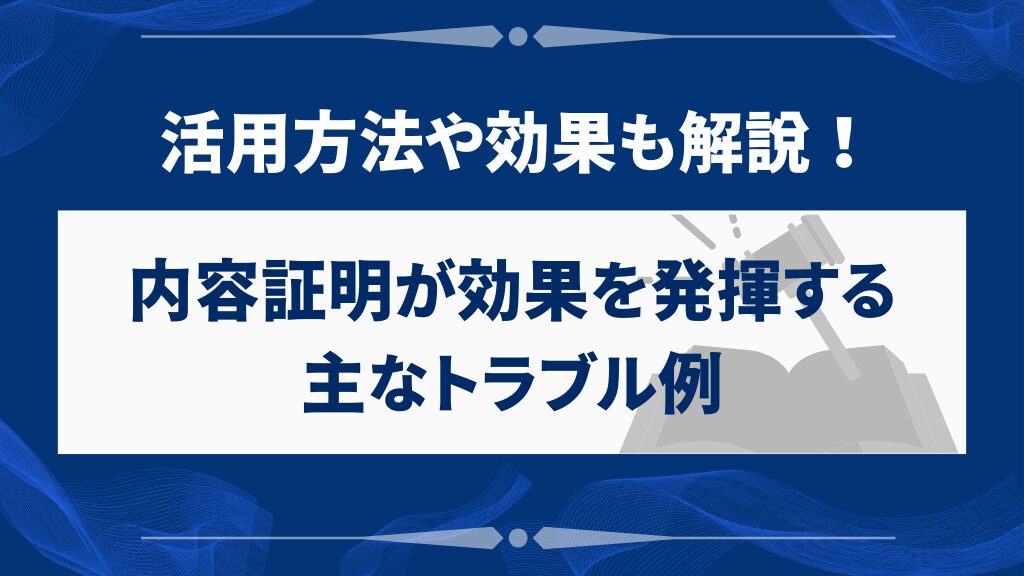
内容証明が特にその力を発揮するのは、金銭の未払いや契約違反など、当事者間の主張が食い違いやすく、後に法的な争いに発展する可能性のある場面です。
ここでは、これらの典型的なトラブル例について、内容証明がどのように活用され、どのような効果をもたらすのかをさらに詳しくご紹介します。
金銭トラブルや契約問題
内容証明は、損害賠償や慰謝料の請求において、口頭で何度催促しても応じない相手に対して有効な手段です。弁護士名義で内容証明を送付することで、相手に心理的なプレッシャーを与える効果もあります。また、裁判に発展した際には、その内容証明が証拠として活用できる点も重要です。
さらに、企業間取引における未払い金の督促にも有効です。支払期日を過ぎても入金がない取引先には、内容証明によって正式に支払いを催告することができます。
期限までに支払いがない場合には、法的手続き(訴訟など)に移行する意向を明確に伝えることもでき、相手に対する強いメッセージとなります。
不倫・いじめ・労働問題例
内容証明は、個人的な問題の解決にも幅広く利用されています。具体的には以下のようなケースがあります。
不倫問題
慰謝料請求に相手が応じない場合に弁護士名義で内容証明を送付することで、相手に法的手続きに進む可能性を強く認識させ、交渉に応じるケースが多くなります。その結果、裁判を起こさずに慰謝料の支払いが実現するなど、早期解決が期待できます。
いじめ問題
学校側の対応が不十分な場合に、具体的な事実や安全配慮義務違反を指摘した内容証明を送付することで、学校側に真摯な対応を促し、問題解決のきっかけになることがあります。
会社との労働問題
未払い残業代の請求を拒否されている場合、具体的な請求内容と法的措置の可能性を記載した内容証明を送ることで、会社が訴訟リスクを回避するために支払いに応じる場合があります。
このように、内容証明は多様なトラブルの解決手段として、相手に強いプレッシャーを与え、法的な主張を明確に伝えることができます。
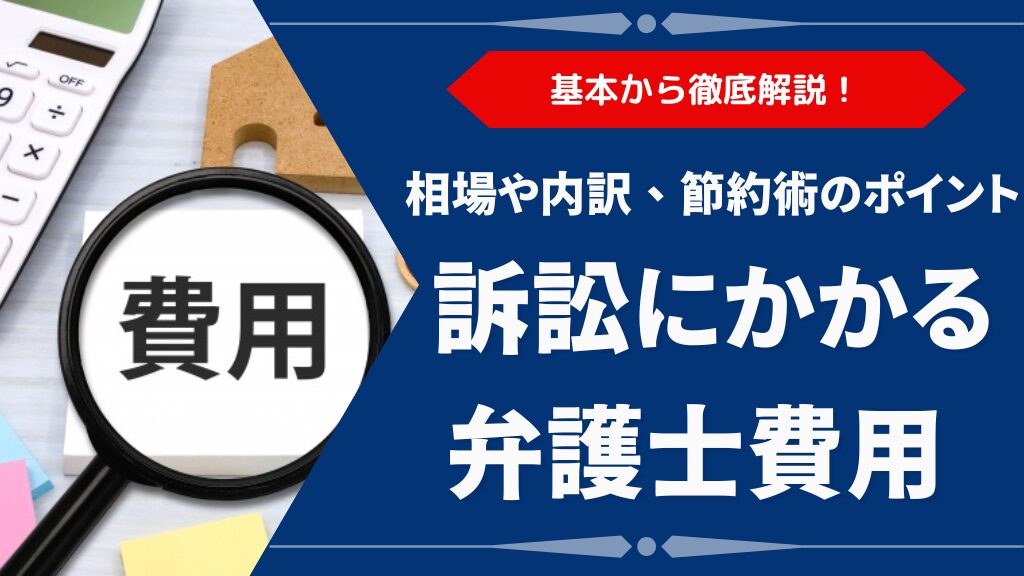
訴訟にかかる弁護士費用はいくら?相場や内訳、支払い負担を軽減する方法を解説
民事訴訟における費用は、個人・法人を問わず気になる方も多いでしょう。訴訟・裁判に費用は大きく分けて裁判費用と弁護士費用の2つがあり、そのうち裁判費用は手続きを行う上で発生するものであるため、費用を抑えるのが難しい場合があ […]
内容証明を自力作成できる?作成・発送手順と注意点まとめ
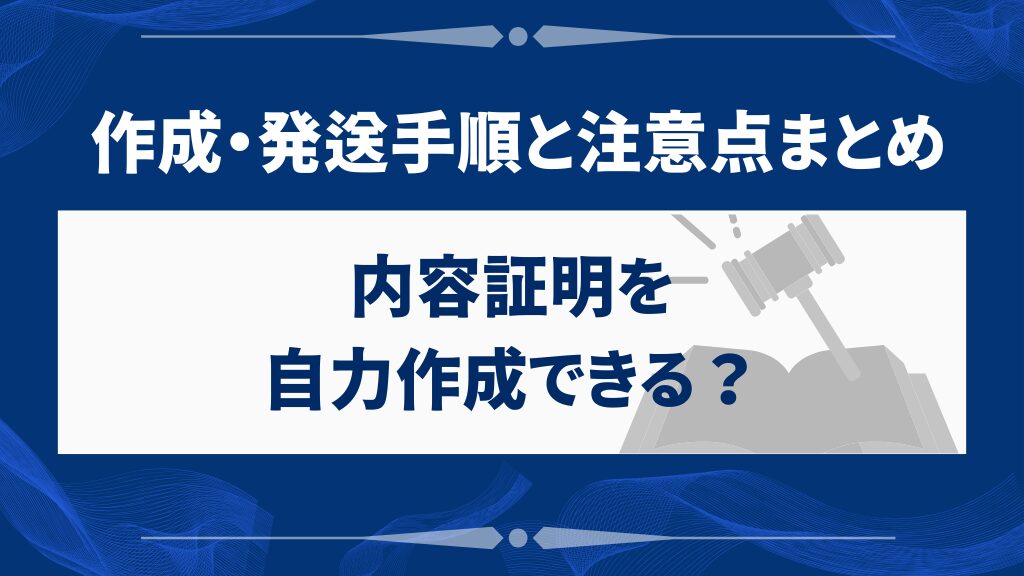
内容証明は、自分で作成し、郵便局から発送することも可能です。しかし、作成や手続きには、文字数・行数制限、使用できる文字など、形式面での細かな決まりごとを守る必要があります。
ここでは、内容証明を自分で作成・発送する際のステップや注意点について詳しく解説します。
内容証明を自力作成する場合のメリット・デメリット
内容証明は、弁護士などの専門家に相談せず、自分で作成し、郵便局から差し出すことも可能です。郵便料金や内容証明、配達証明などの実費のみに抑えられるため、コストが気になる方には嬉しいメリットです。
しかし、自分で作成する場合、以下のようなデメリットも存在します。
- 内容証明には文字数制限などの細かな書式ルールが定められており、これらを正確に守り、不備なく文書を作成するには、かなりの手間と時間がかかる
- 法的な知識がないまま作成すると、記載内容が不正確になったり、請求の根拠が曖昧になったりするリスクがある
- 個人名で送付した場合、弁護士などの専門家名義で送付する場合と比べて、相手に与える心理的なプレッシャーが弱まりやすい。相手が内容証明を軽視し、結果として問題解決が進まない可能性がある
記載すべき項目と文面構成のポイント
内容証明を自分で作成する際には、記載すべき項目は以下のようなものがあります。
- 差出人の氏名と住所
- 法人の場合は会社名と代表者名
- 受取人の氏名と住所
- 文書の作成日や発送日
- タイトルや見出しとなる文言
- 通知や請求などの本文
- 回答や対応を求める期限
- 差出人の電話番号やメールアドレスなどの連絡先
- 差出人の署名と押印
文面構成のポイントは以下の通りです。
- トラブルの経緯や事実関係を客観的かつ具体的に記述すること。「いつ、誰が、何をしたか」を明確にし、感情的な表現は避ける。
- 事実に基づき、相手方に何を要求するのかという請求内容を明確に記載すること。未払い金なら具体的な金額、支払期限、振込先などを明記する。
- 請求の履行期限を具体的に示し、期限内に履行されない場合の法的な措置(訴訟など)を示唆すること。これにより、相手方に事態の深刻さを認識させ、行動を促す。
また、内容証明を利用するにあたって、謄本を作る必要があります。謄本には、以下の書式ルールがあります。
| 書式 | 字数・行数の制限 |
| 縦書きの場合 | 1行20字以内・1枚26行以内 |
| 横書きの場合 | 1行20字以内・1枚26行以内1行13字以内、1枚40行以内1行26字以内・1枚20行以内 |
このように使用できる文字に制限があるほか、句読点やかっこなどの記号についても細かな記載ルールが定められています。また、文書に訂正・挿入・削除を行う場合は、その箇所と字数を欄外や末尾に明記し、差出人の押印をする必要があります。
さらに、謄本が複数枚にわたる場合には、すべての綴じ目に契印(割印)を押さなければなりません。こうしたルールに不備があると、内容証明として受理されない可能性もあるため、十分な注意が求められます。
形式面での不備によるトラブルを避けるためにも、内容証明の作成は弁護士などの専門家に依頼するのが安心です。
郵送方法・費用・送付後の対応までの流れ
内容証明を郵送する際には、まず同じ内容の文書を3通用意する必要があります。それぞれ、「相手用」「日本郵便保管用」「差出人控え」として使用します。また、封筒と訂正用の認印も準備しておくとスムーズです。
発送は、郵便局の「一般書留」で行う必要があり、料金は次の4つの合計になります。
- 郵便の基本料金
- 一般書留の加算料金
- 内容証明の加算料金
- 配達証明の料金(任意)
内容証明の加算料金は、文書の枚数によって増減します。1枚目は固定料金ですが、2枚目以降は1枚ごとに追加料金が発生する点に注意が必要です。
また、相手が受け取った証明が必要な場合には「配達証明」を付けることで、郵便局から配達完了の通知が届きます。
以下は、定形郵便(50gまで)の場合の代表的な料金内訳です。
| 区分 | 料金 | 備考 |
| 基本料金 | 110円 | 定形郵便物(50gまで)の場合 |
| 一般書留 加算料 | 435円 | 基本料金に加算 |
| 内容証明 加算料 | 480円 | 文書1枚の場合 |
| 2枚目以降の加算 | 290円/1枚 | 内容証明文書が複数枚ある場合 |
| 配達証明 | 350円 | 任意 |
相手が受け取り拒否・無視した場合の対処法
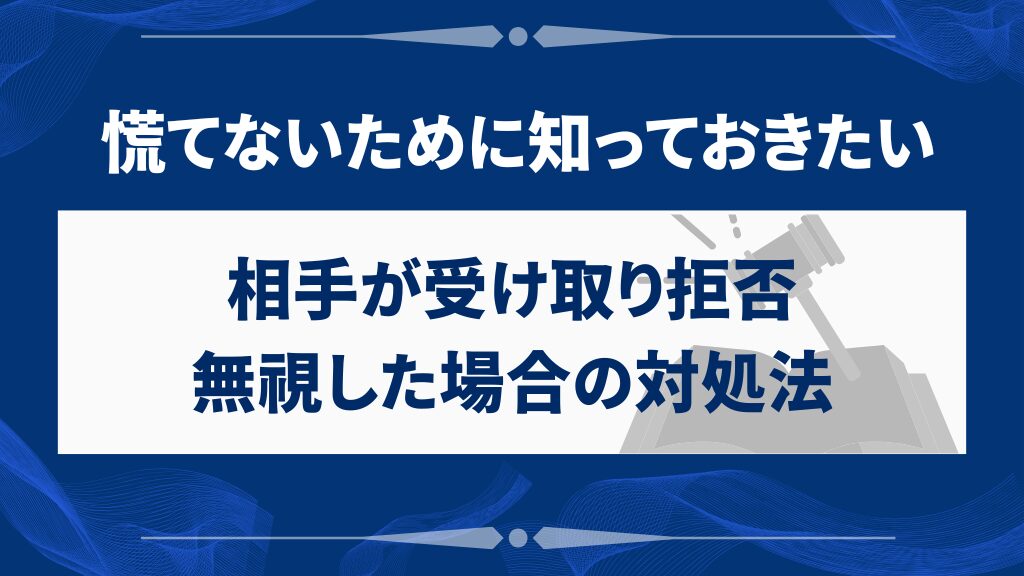
内容証明郵便を送った後、相手が受け取りを拒否したり、不在通知を無視して郵便物が返送されてしまうこともあります。
このような場合の法的な扱いは、それぞれの状況によって異なります。
受け取り拒否の場合
郵便は差出人に返送されますが、「受け取ろうと思えばできた」と判断される状況であれば、法的には相手に内容が「到達した」とみなされます(到達擬制)。この場合、内容証明を送った証拠はしっかり残ります。
不在で返送された場合
相手が単に不在で保管期間が過ぎて返送された場合は、「内容を知る機会がなかった」と判断され、「到達」とはみなされない可能性が高いです。
受け取ったのに無視された場合
相手が内容証明を受け取ったにもかかわらず反応がない場合は、当事者同士の話し合いでの解決が難しい状況です。この場合は、次のステップとして法的手続きを検討しましょう。
法的手続きが必要になった場合は、事案の内容や目的に応じて、裁判所を通じた支払督促・民事調停・訴訟提起等の中から、どの手段を選ぶかを判断する必要があります。 受け取り拒否や無視という状況は、問題がさらに複雑化し、解決のために専門的な対応が必要となる可能性が高いです。
そのため、もし対応に迷った場合は、弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
弁護士に内容証明を依頼する4つのメリット
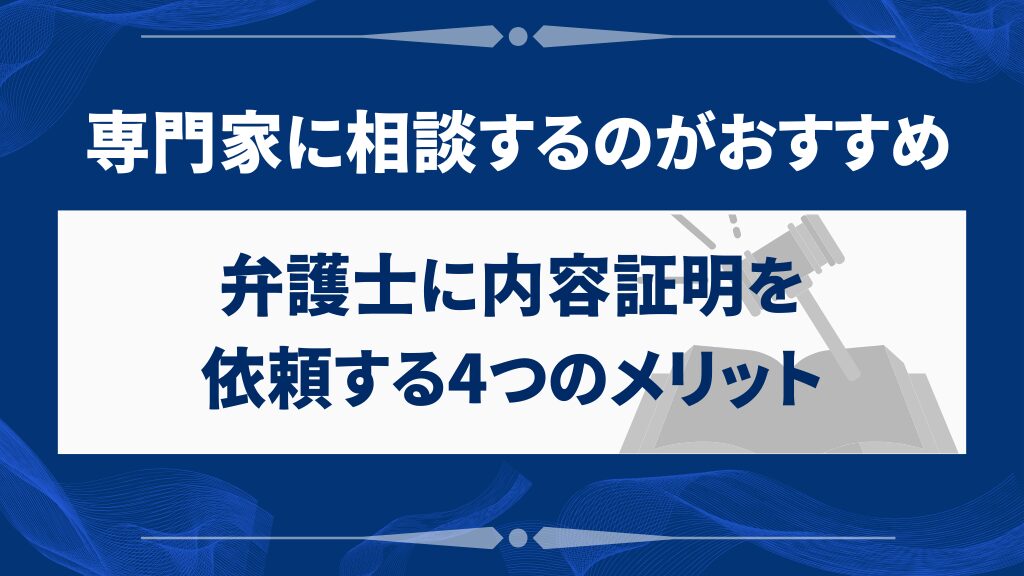
内容証明は自分で作成・発送することも可能ですが、トラブルを確実に解決し、より有利な状況を生み出すためには、弁護士に依頼するのが効果的です。
ここでは、 内容証明を弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。
法的専門性によって文章に説得力が増す
弁護士に内容証明の作成を依頼する大きなメリットは、その文章が持つ法的な説得力です。弁護士は法律の専門家として、単に依頼者の要望を書き記すだけではありません。要求の根拠となる関連法規や過去の裁判例を踏まえ、論理的な構成で文書を作成します。
これによって主張が法的に正当であることが明確になり、相手方もその内容を軽視しづらくなります。
また、法律の専門家が用いる正確な用語や客観的な記述は、感情的な押し付けではなく、冷静かつ法的な要求として受け止められやすくなるのも大きな特徴です。
さらに、法的に不正確な記述や主張の曖昧さを排除できるため、相手に不要な誤解を与えたり、反論の隙を与えたりするリスクも大幅に減少します。このように、正確で説得力のある内容は、その後の交渉を有利に進めるためにもとても重要です。
相手に与える心理的プレッシャーの大きさ
弁護士に内容証明の作成・送付を依頼することで、相手に強い心理的なプレッシャーを与える効果が期待できます。
特に、これまで個人の催促や要求を無視していた相手に対しても、弁護士からの通知は「要求に応じなければ次は裁判などの法的措置に移行する」という強い意思表示として伝わります。
また、依頼者が費用をかけてまで弁護士に依頼しているという事実も、問題解決に対する本気度を相手に伝えることになり、誠実な対応を引き出しやすくなる効果が見込めるでしょう。
相手が企業である場合、法的な紛争を避けたいと考える傾向が強く、弁護士からの通知が届いたことで、速やかに対応を始めるケースも少なくありません。このように、弁護士名での内容証明は、相手にプレッシャーを与え、早期の行動を促す有効な手段となります。
やり取りも含めて全面的に弁護士に任せられる安心感
トラブル発生時、相手方と直接やり取りをすることは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。特に感情的な対立がある場合、冷静な話し合いは困難になりがちです。
このような関係者同士の直接的なやり取りから解放される点は、弁護士に内容証明の作成や送付を依頼する大きなメリットといえます。弁護士があなたの代理人として対応することで、感情的な衝突を避け、冷静かつ法的な観点から交渉を進めることが可能です。。
さらに、弁護士に依頼すれば、内容証明の作成、発送手続きだけでなく、郵便送付後の相手方からの連絡や反論への対応、その後の交渉まで、一連の流れすべてを任せることができます。これにより、煩雑な手続きや相手とのやり取りといった負担も軽減される点も大きな魅力です。
また、相手方が内容証明を無視したり、不誠実な反応を示したりした場合でも、弁護士が法的な知見に基づき、次に取るべき最適な対応策を提案してくれます。問題解決に向けて専門家が常に状況を管理し、対応してくれるという事実は、依頼者にとって非常に大きな安心感につながるでしょう。
裁判を見据えた証拠化が可能になる
弁護士に内容証明の作成を依頼することで、内容証明の証拠としての価値を最大限に引き上げることができます。弁護士は法律の専門家として、将来裁判で争点となりうる法的要件(例えば、請求の根拠、損害額の算定方法など)を正確かつ網羅的に文書に記載します。
これにより、内容証明は単なる通知書ではなく、法的な主張の根拠を明確に示す文書となり、証拠としての効力を高められます。
また、弁護士は内容証明の段階から訴訟を視野に入れた戦略的な文面を作成します。これにより、もし交渉が決裂して裁判に移行した場合でも、内容証明での主張と裁判での主張に一貫性が生まれ、手続きをスムーズに進めることが期待できます。
弁護士が関与した事実そのものが、事態を解決に向けた真摯な法的手続きと位置付けられ、裁判においてもこちらの誠実な姿勢を証明する材料となるでしょう。
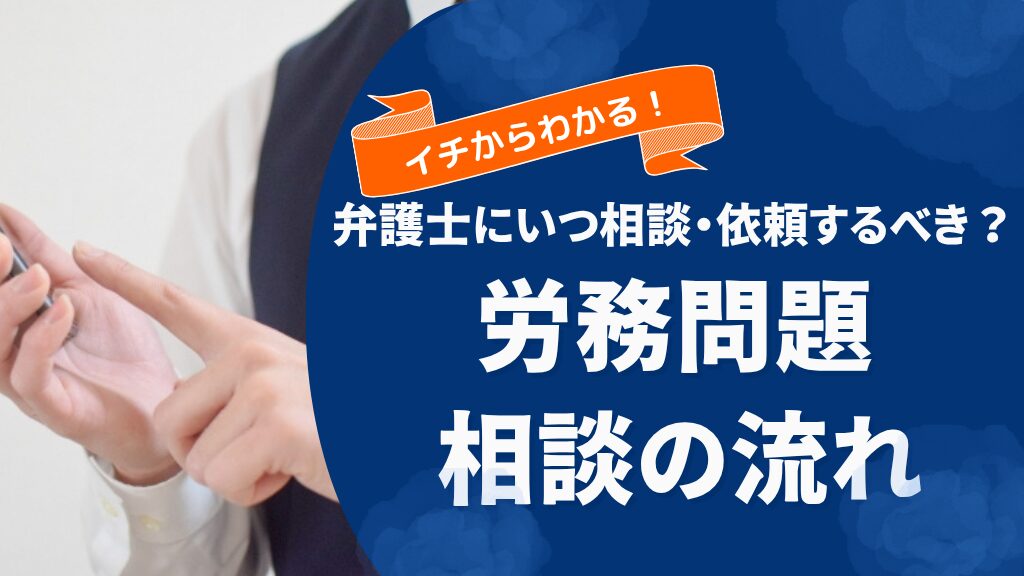
労務問題 弁護士に相談すべきタイミングとは?中小企業が知っておきたい実務対応ガイド
社内での労務トラブルに、どのように対応すべきかお悩みではありませんか?解雇や残業代請求、ハラスメント対応など、企業が直面する労働問題は年々複雑化しています。 特に法務部門を持たない中小企業では、正しい対応がわからず、後手 […]
内容証明を弁護士に依頼する場合の費用相場・依頼方法とは?
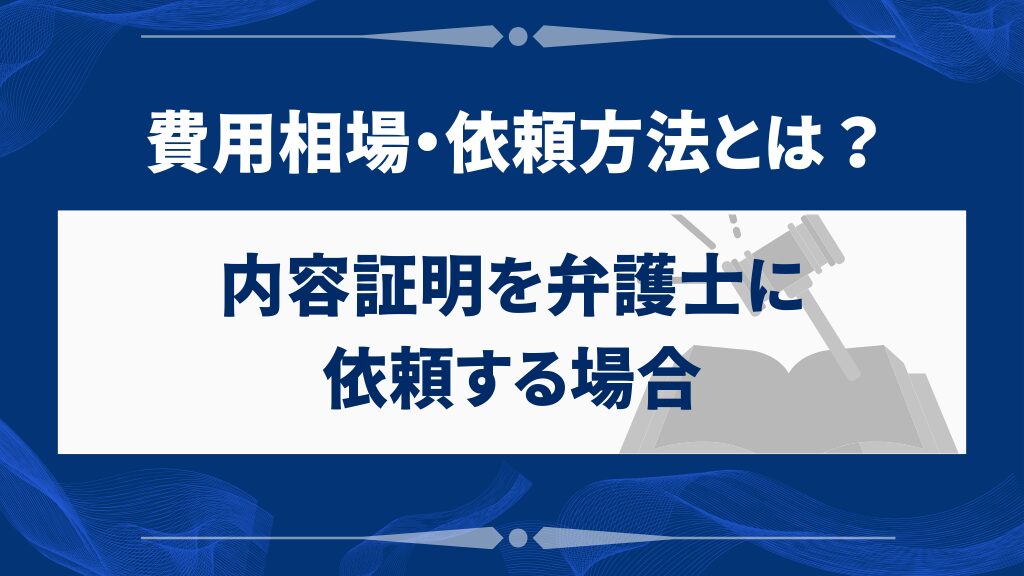
内容証明を弁護士に依頼する場合の費用相場
弁護士に内容証明の作成・発送を依頼する場合、弁護士費用は作成・発送のみで3万円から10万円程度が目安となります。事案の複雑さによって費用は変動します。
もし、内容証明送付後の相手方との交渉や訴訟代理まで一括して依頼する場合は、内容証明作成費用とは別に、別途着手金や成功報酬が発生する料金体系が一般的です。
具体的な費用については、依頼前に必ず弁護士に確認しましょう。
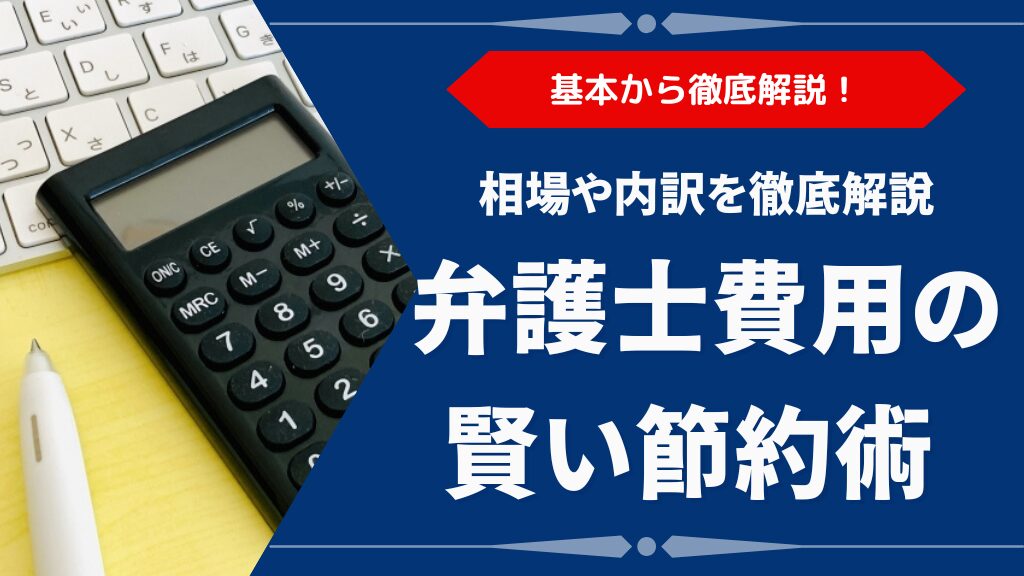
知らないと損!弁護士費用の相場と賢い節約術を徹底解説
弁護士に依頼したいが、「費用がどれくらいかかるのか不安…」と感じていませんか? 弁護士費用は、相談料・着手金・成功報酬などさまざまな項目があり、案件によっても大きく異なります。そのため、事前に相場を把握しておくことで、高 […]
弁護士への依頼方法
弁護士への依頼は、一般的に以下の流れで進みます。
- まずは相談したい弁護士を探します。
- 法律相談を予約します。相談時には、トラブルの経緯をまとめたメモや契約書、メールなどの関連証拠を準備しておくとスムーズです。
- 相談後、正式に依頼を決めたら委任契約を締結します。
- 弁護士が内容証明を作成・発送します。
依頼する弁護士を選ぶ際は、解決したいトラブル分野における実績や専門性、費用体系の明確さ、そしてコミュニケーションが取りやすいかなどを考慮することが重要です。複数の弁護士に相談し、比較検討するのも良いでしょう。
以下は、自力で作成した場合と弁護士に依頼した場合の比較表です。
| 項目 | 自力で作成 | 弁護士に依頼 |
| 費用 | 郵便料金・内容証明・配達証明などの実費のみで安価 | 作成・発送で3万~10万円程度(事案により変動)+交渉・訴訟は別途費用 |
| 手間・時間 | 書式や文字数制限を自分で調べて作成。手間や時間がかかる | 弁護士が作成・発送・相手とのやり取りまで一括で対応。手間が大幅に減る |
| 書式ミスのリスク | 文字数・行数・記載内容など細かなルールを守る必要があり、不備で受理されないことも | 法的要件や書式を専門家がチェック。不備の心配がほぼない |
| 法的な説得力 | 法的根拠や主張の記載が不十分になりがち。相手に軽く見られるリスク | 法律の専門知識に基づいた説得力のある文書。相手に強いプレッシャーを与えやすい |
| 心理的プレッシャー | 個人名義では相手に与える圧力が弱く、無視される可能性がある | 弁護士名義で送付することで「訴訟リスク」を強く意識させ、交渉に応じやすくなる |
| トラブル解決力 | 相手が対応しない場合、次の法的手続きへの移行が個人では難しい | 弁護士が交渉・訴訟まで一貫して対応でき、早期解決や有利な展開が期待できる |
このように、コスト重視ならDIY、確実性や安心感を求めるなら弁護士依頼がおすすめです。
まとめ|内容証明を送るなら弁護士依頼が安心
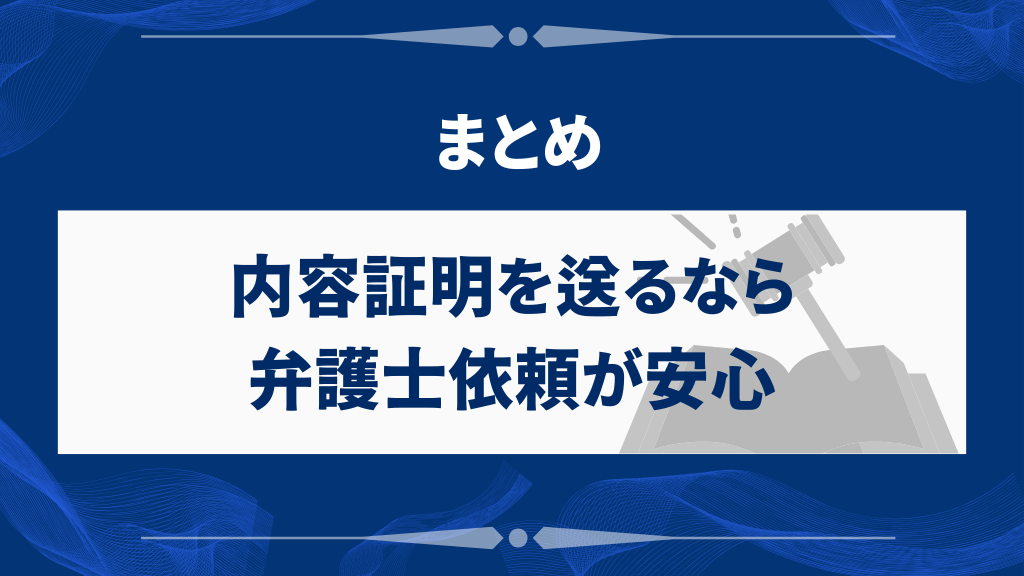
内容証明は、「いつ・どのような内容の文書を・誰から誰に送ったか」を公的に証明できる手段です。金銭トラブルや契約違反、不倫、労働問題など、幅広い場面で活用されるほか、時効を一時的に止める効力もあります。
自分で作成・発送することも可能ですが、1行20字以内・1枚26行以内とのような厳格な書式・文字数ルールがあり、不備があると郵便局で受理されない場合があります。また、内容が曖昧だと相手に伝わらず、かえって不利になるリスクもあるため、法的知識に不安がある場合は注意が必要です。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
- 法的根拠に基づき、正確で説得力のある文書を作成できる
- 弁護士名義で送ることで、相手に強い心理的プレッシャーを与えやすい
- 交渉や訴訟対応まで一貫して任せられ、精神的負担を軽減できる
- 将来的な法的トラブルやリスクを回避しやすい
費用の目安は文書作成のみで3~5万円程度が相場ですが、相手に強い効果を与えられ、早期解決やトラブル防止につながる点を踏まえると、費用対効果は高いといえます。
内容証明の活用や弁護士への依頼を迷っている場合は、初回無料相談などを利用して、専門家にアドバイスを求めるのがおすすめです。
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












