民事訴訟の流れは?手続きの詳細や必要書類、準備事項を徹底解説
訴訟・紛争解決
2025.03.26 ー 2025.03.27 更新
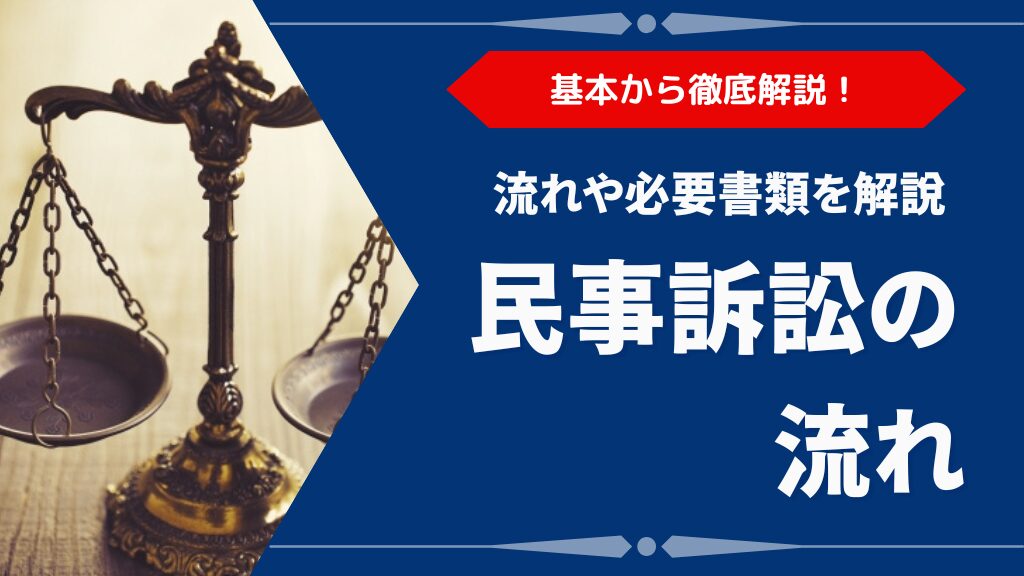
民事訴訟を起こすうえで、訴訟の流れは把握しておく必要があります。手続きの進め方や必要書類、準備事項を用意していないと、適切に訴訟を進行することができません。
民事訴訟は弁護士に依頼することも可能ですが、最低限の流れは把握しておくべきでしょう。提訴する側も大まかな手順を押さえておくことで、どうやって訴訟を進めればいいか、自分でどんな準備ができるか理解できます。
この記事では、民事訴訟の流れや必要書類について解説していきます。民事訴訟のプロセスを理解したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>民事訴訟とは?

民事訴訟は、個人や企業間の権利や利益に関するトラブルを法的に解決する手続きです。裁判所が中立の立場で判断を下し、公正な解決を目指します。
民事訴訟は当事者が証拠を提出し、主張を展開することで進行し、裁判所が法律に基づいて判断します。当事者の自主性が尊重されるのが特徴で、訴訟の提起や和解など、重要な決定は当事者自身が行います。
刑事裁判・調停との違い
刑事裁判と調停は、民事訴訟と異なる解決アプローチを提供します。
- 刑事裁判:国家が犯罪を裁き、社会秩序の維持を目的とする
- 調停:裁判に進む前に当事者同士の合意を目指す手続き
民事訴訟では「当事者主義」が基本となり、裁判所は中立的な立場を維持しながら、当事者が証拠を提出し、主張を展開するという仕組みです。刑事裁判とは異なり、「疑わしきは被告人の利益に」という原則は適用されません。
また、民事訴訟の判決は勝訴・敗訴の二択だけではなく、和解という選択肢もあります。
民事訴訟の流れは?

民事訴訟の流れは、訴訟内容や規模によって多少異なるものの、基本的には以下のように進めます。
- 訴状を裁判所に提出する
- 被告への訴状の送付・送達
- 口頭弁論期日の指定・呼び出し
- 答弁書の受領
- 裁判所での審理
- 控訴・上告
それぞれの手順について解説していきます。
訴状を裁判所に提出する
訴状とは、原告が自らの請求を明確にし、裁判所に対して訴えを提起するための正式な書類です。適切に作成し、必要な添付書類とともに裁判所へ提出する必要があります。
訴状には、訴訟の基本情報として、以下を記載します。
- 原告の氏名や住所
- 被告の氏名や住所
- 請求の趣旨:裁判でどのような判決を求めるのかを示す部分
- 請求の原因
請求の趣旨には、「被告は原告に対し○○円を支払え」といった内容を記載します。請求の原因とは、その請求がなぜ正当であるのかを説明するもので、契約違反や損害賠償請求の根拠となる事実関係を詳細に記載します。
訴状を作成したら、訴訟を提起する管轄の裁判所を確認し、必要な訴訟費用を支払います。裁判所の管轄は被告の住所地を基準とすることが一般的ですが、契約に関する紛争であれば契約履行地が適用される場合もあります。
提出方法は、裁判所の受付窓口へ直接持参するか、郵送することが可能です。
被告への訴状の送付・送達
訴状が裁判所に受理されると、被告への送達が行われます。訴状の送達が完了しなければ、被告は訴訟の存在を知らないままとなり、裁判手続きが進められません。
送達の方法には、特別送達という裁判所からの書留郵便が一般的です。通常の郵便とは異なり、受取人である被告が直接受け取る必要があります。被告が自宅にいない場合は、同居する家族が代理で受け取ることも可能ですが、その際は必ず被告本人に伝えなければなりません。
送達がうまくいかない場合、公示送達という裁判所の掲示板や官報に一定期間告知を掲載し、被告が確認できる状態を作ることで送達が成立したとみなす送達が適用されます。
口頭弁論期日の指定・呼び出し
被告への訴状の送達が完了すると、裁判所が口頭弁論期日を指定し、原告と被告に対して出頭を求めます。口頭弁論は当事者双方が自らの主張を述べ、証拠を提示する機会となります。
裁判所は訴状の送達後に期日を決定し、当事者に対して呼び出し状を送付します。
訴状送達から初回の口頭弁論期日設定まで:1~2か月後
期間は裁判所の混雑状況や訴訟内容によって変動することもあります。呼び出し状には、出頭すべき日時や場所が記載されており、これに従って出廷します。
口頭弁論では当事者本人が出廷することが求められますが、弁護士を代理人として出席させることも可能です。
答弁書の受領
口頭弁論期日が指定されると、被告は裁判所に対して答弁書を提出する必要があります。答弁書は原告の訴えに対する被告の公式な回答であり、訴訟における主張の方向性を示す重要な書類です。
答弁書の提出期限:訴状の送達から30日以内(裁判所が指定する期限内)
答弁書には、原告の請求に対する基本的な態度が記載されます。請求を全面的に認める場合、答弁書にはその旨が明記され、裁判は早期に終結する可能性が高まります。
被告が請求を争う場合は、反論の根拠や主張を簡潔に記載し、裁判でどのように主張を展開するかの方向性を示します。例えば、契約の成立自体を否認する場合や、原告の請求額が過大であると主張する場合など、具体的な争点を明確にすることが求められます。
裁判所は、被告から提出された答弁書を原告に送付します。これにより、原告は被告の主張を把握し、次の手続きに向けた準備を進めることが可能です。
裁判所での審理
裁判所での審理は、口頭弁論を通じて原告と被告がそれぞれの主張を述べ、証拠を提出しながら裁判を進める手続きです。審理は1回で終了するものではなく、複数回にわたって行われ、争点の整理や証拠の精査が進められます。
初回の口頭弁論では、原告と被告の双方が裁判所に出廷・主張が可能です。原告は訴状に記載した請求の理由を説明し、被告は答弁書の内容に基づいて反論します。
審理が進むと、双方の主張を裏付ける証拠が提出されます。証拠には以下のようなものが有効であり、裁判所は証拠を検討しながら事実関係を明確にしていきます。
- 契約書
- 領収書
- メールのやり取り
- 証人尋問
- 本人尋問
審理の回数や期間は、事件の複雑さによって異なりますが、数か月から1年以上かかることもあります。審理が終了し、裁判官が事実関係を十分に確認すると、最終的な判決へと進みます。
控訴・上告
第一審の判決が下された後、その結果に不服がある場合、控訴や上告といった手続きを通じて上級裁判所に審理を求めることがあります。
控訴とは、地方裁判所や簡易裁判所の判決に対し、高等裁判所で再度審理を求める手続きです。控訴の期限は、判決の送達を受けた日から2週間以内と定められています。控訴審では第一審の判断が適切であったかを検討し、新たな証拠の提出や追加の主張が認められます。
控訴審の判決にも不服がある場合、最高裁判所への上告が可能です。上告の期限も控訴と同様に、判決の送達を受けた日から2週間以内です。ただし、原則として事実関係の再審理は行われず、法律の適用や解釈が正しかったかが審理の中心となります。
控訴や上告を行う場合、法律の専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することが重要です。特に上告は要件が厳しく、すべての事件で認められるわけではないため、専門家のサポートを得るのがおすすめです。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。民事訴訟について専門家に相談したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
訴訟提起から裁判までの期日

民事訴訟を提起してから裁判が進行するまでには、それぞれに一定の期間が必要となります。
| 手続き | 期間 |
| 裁判所による訴状の受理の決定 | 訴状提出から1~2週間程度 |
| 被告の訴状受け取り | 1~2週間程度 |
| 答弁書の提出期限 | 訴状送達から30日以内 |
| 口頭弁論の初回期日 | 訴状提出から約1~2か月後 |
裁判が始まるまでの期間は、原告・被告ともに主張や証拠の整理を行う準備期間となります。適切な準備を進めることで、裁判を有利に進めることができるため、各期日の確認と対応を怠らないことが重要です。
民事訴訟に必要となる書類一覧

民事訴訟において提出が必要となる書類は、以下の通りです。
- 訴状
- 収入印紙
- 契約書
- 領収書
- 請求書
- 送金記録
- 事故報告書(損害賠償請求の場合)
- 診断書(損害賠償請求の場合)
- 修理見積書(損害賠償請求の場合)
- スクリーンショットやメールの印刷
- 答弁書
- 準備書面
- 証人申請書
- 和解申立書
このように、民事訴訟では多くの書類が必要となります。損害賠償も請求する場合は、追加で書類を用意しなければいけません。
和解で解決するメリット

民事訴訟における和解は、判決を待たずに当事者双方が合意に至ることで、迅速に問題を解決できる方法です。長期化しがちな裁判を回避する方法として、和解は有効です。
和解による解決を目指すメリットは、以下の通りです。
- 時間と費用の節約:訴訟手続きを早期に終結できる
- 柔軟な対応が可能:当事者の合意に基づいて条件を決定できる
- 心理的負担の軽減:早期解決がプレッシャーからの解放に役立つ
長期化する訴訟を避けたい場合や、互いに納得できる形での解決を望む場合には、和解という選択肢を検討しましょう。
控訴や判決後の対応

民事訴訟で第一審の判決に不服がある場合は控訴を検討し、判決を受け入れる場合はその後の手続きを進めることになります。いずれの対応を選ぶにしても、判決後も手続きが必要です。
判決に納得できない場合、控訴することで上級裁判所に再審理を求めることができます。控訴の期限は、判決の送達を受けた日から2週間以内と厳格に定められているため、早急に対応を決定しなければなりません。
控訴審では、第一審の判断が正当であったかを審理し、新たな証拠や主張を追加することも可能です。ただし、控訴には費用や時間がかかるため、勝訴の見込みやリスクを慎重に検討しなければいけません。
判決を受け入れる場合は、その内容に従って履行手続きを進めます。敗訴した側は、判決で命じられた金銭の支払いや義務の履行を行わなければなりません。
強制執行とは?
強制執行とは、裁判所の判決に基づいて債務者の財産を差し押さえ、債権者が請求を実現できるようにする法的手続きです。
判決が確定すると、裁判所から強制執行に必要な書類である「執行文」が付与されます。この執行文を取得することで、正式に強制執行の申立てが可能となります。
強制執行の方法は、以下の通りです。
- 給与差押え:給料の一部を直接回収する
- 銀行口座の差押え:債務者の預金から直接回収
- 不動産の差押え・競売:売却代金から債権回収を図る
強制執行を申し立てる際は、裁判所に強制執行申立書を提出し、対象となる財産を特定する必要があります。ただし、生活維持に必要な最低限の財産は法律で保護されており、すべての財産を差し押さえることはできません。
民事訴訟にかかる費用

民事訴訟では、訴額に応じた収入印紙代と弁護士費用を負担することになります。
- 収入印紙代:訴額の約0.5%
- 弁護士費用:着手金が訴額の3~5%、成功報酬が獲得額の10~20%程度
ただし、弁護士によって料金体系が異なるため、事前に相談して確認しましょう。
訴訟にかかる費用は個々のケースによって異なるため、具体的な見積もりを把握するためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>まとめ
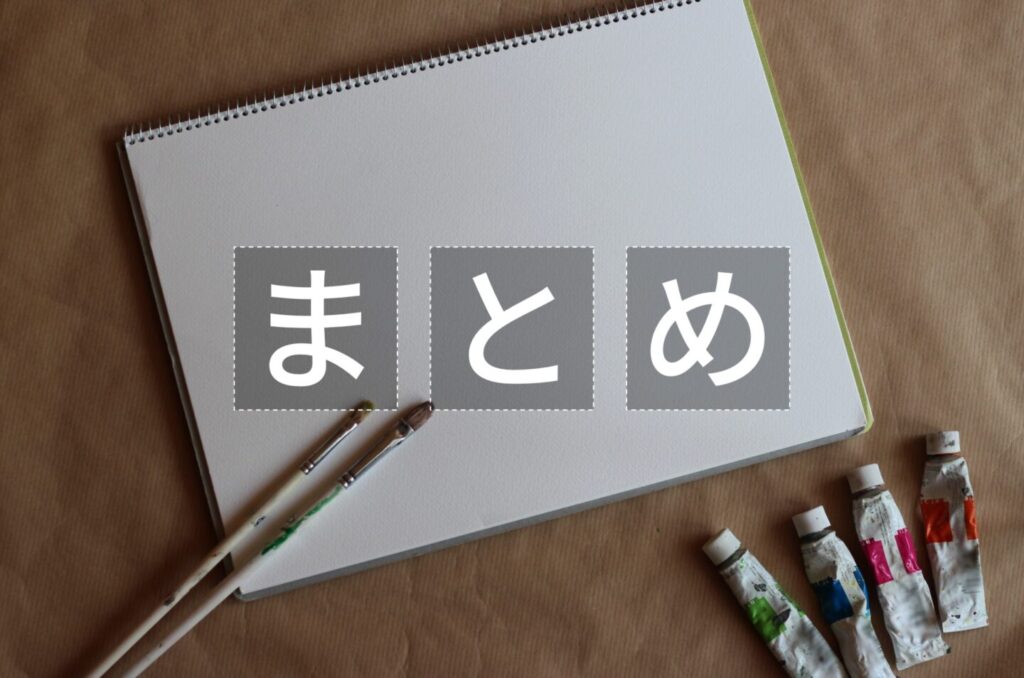
民事訴訟は、裁判所に訴状を提出することで開始します。そのため、まずは訴状を適切に作成する必要があります。
しかし、訴状の内容に不備があると裁判所が受理せず、民事訴訟を提訴することができません。また、受理後も法的手続きが必要になり、数か月にわたって対応する必要があります。そのため、民事訴訟では弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士費用はかかりますが、民事訴訟の専門性や自己負担とする場合の業務量・精神的疲労を考慮すると、弁護士に依頼が望ましいでしょう。信頼できる弁護士を見つけ、民事訴訟を進めてください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。民事訴訟を専門家に依頼したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












