民事訴訟とは?基本の流れや注意点、解決手段を徹底解説
訴訟・紛争解決
2025.02.26 ー 2025.03.06 更新
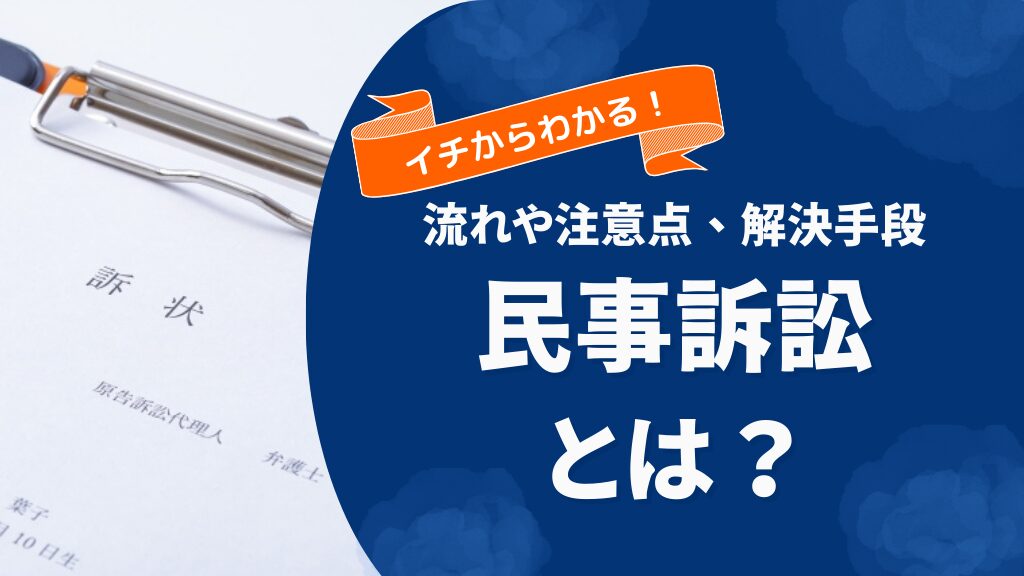
日常生活で、突如としてトラブルに巻き込まれた場合、法的な対策が必要です。借金問題や契約違反、名誉毀損など、話し合いでは解決できないケースについては、民事訴訟が効果的です。
しかし、「そもそも民事訴訟とは何か?」「自分のケースに該当するのか?」「どのように手続きを進めるのか?」といった疑問を抱える方も多いでしょう。民事訴訟はめったに経験することがないため、いざ当事者になると不安になる方もいるはずです。
本記事では、民事訴訟の基本から手続きの流れ、注意点、訴訟以外の解決手段について解説します。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>民事訴訟とは?

民事訴訟とは、個人や法人間のトラブルを解決するために裁判所を通じて行われる手続きです。刑事事件と異なり、国家が介入するのではなく、当事者同士の主張と証拠をもとに裁判所が判断を下します。
民事訴訟の対象となるトラブルは、以下の通りです。
- 金銭トラブル
- 契約違反
- 名誉毀損
- 損害賠償請求
民事訴訟を起こすには、訴えを提起する必要があります。訴状を作成し、相手方の住所地を管轄する裁判所に提出することで手続きが開始されます。裁判所は訴状を受理すると、被告に通知を送り、双方の主張や証拠をもとに審理を進めます。
民事訴訟の目的
民事訴訟の目的は、個人や法人間の法律上のトラブルを公平かつ適正に解決することにあります。裁判所が中立的な立場で双方の主張を聞き、証拠を精査し、法律に基づいて判断を下します。
これにより、損害賠償請求や契約履行の強制など、さまざまな民事上の紛争を解決し、社会の秩序維持と個人の権利保護を図る役割を果たします。
裁判所の判断には法的拘束力があり、当事者は判決内容に従う義務を負います。この仕組みによって、一方的な力関係に左右されない公正な解決が実現し、紛争の再発防止や社会の安定にも寄与します。
また、民事訴訟は必ずしも判決に至るとは限らず、途中で和解が成立するケースもあります。
民事訴訟の手続きの流れ

民事訴訟の手続きは、以下のような流れで進めることになります。
- 訴状の提出
- 被告による答弁書の提出と反論
- 裁判所での期日と審理の進行
- 判決の確定
それぞれのステップについて解説していきます。
訴状の提出
訴状とは、原告が裁判所に対して訴えを提起するために作成する正式な書類です。訴えの内容や請求の趣旨、事実関係、法律的根拠などを記載することで、民事訴訟を提訴することができます。
訴状の作成にあたっては、請求の根拠となる事実を整理し、どのような法律に基づいて主張するのかを明確にすることが求められます。訴状の提出先は、被告の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所となります。
訴状の提出には訴訟費用として収入印紙を貼付する必要があり、請求金額に応じて印紙代が異なります。また、裁判所から被告へ訴状を送付するための郵便切手も併せて準備します。
訴状が受理されると、裁判所が被告に訴状を送達し、訴訟手続きが正式に開始されます。
被告による答弁書の提出と反論
被告が訴状を受け取ると、通常30日以内に答弁書を裁判所に提出する必要があります。
答弁書とは、原告の主張に対する反論や被告の主張を示す書類であり、裁判の行方を左右する役割を果たします。被告は原告の請求を認めるか否かを明確にし、認めない場合はその理由を論理的に示すことが求められます。
答弁書には、事実関係の否認や抗弁の主張が含まれます。例えば、契約内容の解釈の相違や原告が請求する損害額の正当性を疑問視するなど、具体的な反論が記載されます。
裁判所での期日と審理の進行
民事訴訟における期日は、裁判の進行を決定する上で重要です。
口頭弁論期日では、原告と被告が裁判官の前で主張を述べ、それぞれの立場を明確にします。その後、争点整理手続きが行われ、当事者間の意見の食い違いを整理し、具体的な争点を特定します。
審理は裁判官の指揮のもとで進行し、当事者双方が主張や証拠を提出しながら、裁判所が事案を分析します。提出された証拠や主張を総合的に判断し、最終的な判決を下します。
判決の確定
民事訴訟の判決が下されても、それで訴訟が完全に終結するとは限りません。判決内容に不服がある場合、当事者は控訴や上告を通じて再審理を求めることが可能です。
控訴は第一審の判決を不服として高等裁判所に審理を求める手続きであり、上告は高等裁判所の判決に対して最高裁判所での審理を求めるものです。控訴や上告を行うには期限があり、通常は判決の言い渡しから2週間以内に申し立てる必要があります。期限内に手続きをしないと判決は確定し、法的拘束力を持ちます。
ただし、控訴や上告が認められるのは、法律の解釈に誤りがある場合や、重大な事実誤認がある場合といった一定の要件を満たした場合に限られます。
判決が確定すると、勝訴した側は強制執行の申し立てを行うことができます。これにより、裁判所の命令に基づいて財産差押えなどの措置が取られ、判決内容の履行が強制されます。
民事訴訟の準備で必要になるもの
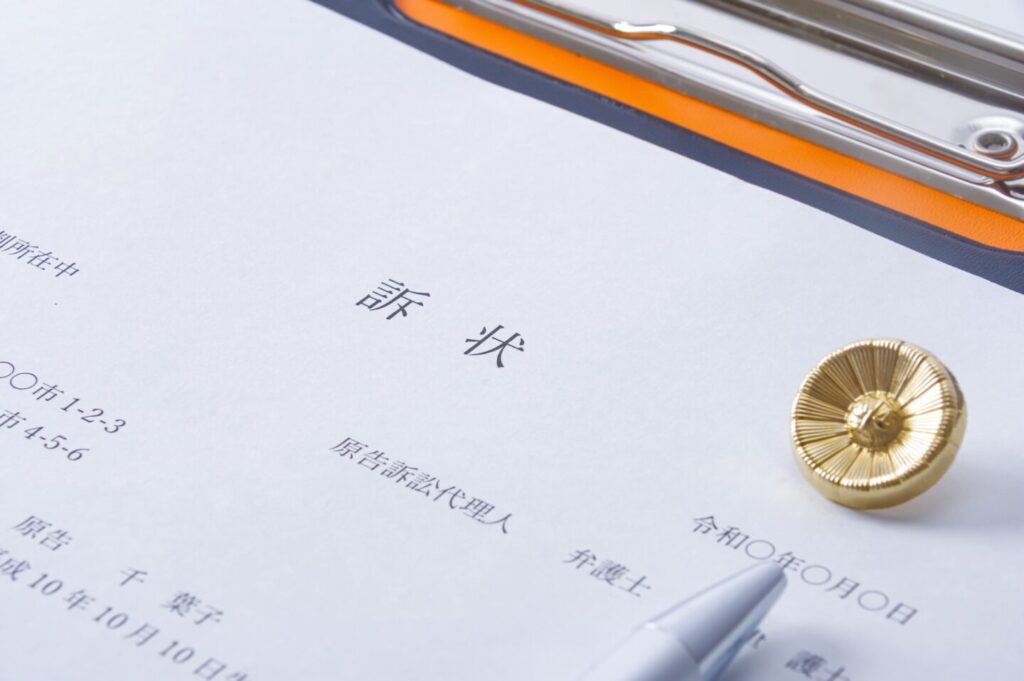
民事訴訟を進めるにあたって、公的書類や関連資料、費用などを用意しなければいけません。訴訟の内容によって準備するものは異なるものの、以下のようなものはどの訴訟でも共通して用意が必要です。
- 訴えの証拠となる文書や物的証拠
- 訴状
- 答弁書や陳述書
それぞれの準備書類について解説していきます。
訴えの証拠となる文書や物的証拠
民事訴訟において、訴えの証拠となる文書や物的証拠は、裁判の結果を左右する重要な要素です。裁判所は、当事者の主張を裏付ける証拠の有無によって判断を下すため、証拠の準備は訴訟の成功に直結すると言えるでしょう。
証拠として認められる文書は、以下があります。
- 契約書
- 領収書
- 請求書
- メールのやり取り
- 日記
- 録音データ
名誉毀損の訴えを提起する場合は、誹謗中傷の書き込みが残るSNSのスクリーンショットなどが有効です。
物的証拠として有効なのは、以下の通りです。
- 損害を証明するための写真や動画
- 破損した物品
- 診断書
例えば交通事故の裁判では、事故現場の写真や修理費用の見積書が証拠として用いられます。これらの証拠は、事実を客観的に示すものとして裁判で重視されます。
訴状
訴状は、裁判所に対して正式に訴えを提起するための書類であり、訴訟の目的や請求内容を記載します。内容が不十分であったり要件を満たしていない場合、裁判所に受理されない可能性があります。
訴状には、原告と被告の氏名・住所を明記し、具体的な請求内容を記載します。「被告は原告に対し○○円を支払え」といった形で請求の趣旨を明確にし、その請求の根拠となる事実を時系列で整理しながら説明します。
また、法律的な主張も加え、請求が正当である理由を示すことも必要です。
訴状の内容が法的に正当であるかを判断するのは、専門的が知識が求められます。民事訴訟を優位に進めたいのであれば、弁護士に訴状の作成・確認を依頼しましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
下記のサイトから弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>答弁書や陳述書
答弁書は、被告が原告の訴えに対して反論するための書類です。訴状に記載された請求内容を認めるか否かを明確にし、認めない場合はその理由を記載します。また、契約の解釈の違いや請求金額の妥当性など、具体的な争点について主張し、必要に応じて証拠を提示します。
答弁書は通常、訴状を受け取ってから30日以内に裁判所へ提出しなければいけません。適切な反論を行わないと、原告の主張を認めたとみなされる可能性があります。
一方、陳述書は当事者や関係者が自らの経験や事実を記載する文書であり、証拠の一つとして扱われます。例えば、契約の経緯や金銭の貸し借りに関する詳細な事情を説明する際に用いられます。
陳述書には証拠となる資料を添付し、事実関係を具体的に記載します。裁判では書面だけでなく口頭での主張も行いますが、陳述書があれば主張の一貫性を保ちやすくなります。
民事訴訟と民事調停の違い

民事訴訟と民事調停は、いずれも個人同士の間におけるの紛争を解決するための手続きですが、進め方や特徴に違いがあります。
民事訴訟は裁判所が判決を下し、法的拘束力を持つため、強制力のある解決手段として利用されます。一方、民事調停は当事者同士の話し合いを重視し、調停委員が間に入って合意形成をサポートします。
どちらの手続きを選ぶべきかは、紛争の内容や当事者間の関係性を考慮することが重要です。権利関係を明確にしたい場合や、強制的な解決が必要な場合は民事訴訟が最適です。当事者同士が歩み寄りやすく、人間関係の維持を重視する場合は、民事調停が適しているでしょう。
最適な解決手段は個々の状況によって異なるため、一概にどちらが優れているとは言えません。紛争の解決を目指す際には、専門家と相談しながら、どの方法が適しているかを慎重に判断することが必要になります。
民事訴訟を有利に進めるための注意点

民事訴訟を提起する以上、勝訴を目指すために優位に進めるべきでしょう。その際は、以下の点に注意してください。
- 主張を裏付ける証拠を徹底的に準備する
- 人証や尋問の準備も進める
- 弁護士に相談する
それぞれの注意点について解説していきます。
主張を裏付ける証拠を徹底的に準備する
民事訴訟では、主張を裏付ける証拠の準備が重要です。証拠があるかないかで、裁判の優位性は大きく変わります。
証拠収集の際は、自身に有利な証拠だけでなく、相手の主張を覆すための反証を準備することが重要です。ただし、違法な手段で入手した証拠は採用されない可能性があるため、証拠収集の際には法的な規制に注意しましょう。
証拠の準備には時間と労力がかかるものの、この過程を通じて自身の主張の強みや弱点を把握し、訴訟戦略を見直す機会にもなります。
人証や尋問の準備も進める
人証とは、証人や当事者本人の証言を指し、裁判における重要な証拠として扱われます。契約の経緯や金銭の貸し借り、損害の発生状況など、書面だけでは証明しきれない事実を補強する役割を果たします。
証人を選定する際には、当該事件の経緯を直接知っている人物を選ぶことが重要です。証人の証言が客観的で一貫性があるほど、裁判官の心証を良くし、訴訟を有利に進めることができます。
尋問の準備としては、事前に証人と打ち合わせを行い、証言の要点を整理することが大切です。適切な質問を用意し、証人が冷静に事実を伝えられるようにサポートします。
また、相手側の証人尋問にも備える必要があります。相手の証言内容を想定し、反対尋問でどのように反論するか戦略を立てておくと、裁判を有利に進められるでしょう。
弁護士に相談する
民事訴訟は法律や裁判手続きに関する専門知識が必要なため、個人で対応すると主張や証拠の提示ができず、不利な結果を招く可能性があります。そこで、弁護士に相談することをおすすめします。
法律の専門家である弁護士は、訴訟の進め方や証拠の整理、法律的な主張の組み立てなどをサポートします。訴訟提起の過程で弁護士が関与することで、早期解決や優位な判決が目指しやすくなります。
弁護士費用は発生しますが、結果的に訴訟での不利益を防ぎ、最適な解決を得ることが可能です。訴訟を検討する際は、早い段階で弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けましょう。
まとめ
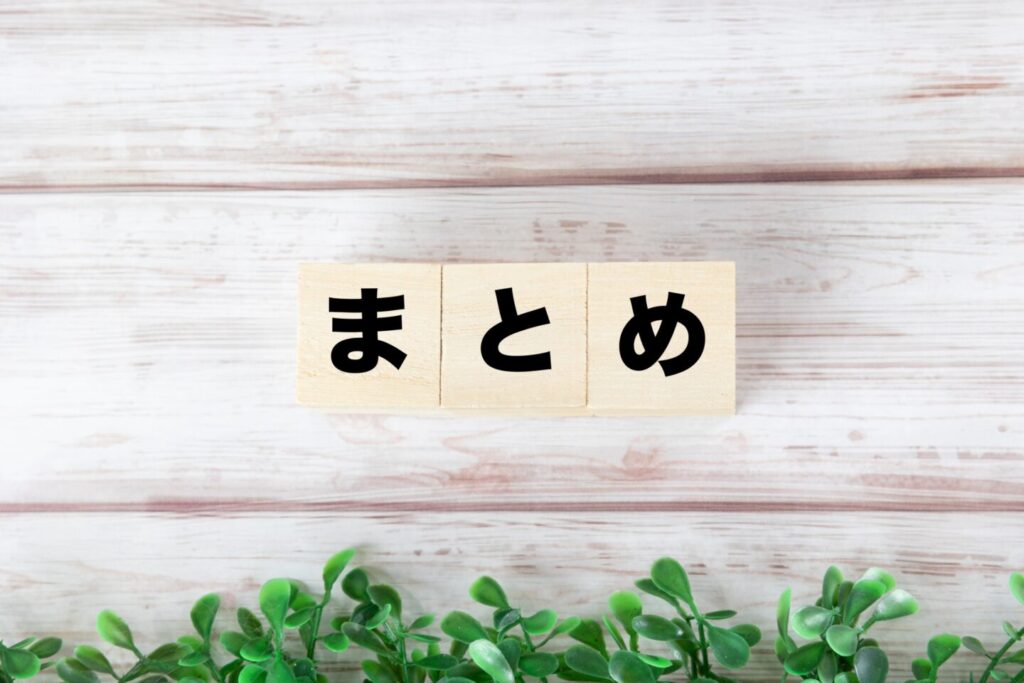
トラブルに対して法的措置を検討する場合、民事訴訟が一般的な対策となります。しかし、民事訴訟では裁判の手続きや書類作成などが必要になるため、専門的な知識がないと適切に進めるのは難しいでしょう。
そのため、弁護士に依頼してしまうのがおすすめです。多少の費用はかかりますが、それによって弁護士の専門性や手続きの負担を軽減できるということであれば、必要な投資と言えます。
弁護士と協力して、民事訴訟を有利に進めましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。民事訴訟について専門家に相談したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












