民事裁判・民事訴訟の進め方と弁護士の役割とは?初めての方向け完全ガイド
訴訟・紛争解決
2025.02.25 ー 2025.03.05 更新
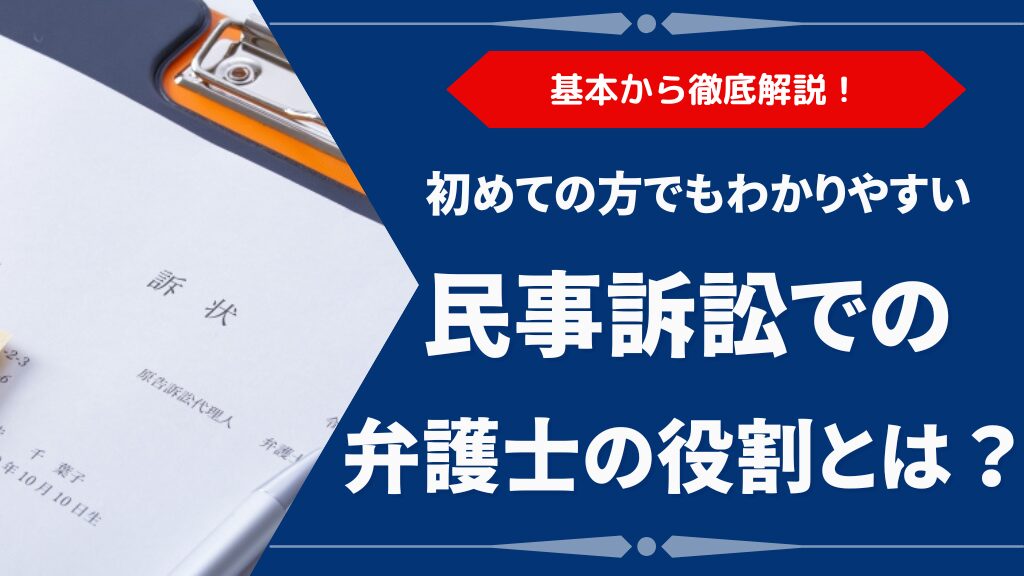
民事訴訟を検討しているものの、「弁護士に依頼すべきか?」「費用はどのくらいかかるのか?」「自分のケースは裁判になるのか?」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
契約違反や金銭トラブル、消費者トラブル、家庭内の問題など、民事訴訟の対象となるケースはさまざまです。しかし、訴訟は手続きが複雑で、弁護士なしで進めるには大きなリスクが伴います。
本記事では、民事訴訟における弁護士の役割や、依頼するメリット・デメリット、費用相場、手続きの流れなどを詳しく解説します。また、「弁護士なしで裁判を進められるのか?」といった疑問にも答え、訴訟を回避するための示談やADR(裁判外紛争解決手続き)についても紹介します。
さらに、弁護士を選ぶ際のポイントや、費用を抑える方法、無料相談を活用するコツなど、実際に弁護士を探す際に役立つ情報も提供します。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>民事訴訟の基本と弁護士が必要なケースを解説

民事訴訟を弁護士に依頼するべき状況は、案件の複雑さや重要性によって異なります。
弁護士への依頼を検討する際は、事案の重要性や自身の時間的・精神的負担、さらには費用対効果を総合的に判断することが大切です。
ただし、弁護士に依頼するタイミングは、明確な基準がないため、個々の状況に応じて慎重に判断する必要があります。
民事訴訟の基本的な仕組み
民事訴訟は、個人や法人間の権利や義務をめぐる紛争を解決するための法的手続きです。裁判所が中立的な立場から判断を下し、当事者間の争いを解決します。
- 民事訴訟の基本的な流れ:訴状の提出から始まり、被告の答弁、証拠調べ、弁論、判決という段階を経ます。
- 民事訴訟の特徴:当事者主義が挙げられます。これは、原告と被告が主体的に主張や立証を行い、裁判所はそれらを基に判断するという原則です。また、訴訟物の処分権主義も重要で、当事者が訴訟の対象や範囲を決定できます。
- 民事訴訟で可能な請求:損害賠償請求や契約履行の強制、所有権の確認などの請求が可能です。ただし、訴訟には一定の要件があり、当事者適格や訴えの利益などが必要です。また、訴訟費用や時間的コストも考慮すべき点です。
民事訴訟の進行には専門的な法律知識が必要で、複雑な事案では弁護士の助言が有効です。
民事訴訟で弁護士が必要になる状況
複雑な法律問題や高額な賠償金が絡む場合、専門知識を持つ弁護士の助言が不可欠です。例えば、医療過誤や製造物責任、知的財産権侵害などの専門性の高い訴訟では、弁護士の支援が重要です。
また、離婚や相続など、感情的要素が強く絡む家事事件でも、冷静な判断と法的助言を提供する弁護士の存在が有効です。
企業間の契約紛争や不動産トラブルなど、経済的利害が大きい案件においても、弁護士の専門的な交渉力が求められます。さらに、名誉毀損やプライバシー侵害など、個人の権利を守る必要がある場合も、弁護士の支援が重要です。
一方で、少額訴訟や簡易な交通事故の示談など、比較的単純な案件では、必ずしも弁護士が必要とは限りません。しかし、訴訟の進行に不安がある場合や、相手方が弁護士を立てている場合は、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士なしで対応できるケース
民事訴訟において、少額訴訟制度を利用する場合は、比較的簡単な手続きで自ら訴訟を進めることが可能です。この制度は60万円以下の金銭トラブルを対象としており、一回の口頭弁論で審理が終了するため、法律の専門知識がなくても対応しやすいのが特徴です。
また、内容証明郵便の作成や送付など、裁判外での交渉段階であれば、自力で対応できることも多いでしょう。ただし、相手方との関係性や交渉の難易度によっては、弁護士の助言を得ることが望ましい場合もあります。
さらに、調停や和解などの代替的紛争解決手段を選択する際も、当事者同士で話し合いを進められる可能性があります。ただし、これらの方法でも、複雑な法律問題が絡む場合や、相手方との力関係に大きな差がある場合は、弁護士のサポートを検討した方が良いかもしれません。
民事訴訟を弁護士に依頼するメリットとデメリット
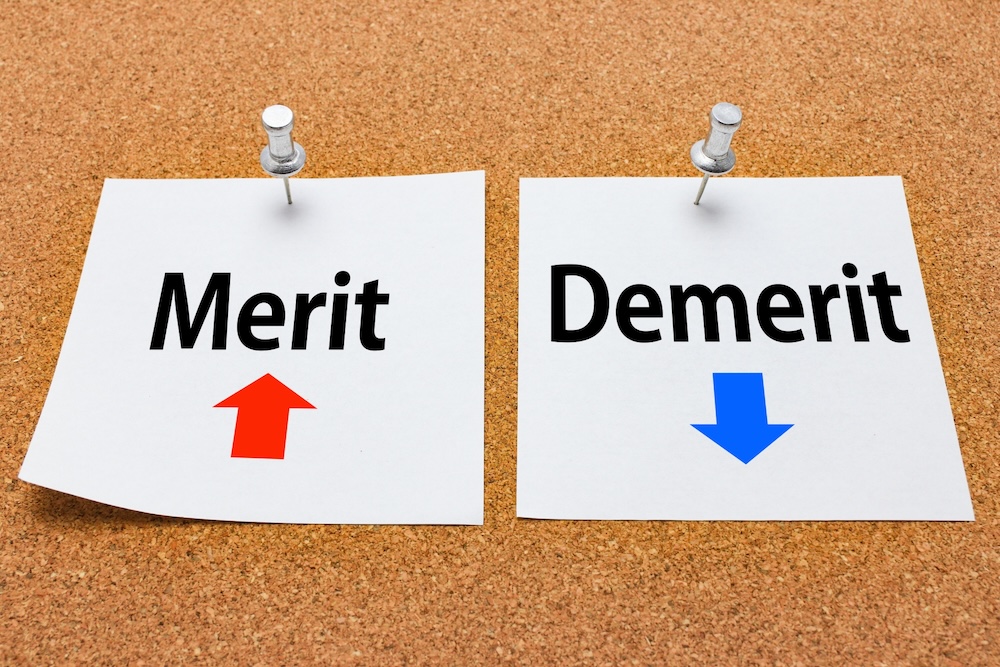
民事訴訟を弁護士に依頼することには、メリットとデメリットが存在します。以下で詳しく説明していきます。
民事訴訟を弁護士に依頼するメリット(時間短縮・手続き代行など)
民事訴訟を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 時間の大幅な短縮:法律の専門家である弁護士は、複雑な手続きを効率的に進められるため、依頼者の負担が軽減されます。また、裁判所への書類提出や相手方とのやり取りなど、煩雑な手続きを代行してくれるのも大きなメリットです。
- 訴訟が有利になる:弁護士は法的な観点から事案を分析し、最適な戦略を立てられます。これにより、勝訴の可能性が高まるだけでなく、和解交渉などでも有利な条件を引き出せる可能性があります。
- 精神的な負担の軽減:訴訟は多くの人にとってストレスフルな経験ですが、弁護士に依頼することで、専門家のサポートを得られる安心感があります。
- 効果的な主張:弁護士は法廷での弁論や尋問などにも慣れているため、依頼者の主張をより効果的に裁判所に伝えられます。これは、自分で対応する場合には難しい部分かもしれません。
弁護士に依頼するデメリット(費用・相性問題など)
弁護士に民事訴訟を依頼する際には、メリットだけでなくデメリットも考慮する必要があります。
- 費用面:弁護士費用は相談料、着手金、成功報酬など複数の要素で構成され、事案の複雑さや訴訟の長期化によっては高額になる
- 弁護士との相性:コミュニケーションがうまくいかない場合、訴訟の進行に支障をきたす
- 法的知識や経験を得る機会が失われる:自身で訴訟に関わる機会の減少
- 依頼者の意向が十分に反映されない
- 弁護士の判断と依頼者の希望にズレが生じる
自己対応するべきか弁護士へ依頼するべきかは事案や状況により異なる民事訴訟を自分で対応するか弁護士に依頼するかは、状況によって判断が分かれる重要な選択です。
- 自己対応の場合:費用面での負担は軽減されますが、法律知識や手続きの複雑さに直面する可能性があります。
- 弁護士に依頼する場合:専門的なアドバイスや手続き代行が得られますが、費用面での負担が増えます。
訴訟の内容や複雑さ、争点の重要性、自身の法律知識や時間的余裕などを総合的に考慮する必要があります。また、自己対応の場合でも、初期段階で弁護士に相談し、方針や注意点についてアドバイスを受けることで、より効果的に訴訟を進められる可能性があります。
自己対応と弁護士依頼のどちらが適しているかは、個々の事案や個人の状況によって異なります。重要なのは、自分の置かれた状況を冷静に分析し、最適な選択をすることです。
民事訴訟の費用はどのくらい?弁護士費用の内訳を解説

民事訴訟にかかる費用は、案件の複雑さや争点の数によって大きく変動します。す。以下で、弁護士費用の内訳、民事訴訟にかかるその他の費用、費用相場の目安を解説します。
弁護士費用の内訳
弁護士費用は主に相談料、着手金、成功報酬の3種類に分類されます。
- 相談料:初回面談時に発生し、案件の概要を把握するための費用です。
- 着手金:依頼を受けた時点で支払う前払い金で、訴訟の準備や書類作成などの初期作業に充てられます。
- 成功報酬:和解や判決などの結果に応じて支払う報酬で、弁護士の努力に対する対価となります。
これらの費用体系は弁護士によって異なる場合があり、一般的に着手金と成功報酬を組み合わせた方式が多く採用されています。ただし、近年では固定報酬制や時間制報酬など、新しい料金体系を導入する事務所も増えつつあります。
費用の具体的な金額は案件の複雑さや争点の数、訴訟額などによって大きく変動します。そのため、依頼前に弁護士と十分に相談し、費用の見積もりや支払い方法について確認することが重要です。
また、一部の弁護士事務所では分割払いや後払いなどの柔軟な支払い方法を提供している場合もあります。
民事訴訟にかかるその他の費用(訴訟費用・実費など)
民事訴訟では、弁護士費用以外にも以下の費用が発生します。
- 印紙代
- 訴訟を提起する際に必要。訴訟の目的の価額に応じて変動し、高額になることも。
- 証拠の収集や提出にかかる費用
- 証人の旅費や日当
- 鑑定が必要な場合は鑑定費用
- 裁判所に提出する書類の作成費用
- 相手方への送達費用
これらの実費は案件によって大きく異なるため、事前に弁護士と相談して概算を把握しておくことが重要です。
また、訴訟が長期化すれば、その分費用も増加していきます。和解や調停などの代替手段を検討することで、費用を抑えられる可能性もあります。ただし、これらの方法が常に最適とは限らず、事案に応じた判断が求められます。
結果的に、民事訴訟にかかる総費用は予想以上に高額になることがあります。そのため、訴訟を起こす前に、費用対効果を十分に検討することが賢明です。
費用相場の目安
民事訴訟の弁護士費用は案件の複雑さや争点によって大きく異なりますが、一般的な相場感を把握しておくことは重要です。
着手金は50万円から100万円程度が目安となり、成功報酬は勝訴した場合の経済的利益の10%から20%程度が多いでしょう。例えば、1000万円の損害賠償請求訴訟では、着手金が80万円、成功報酬が150万円といったケースが考えられます。
ただし、これはあくまで一例であり、実際の費用は事案ごとに変動します。交通事故の示談交渉のような比較的単純な案件では、着手金30万円程度で済むこともあります。一方、複雑な企業間紛争では、着手金が200万円を超えることも珍しくありません。
また、弁護士によって料金体系が異なる場合もあるため、複数の弁護士に相談して見積もりを比較検討することをおすすめします。中には、着手金を抑えて成功報酬を高めに設定する弁護士もいます。依頼者の経済状況に応じて、柔軟な支払い方法を提案してくれる場合もあるでしょう。
弁護士なしで民事訴訟は可能だがリスクと注意点の理解が必要

民事訴訟を弁護士なしで進めることは法律上可能ですが、リスクと注意点を十分に理解する必要があります。
自己代理人として訴訟を進める場合、法律の専門知識や手続きの複雑さに直面することになります。裁判所への書類提出や証拠の準備、相手方とのやり取りなど、すべてを自分で行わなければなりません。
これには多大な時間と労力がかかり、ミスをすると不利な結果を招く可能性があります。また、法律の解釈や戦略的な対応が求められる場面では、専門家の助言がないことで不利な立場に立たされることもあるでしょう。
以下で、弁護士なしで民事訴訟を進める際の方法と手続きの流れとリスクを解説します。
弁護士なしで民事訴訟を進める際の流れ
民事訴訟を弁護士なしで進めることは可能ですが、手続きの複雑さや法律知識の必要性から、一般的には推奨されません。しかし、少額訴訟や簡易な事案では自己対応も選択肢となります。以下の流れを理解しておきましょう。
- 訴状の作成:請求の趣旨と原因を明確に記載し、関連する証拠を添付する。
- 訴状を裁判所へ提出
- 相手方への送達
- 口頭弁論:期日に裁判所へ出頭し、主張や反論を行う。
- 証拠調べ:書証の提出や証人尋問などを行う。
- 判決
これらの過程で法律用語や手続き規則の理解が求められるため、事前に十分な準備が不可欠です。また、相手方とのやり取りや和解交渉なども自ら行う必要があります。
弁護士なしで訴訟を進めるには相当な時間と労力がかかりますが、費用面では節約できる可能性があります。ただし、複雑な事案や高額な請求の場合は、専門家のサポートを検討すべきでしょう。
弁護士なしで民事訴訟を進める際のリスク(法律知識・手続きの負担など)
弁護士なしで民事訴訟に臨むことは、法的な専門知識が不足している一般人にとって大きなリスクを伴います。
- 法律用語や手続きの複雑さに直面し、適切な主張や証拠の提出が困難になる
- 相手方の弁護士が専門的な戦略を駆使してくる場合、対応に苦慮する
- 訴訟の進行に伴う膨大な書類作成や期限管理など、時間的・精神的な負担
- 裁判所からの指示を正確に理解し、適切に対応することは困難
- 誤った解釈や対応により、自身の主張が十分に伝わらず、不利な判決につながる
- 和解交渉の場面では、経験不足から不利な条件を受け入れてしまう
民事訴訟を依頼する弁護士の選び方と相談の流れ

民事訴訟を弁護士に依頼する際、適切な専門家を選ぶことが重要です。以下で、弁護士選びのポイントと相談の流れ、相談時に準備すべき資料を説明します。
弁護士を選ぶ際には専門分野と実績を重視する
弁護士を選ぶ際には、民事訴訟の内容に応じて、その分野に精通した弁護士を探すことで、より適切な対応が期待できます。
例えば、不動産関連の訴訟であれば不動産法に詳しい弁護士、労働問題であれば労働法に強い弁護士を選ぶといった具合です。
実績については、過去の類似案件の取り扱い数や勝訴率などを確認するとよいでしょう。ただし、勝訴率だけでなく、依頼者の満足度も重要な指標です。また、弁護士の経験年数も考慮に入れると良いかもしれません。
さらに、弁護士の人柄や対応の丁寧さも選択の基準になります。初回相談時の印象や説明の分かりやすさなども、長期的な信頼関係を築く上で大切です。費用面については、着手金や成功報酬の料率を比較し、自身の予算に見合うかどうかを検討しましょう。
最後に、所属する法律事務所の規模や評判も考慮に入れると良いかもしれません。大手事務所か個人事務所かによって、サポート体制や対応の柔軟性に違いが出る可能性があります。
弁護士相談の具体的な流れ
弁護士への相談は、多くの方にとって人生で初めての経験かもしれません。一般的に、無料相談から始まり、その後本格的な依頼へと進んでいきます。
まず、電話やメールで予約を取り、初回相談の日時を決めます。この際、簡単な状況説明を求められることもあります。
初回相談では、事案の詳細を弁護士に説明し、法的な見解や今後の方針について助言を受けます。多くの場合、30分から1時間程度で終わりますが、複雑な案件では 長時間 になることもあります。相談後、依頼を決めた場合は委任契約を結びます。
契約時には、着手金や報酬について話し合い、合意します。依頼後は、弁護士が主導で訴訟準備を進めますが、適宜連絡を取り合い、方針の確認や新たな情報の共有を行います。このプロセスは案件によって異なる場合があり、必ずしも一律ではありません。
相談時に準備すべき資料とチェックポイント
弁護士への相談を効果的に進めるためには、適切な準備が不可欠です。以下の資料を準備しておきましょう。
- 事案に関連する書類や証拠:契約書、領収書、メールのやり取りなど、争点に関わる資料を時系列で整理する
- 事実関係を簡潔にまとめた経緯書:弁護士との相談がスムーズに進めるため
相談時のチェックポイントは下記を参照してください。
- 自分の主張や希望する解決策を明確にする
- 相手方との交渉経緯や、これまでの対応状況を伝える
- 訴訟にかかる費用や期間についての質問を準備する
- 弁護士との相性をチェック
- 初回相談時に、弁護士の経験や専門分野、対応方針などを確認し、自分の期待に沿うかどうかを見極めることが大切です。
- 相談時には率直に疑問や不安を伝える
- 弁護士との信頼関係を築くためにも、オープンなコミュニケーションを心がけましょう。
これらの準備と心構えがあれば、民事訴訟の相談をより効果的に進められるでしょう。
弁護士費用を抑えるには?法テラスや補助制度を活用しよう

民事訴訟の弁護士費用を抑えるには、法テラスや各種補助制度の活用が効果的です。さらに、弁護士選びの際にも工夫の余地があります。以下で詳しく見ていきましょう。
法テラスを利用すると民事訴訟がスムーズになる
法テラスは、経済的に困難な状況にある人々に対して法的支援を提供する公的な機関です。民事訴訟を進める上で、法テラスを利用することで様々なメリットが得られます。
まず、無料の法律相談を受けられるため、事前に専門家のアドバイスを得られます。また、収入や資産が一定基準以下の場合、弁護士費用の立替えや分割払いなどの支援を受けられる可能性があります。これにより、経済的な負担を軽減しつつ、必要な法的サポートを得られます。
ただし、法テラスの利用には条件があります。収入や資産が一定基準以下であることが求められ、また事案の内容によっては支援対象外となる場合もあります。さらに、立替金の返済が必要な場合もあるため、長期的な視点での検討が必要です。
法テラスを利用することで、専門的な法的支援を受けやすくなり、民事訴訟の進行をスムーズにできます。ただし、個々の状況や事案の内容によって適用条件が異なるため、詳細な確認が必要です。
費用補助制度の利用は経済的負担を軽減し法的支援を受ける機会が広がる
民事訴訟の費用負担を軽減するための補助制度は、経済的な理由で法的支援を受けられない人々にとって重要な選択肢です。
- 法律扶助制度:日本司法支援センター(法テラス)が運営する制度で、一定の資力基準を満たす人に対して弁護士費用などを立て替えます。この制度を利用するには、法テラスに相談し、審査を受ける必要があります。
- 自治体独自の支援制度:例えば、東京都では「法律相談」や「弁護士費用立替制度」を設けており、都民が利用できます。ただし、自治体によって制度の内容や対象者が異なるため、居住地の自治体に確認することが重要です。
これらの制度を活用する際は、事前に詳細な情報収集が必要です。資力基準や対象となる事案の種類、申請手続きなどを確認し、自身の状況に適した制度を選択することが大切です。また、制度によっては利用後の返済義務があるケースもあるため、注意が必要です。
補助制度の利用は、経済的負担を軽減するだけでなく、適切な法的支援を受ける機会を広げることにもつながります。しかし、制度の利用には一定の条件や手続きが必要なため、早めの相談と準備が重要です。
費用を抑えるための弁護士選びのコツ
弁護士費用を抑えるためには、以下の効果的な方法があります。
- 複数の弁護士に相談し、料金体系を比較する
- 初回相談が無料の事務所を探す
- 実績と評判を確認する
- 経験豊富な弁護士が必ずしも高額というわけではない
- 依頼内容を明確にし、必要最小限のサービスに絞る
- 柔軟な支払い方法を相談する
- 地域の弁護士会が提供する無料相談サービスを利用する
- 加入している保険の内容を確認する
- 弁護士費用の一部を保険でカバーできる場合もある
ただし、費用だけでなく、相性や信頼関係も重要な要素です。安さを追求するあまり、質の低いサービスを選んでしまうリスクにも注意が必要です。総合的に判断し、最適な弁護士を選ぶことが大切です。
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務救済がおすすめ
法務救済は、契約書のリーガルチェックから労務、国際取引時の法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争など、企業法務に精通する専門家を相談内容に応じて、検索・相談できるポータルサイトです。
全国の弁護士事務所を「相談内容」や「エリア」から簡単に検索・相談できます。なお、お問い合わせは無料で、当サイトから費用を頂戴することはありません。民事訴訟について検討されている方は、ぜひ法務救済をご活用ください。
法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












