顧問弁護士の費用相場は?中小企業向けの契約形態や料金プランを徹底解説
企業法務
2025.04.08 ー 2025.04.08 更新
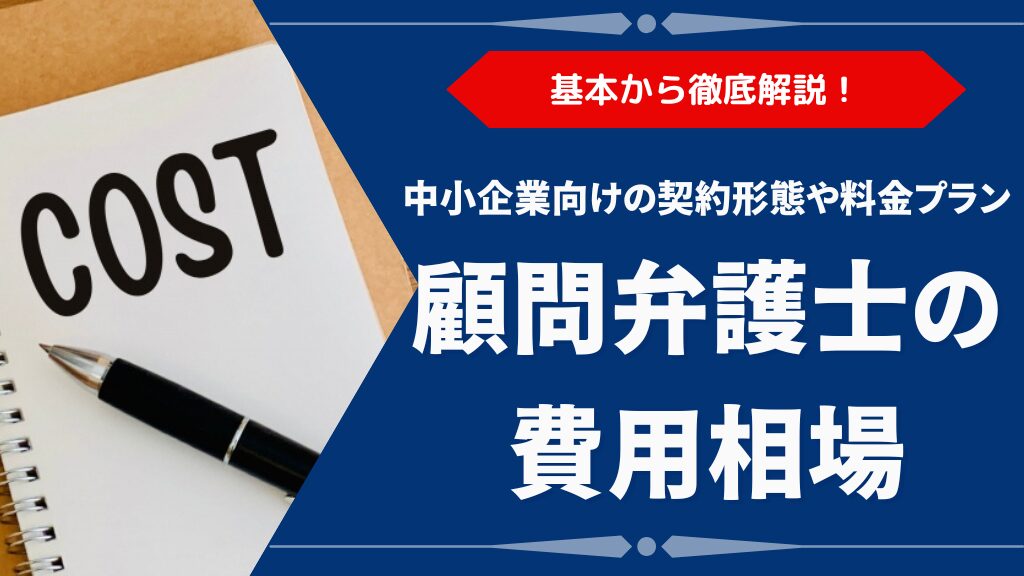
中小企業の経営者や法務担当者にとって、法的リスクの防止は経営における重要な課題として位置付けられます。専門的かつ有効な対策として、顧問弁護士がありますが、自社の費用負担は常に懸念されるでしょう。
顧問弁護士の費用は、以下のような契約形態によって異なり、企業のニーズに合わせて選ぶことが可能です。
- 定額制
- 時間制
- 成功報酬型
特に中小企業の場合、月額3万円~10万円程度が相場とされていますが、実際にどのようなサービスが含まれるのか、費用対効果は見合うのかを事前に確認しなければいけません。
この記事では、顧問弁護士の料金相場や中小企業向けの契約プランについて解説します。顧問弁護士の導入を検討している方や、現在の契約を見直したい方はぜひ参考にしてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>中小企業が顧問弁護士に依頼する必要性

中小企業にとって、顧問弁護士を活用することは経営の安定と成長を支える有効な手段と言えます。法務部門を持たない場合、以下のような日常的に発生する法的課題に対応する必要があります。
- 契約書のチェック
- 労務管理
- 取引先とのトラブル対応
トラブルが表面化してから弁護士に相談する場合、対応が後手に回り、時間やコストが大きく膨らむおそれがあります。一方、顧問弁護士を契約しておけば、初期段階からの相談が可能となり、法的リスクの予防や早期解決につながります。
企業規模に応じて無理のない料金プランを選べば、コストを抑えつつ質の高い法務サポートを受けることができます。このように、中小企業にとっても顧問弁護士によるサポートは必須と言えるでしょう。
顧問契約を結ぶメリット
中小企業が顧問弁護士と契約を結ぶことには、多くのメリットがあります。
最大の利点は、企業活動における法的リスクを未然に防ぎ、迅速な対応が可能になることです。たとえば、契約書の内容確認や法律相談を日常的に行えることで、経営判断のスピードと正確性が向上します。
また、頻繁に行われる法改正への対応や、労務トラブルへの助言も顧問弁護士が担う役割の一つです。企業の業務内容や体制を深く理解している弁護士が対応してくれることは、大きな安心材料となります。
費用はかかるものの、それ以上のサービスを提供してくれるため、メリットは非常に大きいと言えるでしょう。
中小企業向けの顧問弁護士の費用相場
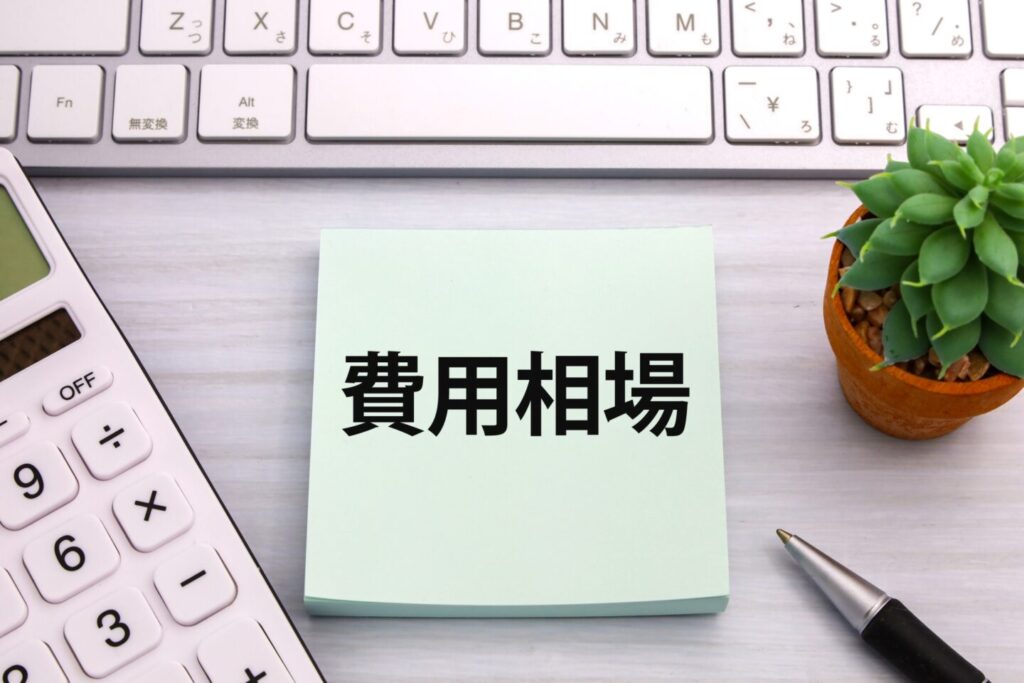
中小企業が顧問弁護士と契約する際の費用相場は、月額3万円〜10万円程度が相場とされています。依頼するタスクが多ければ、費用も高くなります。
企業の規模や業種によって必要な法務サポートは異なるため、自社のリスクや業務内容に適した契約プランを選定することが重要です。コストを抑えたい場合でも、最低限の相談体制を整えることで法的リスクの回避につながります。
以下では、料金ごとのサービス内容について解説していきます。
費用ごとのサービス内容
中小企業向けの顧問弁護士によるサービスの内容は、料金に応じて違いがあります。高額になるほどサービスも手厚くなり、自社で対応する業務が少なくなります。
料金ごとのサービス内容は、以下の通りです。
- 月額3万円のプラン:簡易な法律相談、契約書の確認、電話・メールでの対応
- 月額5万円のプラン:訪問による面談対応、社内規程の整備、法改正に関する情報提供
- 月額10万円のプラン:取引先との交渉、訴訟前の対応、労務トラブルへの個別助言
料金が高くなると、より専門的なサービスを提供してくれます。企業ごとの業種やリスクの程度に応じて、必要なサービス内容を明確にし、料金に見合った顧問契約を選定することが重要です。
顧問弁護士の費用が変動はどのように決まる?

顧問弁護士の費用は一律ではなく、複数の要因によって変動します。弁護士の対応する業務が専門的になれば、それ相応の金額になるということです。
費用を変動させる要因として、以下のようなものが挙げられます。
- 契約内容
- 相談の頻度
- 対応する業務量
- 企業の規模・業種
- 弁護士の専門性
最も大きな要因となるのは、相談の頻度や業務量です。月に数回の相談に留まる場合と、頻繁な契約書の確認や交渉対応を求める場合とでは、必要な工数が大きく異なるため、費用にも差が出ます。
また、弁護士の経験や所属する法律事務所の規模も費用に影響を与えます。経験豊富な弁護士や大手事務所では、サービスの質が高い反面、相場より高額になることがあります。
これらを総合的に判断し、自社にとって最適な契約内容を選ぶことが重要です。
中小企業が依頼する顧問弁護士の契約形態とサービス内容を3つ紹介

顧問弁護士の契約形態は、以下の3つが代表的です。
- 定額制
- 時間制
- 成功報酬型
これらの契約形態は費用にも影響を与えるため、契約前にチェックしておくことが必要です。それぞれの契約形態について解説していきます。
定額制
定額制とは、毎月一定の料金を支払うことで、あらかじめ定められた範囲の法務サービスを受けられる契約形態を指します。
主なサービス内容は、以下のようなものです。
- 日常的な法律相談
- 契約書の作成・チェック
- 労務管理
- 取引先との対応
月額の相場は3万円〜10万円程度で、相談回数や対応内容によって価格帯が分かれます。
定額制のメリットは、突発的な相談でも追加費用が発生しにくく、コストの見通しが立てやすい点にあります。法的リスクを早期に察知しやすくなるため、問題の拡大を防ぐ予防的な効果も期待できます。
一方で、対応範囲や回数に上限が設定されているケースもあるため、契約内容を事前に十分確認するようにしましょう。
時間制
時間制は、実際に弁護士が対応した業務時間に応じて費用が発生する契約形態を指します。
一般的には、1時間あたり2万円程度が相場とされており、業務内容の複雑さや弁護士の経験により料金は変動します。弁護士の単価に、対応した時間をかけることで、トータルの費用が算出されます。
時間制の特徴は、必要なときに必要な分だけ依頼できる点にあります。契約書の作成や法的トラブルへの初期対応など、限定的なサポートを求める中小企業に適しています。
また、法務対応の頻度が少ない企業にとっては、月額固定の定額制よりもコストを抑えやすいという利点もあります。
一方で、業務の内容によっては想定よりも工数がかさみ、結果として費用が高額になるケースもあります。時間制は柔軟性に優れた契約形態であり、スポット的な法務対応を希望する企業にとっては有効な選択肢といえるでしょう。
成功報酬型
成功報酬型は、法律相談や交渉、訴訟などの結果に応じて報酬が発生する仕組みであり、成果に応じて費用が決定されます。
成功報酬型は金銭的な利益が発生する案件で活用されることが多く、債権回収や損害賠償請求など、成果が得られた場合にのみ報酬を支払う点が特徴です。
算出方法としては、着手金を低額または無料に設定し、成功時に回収額の一定割合(たとえば20~30%)を報酬として支払うケースが一般的です。
中小企業にとっては、初期費用を抑えつつ法的対応を進められるというメリットがあります。ただし、全ての業務に成功報酬型が適用されるわけではなく、定型的な相談や契約書レビューなどには不向きです。
また、成果の定義や報酬割合については明確にしておく必要があります。成果がどのようなものか弁護士と企業が共有できていないと、トラブルの原因となるでしょう。
顧問弁護士の費用を抑える4つのポイント

中小企業にとって、顧問弁護士の費用はなるべく抑えたいものです。「専門的なサービスのための支出」と分かっていても、高額な費用負担は無視できません。
そのため、ポイントを抑えて費用を抑えることが重要です。具体的には、以下の4つを意識しましょう。
- 自社のニーズに合った契約形態を選ぶ
- スポット相談を併用する
- 社内の法務教育を推進する
- 複数の法律事務所を比較する
それぞれのポイントについて解説していきます。
自社のニーズに合った契約形態を選ぶ
顧問弁護士の費用を抑えるためには、自社のニーズに適した契約形態を選ぶことが非常に重要です。契約形態には主に以下の3つがあると紹介しましたが、それぞれに特徴と向き不向きがあります。
- 定額制
- 時間制
- 成功報酬型
例えば、日常的に法律相談が発生しやすい業種や法務リスクが高い企業であれば、月額で一定のサービスを受けられる定額制が有効です。一方で、法的対応が必要になる頻度が少ない場合は、時間制の契約を選ぶことで、無駄な支出を避けることができます。
また、成果が得られた場合にのみ報酬を支払う成功報酬型は、債権回収や訴訟といった結果が明確な案件に適しています。
企業の業種や事業規模、直面している課題によって、必要な法務サービスの範囲は異なります。あらかじめ自社の課題や相談頻度を把握した上で、柔軟に契約形態を選ぶようにしましょう。
スポット相談を併用する
スポット相談とは、必要なときだけ弁護士に依頼する形式で、顧問契約を結ばずに単発で対応を受けることが可能です。
月額制の顧問契約では、毎月一定額の費用が発生しますが、頻繁に法的支援を必要としない企業にとっては費用対効果が見合わない場合もあります。そうした場合、特定の案件に限定して相談することで、コストを抑えることができます。
例えば、契約書のチェックや労務対応など、限定的な業務であれば1回数万円程度で依頼することが可能です。
ただし、継続的な法的支援を必要とする場合は、顧問契約のほうが適しているケースもあるため、事案の性質や緊急性を踏まえて選択することが重要です。スポット相談と顧問契約を使い分けることで、コストを抑えつつ、必要な法務サポートを確保できます。
社内の法務教育を推進する
顧問弁護士に依頼することで、法的に効果のある企業活動が行えます。しかし、すべての業務を弁護士に依頼していては、相談回数が増え、結果的に顧問料も高額になってしまいます。
そのため、基本的な法律知識を社内で共有し、一定レベルの対応を自社内で完結できる体制を整えることが必要です。これにより、弁護士への依存度を下げることが可能です。
社内の法務教育を実施するには、以下のような対策が有効です。
- 法務担当者や管理職が法律の基礎知識を身に付ける
- 簡単な業務は社内で担当する
- 法務研修や弁護士によるセミナーを実施する
こうして社内での法律理解が進めば、弁護士には最終確認や複雑な案件のみに対応してもらうという役割分担が可能になります。
結果として顧問弁護士の活用は必要最小限にとどめつつ、法的リスクの管理水準は維持でき、結果として費用対効果の高い法務体制が実現します。
複数の法律事務所を比較する
料金体系は法律事務所ごとに異なり、同じようなサービス内容であっても月額費用に差が生じることがあります。そのため、複数の弁護士や事務所から見積もりや契約条件を取り寄せ、サービスと費用のバランスを比較することが重要です。
比較する際は、料金の安さだけでなく、以下のような項目もチェックしましょう。
- 相談対応の範囲
- 対応スピード
- 弁護士の専門分野
- 企業理解の深さ
また、無料相談を活用して確認することも、最適な契約を実現するのに役立ちます。なかには中小企業向けに特化した柔軟な料金プランを用意している事務所もあり、無理のない費用で質の高い法務支援を受けることが可能になります。
事前の比較検討を怠らず、自社に最適なパートナーを選ぶようにしましょう。
まとめ
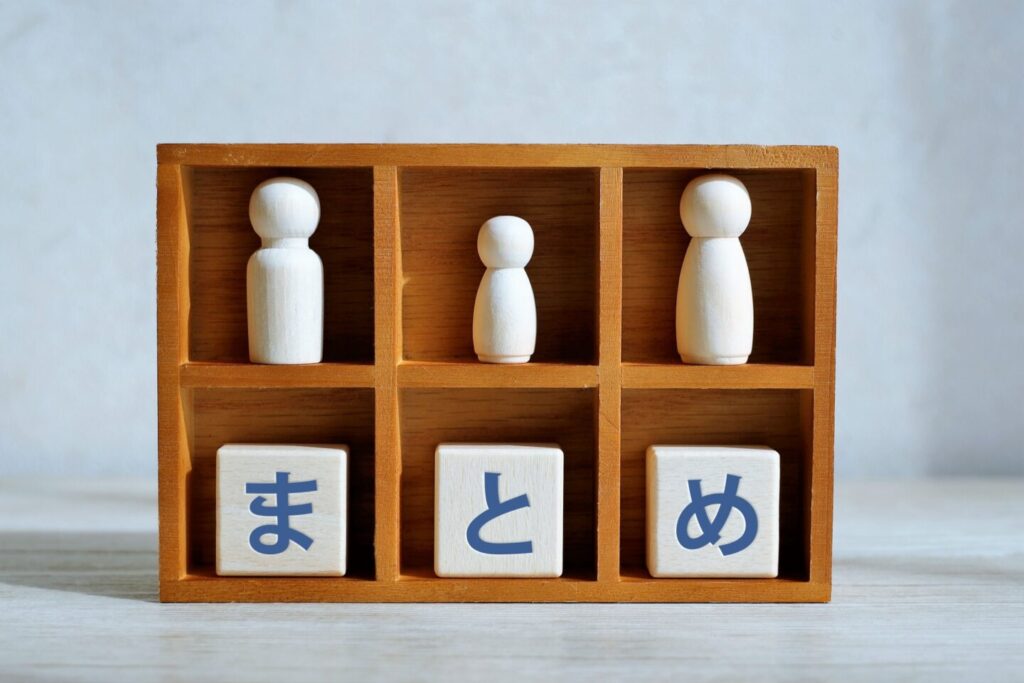
中小企業の経営者・法務担当者からすると、顧問弁護士は費用がかかる手段に思えるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
契約プランや対応業務の範囲を弁護士と相談すれば、無理のない範囲で弁護士のサポートを継続的に受ける体制を整えることが可能です。
自社に適した契約形態や弁護士を選ぶことで、費用に見合った法的サービスを受けることができます。相談するだけでもいいので、まずは法律事務所を訪ねて専門家に聞いてみましょう。
中小企業向けのサービスを提供している弁護士を探すなら、法務救済がおすすめです。法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を全国から検索・依頼することが可能です。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。法務救済を通じて、最適な顧問弁護士を見つけてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












