簡易訴訟とは?流れ・費用・メリットや利用条件をわかりやすく解説
訴訟・紛争解決
2025.08.05 ー 2025.08.07 更新
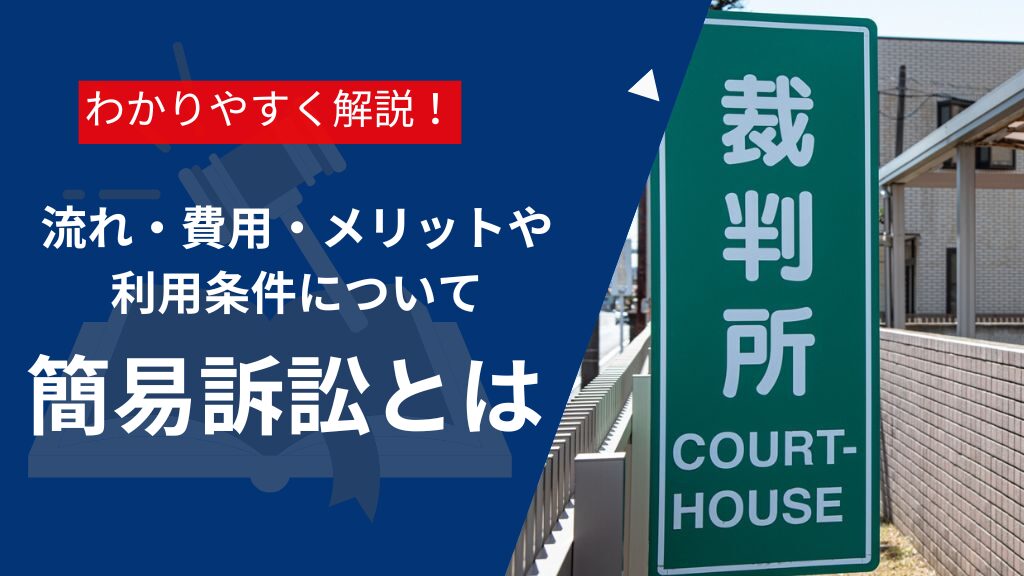
少額の貸し借りや未払い請求、敷金の返還トラブルなど、「お金に関する法的トラブル」は日常の中でも意外と身近に起こり得ます。
家賃の未払い・少額ローンの返済・敷金返還など、60万円未満の金銭トラブルに対応できるのが『簡易訴訟』です。
この制度は、本人訴訟(弁護士なしで自分で訴える)が可能で、支払督促や通常の民事訴訟と比べて手続きが簡素化されている点が特徴です。
簡易訴訟のおおまかな流れは、訴状の提出→裁判所による送達→和解・交渉→判決確定→強制執行です。基本的な流れを理解して、スムーズに対応できるようにしましょう。
この記事では、簡易訴訟の流れ・費用・利用条件・控訴の可否といった基本情報から、通常訴訟や少額訴訟との違い、失敗しないための注意点を、民事訴訟法のルールに基づいてわかりやすく解説していきます。
簡易訴訟で、少額の法的トラブルを解決していきましょう。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>簡易訴訟とは?60万円以下の金銭トラブルに使える制度をやさしく解説
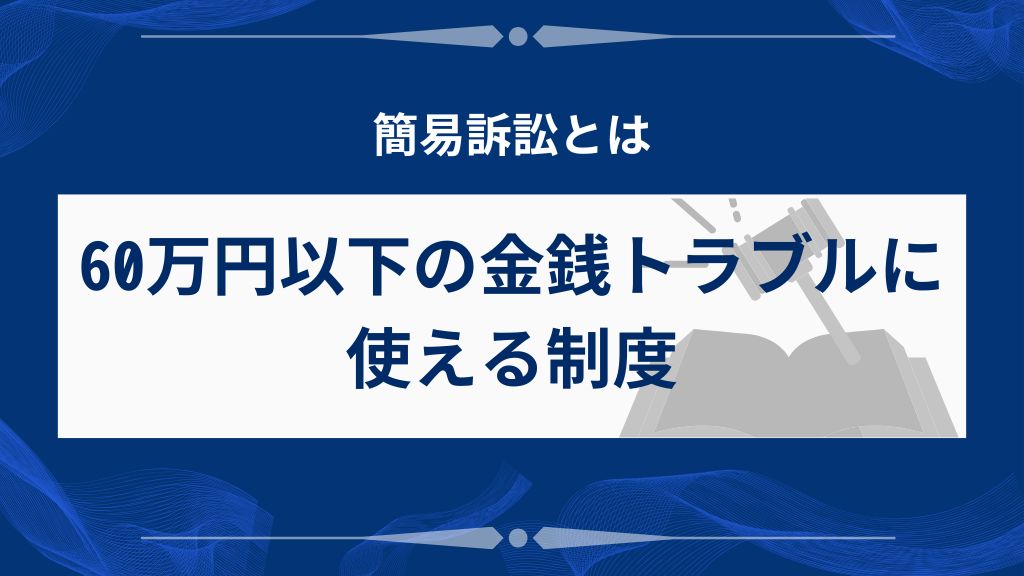
簡易訴訟とは、少額の金銭トラブルを迅速に解決するための特別な裁判手続きです。通常の訴訟と比べて手続きが簡略化されており、対象となるのは、金銭的な請求額が60万円以下の民事紛争です(訴額基準)。
裁判所に出向く回数も少なく、原則1回の審理で結論が出るため、時間的・経済的な負担を軽減することができます。
この制度は、少額の貸金返還や未払い賃金の請求など、日常生活で発生する金銭トラブルの解決に適しています。基本的な流れは、裁判所の書式に従って訴状を作成し、必要な証拠を添付して提出の2ステップです。
しかし、すべての事案に向いているわけではないので、自分の抱える問題が簡易訴訟に適しているかどうか、事前に確認しましょう。簡易訴訟は、専門的な法律知識がなくても自分で手続きを進められる点はメリットですが、証拠の準備や主張の組み立てなど、いくつか注意点もあります。
通常の民事訴訟に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
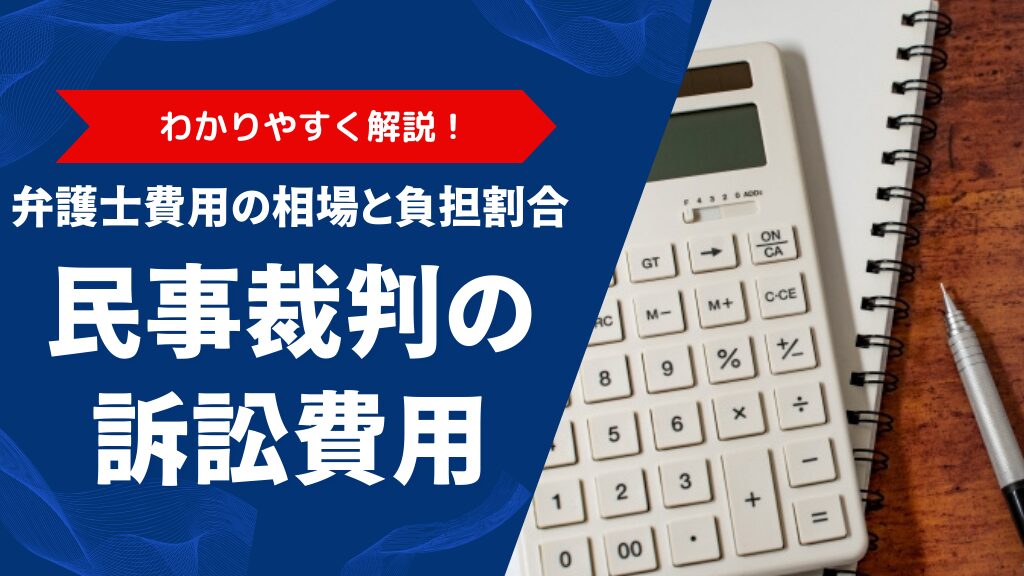
民事裁判にかかる費用とは?訴訟費用・弁護士費用の相場と負担の仕組みを徹底解説
民事裁判において費用は避けて通れない課題です。弁護士への依頼料や裁判所に支払う費用など、訴訟にかかるコストは決して安くはありません。そのため、具体的な金額や内訳が分からず、予算の見通しが立たないために次の行動に踏み出せな […]
簡易訴訟が使える条件と活用メリット|誰に向いている?
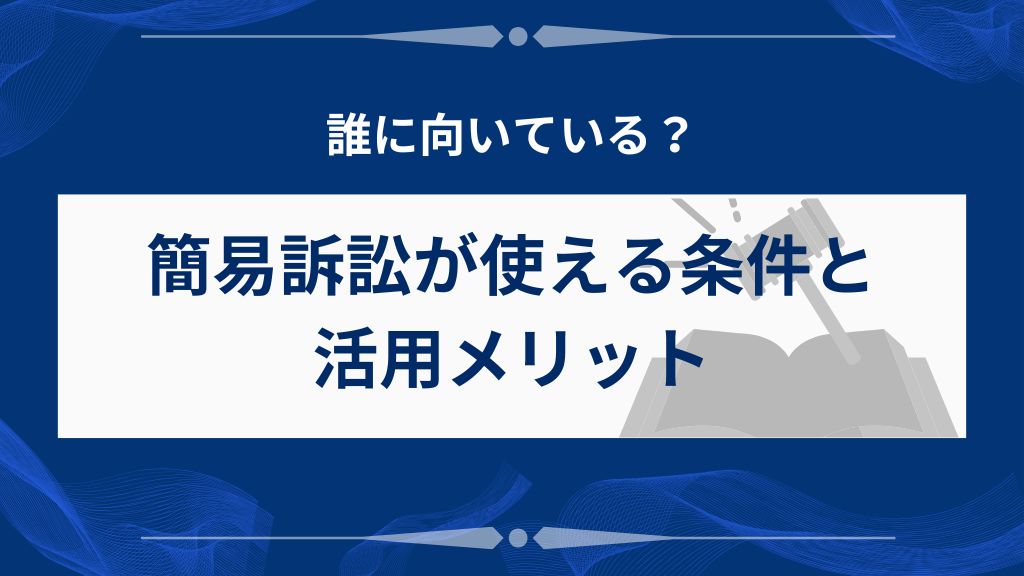
簡易訴訟は、一定の条件を満たす場合に利用できる特別な訴訟手続きです。ここでは、以下の項目を詳しく解説します。
- 簡易訴訟の利用条件は訴訟額が60万以下であること
- 簡易訴訟が適するケースを解説
- 簡易訴訟の3つのメリット
簡易訴訟の利用条件は60万以下であること
簡易訴訟を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。中でも最も重要なのが「訴額が60万円以下であること」です。訴額とは、請求する金額(元本+利息など)を指します。
もしこの金額を1円でも超える場合は、簡易訴訟は利用できず、通常訴訟による対応が必要となります。
また、簡易裁判所の管轄内で手続きが行われるため、被告の住所地や訴訟の原因となった行為地が管轄区域内にあることも条件です。
さらに、簡易訴訟では証拠の提出方法にも一定の制限があり、複雑な証拠調べを必要とするケースには不向きです。
基本的に書面での証拠提出が中心となり、証人尋問などの手続きは簡略化されています。当事者間の争いが比較的単純で、事実関係が明確なケースに適しているといえるでしょう。
また、簡易訴訟を申し立てる際には、訴状に「簡易裁判所における簡易な手続きによる審理及び裁判を求める」旨を明記する必要があります。この記載がない場合、通常の訴訟手続きとして扱われることもあるため注意が必要です。
なお、簡易訴訟は原則として1回の期日で審理を終えることを目指していますが、状況によっては複数回の期日が設けられることもあります。当事者の合意があれば、簡易な手続きから通常手続きへの移行も可能です。
簡易訴訟が適しているケース
簡易訴訟は以下の状況において特に効果的な解決手段です。
- 金銭的な請求が比較的少額である場合
少額の貸金返還や未払い賃金の請求など - 事実関係が比較的明確で複雑な法律解釈を必要としない場合
- 証拠が整っている場合
契約書や領収書、メールのやり取りなど、請求の根拠となる書類が揃っていれば、手続きがスムーズに進みやすい、 - 早期解決を望む場合
通常訴訟と比較して審理期間が短く、原則として初回期日で審理が終了することが多い
相手方との交渉が行き詰まっている状況や、内容証明郵便などでの請求に応じてもらえないケースでも、簡易訴訟は有効な手段となり得ます。
ただし、請求内容が複雑で専門的な知識を要する場合や、争点が多岐にわたる紛争については、通常訴訟の方が適切なこともあります。
自分の状況に最も適した手続きを選択するためには、事前に法律の専門家に相談することも検討すべきです。
簡易訴訟の3つのメリットは手軽さ・スピード・費用
簡易訴訟を選ぶ最大のメリットには、以下があります。
手続きの簡略化
一般的に審理が1回で終了することが多く、短期間での解決が期待できます。特に少額(60万円以下)の金銭トラブルでは、訴訟コストや時間の負担が軽く済むため、おすすめです。
費用面でのメリット
訴額に応じた印紙代は必要ですが、通常訴訟と比べて低額に抑えられることが多く、経済的な負担が軽減されます。弁護士に依頼せずとも本人訴訟が可能なため、弁護士費用を節約できる場合もあるでしょう。
時間的なメリット
簡易裁判所では調停前置主義が採用されていないため、いきなり訴訟を提起できます。裁判官も市民にわかりやすい進行を心がけており、法律の専門家ではない一般の方でも比較的参加しやすい雰囲気があります。
ただし、証拠の提出や主張の組み立てには一定の準備が必要で、相手方の反論に対する対応力も必要です。それでも、小規模な紛争を効率的に解決したい場合には、簡易訴訟は現実的な選択肢の一つといえるでしょう。
簡易訴訟の手続きの流れをわかりやすく解説
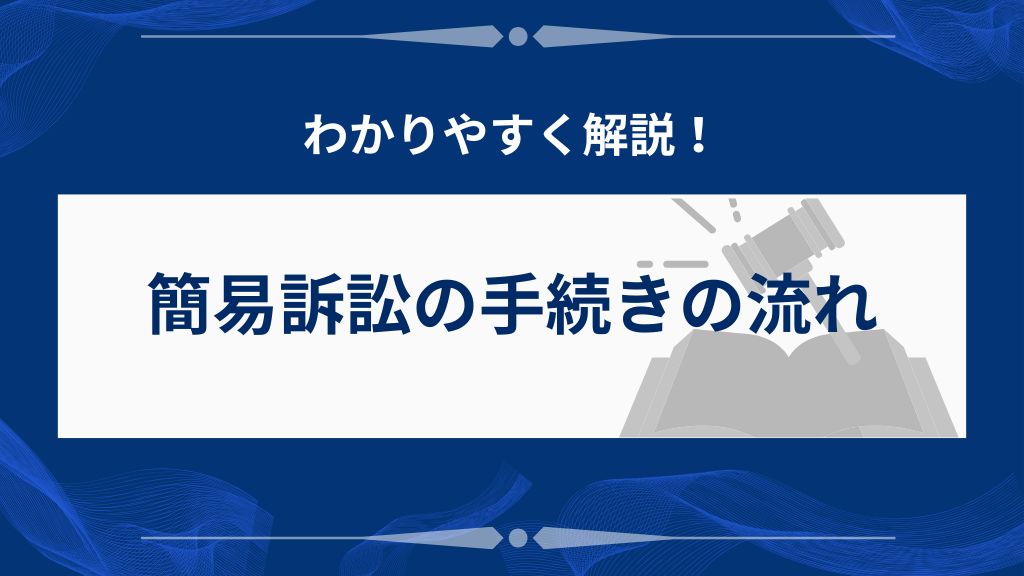
簡易訴訟の手続きは、一般的な裁判手続きと比較してシンプルに設計されています。ここでは、以下のステップで簡易訴訟の手続きを解説します。
- 訴状の作成から判決までの流れ
- 訴状提出後に裁判所はどんな対応をしてくれる?
- 判決までの期間はどれくらい?流れと目安をチェック
- 出廷日の変更はできる?簡易訴訟で注意すべきポイント
訴状の作成から判決までの流れ
簡易訴訟の流れは、訴状の作成から始まります。訴状には、当事者の氏名・住所、請求の趣旨と原因を明確に記載します。
特に請求原因では、なぜ相手に支払い義務があるのかを具体的な事実と共に説明することが大切です。訴状が完成したら、必要な証拠書類を添付して管轄の簡易裁判所に提出します。
提出後、裁判所は訴状を審査し、問題がなければ第一回口頭弁論期日を設定して当事者に通知するのが次のステップです。この期日には原告・被告双方が出席し、主張を行います。
簡易訴訟では通常1〜3回程度の期日で審理が終了することが多いですが、事案によっては若干長引くことも留意してください。
審理が終わると、裁判官は判決を下します。判決は通常、最後の口頭弁論から2週間程度で言い渡されます。
当事者は判決に不服がある場合、判決書の送達から2週間以内に控訴が可能です。ただし、控訴審では新たな証拠提出に制限があるため、第一審での主張・立証が非常に重要です。
訴状提出後に裁判所はどんな対応をしてくれる?
訴状を裁判所に提出すると、裁判所側は以下の手続きが開始されます。
- 訴状の内容を確認し、不備がないかチェック
- 要件を満たしていれば、被告に対して訴状の写しと答弁書の用紙を送付
- 被告が訴状受領後、答弁書を提出する期間が設けられる
- 被告からの答弁書提出後、その内容を原告に送付・争点を整理
場合によっては、裁判所が当事者に追加の証拠や書類提出を求めることもあります。特に、簡易訴訟では、迅速な解決を目指すため、裁判所が積極的に争点整理を行うことが多いです。
ただし、地域や裁判所の混雑状況によって、この手続きが進むスピードは若干の違いが生じます。このように、訴状提出後は裁判所主導で手続きが進められ、当事者は指示に従って必要な対応を取ることになります。
判決までの期間はどれくらい?流れと目安をチェック
簡易訴訟の判決までの期間は一般的に通常訴訟よりも短く、多くの場合2〜3ヶ月程度で結論に至ります。初回期日から判決言渡しまでの進行は、事案の複雑さによって変動しますが、基本的には1〜2回の期日で終結することが多いです。
裁判所は当事者の主張を整理し、争点を明確にして審理を進めていきます。証拠調べの段階では、書証の取り調べが中心となり、必要に応じて当事者本人や証人の尋問が行われることもあります。
ただ、証拠調べが複雑になると予想外に期間が延びることもあるため注意が必要です。
簡易裁判所は、調停への移行を勧める場合もあります。これにより和解が図られると、判決を待たずに紛争が解決することも期待できます。また、当事者間で和解が成立すれば、その時点で訴訟は終了します。
進行状況は裁判所の通知で確認できますが、期日の間隔は裁判所の混雑状況にも左右されます。地域によっては次回期日までの待ち時間が長くなることもあり、この点は事前に把握しておきましょう。
出廷日の変更はできる?簡易訴訟で注意すべきポイント
簡易訴訟の期日が指定されたら、その日程は原則として変更できないものと考えておきましょう。なお、やむを得ない事情がある場合のみ、裁判所に期日変更の申立ては可能です。
変更を希望する場合は、できるだけ早く裁判所に連絡し、具体的な理由と証拠(診断書など)を提示しましょう。
出廷時には、時間に余裕をもって裁判所に到着しましょう。遅刻すると欠席とみなされ、不利な判決が下される可能性があります。
また、主張を裏付ける証拠資料を持参し、裁判官からの質問に簡潔に答えられるよう準備しておきましょう。
服装は、スーツなどの正装である必要はありませんが、裁判所という場にふさわしい清潔感のある服装を心がけてください。
緊張のあまり言い忘れることもあるため、伝えたいポイントをメモにまとめておくと安心です。
簡易訴訟にかかる費用は?知っておくべき料金の詳細
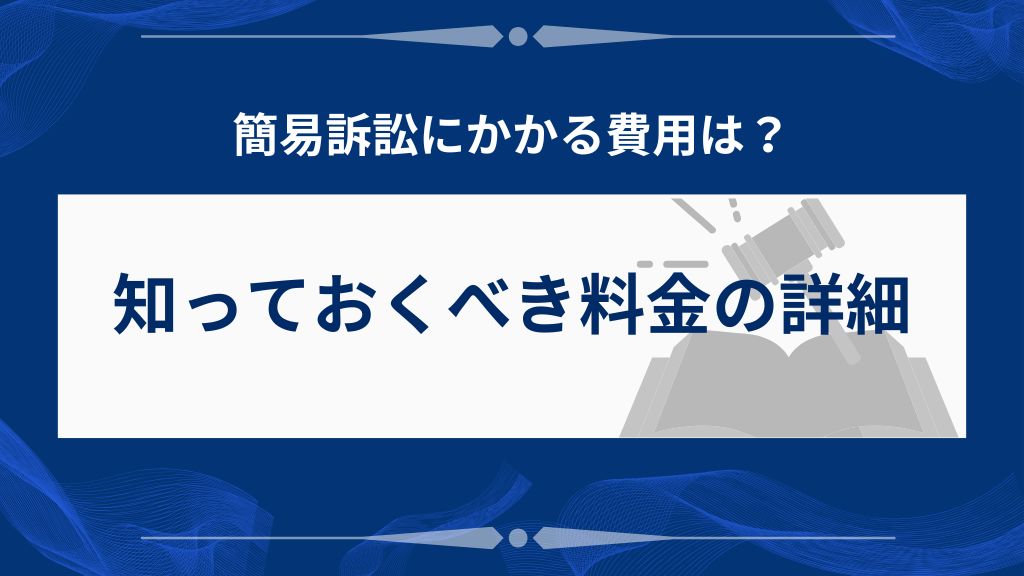
簡易訴訟を利用する際には、いくつかの費用が発生します。ここでは、訴訟費用の基本・費用を抑えるための工夫・その他のコストについて説明します。
訴訟費用の基本は印紙代と郵便切手
簡易訴訟を行う際に必ず発生する費用として、印紙代と郵便切手があります。印紙代は訴額(請求する金額)によって決まり、訴額が10万円以下なら1,000円、30万円以下なら3,000円というように段階的に増加します。
この印紙は訴状に貼付して提出することが必要です。一方、郵便切手は裁判所からの通知や相手方への書類送付に使用されるもので、裁判所によって金額が異なりますが、一般的に数千円程度を予納します。
使い切れなかった切手代は後日返還されますが、訴訟が長引くと追加で必要になることも考慮しておきましょう。
また、訴額が大きくなるほど印紙代も高額になるため、請求金額の設定は慎重に行う必要があります。特に支払督促から移行した場合、印紙代が異なる場合があるため注意が必要です。
これらの基本費用は必ず発生するものですが、裁判所のウェブサイトや窓口で事前に確認しておくと安心です。訴訟を起こす前に、これらの費用を含めた総コストを把握しておくことが賢明といえます。
費用を抑えるには?簡易訴訟でコスト削減する5つの工夫
簡易訴訟の費用を抑えるためには、いくつかの実用的な工夫があります。
自分で訴状を作成する
裁判所のウェブサイトには訴状のテンプレートが公開されており、これを参考にすれば初心者でも作成可能で、弁護士費用を節約できます。
証拠書類の事前コピー
証拠書類はコピーではなく原本を提出する必要がありますが、提出前に自分でコピーを取っておくことで追加費用を抑えられます。
交通費の節約
裁判所への出頭回数を減らすため、電話会議システムの利用を裁判所に申請するという方法もあります。ただし、これが認められるかどうかは事案によって異なるため、事前確認が必要です。
訴訟をまとめる
複数の相手に対して同種の請求を行う場合、可能であれば一つの訴訟にまとめることで印紙代を節約できることもあります。ただし、この方法が適切かどうかは事案の性質によって判断が必要です。
訴訟前に内容証明郵便で相手に請求を行う
訴訟に至る前に解決できる可能性が高まります。これにより訴訟費用全体を節約できるケースも少なくありません。
その他のコスト|交通費やその他手数料
簡易訴訟を進める際には、印紙代や郵便切手以外の費用も考慮すべきです。まず交通費は意外と大きな負担になることがあります。
裁判所への出廷は複数回必要となる場合が多く、遠方に住んでいる方は往復の交通費が積み重なります。特に地方在住で都市部の裁判所に通う場合、この負担は無視できません。
また、証拠書類の準備にかかるコピー代や資料作成費も発生します。重要な証拠を提出する際には、原本ではなく複製を用意することが一般的で、大量の書類がある場合はそれなりの費用がかさみます。
さらに、証人を呼ぶ場合には日当や交通費を支払う必要があることも留意してください。専門的な意見が必要な場合には、鑑定料などの特別な費用も生じる可能性があります。
これらの「見えない費用」は事前に計算しておかないと、予想外の出費に驚くことになります。簡易訴訟は比較的低コストと言われていますが、実際の総額を把握するためには、これら付随する費用も含めて検討することが大切です。
少額訴訟を弁護士に依頼するメリットと注意点
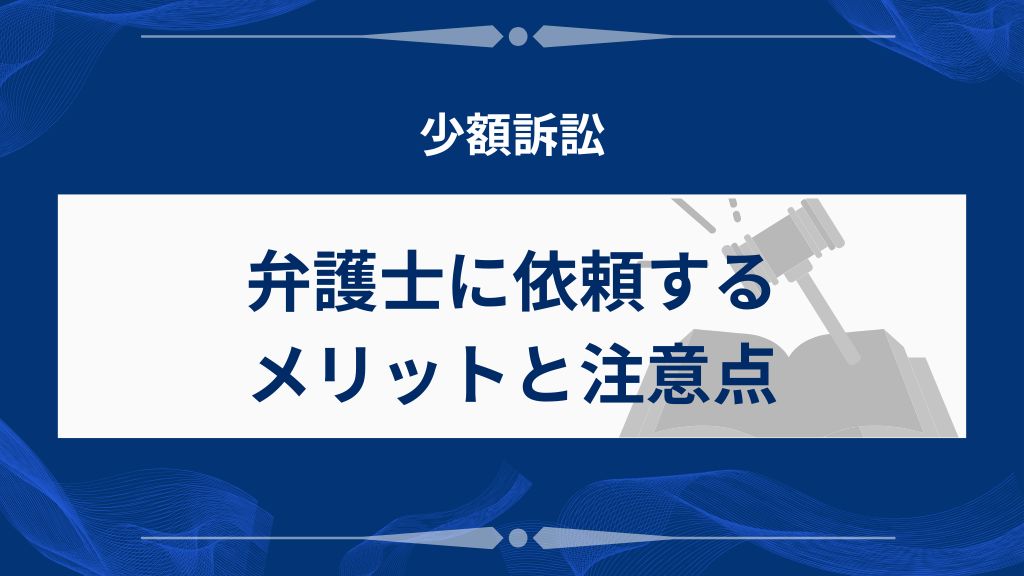
少額訴訟を弁護士に依頼することで、法的な専門知識がなくても適切な手続きを進められる安心感が得られます。ここでは、以下の3つの観点から、そのメリットと注意点を解説します。
- 弁護士に依頼する3つの安心ポイント
- 弁護士に依頼しない場合のリスク
- 弁護士を選ぶときに失敗しないためのチェックポイント
弁護士に依頼する3つの安心ポイント
簡易訴訟において弁護士に依頼することは、法的知識が限られている一般の方にとって大きな安心感をもたらします。
弁護士は法律の専門家として、適切な証拠の収集方法や効果的な主張の組み立て方を熟知しています。特に相手方が法的知識を持っていたり、弁護士を立てている場合には、専門家のサポートがあることで交渉力のバランスが保たれるでしょう。
また、訴訟手続きには複雑な書類作成や期限管理が必要ですが、弁護士はこれらを適切に処理してくれます。自分で行うと見落としがちな法的リスクの把握や、勝訴の可能性を高める戦略的なアプローチも弁護士の重要な役割です。
さらに、法廷での発言や質問への対応は緊張するものですが、弁護士が代理することで精神的な負担が軽減されます。時間的な制約がある方にとっては、煩雑な手続きを任せられる点も大きなメリットといえるでしょう。
ただし、簡易訴訟は比較的少額の案件が多いため、弁護士費用と回収可能額のバランスを考慮する必要があります。事案の複雑さや争点によっては、弁護士の専門性が勝敗を分ける決定的な要素となることもありえます。
弁護士に依頼しない場合のリスク
簡易訴訟を自分で進める場合、法的知識の不足によるリスクが少なからず存在します。まず、適切な証拠の収集や法的主張の組み立てが不十分になりがちです。
専門知識がないため、自分にとって有利な証拠を見逃したり、法的に重要な論点を見落としたりする可能性は無視できません。
また、相手方から予想外の反論や証拠が提出された場合、その場で適切に対応することが難しく、結果として敗訴につながることもあります。
手続き面でも、書類作成の不備や提出期限の見落としなど、技術的なミスが生じやすくなります。こうした手続きの誤りは、場合によっては訴えの却下という厳しい結果を招くこともあるでしょう。
さらに、法廷での発言や態度も判決に影響します。感情的になりすぎたり、裁判官の質問に適切に答えられなかったりすると、事案の本質とは関係なく不利な印象を与えてしまうことがあるため、注意が必要です。
これらのリスクは、争点が複雑になるほど、また請求額が大きくなるほど深刻になる傾向があります。自分で対応するか弁護士に依頼するかは、事案の複雑さと重要性を考慮して判断すべきです。
弁護士を選ぶときに失敗しないためのチェックポイント
簡易訴訟で弁護士に依頼する場合、適切な専門家選びが勝敗を左右します。以下のチェックポイントを参考にしてください。
- 少額訴訟や簡易裁判所での実績があるかどうか
経験豊富な弁護士は手続きの効率化や適切な証拠収集ができるため、成功率が高まります。 - 料金体系の透明性
簡易訴訟は比較的低コストが魅力ですが、弁護士費用が予想外に膨らむと本末転倒です。着手金と成功報酬の内訳、追加費用の可能性について事前に明確な説明を求めるべきです。 - コミュニケーション能力
あなたの状況や希望をしっかり理解し、法律用語をわかりやすく説明してくれる弁護士が理想的です。初回相談での対応や質問への答え方から、信頼関係を築けるか判断できるかもしれません。 - 地域性を考慮する
裁判所近くの事務所なら移動時間や費用の節約になります。
相性の良い弁護士を選ぶことで、精神的負担を軽減しながら簡易訴訟に臨めるでしょう。
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
簡易訴訟と通常訴訟の違いを徹底比較!
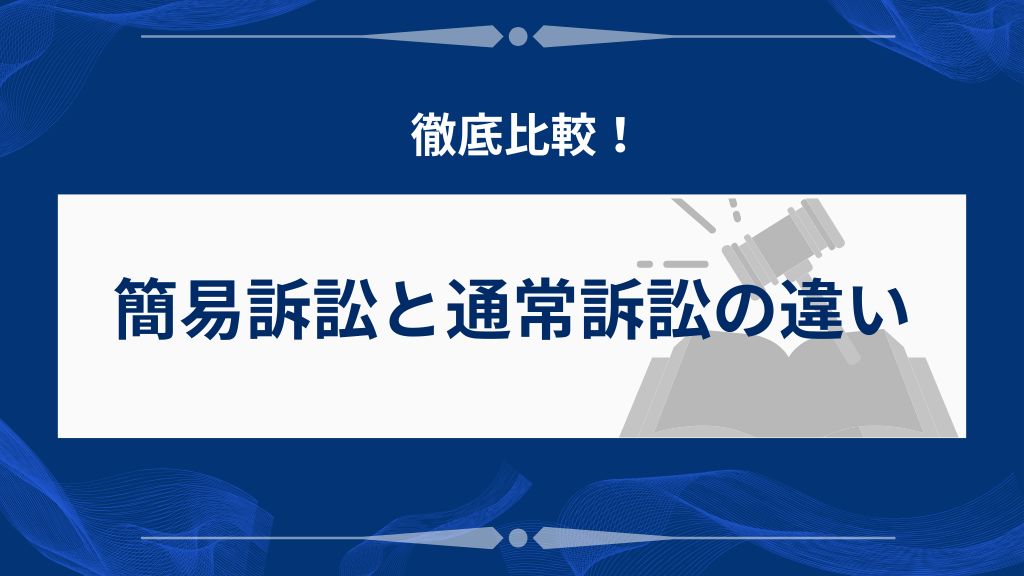
簡易訴訟と通常訴訟には、いくつかの大きな違いがあります。ここでは、手続きの違い・費用面での違い・時間的な違いの3点を解説します。
簡易訴訟は少額の紛争解決に適した制度である一方、通常訴訟は複雑な事案や高額な請求に対応できる柔軟性を持っています。どちらを選択するかは、紛争の内容や求める解決方法によって慎重に判断すべきでしょう。
手続きの違いを徹底比較|簡易訴訟と通常訴訟で何が違う?
簡易訴訟と通常訴訟では、手続きの面で重要な違いがいくつか存在します。まず、簡易訴訟は訴額が60万円以下の請求に限定されており、対象外の高額案件は通常訴訟となります。
一方、通常訴訟には金額制限がなく、複数回の期日を設けて詳細な審理が行われるのが一般的です。また、簡易訴訟では口頭での申立てが認められていますが、通常訴訟では必ず書面による訴状の提出が必要となります。
証拠調べの範囲にも違いがあり、簡易訴訟では即時に取り調べできる証拠に限定されることが多いです。これに対し通常訴訟では、より広範な証拠調査が可能で、必要に応じて鑑定や検証なども実施されます。
判決は、簡易訴訟では原則言い渡しから2週間以内に確定しますが、通常訴訟は控訴期間が2週間あり、その後も上告などの手続きが続く可能性があります。
このように、簡易訴訟は迅速な解決を重視した簡略化された手続きである一方、通常訴訟はより慎重かつ詳細な審理を行う手続きといえます。
どちらを選択するかは、請求金額だけでなく、事案の複雑さや求める解決の質によっても判断しましょう。
費用面の違い
簡易訴訟と通常訴訟では費用面において大きな違いがあります。まず印紙代は、簡易訴訟の場合、訴額に応じた印紙代が必要ですが、通常訴訟と比較するとやや低額に設定されています。
また、簡易訴訟では原則として1回の期日で審理が終了するため、何度も裁判所に足を運ぶ必要がなく、交通費や時間的コストが大幅に削減できます。
弁護士費用に関しても違いがあり、簡易訴訟は手続きがシンプルなため、依頼する場合でも通常訴訟より低額な報酬設定となっていることが多いようです。ただし、訴訟の内容によっては費用感が変わるため、一概には言えない部分もあります。
さらに、簡易訴訟では証拠収集の範囲が限定的であるため、鑑定費用などの特別な費用が発生しにくいという特徴があります。
総じて、簡易訴訟は通常訴訟と比較して、費用面での負担が軽減されるよう制度といえます。
解決までのスピードを比較!簡易訴訟と通常訴訟の時間差とは
簡易訴訟は通常訴訟と比較して、解決までの期間が大幅に短縮されるのが特徴です。一般的に簡易訴訟は、第一回の口頭弁論から1〜3ヶ月程度で判決が出ることが多いです。
これに対し通常訴訟では、複雑な争点の整理や証拠調べなどにより、解決までに半年から1年以上かかるケースも少なくありません。
簡易訴訟の審理は原則として1回の期日で終了することを目指しており、証拠調べも書証を中心とした簡易な方法で行われます。当事者の主張も口頭でのやり取りが中心となるため、手続きがスムーズに進行しやすい環境が整っています。
ただし、事案によっては予想以上に時間がかかることもあるため、完全に短期間で終わると断言はできません。
また、簡易訴訟では控訴の制限があるケースもあり、これによって紛争の早期確定・解決が図られています。時間が限られている方や、長期化する法的紛争を避けたい方は簡易訴訟が効率的な選択肢といえます。
まとめ
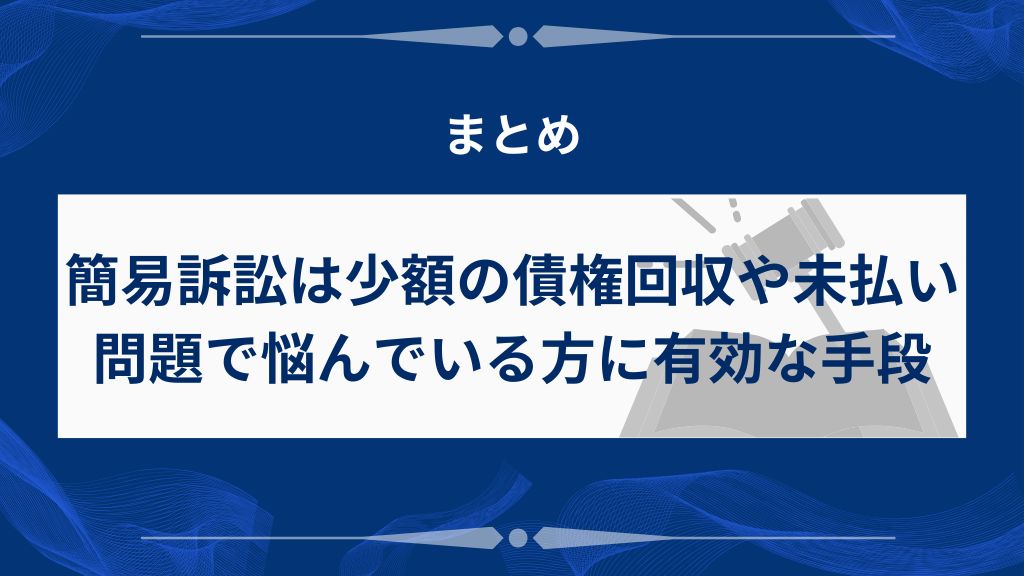
少額の金銭トラブル(例:60万円以下)に対応する迅速・低コストな制度として、簡易訴訟は現実的な選択肢です。通常訴訟と比べて手続きが簡略化されており、原則1回の期日で審理が完結するため、2〜3ヶ月程度で判決を得られます。
証拠が明確で争点がシンプルなケースでは、弁護士に依頼せずとも本人訴訟で対応可能な場合が多く、印紙代や郵便切手代などの基本費用も比較的抑えられます。
少額の債権回収や未払い問題で悩んでいる方にとって、簡易訴訟は法的知識がなくても活用できる現実的な解決手段となるでしょう。
まずは自分の抱える問題が簡易訴訟の対象となるかを確認し、証拠書類を整理して管轄の簡易裁判所に相談してみることから始めてみてください。
法務関連に強い弁護士をお探しなら法務急済がおすすめ
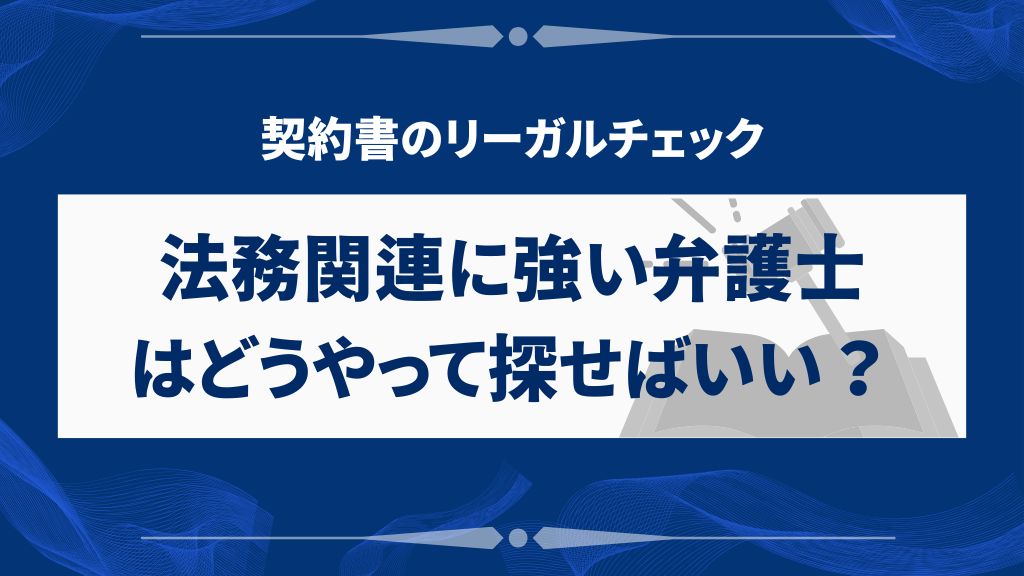
法務急済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士への相談をご検討の方は、ぜひ法務急済をご活用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












