会社の破産手続きの流れや費用、弁護士に依頼するメリットを徹底解説
民事再生・法人破産
2025.03.26 ー 2025.03.27 更新
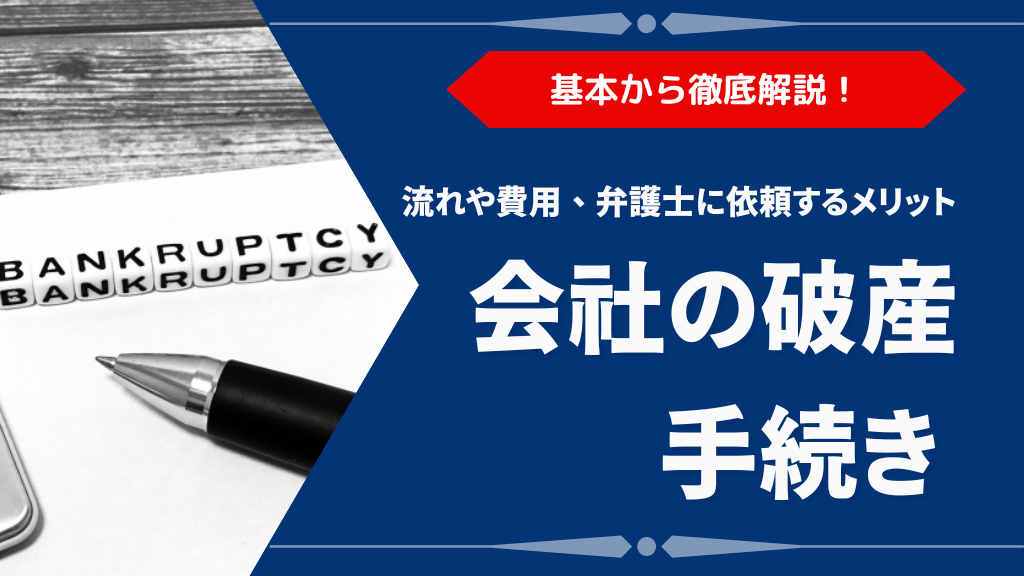
会社の経営が行き詰まり、破産を検討せざるを得ない状況に直面すると、多くの経営者や関係者は破産に関する悩みを抱えることになるでしょう。破産手続きには法律上のルールがあり、適切な対応を取らなければ、経営者個人の責任や従業員の処遇に影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、会社破産の手続きの流れや必要な準備、費用や期間、破産後の影響について解説します。また、弁護士に依頼するメリットについても紹介しますので、不安な方は弁護士への相談も検討してみてください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>会社破産と倒産の違い

会社の経営が行き詰まった際、「破産」と「倒産」という言葉が使われますが、これらは意味が異なります。
倒産とは、企業が経済的に立ち行かなくなる状態全般を指す概念です。資金繰りの悪化により、借入金の返済や仕入れ代金の支払いが困難になった場合、倒産とみなされます。倒産には法的手続きを伴わないケースも含まれ、資金調達や事業再建により回避できることもあります。
一方、破産とは倒産状態に陥った企業が裁判所に申し立てを行い、法律に基づいて清算する手続きのことです。破産手続きが開始されると、会社の資産は破産管財人によって管理・換価され、債権者に公平に分配されます。
つまり、倒産は経営が行き詰まる広い概念を指し、破産はその解決策の一つとして選ばれる法的手続きです。企業が倒産しても、民事再生や私的整理といった再建手段が取られる場合もありますが、破産は最終的な清算を意味します。
会社破産が適用されるケースとは?
会社破産が必要な企業として、以下の状態が対象になります。
- 債務超過:負債が資産を上回る状態
- 支払不能:債務の支払いが継続的に困難な状況
これらの状態にある場合、再建が難しいと判断されると、破産手続きが選択肢として浮上します。
具体的なケースとして、以下のような事例が挙げられます。
- 銀行融資も受けられない
- 売上の急激な減少により運転資金の確保が困難
- 大口取引先の倒産
- 突発的な事故による高額な損害賠償請求
このように、予期せぬ事態で財務状況が悪化したケースも該当します。
ただし、破産は企業にとって最終手段であり、他の再建方法を検討した上で決断することが重要です。安易に破産に踏み切ることはやめましょう。
破産以外の選択肢
会社が経営難に陥った際、必ずしも破産を選択する必要はありません。破産以外の再建手続きとしては、以下の方法が有効です。
- 民事再生法:債務者が事業を継続しながら再建を目指す
- 会社更生法:裁判所が選任した管財人が経営を主導する
- 特別清算:会社が解散し、債務超過の状態にある場合に行われる清算手続き
企業の規模や財務状況、再建の可能性によって最適な手続きは異なります。例えば、事業に将来性があり、債権者の協力が得られる場合は民事再生法が適する可能性があります。一方で、債務が過大で再建が困難な場合は、破産手続きを選ばざるを得ないこともあります。
会社破産の手続きの流れ

会社の破産手続きは、基本的に以下のような流れで進めることになります。全体の流れを理解しておくと、何をするべきか把握して対応することが可能です。
- 破産申立ての準備
- 裁判所への申し立て
- 破産手続開始の決定
- 破産管財人による財産の管理・換価
- 債権者集会の開催
- 債権者への配当
それぞれの流れについて解説していきます。
破産申立ての準備
会社破産の手続きにおいて、最初にやるのが破産申立ての準備です。必要書類を用意することになるのですが、用意するべき書類は以下の通りです。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 債権者一覧表
- 従業員の給与台帳
- 契約書類
破産手続きを進めると、会社の事業活動は停止し、従業員や取引先への影響も大きくなるため、慎重に進める必要があります。適切な準備を行うことで、スムーズな破産申立てが可能となり、手続きの遅延やトラブルを防ぐことができます。
裁判所への申し立て
破産申立ての準備が整ったら、裁判所への申し立てを行います。
破産申立ては、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に対して行う必要があります。裁判所に提出する書類としては、以下の通りです。
- 破産申立書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 従業員の雇用状況を示す書類
裁判所は申立書を受理すると、書類の内容を精査し、会社の財務状況や破産が必要な状態かを審査します。審査の過程では、裁判官や破産管財人が経営者に対して事情聴取を行う場合があります。
特に、債権者への対応や資産の管理状況、不正な資産隠しがないかなどが確認されます。この審査を経て、裁判所が破産手続きの開始決定を下します。
破産手続開始の決定
破産手続開始の決定とは、裁判所が会社の財務状況を審査し、正式に破産手続きを開始することを認めることです。
破産の申し立てが受理されると、裁判所は申立書や提出された財務資料を確認し、会社が破産の要件を満たしているかを判断します。具体的には、債務超過や支払不能の状態にあるかどうかが審査されます。
裁判所が破産手続開始を決定すると、その旨が官報に公告され、債権者に対して破産手続きが進行することが通知されます。この決定により、会社の財産は破産管財人の管理下に置かれ、経営者は財産の処分や営業活動を行う権限を失います。会社は事実上の業務停止状態となります。
それと同時に、従業員の解雇手続きや未払い賃金の対応も必要です。
破産管財人による財産の管理・換価
裁判所が選任した破産管財人は、破産した会社の財産を調査・管理し、債権者に対する公平な分配を行う役割を担います。
まず、破産管財人は会社の資産状況を把握するために財務資料を精査し、以下の資産を評価します。
- 現金・預金
- 不動産
- 在庫
- 設備
- 知的財産権
換価の方法には、競売や任意売却、オークションなどがあり、できるだけ高値で売却することが求められます。また、未回収の売掛金や貸付金がある場合は、破産管財人が回収を進めます。
負債の整理では、リース契約や賃貸借契約を解約し、不要な支出を抑えます。従業員の未払い給与や退職金の精算も必要で、労働基準監督署を通じた未払賃金立替払い制度の活用が検討されることもあります。
財産の換価後、破産管財人は債権者の債権額に応じて公平に分配を行うための準備を進めます。この過程で、債権者からの異議申し立てや財産処分に関する交渉が発生することもあるため、慎重な対応が求められます。
債権者集会の開催
債権者集会の開催は、破産手続の中で債権者に対し、破産会社の財産状況や換価・分配の進捗を説明する機会になります。
債権者集会では、破産管財人がこれまでの業務報告を行い、以下の内容について説明します。
- 会社の財産調査結果
- 換価処分の状況
- 債権者への分配見込み
債権者は自らの債権の取り扱いについて説明を受け、必要に応じて意見を述べることができます。
この集会では、破産管財人の今後の方針についても議論される場合があります。特に、財産の売却方法や配当計画に関する質問や意見が出されることが多く、公平な手続きが求められます。破産手続が円滑に進んでいれば、最終的な配当時期や具体的な金額についての見通しが示されることもあります。
債権者集会の出席は義務ではありませんが、債権回収を目的とする債権者にとって重要な機会となります。
債権者への配当
破産手続開始後、破産管財人は会社の財産を売却し、その収益を債権者への配当に充てます。配当の実施にあたっては、法律に基づいた優先順位があり、以下の順番で配当します。
- 優先債権の支払い
- 一般債権者への配当
優先的に支払われるのは、税金や未払いの従業員給与などの「優先債権」です。 これらは破産財団から最初に弁済されるため、一般の債権者よりも優遇されます。
次に、破産財団債権(破産手続中に発生した費用)や担保権付き債権が処理され、残った資産が一般債権者に配当されます。
配当が完了すると、破産手続は終結し、会社は法人格を失い、正式に消滅することになります。
会社破産の影響

会社が破産すると、以下に影響を与えます。会社だけで解決することではないため、破産に踏み切るには慎重に検討する必要があります。
- 経営者
- 従業員
- 取引先や債権者
破産がもたらす影響について解説していきます。
経営者への影響
会社破産は経営者に多大な影響を及ぼし、財産や社会的信用、今後のビジネス活動に大きな制約をもたらします。
経営者が会社の連帯保証人となっている場合、会社破産後も個人として債務の返済義務が残ります。返済が困難な場合、経営者自身が自己破産を検討しなければならないケースもあります。
破産手続きが進むと、経営者は会社の財産管理権を失い、破産管財人の監督下に置かれます。これにより、会社資産の処分や取引が制限され、破産手続が完了するまで一定の行動制限が生じます。
破産手続の過程で不正な財務処理や財産隠しが発覚した場合、破産犯罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
加えて、経営者の社会的信用にも影響を及ぼします。融資や会社設立においても、金融機関や投資家からの信用を得るのが難しくなることが考えられます。
従業員への影響
会社破産が従業員に与える影響は大きく、特に雇用の継続や未払い給与の支払いが問題となります。
破産手続きが開始されると、会社は事業を継続できなくなり、従業員は解雇されるのが原則です。解雇は法律に基づいた手続きが必要であり、会社は従業員に対して解雇通知を行い、解雇予告手当を支払う義務があります。
未払い給与や退職金が発生してしまうと、従業員から請求される可能性があります。給与や退職金は一定の優先順位が与えられており、破産財産の中から優先的に支払うことが法律で定められています。
会社側は従業員の権利を守るため、破産管財人や労働基準監督署と連携し、適切な手続きを取ることが求められます。
取引先や債権者への影響
取引先にとって、会社破産は売掛金の回収が困難になるリスクがあります。取引先の売上の多くを破産した会社が占めていた場合、その損失によって資金繰りが悪化し、連鎖倒産を引き起こすかもしれません。
また、新たな取引契約の見直しを余儀なくされることがあります。破産した会社との取引が停止することで、仕入れ先や販売先の変更を検討する必要が生じます。
債権者にとっては、貸し付けた資金の回収が難しくなる点が問題となります。破産状況によっては債権者全員が満額を回収できるとは限らず、場合によっては一部のみ、または全く回収できないケースもあります。
さらに、破産情報は官報や信用調査機関を通じて公表されるため、破産した会社との取引履歴が、他の取引先の信用評価に影響を与える可能性もあります。取引先や債権者にとって、会社破産は資金面だけでなく、信用面でも大きな影響を及ぼすでしょう。
破産手続きにかかる費用と期間

会社の破産手続きには、主に弁護士費用と裁判所への予納金が必要です。それぞれの相場や以下の通りです。
- 弁護士費用:50万円
- 予納金:50万円以上
- 実費:~数万円
裁判所に納める予納金は、負債総額や手続きの内容によって異なり、少額管財事件では20万円となることがあります。
手続きに要する期間は、一般的には6ヶ月から1年程度とされています。財産の処分や債権者との調整に時間がかかる場合、手続きが長引くこともあります。
破産手続きを弁護士に依頼するべき理由

会社破産の手続きは、弁護士に依頼しなければならない義務はありません。しかし、以下のような理由から、特別な事情がない限りは弁護士に依頼するべきと言えます。
- 法的手続きをスムーズに進められる
- 債権者対応を代行してもらえる
- 違法行為を避けるためのアドバイスを受けられる
- 破産後のリスクを最小限に抑えられる
それぞれの理由について解説していきます。
法的手続きをスムーズに進められる
破産手続きは法律に基づいた複雑なプロセスであり、弁護士の専門知識と経験が必要です。弁護士は以下のプロセスにおいて、法的サポートをしてくれます。
- 必要書類の作成
- 裁判所への提出
- 裁判所とのやり取り
弁護士の指導を受けることで、手続きにおけるトラブルを未然に防ぐことができます。経営者がカバーできない法律分野をフォローし、スムーズな手続きをしてくれます。
債権者対応を代行してもらえる
会社破産の手続きは、債権者対応が必須です。債権者との交渉や連絡には法的知識と経験が求められ、不適切な対応をするとトラブルに発展する可能性があります。
弁護士は債権者からの問い合わせや請求に対し、法律に基づいた回答をしながら破産手続きを進めます。債権者集会の準備や運営においても弁護士のサポートは不可欠で、債権者の意見を整理し、公正な配当計画を策定する役割を果たします。
また、弁護士が債権者対応の窓口となることで、破産企業の経営者が直接対応する負担を軽減し、精神的なストレスを和らげる効果も期待できます。債権者との関係を円滑に進めることで、破産手続きの遅延や不要なトラブルを防ぐことが可能です。
違法行為を避けるためのアドバイスを受けられる
弁護士に依頼することで、違法行為を防ぐための専門的なアドバイスを受けられ、破産手続きの適正な進行をサポートしてもらえます。経営者が気付かずに行う可能性のある問題行為として、以下のようなものが挙げられます。
- 特定の債権者への偏った支払い(偏頗弁済)
- 会社財産の隠匿
- 従業員の解雇手続きの不備
また、資産管理や債権者対応についても、アドバイスを受けながら適切に対処できるため、予期せぬトラブルのリスクを軽減できます。
ただし、弁護士のアドバイスを受けたとしても、最終的な判断と責任は経営者自身にあります。そのため、適切な法的サポートを受けながら、慎重に破産手続きを進めるようにしましょう。
破産後のリスクを最小限に抑えられる
破産手続きには法律上の規定が多く、適切に進めなければ経営者個人への責任追及や資産への影響が生じる可能性があります。弁護士に依頼することで、法的なトラブルを回避しながら進めることが可能になります。
破産申立ての準備から裁判所への対応だけでなく、破産後の生活設計や再起に向けたアドバイスを受けることもでき、将来的なリスクを最小限に抑えることが可能です。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>弁護士選びで後悔しないために押さえるべきポイント

弁護士にはそれぞれ得意分野や専門領域があり、全ての法律事務所で同じレベルのサポートを受けられるとは限りません。会社破産を弁護士に依頼する場合、以下のポイントを押さえて選ぶ必要があります。
- 破産案件の実績が豊富
- 料金体系が明確
- コミュニケーションがしやすい
それぞれのポイントについて解説していきます。
破産案件の実績が豊富
破産手続きには多くの法律や裁判所の手続きが関わるため、経験が浅い弁護士では対応ができない可能性があります。特に、会社破産の場合は債権者への対応や財産処分の手続きが必要になるため、豊富な実績を持つ弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士の実績を確認する方法としては、弁護士の公式サイトで、過去の破産案件の取り扱い実績をチェックすることが有効です。また、無料相談を活用し、具体的な事例や対応方針について尋ねることで、その弁護士が破産手続きにどれだけ精通しているかを見極めることができます。
経験豊富な弁護士を選ぶことで、破産手続きの負担を軽減し、無用なトラブルを回避できます。
料金体系が明確
弁護士選びで後悔しないためには、料金体系が明確であることが重要です。弁護士費用の内訳は、以下の通りです。
- 着手金
- 報酬金
- 実費
- 成功報酬
破産手続きの場合、会社の財務状況によって費用が変動することがあるため、具体的な金額や支払い条件について事前に確認することが必要です。例えば、着手金が低く設定されていても、手続きの途中で追加費用が発生するケースもあります。
不明確な費用設定の弁護士に依頼すると、破産手続きの進行中に想定外の負担が生じ、経営者の負担が増すことになりかねません。そのため、契約前に料金体系を確認し、明確な見積もりを提示してくれる弁護士を選んでください。
コミュニケーションがしやすい
弁護士選びで後悔しないためには、コミュニケーションのしやすさが選び方のポイントです。弁護士と円滑に意思疎通を図れるかどうかが、手続きの進行速度に影響します。
コミュニケーションがしやすいかどうかをチェックする際は、以下の点を意識してみましょう。
- 分かりやすく説明してくれる
- 質問や相談に対応してくれる
- 連絡のレスポンスが早い
弁護士との相性は軽視されがちですが、非常に重要なポイントです。破産手続きは長期間にわたるため、依頼者が安心して相談できる関係性を築けるかどうかが大切です。
初回相談の際に弁護士の対応や話し方を確認し、信頼できると感じるかどうかを判断しましょう。信頼できる弁護士を選ぶことが、後悔しないためのポイントとなります。
まとめ

会社破産は経営者にとって試練となりますが、適切な知識と専門家のサポートを活用することで、負担を軽減しながら手続きを進めることが可能です。
特に重要なのは、早期の対応と弁護士への相談です。経験豊富な弁護士に依頼することで、債権者との交渉や手続きの準備をスムーズに進め、トラブルを未然に防ぐことができます。
重要なのは、破産に関する情報を収集し、リスクを抑えながら手続きを進めることです。従業員や債権者、取引先との関係も考慮しながら、適切に破産手続きを進めましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。会社破産の手続きを弁護士に依頼したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












