会社破産は弁護士に依頼しよう!手続きの概要や弁護士に相談するタイミング、選び方を徹底解説
民事再生・法人破産
2025.03.26 ー 2025.03.27 更新
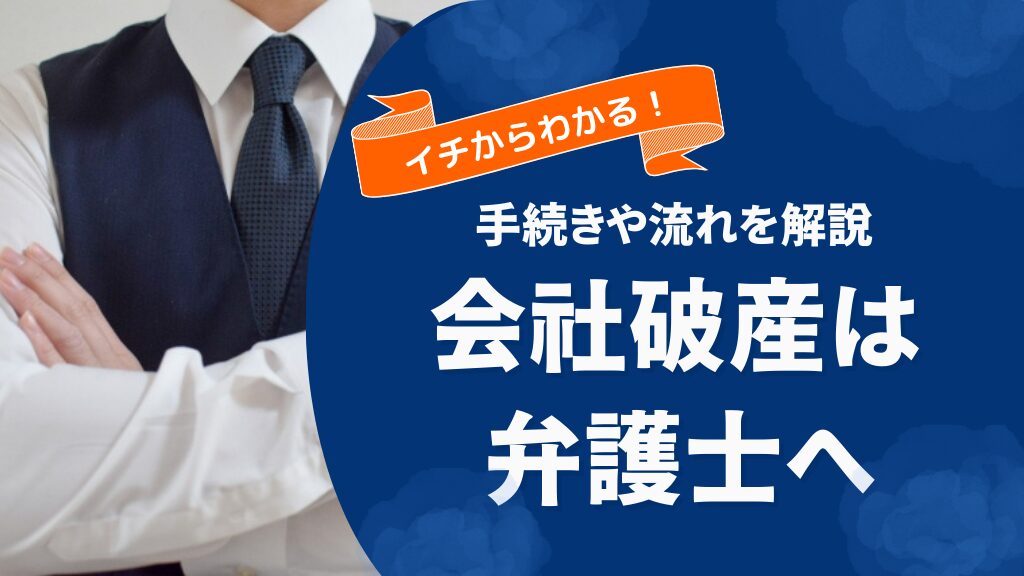
会社の資金繰りが悪化し、倒産を検討している経営者の方にとって、「会社破産」は最後の選択肢となるでしょう。しかし、会社破産の手続きも適切に行わなければ、経営者自身や従業員・取引先へ影響を与えることになります。
そのため、破産を進める際は弁護士に相談するのがおすすめです。法律の専門家である弁護士に依頼することで、適切に会社破産を進めることができます。
本記事では、会社破産の具体的な流れや弁護士に依頼するタイミング、弁護士の選び方について解説します。「倒産手続きを進めるべきか迷っている」「破産すると社長はどうなるのか」「取引先への影響を最小限に抑えたい」と悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>会社破産(法人破産)とは?

会社破産(法人破産)とは、会社が多額の負債を抱え、事業の継続が困難になった際に、裁判所を通じて法的に清算する手続きのことを指します。会社破産には、以下の2種類があります。
- 自主破産:会社が自ら破産を申し立てる
- 破産申立:債権者が申し立てる
会社破産を行うと、会社の営業活動は停止し、資産は処分されて債権者への弁済に充てられます。これにより、未払いの債務についても法的な手続きに基づいて整理されます。
ただし、破産手続きによってすべての債務が弁済されるわけではなく、一定の負債が残ることもあります。経営者の個人保証がある場合には、経営者自身も負債の返済義務を負う可能性があるため、慎重な対応が求められます。
個人破産との違い
個人破産は個人事業主や会社経営者、一般の個人が借金を返済できなくなった場合に利用する手続きです。いずれも経済的に立ち行かなくなった場合に利用できる法的手続きですが、対象や手続きの内容に違いがあります。
会社破産の場合、破産手続きが完了すると法人は消滅し、経営者の責任も原則として終了します。ただし、経営者が会社の債務を個人保証していた場合は、会社破産後もその債務を返済する義務が生じるため、個人破産を併せて検討する必要があります。
一方個人破産では、裁判所の免責許可が下りれば、対象となる借金の返済義務が免除されます。ただし、税金や養育費など一部の債務は免除の対象外です。
また、手続きの流れにも違いがあり、それぞれ以下のように進めます。
- 会社破産:裁判所が選任した破産管財人が資産の処分や債権者への配分を行う
- 個人破産:一定の条件を満たせば、管財人を選任せずに手続きを進められる
どちらの手続きを選択するかは、経営者の状況や負債の内容によって異なります。
法人破産後の影響

法人破産を行うことで、以下に影響を与えます。
- 会社の経営者
- 従業員
- 取引先・債権者
会社内の人間だけでなく、取引先や債権者へも影響を与えるため、会社破産は最終手段として、安易に選択するべき法的手続きではありません。それぞれへの影響について解説していきます。
経営者への影響
経営者が会社の債務を保証している場合、破産後も返済義務が残り、個人資産の差し押さえや生活への影響が避けられません。個人保証がなければ会社の債務とは切り離されるため、個人の財産への影響は比較的軽微です。
しかし、法人破産をすると社会的信用の低下は避けられず、金融機関や取引先との関係が悪化する可能性があります。その結果、新たな事業を立ち上げる際に融資が受けにくくなるなどの問題が生じます。
また、経営者としての責任が問われる場合もあります。不正経理や違法行為が明らかになれば、破産手続きとは別に刑事責任を追及されるでしょう。
従業員への影響
法人破産が決定すると、従業員にも直接的な影響として、雇用契約が終了する可能性があります。
破産申請後は会社が事業を継続できなくなるため、従業員は解雇されることになります。解雇手続きは労働基準法に基づいて行われ、原則として30日前の解雇予告または30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。
未払い賃金については、「未払賃金立替払制度」を利用することで、一定の範囲内で補填を受けられる場合があります。また、従業員は失業保険の給付を受けることができ、ハローワークの職業紹介や会社の取引先への推薦など、再就職のサポートを活用できます。
退職金が未払いの場合、破産手続の中で優先的に支払われる場合もありますが、会社の資産状況によっては全額受け取れない可能性もあります。従業員にとっては、急な収入の断絶による生活の不安が問題となるでしょう。
取引先・債権者への影響
法人が破産すると、取引先や債権者にも影響を与えます。
未払いの債務が発生している場合、取引先や金融機関などの債権者は回収が困難になります。破産手続が開始されると、債権者は勝手に債権回収を行うことができず、裁判所の監督のもとで破産管財人が資産を整理し、債権者への配当が決定されます。
また、継続的な取引を行っていた取引先にとっては、突然の取引停止により業務に支障をきたす可能性があります。主要な取引先が破産すると、代替供給先の確保や取引条件の見直しが必要となり、事業の継続に影響を与えるでしょう。
保証人がいる場合は、その保証人に対して債権回収が行われます。経営者が個人保証をしている場合は、法人破産と同時に個人破産の検討が必要です。
会社破産の流れ

会社破産の手続きは、以下の流れで進めるのが一般的です。
- 弁護士への相談
- 債権者への通知
- 従業員の解雇・テナントの立ち退き
- 申立書や必要書類の準備
- 裁判所への申し立て
- 破産管財人による法人資産の売却
- 債権者集会の開催
- 債権者への配当
それぞれについて解説していきます。
弁護士への相談
経営状況が悪化し、債務の返済が困難になった場合、まずは弁護士に相談します。早めに弁護士に相談することで、弁護士は会社の財務状況を分析し、破産手続きが最適な選択肢かどうかを判断してくれます。
会社の破産を成立させるには、債権者対応や従業員への通知、裁判所への申立てなど多くの手続きが必要です。これらを適切に進めるには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士が介入することで、債権者からの直接的な督促を防ぐことも可能となり、破産手続きを円滑に進めることができます。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。会社破産に対応してくれる弁護士を探している方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>債権者への通知
破産手続きを正式に開始する前に、取引先や金融機関などの債権者に通知することが必要です。破産の事実を突然知らされると、債権者は不安を抱え、混乱を招く可能性があります。
弁護士に依頼した場合、債権者に対して「弁護士が代理人となった」ことを通知し、今後の交渉や問い合わせは弁護士を通じて行うように伝えます。正式な破産手続きが開始されると、裁判所を通じて債権者に破産手続きの通知が送られます。
取引先との関係性によっては、事前に個別の説明を行うことが望ましい場合もあります。長年取引をしてきた企業に対しては、突然の破産通知ではなく、事前に状況を説明し、理解を得る努力をすることで、今後の関係性にも配慮できるでしょう。
従業員の解雇・テナントの立ち退き
会社破産が申請されると、会社は事業を継続できなくなるため、事前に従業員の解雇やテナントから立ち退く必要があります。
従業員の解雇については、労働基準法の規定を守りつつ進めましょう。原則として、解雇を行う30日前までに予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。
資金不足により解雇予告手当の支払いが困難な場合は、ハローワークを通じて「未払賃金立替払制度」を活用し、従業員が一定額の未払い賃金を受け取れるよう支援することも検討すべきです。また、従業員の不安に寄り添い、再就職支援についても可能な範囲で情報提供を行うことが望ましいでしょう。
テナントの立ち退きについては、賃貸借契約の内容を確認し、貸主との交渉を進める必要があります。契約期間内であっても賃料が支払えなくなった場合、貸主から契約解除を求められることが一般的です。
ただし、原状回復義務が発生する可能性があるため、立ち退きに際しては事前に条件を確認し、撤去費用や違約金などの発生を最小限に抑える対応を取るようにしましょう。
申立書や必要書類の準備
会社の状態を整理したら、破産手続開始の申立てに必要な申立書や必要書類を準備します。申立書には、以下の情報を記載します。
- 会社の基本情報
- 破産の理由
- 負債の状況
また、必要書類として以下の資料を用意しましょう。
- 会社の登記簿謄本
- 直近の決算書
- 財産目録
- 債権者一覧表
- 従業員名簿
- 取引先
不備があると裁判所から追加の書類提出を求められ、手続きが遅れる可能性があるため、慎重に作成することが必要です。
さらに、破産費用を支払うための予納金も準備しなければなりません。予納金額は会社の資産状況や負債総額によって異なりますが、一般的に数十万円から数百万円が必要となります。費用を準備できない場合、破産手続が開始されない可能性があります。
こうした書類の準備には時間がかかるだけでなく、不備がないようにしないといけないため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。会社破産に対応してくれる弁護士を探している方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>裁判所への申し立て
必要書類を集めたら、裁判所への申し立てを行います。申し立ては、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所で行うのが原則です。
裁判所に申し立てを行うと、数週間以内に審理が行われ、問題がなければ破産手続の開始決定が下されます。
破産管財人による法人資産の売却
会社破産が裁判所で認められると、破産管財人が選任され、法人の資産整理が開始されます。破産管財人は裁判所の監督のもと、会社の資産を売却し、その売却代金を債権者への配当に充てる役割を担います。
売却の対象となるのは、以下のような会社が保有する資産です。
- 不動産
- 設備
- 在庫
- 車両
- 知的財産権
これらの資産は、一般的に競売や入札、または適切な買い手を見つける形で売却されます。資産価値が高い場合、より多くの債権者に配当が行われる可能性がありますが、資産がほとんど残っていない場合は配当がごくわずかになることもあります。
債権者集会の開催
破産手続きが進むと、裁判所の指示のもとで債権者集会が開催されます。債権者集会とは、破産管財人が破産手続の進行状況を債権者に報告し、今後の方針について説明を行う場です。
通常、債権者集会は破産手続開始決定後、数か月以内に裁判所で開催されます。破産管財人は、以下の情報について報告します。
- 会社の資産状況
- 売却の進捗
- 債権者への配当の見込み
債権者が集会に出席する義務はなく、出席しなくても手続きは進行します。
債権者集会は複数回開催されることもあり、最終的な集会では破産手続の終了に向けた報告が行われます。
債権者への配当
破産管財人による資産の売却が完了すると、債権者への配当が行われます。配当の優先順位は法律で定められており、以下のような順番で支払われます。
- 財団債権:税金や社会保険料
- 優先的破産債権:従業員の未払い賃金
- 破産債権:債権者への配当
財団債権は破産手続きの費用や破産管財人の報酬などを含み、最優先で支払われるため、一般の債権者へ配当される金額は限られることが多いです。
裁判所の指示のもとで配当表が作成され、各債権者に対して配当額が通知されます。その後、一定の期間を経て、債権者に対して実際の支払いが行われます。
しかし、破産財団の資産がほとんどない場合は「無配当」となり、債権者への支払いが一切行われないケースもあります。
債権者への適正な配当を行うことで、法人の清算が完了となり、破産手続きが終了となります。
倒産の危機にある経営者が弁護士に相談すべきタイミング

経営難に直面した企業の経営者にとって、弁護士への相談は早期に行うべきです。資金繰りが悪化し、債務超過の兆候が見え始めた段階で弁護士に相談すれば、破産だけでなく、民事再生や任意整理といった他の解決策も検討できます。
特に、取引先からの支払い催促が増えたり、銀行融資の継続が難しくなったりした場合は、早急な対応が必要です。しかし、「まだ何とかなる」と楽観視し、相談を先延ばしにすると、法的整理の選択肢が限られ、事業の再建が難しくなる恐れがあります。
弁護士に相談することで、現在の財務状況を客観的に分析し、適切な対策を講じることが可能です。
弁護士への相談は、必ずしも即座に破産を意味するわけではありません。破産以外の解決策を模索してくれるため、なるべく早く相談するようにしましょう。
弁護士に相談せず破産手続きを進めるリスク
弁護士に相談せずに会社破産の手続きを進めることには、さまざまなリスクが伴います。具体的には、以下の通りです。
- 破産手続きの遅延
- 資産整理作業の停滞
- 債権者からの督促
- 取引先や金融機関との関係悪化
- 未払い賃金
- 損害賠償請求
弁護士のサポートを受けることで、破産手続きをスムーズに進めるだけでなく、債権者や従業員への影響を最小限に抑えることができます。自己判断で進めるリスクを避けるためにも、早い段階で弁護士に相談しましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。会社破産に対応してくれる弁護士を探している方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>会社破産に強い弁護士の選び方

会社破産を適切に進めるには、会社破産に強い弁護士に依頼する必要があります。全ての弁護士が同じ能力を持っているわけではないため、慎重に選ぶことが重要です。
弁護士を選ぶ際のポイントは、以下の通りです。
- 破産手続きの経験が豊富
- コミュニケーションが取りやすい
- 地域の案件を受けている
それぞれのポイントについて解説していきます。
破産手続きの経験が豊富
破産手続きの経験が豊富な弁護士を選ぶことは、手続きをスムーズに進める上で欠かせないポイントとなります。
破産手続きは、裁判所への申し立てから資産の整理、債権者対応、従業員の解雇手続きなど、多岐にわたる業務が含まれます。そのため、過去に多数の会社破産案件を担当した実績のある弁護士を選ぶことで、円滑な手続きを期待できるでしょう。
弁護士の実績は、過去の対応案件を確認することでチェックできます。弁護士事務所のウェブサイトや相談時に、どの程度の会社破産案件を扱ってきたかを確認し、自社の状況に適した弁護士を選びましょう。
コミュニケーションが取りやすい
破産手続きは長期間にわたるため、精神的な負担がかかります。そのため、弁護士と円滑に意思疎通ができるかどうかは、手続きをスムーズに進めるための重要な要素となります。
コミュニケーションが取りやすいかどうかは、以下の点をチェックしましょう。
- 丁寧に説明してくれる
- わかりやすい言葉を使ってくれる
- メールや電話のレスポンスが早い
こうした要素を満たしている弁護士だと、破産について理解を深めながら、手続きに参加することができます。自社のことであるため、弁護士に任せきりにすることはおすすめしません。
弁護士を選ぶ際には、初回相談時の対応を確認し、信頼して相談できる相手かどうかを慎重に見極めることが大切です。
地域の案件を手掛けている
会社破産の手続きは、裁判所や債権者、取引先とのやり取りが必要となるため、地域の事情をよく理解した弁護士に依頼するのがおすすめです。
地域の裁判所の運用ルールや、破産手続きにおける傾向は場所によって異なる場合があります。地元での案件を多数扱っている弁護士であれば、裁判所の審理の流れや必要書類の細かい要件などを熟知しているため、申立手続きを的確に進めることができます。
また、地域の金融機関や取引先との関係性にも配慮した対応が期待できます。取引先が地元企業である場合、今後の関係を考慮した対応を取ることも重要です。
破産手続きには何度か弁護士との面談が必要になるため、遠方の事務所では移動の負担が大きくなることも考えられます。迅速な対応や緊急時の相談がしやすい点でも、地元の案件を手掛ける弁護士に依頼するのがおすすめです。
まとめ

会社破産の手続きでは、弁護士のサポートが不可欠です。法律の専門知識がないと、必要書類や債権者への対応でミスが発生しやすくなり、場合によっては督促や請求を受けるリスクもあります。また、従業員への対応も適切に行わないと、法的措置を取られるかもしれません。
依頼する際は費用がかかりますが、トラブルに対応する負担を考慮すれば、弁護士に依頼するべきでしょう。専門家のサポートを得て、スムーズに会社破産の手続きを進めましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。会社破産の手続きを弁護士に依頼したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












