- 法務救済
- コラム
- 予防法務
- 契約書・リーガルチェック
- 秘密保持契約書(NDA)の作成方法とおすすめテンプレート雛形を徹底解説
秘密保持契約書(NDA)の作成方法とおすすめテンプレート雛形を徹底解説
契約書・リーガルチェック
2025.03.26 ー 2025.05.13 更新
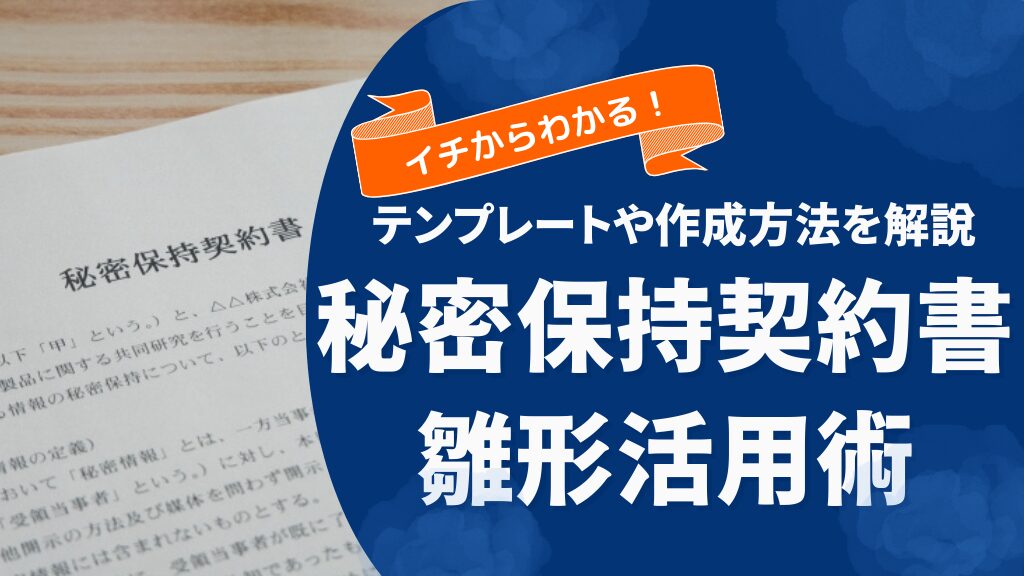
秘密保持契約書を作成する場合は、雛形を使うのがおすすめです。秘密保持契約の基本条項やフォーマットが作られているため、一から作成するよりも手間や時間を省くことができます。
しかし、雛形をそのまま契約に使うことはおすすめしません。秘密保持契約の内容は企業や相手方によって異なるため、カスタマイズが不可欠になります。「雛形を使えば楽に契約書が作成できる」というのは間違いであるため、注意しなければいけません。
この記事では、秘密保持契約書の概要や重要性から、雛形を提供するサイトや作成方法について解説していきます。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>秘密保持契約書(NDA)とは?
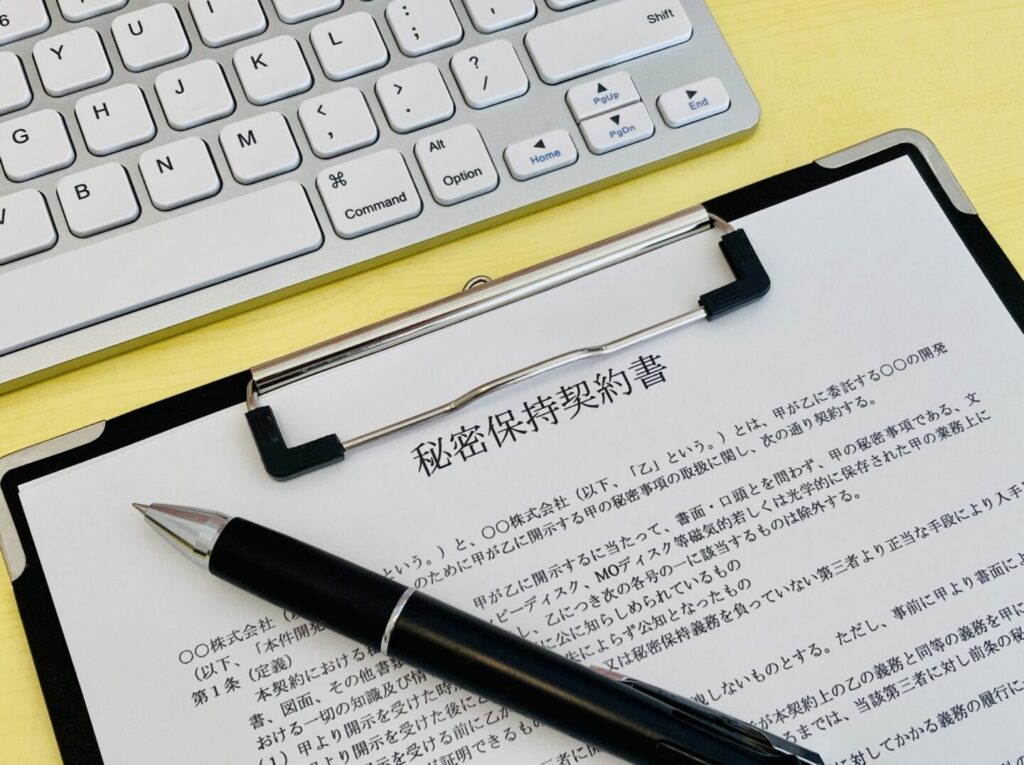
秘密保持契約書(NDA)は、企業や個人が事業活動において秘密情報を開示する際に、情報の漏洩を防ぐために締結する契約です。秘密保持契約を交わすことで、秘密情報の取り扱いに関するルールが定められ、情報が外部に漏れるリスクを低減できます。契約においては、同意や承諾が必須であり、企業間の信頼関係を築くためにも重要です。
秘密保持契約には、以下の2種類があります。
- 片務契約:一方が情報を開示する
- 双務契約:双方が情報を共有する
秘密情報の定義を曖昧にすると、後のトラブルにつながる可能性があるため、具体的な内容を記載することが重要です。
近年では、ビジネスのグローバル化や情報技術の進展により、秘密情報の取り扱いが厳格化しています。適切な秘密保持契約を結ぶことで、企業の競争力を守り、会社の信頼関係を構築できます。
秘密保持契約が必要なケース
秘密保持契約が必要となる場面は、以下の通りです。
- 新規事業の立ち上げ
- 他社との業務提携・共同開発
- M&A交渉
- 製品開発
- 技術提携
- 人材採用
- フリーランスや外部コンサルタントとの業務委託契約
- 資金調達
NDAの目的は、企業にとって価値のある情報を適切に保護することにあります。適切な契約内容を設定することで、機密情報を守りながら円滑な取引を進めることが可能になります。
ただし、どの程度の情報を開示し、どこまで制限を設けるべきかは、ビジネスの状況によって異なるため、注意が必要です。
秘密保持契約の重要性

秘密保持契約書は、作成しなくても契約は可能です。しかし、ほとんどの取引では秘密保持契約が締結されており、もはや必須となっています。
秘密保持契約が重要とされる理由として、以下の3つがあります。
- 企業の秘密情報の漏洩防止
- 情報の流出時に損害賠償を請求できる
- 秘密情報の範囲を特定可能
それぞれの重要性について解説していきます。
企業の秘密情報の漏洩防止
企業の秘密情報の漏洩防止は、秘密保持契約の重要な目的の一つです。企業の秘密情報が外部に流出すると、競争優位性が失われたり、不正利用されるリスクが高まります。
秘密保持契約を締結することで、開示された情報の取り扱いや利用範囲が明確になり、不適切な開示や第三者への漏洩を防止できます。さらに、契約違反時の法的措置を明記することで、情報を扱う相手方に対し抑止力を働かせることが可能です。禁止事項を明記し、一切の不正使用を防ぐことができます。
情報の流出時に損害賠償を請求できる
秘密保持契約(NDA)の役割の一つは、情報が流出した際に損害賠償を請求できることです。
契約に違反して機密情報が外部に漏れた場合、企業は事業上の損失や信用の低下などの影響を受ける可能性があります。事前にNDAを締結しておけば、違反者に対し法的措置を講じる根拠が明確になり、損害賠償の請求が可能となります。利用規約に基づき、契約違反に対する責任を明確にします。
秘密保持契約書には、違反時の対応として、損害賠償の範囲や計算方法を明記することが一般的です。また、流出の危険性を抑止するために違約金条項を設ける場合もあります。
秘密情報の範囲を特定可能
秘密保持契約書には、どの情報が秘密情報に該当するのかを定義することで、不要なトラブルを防ぎ、情報の保護範囲を明確にできます。技術データや顧客リスト、事業戦略など、対象となる情報を記載することで、契約当事者間の認識のズレを防げます。
開示側は重要な情報を保護でき、受領側もどの情報が保護対象なのかを正しく理解できます。不必要な制約を避けながらも、機密情報の適切な管理が可能になります。
情報が特定されていない場合、意図しない情報の漏洩リスクが高まり、法的トラブルに発展する可能性もあります。そのため、契約締結時には、秘密情報の範囲を具体的に定めることが重要です。
秘密保持契約書の雛形はどこで入手できる?

秘密保持契約書を作成する上で、雛形(テンプレート)を活用するのがおすすめです。フォーマットが既に作成されているため、一から作る必要がありません。
秘密保持契約書の雛形は、以下のような方法で入手可能です。
- 経済産業省の公式サイト
- 弁護士事務所の公式サイト
- クラウドサービス
それぞれについて解説していきます。
経済産業省の公式サイト
秘密保持契約書(NDA)の雛形を入手する方法の一つに、経済産業省の公式サイトを利用する方法があります。経済産業省は「秘密情報の保護ハンドブック」を公開しており、その中の「参考資料2 各種契約書等の参考例」において、NDAの雛形を提供しています。
企業法務の専門家と経済産業省が共同で作成したテンプレートであるため、信頼性が高く、標準的なNDAとして活用できます。
経済産業省の公式サイトからダウンロードできるこの雛形は、秘密保持契約書の作成に役立つリソースとして、多くの企業で活用されています。
弁護士事務所の公式サイト
多くの弁護士事務所では、契約書のひな形を無料で公開しています。例えばクレア法律事務所では、秘密保持契約書の雛形をダウンロードでき、各案件に応じて条項の追加や修正が可能です。
これらの雛形は、基本的な構成や条項が整備されており、契約書作成の際の参考になります。雛形を利用する際は、自社の実情に合わせて内容を精査し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
クラウドサービス
クラウドサービスでも、秘密保持契約書の雛形を入手することが可能です。例えばクラウドサインは、経済産業省が公開している秘密保持契約書のフォーマットを忠実に再現した雛形を提供しています。
また、以下のようなクラウドサービスもおすすめです。
- クラウドコントラクト:弁護士が監修している
- Shachihata Cloud:オンライン上で完結できる電子契約サービスを提供
これらのクラウドサービスを活用することで、秘密保持契約書の雛形を入手でき、業務効率化や契約手続きの迅速化が可能です。
雛形で秘密保持契約書を作成する際の注意点

雛形は作成プロセスを軽減できる便利なサービスですが、そのまま使うことはおすすめしません。雛形を活用して秘密保持契約書を作成する際には、以下の点に注意しなければいけません。
- 事業内容に応じてカスタマイズする
- 最新の法律に適用するかチェックする
- 条項が自社のニーズをカバーしているか確認する
- 弁護士にリーガルチェックを依頼する
それぞれの注意点について解説していきます。
事業内容に応じてカスタマイズする
秘密保持契約書の雛形は一般的な構成になっているため、そのまま使用すると自社の実情に合わない内容になり、リスクを招く可能性があります。秘密情報の定義や開示範囲、契約期間、違反時の対応措置などは、業種や事業規模によって適切な内容が異なります。
- IT業界:ソースコードやアルゴリズム、データベース構造
- 製造業:製品の設計図や生産プロセス
また、情報の開示範囲についても、関係者のみに限定するのか、一定の業務委託先まで許可するのかを明確にすることが求められます。
違反時の対応措置についても、損害賠償の規定を明確にし、実際にトラブルが発生した際の対応を定めておくようにしましょう。
最新の法律に適用するかチェックする
秘密保持契約に関する法律は改正されることがあり、以前の契約内容が現行法に合致しなくなる可能性があります。機密情報の取り扱いに関連する法律の変更があれば、契約の内容を見直さなければいけません。
例えば個人情報保護法は、近年複数回改正されています。
- 令和2年改正:漏えい等報告・本人通知の義務化、利用停止・消去等の請求権の拡充、保有個人データの開示方法の規定
- 令和3年改正:国や独立行政法人、学術研究機関等に関する規律の見直し、地方公共団体に関する規律の見直し
- 令和5年改正:国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等における個人情報の取扱い規律
企業が従業員や顧客の情報を第三者と共有する場合、その範囲や目的を明確にしなければなりません。秘密保持契約書に個人情報の取り扱いに関する条項を適切に盛り込んでいないと、法的な問題が発生する可能性があります。
また、国際取引が関係する場合は、外国の法律にも適用するか確認が必要です。欧州の一般データ保護規則(GDPR)や米国のデータ保護法など、各国の規制に準拠しているかどうかをチェックすることが求められます。
条項が自社のニーズをカバーしているか確認する
雛形は一般的な契約内容を網羅していますが、すべての企業や取引に適したものではありません。事業内容や取引の特性に応じて適切な修正を加えなければ、契約後に問題が発生する可能性があります。
秘密情報の範囲が曖昧な場合、想定していない情報が保護の対象外となることがあります。そのため、以下のような具体的な情報を明記します。
- 技術情報
- 事業戦略
- 顧客リスト
- 秘密保持義務の期間
また、情報の開示範囲についても注意が必要です。業務委託先や親会社、関連会社に情報を提供するケースがある場合、それらの関係者にも秘密保持義務を適用できるような条項が含まれているかを確認する必要があります。
弁護士にリーガルチェックを依頼する
雛形を活用して秘密保持契約書を作成する際は、弁護士にリーガルチェックを依頼するのが有効です。企業の業種や取引内容、開示する情報の種類によって、適切な条項や表現を追加・修正する必要があります。
情報漏洩や違反が発生するリスクを回避するためにも、弁護士にリーガルチェックを依頼し、契約の適法性やリスク管理の観点から適切な内容になっているかを確認してもらうことが推奨されます。
秘密保持契約書は企業の機密情報を守る重要な書類であり、リスクを最小限に抑えるためにも、専門家の意見を取り入れることが望ましいでしょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。秘密保持契約書の作成を弁護士に依頼したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>秘密保持契約書の作成方法

秘密保持契約書は、以下のような流れで作成します。テンプレートを使用することを前提に紹介していきます。
- 秘密保持契約に関する情報を収集する
- テンプレートを選択・ダウンロードする
- テンプレートに記載・カスタマイズを加える
- 弁護士や法務担当者にレビューを依頼する
- 契約書を相手方に提示・交渉する
それぞれについて解説していきます。
1,秘密保持契約に関する情報を収集する
まずは、秘密保持契約に関する情報を収集します。
経済産業省や公的機関が提供するガイドラインを確認すると、秘密保持契約の基本的な考え方や注意点を把握できます。また、弁護士事務所や法律関連のウェブサイトでも、実務に即した解説が提供されているため、参考にできるでしょう。
また、過去に類似の契約を締結した経験がある場合は、その契約書を参考にしながら、必要になる情報を整理しましょう。以前の契約で問題が発生した場合は、その原因を分析し、より実効性の高い契約内容に修正することで、秘密保持契約書の精度を高めるのに役立ちます。
2,テンプレートを選択・ダウンロードする
テンプレートを選ぶ際には、信頼性のある提供元から入手しましょう。経済産業省や日本弁護士連合会、各種法務系のサイトでは、企業が実務で活用できる標準的なNDAのテンプレートを提供しています。また、クラウドサインやShachihata Cloudなどの電子契約サービスでも、実務に即した雛形を提供しています。
次に、契約の種類に応じたテンプレートを選ぶことも重要です。秘密保持契約には、一方が情報を開示する「片務契約」と、双方が情報を共有する「双務契約」の2種類があります。
例えば、自社が情報を開示する側であれば片務契約のテンプレートを、相互に機密情報をやり取りする場合は双務契約のテンプレートを選びます。取引の性質に合わないテンプレートを選んでしまうと、契約の実効性が低下し、後にトラブルの原因となる可能性があります。
3,テンプレートに記載・カスタマイズを加える
テンプレートをダウンロードした後は、自社の取引内容や業務に合わせて記載事項を修正し、カスタマイズしていきます。テンプレートはあくまで一般的な契約書のひな形であるため、各項目を慎重に確認しながら調整を行う必要があります。
具体的には、以下の項目に注意しましょう。
- 秘密情報の定義:曖昧な表現では契約対象が分かりにくい
- 契約期間・秘密保持義務の期間:過度に長い期間を設定すると契約相手との交渉が難しくなる可能性がある
- 違反時の措置:テンプレートの条項が自社のリスク管理に適しているかを確認する
例えば秘密保持の定義については、「技術情報」や「営業情報」といった大まかなカテゴリーではなく、「開発中のソフトウェアコード」や「未公開のマーケティング戦略」など、具体的な情報の種類を明記することで、契約の実効性を高められます。
適切なカスタマイズを施すことで、秘密保持契約の実効性を高め、安全な取引を実現することができます。
4,弁護士や法務担当者にレビューを依頼する
秘密保持契約書(NDA)をカスタマイズした後は、弁護士や法務担当者にレビューを依頼します。契約書の内容に法的な不備や曖昧な表現が含まれていると、トラブルが発生した際に適切な対応が取れず、自社にとって不利な状況に陥る可能性があります。
特に、以下のような条項を見直すことが重要です。
- 秘密情報の定義
- 契約期間
- 違反時の対応
例えば、「秘密情報の範囲」が広すぎると契約相手の負担が大きくなり、交渉が難航する可能性があります。一方で、範囲が狭すぎると、自社の情報が保護されないリスクがあります。このような点について、法務の専門家のアドバイスを受けることで、適切なバランスを取ることが可能です。
また、契約書の条項が自社にとって公平かつ有利な内容になっているかを確認することも重要です。例えば、契約違反が発生した際の損害賠償額の設定が適切か、情報漏洩時の責任範囲が明確かなど、実際に問題が発生した際のリスク管理の観点から確認を行います。
適切なリーガルチェックを受けることで、契約の有効性を確保し、将来的な紛争を防ぐことができます。
5,契約書を相手方に提示・交渉する
秘密保持契約書のチェックを受けた後は、契約相手に提示し、交渉を行う段階に入ります。契約の目的や条項の内容について相手方と合意を形成し、双方が納得できる契約に仕上げることが重要です。
契約交渉では、双方が公平な条件で合意できるよう、具体的なポイントを話し合います。その際に秘密保持に関する情報を説明する必要があるため、契約書の内容を理解しておく必要があります。
また、相手方が独自のNDAを提示してきた場合は、その内容を精査し、自社にとって不利な条項がないか確認します。特に、違反時の責任範囲や損害賠償の条項については、リスク管理の観点から慎重に検討し、不適切な条件が含まれていれば修正を依頼しましょう。
契約内容に双方が合意した後は、正式な契約書として締結し、適切に保管します。
スムーズに契約したいなら電子契約がおすすめ!

スムーズに秘密保持契約(NDA)を締結したい場合、電子契約の活用がおすすめです。電子契約を導入することで、以下のプロセスを効率化し、契約手続きを迅速に進めることが可能になります。
- 契約書の印刷
- 押印
- 郵送
- 保管
- 締結
電子契約では、クラウド上で契約書を作成・送信し、契約が成立します。遠隔地にいる取引先との契約でも即時に締結でき、業務のスピードが向上します。
また、電子契約は法的に有効な手段として認められており、電子署名法に基づいて適切な認証が行われるため、契約の信頼性も確保されています。契約件数が多い企業にとっては、電子契約を導入することで業務の効率化とコスト削減の両方を実現できます。
おすすめの電子契約サービスは、以下の通りです。
このように電子契約を活用すれば、秘密保持契約を迅速かつ安全に締結でき、契約業務の負担を軽減できます。スムーズな契約締結を実現するために、電子契約の導入を積極的に検討することをおすすめします。
まとめ
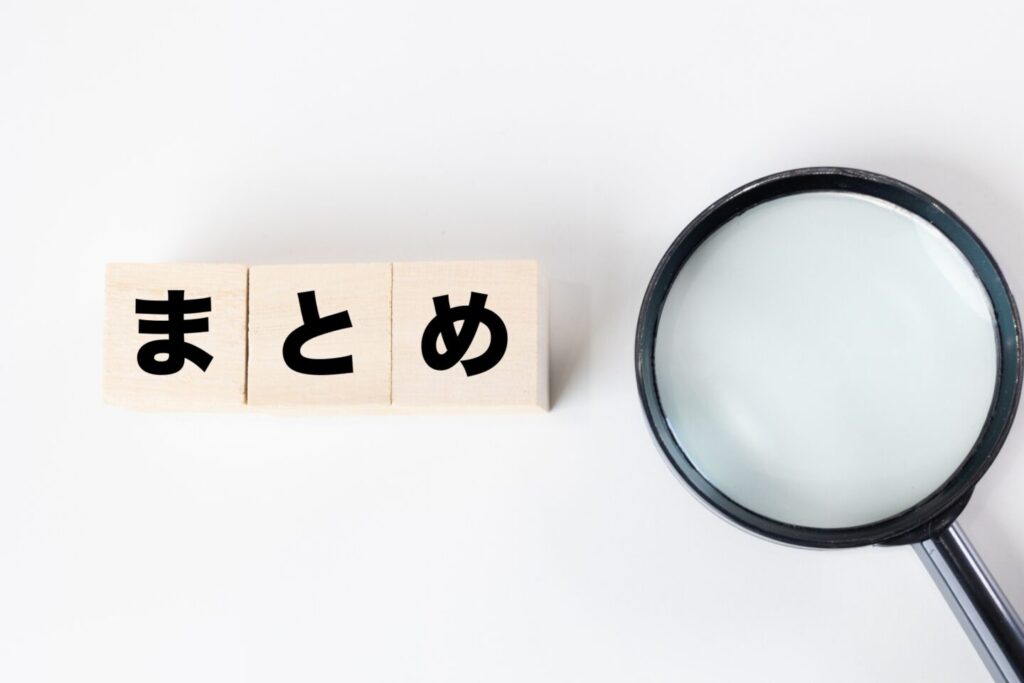
秘密保持契約書(NDA)は、情報漏洩を防ぐために企業が締結すべき重要な契約です。同意や承諾を得た上で、適切な契約書を締結することが重要です。また、テンプレートを利用しつつ、最新の法律に合わせてカスタマイズすることが必要です。契約の内容については、書面で会社の実情に合った形に整え、メリットを最大化するために、書式を適切に調整しましょう。
デジタル化が進む現代においては、秘密保持契約書を一から作成する必要はなく、雛形を活用することが可能です。また、電子契約も利用できるため、契約書を作成しやすくなっていると言えるでしょう。
雛形を活用する場合は、弁護士に作成を依頼することをおすすめします。テンプレートがあれば問題ないというわけではないため、専門家の意見やチェックを取り入れながら秘密保持契約書を作成していきましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。秘密保持契約書の作成やリーガルチェックを依頼したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












