- 法務救済
- コラム
- 予防法務
- 契約書・リーガルチェック
- 秘密保持契約書(NDA)の作成におすすめのテンプレートやクラウドサービスを解説!
秘密保持契約書(NDA)の作成におすすめのテンプレートやクラウドサービスを解説!
契約書・リーガルチェック
2025.03.26 ー 2025.03.28 更新
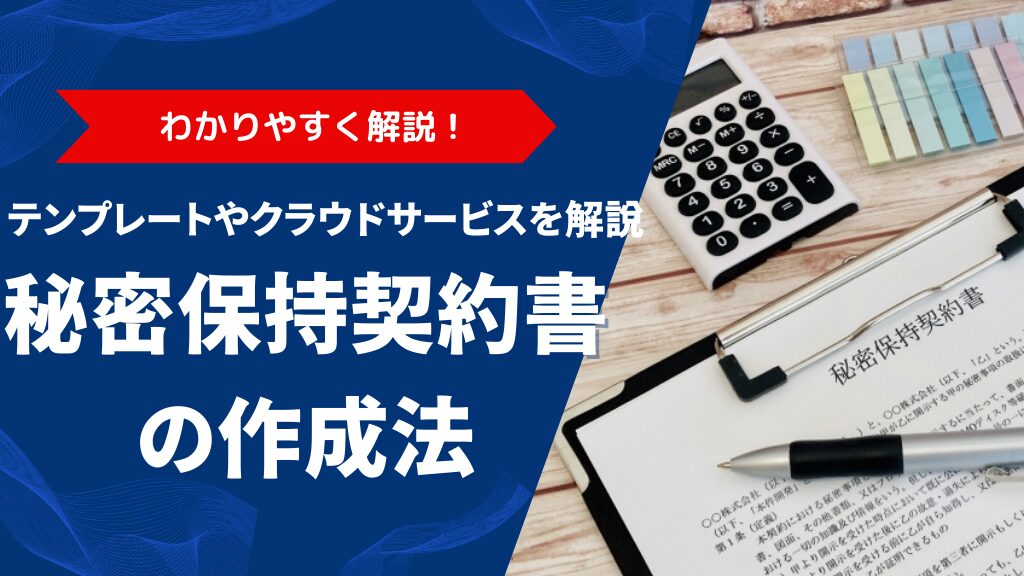
秘密情報の取り扱いに関するルールを定める秘密保持契約書(NDA)。企業活動において用いるケースが多いため、求められた際にはスムーズに書類を作成できるようにしておく必要があります。
秘密保持契約書を作成する際には、無料のテンプレートを活用するのがおすすめです。一から作成すると手間がかかるため、法務担当者にとっては大きな負担となるでしょう。
この記事では、秘密保持契約書の作成におすすめの無料テンプレートについて解説していきます。秘密保持契約書の内容や作成方法についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。秘密保持契約書の作成を弁護士に依頼したい方は、法務救済から探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>秘密保持契約書(NDA)とは?
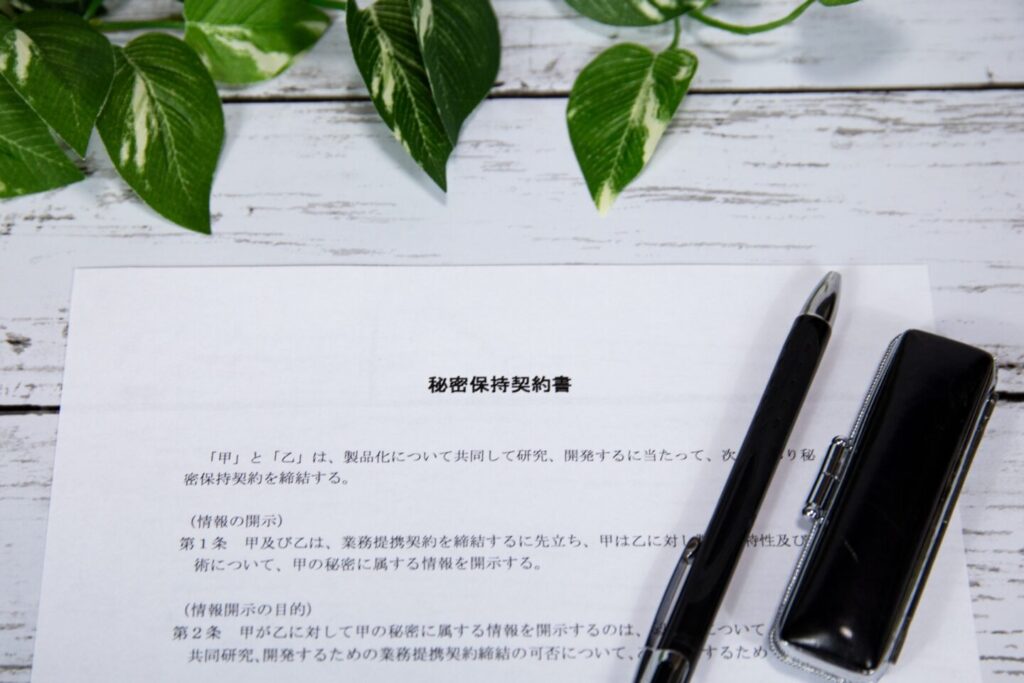
秘密保持契約書(NDA)は、企業や個人間で機密情報を保護することを目的とした法的文書です。機密情報の範囲や取り扱いルールを明確にし、不正利用や第三者への開示を防止します。
秘密保持契約を締結することで、知的財産の保護や競争優位性の確保につながります。また、企業機密の外部流出を防ぎ、取引先との信頼関係を構築するうえでも欠かせません。
NDAが必要になるケース
秘密保持契約書は、企業活動において機密情報を保護する重要な契約です。必要になるケースとして、以下のような場面が挙げられます。
- 新規事業の立ち上げ
- 企業間の共同開発プロジェクト、
- M&Aの検討段階
- フリーランスや外部コンサルタントとの業務委託契約時
- 機密性の高い業務を担当する従業員の入社時・退職時(研究開発部門や経営企画部門)
また、ベンチャー企業が投資家とのミーティングで事業計画や財務情報を開示する際も、NDAを締結することで機密情報を保護できます。
ただし、NDAの必要性はケースバイケースで異なり、常に締結すべきとは限りません。相手との信頼関係や情報の性質を考慮した上で判断しましょう。
秘密保持契約書の条項一覧

秘密保持契約書を作成する際には、以下のような条項を記載するのが基本です。これらの条項は、テンプレートに事前に記載欄があります。
- 機密情報の目的外利用の原則禁止
- 機密情報の複製に関する制限
- 契約終了における機密情報の取り扱い
- 情報漏洩時の報告義務
- 権利義務の譲渡禁止
- 反社条項
- 損害賠償に関する規定
- 秘密保持契約の有効期間
- 準拠法・管轄裁判所に関する規定
それぞれの条項の概要について解説していきます。
機密情報の目的外利用の原則禁止
「機密情報の目的外利用の原則禁止」は、受領者が提供された機密情報を、契約で定められた目的以外に使用してはならないという条項です。機密情報の不正使用や競争上の不利益を防ぎ、情報の適切な管理を確保します。
例えば、企業間で共同開発を行う際に技術情報を共有した場合、受領者はその情報を契約で定めた開発目的のみに使用しなければなりません。仮に受領者が競合企業と類似製品を開発するために流用した場合、契約違反となり、法的責任を問われる可能性があります。
この条項を明確に定めることで、情報提供者は安心して機密情報を共有でき、ビジネスの信頼関係を構築できます。また、契約には違反時の措置として、損害賠償請求や差止請求を定めることが一般的です。
機密情報の複製に関する制限
秘密保持契約書では、機密情報の複製に関する制限を設ける条項が含まれます。受領者が機密情報をどのように扱うべきかを明確にし、不正な流用や漏洩リスクを防ぐ目的で設定されます。
機密情報の複製に関する制限では、受領者が提供された情報を以下のように扱うことを、原則として禁止・制限します。
- 複製
- 記録
- コピー
- スキャン
ただし、契約で特別に許可された範囲内でのみ、業務遂行に必要な複製を認めるケースもあります。この場合、複製の数量や用途を限定し、不正利用を防ぐための管理体制を求めることが一般的です。
また、複製が必要な場合の手続きや管理方法も定められます。例えば、以下のようなルールが設けられることがあります。
- 複製する際は事前に書面で許可を得る
- 複製物には「機密」などの明確なラベルを付与する
- 複製物の保管場所や廃棄方法を指定する
契約終了時や機密情報の利用目的が終了した場合には、複製物を廃棄または返却する義務を負うケースもあります。
契約終了における機密情報の取り扱い
秘密保持の契約が終了したとしても、開示された機密情報の保護が解除されるわけではなく、一定期間または無期限にわたって守秘義務が継続する場合があります。こうした守秘義務についても、秘密保持契約書に記載します。
契約終了後の機密情報の取り扱いに関する条項では、情報の返還・廃棄義務が規定されます。開示を受けた側は、契約終了時に保有するすべての機密情報を返還または完全に削除・破棄する必要があります。紙媒体の資料は裁断処理、電子データは復元不可能な方法で削除することが求められるケースが多いです。
また、契約終了後も一定期間にわたり秘密保持義務を継続する規定が設けられます。例えば、「契約終了後3年間は機密情報を第三者に開示・漏洩しない」といった形で期間を定めることが多く、企業の競争力に関わる情報では無期限の義務が課されることもあります。
これらの規定を明確にすることで、契約終了後も機密情報の漏洩リスクを防ぎ、企業の信頼性を確保することが可能です。
情報漏洩時の報告義務
情報漏洩時の報告義務の条項は、秘密情報が第三者に漏洩した場合や漏洩の可能性が生じた際に、速やかに報告することを義務付けるものです。
報告義務の内容としては、漏洩の事実や状況を発覚後すぐに相手方へ通知し、調査を実施することが求められます。また、漏洩による影響を最小限に抑えるための対策を講じ、必要に応じて再発防止策を提示することも含まれます。
報告の期限については、発覚後〇〇日以内など具体的な期間を明記することで、迅速な対応を促すことが可能です。
この条項を設けることで、万が一の情報漏洩時に迅速な対応を取る体制を整え、被害の拡大を防ぐことができます。法的リスクや信用の失墜を防ぐためにも、適切に記載しましょう。
権利義務の譲渡禁止
「権利義務の譲渡禁止」は、契約当事者が契約上の権利や義務を第三者へ譲渡することを禁止する規定です。契約当事者間でのみ秘密情報を取り扱うことを保証し、情報の管理を厳格に行うために設けられます。
もし当事者が契約上の権利や義務を自由に譲渡できる場合、秘密情報を扱う相手が変わり、情報管理が不十分になるリスクが生じます。特に、情報の取扱いに慎重さが求められる業界や技術分野では、この条項の明記が重要です。
権利義務の譲渡禁止を定める条項は、以下のように記載します。
「当事者は、本契約上の権利および義務の全部または一部を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者へ譲渡、移転、または担保設定することはできない」
事業譲渡や合併などのケースでは、特例として譲渡が認められる場合もあります。このケースでは、契約条項に「相手方の同意がある場合」や「合併・事業譲渡など合理的な理由がある場合は適用外」といった例外規定を盛り込みます。
反社条項
反社会的勢力排除条項(反社条項)とは、契約の相手方が暴力団や詐欺グループなどの反社会的勢力と関係がないことを保証し、万が一関与が判明した場合に契約を解除できるようにするための規定です。
反社条項の目的は、企業が反社会的勢力と無意識に関与し、取引を行うリスクを排除することにあります。契約相手が反社勢力とつながりを持っていた場合、企業の社会的信用が損なわれるだけでなく、法的・経済的な損害を受ける可能性もあります。
反社条項には一般的に以下の内容が含まれます。
- 表明・確約の条文:暴力団やその関連団体、反社会的勢力に属していないことの証明
- 解除条項:契約期間中に相手方が反社勢力と関与した場合、即時に契約を解除できる旨
- 契約違反に関する条項:相手方が第三者を通じて不当な要求を行った場合の対策
企業のコンプライアンスが重視される現代において、反社条項はNDAを含む契約書の必須項目となっています。契約締結時には、この条項が適切に含まれているかを確認し、安全な取引環境を確保するようにしましょう。
損害賠償に関する規定
「損害賠償に関する規定」は、契約当事者が秘密保持義務に違反した場合の責任を明確にし、違反による損害を適切に補償するために設けられます。
損害賠償の対象となるのは、以下の2パターンがあります。
- 直接的損害:機密情報の不正開示や漏洩
- 間接的損害:営業上の信用失墜や顧客離れ
一般的には、違反した当事者は被害を受けた側に対し、発生した損害を賠償する義務を負います。
また、損害賠償額の算定方法についても規定します。一部の契約では、違反が発覚した場合に一定額の違約金を支払う「違約金条項」を設けることもあります。
実際に損害賠償請求を行うことになると、違反の事実や損害額を証明する必要があるため、秘密情報の管理体制を整え、契約違反が発生した際の対応方針を事前に検討しておくことが重要です。
秘密保持契約の有効期間
秘密保持契約の有効期間は、契約締結後、当事者が秘密情報をどの程度の期間守るべきかを定める条項です。
契約期間は、1〜5年程度に設定されることが一般的です。一方で、個人情報や企業の根幹に関わる技術情報などは、長期間もしくは無制限での機密保持が必要とされることがあります。
ただし、無期限の秘密保持義務は当事者間の負担が大きくなるため、合理的な期間を設定することが重要です。裁判例などでは、「過度に長い期間の義務は無効と判断される可能性がある」とされるため、業界の慣習や情報の重要度を考慮して期間を定めます。
記載方法としては、以下のように記載します。
- 「契約期間中および終了後○年間」
- 「契約終了後も○年間は秘密保持義務が継続する」
準拠法・管轄裁判所に関する規定
準拠法とは、契約の有効性や解釈、履行に関する法的基準として適用される法律を指します。国際取引や異なる法域の企業間でNDAを締結する場合、どの国・地域の法律を基準に契約を解釈するかを明確に定める必要があります。
例えば、日本企業同士の契約であれば「本契約の準拠法は日本法とする」と記載するのが一般的です。
管轄裁判所に関する記述は、契約に関する紛争が訴訟に発展した場合に、どの裁判所が判断を下す権限を持つかを定めるものです。例えば、「本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」と記載すれば、東京地方裁判所でのみ訴訟を提起できることになります。
日本企業同士での契約では重要視されにくいですが、海外企業との契約になると、準拠法や管轄裁判所をどの国にするかが交渉のポイントになります。日本の裁判所を指定しても、相手国での執行が難しい場合があるため、仲裁機関の利用を検討することもあります。
準拠法・管轄裁判所の規定を明確に定めることで、契約の安定性を高め、法的リスクを回避できます。
秘密保持契約書の無料テンプレート5選
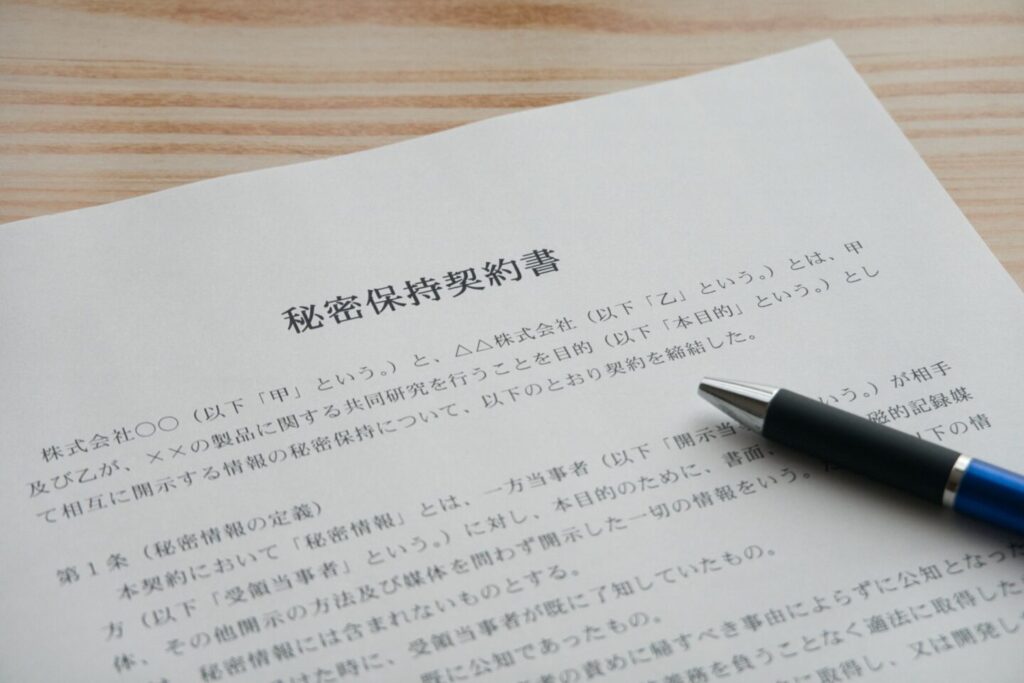
秘密保持契約書を作成する際は、テンプレートを活用するのがおすすめです。必要な項目があるため、契約内容を記載するだけで秘密保持契約書が完成します。
無料で利用できるおすすめのテンプレートは、以下の5つのサイトです。
- 経済産業省
- クレア法律事務所
- クラウドサイン
- 契約書の森
- テンプレートバンク
それぞれについて解説していきます。
経済産業省
経済産業省は、企業間取引や事業活動で必要となる秘密保持契約書のひな形を公開しています。これらのテンプレートは、企業が機密情報を適切に保護するための指針として活用されています。
経済産業省が作成した「秘密情報の保護ハンドブック」内の〖参考資料2〗各種契約書等の参考例(令和6年2月改訂版)では、NDAの具体的なサンプルが提供されています。
この資料は、経済産業省の公式ウェブサイトから無料でダウンロード可能であり、企業が自社の状況に合わせてカスタマイズする際の基礎資料として有用です。
クレア法律事務所
クレア法律事務所は企業法務を専門としており、秘密保持契約書を含む多様な契約書のテンプレートを無料で提供しています。会員登録やログインなしで即座にダウンロード可能であり、Word形式で提供されているため、ニーズに合わせて編集可能です。
クレア法律事務所の公式サイトでは、秘密保持契約書のひな形が複数掲載されており、案件に応じて適切な条項を盛り込むことが推奨されています。
クラウドサイン
クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。秘密保持契約書の無料テンプレートを提供しており、経済産業省のテンプレフォーマットを再現したWord形式のひな形をダウンロードできます。
また、他にも業務委託契約書や雇用契約書など、利用頻度の高い契約書のテンプレートを多数揃えており、すべて弁護士が監修しています。これらのテンプレートを活用することで、契約書作成の手間を省き、法的リスクを軽減することが可能です。
契約書の森
契約書の森は、弁護士・中小企業診断士が運営するサイトです。このサイトが提供する秘密保持契約書のテンプレートでは、以下のような条項を網羅しています。
- 契約締結の目的
- 秘密情報の定義
- 秘密保持義務
- 目的外使用の禁止
- 複製
- 返還または破棄
- 権利義務の譲渡等の禁止
- 責任及び損害賠償
- 有効期間
- 合意管轄
- 協議事項
各条項には赤字で解説が付されており、利用者が理解しやすいよう工夫されています。ただし、テンプレートは中立的に作成されていますが、契約の目的や状況に応じて条項の追加や調整が必要となる場合があります。
テンプレートバンク
テンプレートバンクは、企業や個人が利用できるテンプレートを提供するWebサイトです。秘密保持契約書の無料テンプレートも充実しており、取引上知り得る機密情報の取扱いを定めた契約書を簡単に作成できます。
これらのテンプレートは書面契約や電子契約のどちらにも対応しており、Word形式でダウンロード可能です。さらに、各テンプレートには更新日が記載されており、最新の法改正にも対応しています。
会員登録を行うことで、これらのテンプレートを無料で利用でき、ビジネスシーンでの契約書作成を効率化するのに役立ちます。
秘密保持契約は電子契約でも可能?

秘密保持契約は、電子契約でも締結可能です。近年では電子契約サービスの普及により、オンラインでの契約締結が増えています。
日本では電子署名法により、一定の要件を満たせば電子契約も書面契約と同様に法的効力を持つとされています。例えば、クラウド型の電子契約サービスを利用すれば、契約締結の手間を省きながら、安全に機密情報を保護できます。
電子契約を導入するメリットとして、印紙税が不要である点も挙げられます。書面契約の場合、契約金額に応じて印紙税が発生しますが、電子契約では非課税となるため、コスト削減につながります。また、署名や押印の郵送手続きが不要なため、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。
電子契約におすすめのサービス
電子契約サービスの中でも、クラウドサインとGMOサインは高い信頼性と使いやすさで多くの企業に採用されています。どちらも電子署名法に準拠し、秘密保持契約を含むさまざまな契約に対応可能です。
クラウドサインは、弁護士ドットコムが提供する電子契約サービスで、国内企業の導入実績が豊富です。シンプルなインターフェースで操作が容易なため、電子契約を初めて導入する企業でもスムーズに利用できます。
GMOサインは、GMOグローバルサインが提供する電子契約サービスで、電子署名とクラウド型の電子契約を併用できるのが特徴です。高いセキュリティ性を備えた電子認証技術を採用し、政府や大企業の利用実績も多数あります。
相手方が電子署名に対応していない場合でも、押印画像を利用した契約締結が可能な点が強みです。
テンプレート利用時の注意点
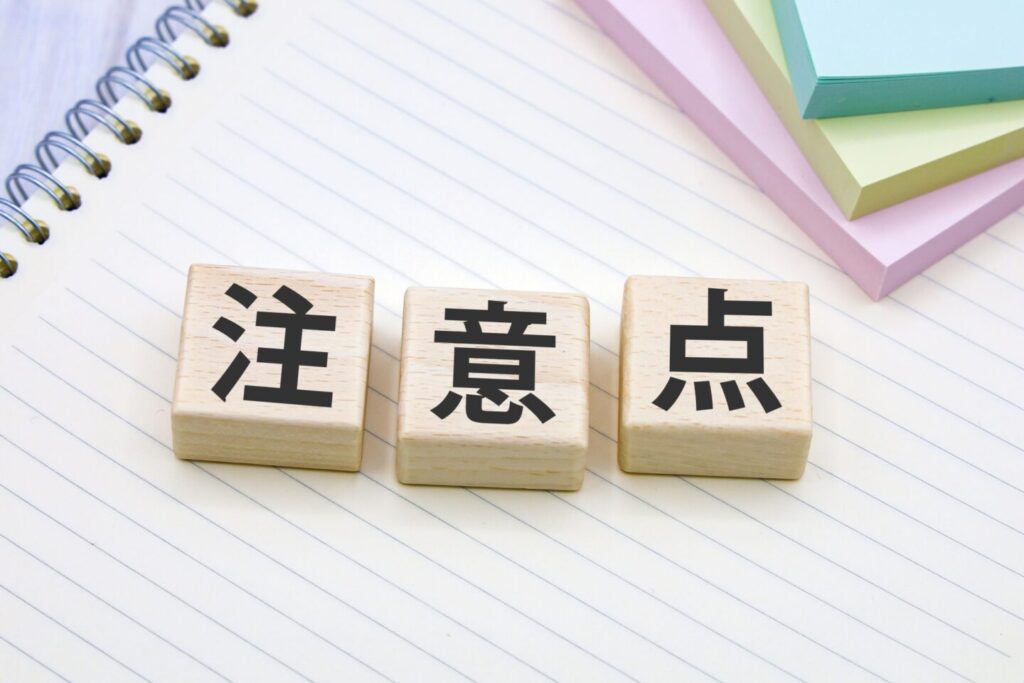
テンプレートを活用して秘密保持契約書を作成する場合、以下のような点に注意しなければいけません。
- 自社用にカスタマイズすることが不可欠
- 最新の法律に適しているかチェックする
- 弁護士にリーガルチェックを依頼する
それぞれの注意点について解説していきます。
自社用にカスタマイズすることが不可欠
秘密保持契約書のテンプレートをそのまま使用するのではなく、自社の状況に合わせてカスタマイズすることが不可欠です。企業ごとに秘密情報の範囲や管理方法、契約の目的は異なるため、一般的なフォーマットでは内容が不十分となる可能性が高いです。
自社の事業内容に応じて、どの情報を秘密情報とするか記載することで、後の紛争を防ぐことができます。また、秘密情報の開示範囲を調整し、どの従業員や取引先がアクセスできるのかを明確にすることも重要です。
さらに、テンプレートでは「契約終了後〇年間」といった記述が多いですが、業種や取引内容によっては、より長期間の保持義務が必要なケースもあります。例えば、技術開発に関する情報であれば、5年や10年といった長期間の保持が求められるでしょう。
テンプレートはあくまで参考資料であり、自社の実情に合った内容へ修正することが必須です。
最新の法律に適しているかチェックする
法律は随時改正されるため、古いテンプレートをそのまま使用すると、現在の法規制に適合しない可能性があります。秘密保持契約に関連する以下の法律が改正された場合、契約の有効性やリスク管理に影響を及ぼします。
- 個人情報保護法
- 不正競争防止法
- 電子契約に関する規定
旧来のNDAでは法律の変更が反映されていない可能性があるため、最新の法改正に対応した契約内容に修正する必要があります。また、電子契約が普及する中で、電子署名法に適合した契約書のフォーマットや締結方法を採用することも求められます。
テンプレートを利用する際は、提供元が信頼できるか、更新日が明記されているかを確認することが重要です。 これによって契約の有効性を確保し、将来的な法的リスクを回避することが可能となります。
弁護士にリーガルチェックを依頼する
秘密保持契約書のテンプレートを利用する際は、内容の適切性を確認するために、弁護士にリーガルチェックを依頼することが重要です。すべての取引や状況に最適化されているわけではなく、適用範囲や条項の内容が不十分な場合があるため、専門家の視点から契約の妥当性を確認・修正することが推奨されます。
秘密情報の定義や保持期間、情報の開示範囲などが曖昧な場合、契約締結後に解釈の違いが生じ、トラブルへ発展する可能性があります。そのため、弁護士によるチェックを受けることで、自社の利益を守りながら適切な契約を締結することが可能です。
弁護士にリーガルチェックを依頼する際は、以下のポイントを重点的に確認してもらいましょう。
- 秘密情報の範囲:自社の重要な情報が守られるか
- 契約解除や違反時の対応:違反時のペナルティが適切に定められているか
- 準拠法や管轄裁判所の指定:訴訟リスクを考慮した内容になっているか
弁護士によるリーガルチェックの費用は、契約内容や依頼する事務所によって異なりますが、数万円~十数万円程度が相場です。企業の顧問弁護士に依頼するほか、スポットで対応可能な法律相談サービスを活用する方法もあります。
まとめ

秘密保持契約書を作成する際は、テンプレートを活用するのがおすすめです。書類の形式から作成するのは時間がかかるため、弁護士事務所やクラウドサービスなどが提供しているテンプレートを利用することを推奨します。
特に経済産業省のテンプレートは、国が公開している雛形であるため、安全に利用することが可能です。
ただし、テンプレートを使って適切な秘密保持契約書を作成できるとは限りません。法的トラブルを回避する契約書を作成する際は、弁護士に相談してみましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。秘密保持契約書の作成やリーガルチェックを依頼したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。











