経営者必読!法人破産手続きの流れとリスクを解説
事業承継・相続対策
2025.02.22 ー 2025.03.05 更新
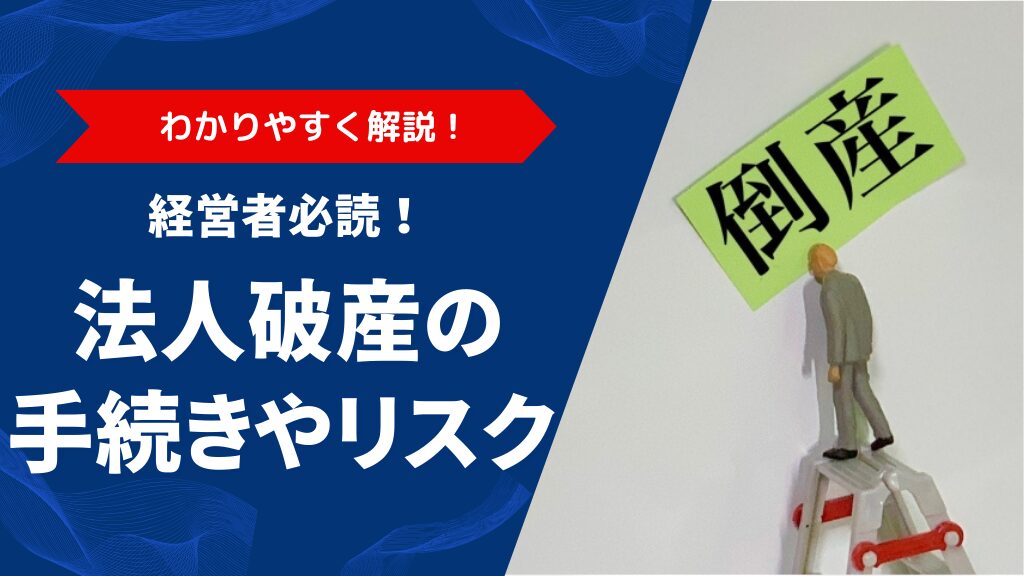
法人破産は、企業が債務を返済できなくなった際に取る最終的な手段です。この手続きにより会社は債務から解放され、清算して消滅します。破産手続きは、裁判所の管理下で進められ、債権者の利益を保護しつつ、公平な資産の分配を目指します。
法人破産の仕組みは複雑ですが、基本的には債務超過状態にある企業または疑いをもった債権者が裁判所に申立てを行うことから始まります。申立てが認められると、破産管財人が選任され、会社の資産を管理・換価する役割を担います。この過程で、債権者への返済や従業員の処遇などが決定されていきます。
破産手続の期間は案件によって異なりますが、通常数ヶ月から1年程度かかることが多いです。ただし、複雑な案件ではさらに長期化する可能性もあります。法人破産は経営者個人にも影響を及ぼす可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
法人破産と個人の自己破産の違い
法人破産と個人破産は、破産手続きの基本的な枠組みは共通していますが、いくつかの重要な違いがあります。法人破産の場合、会社という組織が破産するため、経営者個人の財産は原則として保護されます。一方、個人破産では個人の全財産が対象となります。
また、法人破産では会社の解散が前提となりますが、個人破産では生活の再建が目的となります。債務の免除についても、法人破産では会社の債務が消滅しますが、個人破産では免責手続きが別途必要な上に、一部の債務が残る可能性があります。
手続きの面でも違いがあり、法人破産は管財事件となり破産管財人が必ず選任されます。これに対し個人破産では破産開始決定と同時に廃止決定が行われるケースも多く、管財事件が必要な場合にのみ破産管財人が選任されます。さらに、法人破産によって会社は消滅しますが、個人は破産後も個人として再出発が可能です。
法人破産の流れ|申立てから破産手続き終了まで

法人破産は、法的な手続きとしては破産手続きの申立てから開始され、破産手続き終了まで複数のステップを経ます。
ただし、その前に会社の財産等を調査し、事業売却や民事再生、会社更生など破産以外の最適な方法を検討するステップも必要です。
以下では、破産を選択する場合の手続きの大まかな流れを次のステップに分けて解説していきます。
- Step1:弁護士への相談と意思決定
- Step2:従業員の解雇と事業の停止
- Step3:債権者への通知と会社財産の保全
- Step4:破産申立書の作成と必要書類の準備
- Step5:裁判所へ破産手続きの申し立てを行う
- Step6:破産管財人による財産の整理・売却
- Step7:債権者集会での説明と手続き進行
- Step8:配当手続きの完了と法人消滅
Step1:弁護士への相談と事前準備
経営状況が悪化し、破産を検討せざるを得ない状況に陥った場合、早めに専門家のアドバイスを求めることが重要です。破産や再生に精通した弁護士に相談することで、現状の正確な把握と今後の方針決定が可能となります。
弁護士との初回相談では、会社の帳簿や財務諸表、契約書類などの重要書類を整理します。また、債権者リストの作成や従業員への説明準備も必要です。これらの情報を基に会社の財務状況や負債の詳細、資産の状況などを相談し、再建が可能なのか他の選択肢も含めて今後の方針を検討します。
判断基準はさまざまですが、以下の点などを考慮する櫃ようがあります。
- 経営者、従業員に再建の意欲とスキルがあるか
- 借り入れなく当面の間の運転資金が確保できるか
- 取引先との取引が継続できるか
- 破産の予納金を準備できるか
相談の結果、破産が最適な選択肢と判断された場合、事業停止の日程を決めるなど具体的な準備に入ります。
ただし、弁護士への相談費用や準備にかかる時間的コストは、会社の状況によって大きく異なる可能性があります。また、事前準備の段階で予期せぬ問題が発覚することもあるため、柔軟な対応が求められます。
Step2:従業員の解雇と事業の停止
破産手続きを行うと決めたら、従業員に対しては破産手続きの開始を伝え、雇用契約の終了を通知する必要があります。
この際には労働基準法に基づき、30日前の予告か、30日分以上の平均賃金を支払うことが求められます。ただし会社の資金状況によっては未払い賃金が発生する可能性もあります。
テナントの明け渡しについては、賃貸借契約を解除し、物件を所有者に返還する手続きを進めます。契約内容によっては違約金が発生する場合もあるため、慎重な対応が求められます。またオフィス内の備品や設備の処分も必要となり、これらの作業には一定の時間を要することがあります。
従業員の解雇とテナントの明け渡しは、会社の実質的な活動終了を意味するため、関係者への配慮と適切な対応が求められます。
特に従業員に対しては、再就職支援や社会保険の手続きなど、可能な範囲でのサポートを検討することも重要です。これらの手続きを適切に行うことで、円滑な破産手続きの進行につながります。
Step3:債権者への通知と会社財産の保全
破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士が代理人になった旨の受任通知を債権者に送付します。弁護士が代理人になることにより、債権者は当事者である会社への請求や取り立てをストップさせます。
弁護士は裁判所によって破産管財人が選任されるまで、会社財産が散財しないように管理します。
Step4:破産申立書の作成と必要書類の準備
申立書には会社の財務状況や債務の詳細、破産に至った経緯などを正確に記載する必要があります。多くの場合、弁護士の助言を得ながら作成することが望ましいでしょう。
申立書と共に提出する必要書類には、決算書や税務申告書、債権者一覧、資産目録などが含まれます。これらの書類は会社の経理担当者や税理士と協力して準備することになるでしょう。特に債権者一覧の作成には細心の注意を払い、漏れがないよう確認することが重要です。
また、破産手続開始決定後に裁判所に提出する財産目録や貸借対照表なども、この段階で準備を始めておくと良いでしょう。
申立書や必要書類の作成には通常1〜2週間程度を要しますが、会社の規模や状況によっては更に時間がかかる場合もあります。慎重に準備を進めつつ、できるだけ迅速に対応することが求められます。
Step5:裁判所へ破産手続きの申し立てを行う
破産申立書と必要書類が揃ったら裁判所に提出します。通常、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に申し立てを行いますが、代表者個人の破産申立を同時に行う場合、代表者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てることも可能です。
申し立ての際には、弁護士が代理人として手続きを行うことが一般的です。裁判所に提出する書類には、破産申立書のほか、財産目録や貸借対照表、債権者一覧などが含まれます。
申し立てが受理されると、裁判所は各書類を調査し、破産手続開始決定を行います。この決定により、会社の財産管理権が裁判所に移り破産管財人が選任されます。破産手続開始決定は官報や裁判所の掲示板で公告され、債権者に通知されます。
なお、申立ての際には予納金の納付が必要となります。予納金の額は会社の規模や財産状況によって異なりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。この予納金は破産手続きの費用に充てられます。
Step6:破産管財人による財産の整理・売却
裁判所から選任された破産管財人は、破産財団の管理と換価を担当します。まず破産会社の全ての財産を調査しリストを作成します。これには不動産のほか、動産、債権、知的財産権などが含まれます。次にこれらの財産を適切に評価し、最も有利な方法で売却を進めます。
不動産や高額な設備は競売にかけられることが多く、在庫品や備品は一括売却や個別売却が行われます。債権回収も破産管財人の重要な業務の一つです。また、破産前に行われた不適切な取引の有無も調査し、必要に応じて否認権を行使します。
ただし、財産の換価には時間がかかることもあり、市場の状況によっては予想以上に時間を要する場合もあります。
破産管財人は、債権者の利益を最大化するため、適切なタイミングと方法で財産の処分を進めていきます。このプロセスは、法人破産手続きの中でも特に専門性が求められる部分といえるでしょう。
Step7:債権者集会での説明と手続き進行
債権者集会は法人破産手続きの重要な段階です。この集会では、破産管財人が債権者に対して破産者の財産状況や破産に至った経緯を説明します。
通常、裁判所で開催され債権者が一堂に会する機会となります。破産管財人は、財産の換価状況や配当見込みについても報告を行い、債権者からの質問に答えます。
集会では、破産手続きの進行について債権者の意見を聴取することもあります。例えば、財産の処分方法や破産者の免責に関する意見を求めることがあります。ただし、債権者集会での決議には法的拘束力がないため、最終的な判断は裁判所が行います。
債権者集会の開催回数は案件によって異なりますが、通常は1回から数回程度です。複雑な案件では追加の集会が必要になることもあります。
債権者集会は、破産手続きの透明性を確保し、債権者の理解を得るための重要な機会となります。
Step8:配当手続きの完了と法人消滅
配当手続きの完了は、法人破産の最終段階を意味します。
破産管財人が債権者に対して配当を行い、全ての債権者への支払いが終わると、法人は正式に消滅します。この過程では、残余財産の清算と債権者への分配が厳密に行われ、公平性が保たれます。
清算が完了すると法人は消滅し、会社の登記が閉鎖されることで法人格が失われます。これにより、その法人の権利義務関係は全て終了し、事業活動を行うことは不可能となります。
ただし、破産手続き終了後も、税務上の処理や未解決の法的問題が残る可能性があるため、注意が必要です。
破産手続きの終結により、債務者である法人は債務から解放されますが、個人保証を行っていた役員等は別途対応が必要となる場合があります。
法人破産後の影響

法人破産後の影響は、経営者や関係者にとって大きな課題となります。経営者は、破産手続きが完了してもその責任から完全に逃れることはできません。
破産法に基づき経営者個人の財産が保護される場合もありますが、不正行為や重大な過失があった場合は、個人資産の差し押さえなどの制裁を受ける可能性があります。
また、破産後の事業再開には制限が課されることがあります。一定期間、同業種での起業や役員就任が禁止されるケースもあり、再起の障壁となることも考えられます。さらに取引先や金融機関との関係性も悪化し、信用回復には相当な時間と努力を要するでしょう。
一方で破産によって債務が整理されることで、新たなスタートを切るチャンスともなります。経営者は、破産後の生活設計や再起に向けた準備を慎重に行う必要があります。
法人破産をする際の注意点とリスク
法人破産を検討する際には、様々な注意点とリスクを十分に理解しておくことが重要です。
まず破産手続前の資産処分には細心の注意が必要です。特定の債権者を優遇する弁済や不適切な処分は破産法による否認の対象になるほか、財産隠しは詐欺破産罪として刑罰の対象になる場合があります。
また、取引先や従業員への影響も考慮しなければなりません。突然の破産は信用の失墜や雇用問題につながる恐れがあるため、適切な対応が求められます。
経営者個人の責任や影響も無視できません。法人格が消滅しても、個人保証や不正行為があった場合または合名会社・合資会社の無限責任社員となっている場合、代表者等の個人も破産申請をしなければならない場合があります。法人破産の際は、個人での生活への影響も考慮すべき点です。
一方で、破産手続きを進める上での準備不足やタイミングの見極めミスも大きなリスクとなります。必要書類の不備や不適切な時期の申立ては、手続きの遅延や複雑化を招く可能性があります。これらのリスクを最小限に抑えるためには、専門家のアドバイスを受けることが賢明です。
法人破産をスムーズに進めるための準備とポイント
法人破産を円滑に進めるには、事前の準備と重要なポイントを押さえることが不可欠です。
まず、財務状況を正確に把握し、必要な書類を整理することから始めましょう。破産手続きに必要な決算書や帳簿類、債権者リストなどを準備することで、手続きがスムーズに進みやすくなります。
また、破産を検討するタイミングの見極めも重要です。資金繰りが厳しくなった段階で早めに専門家に相談することで、より適切な対応が可能になることがあります。ただし、この判断は難しい面もあり、経営者の心理的な葛藤も伴うでしょう。
経営が困難な状況ではこうした調査が難しい場合もあるかもしれません。また、複数の会社を経営している場合で一方の会社が負担となるケースもあります。
経営についての負担が大きくなっている場合、早めに税理士や弁護士に相談すると良いでしょう。
経営難に関する問題を弁護士に相談するメリット

経営に関するさまざまな問題は専門知識を持つ弁護士に相談することが非常に重要です。
弁護士は法的な観点から適切なアドバイスを提供し、複雑な手続きをサポートしてくれます。また、債権者との交渉や必要書類の作成などの作業を代行できるため、経営における法的問題に関する負担を大幅に軽減できます。
また破産だけでなく、民事再生や会社更生、事業売却等の解決方法が見つかる可能性もあります。破産後の再起に向けた助言も得られるため、将来的な事業再建の可能性も広がります。
さらに法的な手続きを確認することで見通しがわかるため精神的にも安定が得られ、クリアな思考で行うべき行動が分かってくるでしょう。
コミュニケーション能力が高く、最適な解決を目指すことができる弁護士を選ぶことが望ましいでしょう。費用面についても事前に確認し、十分な納得を得た上で依頼することが大切です。
弁護士・法律事務所の検索には『法務救済』をご利用ください
法務救済は『エリア』と『相談内容』から相談者にあった法律事務所を検索できるサービスです。登録不要、手数料不要で利用できますので、以下のリンクからぜひご利用ください。
当サイトで紹介する法律事務所へは無料相談が可能です。経営難に関する相談は早めが大切ですので、この機会にまずはご相談してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>司法書士 白河(筆名)
2019年司法書士登録 補助者時代から複数の事務所勤務を経て2021年独立。同時にWebライター・記事監修業務を開始。 できるだけ一般的な表現での記事作成を心がけているます。法律関係の諸問題は、自己判断せずに専門家に相談することが解決への近道です。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












