自己破産と生活保護の両立は可能?債務整理や手続きの流れを解説|弁護士に相談すべき理由
民事再生・法人破産
2025.11.01 ー 2025.11.05 更新

借金問題で生活に不安を抱え、自己破産や生活保護の利用を検討している方もいるでしょう。これらはあなたの生活再建を支える制度であり、適切な活用で新しい一歩を踏み出せます。

自己破産と生活保護の基礎知識

自己破産とは?どんな場合に選ぶべきか
自己破産は、裁判所を通して借金の返済義務を免除してもらう法的な手続きです。事業の失敗や保証債務などで収入に対して借金が過大になった場合、任意整理や個人再生でも解決が難しい状況で選ばれることが多い制度です。
例えば、月収15万円で事業資金や保証債務が合計500万円を超えるようなケース。返済に5年以上かかる、高齢で収入増が見込めない、病気で働けないといった状況であれば、自己破産が現実的な選択肢となります。
デメリットとして、手続き中は一部の職業に就けない制限があったり、約7年間は信用情報に記録が残り、新たな借り入れが難しくなったりします。しかし、これらを上回るのが、借金という重荷からの解放という大きなメリットです。
生活保護とは?受給条件と支給内容
生活保護は、憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための、最後のセーフティーネットです。病気や高齢、失業などで生活に困窮した方に、国が最低限の生活費を支給し、自立を支援します。
主な受給条件は以下の通りです。
- 世帯全体の収入が、厚生労働省が定める最低生活費を下回っていること
例:東京都区部単身世帯の場合、住宅扶助を含め月額約13万円程度が目安。 - 預貯金や不動産など、活用可能な財産は原則として処分し、生活費に充てていること。
- 働く能力がある場合、就労に向けた努力が求められます。
- 親族からの援助が期待できない状況であること。
生活保護の支給内容は、以下の8つの扶助に分かれます。
- 生活扶助(食費・光熱費など)
- 住宅扶助(家賃)
- 医療扶助(医療費)
- 介護扶助
- 教育扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
中小企業の経営者や個人事業主の場合、事業用資産の扱いに注意が必要です。収益が見込める場合は保有が認められる可能性もありますが、判断は複雑なため専門家への相談が不可欠です。申請から決定までは原則14日以内(特別な理由があれば30日以内)ですが、調査に時間がかかることも。制度を理解し、専門家への相談も検討しましょう。 専門家への相談はこちらから>>>
自己破産と生活保護は両立できる?条件・注意点を詳しく解説
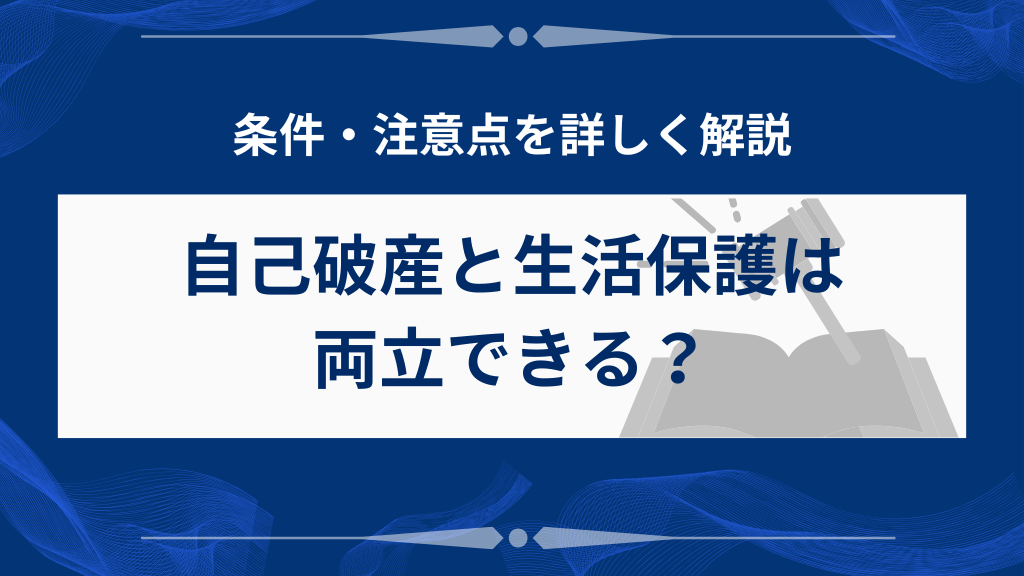
自己破産しても生活保護をもらえる?基本的な受給条件
自己破産と生活保護は法的に両立可能な制度です。生活保護の受給は、過去に自己破産をしたかどうかではなく、「現在の生活困窮度」で判断されます。自己破産歴があっても、今の収入や資産が生活保護の基準を下回っていれば、受給対象となる可能性は十分にあります。
生活保護の基本的な受給条件は、以下の3点です。
- 資産の活用: 預貯金が生活保護基準額の半月分程度以下であること。換金できる資産は原則として処分済であること。
- 能力の活用: 病気やケガなどで働けないか、働いていても収入が最低生活費を下回っていること。
- 扶養義務者からの扶養: 親族からの経済的支援が期待できない状況であること。
自己破産で借金が免責されると、返済義務がなくなるため「真の困窮状態」が明確になり、生活保護の受給条件を満たしやすくなる側面もあります。大切なのは、今の生活状況を正確に伝え、必要な支援を求めることです。
生活保護受給中でも自己破産は可能?流れと注意点
生活保護受給中でも、自己破産の手続きを行うことは可能です。生活保護を受けている方の中には、生活再建のために自己破産を検討するケースが少なくありません。
生活保護受給中に自己破産をすることには、次のようなメリットがあります。
- 予納金の負担軽減: 裁判所へ納める予納金が、生活保護受給者の場合、減額・免除される可能性があります。
- 弁護士費用の立て替え制度: 法律扶助制度を活用すれば、弁護士費用も立て替え払いを受けられるでしょう。
- 生活の安定維持: 生活保護費は差押禁止財産として法的に保護されており、手続き中でも安定した生活を維持できます。
手続きは、まず担当のケースワーカーに相談し、その後法律相談を利用して専門家とともに進めます。注意点として、破産手続き中は一部の職業に資格制限が生じる場合があります。また、生活保護費から弁護士費用を支払うことは認められていません。
自己破産歴が生活保護審査に与える影響
自己破産歴それ自体が、生活保護の受給を妨げる要因になることはありません。生活保護は「最低限度の生活を営む権利」を保障する制度であり、過去の経済的失敗を理由に支援を拒否することは制度の趣旨に反するからです。
福祉事務所が審査で重視するのは、「現在の生活困窮の状況」です。現時点での収入、資産、健康状態、家族構成などが主な判断材料となります。自己破産歴があることで、借金返済の負担がない状態として、困窮度を正確に把握しやすくなる側面もあります。
自己破産に至った経緯について質問・問い合わせされる可能性はありますが、これは審査のための情報収集であり、責任を問うものではありません。病気やリストラ、事業の失敗等、やむを得ない事情であれば、支援の必要性を裏付ける材料として理解されます。大切なのは、今の状況を正直に伝えることです。
自己破産・生活保護の両方を検討する場合のよくある誤解
自己破産と生活保護を両方検討する際、多くの誤解があります。
- 「どちらか一方しか選べない」: 実際には、これらは目的が異なる制度であり、状況に合わせて併用したり、順序を選んだりすることが可能です。
- 「生活保護を受けていると自己破産できない」: 生活保護受給中でも自己破産の手続きは可能です。支援制度を使えば費用面の心配も減らせます。
- 「自己破産すると生活保護を受けられなくなる」: 自己破産は借金をリセットする手続きであり、その後の生活困窮に対する支援を妨げるものではありません。
- 「どちらの制度も恥ずかしい」: これらは法律で定められた正当な権利であり手続きです。適切な制度を活用することは、賢明な判断と言えるでしょう。一人で抱え込まず、弁護士や司法書士、福祉事務所などの専門家に相談し、最適なサポートをしてもらうことが大切です。
一人で抱え込まず、弁護士や司法書士、福祉事務所などの専門家に相談し、最適なサポートを受けることが大切です。

自己破産・生活保護の手続きの流れと必要書類
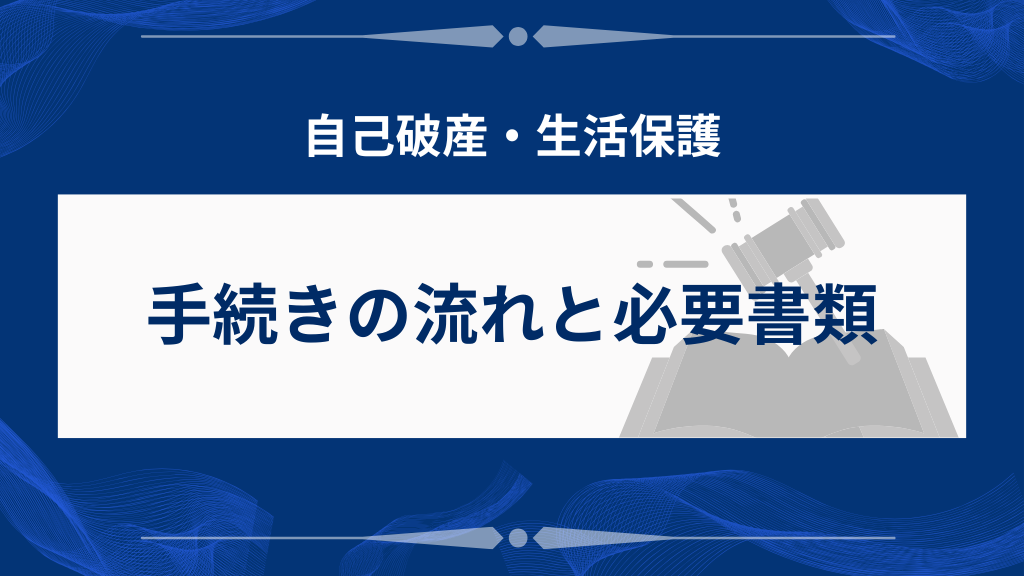
自己破産の手続きと必要書類(費用も解説)
自己破産の手続きは「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれ、財産がほとんどない場合は同時廃止事件となり、比較的簡素です。
まず、債権者一覧表の作成と借入状況の整理が重要です。全ての借入先と残高を正確に把握しましょう。
主な必要書類は以下の通りです。
- 本人確認書類: 住民票、戸籍謄本など。
- 収入関係書類: 給与明細書、源泉徴収票、年金通知書、保護決定通知書など。
- 財産関係書類: 預貯金通帳のコピー、不動産登記簿謄本、生命保険証券、車検証等
特に預貯金通帳は、資金の流れを詳しくチェックされるため、記帳漏れがないか注意が必要です。
費用は、裁判所に納める予納金と弁護士費用が主です。
| 費用の種類 | 金額の目安 |
| 予納金(同時廃止事件) | 1万円〜3万円程度 |
| 予納金(管財事件) | 最低20万円 |
| 弁護士費用(着手金) | 20万円〜40万円程度 |
費用に不安がある場合は、民事法律扶助を利用することで、分割払いや、生活保護受給者の場合は償還免除も可能です。手続きは、弁護士との委任契約から始まり、受任通知送付後に督促が止まります。その後、申立書類準備、裁判所への申立て、破産手続開始決定、免責許可決定へと進みます。
生活保護申請の手続きと必要書類
生活保護の申請は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で行います。まずは福祉事務所での相談から始め、生活状況や他の社会保障制度の利用可能性、親族からの援助の可能性などを話し合います。
正式な申請に必要な書類は次の通りです。
- 保護申請書(福祉事務所で入手)
- 本人確認書類
- 預貯金通帳のコピー
- 収入申告書、資産申告書
- 扶養義務者に関する書類
- 健康保険証、年金手帳、各種手当の受給証明書など
- 収入に関する書類(給与明細書、年金・手当の受給証明書、失業給付金受給資格者証など)
- 住居に関する書類(賃貸借契約書、家賃・光熱費領収書など)
審査期間は原則14日以内(特別な理由があれば30日以内)です。この間に、ケースワーカーによる家庭訪問、金融機関への資産調査、扶養義務者への照会などが行われます。特別な事情があれば扶養照会をしないよう配慮されることもあります。
各手続きの期間と進め方のコツ
自己破産の期間は、弁護士に依頼してから免責許可決定までトータルで6ヶ月から10ヶ月程度を見込んでおく必要があります。同時廃止事件の方が短期間で済みます。
期間を短縮するコツは、書類準備を完璧に目指しすぎず、8割程度揃ったら弁護士と相談し、並行して進めることです。
生活保護の申請から決定までは最短14日ですが、実際には1ヶ月程度かかることも少なくありません。申請を急ぎたい場合は、事前相談で必要書類のリストをもらい、準備を整えてから正式申請に臨むと良いでしょう。
両方の手続きを同時に進めるなら、生活保護の申請を先に進め、受給開始後に自己破産の手続きを行う方がスムーズな場合が多いです。生活保護受給中であれば、自己破産の弁護士費用が償還免除の対象となりやすいメリットがあるためです。ただし、債権者からの督促が厳しい場合は、自己破産の受任通知を先に送ることを優先することもあります。
手続きは複雑なため、一人で抱え込まず専門家のサポートを得ることで、効率的に進められ、新しい生活への第一歩を踏み出せるでしょう。
どちらを先にするべき?最適な順番と選び方

自己破産と生活保護の手続きには、それぞれ異なるメリットと注意点があります。あなたの状況に合わせた最適な順番を選ぶことが、スムーズな生活再建への鍵となります。
自己破産→生活保護の流れとメリット
自己破産を先に行う最大のメリットは、借金という重荷を完全に取り除いてから生活保護の申請に進めることです。精神的な負担が大幅に軽減され、生活保護受給後の家計管理もシンプルになります。
まず自己破産の申立てを行い、免責許可決定を受けます。その後、借金がゼロになった状態で生活保護を申請します。この方法であれば、生活保護のケースワーカーに借金は解決済みと説明でき、審査もスムーズに進みやすくなります。
自己破産の手続き費用は立替制度を利用できる場合もあり、生活困窮状態の方なら月々5,000円程度の分割払いで済むケースが多く、生活保護受給開始後は償還が猶予され実質的な負担はほとんどありません。ただし、自己破産の手続き期間中の生活費確保が課題となる場合があるため、専門家と資金計画を立てておくことが重要です。
生活保護→自己破産の流れとメリット
生活保護を先に受給する最大のメリットは、生活の基盤を安定させてから借金問題に向き合える点です。日々の食事や住居の心配がなくなることで、冷静な判断力を保ちながら自己破産の手続きを進めることが可能になります。
この方法では、まず福祉事務所で生活保護を申請し、受給が始まった後に自己破産の準備を始めます。生活保護受給中でも立替制度は利用でき、弁護士費用の心配は不要です。むしろ、生活保護受給者は援助条件を満たしているため、手続きがより円滑に進むケースも多いです。
ただし、生活保護のケースワーカーには借金の存在を正直に報告することが必要です。申請時から「借金問題も並行して解決する予定です」と伝えておくのが安心です。
並行して進める場合のポイント
自己破産と生活保護の申請を同時期に進めることも可能です。この方法は、手持ち資金が極めて少なく、どちらか一方を先にすること自体が難しい方に適しています。
並行して進める上で大切なのは、両方の手続きに詳しい専門家に相談することです。弁護士とソーシャルワーカーが連携すれば、お互いの手続きが相乗効果を生み出すこともあります。
ただし、並行する場合は注意深い調整が求められます。生活保護申請時には現在の借金総額を正確に報告し、自己破産申立て時には生活保護申請中または受給予定であることを裁判所に伝える必要があります。また、両方の手続きで提出する書類に矛盾がないよう、事前の準備と確認も欠かせません。
一人で悩まず、法律と福祉に詳しい専門家に相談し、最適な進め方のアドバイスを受けることが、人生再出発への確実な一歩です。
経営者が知っておくべき法人破産と従業員支援

事業が思うようにいかない時、経営者として最も心配なのは、従業員や取引先への影響でしょう。法人破産や債務問題は決して他人事ではありません。適切な知識と早期の対応が、重要な局面を左右します。
法人破産と個人破産の違い・経営者保証の扱い
法人破産と個人破産は、手続きの主体が異なり、その後の生活や事業への影響も大きく変わります。法人破産では会社という法人格が消滅し、法人が抱えていた債務も原則として消滅します。一方、個人破産は経営者個人の債務を整理する手続きです。多くの中小企業では、経営者が会社の借り入れに対して個人保証をしているため、法人破産だけでは問題が解決しないケースが大半です。
「経営者保証」については、「経営者保証に関するガイドライン」があり、一定条件を満たせば保証債務の整理がしやすくなる場合があります。法人の資産・経理が明確に分離されており、法人の資産だけで相当程度の弁済が可能な場合などです。このガイドラインを活用することで、経営者の自宅など最低限の生活基盤を残しながら保証債務を整理できる可能性も開かれます。ただし、適用には金融機関との合意が必要なため、早期に専門家へ相談することが重要です。
従業員が債務問題を抱えた際の会社としての対応方法
もし従業員から債務問題の相談を受けたら、会社としてどのような支援ができるでしょうか。
最も重要なのは、従業員のプライバシーを十分に配慮し、適切な相談先を紹介することです。多くの自治体には無料の法律相談窓口があり、公的機関も利用できます。会社として直接的な金銭支援が難しくても、勤務時間中の相談対応への配慮や、必要に応じた休暇の取得支援は行えるでしょう。
給与の前払いや貸付制度も一つの方法ですが、会社の財務状況を慎重に検討した上で判断すべきです。会社の資金繰りが厳しい状況では、従業員への支援が会社全体のリスクを高める可能性もあります。
従業員の債務問題が業務に影響する場合、人事労務の観点からも適切な対応が求められます。単純な解雇ではなく、まずは従業員と話し合い、問題解決に向けた支援や適切な解決策を一緒に検討することが大切ですし、ハラスメントに発展しないよう注意が必要です。
事業継続困難時の従業員への影響と支援制度
会社の経営が悪化し、事業継続が困難になった時、従業員への影響は避けられません。しかし、適切な制度を活用することで、従業員の生活への打撃を最小限に抑えることができます。
まず、労働基準法に基づく解雇予告や解雇予告手当の支払いは、会社の義務として確実に履行すべきです。30日前の予告、または30日分以上の平均賃金の支払いが基本です。
未払い賃金については、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する「未払賃金立替払制度」を活用できます。この制度は、企業が倒産した際に、未払い賃金や退職金の一部を国が事業主に代わって支払うものです。
雇用保険の失業給付は、会社都合による離職の場合、自己都合退職よりも有利な条件で受給できます。給付制限期間がなく、給付日数も長くなるため、従業員にとっては重要な生活保障となります。事業主として、離職票の交付や必要な手続きを迅速に行うことが大切です。
経営者自身の自己破産が会社・従業員に与える影響
経営者個人の自己破産が、会社や従業員に与える影響は、会社の法的形態や経営者の役割によって大きく変わります。
株式会社の場合、経営者個人の破産が直接会社の存続に影響することはありません。しかし、経営者が会社の中心を担っている場合、取引先との関係悪化や資金調達の困難化は考えられます。個人事業主の場合は、事業そのものの継続が難しくなるケースが多く、従業員は離職を余儀なくされるため、各種制度の活用がより重要です。
経営者が破産を検討する際は、会社の事業継続可能性も同時に検討し、可能であれば事業譲渡や経営者交代なども選択肢となります。破産手続き中は、取締役など一部の職業制限がありますが、復権すれば再び就任可能です。
これらの複雑な問題に直面した際、経営者一人で判断するのは非常に困難です。弁護士や司法書士などの専門家へ早期に相談し、法的な手続きだけでなく、従業員への影響や今後の事業継続性なども含め、総合的に検討することが重要です。
弁護士・司法書士に相談すべき理由と選び方

経営難や個人的な債務問題で、毎日不安を抱えていませんか。「弁護士費用が高そう」「自分で手続きできるかも」と迷っているうちに、状況がさらに悪化してしまうケースも少なくありません。
専門家に任せるメリットと費用相場
債務整理を専門家に依頼する最大のメリットは、債権者からの督促がすぐに止まる点です。弁護士や司法書士が受任通知を送付した時点で、貸金業法により債権者は直接あなたに連絡できなくなります。精神的な負担が大幅に軽減されるでしょう。
さらに、専門家は債権者との交渉において圧倒的な優位性を持っています。利息制限法に基づく引き直し計算で過払い金が発生している可能性もあり、専門家は過去の判例や業界慣行を熟知しているため、現実的な返済条件を提示できます。
費用相場は以下の通りです。
| 手続きの種類 | 着手金(目安) | 成功報酬(目安) |
| 任意整理 | 1社あたり2万円〜5万円程度 | 減額できた金額の10%〜20% |
| 自己破産 | 30万円〜50万円程度 | なし(または含) |
| 個人再生 | 35万円〜60万円程度 | なし(または含) |
専門家に依頼することで得られる減額効果や時間的なメリットを考えると、多くの場合で費用対効果は十分に見込めるでしょう。特に事業主の場合、手続きに時間を取られると本業に支障が出ることも。専門家に任せ、事業の立て直しや収入確保に専念することで、長期的に経済的メリットが得られるでしょう。
「自分でやる」と「専門家に依頼」の違い
自分で債務整理を行う場合と専門家に依頼する場合とでは、手続きの難易度と結果に大きな差が生まれます。個人では債権者との交渉が難航しがちですが、弁護士や司法書士からの連絡であれば、債権者も交渉に応じる姿勢を見せることが多いものです。
書類作成の精度も大きく異なります。自己破産や個人再生の申立書は膨大な書類が必要で、不備があれば手続きが遅れたり却下されたりする可能性もあります。裁判所での面談でも、専門知識がないまま臨むと不利な印象を与えてしまうリスクがあります。
時間的な負担も無視できません。債務整理の手続きには平均して3ヶ月から1年程度かかりますが、この間、債権者への対応や書類収集、裁判所とのやり取りに相当な時間を割くことになります。
生活保護受給中の方や検討されている方が債務整理を行う場合は、ケースワーカーとの調整も必要ですが、専門家であれば生活保護制度と債務整理の両立について適切なアドバイスを提供し、福祉事務所との連携もスムーズに進められます。
最も重要なのは、専門家が収入・財産・家族構成などから最適な債務整理方法を選べる点です。誤った選択は根本的な解決に至らず、問題が再発する可能性もあります。専門家への相談は、多くの場合無料で受けられます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りて、新たなスタートを切るための一歩を踏み出しましょう。

よくある質問・トラブル事例と解決法
経営者として従業員の生活問題に直面したとき、また個人として債務整理を検討する際に、「具体的に何がどう変わるのか」という不安を抱えていませんか。ここでは、実際によくある質問と解決策を、経営者・個人両方の視点から詳しく解説します。
Q. 自己破産や生活保護で、今住んでいる賃貸物件は追い出されますか?
自己破産したからといって、すぐに賃貸物件から追い出されることはありません。破産法では居住権が一定程度保護されており、破産管財人も無理な退去を求めることは通常ありません。ただし、家賃滞納がある場合は、大家さんは債権者として扱われます。
家賃を継続して支払えている状況であれば、破産後も賃貸契約を継続できるケースがほとんどです。しかし、賃貸契約書に「破産した場合は契約を解除する」という条項がある場合、その有効性は個々のケースで異なります。
生活保護受給者の場合、住宅扶助の範囲内で家賃が支給されるため、基本的に家賃支払いの問題は生じません。ただし、住宅扶助の上限額を超える物件にお住まいの場合は、転居指導を受ける可能性があります。
Q. 自己破産や生活保護で、全ての借金や費用が免除されますか?
自己破産で免除される債務(免責債権)と、免除されない債務(非免責債権)があります。
| 免除される債務 (免責債権) | 免除されない債務 (非免責債権) |
| 一般的な借金、クレジットカード、消費者金融 | 税金、社会保険料 |
| 銀行ローン、個人間の借金 | 故意・重過失による損害賠償債務 |
| 個人保証債務(保証人個人の自己破産による) | 養育費、婚姻費用 |
免除される債務は「破産債権」として、免責許可決定で支払義務がなくなります。一方で、非免責債権は破産しても支払義務が残ります。
生活保護では、医療費や介護サービス費用、就労に必要な資格取得費用、子どもの学用品費などが一定条件下で支給されます。ただし、生活保護受給中に得た収入は、基本的に収入認定され保護費から差し引かれますが、勤労控除などにより一部は手元に残る仕組みです。
従業員が自己破産した場合でも給与債権は優先債権として扱われますが、会社自体が倒産手続きに入る場合は未払賃金立替払制度の活用など総合的な対応が必要です。
Q. 自己破産や生活保護の後に気をつけるべきことは?
自己破産後、信用情報機関に事故情報が登録され、5年から10年程度はクレジットカードの新規作成や各種ローンの利用、携帯電話の分割払い購入などができません。しかし、デビットカードや家族カード、口座振替は問題なく利用できます。
生活保護受給中は、収入や資産の申告を正確に行う義務があり、怠ると不正受給として追及される可能性があります。生命保険や自動車の保有にも制限があるため、事前にケースワーカーに相談しましょう。
金銭管理では、破産前と同じ金銭感覚を持たないよう注意が必要です。家計簿をつける、現金払いを基本とするなど、計画的な貯蓄を心がけましょう。就職活動では、警備員など一部の職種で破産者に対する欠格事由がありますが、これらは復権により解除されます。
Q. 従業員の債務問題、いつ専門家に相談すればいい?
従業員の債務問題は、職場環境や業務運営に影響を与える可能性があります。適切なタイミングで専門家に相談することが、従業員支援と会社への影響を最小限に抑えることの両立につながります。
相談を検討すべきサインは以下の通りです。
- 従業員の勤務態度や業務品質に変化が見られる(遅刻、集中力低下、体調不良など)。
- 給与の前借りや借り入れの依頼が増えている、同僚間での金銭トラブルが発生している。
法的な緊急性が高いのは、従業員が会社の資金や商品に手をつけてしまった場合や、取引先・顧客との間で金銭問題を起こした場合です。これらは会社の信用問題にも発展するため、速やかに弁護士に相談し、対応策を検討する必要があります。
従業員から直接相談を受けた場合も、具体的な債務整理方法や法的手続きについてアドバイスすることは避け、信頼できる弁護士や司法書士を紹介することがベストです。会社として従業員を支援する制度を整備したい場合も、専門家への相談が有効です。
経営者として従業員のプライバシーに配慮しつつ、適切な専門家のサポートを受けながら対応することで、従業員の生活再建を支援し、健全な職場環境を維持することが可能です。一人で抱え込まず、信頼できる専門家への相談を検討なさってみてください。
法律事務所または専門家へのアクセスは以下のページから。
弁護士の詳細をサイトで確認し、トップ検索ページから気軽に問い合わせてみましょう。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。











