民事再生と破産の違いとは?事業継続か清算かを徹底解説
民事再生・法人破産
2025.10.31 ー 2025.11.05 更新
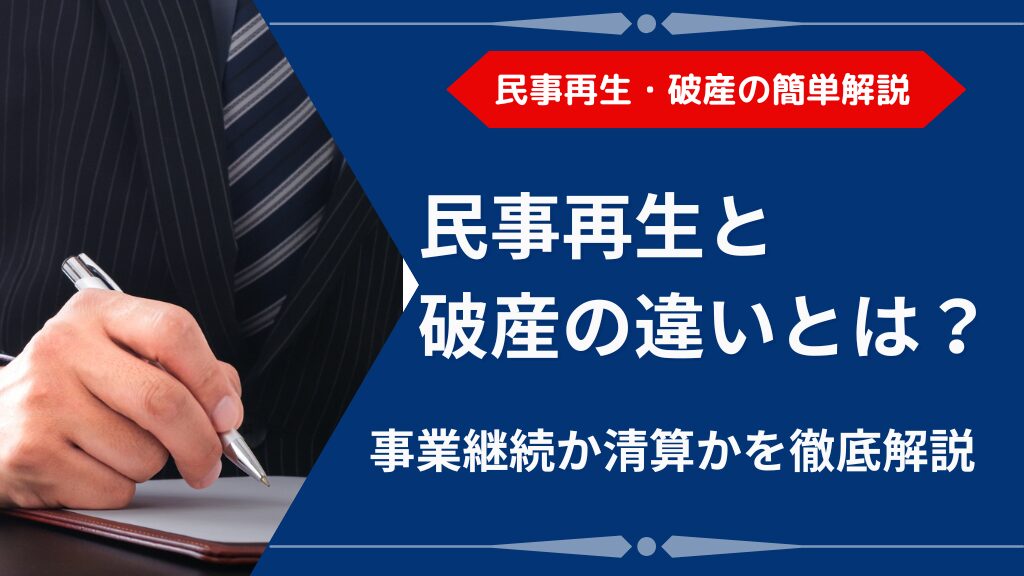
借入返済が困難な状況で、事業再建か清算か、最適な選択肢を見極めるのは容易ではありません。本記事では、会社を再建する「民事再生」と清算する「破産」について、その違い、判断基準、手続きを解説します。合理的な決断を下すための、具体的な判断材料がここにあります。

民事再生と破産の基本的な違い【図解で専門解説】
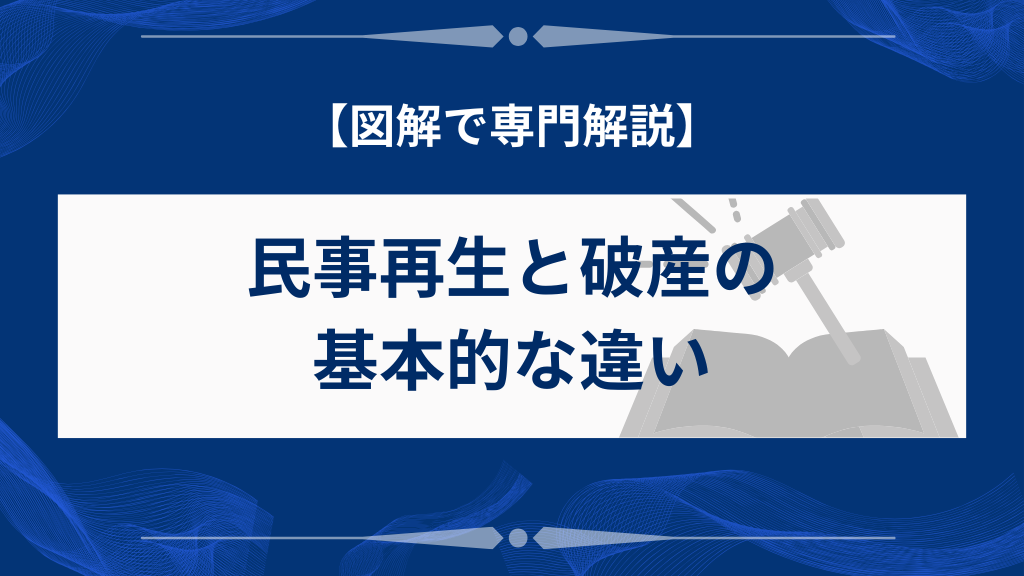
経営悪化時に検討される「民事再生」と「破産」は、根本的な目的が異なります。まずは以下の比較表で違いを確認し、詳細解説の基礎としてください。
| 項目 | 民事再生 | 破産 |
| 目的 | 事業の継続・会社の再建 | 会社の清算・法人格の消滅 |
| 事業の継続 | 可能(DIP方式) | 不可(即座に事業停止) |
| 経営権の維持 | 可能 | 不可(破産管財人に移行) |
| 従業員の雇用 | 維持できる可能性が高い | 全員解雇 |
| 債務の扱い | 一部カット、返済条件変更 | 全ての債務が消滅(免責) |
| 期間の目安 | 申立てから認可まで約6ヶ月、返済は3〜5年 | 申立てから終結まで約6〜12ヶ月 |
| 費用の目安 | 予納金200万円〜、弁護士費用300〜500万円〜 | 予納金20〜50万円〜、弁護士費用50〜100万円〜 |
民事再生とは?会社を残して再建を目指す手続き
民事再生とは、経営が困難になった会社が事業を継続しながら債務を整理し、再建を図るための法的手続きです。会社を残しながら借金を減らし、立て直す「攻めの債務整理」といえます。
裁判所の監督のもと、再生計画を立て債権者の同意を得て、債務の一部カットや支払い条件変更を行います。最大の特徴は、現在の経営陣がDIP(Debtor in Possession)方式で経営を続けられる点です。従業員の雇用や取引関係も維持しやすいというメリットがあります。
成功には、事業の将来性、再生計画を実行できる収益力、債権者の理解と協力が不可欠です。申立てから認可まで約6ヶ月、返済は3〜5年が目安です。費用は予納金200万円〜、弁護士費用300〜500万円〜が目安ですが、会社の規模や債務額で変動します。
破産とは?会社を清算して終了する手続き
一方、破産は会社の財産をすべて現金化し債権者に配当し、法人格を消滅させる手続きです。会社を完全にたたみ、残った財産で借金を返す方法です。
手続き開始で裁判所が選任した破産管財人が業務を引き継ぎ、経営者は関与できません。管財人は資産を売却し債権者に公平に分配します。従業員は全員解雇、事業所も閉鎖されます。
大きなメリットは「免責」制度で、会社の財産を処分しても返しきれなかった債務が消滅することです。期間目安は約6〜12ヶ月。費用は予納金20〜50万円〜、弁護士費用50〜100万円〜が一般的です。
破産を選択する判断基準としては、事業継続が現実的でない、債務額が収益力に比べ過大、再建の時間がないといった状況が挙げられます。
どちらを選ぶべき?3つの判断基準【フローチャート】
民事再生と破産、どちらの道を選ぶべきか。以下のフローチャートで、あなたの会社に最適な選択肢を簡易的に判断してみましょう。
- 事業に継続性・将来性があるか?
- YES → 2へ
- NO → 破産を検討
- 経営者保証など、個人保証の債務が大きく、会社と一体での整理が必要か?
- YES → 個人も含めた再生計画を立てられるか、弁護士と相談(民事再生または個人再生+法人破産)
- NO → 3へ
- 再生計画に必要な資金(弁護士費用、予納金など)を確保できるか?
- YES → 民事再生を検討
- NO → 破産を検討
このフローチャートはあくまで簡易的な判断基準です。具体的な状況は複雑であり、専門家との詳細な相談が不可欠です
あなたに適した選択肢を見極める5つのチェックポイント
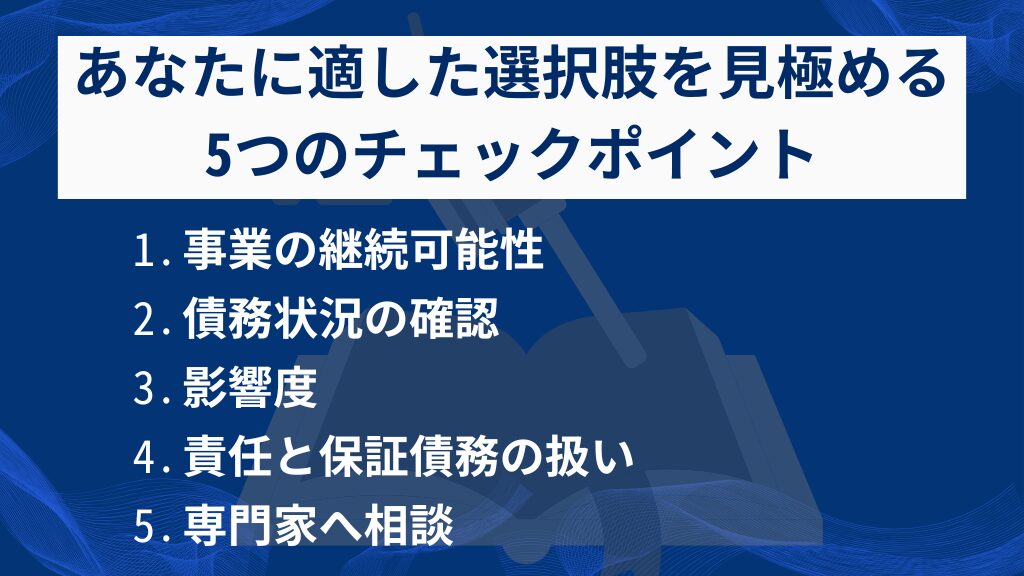
損失を抑え、最適な解決策を見つけるためには、客観的な基準に基づいて現状を整理することが重要です。ここでは、あなたの会社に適した選択肢を見極めるための5つのチェックポイントを提示します。
事業の継続可能性:売上回復の見込みはあるか
事業が本当に立て直せるか、具体的な数字で冷静に分析してください。一時的な売上減少か、業界全体の構造変化によるものかを見極め、現実的に達成可能な売上目標で現在の債務を返済しながら事業を継続できるか判断します。継続可能性が低い場合は、早期の事業再生手続きや廃業も検討が必要です。
債務状況の確認:返済可能な範囲内かどうか
現在の債務状況を正確に把握し、返済可能な範囲を明確にしましょう。月々の返済額が売上総利益の30%以内に収まるかどうかが一つの目安です。税金や社会保険料、従業員の給与は優先支払いが必要ですが、金融機関への返済はリスケジュールも視野に入ります。
従業員と取引先への影響度
従業員の雇用維持や、あなたの企業が取引先の事業にどの程度重要かを客観視してください。無理な事業継続は結果的により大きな被害を与える可能性があります。誠実な対応と早期の相談が、結果的に関係の維持につながることも多いでしょう。
経営者の責任と保証債務の扱い
中小企業の経営者にとって重い個人保証や連帯保証の問題です。個人保証の範囲と金額を正確に把握し、配偶者や親族への影響も考慮します。経営者保証に関するガイドラインにより減免や分割返済が可能になるケースもありますが、専門家の助言が不可欠です。感情的ではなく冷静に選択肢を検討しましょう。
専門家へ相談が必要なタイミング
これまでの4つのポイントを検討し、状況の深刻さや複雑さが明らかになったら、すぐに弁護士や司法書士、認定支援機関などの専門家へ相談すべきです。債務問題は時間が経過するほど解決が困難になります。多くの専門家が初回相談を無料で行っているので、まずは現状を整理し、どのような選択肢があるのかを把握することから始めてみませんか。

民事再生の3つの大きなメリット
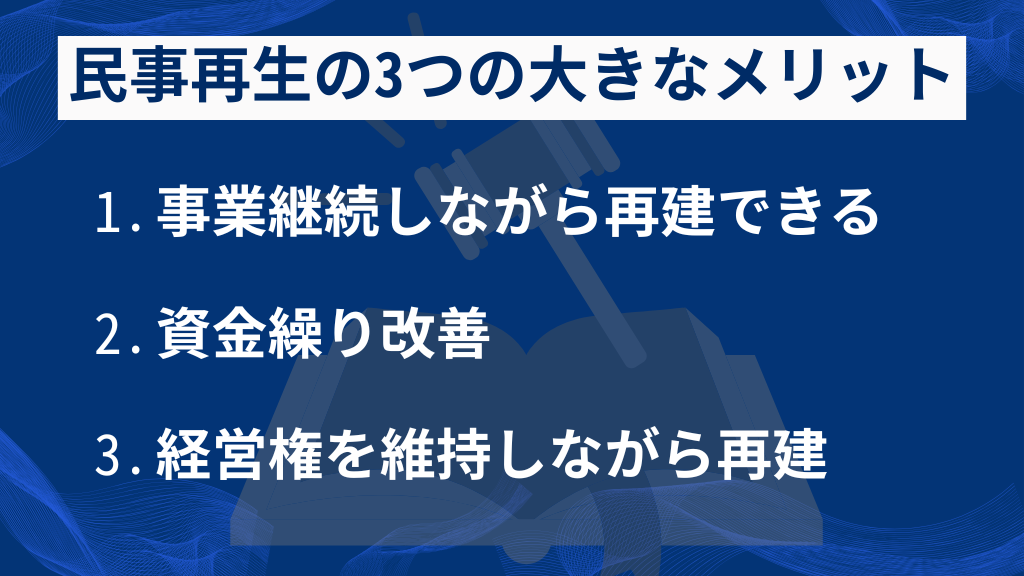
事業継続が困難な時、民事再生は事業を継続しながら債務整理できる制度です。そのメリットを正しく理解しましょう。
事業継続しながら再建できる最大の価値
会社を潰すことなく事業を継続しながら債務整理が可能です。従業員の雇用、取引先との関係を維持し、これまで築いてきた技術ノウハウや顧客基盤を失わずに再建を目指せます。
債務の大幅カットによる資金繰り改善
債務を大幅にカットできる可能性があります。一般的に8〜9割程度の減額が認められるケースが多く、月々の返済負担を劇的に軽減できます。この差額分を運転資金や設備投資に回し、事業の立て直しに専念できます。
経営権を維持しながら再建に取り組める
基本的に現在の経営陣がDIP(Debtor in Possession)方式で引き続き会社を運営できます。これまでの経営方針や事業戦略を活かし、関係者へ「経営者が変わらず責任を持って立て直す」というメッセージを発信し、信頼を維持しやすくなります。
知っておくべき民事再生のリスクとデメリット
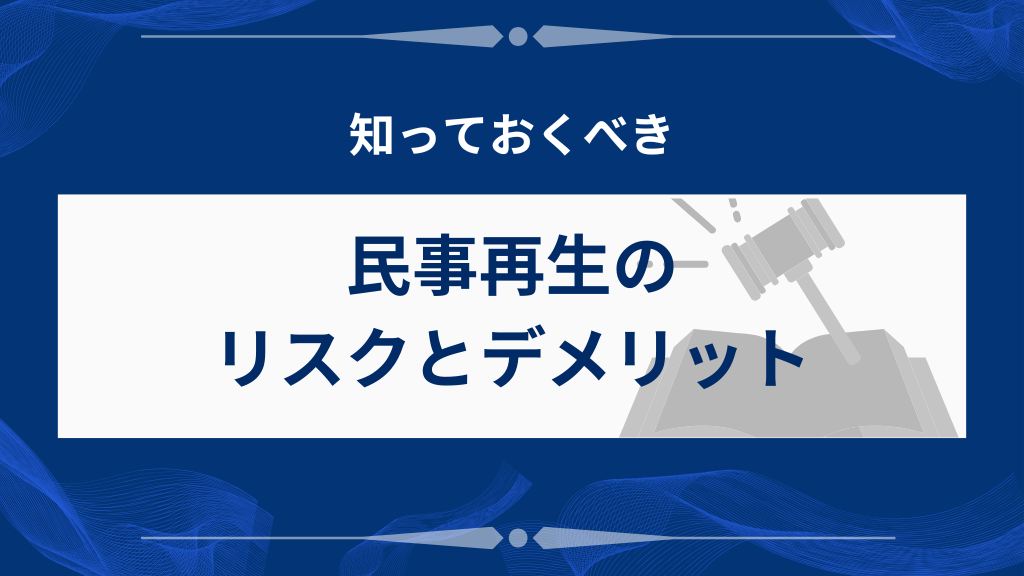
信用失墜による取引関係の悪化リスク
民事再生の申立ては官報に掲載され、信用情報機関にも登録されます。これにより、既存取引先から取引条件見直しや停止を求められる、新規借入れが困難になるなどのリスクがあります。原材料の仕入れ先から現金決済を求められたり、下請契約を打ち切られたりする可能性も覚悟が必要です。
手続きの複雑さと高額な費用負担
民事再生手続きは法的に非常に複雑で専門知識が必要です。弁護士費用や裁判所への予納金を含め、総額で数百万円から1,000万円を超える費用がかかる場合があります。手続き期間中は経営者が多くの時間を割かれ、事業への影響も無視できません。
再生計画の履行義務と将来への重荷
再生計画が認可された後は、通常3年から5年間にわたって毎月決まった金額を支払い続ける義務が生じます。この間に業績が悪化すると再び経営危機に陥り、最悪の場合、破産手続きに移行せざるを得ないこともあります。その場合、かけた時間と費用が無駄になるリスクも伴います。
民事再生が成功しやすい会社の条件
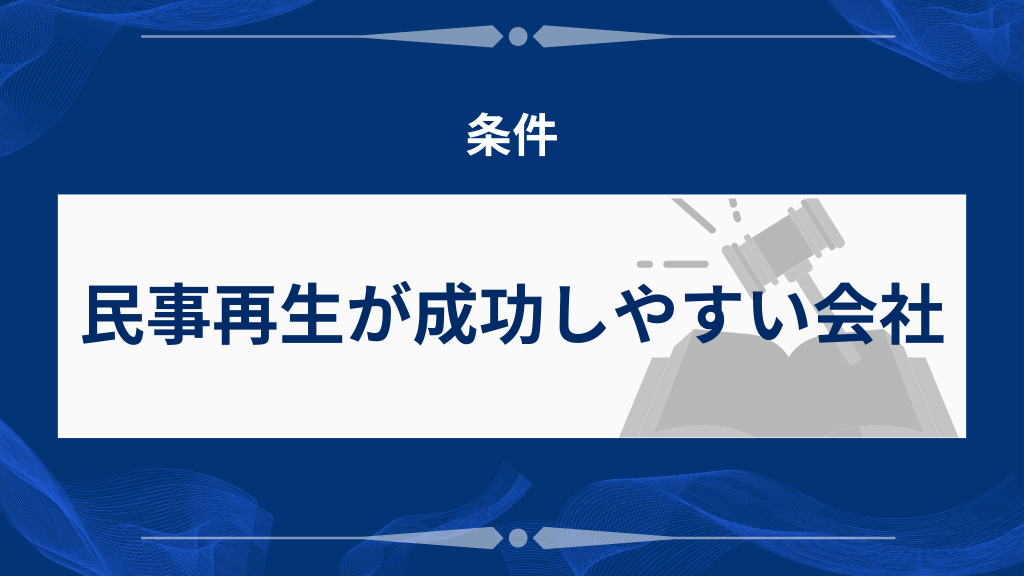
事業の収益性と将来性が確保できている
民事再生が成功する前提は、事業自体に収益性と将来性があることです。債務負担軽減で黒字経営に転換できる見込みがあり、市場での競争力を維持できる事業でなければ、債権者の同意は困難です。独自の技術力や顧客基盤も有利に働きます。
十分なキャッシュフローと資産価値の存在
手続き中も事業を継続するため、当面の運転資金と安定したキャッシュフローが必須です。また、不動産や機械設備などの資産価値が一定程度あることも、債権者の理解を得る上で有利に働きます。
経営者の強いリーダーシップと関係者の協力
経営者自身の強い意志と実行力が不可欠です。従業員や取引先、債権者といった関係者全員を巻き込み、再建に向けた協力を取り付けるためのコミュニケーション能力と信頼関係の構築が重要になります。
会社更生や特別清算との違い
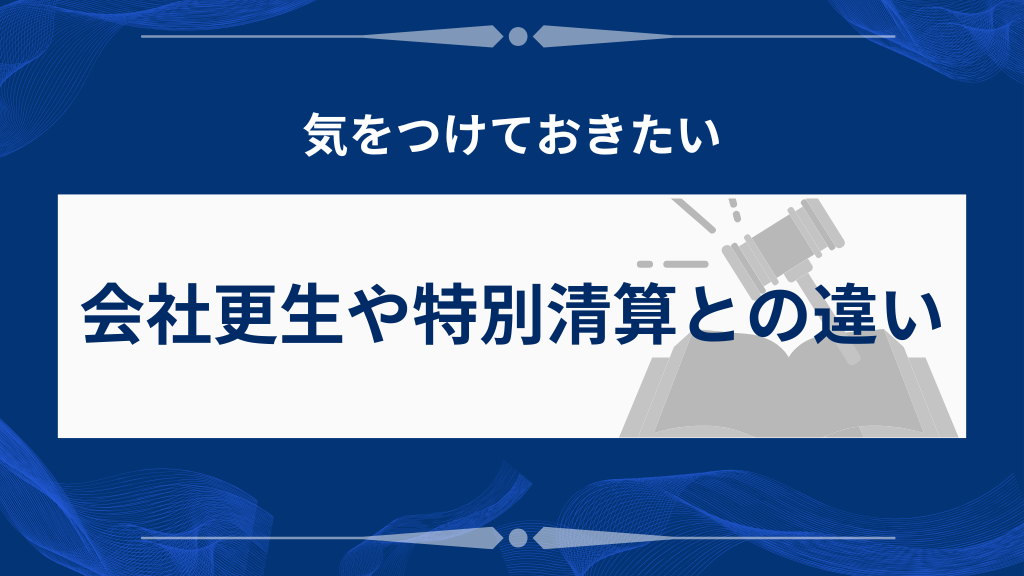
経営権の維持と手続きの簡素化
民事再生では現経営陣が経営権を維持でき、手続きが会社更生に比べて簡素です。会社更生は裁判所が選任する管財人が経営権を握る大規模企業向けの制度です。
事業継続と清算の根本的な違い
特別清算は事業を停止して会社を解散する清算型の手続きであり、民事再生のように事業継続を目指すアプローチとは正反対です。事業基盤や従業員の雇用を維持したい場合には適しません。
専門家への相談で最適な選択を見つける
これらの制度は適用要件や特徴が異なり、会社の状況によって最適な選択肢は変わります。債務規模、収益性、資産状況などを総合的に判断するため、企業再建に精通した弁護士に早期に相談し、客観的な判断を仰ぐことが重要です。
民事再生の種類と手続きの流れ【期間・費用も解説】
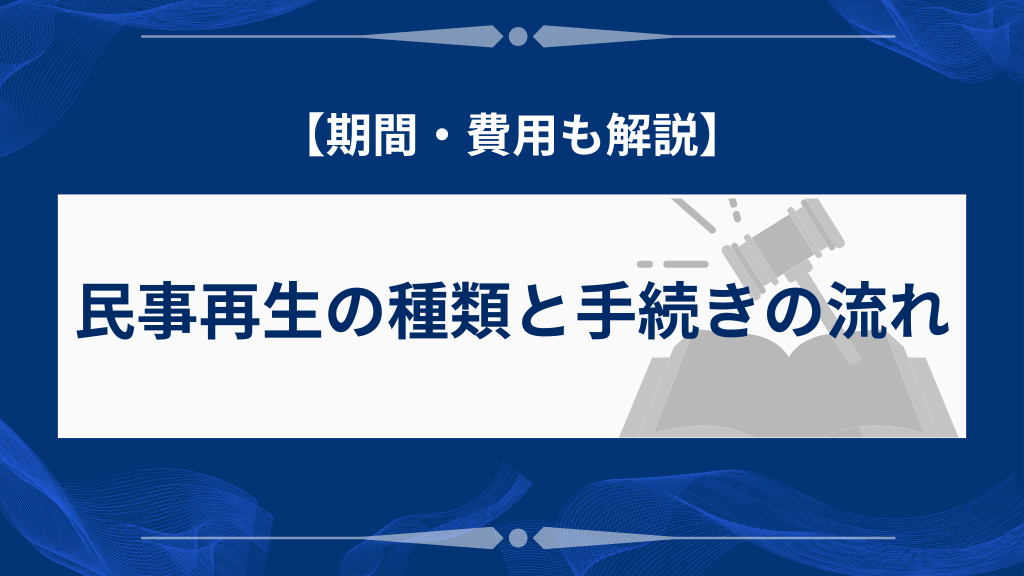
民事再生は、事業状況と将来性に応じていくつかの選択肢があります。経営者自身の意思と体力を総合的に考慮し、最適な再生方法を選択しましょう。
自力再建型民事再生:既存事業での立て直し
現在の事業を継続しながら収益性を改善し、債務圧縮と返済計画見直しで経営を立て直す方法です。事業自体に収益性があり、一時的な資金繰り悪化が主な問題である場合に適用されます。債権者の同意を得るには、過去の課題分析と具体的な改善策を示した、実現可能な事業計画が不可欠です。
スポンサー型民事再生:出資者を見つけての再建
外部の投資家や企業(スポンサー)からの出資や支援を受けながら事業再生を図る方法です。資金調達と経営ノウハウの両面で支援を受けられるメリットがあります。スポンサー選びは極めて重要で、事業に対する理解と長期的なビジョンを共有できる相手を見つける必要があります。
清算型民事再生:事業譲渡による整理
事業の一部または全部を第三者に譲渡し、その譲渡代金で債務を整理する方法です。事業継続が困難だが、破産よりも高い回収率を目指したい場合に選択されます。事業の価値を最大化して売却し、譲渡先の選定では事業の継続性と従業員の雇用維持を重視するのが理想です。
民事再生手続きの流れと必要期間
民事再生手続きは、申し立てから再生計画の承認・確定まで、通常6ヶ月から1年程度を要します。
- 申し立て準備(1~2ヶ月):財産目録、債権者一覧表、事業計画書などの詳細資料を作成。
- 申し立て・開始決定(1~2週間):裁判所が開始決定を行い、債権者からの取り立てが中断。監督委員が選任される。
- 債権の調査・確定(2~3ヶ月):全債権者に債権届出を求め、再生計画の骨子を検討。
- 再生計画案の提出・決議(2~3ヶ月):債権者集会で計画案を説明し、書面決議で承認を求める。承認後、裁判所が認可決定を行う。
民事再生・破産にかかる相談費用や手続き費用
民事再生にかかる費用は、弁護士費用と裁判所費用に大別され、総額で500万円から2000万円程度を見込む必要があります。弁護士費用は着手金と成功報酬の組み合わせが一般的です。裁判所費用には、申立手数料、予納金、公告費用などがあります。
一方、破産手続きの費用は民事再生より抑えられ、弁護士費用は100~500万円程度、裁判所費用も50~200万円程度が一般的です。多くの弁護士事務所で分割払いや着手金の減額に応じてくれます。経営が厳しい状況でも、専門家に相談し、最適な方法を見極めることが重要です。
破産手続きのメリットとデメリット【経営者目線】
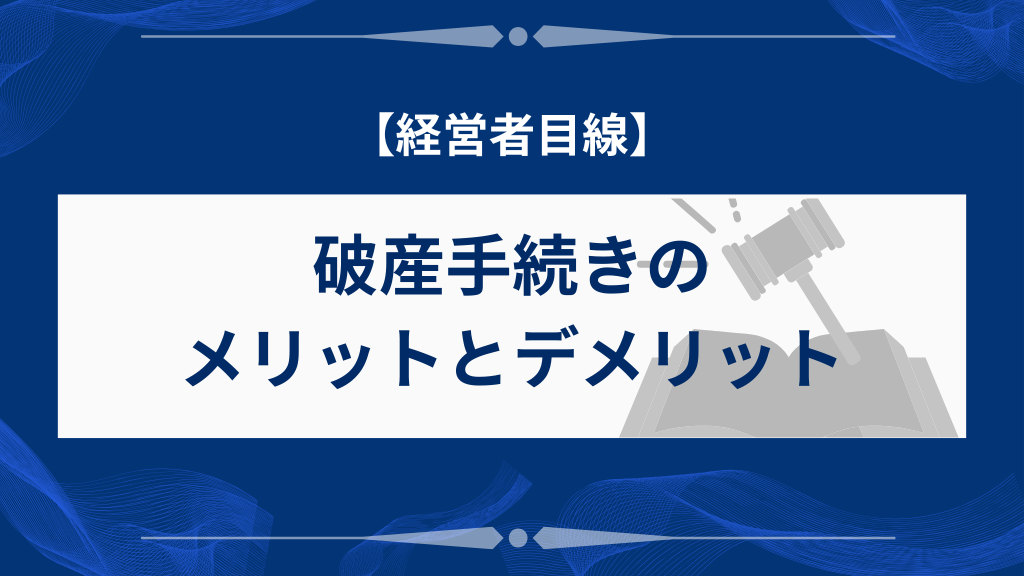
返済が困難になった時、破産手続きは重い決断です。感情的になりがちな状況だからこそ、メリットとデメリットを客観視し、将来を守る選択をしましょう。
破産手続きの3つのメリット
- 債務からの完全な解放
手続き完了後、会社の全ての借金が法的に消滅します。個人保証をしている経営者の場合、個人の自己破産手続きも同時に行うことで、個人保証債務も免除され、借金から完全に解放されます。 - 取り立て・督促の即座停止
弁護士が破産手続きの準備に入ったことを債権者に通知した瞬間から、電話や訪問による督促、支払い催促書の送付などが全て止まり、精神的な負担が大幅に軽減されます。 - 早期の事業整理による損失拡大の防止
返済困難な状況での事業継続は、新たな債務発生で損失が拡大する可能性があります。破産手続きでこれ以上の損失拡大を防ぎ、関係者への被害を最小限に抑えることが可能です。
破産手続きで覚悟すべきデメリット
- 事業の完全停止と財産の処分
破産手続き開始で会社の営業活動は即座に停止し、工場設備、在庫、売掛金など会社が保有する全ての財産が破産管財人によって換価処分されます。長年築き上げてきた事業基盤、顧客関係、従業員との絆、全てを手放さなければなりません。 - 従業員への深刻な影響
手続き開始と同時に全従業員を解雇せざるを得ません。退職金の支払いも困難になり、未払い給与についても破産手続きの中で処理されるため、従業員が全額を受け取れる保証はありません。 - 経営者個人の信用情報への長期影響
個人保証により個人破産も同時に行った場合、信用情報機関に5〜10年間記録が残り、この期間中は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。
破産を選択すべき会社の特徴
- 債務超過の状態が長期化し、改善の見通しが立たない場合。
- キャッシュフローが完全に破綻し、日々の資金繰りが限界に達している状況。
- 経営者の個人保証額が個人資産を大幅に超えている場合。
破産後の社員や経営者の生活はどうなる?
従業員には国の「未払賃金立替払制度」が一定の救済を提供します。経営者自身の生活再建については、破産後も一定の財産(生活必需品、99万円以下の現金など)を手元に残すことが認められています。破産は人生の終わりではなく、新しいスタートを切るための手続きです。経験豊富な弁護士に相談し、最適な選択肢を見つけることが重要です。 弁護士への相談はこちら>>>

よくある質問・失敗事例 Q&A
経営が厳しくなった時、法的手続きを検討する経営者の方が陥りやすい落とし穴や疑問点をQ&A形式で解説します。
民事再生・破産の進め方でミスしやすいポイント
- 手続きの先延ばし
「まだ大丈夫だろう」という楽観的判断による手続きの先延ばしは最も危険です。民事再生は一定以上の資産や将来の収益見込みがなければ認められません。破産も手続き費用を捻出できない状態では選択肢が狭まります。早期に専門家へ相談することが重要です。 - 取引先や従業員への対応の後回し
特定の債権者にだけ優先的に支払いを行う「偏頗弁済」は問題となる可能性があります。また、従業員の給与についても適切な説明と準備が必要です。民事再生の場合は主要取引先との関係維持が極めて重要であり、透明性と誠実さを保った段階的な情報共有戦略が必要です。
専門家に依頼する際の注意点
弁護士選びは手続きの成否を左右します。
- 専門分野の確認: 企業の倒産手続きに精通しているか、過去の実績、同業種や同規模企業での経験があるかを確認しましょう。
- 地域性と経験: 地元の商慣習を理解している弁護士か、複雑な案件に対応できる大手事務所か、状況で選択肢は異なります。
- 費用面の透明性: 着手金、成功報酬、実費など、どの段階でどれくらいの費用が発生するのかを事前に明確にしてもらいましょう。
- コミュニケーション能力: 経営者の立場に立って分かりやすい言葉で説明してくれるか、質問に丁寧に答えてくれるかを見極め、緊急時の連絡体制も確認が必要です。
読者からよくある質問まとめ
Q: 民事再生と破産、どちらを選ぶべきか判断基準が分からない
A: 最も重要なのは事業に将来性があるかです。債務をカットした状態で3年程度で黒字化できる見込みがあり、主要取引先との関係を維持できるなら民事再生を検討。事業自体に将来性が見込めない場合は、破産で損失を最小限に抑える方が良いでしょう。
Q: 手続き開始前に、個人資産を家族名義に移しても大丈夫?
A: 非常に危険です。詐害行為として取り消される可能性があり、意図的な財産隠匿とみなされれば免責不許可事由に該当し、破産しても債務が残る可能性があります。絶対に避けてください。
Q: 従業員の給与や退職金はどうなる?
A: 労働債権は一般債権より優先されます。破産の場合、破産財団から優先的に支払われ、不足分は未払賃金立替払制度を利用できる場合があります。民事再生の場合も、手続き開始前3ヶ月分の給与などは随時弁済が認められることが多いです。
Q: 取引先への支払いを一部だけでも続けることはできる?
A: 手続き開始後は、原則として債権者平等の原則により特定の債権者にだけ支払いを行うことはできません。ただし、民事再生の場合は、事業継続に必要不可欠な取引先について、裁判所の許可を得て新規取引を継続できる場合があります。
Q: 保証人になっている代表者個人はどうなる?
A: 会社が民事再生や破産をしても、代表者の個人保証債務は原則として残ります。経営者保証ガイドラインに基づき減免が認められるケースもありますが、代表者個人についても自己破産や個人再生といった手続きを検討する必要が生じることも多いです。
これらの法的手続きは、経営者お一人で判断するには複雑すぎます。早期に専門家に相談することで、ご自身の状況に最も適した選択肢を見つけ、関係者への影響を最小限に抑えながら、新たなスタートを切ることが可能になります。一人で抱え込まずに、まずは専門家の意見を聞いてみることから始めてみましょう。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。











