企業が民事訴訟されたらどうなる?訴状への適切な対処法や注意点を解説
訴訟・紛争解決
2025.04.08 ー 2025.04.15 更新
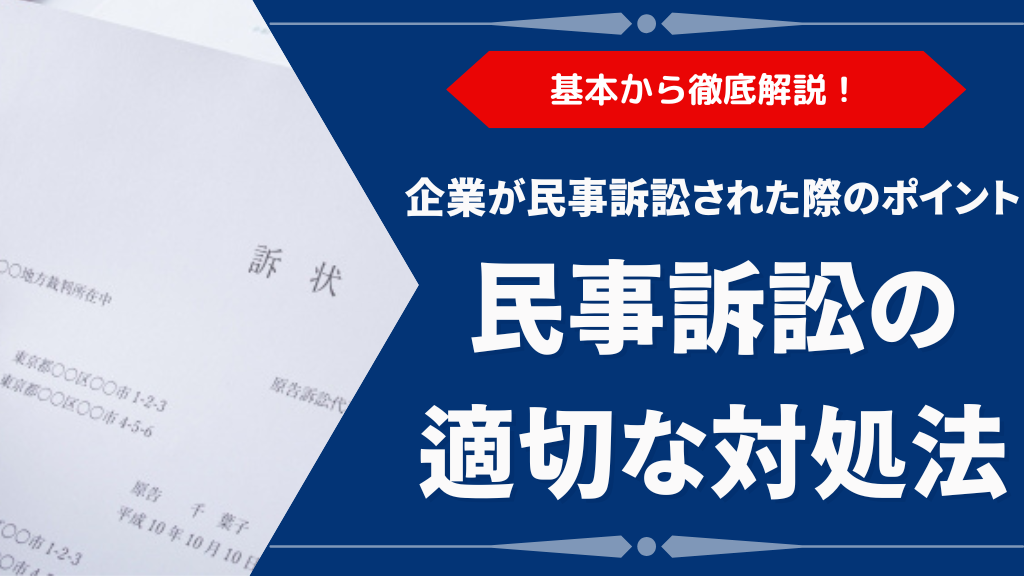
ビジネスや日常生活において、契約トラブルや金銭の未払い、損害賠償の請求など、法的な問題に直面することは決して珍しくありません。
こうした問題が話し合いで解決せず、最終的に裁判へと発展するのが「民事訴訟」です。しかし、訴訟と聞くと「時間や費用がどれくらいかかるのか?」「訴えられた場合、どう対応すればいいのか?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では民事訴訟の基本から、訴訟の流れ、費用、必要な手続き、さらには裁判以外の解決策まで 分かりやすく解説します。また、企業の法務担当者や個人事業主の方が取引先とのトラブルで訴訟を検討する際、または突然訴えられた際に適切な対策を講じるためのポイントも紹介します。
自分の立場に合った最適な対応を知るために、ぜひ最後までご覧ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>民事訴訟とは?
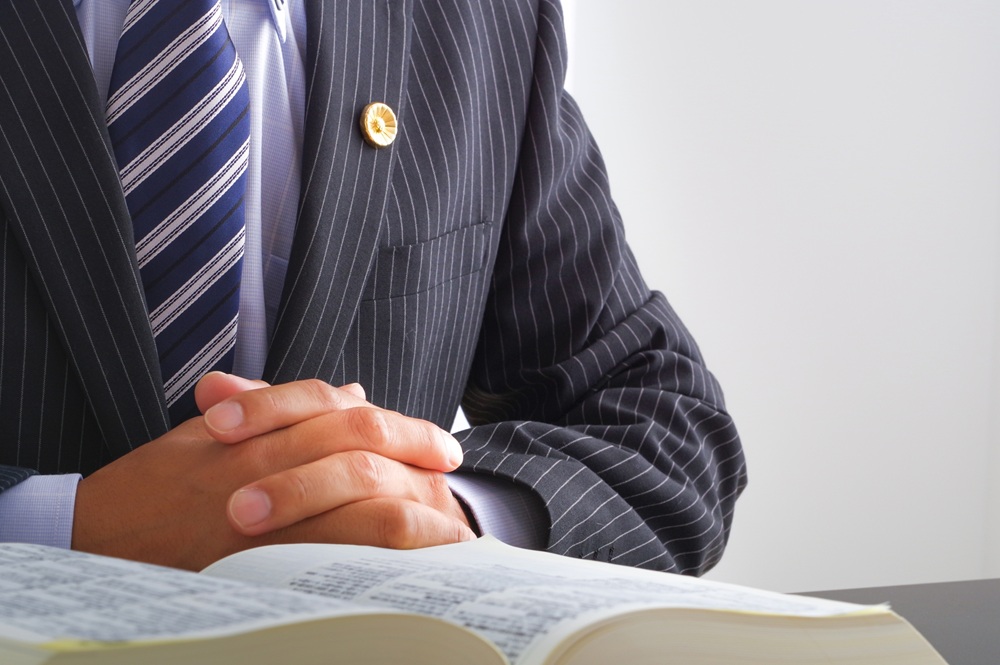
訴訟は大きく民事訴訟・行政訴訟・刑事訴訟に分類されます。
このうち民事訴訟とは、私人の間の法律上の権利・義務に関する争いを、裁判所で解決する手続きです。私人とは、個人や法人のほか法人格のない団体も含みます。
また市町村等の自治体が相手の場合でも、損害賠償請求などの民事上の権利の得喪を争う場合には行政事件ではなく民事事件になります。
一つの行為が民事事件・刑事事件の双方に該当する場合も多くありますが、訴訟は別の法律根拠に基づいて、各別に行われます。
企業が民事訴訟を起こされるケースとは?

刑事事件・行政事件以外の事件は、原則として全て民事事件です。
トラブルのほとんどは民事事件であり、企業が民事訴訟を起こされるケースは次のようなものがあります。
- サービスの質や納期、支払いに関する顧客とのトラブル
- 労働環境、パワハラ、労災、残業代未払いなどの従業員とのトラブル
- 勤務中の交通事故や、提供するサービス・商品による事故などの被害者とのトラブル
- 著作権、意匠権などの知的財産権についての競合企業や個人とのトラブル
これらは、企業が取引先や顧客、競合他社との間で発生する問題であり、多くの場合は契約書や合意内容の解釈に関する争いに発展します。
従業員との間でのパワハラのトラブルや労働条件・労働環境に関する労働紛争も民事訴訟の対象です。この場合、未払い残業代の支払いを求める訴訟や、不当解雇による労働者の地位確認訴訟などが考えられます。
また事故やセクハラ・パワハラ、著作権違反などは民事事件と同時に刑事事件にも発展する場合があります。
これらのトラブルは、企業内の管理体制やコンプライアンスの欠如が原因となる場合も少なくありません。企業としてはリスクを事前に認識し、適切な対応策を講じておくことが重要です。
特に取引や労働に関する合意内容を明確にすることや、問題発生時に迅速に対応することで、無用な訴訟のリスクを回避できます。
民事訴訟の流れと企業の初動対応

民事訴訟のおおまかな流れは次のとおりです。
- 原告が裁判所に訴状を提出
- 訴状の受理・審査
- 被告に訴状が送達される
- 口頭弁論の開始から終結
- 判決言渡
金銭トラブルの場合などは、本訴訟の訴状提出前に仮差押え(銀行口座への仮差押え)などの民事保全手続きが行われる場合があります。
判決の言渡しのあとは、判決に従って損害賠償の支払いをしたり、納得がいかない場合には上級裁判所に上訴したりという流れになります。
判決で確定した債務の履行を任意で行わない場合には、強制執行等の手続に進みます。
現実のケースでは、訴訟の前にトラブルが明確化し、直接相手方に口頭や書面で請求が行われる場合も多いです。これらの請求に応じない場合、相手方から訴訟が用いられることになります。
訴状が届いたら最初にすべきこと
企業が訴状を受け取った際に最初に行うべきは、内容を詳細に確認し、どのような請求がなされているかを正確に把握することです。
訴状には請求の根拠や理由が記載されていますが、法律用語が多く含まれているため、少しでも難しいと感じたら企業法務部門や外部の弁護士に内容を確認してもらうことが重要です。
早急な対応が求められるため、訴状に記載された期日を確認し、早めに対応策を策定する必要があります。
また訴状に見せかけた特殊詐欺も流行しています。全く身に覚えのない請求の場合には、まず弁護士へ相談すると良いでしょう。
無視は不利になる
訴状を無視すると、原則として反対の意思がないとみなされ不利になります。
これを避けるためには訴状に記載される指示に従って答弁書を作成し、期日までに必ず裁判所に提出しましょう。口頭弁論期日が決定されたら、指定期日に裁判所に出頭しましょう。
民事訴訟にかかる費用と費用負担の仕組み

民事訴訟にかかる費用は、訴訟の性質や争点の複雑さに応じて変動します。
通常、訴訟費用には裁判所に支払う手数料、弁護士報酬、証拠収集にかかる費用が含まれます。費用負担の仕組みは、一般に訴訟結果次第で変わることがあります。
勝訴した場合には相手側が一部を負担する場合もありますが、全てが補償されるわけではありません。
企業は予測できない費用負担を軽減するために、事前に法律顧問との契約を検討することも有効です。
特に複雑な訴訟では費用が膨らむケースも考えられ、慎重な財務計画が必要となります。弁護士費用特約など、費用を管理するための制度を積極的に活用することが、企業にとって長期的なリスク管理となるでしょう。
訴訟費用の主な内訳とは?
訴訟費用は、裁判所に支払う費用と、弁護士に支払う弁護士費用に分かれます。
裁判所に支払う費用には次のようなものがあります。
- 訴訟手数料
- 郵送料(訴状等の送付・送達費用)
- 出頭日当、出頭旅費、宿泊料
- 証人の日当・旅費・交通費
- 書類作成提出費用
- 鑑定等を行った場合の費用
- 裁判記録の謄写費用
弁護士に支払う費用には次のようなものがあります。
- 着手金
- 日当
- 相談料
- 成功報酬
民事訴訟において、企業が負担する訴訟費用は多岐にわたる項目から成り立っています。
まず、訴訟を提起する際に必要とされるのが、裁判所に納める訴訟手数料です。この手数料は請求額に応じて算出されるため、訴訟の規模によって大きく変動します。
これらの訴訟費用は原則として敗訴者が負担することになります。
弁護士費用はその経験や専門性により幅がありますが、企業にとっては無視できないコスト要素です。弁護士費用の最も大きな部分は成功報酬でしょう。報酬基準は訴訟の難易度等により弁護士事務所によっても変わります。
ただし敗訴しては元も子もありませんので、報酬よりも専門性によって依頼する弁護士を決定するとよいでしょう。
負担軽減のために活用できる制度
訴状が送達されても、必ず判決によって決着をつけなければならない訳ではありません。裁判中でも相手方との交渉によって和解が成立すれば、相手方が訴訟を取り下げて訴訟終了になることもあります。
そのほか、裁判外紛争解決手続(ADR)や、民事調停は訴訟を経ずに紛争を解決するための手段として活用されています。
訴訟前にこうした解決を模索できるよう予防することが大切です。弁護士と法律顧問契約を結ぶことで、常に専門家のアドバイスを受ける体制を整えておくと、効果的に負担軽減対策ができるでしょう。
法律顧問は、契約書のレビューや労務問題など、日常的な法務ニーズに応じたサポートを提供し、予防的な視点でリスクを最小限に抑える役割を果たします。これらの制度を効果的に利用することで、企業は予想外の法的トラブルへの備えを強化しつつ経営資源を本業に集中できるようになります。
企業が民事訴訟で不利にならないためのポイント

企業が民事訴訟で不利にならないためには、まず訴訟の本質を理解し、法に従った適切な対応が不可欠です。
一般的な対応は以下のとおりです。
- 裁判所から指定された期限は必ず守る
- 資料は処分せずに証拠を保全する
- 不用意な発言を避け、不利にならないよう立ち回る
証拠の確保には契約書やメール、その他のコミュニケーションの記録が含まれ、これらが裁判所での立証能力を高めます。また専門の法律顧問を日常的に活用することで、予防的な対策が可能となります。こうした対策により訴訟そのものを防ぐことも可能です。
結果として法的リスクを最小限に抑えつつ、企業の信頼を守ることができるでしょう。
和解と裁判、どちらを選ぶべきか?
企業が民事訴訟に直面した際、和解と裁判のどちらを選ぶべきかは、状況に応じた慎重な判断が求められます。
和解は時間と費用を抑える効果的な手段であり、特に双方の主張が拮抗し、長期化が予想される場合には有効です。和解によって得られる合意は、企業の評判を守る上でもメリットがありますが、譲歩が必要であるため全てのケースで最善とは限りません。
一方、裁判は法的な正当性を明確にすることが可能であり、判決により社会的信用を獲得することもあります。しかし過去の判例が示すように、裁判は多額の費用と時間がかかり結果が予測困難なため、企業の経営に大きな負担を及ぼすことがあります。
選択には訴訟の内容、企業の立場、顧問弁護士のアドバイスを総合的に考慮する必要があるでしょう。
民事訴訟を有利に進めるために必要な証拠とは?
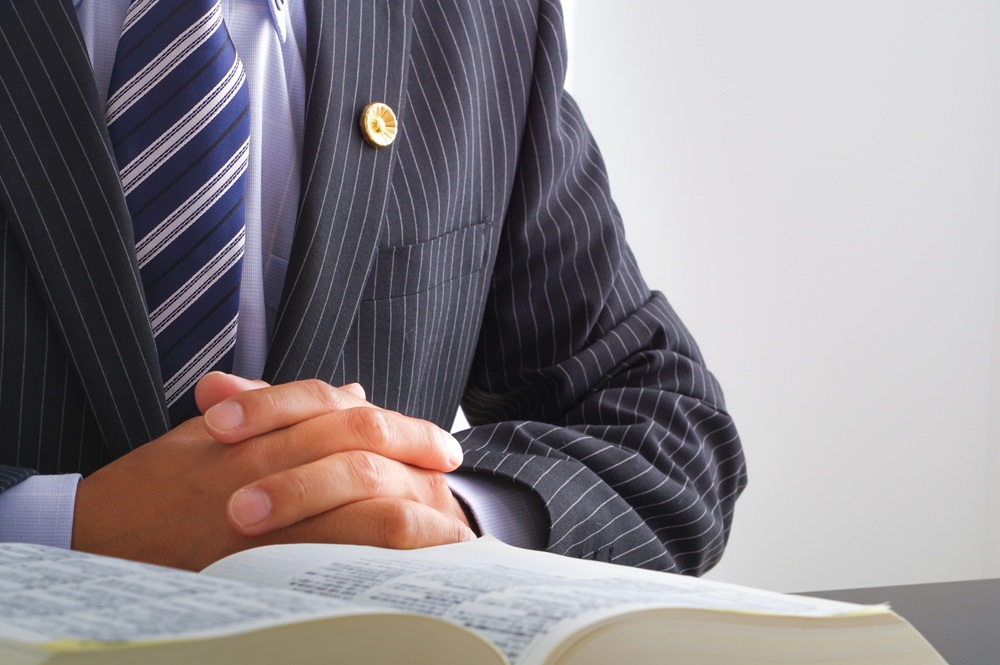
民事訴訟を有利に進めるためには、確固たる証拠の収集が欠かせません。
まず、契約書は双方の権利義務を明示する重要な文書です。さらに録音データや記録も、口頭契約や交渉の事実を示すために活用されることが多いです。
交渉過程や契約後の履行状況を裏付けるメールもまた有効な証拠となります。
また債務の履行の有無や遅延損害金の発生を示すためには、履行の日付や請求の有無が重要な要素です。そのため録音データや内容証明郵便などは重要な証拠となります。
証拠が不十分な場合には、不利な判決が下されたり、和解交渉において弱い立場に立たされるリスクが高まります。したがって、訴訟の可能性を考慮し、日常的に適正な証拠の保全と管理を心がけることが求められます。
証拠が不十分な場合のリスク
証拠が不十分な場合、企業にとって民事訴訟は不利な結果を招く可能性が高まります。
具体的には、証拠が足りないと主張の信憑性が低下し、裁判官に有利な判断を得るのが難しくなるためです。証拠が乏しい状況では相手側の主張が優勢になる可能性があり、企業側が反論できる余地を狭めることになります。
これにより裁判の結果として想定外の損害賠償を命じられたり、企業の信用を著しく損なったりするリスクがあります。しかし所有する証拠を最大限に活用しつつ、関連する新たな証拠を適時に取得することで、状況を改善することも可能です。
このようなリスクを軽減するため平時から証拠の適切な保管や関係者とのコミュニケーションの整理を行うことが求められます。企業は、訴訟になった際に迅速に対応できる準備を怠らないことが重要です。
弁護士なしで民事訴訟に対応するリスクとは?

企業が弁護士を雇わずに民事訴訟に対応することは、法律の専門知識が欠如しているため大きなリスクを伴います。
法廷での戦略や証拠の取扱いに精通していない場合、訴訟の進行を誤り不利な結果を招くことがあります。また訴訟への対応は時間と労力を必要とし、日常業務に支障をきたす可能性が高まります。
このような状況において、企業法務担当者だけで対応しようとすることは、リスク管理の観点から危険を伴うと言えるでしょう。
特に意図しない発言や行動が裁判の展開に影響を与える可能性もあるため、民事訴訟には法律の専門家である弁護士の支援が不可欠です。弁護士に相談すること、法的手続きの複雑さを軽減し、企業の利益を最大限に守ることができます。
企業の法務リスクを減らすための予防策とは?

企業が法務リスクを減らすためには、まず訴訟リスクを事前に防ぐための契約書の見直しが重要です。契約書には曖昧な表現を避け、両当事者の責任範囲を明確に記載することで、誤解や紛争を未然に防げます。
条件変更時には必ず文書で合意を確認し証拠として残しておくことで、いざという時のリスクを軽減できます。
また社内でコンプライアンスを強化し、定期的な研修を実施することで、従業員の法令遵守意識を高めることができます。
さらに法律顧問を活用して日常的な法務相談を行うことで、潜在的なリスクを早期に発見できます。
こうした継続的な取り組みが、企業の法務リスクを大幅に減少させる鍵となります。しかしこれらの対策を講じても完全にリスクをゼロにすることは難しく、時には想定外のトラブルが発生する可能性があります。このため常に柔軟な対応が求められます。
契約書のリーガルチェックを受ける
契約書を明確に作成するためには専門家によるリーガルチェックが有効です。
法律の専門家によって各条項を見直し、取引内容や義務を具体的にすることで法律根拠を明確に反映させることができます。また、双方の責任範囲を詳細に定めることで、誤解を防ぎトラブルを未然に防ぐことができます。
契約履行に関する条件等も明確にすることで、例えば納品期限や検収手続きの詳細を盛り込み、期待値の齟齬を防ぐことができます。
特に初めてのタイプの契約や繰り返し利用する業務委託契約書、あるいは雇用契約書等については、リーガルチェックを受けることでリスクを大きく減らすことができるでしょう。
社内コンプライアンス強化の重要性
社内コンプライアンスの強化は、企業が民事訴訟に巻き込まれないための重要な手立てです。
コンプライアンスとは、法令や倫理基準の順守を指し、社内規程として具体化されます。これにより従業員は業務遂行上のルールを理解し、適正な行動が促されます。
特に企業活動における透明性を高め、不正行為や不適切な取引を防ぐことでリスクを未然に防ぎます。外部の法務顧問等を通じて社員教育を行うことで、契約の重要性や法律の基礎知識を共有し、企業の法務リスクを縮小できるでしょう。
また定期的な監査や内部調査の実施も、潜在的な問題の早期発見に寄与します。このような取り組みにより、法的トラブル回避の一助となるだけでなく、企業の信頼性と社会的評価が向上します。しかし制度が機能しない可能性もあるため、柔軟な対応が求められます。
外部の法律顧問を活用したリスク管理
法律顧問を活用することは、企業が日常的に直面するリスクを管理するための有効な手段です。
企業活動においては、取引や契約関係における不備、従業員との労使トラブル、顧客対応に関する苦情など、さまざまな問題が法的リスクとして浮上します。これらのリスクを管理してトラブルを未然に防ぐためには、法律顧問の適切なアドバイスが欠かせません。
法律顧問は、企業が行う取引や契約の条項を事前にレビューし、リスク要因を特定し改善策を提案します。また従業員に対する適正な労務管理やコンプライアンスの遵守を徹底することで、民事訴訟に発展する可能性のある問題を予め抑えることが可能です。
こうして訴訟発生のリスクを抑制することで、企業の信用や評判の維持にもつながります。このように、法律顧問を活用することで、企業は持続可能な経営基盤を築くことができるのです。
民事訴訟を起こされたら法律事務所に相談を!

企業が民事訴訟を起こされた場合、迅速に法律事務所に相談することが重要です。初動対応が遅れると、企業の信用や財務に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
法律事務所は、専門的な知識で迅速かつ適切なアドバイスを提供し、最適な対応策を提案します。また、法律事務所に相談することで、訴状の内容を正確に把握し、必要な証拠を早期に収集するための助言を受けることができます。
この早期対応が、企業にとって有利な結果を導く鍵となります。弁護士は和解の可能性や裁判へ進むかどうかの判断もサポートしてくれます。
弁護士選びで重視すべきポイント
弁護士を選ぶ際には、専門分野における経験と実績を確認することが不可欠です。
企業法務に熟練し過去に成功した実績を持つ弁護士は、より的確なアドバイスと戦略を提供できます。またコミュニケーション能力も重要な要素です。複雑な法律用語を分かりやすく説明できる能力は、経営層や関係者との連携において有益です。
これらのポイントを見極めることで、企業はより効率的で効果的な法的支援を受けることができます。弁護士の選択次第では訴訟の結果に大きな影響を及ぼす可能性があるため、慎重な選定が求められます。
民事訴訟についてのご相談は、法務救済から弁護士をお探しください
『法務救済』では、企業法務や民事トラブルに強い弁護士を全国から検索できます。
下部より『相談内容』『エリア』を選択し、弁護士検索にご活用ください。
本サイトへの登録や手数料は一切不要です。また本サイトで紹介する事務所へは無料で相談が可能です。ぜひこの機会に『法務救済』から弁護士検索をご活用くださいませ。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












