弁護士費用と訴訟費用の違いとは?料金体系・節約方法・弁護士の探し方を解説
訴訟・紛争解決
2025.02.26 ー 2025.03.06 更新

法的トラブルを抱えたとき、裁判という選択肢は有効です。しかし、裁判を進めるにあたって費用が必要になるため、見通しが立たないと判断に迷うかもしれません。
裁判では大きく分けて、弁護士費用と訴訟費用の2つが発生します。どちらも訴訟内容や依頼業務によって料金は変動しますが、およその目安を把握しておくだけでも、費用負担がどれくらいか見通しが立てられるはずです。
この記事では、弁護士費用と訴訟費用の違いや料金体系について解説します。また、民事訴訟に向けた弁護士の探し方についても言及するので、ぜひ最後までご覧ください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。民事訴訟について弁護士に相談したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>弁護士費用の内訳と相場

民事訴訟にかかる弁護士費用の内訳は、以下のようになっています。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
それぞれの費用の相場について解説していきます。
相談料の相場
相談料とは、弁護士に法的アドバイスを求める際に発生する費用です。
多くの法律事務所で時間制で設定されており、一般的には30分あたり5,000円程度が相場とされています。1時間相談すると1万円前後かかることが多いですが、事務所によって料金体系は異なります。
初回相談を無料で実施する法律事務所もあり、債務整理や離婚問題などの分野では無料相談の機会が多く提供されています。ただし、無料相談は時間が制限されていることが多いです。
着手金の相場
着手金とは、弁護士に事件を依頼した時点で支払う費用であり、結果に関係なく返還されないのが特徴です。弁護士が案件に着手し、法的手続きを進めるための対価として支払われます。
着手金の相場は、一般的に請求額の5%〜8%程度が目安とされています。請求額が大きくなるほど割合は低くなり、1,000万円を超える請求では3%〜5%程度に設定されることもあります。また、交渉・調停・訴訟など手続きの種類によっても金額は変動します。
法律事務所によって料金体系は異なり、定額制や成功報酬を重視する事務所もあります。そのため、依頼前に費用を確認し、見積もりを取るようにしましょう。
成功報酬の相場
成功報酬とは、訴訟の勝訴や和解の成立など、依頼者にとって有利な結果が得られた場合に発生します。成功報酬の金額は、案件ごとに異なり、弁護士と依頼者の契約内容によって決まります。
一般的な成功報酬の相場は、獲得した金額の10〜16%程度が目安とされています。ただし、事案の難易度や弁護士の経験によって変動するため、事前に確認しておくようにしましょう。
また、成功報酬は金銭的な利益だけでなく、例えば不動産の所有権を獲得する場合や、権利関係の確認が認められるケースでも発生することがあります。金額の算定基準は案件ごとに異なるため、詳細な取り決めが必要です。
弁護士費用を依頼前にしっかり確認し、成功報酬の発生条件や支払い方法について納得した上で契約してください。
弁護士費用は相手に請求できる?

民事裁判において、弁護士費用を相手に請求できるかどうかは、法律上の原則と例外によって異なります。
日本の民事訴訟では、「弁護士費用は原則として自己負担」というルールがあります。仮に訴訟に勝訴しても、依頼した弁護士費用をそのまま相手に請求することは基本的に認められていません。
しかし、例外的に弁護士費用の一部を相手に請求できるケースもあります。例えば、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、弁護士費用も損害の一部とみなされることがあります。裁判所は、一般的に認められる範囲として請求額の10%程度を弁護士費用相当額として損害賠償に含めることが多いです。
また、契約書に「弁護士費用を相手方が負担する」という特約がある場合、裁判所がその内容を有効と判断すれば、弁護士費用の請求が可能になることもあります。
訴訟費用では「敗訴者負担の原則」が適用される
民事訴訟では、「敗訴者負担の原則」が適用されます。これは、裁判にかかる訴訟費用を原則として敗訴した側が負担するというルールです。
例えば、原告が訴えを起こして勝訴した場合、被告は裁判所が認めた訴訟費用を支払う義務を負います。
敗訴者負担の原則に基づく訴訟費用の支払いは、裁判所の判決で確定します。勝訴者が訴訟費用の請求を行い、敗訴者が支払わない場合は、強制執行の手続きを取ることも可能です。
弁護士費用を抑える方法

弁護士に民事訴訟を依頼する場合、決して少額な費用で済むことはありません。そのため、弁護士費用に不安のある方は、以下の方法で費用を抑えることが効果的です。
- 法テラスを利用する
- 弁護士保険に加入する
- 分割払い・後払い制度を利用する
それぞれの方法について解説していきます。
法テラスを利用する
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない人でも法的支援を受けられるように設立された公的機関で、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を提供しています。
法テラスの立替制度は、一定の収入・資産要件を満たす人が対象となり、弁護士費用や訴訟費用を立て替えてもらうことができます。これにより、一括で高額な弁護士費用を支払うことが難しい場合でも、適切な法的支援を受けることが可能です。
また、法テラスを通じて弁護士を紹介してもらうことで、通常の弁護士費用よりも低額な料金で依頼できるケースもあります。弁護士費用の基準が法テラスによって設定されているため、費用が不透明になる心配が少なく、安心して利用できます。
弁護士保険に加入する
弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際に、弁護士費用の一部または全額を補償する保険です。契約者は毎月一定の保険料を支払うことで、万が一の訴訟や法律相談にかかる費用負担を軽減できます。
弁護士保険の補償内容は保険会社や契約プランによって異なりますが、一般的には以下のような費用が該当します。
- 法律相談
- 示談交渉
- 訴訟費用
一部の保険では着手金や成功報酬の補助も受けられるため、弁護士を依頼する際の経済的負担を大幅に軽減できます。
弁護士保険は、個人向けだけでなく企業向けのプランもあります。法人向けの保険では、契約トラブルや労務問題など、事業運営に伴う法的リスクに対応できるものもあり、企業の法務対策として有効です。
分割払い・後払い制度を利用する
弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合、分割払いもしくは後払いで負担を軽減できます。
分割払いは、弁護士と契約時に合意すれば、着手金や報酬金を複数回に分けて支払うことができます。特に高額な費用が発生するケースでは、一度に全額を用意する必要がなく、計画的に支払うことが可能になります。
後払い制度では、裁判が終了した後に報酬金を支払うことが可能です。損害賠償請求訴訟や未払い給与の回収など、裁判の結果として金銭を得られる可能性が高い場合に適用されることが多いです。
どちらを採用するかは弁護士と打ち合わせ、どうやって支払うかお互いに共有しておくようにしましょう。
適正価格で依頼できる弁護士の探し方
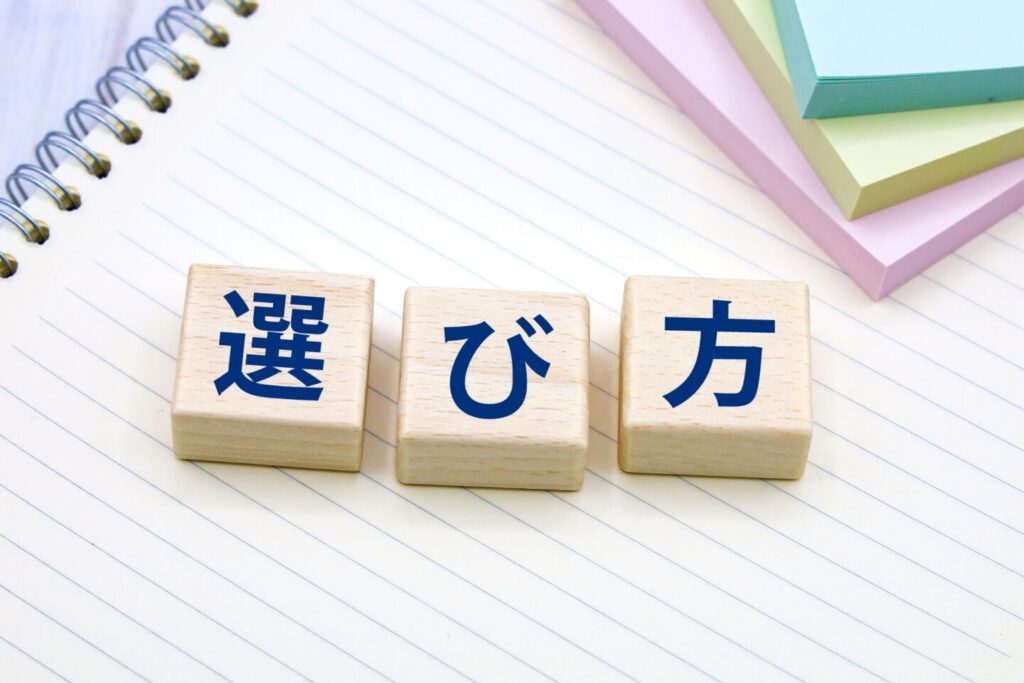
ここまで弁護士費用の相場について解説しましたが、詳細な費用は弁護士や法律事務所によって異なります。
適正価格でサービスを受けるには、以下のような方法で弁護士を探してください。
- 複数の法律事務所に相談する
- 弁護士の専門性と経験を考慮する
- 費用体系が透明であるか確認する
それぞれの探し方について解説していきます。
複数の法律事務所に相談する
弁護士費用は法律事務所ごとに異なり、同じ案件でも費用の設定や報酬体系が変わることがあります。そのため、1か所だけで決めるのではなく、複数の事務所を比較検討することが必要です。
比較する際は、法律事務所の公式サイトなどで費用の目安を確認し、無料相談を実施している事務所を探すとよいでしょう。初回相談が無料であれば、複数の弁護士と話をすることができ、費用だけでなく、対応の丁寧さや専門性の違いを比較できます。
複数の法律事務所に相談することで、相場を把握し、自分に合った弁護士を選ぶ判断材料を増やすことができます。
弁護士の専門性と経験を考慮する
適正価格で依頼できる弁護士を選ぶには、費用の安さだけでなく、取り扱う分野での実績や専門性を確認することが大切です。
特に民事訴訟では、該当する分野に精通している弁護士に依頼することで、適切な戦略を立て、訴訟を有利に進めることが可能です。経験豊富な弁護士であれば、訴訟の見通しや解決策について的確なアドバイスを提供できるため、無駄な費用が発生するリスクを抑えることができます。
専門性と経験を見極めるためには、弁護士のホームページや法律相談サイトを活用し、過去の実績や取り扱い事例を確認するのが有効です。ここでも、比較検討が重要になります。
費用体系が透明であるか確認する
料金体系が明確でない場合、想定以上の費用が発生するリスクがあります。そのため、事前に費用の内訳を確認し、納得できる条件で契約することが必要です。
弁護士費用の場合、成功報酬は変動しやすいため、請求額の何パーセントが適用されるのかを事前に把握しておく必要があります。他の費用についても、契約前におよそいくらかかるか把握できるかをチェックしましょう。
料金表が公開されている事務所は、透明性が高く、後から不明瞭な請求が発生するリスクが低い傾向があります。逆に、費用の説明が不十分な場合は注意が必要です。
まとめ
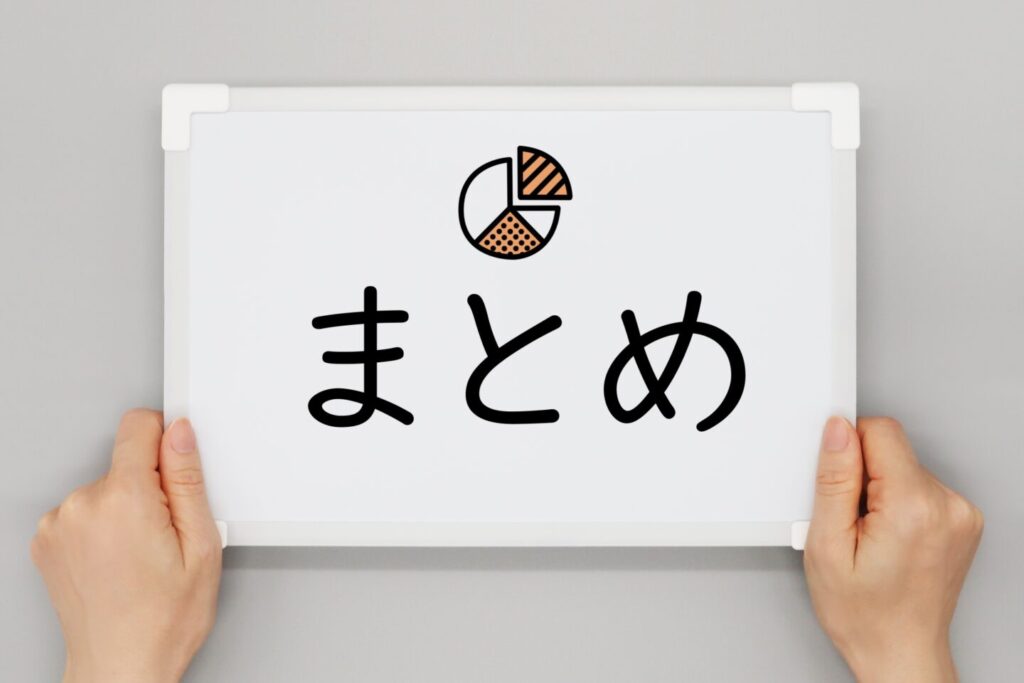
訴訟における弁護士費用は、原則として自己負担です。判決によっては一部を相手方に請求することも可能ですが、基本は自分で全て負担するとして資金を準備するべきでしょう。
ただし、詳細な弁護士費用は訴訟内容によって異なるため、正確な金額を算出するのは難しいでしょう。実際に訴訟を提起することになった場合は、弁護士に相談して、具体的な金額を把握してください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。弁護士費用の詳細を把握したい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












