英文契約のリスクを徹底解説!見落としやすい条項と実践チェック法
英文契約
2025.12.16 ー 2025.12.16 更新

海外企業との取引が増える今、英文契約書に目を通す機会も増えていませんか?「内容を本当に理解できているか不安」「専門用語が多くて正確に把握しきれない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、英文契約には日本語契約とは異なる考え方や構造があります。それを知らずに進めてしまうと、思わぬリスクにつながることも。
この記事では、英文契約に関わる基本的な知識とリスクの実態を、現場の担当者の視点でやさしく解説します。

英文契約リスクの基礎知識
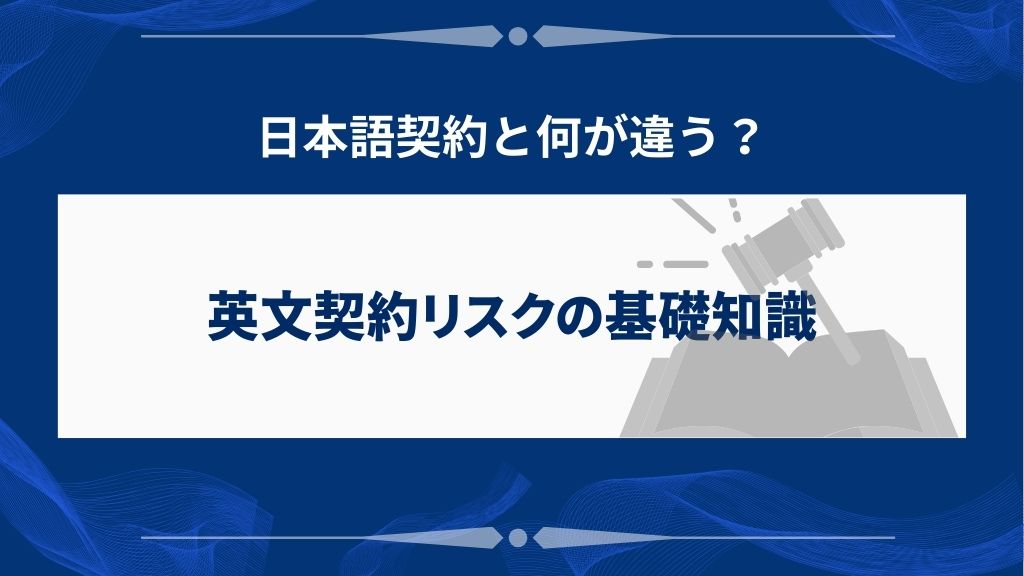
英文契約と日本語契約の違いと注意点
英文契約と日本語契約は、言語だけでなく法制度や商習慣も異なります。そのため、同じような条項に見えても実際の意味合いや効力が大きく違うことがあり、これがトラブルの火種になりがちです。
まず大きく異なるのは、契約の構成と詳細度です。日本の契約書は、商慣習や信頼関係を前提に、曖昧な表現を許容する書き方が一般的です。「誠実に協議する」「合理的な期間内に」といった抽象的な表現が多くても、実務上は問題視されないケースも珍しくありません。これに対し、英文契約(特に米国・英国系)は「すべてをこの契約書に書き込む」という姿勢で作られます。これが完全合意条項(Entire Agreement Clause)です。つまり、この契約書に書かれていない内容は原則として無効です。商談時のメールや口頭でのやりとりも、契約書に記載がなければ法的拘束力はないと見なされるのです。
次に、準拠法と管轄の選択にも大きな違いがあります。日本国内の取引では、何も規定がなくても日本法が自動的に適用されます。しかし英文契約では、「この契約はニューヨーク州法に準拠する」「紛争はロンドンの裁判所で解決する」といった条項が必ず記載されています。例えば、米国法には懲罰的損害賠償(Punitive Damages)という制度も。悪質な契約違反に対し、通常の損害額を大幅に超える賠償が科されるため、日本の契約では想定しにくいリスクが存在します。
また、英文契約では責任制限条項(Limitation of Liability)が頻繁に設定されます。「契約金額の範囲内にのみ責任を負う」「間接損害については一切責任を負わない」といった記載がある場合、万が一トラブルが起きても相手方からの損害賠償請求が制限されます。逆に言えば、自社がこうした条項を見逃していると、予想をはるかに超える損害賠償を請求されかねないのです。
英文契約では、こうした違いを理解したうえで、自社にとって不利な条項がないか、曖昧な表現がリスクになっていないかを慎重に確認する姿勢が求められます。社内に法務担当者がいない場合や、英語力に不安がある場合は、専門家のサポートを得るのがトラブル防止に役立ちます。
英文契約でよくある誤解・失敗事例
英文契約に不慣れな担当者が陥りやすいのは、「契約書は形式的なものだ」「日本の感覚で対応すれば大丈夫」といった誤解です。こうした認識のズレが、実際の取引現場で思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。
誤解①:「契約書に書いていなくても、商談で話した内容は有効」
日本では、契約書に記載されていない事項も、商談時のメールや口頭でのやりとりが証拠として認められるケースが多く見られます。しかし英文契約では、完全合意条項があるため、契約書に書かれていない内容は原則無効と見なされます。実際に、納期の遅延で損害賠償を請求された日本企業が、口頭での合意を主張したものの認められず、多額の支払いを余儀なくされた事例もあります。
誤解②:「英文契約書は相手が作ったものだから、こちらが修正提案するのは失礼」
日本のビジネス文化では、「相手の提案を尊重する」姿勢が美徳とされることもあり、海外企業から提示された契約書に対して遠慮してしまう方もいるでしょう。しかし、英文契約の世界では交渉は当然の前提であり、契約内容を修正すること自体が失礼に当たるわけではありません。むしろ、何も言わずにサインすることは「すべての条項に合意した」と見なされるため、後から「不利な条項だと気づかなかった」と主張しても通用しません。日本企業にとっては裁判費用や移動コストが膨大になりますが、交渉なしに署名してしまうと、その条項に拘束されてしまいます。
誤解③:「翻訳ツールを使えば十分理解できる」
近年、DeepLやGoogle翻訳、ChatGPTなど、生成AIの進化で英文契約書の翻訳は驚くほど手軽になりました。数秒で全文を日本語に変換でき、一見すると正確な文章に見えるかもしれません。しかし、契約書で使われる法律用語や定型表現は、一般的な英語とは異なるニュアンスを持つことが多く、翻訳ツールでは正確に捉えきれないのです。例えば「shall」は単なる未来形ではなく「義務を負う」という意味であり、「may」は「してもよい」ではなく「権利がある」という意味で使われます。また、「material breach(重大な違反)」と「minor breach(軽微な違反)」の違いを翻訳ツールが正確に訳し分けるのは難しく、法的リスクの判断を誤る原因になりがちです。
失敗事例:損害賠償の範囲を見落としたケース
ある日本企業が、海外企業とソフトウェアのライセンス契約を締結した際、「Consequential Damages(間接損害)についても責任を負う」という条項が含まれていました。日本側の担当者は「損害賠償は契約金額の範囲内だろう」と考え、特に問題視せずにサイン。しかし、ソフトウェアの不具合によって取引先のシステムが停止し、間接的に顧客への納品遅延が発生しました。取引先は「間接損害」として数百万円の賠償を請求。日本企業側は「そんな大きなリスクは想定していなかった」と主張しましたが、契約書に明記されていたため、支払いに応じざるを得ませんでした。
このように、英文契約では「知らなかった」「誤解していた」では済まされないリスクが潜んでいます。契約内容を正確に理解し、必要に応じて交渉や修正提案を行うこと。それが後々のトラブルを防ぐ重要なステップとなります。
英文契約リスクが発生しやすい場面(実例付き)
英文契約リスクは、取引の種類や契約内容によって発生しやすい場面が異なります。ここでは、現場でよく見られる具体的なシチュエーションと、それに伴うリスクの実例を紹介します。
・製造委託契約(Manufacturing Agreement)でのリスク
海外の工場に製品の製造を委託する際、品質基準や検査方法が曖昧なまま契約を結んでしまうと、後々トラブルにつながる可能性があります。例えば、「製品は業界標準に準拠する」という条項だけが記載されていた場合。日本企業が考える「業界標準」と海外工場が認識する「業界標準」が異なることもありえます。このような場合、契約書に具体的な検査項目や合格基準を明記しておけば、リスクを回避できます。
・ライセンス契約(License Agreement)での知的財産リスク
ソフトウェアや特許のライセンス契約では、「知的財産権の帰属」が曖昧だと大きなリスクになります。例えば、日本企業が開発したソフトウェアを海外企業にライセンス提供する際、契約書に「改変した部分の知的財産権は譲渡される」と記載されていた場合。相手方が改変したバージョンを自由に販売・再ライセンスできてしまう可能性も。こうしたリスクを防ぐには、「派生物の知的財産権は元のライセンサーに帰属する」といった条項を明示しておくことが重要です。
・販売代理店契約(Distribution Agreement)での独占条項リスク
海外市場での販売を任せる代理店契約では、「独占的販売権(Exclusive Rights)」の範囲が曖昧だと、自社の販売機会を失うリスクがあります。例えば、ある日本企業が欧州地域の販売権を独占的に付与したつもりが、契約書には「欧州全域」とだけ記載されており、具体的な国名や販売方法(オンライン販売を含むか)が明記されていませんでした。その後、日本企業が欧州向けにオンライン販売を開始したところ、代理店から「独占契約違反だ」として損害賠償を請求され、裁判に発展。この場合、「独占販売権は店舗販売に限定し、オンライン販売は含まない」といった条項を入れておけば、トラブルを避けられた可能性があったのです。
英文契約リスクを最小化するためのチェックリスト
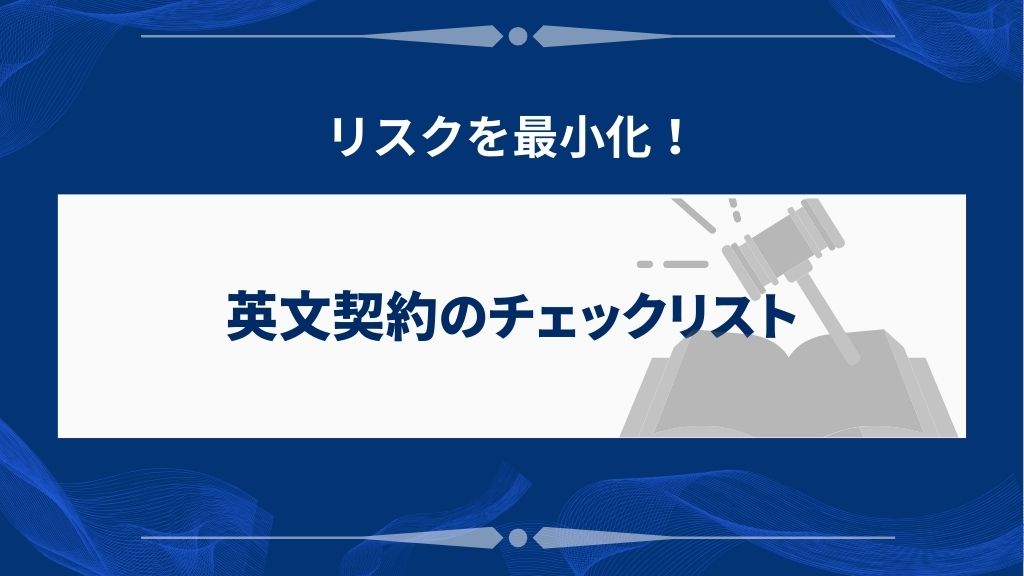
英文契約では、わずか一行の読み飛ばしが後々大きなトラブルを招く可能性もあります。限られたリソースの中でリスクを最小限に抑えるため、押さえておくべき具体的なポイントを見ていきましょう。
英文契約のチェックは、単なる翻訳作業ではありません。相手国の商習慣、法制度、そして自社のリスク許容度を総合的に考慮しながら、契約条項の「意味」と「影響」を正確に把握する必要があります。
すべての条項を完璧に理解しようとするよりも、「どこにリスクが潜んでいるのか」「どの条項を優先的に確認すべきか」という視点を持つことが現実的です。限られた時間と人員の中で効率的にリスクを洗い出すには、チェックリストという形で「見るべきポイント」を明確化し、社内で共有しておくことが有効でしょう。
必ず確認したい重要条項(損害賠償・免責・準拠法など)
英文契約書には数十ページに及ぶ条項が並ぶこともありますが、その中でも特にリスクが高く、トラブル時に直接影響を及ぼす条項があります。それが、損害賠償(Indemnity / Liability)、免責(Limitation of Liability)、準拠法(Governing Law)、紛争解決(Dispute Resolution)といった、いわゆる「ボイラープレート条項」です。
損害賠償条項では、どのような事象が発生したときに、誰がどこまで責任を負うのかが規定されています。例えば、製品の欠陥によって相手方に損害が生じた場合、その賠償範囲が「直接損害のみ」なのか「間接損害・逸失利益まで含む」のかによって、負担額は桁違いに変わります。特に注意すべきは、”indirect, consequential, or incidental damages”(間接的・結果的・付随的損害)という表現です。これが免責されていない場合、予想外の高額請求を受けるリスクがあります。
免責条項は、損害賠償の上限額や免責事由を定めるもので、自社を守るための「防波堤」ともいえる条項です。例えば、”Liability shall not exceed the amount paid under this Agreement”(本契約に基づき支払われた金額を超えない)という文言があれば、賠償額は契約金額が上限となります。一方、相手方が無制限の賠償を求める条項(”unlimited liability”)を盛り込んできた場合は、交渉の余地があるか慎重に検討する必要があるでしょう。
準拠法と紛争解決の条項も見落としてはなりません。準拠法が相手国の法律に設定されている場合、その国の法制度や裁判手続きに従うことになり、自社にとって不利な解釈がなされる可能性も。また、紛争解決の方法が「仲裁(Arbitration)」なのか「訴訟(Litigation)」なのか、仲裁地がどこに設定されているのかも重要です。日本国内での解決や、第三国での中立的な仲裁を提案することも選択肢の一つです。
これらの条項は契約書の末尾にまとめられていることが多く、つい読み飛ばしてしまいがちですが、トラブルが起きたときに真っ先に参照されるのがこの部分です。契約締結前に、必ず自社の法務担当者または外部の専門家(弁護士・司法書士など)に確認してもらうことを強くお勧めします。

AI・翻訳ツール利用時の落とし穴と対策
近年、DeepLやGoogle翻訳、ChatGPTなど、生成AIの進化で英文契約書の翻訳は驚くほど手軽になりました。数秒で全文を日本語に変換でき、一見すると正確な文章に見えるかもしれません。しかし、契約書という性質上、AIや翻訳ツールに全面的に依存することに大きなリスクが伴うのです。
最も危険なのは、文脈に応じた法律用語の誤訳です。例えば”shall”という助動詞は「〜しなければならない」という義務を意味しますが、AIが単に「〜するものとする」と訳してしまうと、義務なのか推奨なのか曖昧なままになります。また”subject to”という表現には「〜に従う」と「〜を条件として」という二つの意味があり、前後の文脈で解釈が異なります。AIはこうした微妙なニュアンスを正確に判断できない場合があるのです。
さらに、専門用語の訳語の不統一も問題です。同じ契約書内で”warranty”が「保証」と訳されたり「担保」と訳されたりすると、読み手が混乱します。また、”indemnify”と”hold harmless”は意味が重なる部分もありますが、厳密には異なる概念です。こうした違いをAIが正確に区別して訳出できるとは限りません。
もう一つ見落とされがちなのが、否定表現や例外条項の誤認識です。英文契約では、”except”や”provided that”、”notwithstanding”といった接続詞で条件や例外が挿入されることが多く、これを見落とすと契約の意味が180度変わってしまいます。AIは文の構造を機械的に処理するため、こうした例外構造を正しく反映できないことがあるでしょう。
では、どう対策すればよいのでしょうか。まず、翻訳ツールはあくまで「下訳」として使うことが基本です。AIに全文を訳させた後、必ず原文と照らし合わせながら、特に重要条項(前述の損害賠償・免責・準拠法など)は人間の目で再確認しましょう。また、専門用語は統一した用語集(グロッサリー)を用意しておくと、社内でのコミュニケーションがスムーズになります。
チェックの流れと社内体制のポイント
英文契約のチェックを属人的な作業に任せきりにすると、担当者の異動や退職時に知識が引き継がれず、同じミスが繰り返される恐れがあります。リスクを最小化するには、組織としてのチェック体制を整えることが不可欠です。
まず、契約書が届いたら全体を俯瞰することから始めましょう。契約の種類を確認し、契約期間、対価、主要な義務内容を把握します。この段階では細部にこだわらず、「この契約で何が約束されているのか」を大まかにつかむことが目的です。
次に、重要条項を優先的にチェックします。前述の損害賠償、免責、準拠法、紛争解決に加え、解除条件(Termination)、守秘義務(Confidentiality)、知的財産権の帰属(Intellectual Property Rights)なども確認が必要です。これらは契約書の後半に配置されていることが多いので、目次(Table of Contents)があれば活用しましょう。
その後、不明点や懸念点をリストアップし、社内で協議します。営業担当者や技術担当者など、契約内容に関わる部門と情報を共有し、「この義務は履行可能か」「このスケジュールは現実的か」といった実務的な観点からも確認を行います。法務担当者だけで判断できない事項は多いため、横断的なチーム体制が理想的です。
外部専門家への相談タイミングも重要です。すべての契約を専門家に依頼する余裕がない場合でも、「高額契約」「初めて取引する国の企業」「複雑な技術が絡む契約」などの基準を設け、リスクが高いと判断されるものは早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。
また、契約チェックのナレッジを蓄積する仕組みも有効です。過去にトラブルになった条項や、交渉でうまくいった修正例を社内データベースに記録しておけば、次回以降の契約交渉がスムーズになります。「このフレーズは削除を求めるべき」「この条件は譲れない」といった判断基準が共有されることで、組織全体のリスク対応力が向上するでしょう。
英文契約のリスク管理・防止の実務ガイド
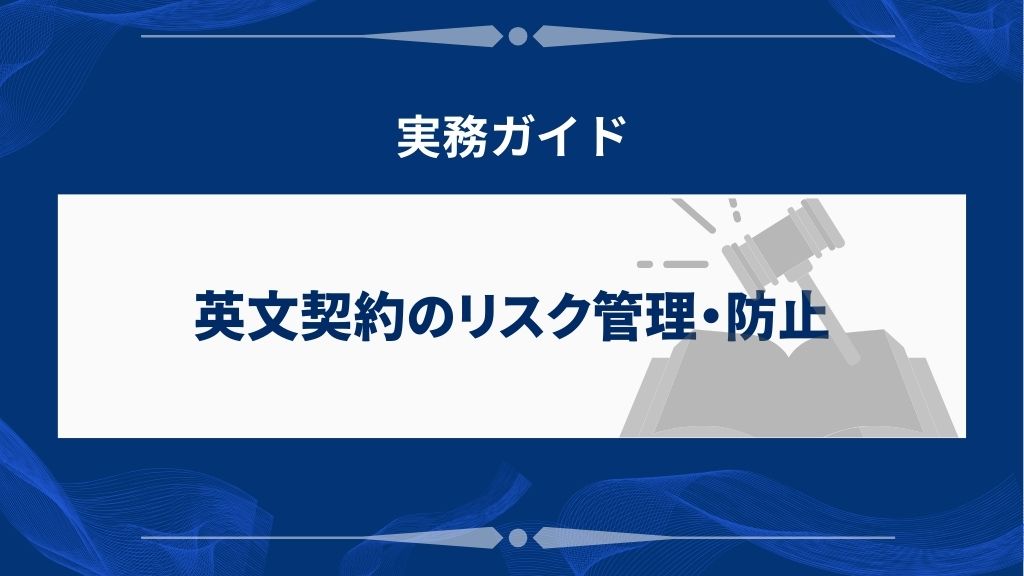
英文契約におけるリスクは、言語の壁だけではありません。契約書のフォーマットや法律用語、準拠法や紛争解決条項など、確認すべきポイントは多岐にわたります。しかし、すべてを完璧に理解する必要はないのです。重要なのは「どこを重点的にチェックすべきか」を知り、「誰に何を任せるべきか」を判断できる体制を整えることです。
チェック体制の作り方と運用のコツ
英文契約のチェック体制は、大企業のように専任の法務担当を置くのが理想ですが、中小企業ではなかなか難しいのが現実です。そこで有効なのが「段階的チェック」と「役割分担」を組み合わせた体制です。契約書を受け取ったら、まずは営業担当者が取引条件の基本部分を確認し、次に管理部門が支払条件やリスク条項をチェックし、最後に経営層または外部専門家が全体を見直すという流れを作ってみましょう。
この体制の要となるのが「チェックリスト」です。英文契約書で必ず確認すべき項目を一覧にまとめておくと、誰がチェックしても一定の品質が保てます。具体的には、契約の当事者名と住所、契約期間と自動更新の有無、支払条件と通貨、納期と品質基準、損害賠償の上限額、知的財産権の帰属、機密保持義務、準拠法と紛争解決方法など。これらを「必須チェック項目」として、契約書ごとにチェックマークを入れていく習慣をつけると、見落としが大幅に減るでしょう。
実務的なコツは「英文契約書のテンプレート化」です。自社が発注側の場合、できるだけ自社側で契約書の雛形を用意し、相手に提案する形を取ると有利になります。取引条件の大枠が自社のルールに沿った形になるため、リスクの入り口を狭められます。ただし、一方的に有利な内容にすると相手から修正要求が出るため、業界標準に近い、公平なバランスの雛形を持つことが理想です。
社内でのチェック体制が回り始めたら、定期的に「契約レビュー会議」を開くことをお勧めします。月に一度、営業・管理・経営が集まり、進行中の契約案件を共有し、問題がないかを確認する場です。この会議があると、属人化を防げるだけでなく、リスクの早期発見にもつながるもの。「この条項、前回と違うけど大丈夫か?」といった気づきは、複数の目があってこそ生まれるのです。
契約管理ツール・AI活用の最新動向
近年、英文契約の管理や分析を支援するツールが急速に進化しています。AIを活用した契約書レビューツールは実用レベルに達しており、中小企業でも導入しやすい価格帯のサービスが増加。これらのツールは、契約書をアップロードするだけで、リスクのある条項を自動抽出し、過去の契約との差分を比較し、さらには修正案まで提示してくれるものもあります。
代表的なツールとしては、クラウド型の契約管理プラットフォームがあります。これらは契約書を一元管理できるだけでなく、更新期限のアラート機能や、契約内容の検索機能も備えているのです。紙やPDFでバラバラに保存している状態から脱却するだけでも、リスク管理の精度は格段に上がります。
AI翻訳の進化も見逃せません。従来の機械翻訳では法律用語の誤訳が頻発していましたが、現在のAI翻訳エンジンは契約書に特化した学習を積んでおり、かなり自然で正確な訳文を出力できるようになっています。ただし、AIはあくまで「第一次チェック」の効率化ツールとして活用するのが賢明です。
一方で、ツール導入時の注意点もあります。まず、どんなに優れたツールでも、自社の業務フローに合わなければ形骸化してしまうもの。導入前に「誰が・いつ・どのように使うのか」を具体的に設計し、スモールスタートで運用テストを行うことが大切です。また、契約書という機密性の高い情報を扱うため、セキュリティ対策やデータ保管場所(国内サーバーか海外か)も確認しておく必要があるでしょう。
社外専門家に依頼すべき判断基準とコスト最適化
「外部の専門家に頼むと高額になるのでは?」という不安から、社内だけで無理に対応しようとするケースもよくあります。しかし、契約上のトラブルが発生したときの損失や対応コストを考えると、適切なタイミングで専門家の力を借りることは、むしろコスト削減につながるのです。
専門家への依頼を検討すべき場面として、まず「初めての取引形態や業種」が挙げられます。過去に扱ったことのない契約書は、リスクの所在が見えにくいため、最初の一件だけでも専門家にレビューしてもらうと安心です。その際、修正ポイントや注意点を詳しく教えてもらい、社内にノウハウとして蓄積すれば、二件目以降は自社でも対応しやすくなるでしょう。
次に、「契約金額が大きい案件」や「長期契約」も専門家の関与が望ましいケースです。数百万円以上の取引や、数年にわたる契約では、一つの条項の解釈ミスが大きな損失につながることも。特に損害賠償条項や製造物責任、知的財産権の扱いなどは、自社に不利な内容が紛れ込んでいても気づきにくい部分です。こうした重要案件では、弁護士や専門の翻訳会社にレビューを依頼することで、後々のトラブルを未然に防げるでしょう。
また「相手方から大幅な修正案が提示された場合」も、専門家の判断を仰ぐべきタイミングです。相手が提示してきた条項が、一見すると合理的に見えても、実は自社に一方的な義務を課していたり、紛争時に不利な立場に立たされる内容だったりすることがあります。特に海外企業との契約では、商習慣の違いから「これが標準」と言われても、日本の取引常識とは異なる場合も。第三者の視点でチェックしてもらうことで、冷静な判断ができます。
近年は、英文契約に強い弁護士だけでなく、契約翻訳の専門家や、法務コンサルタントなど、選択肢が広がっています。弁護士は法的リスクの判断に長けていますが、費用はやや高め。一方、翻訳会社の法務翻訳サービスは、契約書の正確な翻訳と基本的なリスク指摘をセットで提供していることが多く、比較的リーズナブルです。自社のニーズに応じて使い分けることで、コストパフォーマンスを高めることができます。

契約内容変更・修正時のリスクと対策
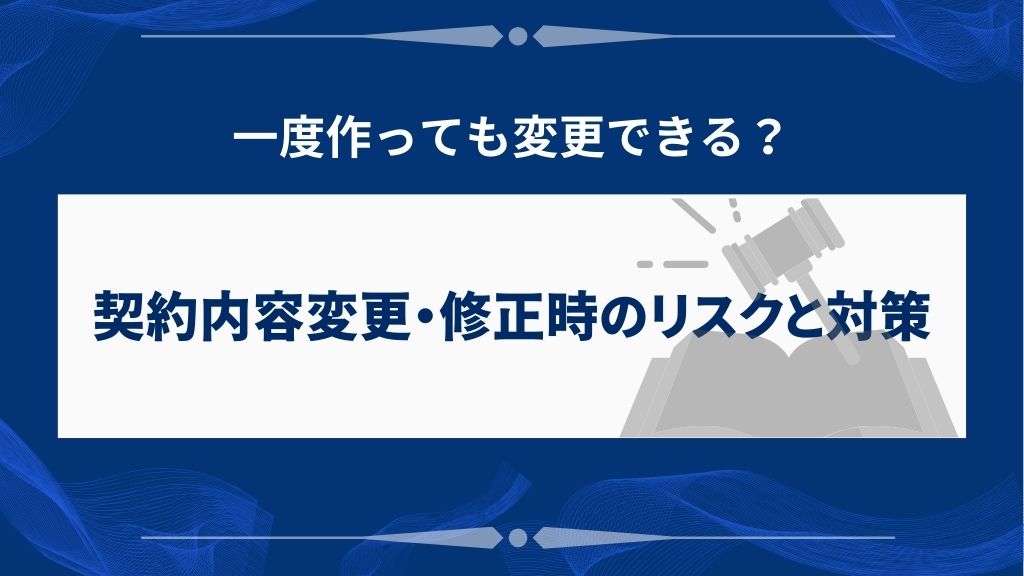
アメンドメント作成の注意点と実践例
契約内容を変更するとき、口頭やメールだけで合意したつもりになっていると、後で「そんな話は聞いていない」とトラブルになるケースがあります。特に海外企業との取引では、言語や文化の違いから誤解が生じやすいため、変更内容を正式な書面で残すことが非常に重要です。この書面を「Amendment(アメンドメント)」または「Addendum(アデンダム)」と呼びます。
アメンドメントとは、既存の契約書の一部を修正・追加する正式な文書のことです。例えば、納品スケジュールを2週間延長する、支払条件を前払いから分割払いに変更する、といった具体的な変更を記録します。この文書には、元の契約書のタイトルや締結日、変更箇所の条項番号、変更前と変更後の文言、そして両当事者の署名が必要です。
また、相手企業の社内承認プロセスを確認しておくことも大切です。海外企業では、契約変更に本社の法務部門や経営層の承認が必要な場合があり、署名までに数週間かかることも珍しくありません。事前に「署名権限を持つのは誰か」「承認にどれくらいの時間がかかるか」を確認しておけば、スケジュールの遅延を防げるでしょう。
アメンドメントを作成するときは、相手企業との信頼関係を保つコミュニケーションも忘れないでください。変更を一方的に通告するのではなく、「状況が変わったため、こちらの提案を検討していただけないか」と丁寧に説明し、相手の事情にも配慮する姿勢を見せることで、スムーズな合意形成につながります。契約書は法的な文書ですが、その背後には人と人との関係があることを忘れないようにしたいものです。
修正履歴管理と合意形成トラブル回避法
契約内容を変更する際、もう一つの大きな課題が「修正履歴の管理」です。特に複数回にわたって契約を変更した場合、どの条項がいつ、どのように変更されたのかを正確に把握できていないと、後で大きなトラブルに発展します。海外企業との取引では、時差や言語の違いから情報共有が遅れがちで、さらに担当者が変わると過去の経緯が分からなくなることも。こうした事態を防ぐために、修正履歴をしっかり管理し、合意形成のプロセスを透明にすることが不可欠です。
まず、修正履歴管理の基本は、すべての変更を時系列で記録することです。Excelやスプレッドシートで「変更管理表(Amendment Log)」を作成し、以下の情報を記録しておくと良いでしょう。
- 変更日(Amendment Date)
- アメンドメント番号(Amendment No.)
- 変更対象の条項(Article/Section)
- 変更前の内容(Original Text)
- 変更後の内容(Amended Text)
- 変更理由(Reason for Amendment)
- 署名者・承認者(Signatories)
- 発効日(Effective Date)
このような一覧表があれば、誰が見ても契約の変遷を把握でき、社内の引き継ぎや監査の際にも役立つでしょう。また、変更理由を記録しておくことで、「なぜこの条項を変更したのか」が後で分かり、将来の交渉の参考にもなります。
さらに、クラウドストレージ(Google Drive、Dropbox、SharePointなど)を活用し、共有フォルダで契約書と修正履歴を一元管理することをおすすめします。フォルダ構造を「契約書原本」「アメンドメント」「交渉メール」のように分けておけば、必要な書類をすぐに見つけられます。アクセス権限を設定して、関係者だけが閲覧・編集できるようにすることで、情報漏洩のリスクも減らせるはずです。
合意形成のトラブルを避けるためには、変更案を提示する際の手順も重要です。まず、変更案を相手企業に送る前に、社内で内容をしっかり確認しましょう。上司や法務担当者のレビューを受け、「この変更が自社にとって本当に有利か、不利な影響はないか」を検証します。その上で、相手企業に送る際は、メールの本文に変更の背景や理由を簡潔に説明することで、相手の協力を得やすくなるでしょう。
さらに、交渉過程のメールや議事録も保存しておくことが、後々のトラブル回避につながります。例えば、電話会議で口頭で合意した内容があれば、会議後すぐに議事録を作成し、「本日の会議で以下の点について合意しました。相違があればご連絡ください」と相手に送って確認を取るのです。この一手間が、後で「そんな話はしていない」と言われるリスクを大幅に減らすでしょう。
また、社内の情報共有も忘れてはいけません。契約変更の交渉を進めている担当者だけが情報を持っていて、上司や他の部署に共有されていないと、後で「そんな変更は承認していない」と社内で揉めることがあります。重要な変更については、定期的に社内会議で報告し、関係者全員が同じ情報を持つようにしましょう。特に、支払条件や納期、知的財産権など、会社の経営に大きく影響する条項の変更は、経営層への報告も必要です。
英文契約リスクに関するよくある質問・失敗事例集

英文契約には、日本語の契約とは異なる「落とし穴」が数多く潜んでいます。実際に起きた失敗事例から学び、よくある疑問への回答を知ることで、トラブルを未然に防ぎましょう。
代表的な失敗事例と解説
- 「準拠法」の見落としによる想定外の訴訟費用
ある日本の製造業A社は、アメリカの取引先と製品供給契約を締結しました。契約書には「Governing Law(準拠法)」として「カリフォルニア州法」と記載されていましたが、担当者はその意味を深く理解せずに署名してしまったのです。
その後、製品の品質トラブルが発生し、相手方から訴訟を提起されることに。日本の法律では製造物責任の範囲が比較的明確ですが、カリフォルニア州法では消費者保護が非常に強く、損害賠償額も高額になる傾向があります。A社は現地の弁護士を雇い、訴訟対応に数千万円の費用と2年以上の時間を費やす結果となりました。
- 支払条件の曖昧さが招いた資金繰り悪化
IT企業のB社は、海外のソフトウェア開発会社と業務委託契約を結びました。契約書には「Payment shall be made upon completion of the project(プロジェクト完了時に支払う)」とだけ記載されていました。
ところが、相手方は「一部機能の納品」を「completion(完了)」と主張し、早期の支払いを要求。一方B社は「全機能の納品とテスト完了」が完了条件だと理解していました。双方の認識のズレから支払いが遅延し、相手方は開発を一時停止。B社のサービスリリースは3ヶ月遅れ、機会損失は数千万円規模に及びました。 - 秘密保持契約の範囲があいまいで技術流出
電子部品メーカーのC社は、海外の販売代理店とNDA(秘密保持契約)を締結しました。しかし契約書の「Confidential Information(秘密情報)」の定義が曖昧で、「書面で『秘密』と明記した情報のみ」が対象とされていたのです。
その後、商談の中で口頭やメールで伝えた製品仕様や製造ノウハウが、代理店から競合他社に流出。C社は訴訟を検討しましたが、「書面で秘密指定していなかった」ために法的保護を受けられず、泣き寝入りする結果となりました。
すぐに解決できるQ&A
Q1:契約書が全文英語で届きました。日本語訳を作るべきでしょうか?
A:はい、できる限り日本語訳を作成することを強くお勧めします。
社内での情報共有のため: 経営層や他部署への説明時に日本語資料があると、意思決定がスムーズになるでしょう。また、トラブル発生時の証拠資料として、後々「こういう理解だった」と主張する際、日本語訳があると説得力が増します。
ただし注意点として、契約の正式な効力を持つのはあくまで「英語原文」です。日本語訳は理解の補助ツールであり、万が一齟齬があった場合は英語原文が優先されます。そのため、翻訳は信頼できる専門業者や法律知識のある翻訳者に依頼することが望ましいでしょう。
Q2:契約書に「E-signature(電子署名)でOK」と書いてありますが、法的に有効ですか?
A:はい、多くの国で電子署名は法的に有効です。ただし、方式や記録の保管が重要です。
日本では2001年施行の「電子署名法」により、一定の要件を満たした電子署名は紙の署名・押印と同等の法的効力を持つと認められています。海外でも、アメリカの「ESIGN法」やEUの「eIDAS規則」など、電子署名を認める法制度が整備されているのです。
なお、一部の契約(不動産売買など)では法律上、紙の書面や公証が必要な場合もあります。重要な契約の場合は、事前に専門家に確認すると安心です。
Q3:相手から送られてきた契約書に「As is(現状有姿)」と書いてあります。これは何を意味しますか?
A:「現状のまま・保証なし」という意味で、買主にとってリスクの高い条件です。
“As is”条項は、主に製品売買や不動産取引で使われ、「売主は商品の品質・性能について一切保証しない」「買主は現状を承知の上で購入する」という意味を持ちます。具体的には、購入後に製品の不具合が見つかっても、売主に修理・交換・返金を求めることが原則としてできなくなります。
買主側としての対策
- 契約前に入念な現物確認・検査(Inspection)を実施し、問題点を洗い出す
- As is条項を削除するか、少なくとも「重大な隠れた瑕疵については保証する」という例外条項を追加する交渉をしてみる
- どうしてもAs isを受け入れざるを得ない場合は、購入価格の値引きや保険付保を検討する
特に高額な機械設備やシステムの購入では、As is条項の有無が後々大きな影響を与えますので、慎重に判断してください。
Q4:契約書に「Indemnity(補償・免責)」という言葉が何度も出てきます。どう理解すればいいですか?
A:Indemnityは「一方が他方の損害を肩代わりする約束」で、責任範囲を大きく左右する重要条項です。
日本語では「損害賠償」「補償」「免責」などと訳されますが、英文契約におけるIndemnity条項は、日本の契約よりもはるかに強力で広範な効果を持つことが多いです。
実務上の注意点
- 対象範囲:「any claims(あらゆる請求)」は範囲が広すぎるため、「合理的に予見可能な範囲」「直接損害のみ」など限定できないか交渉しましょう。
- 金額上限:「最大で契約金額の〇倍まで」など上限(Cap)を設定しましょう。
- 相互性:一方的な補償条項ではなく、双方が相手の過失について補償する「相互補償(Mutual indemnity)」にできないか検討することも重要です。
Indemnity条項は、いざ紛争が起きたときに「誰がどこまで責任を負うか」を決める極めて重要な条項です。安易に受け入れず、必ず内容を精査してください。
Q5:「Arbitration(仲裁)」と「Litigation(訴訟)」はどう違いますか?どちらが有利ですか?
A:仲裁は非公開・迅速、訴訟は公開・慎重という違いがあり、一長一短です。
紛争解決の方法として、英文契約では「Arbitration(仲裁)」または「Litigation(裁判)」のいずれかを選択するのが一般的です。
Arbitration(仲裁)の特徴
- 非公開: 審理内容が外部に漏れないため、企業秘密保護に有利です。
- 迅速: 通常1年前後で結論が出ることが多く、裁判よりもスピーディーです。
- 専門性: 業界専門家を仲裁人に選べます。
- 一審制: 原則として上訴できないため、判断が覆ることはありません。
- 費用: 仲裁機関への手数料が高額になることがあります。
Litigation(訴訟)の特徴
- 公開: 原則として公開法廷で審理されるため、透明性が高いです。
- 慎重: 上訴が可能で、多段階の審理を経るため、時間はかかりますが慎重な判断が期待できます。
- 強制力: 判決は国家権力で強制執行可能です。
- 費用: 国によるものの、仲裁より低コストの場合もあります。
どちらが有利かは状況次第です。技術的・専門的な紛争で迅速な解決を望む場合は仲裁が向いています。一方、複雑な法律解釈が必要で慎重な審理を求める場合や、相手の不当性を社会に訴えたい場合は訴訟が適しているでしょう。
まとめ|企業が取るべき英文契約リスク対策の最適解
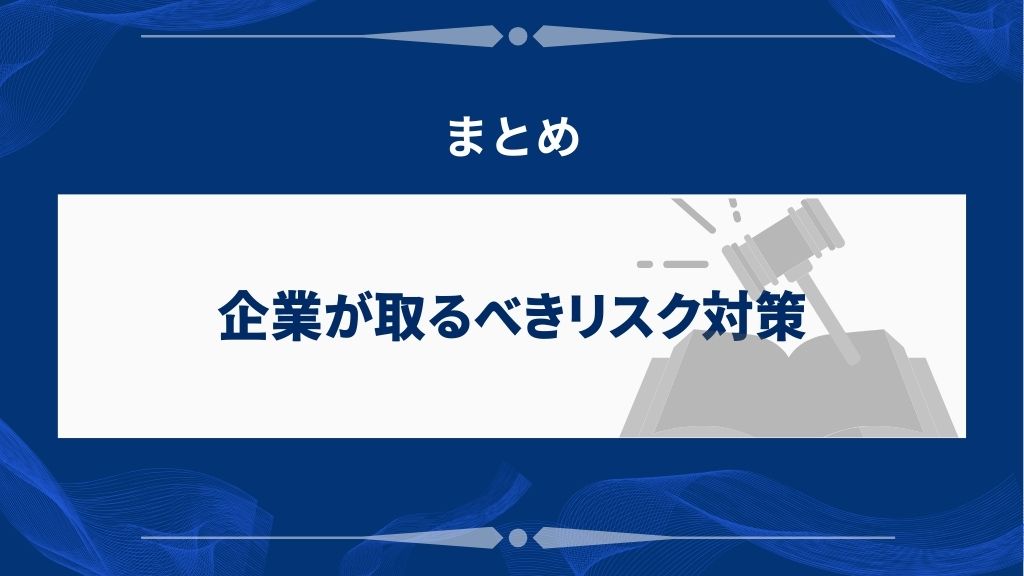
英文契約書のリスク管理は、企業規模や取引頻度に関わらず、海外ビジネスを行う全ての企業にとって避けて通れない課題です。ここまで見てきた通り、英文契約には日本の契約書とは異なる独特の構造や表現、そして法的な落とし穴が数多く存在します。
では、限られたリソースの中で、企業はどのように英文契約のリスクに向き合えばよいのでしょうか。最も重要なのは、「完璧を目指さない」という現実的な姿勢です。全ての英文契約を完璧に理解し、全てのリスクを自社だけで排除することは、大企業であっても困難でしょう。むしろ、「どこに専門家の力を借りるべきか」「何を優先的にチェックすべきか」という判断軸を持つことが、実務上の最適解となります。
法務急済運営事務局
法務急済運営事務局|株式会社WEBY 株式会社WEBYの法務急済運営事務局として、全国400以上の弁護士・司法書士事務所のWEBマーケティングを支援。法律分野に特化したWEB集客の知見を活かし、これまでに1,000本以上の法律系記事の企画・執筆・編集に携わる。HP制作、SEO対策、WEBコンサルティング、LMC(ローカルマップコントロール)など多角的なサポートを通じて、法律業界の最新動向に精通。 企業法務に求められる実務視点と、法律事務所支援で培った専門知識を基に、企業が抱える法務課題に対して実行可能な情報提供を行うとともに、適切な弁護士・司法書士の紹介も行っている。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。











