特許権侵害訴訟の流れと対策を徹底解説
知的財産・知財法務
2025.11.14 ー 2025.11.13 更新
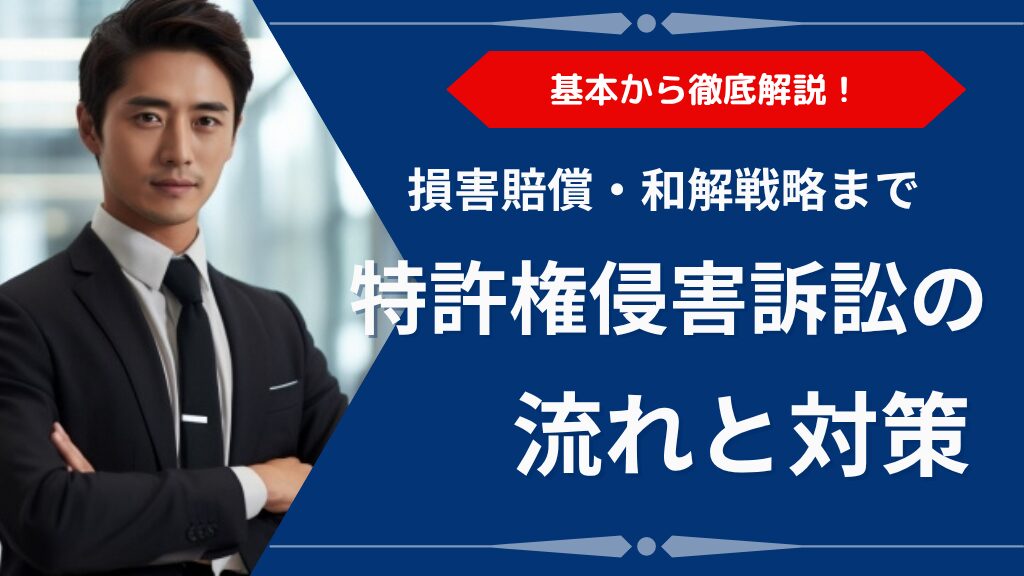
他社から「特許権を侵害している」と訴えられ、どうすればいいかお困りではありませんか?特許権侵害は複雑な問題ですが、正しい知識と対応策を知れば、事業への影響を最小限に抑えることができます。

特許権侵害訴訟とは?経営者が知っておくべき基礎知識
特許権侵害訴訟とは、特許権者が自分の特許権を無断で使用されたと判断した際に起こす民事訴訟です。社長の会社にとって、特許権侵害は事業の存続に関わる重大な問題となり得ます。しかし、訴えられたからといって必ずしも負けるわけではありません。特許権侵害の成立には厳格な要件があり、適切な対応で和解や勝訴につながるケースも少なくありません。この種の法律上の紛争を解決するには、特許権に基づき、その規定や手続を理解することが重要です。
特許権侵害訴訟では、主に損害賠償請求(過去の売上に対する補償)と差止請求(今後の製品販売停止)の2つが争点となります。特に差止請求は、主力商品の販売停止に直結する深刻な影響を与える可能性があるため、慎重な対応が求められます。訴訟は一般的に1年から2年程度の期間を要することも多く、早期解決には専門家のサポートが肝要です。訴訟の当事者は、差止めやライセンスといった当該の事案に係る解決策を探ります。
特許権侵害の定義と判断基準
特許権侵害とは、特許権者の許可なく、その特許発明(技術)を使った製品を製造・販売・使用することです。侵害の判断は、社長の製品やサービスが、特許の「請求の範囲(クレーム)」に書かれた技術的特徴をすべて含んでいるかどうかが基準となります。この判断は非常に専門的で複雑であり、特許の専門家による詳細な分析が欠かせません。特許法第百二条などに記載されるように、特定の物に対する行為が侵害に該当するかを推定し、認定することが求められます。
文言侵害と均等侵害の違い
特許権侵害には「文言侵害」と「均等侵害」という2つの判断基準があります。
- 文言侵害:製品が特許請求の範囲の文言に完全に一致する場合に成立します。比較的明確な判断基準です。
- 均等侵害:文言とは異なるが、実質的に同じ機能・効果を持つ場合に成立します。ただし、均等侵害が認められるには5つの厳格な要件をすべて満たす必要があり、専門的な判断が求められます。
均等侵害の構成要件が満たされるか否かは、解釈が難しく専門的な事項といえるでしょう。専門家に相談してみるのが最適でしょう。
特許の有効性(新規性・進歩性)について
特許権侵害で訴えられた場合の有力な反論手段の一つが、相手方の特許そのものの有効性を争うことです。特許が無効になれば、侵害も成立しません。特許の有効性は主に「新規性」(出願時点で世の中に知られていなかったか)と「進歩性」(専門家にとって容易に思いつくものではなかったか)の2つの観点から判断されます。ここで重要なのは、論点を捉え、一部や概要だけでなく当該の特許を理解することです。無効抗弁を行う前提として、特許の構成や採用された考え方を正確に評価しなければなりません。
特許の有効性を争う際は、特許庁での特許無効審判という手続きを利用することもできます。これは訴訟と並行して進めることができ、特許が無効になれば侵害訴訟での勝訴につながるでしょう。特許庁が下す審決は、訴訟における抗弁の重要な事由の一つと当ることが生じます。
警告書を受け取ったら?経営者が最初に取るべき対応
ある日突然、法律事務所から「特許権侵害の警告書」が届いたとき、まずは「冷静になること」が重要です。感情的な対応は状況を悪化させる可能性があります。警告書は相手方の主張であり、必ずしも法的に正当性があるとは限りません。
警告書への対応は、今後の事業継続に大きく影響する重要な判断です。初期対応が適切であれば、早期解決や相手の主張を退けることも十分に可能となるでしょう。
警告書の内容確認と分析方法
警告書を受け取ったら、まず内容を詳細に確認します。侵害されたとされる特許番号、問題の製品・技術、相手の要求(販売中止、損害賠償など)、そして回答期限が書かれています。
特許番号が記載されていれば、特許庁の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で該当特許の「請求項」を確認します。これは特許権の保護範囲を定めた最も重要な部分ですが、専門的で理解が困難なため、専門家による分析が不可欠です。侵害の態様を全体として捉えるには、警告書以外の参照すべき本やサイトの記事も確認します。
専門家への相談タイミングと選び方
特許権侵害の警告書を受け取った場合、専門家への相談は「できるだけ早く」が鉄則です。警告書には通常2週間から1か月程度の回答期限が設定されており、その間に適切な対応方針を決定する必要があります。
専門家選びで重要なのは、特許法に精通した弁護士や弁理士を選ぶことです。特許事務所出身の弁護士や、知的財産専門の法律事務所なら、より実践的なアドバイスが期待できます。相談時に準備すべき資料として、警告書の原本、自社製品の技術資料、売上データなどがあります。知的財産に詳しい弁護士法人を選ぶことは、訴訟の備えとして非常に重要です。
対応期限と返答の注意点
警告書に記載された回答期限は、無視するのは得策ではありません。期限内に回答しないと、相手はすぐに訴訟を提起するかもしれません。しかし、慌てて不利な内容で回答してしまうと、後の交渉で不利になるリスクもあります。
回答書では、まず「侵害の事実を認める表現」は絶対に避けてください。もし回答期限までに検討時間が確保できない場合は、期限延長を求めることも可能です。返答は記録が残る書面(郵送またはメール)で行いましょう。
特許権侵害訴訟の流れと期間の実態
特許権侵害で訴えられた時、多くの経営者は「一体どれくらいの期間と費用がかかるのか」「事業への影響はどの程度なのか」といった不安を抱えます。訴訟の実態を正しく理解することで、適切な判断と対策を立てられます。
訴訟開始から判決までの具体的ステップ
特許権侵害訴訟は、通常以下の段階を経て進行します。
- 訴状提出・送達:特許権者から裁判所に訴状が提出され、社長の会社に届く。約30日以内に答弁書を提出。
- 争点整理手続き:特許の有効性、侵害の有無、損害の範囲など、双方の主張を明確化。
- 証拠調べ:技術者の証人尋問や、製品の技術的分析結果の提出など。
- 口頭弁論・判決:裁判官による判決が言い渡される。
ただし、判決前に和解による解決が図られるケースも少なくありません。
この手続きでは、原告と被告がそれぞれの側の主張を行います。
審理期間の目安と長期化の要因
特許権侵害訴訟の審理期間は、一般的に1年から2年程度です。ただし、技術内容の複雑さ、特許の有効性に関する争い(無効審判との並行審理)、証拠収集の困難さ、損害額算定の複雑さなど、様々な要因で期間が延びることもあります。大手メーカー同士の訴訟では3年以上の審理期間を要したケースも報告されています。
各段階での企業への影響と対策
訴訟の各段階において、企業が受ける影響は多岐にわたります。法務部門や技術部門の人的リソースが大幅に割かれ、弁護士費用や技術鑑定費などで総額数千万円に及ぶ経済的負担も発生します。また、製品の販売差し止めリスクや、信用失墜リスクも考慮すべきです。
対策としては、訴訟リスクの早期把握(新製品開発時の特許調査徹底)、早期の和解交渉検討、そして特許に詳しい専門家との連携が不可欠です。
専門家への問い合わせはこちら>>>
これらの業務を行う際、知財の管理を徹底し、いずれの事項も本来の考え方のとおりに処理することが重要です。
代表的な過去判決事例の解説
特許侵害で訴えられることは大きな脅威です。過去の判例を知ることで、リスクの実態を把握し、適切な対処法を見つけられます。
中小企業に下された賠償命令の実態
平成28年の東京地裁判決では、従業員50名程度の製造業会社が大手メーカーの特許を侵害し、約5000万円の損害賠償を命じられました。「似たような製品は他にもある」「独自開発した」との主張も、特許の技術的範囲に含まれると判断され、後から独自開発しても侵害となるのが特許制度です。
令和元年の大阪地裁判決では、IT関連の中小企業がソフトウェア特許を侵害し約3200万円の賠償を命じられました。「特許の存在を知らなかった」と主張しましたが、特許侵害は故意・過失を問わず成立するため、通用しません。中小企業だからといって賠償額が軽減されるわけではなく、大企業と同等の法的責任を負うのが現実です。
損害賠償額が高額になったケース分析
損害賠償額が高額になるケースには共通点があります。平成30年の知財高裁判決では、電子部品製造の中小企業が業界大手の特許を侵害し、約1億2000万円の賠償を命じられました。侵害期間が5年間と長期にわたり、侵害品の売上高が年間数億円規模だったため、特許権者の逸失利益が大きく算定されたためです。
賠償額を抑えるためには、「早期発見・早期対処」が重要です。侵害に気づいた時点で速やかに製造・販売を停止し、適切な対応を取ることで、損害の拡大を防ぐことができます。
経営判断の分かれ道となった事例
特許侵害で訴えられた時の経営判断によって、その後の企業運命が大きく分かれることがあります。
- 成功例:プラスチック成形会社が大手化学メーカーから訴えられた際、早期に弁護士・弁理士チームを結成し、技術検討の結果、自社製品は特許の技術的範囲に含まれないことを証明し完全勝訴。約1500万円の訴訟費用を投じるリスクを負ったが、技術への確信から戦う価値があると判断しました。
- 和解例:精密機器の中小企業が早期に和解を選択し、約2000万円を支払って解決。長期間の訴訟による事業停滞リスクを避け、確実性を重視しました。
どちらの判断が正しいかは、技術的な争点の強さ、企業の財務状況、事業への影響度、経営者のリスク許容度など、様々な要素を総合的に考慮する必要があります。感情的にならず、専門家のアドバイスを受けながら冷静に判断することが大切です。これらの事例は顧客や業界のニュースにも生じる影響を示しており、最高裁まで争われた競合に関する事件の評価も得ることができます。
損害賠償請求とそのリスク
特許権侵害の通知を受け取って「損害賠償はいくらになるのか」と不安になっていませんか。中小企業にとって賠償請求は事業継続に関わる深刻な問題ですが、適切な対応で負担を軽減できる可能性を秘めています。
損害賠償額の算定方法(逸失利益・実施料相当額)
特許権侵害による損害賠償額の計算方法は、主に「逸失利益」と「実施料相当額」の2つに分けられます。
- 逸失利益:特許権者が「社長の会社が侵害しなければ得られたはずの利益」を基準に算定されます。特許権者の製品1個あたりの利益に、社長の会社が販売した数量を掛けて計算されます。
- 実施料相当額:「特許を正当に使わせてもらう場合に支払うべきライセンス料」を基準とします。売上高に一定の料率(通常1~10%程度)を掛けて計算され、逸失利益より低額になる傾向があるため、現実的な和解の選択肢となることが多いです。
どちらの方法を選ぶかは基本的に特許権者の判断によりますが、裁判では裁判所が適切と判断する方法で算定されます。算定においては、専用の号や単位が考慮される場合もあります。特許権者の実施権を行使する態様や、譲渡の有無が損害額算定に影響を生じる場合もあります。
中小企業が直面しやすい賠償リスクの範囲
中小企業が特許権侵害で直面する賠償リスクは、大企業とは異なる特徴があります。
- 資金力の制約:大企業なら影響が限定的でも、中小企業にとっては数百万~数千万円の賠償金が経営を脅かす重大な負担となります。
- 特許調査体制の不備:人的・資金的制約から特許調査が不十分になりがちで、知らずに侵害行為を続け、損害額が膨らんでしまうリスクが高いです。
- 交渉力の格差:大企業や特許専門会社を相手にする場合、豊富な訴訟経験と専門知識を持つ相手との交渉になり、不利な条件での和解に追い込まれるリスクがあります。
- 信用失墜リスク:取引先や金融機関からの信用失墜も、今後の事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。
賠償額を抑えるための交渉ポイント
損害賠償額を抑えるためには、いくつかの効果的な交渉ポイントがあります。
- 特許の有効性を検討する:相手の特許に新規性や進歩性などの要件を満たさない無効理由がないか調査し、特許無効審判を請求する。特許が無効になれば、損害賠償義務も消滅します。
- 侵害の範囲を正確に確定する:特許権者は侵害範囲を広く主張しがちですが、技術的な詳細を検討し、侵害に該当しない部分や期間を主張することで、損害算定の基礎となる金額を減額できる可能性があります。
- 支払い能力を適切に伝える:中小企業の財務状況を正確に開示し、高額な賠償金の支払いが事業継続を困難にすることを具体的な数字で示すことで、現実的な金額での和解に応じやすくなります。
- 早期の和解交渉:訴訟に発展すれば、弁護士費用や時間的コストが大幅に増加するため、侵害の事実が明らかな場合は、早期に現実的な和解案を提示し、双方にとって負担の少ない解決を目指しましょう。
独占禁止法との競合や同法の適用についても両者を考慮し、許諾条件を含めて適切に変更を提案します。
特許権侵害訴訟での実践的対策と和解戦略
突然特許権侵害で訴えられた時、多くの経営者が「何から手をつければいいのか分からない」と混乱されます。しかし適切な準備と戦略があれば、事業への影響を最小限に抑えることができます。
中小企業の場合、限られた資金と時間の中で効率的に対応する必要があるため、早期解決を目指すことが重要です。
証拠収集と準備すべき資料一覧
特許権侵害訴訟では、証拠の質と量が勝敗を大きく左右します。
- 開発経緯を示す資料:製品の設計図面、開発会議の議事録、技術者のメモ、プロトタイプの写真など。自社が独自開発したことを証明します。
- 販売開始時期・販売実績を示す資料:請求書、納品書、広告資料、プレスリリースなど。相手の特許出願日よりも前から同様の技術を使っていたことを示せれば、特許の有効性に疑問を投げかけられます。
- 技術的な側面に関する資料:製品の仕様書、技術文書、テスト結果。自社製品と相手方特許の技術内容を比較検討し、業界の技術動向や他社の類似製品情報も収集しておくと良いでしょう。
弁護士選びのポイントと費用相場
特許権侵害訴訟では、弁護士選びが結果を大きく左右します。
- 専門性:知的財産権分野での実務経験が豊富であることが最も重要です。過去の特許訴訟の取扱件数や、類似業界での実績を確認しましょう。
- 費用相場:着手金50万円~200万円程度、成功報酬は経済的利益の10%~20%が一般的です。訴訟の複雑さや期間で変動するため、初回相談時に詳細な見積もりを取り、中小企業の場合は分割払いや成功報酬型の料金体系を相談することも可能です。
- 相性:長期戦になることが多いため、社長として安心して相談できる関係を築けるかを見極めてください。
和解交渉のタイミングと条件設定のコツ
和解交渉は、訴訟費用と時間を大幅に節約できる有効な解決手段です。訴訟提起から3か月から6か月の間が、和解交渉の最適なタイミングと言われています。
- 譲歩範囲の明確化:ライセンス料の支払いは受け入れるが製品販売停止は避けたい、一時金ではなく分割払いなら可能など、具体的な条件を事前に検討します。
- 現実的な金額提示:相手の要求額が高額な場合は、自社の売上規模や利益率を基準とした現実的な金額を提示し、交渉の余地を作ります。
- 将来的な事業展開を考慮:金銭的解決だけでなく、技術改良への協力や共同開発の可能性なども検討し、長期的なビジネスパートナーとしての関係構築を目指すことも有効です。
よくある質問・経営者の失敗&成功体験
特許権侵害の警告書が届いた瞬間、多くの中小企業経営者は不安に駆られます。しかし、適切な対応で事業を守りながら解決できる可能性を秘めています。
対応を誤った失敗例と再発防止策
最も多い失敗は「放置」と「感情的な対応」です。
警告書を放置した結果、「故意の侵害」と判断され通常の3倍の損害賠償を命じられた製造業の事例や、感情的な反論で和解の機会を失った建設機械部品会社の事例があります。放置は悪質性の証拠とみなされやすく、感情的な対応は不利に働くことが多いです。
再発防止のための3つのポイント:
- 72時間以内の専門家相談:警告書を受け取ったら、まず弁理士や特許専門の弁護士に相談する。
- 証拠の整理と保全:開発経緯の資料、設計図面、メールのやり取りなどを時系列で整理しておく。
- 社内の情報管理徹底:従業員が軽率な発言をしないよう、情報管理を徹底する。
成功した和解・解決事例
早期対応と柔軟な姿勢が功を奏した事例:
食品加工機械メーカーは、特許侵害指摘を受け即日専門家に相談。特許の有効性を調査し、類似する部分はあったものの完全に同一ではないことを確認。誠実な対応で相手と建設的な話し合いを進め、製品の一時販売停止と設計変更を条件に、ライセンス料50万円の一括支払いで和解が成立しました。
IT関連会社の成功例:
ソフトウェアの特許侵害で訴えられたIT関連会社は、弁護士と連携して徹底的な先行技術調査を実施。相手の特許よりも前に同様の技術が公開されていた論文を発見し、これを根拠に特許無効審判を請求。特許庁で無効判決を獲得し、相手方が訴訟を取り下げました。
これらの成功事例に共通するのは、「早期の専門家相談」「冷静な現状分析」「建設的な姿勢」の3点です。弁護士や弁理士に相談する際には、これらの成功事例の参照および具体的な説明を引用することも有効です。
法務体制を見直すためのポイント
今回の件をきっかけに、今後の特許トラブルを予防する体制を整える時です。
- 第1段階(即座に実施):顧問弁護士または弁理士との関係構築。月額数万円の顧問契約を結んでおけば、緊急時にスムーズな相談が可能です。
- 第2段階(3ヶ月以内):自社の主力製品・サービスについて、基本的な特許調査を実施。潜在的なリスクを把握します。
- 第3段階(半年以内):新商品開発時の特許チェック体制を確立。設計段階で簡易的な特許検索を行うなど、予防的な仕組みを作りましょう。
法務体制は「完璧」を目指す必要はありません。中小企業の現実的な予算と人員の範囲で、「最低限のリスクヘッジ」ができれば十分です。
用語集・関連リンク
特許権侵害で訴えられてしまい、どこから手をつけていいか分からない、とお困りではありませんか?まずは基本的な用語を理解し、適切な相談先を知ることで、冷静に対処する準備を整えてください。
特許関連の基礎用語解説
- 特許権:新しい技術やアイデアを独占的に使用できる権利。通常20年間保護。
- クレーム(特許請求の範囲):特許権で保護される技術の範囲を具体的に定めたもの。
- 先使用権:他社が特許出願する前から、同じ技術を事業で使っていた場合に認められる権利。
- 無効審判:既に登録されている特許が、本来認められるべきではなかったとして無効を求める手続き。
- 差止請求:特許権侵害行為の停止を求める法的手続き。
また、国際上での法律や当該の事案に関する概要を事前に確認することも重要です。
相談できる公的機関や窓口一覧
特許権侵害の問題に直面した際、まずは公的機関や専門窓口に相談し、状況を整理し、適切な対応方針を検討しましょう。費用負担を抑えながら基本的な情報を得られるため、初期段階での活用をおすすめします。
- 特許庁相談窓口:特許制度全般、特許検索方法、基本的な権利関係。
- 発明協会:中小企業向け、地域密着型アドバイス、特許調査代行。
- 弁理士会の無料相談:特許専門家(弁理士)による直接アドバイス。
- 商工会議所・商工会:経営全般の視点からの助言、専門家の紹介。
- 中小企業基盤整備機構:知的財産専門アドバイザーによる総合的な支援。
これらの公的機関での相談を通じて基本的な情報を収集した上で、具体的な法的対応が必要な場合は、特許訴訟の経験豊富な弁護士への相談を検討することが重要です。

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。











