【特許】 出願の流れを初心者向けに完全解説!図解でわかる登録までの全手順
知的財産・知財法務
2025.11.04 ー 2025.11.06 更新
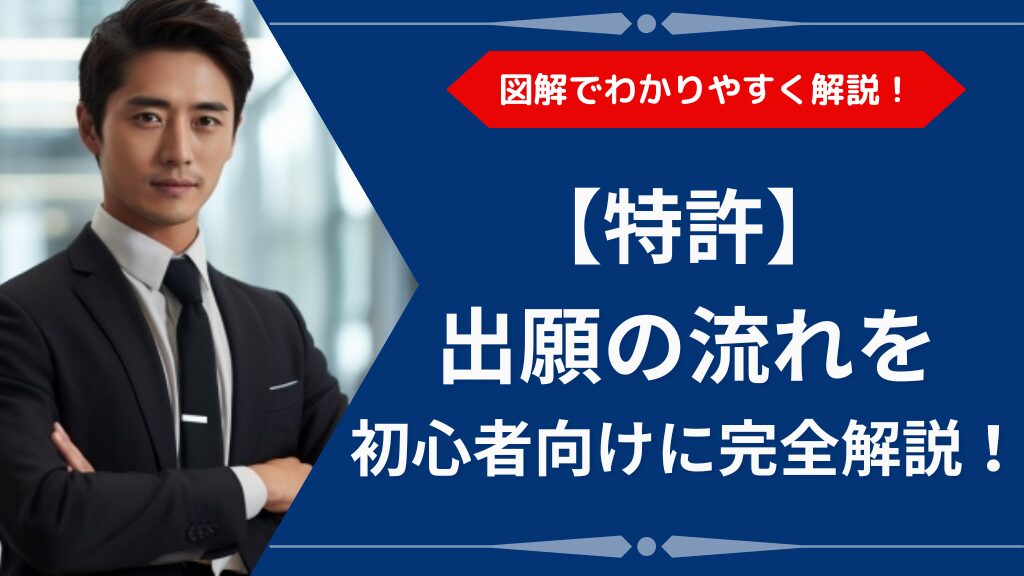
特許を取りたいけれど、「手続きが複雑そう」「どのくらい時間がかかるの?」と不安な気持ちになっていませんか?実は、特許出願は専門的な手続きに見えても、全体の流れを把握すれば思ったより難しくありません。
特許は日本国内における発明を保護するための制度です。発明が成立してから権利として認められるまでの過程では、各段階で定められた要件を一つひとつ満たすことが求められます。

特許出願の基本的な流れと全体スケジュール
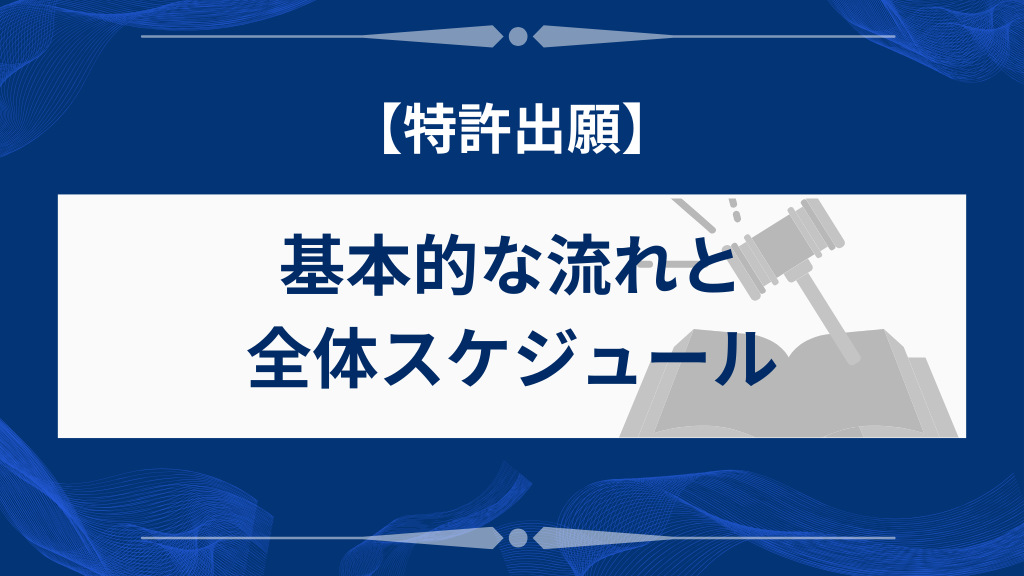
特許出願から権利取得までは、一般的に1年半から3年程度の期間がかかります。これは特許庁の審査がじっくり行われるためで、あなたの申請にミスがあるわけではないんです。この全体の流れを先に知っておくことで、慌てずに一つひとつの準備を進められます。
特許取得までの期間と主要ステップ
特許取得までの道のり、大きなステップは4つです。まずは「出願準備期間」。1〜3ヶ月程度かけて、他の人が同じアイデアを出していないかのチェック(先行技術調査)や、発明のアイデアをまとめた説明書(明細書)の作成を行います。ここでは、あなたの発明が既存の特許と重なっていないか、じっくり確認する作業が中心となりますね。
次に、「出願手続き」です。特許庁へ必要書類を提出します。この提出した日が「出願日」となり、大切な「優先権」が発生するポイント。そして、出願から約18ヶ月後には、あなたの出願内容が公開され、誰もが閲覧できるようになる、という流れです。申請書類を提出することで、この出願日に基づく優先権を確保し、手続きの経過を管理することが重要になります。
「審査請求」は出願から3年以内に行う必要があり、この手続きをしないと、出願は取り下げられたと見なされてしまいます。忘れずに手続きしてくださいね。審査請求をすると、いよいよ特許庁の審査官による本格的な審査(実体審査)がスタート。この審査期間は、最も長く10ヶ月から2年程度かかることが多いものです。
審査の結果、特許庁からの『ここ、直して!』というお知らせ(拒絶理由通知)が届くことがあります。これは約7割の出願で発生するもの。でも、これは決して「特許が取れない」という意味ではないんです。適切な対応をすれば、特許として認められる可能性は十分にあります。意見書や補正書を提出し、審査官の指摘にしっかり対応できれば、最終的に「特許査定」がもらえ、特許権が成立となるわけです。拒絶理由を解消し、特許要件を満たすことができれば審決が下されますが、その審理に不服がある場合は審判を請求することも可能です。
出願前に絶対やっておくべき準備作業
特許出願の成功は、事前の準備にかかっています。特に重要なのが先行技術調査。これは、あなたの発明とそっくりなアイデアが、既に世の中に出ていないかを確認する作業です。特許庁のデータベースや専門の検索サイトで、しっかりチェックしましょう。先行技術調査では、J-PlatPatなどのインターネット上のサイトで、特許公報や関連資料を参照し、過去の記事やページを隈なく一覧でチェックすることがよい準備となります。
次に、発明の内容を明確にすることも、とても大切。具体的に「どこが新しいのか」「今までの技術とどう違うのか」「どんな良い効果があるのか」を整理しておくのです。例えば、新しい調理器具なら「調理時間が従来品より30%短縮される」「操作が簡単で高齢者でも使いやすい」など、具体的な効果を数値や事例で示せるように準備しておきましょう。この整理は、発明が特許対象として認められる基準を満たすために重要であり、他社の製品の平均的な性能と比較して優位性を示す必要があります。
そして、発明を実際に作って実験し、その結果をしっかり記録しておくことも大切です。特許出願では、あなたの発明が本当に実現できることを示す必要がありますからね。試作品の写真、実験データ、性能測定結果など、客観的な証拠を揃えておくと安心です。
また、発明者をはっきりさせる準備も忘れてはいけません。もし複数人で共同発明をした場合は、全員が発明者として記載されるルール。後で揉めないように、誰がどの部分に貢献したのか、明確にしておくことがポイントですね。
必要書類と提出時のチェックポイント
特許出願に必要な書類は、主に次の5つです。これらの申請書類は法律で定められた要件を満たし、書式に沿って作らなければなりません。もし不備があると、修正を求められて手続きが遅れる原因となるので、しっかり確認しましょう。
| 書類名 | 内容 | 注意点 |
| 願書 | 出願人・発明者の氏名・住所、発明の名称など基本的な情報 | 住民票や登記簿謄本通りの正確な記載が必要です。 |
| 明細書 | 発明の詳細な説明(技術分野、課題、解決手段、効果など) | 第三者がその発明を実施できるくらい、具体的に説明しましょう。 |
| 特許請求の範囲 | 特許として保護を求める発明の範囲を定義する部分 | 広すぎず狭すぎず、適切な保護範囲を設定することが重要。専門知識が必要です。 |
| 要約書 | 発明の概要を簡潔にまとめたもの | 審査官が発明の全体像を把握するための書類です。 |
| 図面 | 必要に応じて。発明を視覚的に分かりやすく示す | 明細書の内容と矛盾がないか、しっかり確認しましょう。 |
提出前の最終チェックは怠らないようにしましょう。書類の形式は整っていますか?誤字脱字はありませんか?図面と明細書の内容に食い違いはありませんか?また、出願料は特許請求の範囲の項目数によって変わるので、正確に計算することが大切です。電子出願を使うなら、システムの操作方法も事前に確認しておくと、とてもスムーズです。そして、出願に必要な情報や参考資料は、特許庁サイトのサイトマップから確認したり、出願に関する記事が掲載されているページを一覧で確認したりすると安心です。
ご覧の通り、特許出願は専門的な知識が求められます。適切な権利範囲を設定したり、法的な要件をクリアしたりするには、やはり経験が必要。もし「確実に特許を取りたい!」とお考えなら、弁理士のような専門家に相談することをおすすめします。彼らのサポートがあれば、手続きのミスによる時間のロスを防ぎ、あなたの発明をより強く守る特許権の取得が期待できます。弁理士は、特許実務において専門的な支援を提供し、規定に満たした申請書類を作成する担当として意見を提供できます。
ここまでで、特許出願の全体像と準備作業についてご理解いただけたでしょうか。準備が整えば、いよいよ具体的な手続きへと進みます。難しそうに感じるかもしれませんが、ご安心ください。一つずつステップを踏んでいけば、大丈夫です。
特許出願の具体的な手続きと提出方法
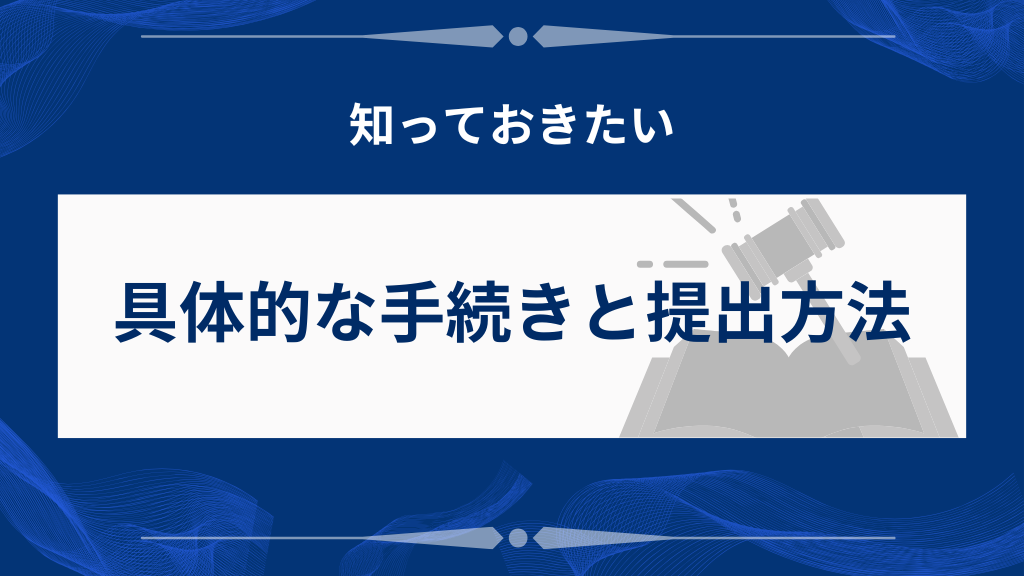
特許を取得するためには、特許庁へ正式な出願手続きを行います。一見複雑そうに見えるかもしれませんが、段階的に進めれば心配はいりません。早期に権利を取得したい場合は、特許庁の審査を早く進めるための早期審査制度の利用も視野に入れるとよいでしょう。
まずは、特許出願の全体的な流れを把握しましょう。書類準備から特許庁への提出、審査、そして特許権取得。この一連のプロセスには、通常1年から3年程度かかるものです。このプロセス全体を通して、特許庁は提供された申請書類を基に審理を行い、発明が特許法上の要件を満たすかを判断します。
出願に必要な基本書類は、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、そして必要に応じて図面、この5つです。それぞれが大切な役割を担っていますので、一つでも欠けていると正式な出願として受け付けてもらえません。特に、明細書と特許請求の範囲は、あなたの発明を正確に伝えるための、非常に重要な書類となるでしょう。
出願方法には、電子出願と昔ながらの紙出願の2種類があります。今では電子出願が主流。インターネット出願ソフトを使って手続きする方がほとんどです。電子出願のメリットは、24時間いつでも提出できること。もし書類に不備が見つかっても、比較的早く修正対応できる点も嬉しいですね。
出願書類の作成方法と記入例
特許出願書類は、決められた様式に沿って正確に書くことが大切です。特に重要なのは「発明のアイデアをまとめた説明書(明細書)」の作成。あなたの発明を、第三者が読んで理解し、実際に作れるくらい詳しく書く必要があります。この明細書が第三者に実施可能であるという基準を満たしているかどうかが、後の審査の重要なポイントとなります。
願書には、発明者や出願人の氏名・住所、発明の名称、出願日といった基本情報を記載します。例えば、個人なら「出願人 田中太郎 住所:東京都渋谷区○○1-2-3」、法人なら「出願人 株式会社△△技術研究所 代表者代表取締役 田中太郎」のように書くイメージです。
明細書では、発明がどんな技術分野で、今までの技術の何が問題で、どんな課題を解決するのか、そのための手段、そしてどんな効果があるか、さらに図面があればその説明、そして発明をどうやって実現するかの具体的な形を順序立てて記載します。特に「発明を実施するための形態」では、全く知らない人が読んでも、あなたの発明を理解し、実際に作れるくらい具体例を挙げて詳しく説明する必要があるのです。つまりこの明細書は、あなたの発明を第三者に正確に紹介し、発明の技術分野を満たした形式で詳細を提供するためのものです。
特許請求の範囲は、あなたの特許権がどこまでを保護するのか、その技術的な範囲を明確にする重要な部分です。「○○を特徴とする△△装置」のように、発明の一番大切な特徴を、簡潔かつ正確に表現しましょう。例えば、「回転軸と、その軸に取り付けられた羽根、そして羽根を回転させるモーターを備えることを特徴とする扇風機」といった具合ですね。この記載が、将来の特許権の範囲を決定するため、慎重に検討して作成してください。適切な範囲を設定するために、過去の審決や審判の参照例や専門家の意見を求めることがよい結果につながります。
電子出願と紙出願の違いとメリット
今の特許出願には、電子出願と昔ながらの紙出願、2つの方法があります。それぞれに良い点があるので、ご自身の状況に合わせて選ぶのがおすすめです。
| 項目 | 電子出願 | 紙出願 |
| 提出時間 | 24時間365日いつでも | 平日の午前9時〜午後5時(特許庁窓口) |
| 手数料 | 14,000円(基本的な出願の場合) | 15,000円(基本的な出願の場合) |
| 修正のしやすさ | 比較的迅速に修正・再提出が可能 | 郵送や窓口での再提出が必要で、手間がかかる |
| 進行状況確認 | オンラインでいつでも確認できる | 通知書などで確認、オンラインでの確認は限定的 |
| 推奨される人 | 効率を重視する方、PC操作に慣れている方 | 電子機器操作に不安がある方、紙で確認したい方 |
どちらの方法を選ぶかは、あなたの好みや状況次第です。ただし、今では約90%以上の出願が電子出願で行われている現実。最初の設定は少し手間がかかりますが、長い目で見れば、電子出願の方が効率的で経済的だと言えるでしょう。電子出願のソフトウェアは無料で提供されており、上記の表の上記の項目や以下に記載される規定を参照し、ご自身の状況に合わせて選択することが推奨されます。
出願後18ヶ月で公開される仕組みと対策
特許出願には、「出願公開制度」という大切な仕組みがあります。これは、出願から18ヶ月が経つと、その出願内容が自動的に世の中に公開される制度のこと。この制度をよく理解して、適切に対応することが重要になります。この公開は、出願後の手続きの経過を示す重要な節目です。
出願公開制度は、新しい技術情報を早く世に出すことで、産業の発展を促すのが目的です。まだ特許権が確定していなくても、18ヶ月経てば特許庁のデータベースで誰でも閲覧が可能。これによって、同じような技術開発の重複を防ぎ、既存技術を元にしたさらなるイノベーションを後押しする効果が期待できますね。公開された情報は特許公報として掲載され、誰もが参照できる公報となります。
この公開されるタイミングを知っておけば、戦略的に動けます。例えば、製品を市場に出す時期と公開タイミングを合わせることで、技術情報の開示と事業化を効果的に連動させることも可能。また、公開されるまでの期間を利用して、関連技術を追加出願したり、改良発明を検討したりするのも賢い戦略の一つでしょう。早期に権利付与を受けたい場合は、公開と同時に審査請求を行う戦略も考えられます。
注意点も頭に入れておきましょう。一度公開された技術情報は、たとえ後で出願を取り下げても、もう世界中からアクセス可能な状態です。ですから、出願前にはじっくり検討し、本当に公開しても問題ない技術なのか、事業戦略に合っているのかを慎重に判断することが大切です。慎重な検討をなさずに出願すると、後で権利を喪失したり、出願が却下されたりするリスクを受けることになるかもしれません。
もし公開を避けたいなら、出願から18ヶ月以内に出願を取り下げる選択肢もあります。しかし、一度取り下げた出願は、残念ながら復活できません。この判断は本当に慎重に行うべきでしょう。また、実用新案出願への変更や、海外出願の優先権として使うなど、他の知的財産戦略との関連も踏まえて考えることが重要です。実用新案への変更等、他の戦略を検討する場合でも、最初の出願日の優先権を満たすための条件を規定通りに行つているか確認が必須です。
特許出願はやはり専門性が高く、一人で全て完璧に進めるのは難しい場面も多いものです。特に初めての出願や、あなたにとってとても大切な技術については、弁理士のような専門家に相談するのが賢明な選択。彼らのサポートがあれば、より確実で効果的な出願手続きができ、あなたの大切な発明をしっかりと守り、事業の成功へつなげられるはずです。専門家である弁理士に担当してもらうことで、複雑な実務における不安を解消し、適切な意見や支援を受けることができます。最適な弁護士検索はこちら>>>
出願手続きが完了すれば、次は特許庁による審査の段階です。ここが、あなたの発明が特許として認められるかどうかの正念場。でも、心配しなくても大丈夫です。審査の仕組みを知り、適切に対応すれば、権利取得の可能性は大きく広がりますよ。

いよいよ審査へ!特許庁とのやり取り
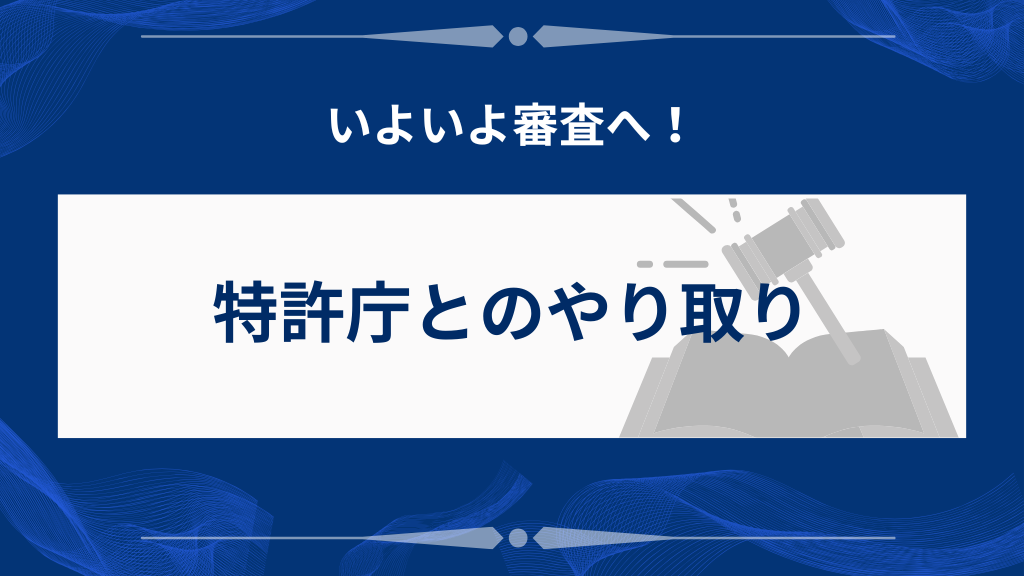
特許を出願しただけでは、特許庁による本格的な審査は始まりません。権利化までには、いくつかの大切な手続きを乗り越える必要がありますね。これらを正しく理解し、適切なタイミングで対応することが、特許権取得への近道となるでしょう。この審査開始までの経過も、全体のスケジュールの中で非常に重要なポイントです。
出願審査請求の期限と手続き方法
特許出願後、最初に行うべき大切な手続きが「出願審査請求」です。これをして初めて、特許庁による本格的な審査(実体審査)が始まる、と考えてください。
この出願審査請求には、特許出願日から3年以内という厳しい期限があります。この期限を過ぎてしまうと、せっかくの出願も取り下げられたと見なされ、特許権はもう取得できません。どんなに素晴らしい発明であっても、この手続きを忘れると、権利化の道は閉ざされてしまうのです。
手続きは、特許庁への書面提出かオンラインで行えます。出願審査請求書に必要事項を記載し、所定の手数料(基本的な料金は約14万円)を納めます。請求項が複数ある場合は、その数に応じて追加料金がかかることも、覚えておきたい点ですね。納める金額は、請求項の数や規定によって変わるため、正確に把握する必要があります。
出願人以外の第三者も審査請求はできますが、ほとんどは出願人自身が行うものです。いつ審査請求をするか、そのタイミングも戦略的に考えるべきポイント。市場の動きや競合他社の出方をよく見ながら決定することが大切になります。この審査請求を行う否かの判断は、出願を担当した専門家と協議し、最適な市場戦略を満たす時期を決定することがよいでしょう。
実体審査で何をチェックされるのか
出願審査請求をすると、特許庁の審査官による「実体審査」が始まります。ここでは、あなたの発明が特許として認められるための条件を、細かくチェックされることになりますね。
主なチェック項目は次の通りです。
- 新規性:あなたの発明と全く同じアイデアが、出願前に世の中に公開されていないか。国内外の特許文献や学術論文、製品カタログなど、あらゆる情報が調べられます。例えば、スマートフォンの新しい操作方法を発明しても、もし他社が既に同じ技術を公開していたら、残念ながら新規性は認められません。調査対象には、日本や国内外の特許公報だけでなく、意匠や商標に関する情報も含まれ、既にある権利の侵害を受ける可能性がないか参照されます。
- 進歩性:その分野の専門家が、既存の技術から簡単に思いつけるレベルの発明ではないか、という点です。単に何かを組み合わせただけ、あるいは少しデザインを変えただけでは、なかなか進歩性は認められないことが多いでしょう。進歩性の基準を満たしていないと判断されると却下され、審査官は既存技術の上位の記事やページの一覧を参照し、その技術水準と比べて進歩性が以下だと判断します。
- 産業上の利用可能性・記載要件:あなたの発明が、ちゃんと産業で使えるものか、そして内容が明確に書かれているか、第三者が実際に作れるくらい詳しく説明されているか、といった点もチェックされます。
審査官からは、通常、出願から6ヶ月〜1年程度で最初の審査結果が通知されます。
拒絶理由通知への対応と意見書提出
実体審査の結果、もし何か問題が見つかると、特許庁から**「ここ、直して!」というお知らせ(拒絶理由通知書)**が届きます。これは「特許として認められない理由」を説明する大切な文書。でも、適切に対応すれば、特許査定まで持ち込める可能性は十分にあるのです。この通知は、発明がまだ特許法上の要件を満たしていないことを意味します。
拒絶理由通知を受け取ったら、指定された期間内(通常3ヶ月、延長もできます)に必ず対応しなければなりません。主な対応方法は2つ。一つは「意見書」で審査官の指摘に反論すること。もう一つは「手続補正書」で、特許請求の範囲を修正することです。多くの場合、この2つを組み合わせて対応を進めることになります。
意見書では、審査官が指摘した拒絶理由に対し、論理的に反論します。例えば、新規性が認められなかった場合なら、引き合いに出された先行技術と自分の発明の「どこが違うのか」を明確に説明し、「なぜ別の発明なのか」を主張するのです。ここには、技術的な専門知識はもちろん、法的な知識も求められる、複雑な作業が待っています。この意見を十分に提供することで、先行技術との侵害関係を否定し、審決が覆らず不服が残る場合には審判を請求することになります。
手続補正書では、特許請求の範囲を修正して、拒絶理由を避けられるようにします。ただし、出願した時の「発明のアイデアをまとめた説明書(明細書)」に書かれていない、全く新しいことを追加することはできませんから、慎重な検討が必要。補正によって発明の範囲が狭くなるリスクも考えられるので、戦略的な判断が非常に重要となるでしょう。補正は当初明細書の規定を満たした範囲で行つてよいとされ、この重要な作業は担当の弁理士と綿密な協議のもとで進められます。
これらの手続きは、技術的にも法的にも高度な専門知識が要求されますから、一人で対応するには限界があると感じるかもしれません。でも大丈夫。特許事務所や弁理士に相談すれば、もっと効果的な対応策が見つかりますし、特許権取得の可能性も高まります。専門家のサポートがあれば、この複雑な審査手続きも、安心して乗り越えられるはずです。
長かった審査も終わり、「特許査定」の通知を受け取ったら、ゴールはもう目の前です。しかし、まだ安心はできません。特許は取得した後も、適切に維持し、活用していく必要があります。ここからは、あなたの発明を最大限に活かすための最終ステップを見ていきましょう。
特許取得後が本番!権利の維持と活用法
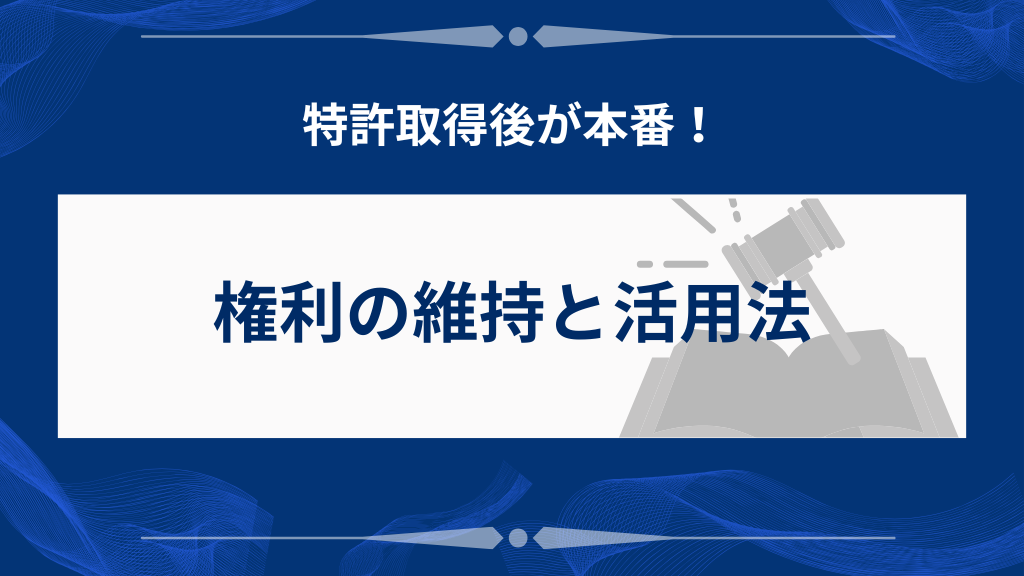
特許査定後の登録料納付手続き
特許査定通知が届いたら、まず最初に行うべきは「登録料」の納付です。この手続きを忘れてしまうと、せっかく審査を通過した特許も、権利として確定されないまま終わってしまいますので、注意が必要です。特許査定という審決を得たことで権利付与が確定しますが、納付なさを用いなかった場合は権利を喪失してしまう可能性があります。
特許査定の通知を受けたら、30日以内に第1年分から第3年分までの特許料(登録料)を一括で納めることになります。もし期限が過ぎてしまっても、6ヶ月以内なら追加料金を払えば納付は可能。でも、無駄な費用はかけたくないですよね。この登録料は、権利を付与される対価として金銭を納め、特許権という独占権をもらうためのものです。
登録料の金額は、特許請求の項目数で決まります。例えば、請求項が1〜10項目であれば、3年分で合計約21万円程度。決して安い金額ではありませんが、これはあなたの発明を強力に守る「独占権」を得るための、大切な投資と考えてくださいね。
納付方法は、特許庁への直接納付、金融機関での振込、インターネット出願ソフトを使った電子納付などがあります。もし特許事務所に依頼しているなら、その事務所経由で納めるのが最も確実で手軽でしょう。個人で手続きする際は、納付書に書かれた番号や金額を間違えないよう、くれぐれも慎重に進めるようにしてください。
登録料が無事に納付されると、通常1〜2ヶ月後に「特許証」が発行されます。この特許証を受け取って初めて、正式に「特許権者」としての地位が確定し、あなたの発明を他者から守る権利を主張できるわけです。特許証は大切な権利の証明書。失くさないように大切に保管してくださいね。
特許権取得後の年金支払いスケジュール
特許権を維持するには、登録後も毎年継続して特許料(年金)を支払い続ける必要があります。この年金制度は、特許権者が本当にその特許を活用する意思があるかを確認し、使われない特許権は自然に消滅させて、社会全体の技術発展を促すために作られた仕組みなのです。この年金は、特許権の維持という基準を満たすために、規定通りに支払う義務があります。
年金は毎年同じ金額ではありません。年数が経つにつれて、段階的に高額になっていくんです。
- 第4年分から第6年分: 年額約8万円程度
- 第7年分から第9年分: 年額約24万円程度
- 第10年分以降: 年額約81万円程度
このように料金が上がるのは、古い特許権の維持費を高くすることで、新しい技術がどんどん生まれるように促す、という国の意図があるためです。
年金の納付期限は、前年の応当日。例えば、2024年4月1日に登録された特許なら、第4年分の年金は2027年4月1日までに納めなければなりません。もし期限を過ぎても、6ヶ月以内なら追加料金で納付できます。しかし、それを過ぎてしまうと、大切な特許権が消滅してしまいますから、ご注意ください。
特許権は出願日から20年間存続しますが、全ての特許権者が20年間維持し続けるわけではありません。事業戦略が変わったり、維持コストが負担になったりして、途中で年金支払いを停止することもよくある話です。これは決して悪い選択肢ではなく、経営判断として合理的な場合もあるのです。
年金の支払い忘れを防ぐためにも、カレンダーアプリやリマインダー機能を活用して、毎年の納付期限をしっかり管理することをおすすめします。特許事務所に維持管理を任せている場合でも、最終的な支払い判断はあなた自身が行う必要がある、という点は覚えておいてください。支払いを怠ると権利が喪失し、以前の状態には戻ることはできないため、特許庁サイトのサイトマップで納付情報や規定を参照し、正確な金額を確認することが重要です。
取得した特許を収益化する方法
特許権を取得したら、次は「この権利をどうやってお金に替えるか?」を考える段階です。特許権は、ただ自分の技術を守るだけの盾ではありません。上手に活用すれば、事業を大きく成長させ、収益を増やすための強力な資産になるんです。権利の活用には、他社の不正使用に対する補償請求や、事業化のための専門的な支援を受けることが含まれます。
最も分かりやすい収益化方法は、もちろん、特許権を活かして製品やサービスを独占販売することです。競合他社は同じ技術を使えませんから、市場での優位性を保ち、利益を最大化できるでしょう。ただし、この方法がうまくいくには、特許で守られた技術が、本当に市場で必要とされていることが大前提となります。
「ライセンス契約」で収益化するのも有効な手段です。自社で製品を作ったり売ったりしなくても、他の企業に特許技術を使わせる許可を与えることで、ライセンス料やロイヤリティ(使用料)を受け取れます。初期費用として数百万円、さらに売上の3〜5%程度のロイヤリティを継続的に設定するケースが一般的。この方法なら、製造設備への投資リスクを負わずに、収益を得られるのが大きな魅力です。ライセンス契約によって、技術使用の対価として金銭をもらうことができ、この契約情報は企業のプレスリリースなどに掲載されることもあります。
特許権を売却する、という選択肢も考えられます。特に個人発明家や小さな企業の場合、大企業に特許権を売ることで、一時的に大きな収入を得ることも可能です。売却価格は特許の内容や市場価値で大きく変わりますが、数千万円から数億円という事例も珍しくありません。ただし、売却後はその技術に関する権利を完全に手放すことになるため、長期的な事業戦略をよく考えて判断することが大切です。
最近注目されているのが、特許権を活かした資金調達です。特許権を担保にして銀行融資を受けたり、投資家に対して自社の特許ポートフォリオの価値をアピールして出資を募ったりすることもできますね。特に技術系のスタートアップ企業では、特許権が会社の評価額を大きく左右する要因となることが多いものです。
どの収益化方法を選ぶにしても、専門家のアドバイスは欠かせません。特許の価値評価、ライセンス契約の条件設定、売却時の適正価格の判断など、専門的な知識が求められる場面がたくさんありますからね。弁理士や知的財産コンサルタントなど専門家に相談すれば、あなたの特許権を最大限に活用するための道筋がきっと見えてくるはずです。知的財産権には、特許のほかにも意匠権や商標権の付与があり、それぞれの規定を考慮した総合的な意見を受けることで、最大限の支援を得られます。

※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。











