訴訟にかかる弁護士費用はいくら?相場や内訳、支払い負担を軽減する方法を解説
訴訟・紛争解決
2025.04.26 ー 2025.05.08 更新
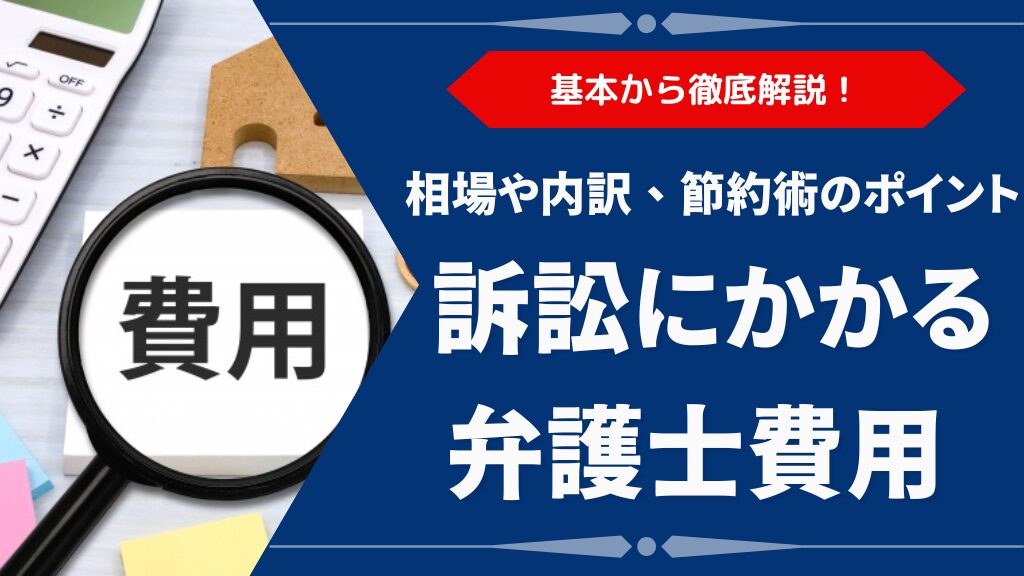
民事訴訟における費用は、個人・法人を問わず気になる方も多いでしょう。訴訟・裁判に費用は大きく分けて裁判費用と弁護士費用の2つがあり、そのうち裁判費用は手続きを行う上で発生するものであるため、費用を抑えるのが難しい場合があります。
一方で、弁護士費用は弁護士にかける金額を指すため、費用を抑えることが可能です。しかし、弁護士費用を下げると訴訟を負担することになるなど、デメリットも考慮しなければいけません。
この記事では、訴訟にかかる弁護士費用の相場や内訳から、費用を抑えるポイントやリスクについて解説していきます。企業の経営者や法務担当者、個人で離婚・労働問題・相続などのトラブルを抱えており、訴訟を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>弁護士費用と訴訟費用の違いとは?

民事訴訟において発生する費用は、大きく以下の2種類に分けられます。
- 弁護士費用
- 訴訟費用
まずは、これらの費用の違いについて見ていきましょう。
弁護士費用:弁護士に支払う費用
弁護士費用とは、依頼者が弁護士に対して支払う報酬を指します。訴訟を進めるにあたって、法律的な助言や書類作成、代理人としての出廷など、弁護士の専門的な業務に対して発生します。
弁護士費用は法律事務所によって異なり、事案の難易度や金額にも左右されます。そのため、弁護士に依頼しない場合は弁護士費用が発生しません。
弁護士費用はあくまで弁護士の活動に対して発生する費用であり、裁判所に支払う訴訟費用とは別に考える必要があります。
訴訟費用:裁判で発生する費用
訴訟費用とは、裁判所に対して支払う費用を指します。代表的なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 収入印紙代:訴状提出時に必要
- 郵便切手代:書類の送達に用いられる
- 証人の日当・交通費:証人尋問が行われる際に必要
これらの費用は原則として原告が一時的に立て替えるものですが、判決によって敗訴者が負担することもあります。つまり、裁判で勝訴した場合には、相手方に一部または全部の訴訟費用を請求できる可能性があります。
訴訟費用は手続きに不可欠であるため、削減することが困難です。あらかじめ必要となる費用の見積もりを行い、支払いが滞らないようにしないといけません。
訴訟にかかる弁護士費用の内訳

訴訟において発生する弁護士費用の内訳は、以下のようになっています。
- 着手金
- 報酬金
- 実費・日当
これらの費用は法律事務所によって異なるものの、目安となる金額があるため、それを目安に予算を立てるのがおすすめです。それぞれの費用について解説していきます。
着手金
着手金とは、手続きの開始時点で支払う費用のことを指します。訴訟の結果に関係なく発生するものであり、仮に裁判に敗訴した場合でも、返金されることはありません。
着手金の金額は弁護士や事務所によって異なりますが、請求額に応じて算定されるのが一般的です。たとえば、請求額が300万円の場合は着手金が8%前後、すなわち20万円から30万円程度となるケースが多く見られます。
また、以下のような点でも金額が変動します。
- 事案の複雑さ
- 争点の数
- 必要な準備の範囲
企業案件や高額訴訟では、着手金が50万円以上に達することも珍しくありません。示談交渉や調停など訴訟以外の対応も含まれる場合は、その分着手金が加算されることもあります。
弁護士との契約時には、着手金の金額だけでなく、どの範囲までの業務が対象となるのかを明確に確認することが重要です。費用を抑えたい場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
報酬金
報酬金とは、依頼者に有利な結果を得た際に支払う成功報酬のことを指します。これは着手金と異なり、訴訟の成果に応じて発生する費用であり、裁判の結果に基づいて支払い義務が生じます。
たとえば、金銭請求において一部でも請求が認められた場合、その金額に応じた割合で報酬金が算出されます。割合は10〜20%程度が一般的な相場とされており、300万円を獲得した場合には30万〜60万円前後の報酬金が必要となります。
ただし、契約内容や事件の難易度によって金額は変動するため、弁護士と取り決めておくことが必要です。
報酬金は成果が出なければ発生しない一方、依頼者にとっては予想外の出費となる可能性もあるため、発生条件や金額の計算方法について説明を受けた上で契約するようにしましょう。
実費・日当
訴訟にかかる弁護士費用の中には、実費や日当といった費用も含まれます。
実費とは、弁護士が業務を行う上で実際に支出する費用を指します。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 交通費
- 郵送費
- 書類のコピー代
- 裁判所に提出する資料の作成
- 証拠収集にかかる費用
- 宿泊費
一方、日当とは弁護士が出張や裁判所への同行など、通常の事務所以外で業務を行う際に発生する報酬です。地方裁判所での出廷や、依頼者との現地調査に同行した場合などが該当します。
日当は1日単位で設定されることが多く、1日あたり3万円〜5万円程度が相場です。これらの費用は依頼者の負担となり、着手金や報酬金とは別に請求されます。
【ケース別】訴訟における弁護士費用の相場

前述したように、訴訟における弁護士費用は訴訟内容によって異なります。そのため、ケース別に費用がどれくらいかかるか知っておく必要があります。
以下では、4つのケースごとに弁護士費用の相場を見ていきましょう。
- 労務問題
- 離婚・男女の問題
- 遺産・相続
- 交通事故
それぞれについて解説していきます。
労働問題
労働問題に関する訴訟では、以下のような問題が争点となります。
- 不当解雇
- 残業代請求
- ハラスメント
このようなケースで弁護士に依頼する際の費用は、事案の難易度や請求額によって異なりますが、おおよその相場としては以下の通りです。
- 着手金:20万円~40万円程度
- 報酬金:獲得額の15%~20%
たとえば、未払い残業代として100万円の請求を行い、判決で全額を得た場合、報酬金として15万円〜20万円前後が発生します。
加えて、実費や日当なども別途発生するため、総額では50万円を超えるケースも少なくありません。実費や日当が発生することも考慮すると、余裕を持って費用を用意する必要があります。
離婚・男女の問題
離婚や男女問題に関する訴訟では、感情的な対立が深まりやすく、弁護士による専門的な対応が求められます。着手金・報酬金それぞれの費用相場は、以下の通りです。
- 着手金:20万円~50万円程度
- 報酬金:獲得した経済的利益の10%~16%
争点が複雑であり、財産分与・親権・慰謝料の請求が含まれるケースでは、金額が上乗せされる傾向にあります。たとえば慰謝料として200万円を獲得した場合には、20万円〜32万円程度が報酬金となります。
また、裁判まで進展した場合は弁護士の対応時間や準備が増えるため、別途追加の費用がかかることもあります。実費や日当なども含まれると、請求額によっては100万円以上必要になるかもしれません。
遺産・相続
遺産・相続に関する訴訟では、親族間の利害が対立する場面も多く、弁護士の関与が不可欠となるケースが少なくありません。この場合の着手金と報酬金は、以下の通りです。
- 着手金:請求額の5%~8%
- 報酬金:10%前後
また、遺産分割調停や審判を経て訴訟に至る場合、手続きが長期化する傾向があるため、弁護士の日当や実費も積み重なるでしょう。特に相続人が多数いる場合や、遺言書の有効性が争点となる複雑な事案では、弁護士のサポートが必須です。
そのため、弁護士と契約する前に追加費用の有無について確認し、予算に応じた対応を検討することが重要です。
交通事故
交通事故に関する訴訟で発生する弁護士費用は、事故の内容や損害額により変動しますが、一定の基準があります。目安となる金額は、以下の通りです。
- 着手金:経済的利益の5%~8%
- 報酬金:経済的利益の10%~16%
また、交通事故の場合には任意保険に弁護士費用特約が付帯されているケースがあり、上限300万円までの弁護士費用が補償されます。この特約を活用することで、自己負担を大きく軽減できる可能性があります。
弁護士への依頼前には、弁護士特約の有無や補償内容を保険会社に確認することが必要です。費用を事前に把握したうえで弁護士に依頼することが、円滑な訴訟対応につながります。
弁護士費用の負担・請求に関するルール

訴訟における費用について、相手方に請求できると聞いたことはないでしょうか。
しかし、負担が軽減されるのは「訴訟費用」として含まれるものが原則とされており、弁護士費用についてはルールが異なります。この点を理解していないと、支払いが困難になり、訴訟後の生活にも影響を及ぼしかねません。
ここでは、弁護士費用の負担・請求について解説していきます。
原則として弁護士費用は相手方に請求できない
民事訴訟においては、原則として弁護士費用は自己負担となり、相手方に請求することはできません。これは日本の民事訴訟制度における基本的なルールであり、訴訟に勝訴した場合でも、弁護士に支払った費用の全額を相手に請求することはできないとされています。
そもそも弁護士に依頼するかどうかは依頼者の判断に委ねられるため、法律上のルールとして請求はできません。
ただし、例外として一定額の弁護士費用を損害の一部として請求できる場合があります。しかし、このような場合でも弁護士費用の全額が認められるわけではなく、損害との相当因果関係があると認められた金額に限られます。
弁護士費用の請求が認められる例外については、次で詳しく解説していきます。
弁護士費用の請求が認められる例外
弁護士費用は各当事者が自己負担するのが原則ですが、一定の例外として弁護士費用の請求が認められる場合があります。
その代表的な例が、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟です。以下の行為が裁判所で不法行為として認定された場合には、弁護士費用の一部を相手方に請求できる可能性があります。
- 交通事故
- 名誉毀損
- 業務妨害
請求が認められる範囲は損害額の1割程度が目安とされており、全額が補償されるわけではありません。
これらの例外に該当するかどうかは訴訟の性質・契約内容に依存するため、事前に弁護士へ相談し、請求の可否を確認することが必要です。
弁護士費用の支払い負担を軽減する方法

弁護士費用は訴訟費用と異なり、個人や会社の判断で負担を軽減することが可能です。具体的には、以下のような方法が挙げられます。
- 分割払い・後払いで支払う
- 早めに弁護士に相談する
- 弁護士に依頼せず訴訟を進める
それぞれの方法について解説していきます。
分割払い・後払いで支払う
弁護士費用の支払いが難しい場合、分割払いや後払いに対応している弁護士に依頼することで、経済的な負担を軽減することが可能です。
弁護士費用の支払いについては、依頼時に着手金として一括で支払うのが一般的ですが、分割払いに対応している事務所では、月々の支払いに応じて費用を分散させることができます。これにより、まとまった資金が手元にない場合でも訴訟を進めることが可能です。
また、後払いは訴訟が終了した後に弁護士費用を支払う方法で、成果報酬型の契約などが該当します。
ただし、分割払いや後払いに対応しているかどうかは事務所ごとに異なるため、必ず事前の確認が必要です。また、分割手数料が設定されることがあるため、契約前の説明をしっかり聞くようにしましょう。
早めに弁護士に相談する
弁護士費用の負担を軽減するには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
訴訟トラブルが深刻化する前に弁護士から法的アドバイスを受けることで、訴訟を回避できる可能性が高まり、結果として費用を抑えられるケースが多くあります。初期対応を誤るとトラブルが複雑化し、証拠の収集や対応に時間と費用がかかってしまうでしょう。
早期の相談によって、必要な証拠の確保や交渉の進め方を弁護士と整理できるため、効率的な解決が期待できます。また、示談交渉や書面の作成だけで解決すれば、訴訟費用全体を大幅に削減することも可能です。
問題が表面化した時点で弁護士の助言を受け、迅速で適切な対応を心掛けましょう。
弁護士に依頼せず訴訟を進める
訴訟の進め方として、弁護士に依頼せず自ら訴訟を進める「本人訴訟」という手段があります。
これは、弁護士を立てずに当事者自身が以下の手続きを行うもので、弁護士費用を大きく削減できるのが利点です。
- 訴状の作成
- 証拠の提出
- 裁判所での主張・立証
特に、請求額が少額な事件や事実関係が明確な場合には、有効な選択肢となり得ます。
しかし、本人訴訟で裁判を行うのは極めてレアなケースであり、おすすめできないというのが結論です。理由やリスクについては、次で詳しく解説します。
弁護士なしで訴訟を進めるリスク

弁護士なしで訴訟を進める本人訴訟には、費用面でのメリットがある一方で、法的なリスクも多く存在します。
最大のリスクは、法律や裁判手続きに関する専門知識が不足していることです。訴状の記載不備や証拠の提出漏れ、主張の整理が不十分な場合、訴訟の進行に支障をきたし、不利な判決につながる可能性があります。
また、相手方に弁護士が付いている場合には、法的な議論の深さや手続き対応で差が生じることもあり、敗訴するリスクが高まります。
さらに、法的判断の見通しが立てにくいため、妥当な和解条件を見極めることが難しくなります。時間や精神的な負担も想定以上に大きく、訴訟が長期化すれば生活や業務に影響を及ぼすことになるでしょう。
こうしたリスクを考慮すると、費用がかかっても弁護士に依頼するべきと言えます。費用負担の軽減を重視すると実際の裁判で不利になるリスクがあるため、弁護士に相談することを想定しておくのがおすすめです。
訴訟手続きを弁護士に依頼するメリット

訴訟手続きを弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。これらのメリットは本人訴訟では得られないもので、弁護士の専門性がもたらす利点と言えます。
- 労力や時間を軽減できる
- 適切な手続きが進められる
- 訴訟の成功確率が上がる
それぞれのメリットについて解説していきます。
労力や時間を軽減できる
訴訟手続きを弁護士に依頼するメリットの一つが、当事者の労力や時間を大幅に軽減できる点です。訴訟では、以下のような作業が発生します。
- 訴状の作成
- 証拠の収集
- 裁判期日の調整
- 出廷対応
これらを専門的な作業を全て対応するとなると、日常生活や業務に負担を及ぼす可能性があります。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きを一括して任せることができるため、依頼者の物理的な負担が軽減されます。訴訟対応の時間も削減され、通常業務に影響なく訴訟が進められます。
これにより、訴訟の早期解決や有利な結果の実現が期待できます。時間と労力の負担が心配な方であれば、弁護士に相談することをおすすめします。
適切な手続きが進められる
裁判は法的手続きに則って進行するため、高度な専門知識が求められます。弁護士はこれらの手続きを熟知しており、法律や判例を踏まえた的確な主張を構築することが可能です。
また、裁判所からの書面や期日呼出への対応も正確に行えるため、手続き上のミスを避けることができます。一方で、証拠の提出期限を守れなかったり、訴状の記載に不備があると、訴訟そのものが不利に進む恐れがあります。
さらに、複雑な法律関係や専門的な争点がある場合でも、専門的見解を交えた適切な対応が可能です。結果として、訴訟の見通しを明確にしたうえで進行できるため、自信を持って裁判に臨むことができます。
訴訟の成功確率が上がる
弁護士による訴訟手続きを経ることで、訴訟の成功確率を高められるメリットもあります。弁護士は訴訟手続きや判例の傾向、裁判官の判断基準にも精通しており、裁判所に説得力のある主張を展開できます。
たとえば、訴状や準備書面の記載においても、法的要件を満たしつつ、主張の趣旨を明確に伝えてくれます。また、訴訟戦略の調整や、相手方の主張に対する反論も、経験豊富な弁護士であれば柔軟に対応することが可能です。
こうした専門スキルは、訴訟に不慣れな個人が単独で行うよりも、有利な結果を導く可能性を高めます。弁護士の専門性を活かすことは、訴訟の成否に大きく影響する重要な要素と言えるでしょう。
まとめ

訴訟で発生する弁護士費用は、弁護士に支払う費用であり、義務として請求されることはありません。しかし、弁護士を介さず訴訟を進める場合は当事者に専門知識が求められるため、基本的には弁護士に相談することになります。
弁護士費用は、訴訟内容や法律事務所が設定する料金体系によって異なります。まずは弁護士に相談し、着手金や報酬金に加え、追加費用が発生するかどうかをしっかり確認してから検討するようにしましょう。弁護士や法律事務所を比較すると、費用面でも安心できる弁護士を見つけられます。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。訴訟にかかる弁護士費用について知りたい方は、法務救済から弁護士を探してみてください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












