弁護士との顧問契約とは?概要や役割から費用相場、メリット・デメリットを解説
企業法務
2025.04.26 ー 2025.05.08 更新
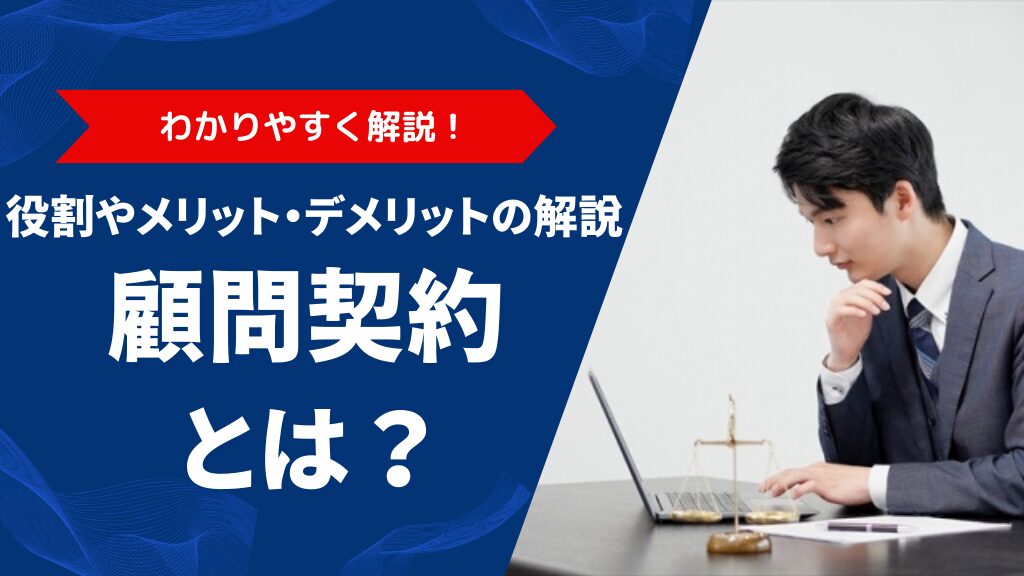
企業法務において、弁護士のサポートは必須です。しかし、費用の面で弁護士に依頼せず自社で完結させたいと考える経営者も多いでしょう。
自社での企業法務は、法務部門や担当者が成熟していない限り、法的リスクが高まります。労務管理や訴訟対応については専門的な知識が必要になるため、弁護士に依頼する方が安全性は高まります。
企業が弁護士と契約する方法の1つとして、顧問契約があります。顧問契約は弁護士からの継続的なフォローを受けられる契約で、長期的な関係を築きながら企業法務を任せることができます。
本記事では、顧問弁護士の役割や仕組み、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。「顧問弁護士をつけるべきか迷っている」「法務リスクを抑えながらコストも最適化したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>弁護士の顧問契約とは?

弁護士との顧問契約とは、企業が継続的に法的サポートを受けるために弁護士と締結する契約形態です。
単発の案件依頼とは異なり、日常的な法務相談やリーガルチェック、トラブル発生時の対応など、企業活動全体を通じた法的支援を受けられる点が特徴です。以下のような分野で予防的な対応が可能となり、リスク管理を強化できます。
- 労務
- 取引
- 知的財産
契約形態は月額制が一般的で、料金相場は契約内容や弁護士の対応業務の規模によって異なります。多くの企業ではこうした顧問契約を締結しており、弁護士の継続的なフォローを受けて経営をしています。
一般的な弁護士契約との違い
顧問契約を締結した顧問弁護士は、一般的な弁護士と異なる役割を果たします。
一般的な弁護士が個別案件ごとに依頼を受けるのに対し、顧問弁護士は企業の幅広い法的課題に対応します。継続的な関与によって、企業の業務内容や内部体制を深く理解し、的確な法的アドバイスを提供できる点が特徴です。
結果として、以下のようなメリットをもたらすことが期待できます。
- 法的リスクの予防
- 業務の効率化
- 経営判断の迅速化
通常の契約であれば、問題ごとに弁護士に相談しなければいけません。しかし、顧問契約は弁護士が常駐している状態であるため、法的フォローを継続的に受けることが可能です。
顧問契約で弁護士に依頼する場合の費用相場

顧問契約における弁護士費用の相場は、一般的に月額3万円から10万円程度とされています。ただし具体的な金額は、契約内容や企業規模、業種によって異なります。
たとえば相談件数が少なく、軽微な業務が中心となる中小企業では、月額3万円から5万円程度が標準となります。一方で、契約書の精査や労務トラブル対応といった専門性・業務量を要する場合には、月額5万円から10万円程度となるケースがあります。
さらに、大企業や複数の支店を持つ企業、頻繁に法的対応が発生する業種では、月額10万円を超える顧問契約が締結されることも珍しくありません。
また、契約の範囲に応じて、対応可能な業務内容や相談回数に上限が設けられることもあります。顧問契約外の業務については、別途費用が発生する場合があるため、契約前に料金体系を明確に確認しておくことが必要です。
顧問契約の料金体系(固定報酬型・従量課金型)
弁護士との顧問契約において採用される料金体系は、主に「固定報酬型」と「従量課金型」の2種類があります。
固定報酬型は一定額を毎月支払う形式で、事前に定めた範囲内であれば、相談回数に関係なく対応を受けられるのが特徴です。安定したコストで継続的な法的支援を受けられるため、頻繁に相談が発生する企業に向いています。
一方、従量課金型は実際に発生した業務量や相談件数に応じて報酬が決まる仕組みで、相談の発生頻度が少ない企業や、限定的なサポートを希望する場合に適しています。例えば、相談1件あたり2万円といった形で費用が発生し、無駄なコストを抑えることが可能です。
ただし、突発的なトラブル時には費用が高額になるリスクがあります。企業の法務ニーズに応じて、両者のメリットとデメリットを見極め、最適な契約形態を選ぶようにしましょう。
月額と年額ではどちらが良い?
顧問弁護士との契約において、月額契約と年額契約のどちらが適しているかは、企業の法務ニーズや業務の変動性により異なります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 月額契約:毎月の支払いで契約内容を柔軟に見直すことができる
- 年額契約:月額よりも単価が割安に設定される傾向がある
法務相談の頻度が安定していない企業や、短期間の顧問契約を試したい場合には、月額制が適しています。
一方で、長期的な関係を築く意志がある企業にとっては、年額契約が最適です。また、年間を通じて安定的なサポート体制を構築しやすく、弁護士側も企業理解を深めやすいため、対応の質が向上しやすいのも強みです。
ただし、年額契約は途中解約が難しいケースもあるため、契約前に条件の確認が不可欠です。法務業務の頻度や今後の見通しを踏まえ、契約期間とコストのバランスを慎重に検討しましょう。
顧問弁護士と契約するメリット

顧問弁護士と契約することで、主に以下の5つのメリットが期待できます。
- 専門スキルや知識が取り入れられる
- 企業の実情を深く理解してくれる
- 緊急時にスムーズな対応を受けられる
- 社内の法務体制強化にも貢献する
- 予算の見通しが立てやすい
それぞれのメリットについて解説していきます。
1.専門スキルや知識が取り入れられる
顧問弁護士と契約するメリットの一つに、企業外の高度な専門スキルや法律知識を取り入れられる点があります。
企業内部で法務部門を持たない、または人員や経験が不足している場合でも、顧問弁護士を通じて専門スキルや知識を得ることが可能です。
特に労務管理や取引トラブル、知的財産といった多岐にわたる法務分野において、専門性を有する弁護士からのアドバイスは非常に有効です。顧問弁護士は企業の事業内容や組織構造を理解したうえで対応するため、表面的な助言にとどまらず、企業の実情に即した実践的なサポートが受けられます。
このように、専門家の知見を継続的に活用できる体制を整えることで、経営判断の精度が高まり、法務面の安定性が向上します。
2.企業の実情を深く理解してくれる
顧問弁護士との継続的な契約は、企業の実情を深く理解するのに役立ちます。単発で依頼する弁護士とは異なり、顧問弁護士は企業における以下のような部分を把握してくれます。
- 業種特有のリスク
- 社内の組織体制
- 経営方針
- 人事制度
この理解があるからこそ、一般論ではなく、企業ごとの実態に即したアドバイスや対応が可能となります。たとえば労務問題においても、過去の経緯や現場の実情を把握している弁護士であれば、現実的かつリスクを抑えた解決策を提案できます。
長期的な関係性の中で信頼が構築されることにより、経営者が安心して相談できる体制が整い、企業活動全体の法的安定性にもつながります。
3.緊急時にスムーズな対応を受けられる
顧問弁護士が企業に継続して携わることで、緊急でトラブルが発生した場合でも素早く対応してくれます。
企業経営においては、労務トラブルや取引先との紛争、行政対応など、予期せぬ法的問題が突発的に発生することがあります。こうした場面で顧問弁護士がいれば、状況を説明する手間が省け、初動対応をスムーズに進めることが可能です。
特に初期対応の遅れが、損害拡大や信用低下につながるリスクがあるため、顧問弁護士の存在は企業にとって大きな価値を持ちます。顧問契約を締結しておくことで、万が一のトラブルにも落ち着いて対処できる体制を整えることができます。
4.社内の法務体制構築にも貢献する
顧問弁護士との契約は、企業の社内法務体制の構築・強化に大きく貢献します。専門的な知見を持つ弁護士が関与することで、日常業務の中に法的視点が浸透し、社内のリスク管理意識が向上します。
以下のような業務であれば、顧問弁護士のサポートを受けながら仕組みを構築・強化することが可能です。
- 契約書のチェック体制
- 労務管理の見直し
- 社内規程の整備
また、法務担当者が在籍している場合には、その育成にも貢献します。実務を通じて弁護士から直接指導を受けることができるため、法的知識や対応力が向上し、将来的には一定の業務を社内で完結できるようになります。
顧問弁護士からの継続的な支援は、法務を外部に依存するのではなく、社内で機能する法務基盤の確立を促進する点で大きなメリットといえます。
5.予算の見通しが立てやすい
顧問弁護士との契約による継続性は、法務コストの予算管理がしやすくなるメリットもあります。顧問契約を締結すれば、月額3万円から10万円程度の一定額で継続的なサポートが受けられるため、年間を通じた法務費用の見通しが立てやすくなります。
特に、契約内容によっては月内の相談回数が無制限となる場合もあり、頻繁に法務相談が必要な企業にとっては、コストパフォーマンスの高い選択肢となります。また、予算に応じて契約内容を調整することも可能で、経営戦略と法務対応のバランスをとりながら効率的にリスク管理ができます。
継続的な支出で法務体制を安定させる点が、顧問契約の利点といえるでしょう。相談件数が多い場合は、顧問弁護士と契約するのがおすすめです。
顧問弁護士と契約するデメリット
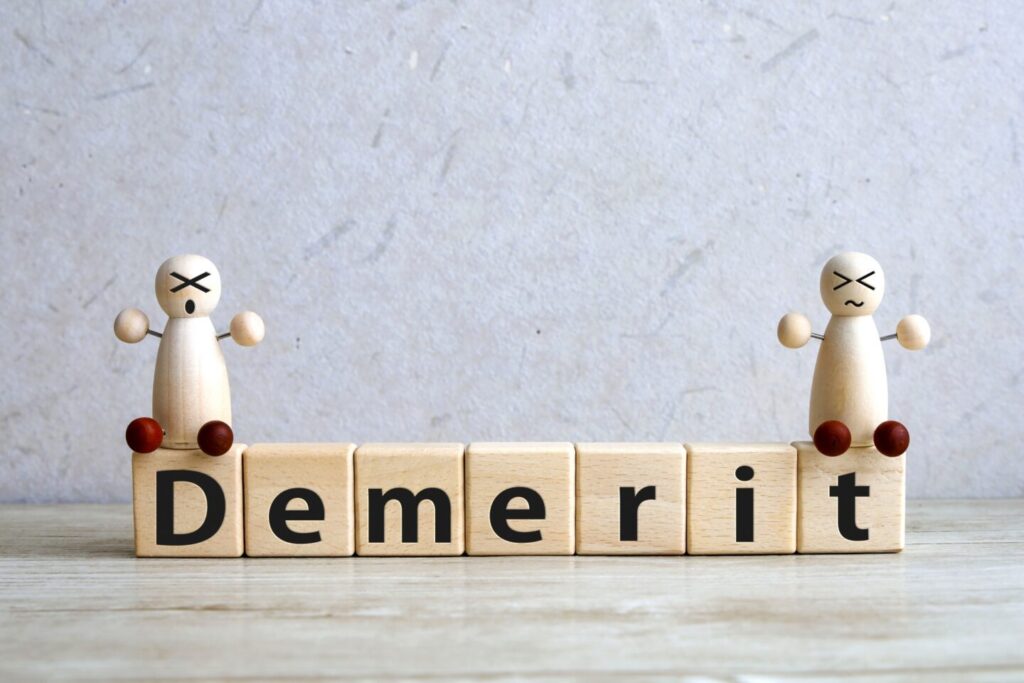
顧問契約は専門的な法的サービスを継続的に受けるというメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。これらのデメリットを考慮した上で、顧問契約を締結するかどうかを判断する必要があります。
- 契約解除が難しい
- 継続的なコストがかかる
- ミスマッチを引き起こす可能性がある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
契約解除が難しい
顧問弁護士との契約では、契約解除が難しいというデメリットがあります。特に年額契約や中長期の契約の場合、途中解約に制限が設けられているケースが多く、一定期間の継続を前提とした契約内容になっていることが基本です。
そのため、契約後に弁護士の対応に不満を感じたり、業務量が想定より少なかった場合でも、すぐに解約できないことがあります。解約には手続きや通知期間が必要となるほか、違約金や未払い報酬の請求が発生する場合もあります。
こうした時間と手間は、企業にとって負担となるでしょう。
継続的なコストがかかる
顧問弁護士との契約による継続的なコストは、場合によってはデメリットとなることもあります。法務相談を行わなかった月でも、契約が継続する限り費用は発生するため、法務対応の必要性が一時的または限定的な企業にとっては、支出に見合った効果を得にくいでしょう。
特に、創業間もない企業や小規模な事業者の場合、限られた経営資源の中で毎月一定額の費用を計上することは、財務的な負担となり得ます。
また、自社での法務が充実している場合も、顧問契約は効果が発揮しにくいと言えます。この場合一部の専門性が問われる案件のみを弁護士に相談することになるため、単発の方が安く済むはずです。
普段の企業法務や弁護士への相談回数を検討し、顧問契約が最適かどうかを判断しましょう。
ミスマッチを引き起こす可能性がある
顧問弁護士と契約する際に、企業と弁護士との間でミスマッチが生じる可能性があります。万が一ミスマッチが起こると、企業にとって弁護士は効果的なサービスとは言えません。
顧問契約は継続的な関係性を前提としているため、弁護士の専門分野や対応スタイルが企業のニーズと合致していない場合、十分なサポートが受けられず、かえって業務効率や法務対応の質を損なう恐れがあります。
このようなミスマッチは、毎月の固定費を支払っているにもかかわらず、実質的なメリットが得られない状況を招きかねません。
そのため、契約前には弁護士の専門領域や対応姿勢をしっかりと確認し、初回面談などを通じて相性を見極めることが重要です。
弁護士と顧問契約を締結する際のポイント
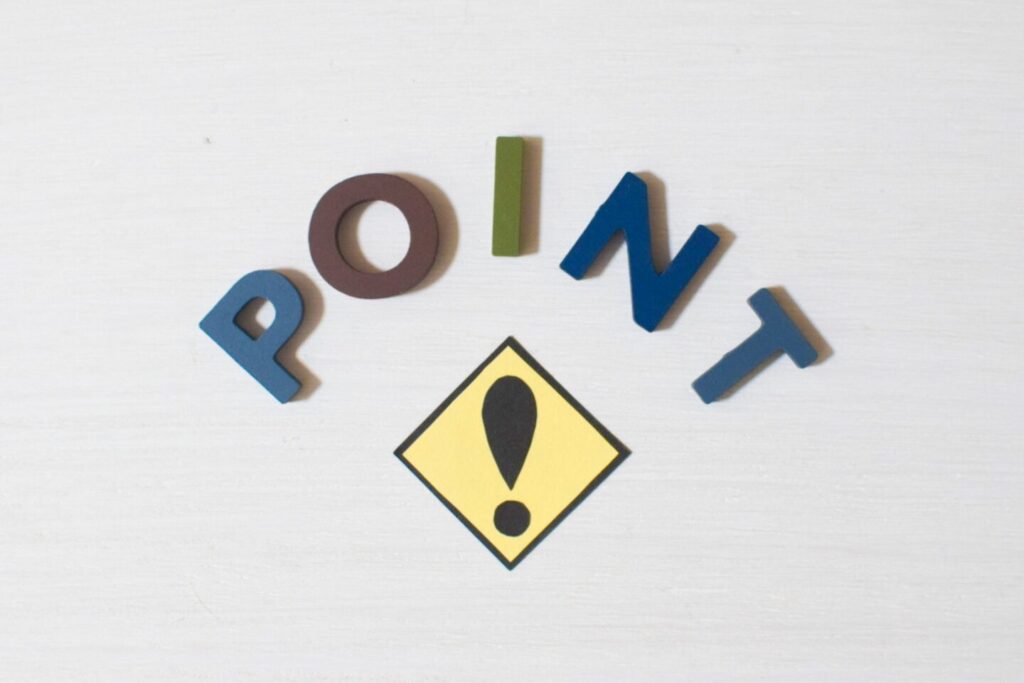
顧問契約において注意しなければいけないのが、弁護士とのミスマッチです。ミスマッチが一度起こると契約解除が難しいため、十分なサポートを受けられない期間が数か月~数年続くことになります。
そのため、以下のポイントを押さえて弁護士を選びましょう。
- 業種や業界に適した弁護士を選ぶ
- 顧問契約内容を精査する
- 複数の弁護士を比較検討する
それぞれのポイントについて解説していきます。
業種や業界に適した弁護士を選ぶ
弁護士と顧問契約を締結する際には、業種や業界に精通した弁護士を選ぶことが極めて重要です。業界特有のリスクや慣習を理解している弁護士を選定することで、より的確かつ迅速な法的アドバイスを受けることが可能となります。
業界知識のある弁護士は、企業のビジネスモデルや取引構造を理解しやすく、初期の説明負担を軽減できる点でもメリットと言えます。また、関連する判例や行政の動向に精通していれば、リスクの予防策や実務に即した対応を提案してもらえるでしょう。
業種や業界に適しているかどうかは、過去の実績が参考になります。取り扱ってきた案件が自社と同じ業種・業界であれば、特有の慣習や動向を把握できていると言えるでしょう。
顧問契約内容を精査する
弁護士と顧問契約を締結する前には、契約内容を細部まで精査する必要があります。顧問契約に含まれる以下の項目については、事前に明確に取り決めておくべきです。
- 業務範囲
- 対応可能な相談内容
- 回数
- 緊急時の対応可否
- 契約期間
- 更新条件
- 途中解約の可否
たとえば、「月○回までの法律相談が可能」「契約書のレビューは○件まで」などの条件が設けられていることが一般的です。これらの条件を把握していないと、想定外の追加費用が発生したり、必要なサポートが受けられなかったりするリスクがあります。
弁護士と企業の間での解釈の違いは、トラブルが生じる原因でもあるため、文章として明文化されているかを確認すべきです。こうした入念なチェックは、ミスマッチを防ぐうえでも重要です。
複数の弁護士を比較検討する
顧問契約を結ぶ弁護士を選ぶ際は、複数の弁護士を比較・検討することが必要です。費用だけでなく、専門分野や対応力、コミュニケーションの質などを多角的に確認するようにしましょう。
具体的には、以下のような項目がチェックポイントとなります。
- 同じ業種の企業への支援実績があるかどうか
- 過去の対応事例
- トラブル時の初動対応の速さ
これらの項目を比較することで、自社に適した弁護士を見極めることが可能です。また、弁護士の考え方や話しやすさ、説明の明瞭さなども判断材料となります。
複数人を検討せずに即決してしまうと、後になって専門性の不足や対応の不満が生じるリスクがあります。つまり、ミスマッチの可能性が高くなるのです。
比較検討においては時間をかけて慎重にチェックし、自社の法務ニーズに合致する弁護士を選定することが不可欠です。
まとめ

弁護士と顧問契約を締結することで、企業への理解度が高まり、さまざまなメリットをもたらします。これにより法務が安定し、企業経営に専念できるようになります。
しかし、弁護士とのミスマッチが起こると、法的フォローの効果が弱まります。こうしたデメリットも想定されるため、顧問弁護士は慎重に、比較検討を徹底して選定してください。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。顧問契約を締結する弁護士を探している方は、法務救済をご利用ください。
無料で相談できる専門家検索はこちらから>>法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。












