- 法務救済
- コラム
- 予防法務
- 契約書・リーガルチェック
- 秘密保持契約書の作成は弁護士に依頼するべき?相談するメリットや流れ、テンプレートの活用方法を徹底解説!
秘密保持契約書の作成は弁護士に依頼するべき?相談するメリットや流れ、テンプレートの活用方法を徹底解説!
契約書・リーガルチェック
2025.04.23 ー 2025.06.17 更新
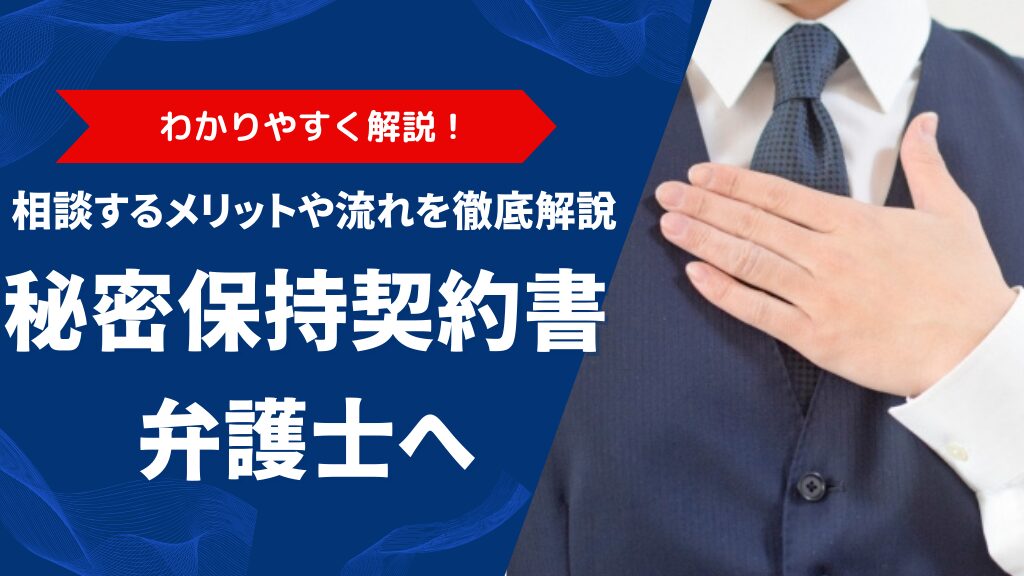
ビジネスで機密情報を扱う際、秘密保持契約書の適切な作成は重要なステップです。企業同士の取引やプロジェクトにおいて情報漏洩リスクを避け、信頼関係を保つために必要になります。
適切な秘密保持契約を結ぶには、具体的な条項の設計や法的なポイントには慎重な対応が求められます。しかし、専門知識の不足や法的リスクへの不安から、契約書の作成に迷いを感じる経営者や法務担当者も少なくありません。
そこで本記事では、秘密保持契約書の作成を弁護士に相談・依頼する場合の費用や流れ、ポイントについて詳しく解説します。適切な契約書作成を通じて、企業の情報保護を強化し、安心してビジネスに取り組める環境を整えましょう。
秘密保持契約書(NDA)とは?

秘密保持契約書(NDA)は、企業や個人間で機密情報を保護するために締結される法的文書です。ビジネスの現場で頻繁に使用されるこの契約書には、情報漏洩のリスクを軽減し、知的財産や企業秘密を守る役割を果たします。主に取引先との商談や新製品開発、M&A交渉など、様々なシーンで活用されています。会社の重要な情報を取り扱うため、契約内容の正確性がビジネス全体に大きな影響を与えることもあります。
弁護士の視点から見ると、秘密保持契約書の作成や確認は重要なプロセスです。適切に作成された秘密保持契約書は、両者の権利と義務を明確にし、将来的なトラブルを未然に防ぐ効果があります。一方で、不適切な内容や曖昧な表現が含まれていると、後々の紛争につながる可能性があります。
そのため、秘密保持契約書の作成や確認を弁護士に依頼することで、法的リスクを最小限に抑え、自社の利益を最大限に保護することができます。弁護士は、各企業の状況に応じたカスタマイズや、最新の法律動向を反映した内容の提案など、専門的なサポートを提供します。
秘密保持契約書に記載すべき項目

秘密保持契約書に記載すべき必須項目には、主に以下のようなものがあります。
- 秘密情報の定義と範囲
- 秘密情報の管理方法
- 秘密保持義務の内容と適用範囲
- 秘密保持義務の例外規定
- 秘密保持義務の期間
- 秘密保持義務違反時の制裁措置
それぞれの項目について解説していきます。
秘密情報の定義と範囲
秘密保持契約書における秘密情報の定義と範囲は、契約の核心となる要素です。
ここでは、どの情報が秘密として保護されるべきかを明確にし、契約の範囲を適切に設定することで、トラブルを未然に防ぎます。秘密情報として扱うものには、以下のようなものがあります。
- 技術情報
- 営業戦略
- 顧客情報
- 財務データ
これらの項目を記載する際は、「当事者が秘密として明示した情報」や「ビジネス上で知り得た全ての非公開情報」といった形で記載することが推奨されます。また、公開情報や法的に開示が求められる情報については、秘密情報から除外する旨を明記することで、双方の理解を一致させることが可能です。
このような明確な定義により、当事者間での誤解を防ぎ、契約の履行が円滑に進むよう配慮します。
秘密情報の管理方法
秘密情報の管理方法は、機密性を確保するための具体的な手段を定める役割を果たす項目です。これにより、情報の漏洩を防ぎ、双方が適切に情報を取り扱う責任を共有することが可能になります。
管理方法としては、情報の保存やアクセス制限、社内の共有範囲の制限が含まれ、契約当事者が同意のもとでどの程度の管理を行うかを明確にする必要があります。例えば、紙媒体での情報管理では施錠された保管庫の利用を定め、電子情報についてはパスワード保護や暗号化の義務付けが一般的です。
また、情報へのアクセス権を特定の役職者やプロジェクトメンバーに限定し、社外への情報流出を防ぐための対策についても明記します。これらの管理方法を契約に明示することで、情報の適切な管理体制を築き、情報漏洩リスクの低減を図ることが可能になります。
秘密保持義務の内容と適用範囲
秘密保持義務の内容と適用範囲は、契約当事者が相手方から開示された秘密情報を保護し、第三者に漏洩しないことを約束するものとして必要な項目です。具体的には、情報の使用目的を限定し、アクセス権限を持つ者を制限することが含まれます。
秘密保持義務の内容は、秘密情報の定義に基づいて決定されます。通常、技術情報、営業情報、顧客データなどが対象となりますが、契約目的に応じて柔軟に設定します。また、口頭で開示された情報や、視察や実演を通じて取得した情報も含まれます。こうした情報がどのような場面で取得されたかも、契約書に明記することで保護の実効性が高まります。
ここで重要になるのは、秘密保持義務の内容を明確かつ具体的に規定することです。例えば、情報の複製や保管方法、従業員への周知義務、契約終了時の情報の返却や破棄などを詳細に定めることが望ましいでしょう。さらに、秘密情報の漏洩や不正使用を防ぐための合理的な措置を講じる義務を課すことも推奨されます。情報の管理体制が不十分であれば問題が発生しやすく、後のトラブルにつながるリスクもあります。
適用範囲については、時間的・地理的制限を設けます。例えば、契約終了後一定期間は秘密保持義務が継続するといった条項や、特定の国や地域でのみ適用されるといった制限を設けることがあります。これらの制限は、ビジネスの性質や情報の重要性に応じて適切に設定するようにしましょう。
秘密保持義務の例外規定
秘密保持義務の例外規定は、契約当事者が秘密情報を開示できる特定の状況を定める規定です。一般的な例外として、公知の情報や独自に開発した情報、第三者から合法的に入手した情報などが挙げられます。また、法令や裁判所の命令に基づく開示も例外として認められることが多いです。
例外規定を設ける際は、その範囲を明確に定義し、開示の条件や手続きを具体的に記載することが重要です。とくに書面での同意を要件とすることで、当事者間の誤解や紛争を防ぎやすくなります。例えば、法的要求による開示の場合、相手方に事前通知を行い、開示範囲を最小限に抑える努力義務を課すなどの条件を付けることがあります。
さらに、秘密情報の受領者が既に保有していた情報や、第三者から制限なく開示された情報も例外として扱われることがあります。これらの例外規定は、ビジネスの実態に即した柔軟性を確保しつつ、重要な秘密情報を適切に保護するバランスを取るために設けられます。
適切な例外規定を設けることで、不必要な紛争を回避し、契約の実効性を高めることができます。ただし、例外規定が広すぎると秘密保持の目的が損なわれる恐れがあるため、弁護士のアドバイスを受けながら慎重に検討することが望ましいでしょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。秘密保持契約書の作成を弁護士に依頼する場合は、法務救済から弁護士を探してみてください。
問い合わせURL:https://houmu931.jp/expert/
秘密保持義務の期間
秘密保持契約書における秘密保持義務の期間は、契約相手が守るべき情報の機密性を保つ期間を明示する項目です。
通常、契約期間中だけでなく、契約終了後も一定期間の秘密保持義務が課されることが多く、これにより情報が長期的に保護される仕組みが確保されます。この期間は契約内容や業種により異なりますが、一般的には契約終了後2年から5年とする例が多いです。
機密情報の価値は時間とともに低下するケースもあるため、必要以上に長期に設定することが適切でない場合もあります。加えて、秘密保持義務の期間については、法律的に妥当であるかの確認も重要で、必要に応じて弁護士の助言を受けることで、過度な義務やリスクを避けることができます。
秘密保持義務違反時の制裁措置
秘密保持義務違反時の制裁措置は、契約の実効性を担保する重要な項目です。制裁措置を決定する際には、違反行為の程度や影響、業界の慣行、法的な制限などを考慮する必要があります。一般的な制裁措置としては、損害賠償請求権の設定が挙げられます。
また、差止請求権を明記することも効果的です。これにより、秘密情報の不正使用や開示の継続を防ぐことができます。さらに、契約解除権を規定することで、重大な違反があった場合に契約関係を終了させる選択肢を確保することが可能です。
ただし、過度に厳しい制裁措置は裁判所で無効とされる可能性があるため、合理的な範囲内で設定するようにしましょう。また、違反の程度に応じて段階的な措置を設けることで、柔軟な対応が可能になります。
秘密保持契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
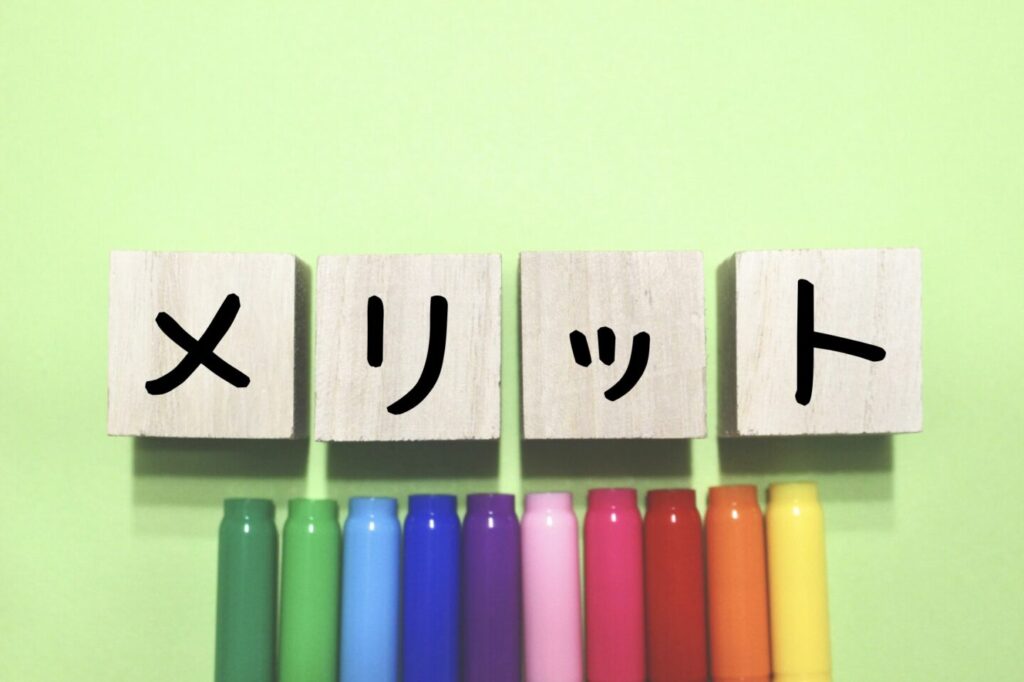
企業機密に関わる契約書であることから、弁護士への依頼を検討するケースも多いでしょう。弁護士に作成を依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 法的に安全な契約書を作成できる
- 契約書作成にかかる時間や手間を省ける
- 作成からリーガルチェックまでを一貫して行える
それぞれのメリットについて解説していきます。
法的に安全な契約書を作成できる
秘密保持契約書の作成を弁護士に依頼することで、法的に安全な契約書を手にすることができます。
秘密保持契約書は企業の機密情報を守るための重要なツールであり、条項の不備や曖昧な表現があると、トラブル時に情報保護が十分に機能しないリスクがあります。弁護士に依頼することで、適用法の確認や最新の法改正を踏まえた内容に基づき、確実に有効性を持つ契約書を作成することが可能です。
また、情報漏洩のリスクや業界ごとの特殊性に応じた条項の追加も行えるため、自社のビジネスに適した実効性のある契約内容が確保されます。法的な視点を取り入れることで、万が一の際にも企業を守る強力な防御策として機能する契約書を作成することが可能です。
契約書作成にかかる時間や手間を省ける
秘密保持契約書の作成を弁護士に任せると、契約書の作成にかかる時間や手間を大幅に軽減できます。
法務の専門知識がないまま契約書を作成すると、適切な条項の選定やリスクの見極めに多くの時間を費やすだけでなく、見落としによる法的リスクを伴う可能性もあります。一方、弁護士に依頼すれば、企業の状況や契約の目的に応じた内容を迅速かつ的確に作成してもらえるため、効率的に作業を進められます。
また、弁護士のサポートにより事前に法的リスクを回避した堅実な契約書を作成できるため、企業としても安心して契約の締結に臨めるでしょう。
作成からリーガルチェックまでを一貫して行える
秘密保持契約書の作成を弁護士に依頼するメリットの一つは、契約書の作成からリーガルチェックまでを一貫して行える点です。
弁護士に依頼することで、契約書の構成や条項の適切性について専門的な視点から作成が進められ、法律的な観点からリスクがないかの確認が徹底されます。企業の取引内容や業界特有のリスクに応じたカスタマイズが可能となるため、一般的なテンプレートでは対応しきれない、詳細な契約書を作成できます。
また、初期段階から法的専門知識が加わることで、後からリーガルチェックを追加する必要がなくなり、効率的かつ正確にプロセスを進められる点も大きな利点です。顧問弁護士がいれば、継続的な法的アドバイスを得ながら契約書を運用することもできます。こうした一貫した対応により、契約書に対する信頼性が向上し、安心してビジネスの取引を進められる環境が整えられます。
秘密保持契約書のリーガルチェックを依頼する流れ

秘密保持契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼する場合は、以下のような流れで進めるのが一般的です。
- 弁護士や法律事務所に問い合わせる
- 秘密保持契約書の概要や目的について打ち合わせを行う
- リーガルチェックの費用やスケジュールを調整する
- リーガルチェック後の契約書を修正する
それぞれの手順について解説します。
弁護士や法律事務所に問い合わせる
秘密保持契約書のリーガルチェックを依頼する際、弁護士や法律事務所に問い合わせることが最初のステップとなります。
依頼を検討する段階では、自社の業界や契約の目的に精通した弁護士を選ぶことが重要です。問い合わせ時には、契約の概要や具体的に確認してほしいポイントを整理し、簡潔に説明するとスムーズに進みます。
法律事務所や弁護士との初回の相談を通じて、信頼関係を築き、スムーズな依頼プロセスが可能になります。この初期対応を丁寧に行うことで、法的リスクの管理がより確実なものとなり、安心して契約書の準備を進められます。
秘密保持契約書の概要や目的について打ち合わせを行う
依頼先となる弁護士や法律事務所が決まったら、秘密保持契約書の概要や目的について打ち合わせを行います。
この打ち合わせでは、契約の対象となる情報の種類、具体的な取引内容、業界特有のリスク要因、契約の目的など、依頼側のビジネス上のニーズや背景を弁護士と共有します。これにより、弁護士はクライアントの事業特性や取引における懸念点を正確に把握し、リーガルチェックを行うことが可能となります。
さらに、契約書に求める具体的な内容や、強化したい保護項目がある場合もこの段階で相談しておくことで、リーガルチェックの効率が上がり、契約書の完成度を高めることができます。これによりリーガルチェックの手戻りを防ぎ、ビジネスに適合した確実な契約書を作成できる確率を高めることが可能です。
リーガルチェックの費用やスケジュールを調整する
秘密保持契約書のリーガルチェックを依頼する弁護士が決まれば、費用やスケジュールを調整する段階に入ります。
秘密保持契約書のリーガルチェックは、5万円から10万円程度が相場です。より複雑な内容や修正が必要な場合は、15万円から30万円ほどになることもあります。契約前に費用を把握することで、予算内で適切に進行させることができます。
スケジュールについては、通常1週間から2週間程度で完了することが多いですが、緊急性が高い場合は数日で対応できることもあります。ただし、複雑な案件や大規模な修正が必要な場合は、1ヶ月以上かかることもあります。
注意点として、リーガルチェックには契約書の条項確認やリスクの特定、業界に応じたカスタマイズの提案が含まれるため、作業の規模や複雑さにより費用や期間が変動します。そのため、予算やスケジュールに余裕を持って依頼することが重要です。
リーガルチェック後の契約書を修正する
秘密保持契約書のリーガルチェックが完了した後は、指摘事項や改善提案を基に契約書を修正する最終プロセスに進みます。この段階では、弁護士が示した法的リスクや条項の不備を踏まえて、実務に適した形へと調整を行います。
例えば、情報漏洩リスクを軽減するための表現や、企業にとって重要な情報を明確に保護するための文言を反映させるのが一般的です。リーガルチェック後に修正を反映させることで、法的な堅牢性と実効性を兼ね備えた契約書に仕上げることが可能となり、リスクの低減とビジネス保護を確実にします。
秘密保持契約書の作成・チェックを依頼する際の注意点
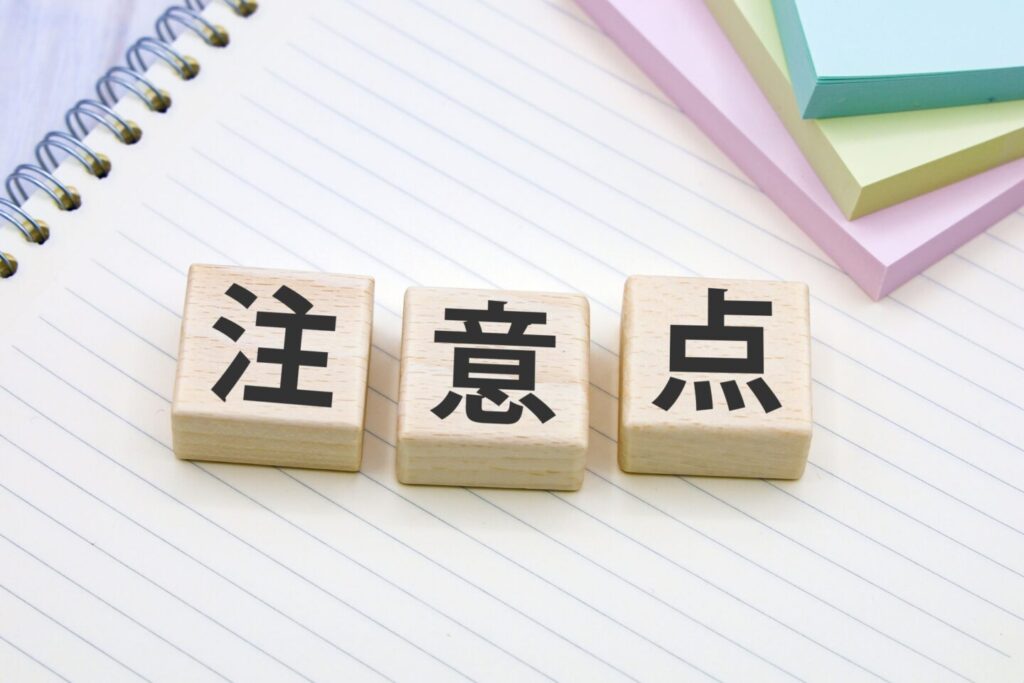
秘密保持契約書の作成やリーガルチェックにおいては、特有の注意点があります。特に気を付けてほしいのが、以下の点です。契約全体の中で、一部の条項が不適切だった場合でも、全体の有効性に影響を与える問題に発展する恐れがあるため、細部までの確認が求められます。
- 秘密情報の範囲を適切に設定する
- 契約の有効期間を明記する
- 条項ごとの法的リスクを検討する
- 取引先となる相手の意見も考慮する必要がある
- 雛形テンプレートはカスタマイズが前提であることを理解しておく
それぞれの注意点について見ていきましょう。
秘密情報の範囲を適切に設定する
秘密情報の範囲を適切に設定することは、秘密保持契約書の有効性を高める上で重要です。秘密情報の定義の明確化については具体的な例を挙げることが大切で、以下のような項目を明記して保護対象を明確にします。
- 技術情報
- 顧客データ
- 財務情報
- 事業計画
また、秘密情報の形態についても言及しましょう。文書や電子データ、口頭での情報といったさまざまな形態があることを考慮し、それぞれを保護対象として明記します。
さらに、秘密情報であることを示す方法も定めるべきです。例えば、文書には「秘」や「Confidential」などの表示を付けることを義務付けるなどの工夫が有効です。
一方で、秘密情報の範囲を広げすぎると、契約の実効性が低下する可能性があります。そのため、公知の情報や受領者が独自に開発した情報などは除外するなど、適切な例外規定を設けることも必要です。
契約の有効期間を明記する
契約の有効期間を決める際には、秘密情報の性質や取引の特性を十分に考慮する必要があります。一般的に、秘密保持契約書の有効期間は3年から5年程度に設定されることが多いですが、業界や情報の重要性によって大きく異なる場合もあります。
技術革新の速い業界では、比較的短期間の契約が適している一方で、製品開発に長期間を要する業界では、より長い期間が必要となるでしょう。また、永久的な秘密保持を求める場合もありますが、これは裁判所で合理的な期間に制限される可能性があるため注意が必要です。
他にも、契約期間終了後の取り扱いも検討しなければいけません。秘密情報の返却や破棄、継続的な秘密保持義務などについて明確に定めておくことで、情報漏洩リスクを軽減できます。
有効期間を決める際は、ビジネスニーズと法的リスクのバランスを取ることが重要です。弁護士に相談することで、適切な期間設定と関連条項の調整が可能となり、より実効性の高い契約書を作成できるでしょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。秘密保持契約書の項目をチェックしてくれる弁護士を探したい場合は、法務救済を利用してみてください。
問い合わせURL:https://houmu931.jp/expert/
条項ごとの法的リスクを検討する
秘密保持契約書を作成・チェックする際には、条項ごとの法的リスクを検討することが欠かせません。契約書の中で特に注意が必要な条項には、以下のようなものがあります。
- 秘密情報の定義
- 秘密保持義務の範囲と期間
- 例外事項
- 違反時の対応措置
これらの条項が不明確であったり、一方に偏り過ぎた内容であったりすると、後々トラブルの原因となる可能性があります。例えば秘密情報の範囲が曖昧であると、何が守るべき情報なのか解釈が分かれ、紛争に発展するリスクがあります。
また、違反時のペナルティが過度に重い場合、契約相手が契約自体を避ける要因となることも考えられます。
こうした法的リスクを未然に防ぐためには、条項ごとにその妥当性や実効性を専門家の目で慎重に検討する必要があります。弁護士に依頼すれば、法的観点からリスクを洗い出し、企業の実務やビジネスの状況に応じた最適な内容へと調整することが可能です。
取引先となる相手の意見も考慮する必要がある
秘密保持契約書を作成する際には、自社の利益やリスクだけでなく、取引先の意見を適切に考慮することが重要です。契約は双方の合意に基づくものであり、相手の意向や事情を無視した一方的な内容では、信頼関係を損なったり、交渉が難航する原因となる可能性があります。
例えば、秘密情報の範囲や秘密保持義務の期間について自社が過度に広範囲や長期間を要求すると、相手にとって不利と感じられる場合があります。一方、相手が提案する条項が曖昧だったり、自社にリスクが生じる可能性がある場合もあります。
弁護士に依頼すれば、取引先の意見を適切に反映しつつ、法的リスクを回避するための表現や代替案を提示することが可能です。相互の意見を尊重した契約書を作成することで、信頼関係を強化し、円滑なビジネス関係を築くことが期待できます。
雛形テンプレートはカスタマイズが前提であることを理解しておく
秘密保持契約書の雛形やテンプレートを利用する際は、そのまま使うのではなく、自社の状況に合わせてカスタマイズすることが前提であることを理解しましょう。
テンプレートは一般的な項目が含まれている一方で、個別の取引内容や業界特有のリスクを反映していないことが多いため、そのまま使用すると不十分な契約内容になりがちです。
例えば、秘密情報の定義や保持義務の範囲、違反時の対応措置などは、取引の内容や相手方の立場によって適切な内容が変わります。テンプレートでは標準的な文言が使われていますが、実際の取引に応じたリスクや特別な条件を含めるためには、細かなカスタマイズが不可欠です。
テンプレートを効果的に活用するには、基本構造を参考にしつつ、自社にとって重要なポイントを盛り込み、取引先と自社双方にとって適切な契約内容に仕上げることが大切です。
秘密保持契約書はテンプレートの活用がおすすめ!
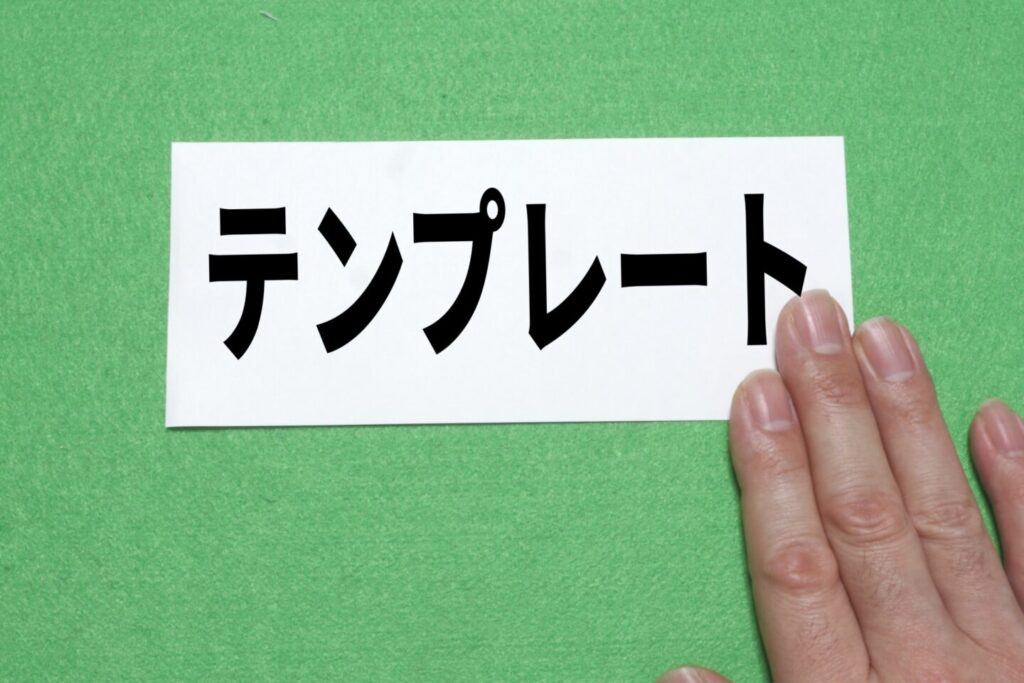
秘密保持契約書を新たに作成する際、雛形やテンプレートの活用は有用です。
テンプレートには一般的な契約書の構造や基本的な条項が含まれており、ゼロから作成する時間や労力を節約できます。契約作成に不慣れな場合でも、主要な項目が網羅されているテンプレートを利用することで、見落としがちな要素をカバーしやすくなります。
ただし、テンプレートはあくまで基礎的な構成を提供するものであり、すべてのビジネスや取引にそのまま適用できるわけではありません。自社特有のリスクや業界の規制に対応するためには、必要な条項の追加や調整が求められます。
テンプレートを利用することで契約作成の負担は軽減されますが、最終的には弁護士にチェックしてもらうことで、法的なリスクをより確実に回避することができます。テンプレートの利便性を活かしつつ、自社に最適化された秘密保持契約書を作成することが、安心して取引を進めるためのカギとなります。
以下では、秘密保持契約書のテンプレートのダウンロード方法や確認すべきポイントについて解説していきます。
秘密保持契約書(NDA)の簡易版テンプレートのダウンロード方法
秘密保持契約書の簡易版テンプレートをダウンロードする方法は、法律関連のWEBサイトや弁護士事務所のホームページを利用するのが一般的です。多くの場合、これらのサイトでは無料または低価格でテンプレートを提供しています。ダウンロードの際は、利用規約を確認し、自社の状況に適したものを選びます。
ただし、簡易版テンプレートはあくまで基本的な内容のみを含んでおり、個別の状況に対応できない可能性があります。そのため、ダウンロードしたテンプレートを使用する前に、自社の需要や取引の特性に合わせて内容を調整することが必要です。
また、テンプレートを使用者に法的な知識が不足している場合、重要な点を見落とす可能性があることにも注意が必要です。そのため、最終的には弁護士によるチェックを受けることで、法的リスクを最小限に抑えることができます。
テンプレートを使用する際に確認すべき点
テンプレートを使用する際には、自社の状況や取引の特性に合わせて内容を精査することが重要です。
一般的な雛形では、個別の取引に必要な条項が不足している可能性があるため、慎重に確認する必要があります。特に秘密情報の定義や範囲、秘密保持義務の期間、違反時の制裁措置などの項目については、自社のニーズに合致しているか十分に検討しましょう。
また、テンプレートの文言が法的に適切かどうかも確認が必要です。法改正や判例の変更により、古いテンプレートでは最新の法的要件を満たしていない可能性があります。さらに、業界特有の慣行や規制にも注意を払い、必要に応じて条項を追加または修正することが求められます。
さらに、相手方との交渉の余地を残すことも意識して作成しましょう。一方的な内容では相手方の反発を招く可能性があるため、ある程度の柔軟性を持たせることが望ましいでしょう。最終的には、両者の利益のバランスを取りつつ、効果的な秘密保持を実現できる内容に調整することが求められます。
まとめ
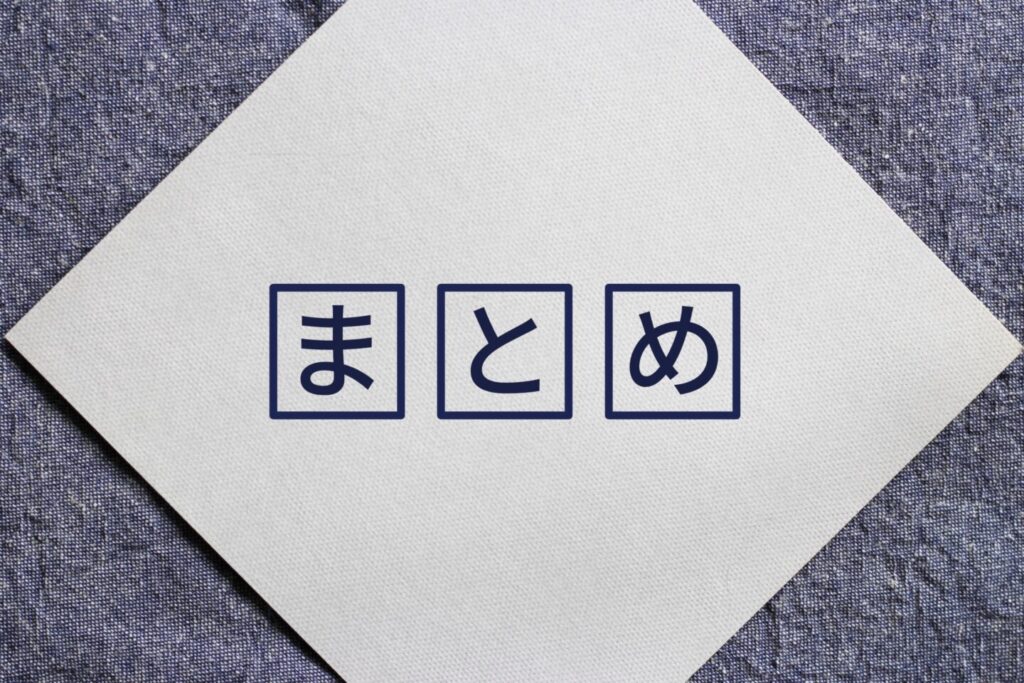
秘密保持契約書は、ビジネスにおける情報保護の基本であり、機密情報の漏洩リスクを軽減するために重要な役割を果たします。
契約書の作成にあたっては、まず秘密情報の範囲や秘密保持義務の期間を適切に設定することがポイントです。これにより、保護対象が明確化され、企業の情報資産を確実に守ることができます。条項ごとの法的リスクを慎重に検討し、取引先の意見も考慮しながらバランスの取れた内容に調整することが求められます。
また、契約書作成の際に雛形やテンプレートを利用するのもおすすめです。ただし、これらはあくまで基礎となるものであり、自社の状況に合わせてカスタマイズすることが不可欠です。
秘密保持契約書の作成に不安がある方は、弁護士に依頼するのを推奨します。専門家のアドバイスを受けることで、潜在的なリスクを事前に洗い出し、実効性の高い契約書へと仕上げることができます。弁護士によるチェックを受け、最新の法的要件を満たしているか確認することで、トラブル回避につながります。
秘密保持契約書は企業の信頼性を支える重要なツールであるため、適切に作成・管理して、安全に取引を進められる環境を整えましょう。
法務救済では、契約書のリーガルチェックから労務、法務観点のサポート、損害賠償などの企業間紛争に対応できる専門家を検索・依頼することが可能です。全国の弁護士事務所から簡単に検索・相談できます。
問い合わせは無料となっており、当サイトから費用は発生しません。秘密保持契約書の作成やリーガルチェックを弁護士に依頼したいと考えている方は、下記のURLから法務救済を利用して探してみてください。
問い合わせURL:https://houmu931.jp/expert/
法務急済運営事務局
株式会社WEBYの法務急済運営事務局。全国400以上の弁護士・司法書士のWEBマーケティング支援に従事。これまでに法律ジャンルの記事執筆・編集を1000記事以上担当。WEBコンサルやHP制作、SEO対策、LMC(ローカルマップコントロール)など様々な支援を通じて法律業界に精通。これらの経験を基に企業法務の際に必要な情報や適切な弁護士・司法書士を紹介している。
※当社(株式会社WEBY)は直接債務整理のサービスを提供しておらず、債務整理の相談や依頼については紹介事務所へのリンク先で対応となるため、当サイトでは債務整理に関する個人の相談や質問にはお答えできません。
当サイトのコンテンツは事実に反しないよう尽力していますが、内容の正確性や信頼性、安全性を担保するものではありません。
債務整理の無料相談や依頼にお申し込みされる際は各弁護士事務所・司法書士事務所等の公式ホームページに記載されている内容をご確認いただき、自己判断していただけますようお願いいたします。
当サイトは株式会社WEBYと提携する企業のPR情報が含まれます。
当サイトで掲載しているコンテンツは個人および法人へ向けた情報提供が目的であり、債務整理を提供する事業者との契約代理や媒介、斡旋を助長するものではありません。











